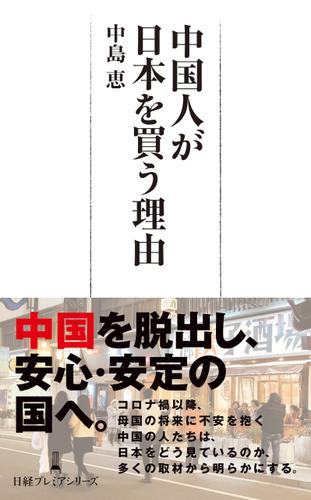
総合評価
(5件)| 0 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年(2024)の初め頃に購入した本ですが、部屋の隅に読みかけとなって埋もれてのを発掘しました。中国が日本のGDPを抜いたのははるか前のこと、今では倍以上の経済大国になっています。それでも中国人には日本が優れているとおもている店があるようです。 その内容を中国の大学を卒業して、中国人を間近で見ることで得られた知見が述べられています。日本は30年近く経済が成長していないので、数字の面では魅力のない国に成り下がってしまいましたが、この本を読んで改めて日本の良さを感じることができました。 以下は気になったポイントです。 ・日本は近いし(生活コストが)安い、(子供が一人で外出しても)安心、安全、食事も安くて美味しくコスパがいい、政治的・社会的に安定していて、空気もいい、日本は本当に理想的な移住先である(p12)日本での生活は政治に影響されない、これが最も中国と違うこと(p44) ・日本では高卒で成功した人、高卒後、いったん社会に出た後、改めて大学に入り成功した人も多い。だが、中国では学歴は一生を左右する。政府の資金が投入される有名大学でなければ、進学する意味がないとさえいう人も多い、卒業した大学によって初任給が異なり、初任給の大学別ランキングも毎年発表される(p54) ・美大に限らず、日本への龍が希望者が増えている要因として、22年に中国の職業教育法が改正されたことも関係がある、職業学校への進学が奨励されるようになったが、そうした学生が職業学校卒では就職が厳しいことから、日本への留学を希望するようになっている、付加価値をつけるために日本の大学院進学を目指す人が多い(p65) ・中国の歴史教科書では、日本の明治維新について教えるが、明治政府で活躍したのが早稲田の創始者、大隈重信であり、そこで学んだ留学生が中国共産党を創設したことは、中国人に強く印象付けられている。早稲田は、アジア太平洋研究科(大学院)の出身者が多い(p72)早稲田は、他大学と比べて英語で受験可能な学部が多いのが特徴、国際教養学部は英語で授業を行う13学部のうち6学部は英語で授業を行うコース(政経・創造理工・期間理工・文化構想・社会科学)が併設されている(p74) ・職人が尊重される日本では、バラエティに富んだ専門学校が全国各地にあり、就職までのサポートも強い、これも日本の強みかもしれない(p84) ・不動産を買う条件として、1)最寄りが大きな駅、2)駅から徒歩6分以内、3)資産価値の高いJR山手線の南側(p99) ・中国の医療体制の脆弱さ、医療の構造的問題も、海外で不動産購入に走ることと関係がある、日本に家を持ち、永住権や国籍を取得して、日本の医療を受けながら老後を過ごせたら本当に心から安心するという中国人が多い(p100)欧米に比べて治安が良い、距離的に近い、利回りが安定している(1当地なら4%)(p108)中国の医療保険は、日本の国民皆保険とは異なり、地域ごとに運営方法や制度が異なる、その人の戸籍などによって自己負担額も異なる、高齢者・学生・農民は任意加入で入っていない人も多い(p1224) ・中国では近年、図書館の整備に力を入れているが、大都市を中心に巨大な図書館が次々と建設されている。どの図書館も、習近平国家主席に関連した図書に大きなペースを割き、利用者の多くは都市の住民のみ、地方には図書館が全くない地区や学校がおい(p1690 ・中国では多くの大学、一部の高校や中学には校歌があるが、一方、日本のように小学校から大学まで、ほぼ全部の学校に校歌があるわけではない(p173)日本では自分が通った学校の校歌を覚えている人は多い、歌う機会が何度もあるから(p174) ・駅ピアノでは、若者から高齢者まで様々な人が、歌謡曲、クラシック、映画やドラマのテーマソングまで様々な曲を演奏する。ごく普通の人が演奏する姿を見ると、日本文化の裾野の広さを実感する、多くの人が言っていたのが「苦しい時、悲しい時、ピアノが心の支えになった」(p176) ・中国の若者は心の支えになるようなものがないまま青春時代を過ごす、若い頃に勉強以外の何かに打ち込んだ経験がないから、打たれ弱い、中郷では芸術は、ごく一部の才能のある人が、その道のプロになるために必死で学ぶものという位置付けである(p177)日本では40年以上も前から、地方の小さい町にもピアノの先生がいて、親がピアノを買ってくれて、月謝も高くなく、誰でも習うことができえた、純粋に音楽を楽しむためにピアノを始めることができた(p177) ・日本のスキー「レジャー白書」によると、最盛期は1993年、当時のスキー人口は約1800万人であった(p187) ・ビザ(査証)なしで投稿できる都市が最も多い国は、日本が1位であった、世界199カ国・地域のパスポートを比較したもの、日本は世界227都市のうち、193都市にビザなしで渡航できる、ビザとは、その人が入国しても問題ないという「お墨付き」(p194) 2024年12月16日読破 2024年12月16日作成
1投稿日: 2024.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「中国人は今何を感じているか」と「他国に自国の資産が買われるとはどういう事か」という二つのテーマが混ざる内容。中国批判ではなく、公平な書き方で好感が持てる一方、記載は感想であり、考察ではないので私見の域を出ない。 共感したのは、日本人の心理。中国人観光客の中には、品がなく、自己中心的な人が比較的多い。だから折角日本に来てくれて、沢山の買い物をしてくれても、あまり感謝できない。何か悪いことをしている気がする。そのために、中国人の要求には柔軟な対応をしない。一人を特別対応すると周りに伝わって集団で既得権化しそうだからだ。日本に来た中国人が一々WeChatで自国に情報伝達しているのを見た事があるので、この心配は間違いないだろう。だからこそ、日本人は塩対応になるし、中国人はそれを不満に思う。 自分や自分の周囲が得をするためなら、恥という概念は生じない。その逞しさは、部外者には害悪である。だから、嫌われても仕方ない、という事になる。 気になったのは、最近の中国人による儀式感という言葉。人生には、一定の儀式感が必要なのかも知れない。
28投稿日: 2024.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国人は日本にあこがれを持ち、その環境に羨んでいるという視点。 中国では社会にモラルがないためお金に頼るしかない。そのため投資に非常に熱心。 そのため中国人が日本の不動産を買う。 それ以上の政治的な意味はない。 読了45分
0投稿日: 2023.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人全体の「素質」の高さ 政治に影響されない安定した社会と生活 安心とやさしさ 機会均等 中国の闇 老後の不安 紙切れになる恐れの元金よりも不動産 いざとなったら大金が必要 医療体制 病院の数が少ない 日本のようなクリニックは中国にはない 社畜 できるだけ ではなく、絶対 の中国ビジネス デジタルとインフラ 利便性よりも管理する側の視点 都市と地方 日本の強み 老舗 アウトドア 美容 農機具 団体スポーツ 儀式 アジア唯一の先進国 日本 いざというときの強さ 中国 一人ひとりが強いがいざというときはバラバラ
0投稿日: 2023.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国人が日本を訪れたり、留学したり、不動産を買うのには理由があった。 安全保障に関わる土地を買収したり、医薬品を爆買いしない限り、日本で商品やサービスにお金をジャンジャン使ってもらうのはいいことだ。 コロナ禍を経て、「くまのプーさん」揶揄されるあの人が支配する中国共産党のやり方に、息苦しさと将来への不安を覚え、日本にやって来る中国人がいる。 中国語に「ツァンツァンジアマー」という言葉がある。 中央の指示が1回なら、その下は2回、さらにその下は3回というように、下へ行けば行くほど、どんどん(締め付けは)厳しくなりますと、ある中国人がコロナ禍での出国審査の状況を語った。 日本は安全で住みやすい、自由がある、チャンスを得る可能性がありなど、中国にはないものを求めている中国人の姿があった。 ネットで中国共産党やあの人のことを批判するだけで一生券になって削除したり、NHKニュースで天安門事件を報道すると突然映らなくなるなど、何があるかわからない。 そんな所で暮らしていたら息が詰まって「脱中国」を夢見ても不思議ではない。
1投稿日: 2023.05.09
