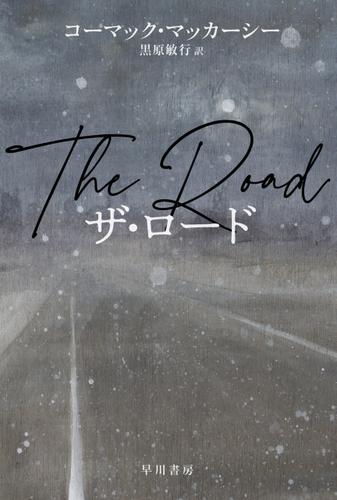
総合評価
(104件)| 25 | ||
| 46 | ||
| 20 | ||
| 5 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ荒廃した世界を旅する父と子の物語。 多くの人々が倫理観を忘れた世界で道半ば出会った人々を助けようとしたり、善きものであろうとする子供の純粋さが美しい。
0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大厄災の後、ほとんどの動植物種・文明は絶滅し、灰色の厚い雲に覆われ、生き残る人類の大部分は人食い部族として存続している地獄の世界。 そんな地獄の中を、主人公の親子は、飢餓や凍死の危機をはじめとする様々な恐怖を経験しながら、倫理や理想を捨てずに進み続けようとする。 極限状態に追い込まれていく描写がとてもリアルで、読みながら何度も何度も「頑張れ!まだ死ぬな!」と応援してしまった。食糧にありつくたびに、自分がとても安堵した。 信仰を捨てず、こどもに無償の愛を注ぎ続ける父親が死んでしまうシーンはとても悲しかった。 少年が新たな夫婦に出会う、救いのあるラストでまだよかったが…いや、この世界には救いなどないか…。 父親がほんとに理想のパパすぎる。自分に息子ができたら、こんな父親になりたいと感じた。
0投稿日: 2025.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきの表現を借りると、北斗の拳の世界の子連れ狼。ありえるかも知れない死と灰の世界で、人間はどのように行動し思考するかという視点ではリアリティを感じられましたが、物語は割と単調に感じました。
5投稿日: 2025.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログハーラン・エリスンの「少年と犬」と並び、私のなかでは2大ディストピア小説。大好きだ。荒廃した世界で生きるために静かに移動し続ける父と息子。何度も読んでいるせいか時々断片的に夢に見る。
1投稿日: 2025.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ物性研の所内者、柏地区共通事務センター職員の方のみ借りることができます。 東大OPACには登録されていません。 貸出:物性研図書室にある借用証へ記入してください 返却:物性研図書室へ返却してください
0投稿日: 2025.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログピュリッツァー賞受賞作。 最後までまったく面白くなかったのに、文章の流れにのると没頭できてしまった。サラエボ包囲を想像して読み進めてからは、純文学的な言葉の川に溺れることができて、それはそれでよきでした。言葉と言葉で緻密に紡がれて形成されたその場限りの世界に篭りたい時ってあるよね。
0投稿日: 2024.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ読書会課題本。ストーリーは「何だがわからないがめちゃくちゃ荒廃し、住民がほぼ野生化したアメリカの近未来で、とある親子が放浪の旅をする」という話。荒廃した理由が不明な上、矛盾している描写も多いので、SFとして読むとかなり物足りない。しかし、現代社会を風刺した寓話として読むと「ああ、なるほど」というのがある。そういう意味で、現地でヒットした理由も、ピューリツァー賞受賞も納得がいく。
0投稿日: 2024.11.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ純文学性が高いが一気読みした。ポストアポカリプスものではあるが、SFという感じはしない。 人間を食べるか食べないかは人として究極の善悪の彼岸だが、善悪というルールは世界の破滅と共に消えてしまった。そんな世界でも人を食べないと誓い、ひたむきに生きる親子はとても美しく、火を運ぶものを名乗ることには神話性も感じる。 2018.3.22
0投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ずっとドキドキしながら読んでいる 読むのを止められない、少年が生きているか?死なないでと思いながら読む 子持ちは読むのが辛い、ハッピーエンドを期待して読む ハッピーエンドなんてありえるのか?全く想像もできないけど少年が死ぬのだけは耐えられない 今後存在しないものは今まで一度も存在しなかったものとどう違うのか 男に刺されそうになる少年をなんとか守り抜いた彼、大事にしているのは少年の生なのか、それとも自分の希望なのかどちらだろうかと思った しかし最後まで読んでみて、そんなエゴの存在はわからなくなってしまった、自分より先にこどもが死ぬ、それが何よりも耐え難いのは分かりきったことだったなと思う 少年は何歳なのだろうか? 読んでいて自分たちを重ねて辛い、読むのをやめればよいのだがここまで読んでしまったのならハッピーエンドまで知りたいとの一心で読む、ピンチのとき彼らが死んでしまうことが受け入れなさすぎるので数ページ先で生きているのを一瞬確認してから読み進める、生きてくれと思う 誰に対してもオススメできる本。 ただ、私にとっては恐ろしい世界の描写が多すぎてもう一度読むぞという元気は今時点ではない。
2投稿日: 2024.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
初コーマック・マッカーシーは、世界的なベストセラー小説でピューリッツァ賞も受賞しているこの本から。 おそらく核戦争があった後のアメリカ大陸を歩いて旅する父と息子の物語。塵によって太陽光が遮られ気温が下がり、人間以外の生物もほぼ死に絶え、生き残った人々は、奪い合い殺し合い、死人を食らうようなことまでしつつ生きているディストピア。 父子も、体臭と汚れにまみれたボロボロの服を着て毛布や防水シートをまとい、ショッピングカートに生活品を乗せて移動しつつ、廃墟を漁り日々を凌ぐ。読んでいるだけで寒いし飢えるし喉が渇く。だが決して人の命や財産を奪うことはしない、生きていくために廃墟を漁ることはしても、人の気配があれば立ち入らない(防衛のためでもあるのだが)何度も飢え死にしそうになり、凍えても南へと歩みを止めない。 荒廃した情景の中で二人の会話が沁みる。静的で詩的で冷徹で少しだけ熱を持つ文章。 同じディストピアが舞台でも、キングとかマキャモンの小説や、マッドマックスや北斗の拳のような感情的だったり動的だったりする描写は極力排しているのが、かえって孤独と絶望感を際立たせる。 凄い小説、読んでるとこちらまで凍えてくる。本から現実の世界に意識が戻ってきたとき「この豊穣な現実を絶対守らないといけない」と心に誓った。
1投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ凄い言葉を生むための物語。 胸に押し当てたいほど美しいものは全て苦悩に起源を持つ。それは悲しみと灰から生まれる。 - 63ページ かたちを喚び起こせ。ほかになにもないところでは無から儀式を創り出しそれに息を吹きかけよ。 - 86ページ 善意が見つけてくれるんだ。いつだってそうだった。これからもそうだよ。 - 326ページ 全て凄い言葉。言葉に、“凄さ”を付与するための話。 「火を運ぶ」という言葉が多義的に解釈されている。解釈に一側面を付け加えるならば、これは“律”だ。そして律は、人間の主観なしには作り得ない。人間が作るものには全てが信仰が含まれる。それは律であっても例外ではない。 世界をあるべき姿に正すためには、律を作り出す時に用いた信仰を実践するしかない。つまるところ、“善い者”でなければならない。これはもちろん、自分にとっての善さに他ならない。 火を運ぶ中で少年は原初の火を灯し続けるが、彼は彼らの作り出したのとは違った律が世界に混ざり込み、たびたび少年と衝突する。その結果、大抵悲惨な事態を引き起こすが、父の世界を取り込み、少年の律も変容する。 しかし、どれだけ律が変わろうと、火を運ぶという目的が変わることはない。なぜなら、火を運ぶことは、律の内容とは全く無関係に行うことができるからだ。 コーマック・マッカーシーは、彼自身が火を運ぶために、我々に「言葉」という手段を用いて語りかけているように思う。それは、キャラクターと、物語による、「凄い言葉」という形をとって成される。 リストを作れ。連禱を唱えよ。憶い出せ。 - 38ページ
1投稿日: 2024.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ破壊され尽くした世界を父と息子の二人が「火を伝える」という目的を持って南に向かって歩き続ける。 廃墟の中、辛うじて残った食糧や必需品を漁る緊張感、掠奪者や老人・子供に遭遇することが孤独を紛らわし物語の現実感を醸し出す。ボロボロの地図を頼りに雨や雪、疲労と飢え、病気と怪我に抗して南に向かう。海に辿り着いても状況は何も変わらない。 二人にとっては「防水シート」がいろいろな場面で何度も出てくる万能資材であり、「カート」が必要品を運んでくれる頼り甲斐のある同行者だ。 大状況がわからないということはこれ程不安を感じさせるものなのか。読者は一瞬も気を抜けず漠然とした期待を求めて読み続け、南にこそ可能性があると思い込むしかない。作者は多くを語らず読者の想像力に委ねる。温暖化による破綻なのか核戦争による破滅か、破壊された世界で二人の親子愛が辛うじて希望の火を灯す。いつまでどこまで続くのかわからない恐怖と諦観そして絶望が異空間を味あわせる。 コーマック・マッカーシーのピューリッツアー賞受賞作である。
0投稿日: 2024.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログゾンビやターミネーターのいない未来社会と思われる世界を父と子が歩いていく。途中の出来事に徐々に吸い込まれる涙なくして読めない傑作。
1投稿日: 2024.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ荒廃した世界をひたすら南に進む父と子の話。 父として、息子としての考え方や心情態度の変化がおもろい。 火を運ぶ者たちである。
0投稿日: 2024.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログただ歩くだけでどんだけ引っ張るんだ?という前半だけど、徐々にこの世界のありようが明らかになってきたりそれなりの物語の起伏もあってまあまあ楽しめる。
1投稿日: 2023.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ灰色の世界を生きる父と子の物語。 作者の「息子に捧げる」という何とも心にズシンとくる計らい。 父の子を守ろうとする強さと、子の父や(こんな状況でも)他人を思いやる純粋無垢さが、世界の荒廃、人間性の崩壊に対して、どう立ち向かい、導かれていくのか。 星の光以外見えないような暗闇、静寂の中で読んだこともあり、世界、人間の行く末を、この本から見てしまったのか…?と深慮を巡らす。
13投稿日: 2023.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ動植物は死に絶え、人が人を喰らう終末世界で続けられる父子の「火を運ぶ」旅。善とは何か、生きるとはどういうことか…。全く光の見えない絶望的な情況の中で「破滅後」しか知らない少年の純粋さが胸を打った。
14投稿日: 2023.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
終末を迎えつつある世界でなんとしてでも息子を守ろうとする男が、最後まで父親として存在していたのが良かった。信じられるのはお互いだけ、という点が揺るがなかった。だから孤独で危険な旅も続けられたし読者としても安心できた。 父親のサバイバルスキルが高くて、色んな工夫を読んでいるだけで面白かった。読点がほとんどない、流れるような思考と会話の中に、記憶が混じってくるのも物語に没入できる理由なのかなと思う。 人が人を食うほど食べ物がない事態で、自分も痩せ細ってしまったのに少年の心は清らかで、他者を殺してまでは生きたくないという意志が強かった。その彼が無惨に殺されるようなことがなく保護者が現れ、いくらか救われた思いだ。
3投稿日: 2023.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ直視できない現実の辛さを見せないように肩代わりする父親。しかし、泣くしかできなかった子供が現実をしっかり受け止め出し、ついには父親を支えるようになり、父親の遺した言葉を胸に、この終末世界の中を生き抜いていく──。 あまりにも辛い、けれど詩的な表現の美しさに魅了されるSF小説の傑作。子育てをしている今だからこそ響く言葉が多く、最後は辛過ぎて泣きそうになってしまいました。
4投稿日: 2023.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ涙ちょちょぎれるぜ…親父 俺の親父といったら俺の最低でも6倍以上金貰ってるくせに青カビ生えたレモンサワーを出すような安い焼肉屋(飲み放題60分500円)に連れていきその後俺は知り合いのとこ行くからと二軒目の代金出したくなかったのか俺を置いてどこかに行っちまいやがった
1投稿日: 2023.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ灰が降る終末世界で父と息子が旅をする。略奪者の目を逃れながら、少しでも暖かい南を目指して。その道は悲惨というほかない。森の中に潜んで防水シートで雨を避けながら焚き火をする。臭い服と毛布にくるまって眠る。次の日にはボロ布を巻きつけた足でまた先へ進む。行く先々で転がっている死体。こんな救いのない場所で生きていくことに何の意味があるのか。銃があるならそれで自分と息子を撃てば終わりじゃないのか。読みながらそう思わずにはいられなかった。生きたいというのは親のエゴなのではないか、とも。それでも生きようとする気持ちの強度に圧倒される。他人を助けたいと思う息子の純粋さや、お互いと一緒にいたいと思う二人の気持ちの真剣さが極限の状況だからこそ照らし出されているように思う。光のない陰鬱な世界でも火をおこすことはできる。
0投稿日: 2023.07.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
戦争か事故か天災か何かが起こった後の、人類の終末期を生きる父子の物語。 解説には近未来と書かれているが、未来的な道具立てがほとんどみられなかったので、例えば冷静時代に核のスイッチが押されたとか、そういう状況もありうるのではないかとか思いながら読んでいた。何であったとしても話にはあまり関係ない。 父子のひたすら南へと進む旅が、とにかく削ぎ落とされた文体によって淡々と表現される。 最後の父の死以外には起承転結に関わるできごとは起こらないが、ものすごい緊張感の中、まったく飽きずに読み進めることができた。 わずかに生き残った人間は、もはや人間としては生きていない。人類どころか、動物も植物もだめになっているので、備蓄食料や他の人間を食べ尽くしてしまえば最後の一人はもう生きる望みはないはずなのに、皆必死で生にしがみつこうとしている。 息子に偽りの希望を与え生き続けさせようとするのは父親の最後のわがままにすぎないので読んでいてつらい。
1投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ『信号弾はしゅーっと長く音を立てながら暗黒の中へ弧を描き海面よりも上のどこかで煙混じりの光にはじけてしばらく宙に懸かった。マグネシウムの熱い巻きひげが数条ゆっくりと闇の中をくだり渚の波が仄白く光って徐々に消えた。彼は少年のあおむいた顔を見おろした。 あまり遠くからだと見えないよね、パパ。 誰に? 誰でもいいけど。 そうだな。遠くからは無理だ。 こっちの居場所を教えたくてもね。 善い者の人たちにかい? うん。ていうかとにかく居場所を教えたい人に。 たとえば誰? わかんないけど。 神さまとか? うん。そういうような人かな。』 目の前の本を読みながらどうしても他の本のことが頭の中を過ってゆく。読み始める前に想像していたのは、書名からの連想で、空想科学小説風の「オン・ザ・ロード」(ジャック・ケルアック)のような話だったのだけれども、実際に連想されたのはデイヴィッド・マークソンの「ウィントゲンシュタインの愛人」とジョゼ・サマラーゴの「白い闇」。翻訳者の解説にもある通り、確かに本書コーマック・マッカーシーの「ザ・ロード」もロードノベルではあるのだろうけれど、本書はそれら二冊同様にいわゆる反理想郷を描いた小説と分類されるのが適切なように思う。ここで描かれているのはいわゆる「核の冬」の時代のようであり、自然も徹底的に破壊され人類以外の生物の痕跡もほぼ無い。 「ウィトゲンシュタインの愛人」は本書と同じように何らかの理由で人類がほぼ滅亡してしまった近未来的な世界に残された女性が主人公の小説(そう呼んでよければ)だが、一人残されていく過程の描写はなく、世界はどこか形而上学的(ウィトゲンシュタインの名が付く位なので当然だが)で、滅んでゆく人類たちの修羅場のような状況は描かれることがない。かつ、自然そのものは何も汚染されていないかのような雰囲気が漂う。一方の「白い闇」はある日突然人類が盲目になるという伝染病が蔓延し社会が機能しなくなっていく世界の中、一人目が見えるまま「取り残された」女性が主人公の小説で、こちらは「目が見えること」を前提として成り立っていた社会通念が倫理観も含めて覆されていく様が、少々糞尿愛好過多気味に描かれている。何らかの理由で人間社会が機能しなくなりやがてほぼ滅亡した状態になるというのがこの類型の空想科学小説の一つの時間の流れだとすると、本書は「白い闇」(未読ながら、続編では疫病は自然と克服されるらしいのだが)と「ウィトゲンシュタインの愛人」の中間の時代を描いており、ひとり取り残されてしまった状況より、その前にこういう時代が来ることの方がもっと過酷だということを改めて認識させる。言わずもがなだが一番凶暴なのは人類なのだ。だから映画「マッドマックス」が描くように、そこに「正義の味方」的な主人公を置きたがる聴衆や読者が多いだろうとも容易に想像できるのだけれど、本書の主人公たちはメル・ギブソンとは違ってタフでもなければ特別な才能に恵まれている訳でもない。ただ温暖な土地、そして残された食料を求めて彷徨い歩くだけだ。道々出会う困難を何とか紙一重でかわしながら進む親子の物語を描くこの小説の終着点は一体どこなのだろうと訝しく思うほどに、終盤に至るまで救いらしい救いの光明は見えてこない。旅を続けながら父親はじわじわと弱っていく。ロードノベルの定番である成長譚という視点から見ても、破壊され尽くした世界に生まれてきて「前の時代」を知らない息子が成長しているようでもない。悲惨さだけがずんずんと降り積もっていく。 しかし、やはり最後はそうなるしかないというエピローグが待っている。ご都合主義的と言ってもいいその終結はハリウッド映画的な世界観と相性がいい。それがいいとも悪いとも思わないのだけれど、ドン・デリーロと並び称されるという作家の作品に何を読めばいいのかを判らなくもさせるように思えてならない。自分の中での置き所が上手く見つからない小説である。
4投稿日: 2023.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ世紀末、自然災害か核戦争か、草木さえ死に絶えた希望のない世界で、生きるために南の海を目指して歩く親子。 読み切るにはなかなかの精神力を要します。 いま自分が住んでいる世界と真逆すぎて、ファンタジーのように見える物語ですが、もしかしたら、人はみんなあんなふうにただ生きるために生きているのかもしれません。 生きるとはどういうことか、当たり前にあるこの世界は何と素敵なものか、色々と考えさせられる作品でした。 散文的で静謐な文体も読みやすく、美しかったです。 ぜひ。
0投稿日: 2023.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログどこまでも続く灰色の世界。 常に死を近くに感じながらも、南は向かう。明確な目的地はなく、ただ暖かいからという理由で。 坦々とした文体で描かれる、容赦ない自然、無惨な光景。 希望とをもつとか未来を見るとかいった言葉がただ上滑りするだけのような状況下、短く交わされる父と子の会話が、読み進めるほどに心に染みてきた。 純粋でまっすぐな視線をもつ少年の、存在そのものが希望か。
0投稿日: 2023.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ「森の夜の闇と寒さの中で目を覚ますと彼はいつも手を伸ばして傍らで眠る子供に触れた」最初の一行が始まる。 おはよう、パパ パパはここにいるぞ。 うん。 繰り返し描写される周りの情景、それは「寒さ」と「飢え」と「怯え」。 理由の見えない状況のなか、南へ向かう父と子の会話は、まるで詩の一遍のような響き。 本当であれば「暖かい家と家族」に囲まれながら将来を夢見るはずの子供が、人を食らう人に怯え、生きるために人を殺めることを恐れ、死を身近に感じたまま、父と話す。 もう死ぬと思っているだろう わかんない 死にはしないよ わかった なぜもう死ぬと思うんだ? わかんない そのわかんないというのはよせ わかった どこまでも続く南への道、結末がいいはずはないのになぜ生き続けるのか……。 ピュリッツァー賞受賞で映画化もされた。 過去でも現在でも未来でもない、父と子の、あるいはいつでも起こる可能性のある地球の姿。 一度は、読んでおく価値のある物語です。
2投稿日: 2023.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
死んでいく世界の中、必死にお互いを支え合う父と子。読み終わり、涙が溢れてきた。二人の会話から伝わる状況や心境の変化。虚しさも痛みもひしひしと伝わってくる。生きる上でどこかで割り切らないといけないという父が下す正しさと、本当にそれで良かったのかと疑問を抱く少年の優しさ。お互いがそれぞれの学びとなり支えになる。父と同じように読んでいる自分も少年に暖かさを感じた。彼から優しさを分けてもらった気がした。
0投稿日: 2023.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ終末の世界。圧倒的な情報の筆致で描かれる世界と、父と子の閉塞的な会話。そして二人の旅がどこに辿り着くか。 多分理解しきれてはないけど、ラストとかはジーンときた。 「」が無かったり句読点が無かったり、締めの文が良かったりした。
0投稿日: 2023.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語版を読んでいたのですが、途中、主人公たちが路上で行き会った狂暴そうな武装集団の持ち物や集団内の階層の描写がよく分からず(「北斗の拳」の悪役風な人々のところね)、でも、そのシーンはすごく気になったので、日本語版も図書館から借りてきました。 よく分からなかったところは、もちろん私の英語力の問題によるもので、その後も、ところどころつまみ食い的に読み比べましたが、日本語訳はいろいろと素晴らしかったです。 ウィル・スミスの映画「アイ・アム・レジェンド」を少し彷彿とさせた。 特に、廃墟となっているいくつかの家屋を捜索するときの緊張感が。 しかし、何があったんでしょうね、あの世界で。 そこは語られてはいないけれど、広範囲にわたる荒廃ぶり、焼け野原っぷり、太陽の見えなさっぷりから考えると、食べ物や建築物が都合よく残り過ぎな気はしました。 要するに、つっこみどころがあり過ぎな感。 そのあたり、元がSF作家じゃないだけに、わりと科学的根拠は適当なのかも。
0投稿日: 2023.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログたぶん近未来のアメリカ。たぶん核戦争後の世界。数多くの動植物が滅んだ終末の世界。僅かな食糧を奪いあう残された人類 ただひたすらに南を目指して歩き続ける、ひと組の父子の物語。暴力が支配する世界で、人は善き存在であり続けることは出来るのか
0投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログはっきりと明示はされていないがおそらく核戦争後のアメリカだった国が舞台。植物は枯れ動物は生き絶え、死が全てを覆った世界。空は灰色の厚い雲に覆われ、どんどん寒冷化が進んでいる。そんな世界で生き残った父子が南を目指して彷徨い歩く。 「北斗の拳」や「ウォーキングデッド」のような終末後の世界を描いた作品だけど、動植物がほぼ完全に生き絶えてて食物生産ができない状況な分こっちの方がずっと条件がキツい。今ある保存食が無くなったら人間は何を食べるのか?読み進めると地獄のような答えがそこに待ち受けている。淡々とした冷静でリアリズムに徹した描写が、その地獄を現実味を帯びた説得力のあるものにしている。 地の文は主観を排した写実的な情景描写がほとんどで、「老人と海」を思い出した。乾いた質感の文体が世界観にマッチしてる。 ただし読点がほぼなく一文が長いため、ちょっと集中力が途切れると状況の把握がしにくい。映画で言うとずっとワンカットで回し撮りしているような文章。会話文もカギカッコが無くわかりづらい。また急に(世界崩壊前の)過去の話が出てきたり夢の話が出てきたりして少し混乱する。章立ても無いので、区切りがつきづらい。 総じて散文のような小説。この父子の旅を実際にワンカットのカメラで追い回しているような感覚になる。 子どもがいる身としては尚更読んでいて辛い、ページをめくる指を止めたくなることが多々ある作品だったけど、この本に出会えて良かったと思う。今後ディストピア小説を読む中でこれを超えるような衝撃作は、ちょっとなかなか出会えないんじゃないか。
10投稿日: 2022.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろかったけど、大騒ぎするほどじゃないかなあ。 うろうろしないでじっとしておけよと思うが、それではこの小説が成り立たないものなぁ。
0投稿日: 2022.05.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ終末世界を旅する父子の過酷な旅路を静かに描く。 詩的で難解な表現、読点や鍵括弧がほとんどない独特の文体で集中して読まないと目が滑るが、没入感と圧倒的な世界観に引き込まれる。 作中何回か登場する火を運ぶという表現。火は様々なものを象徴する。文化、戦争、希望、情熱… ここでは何だったのだろうか。それは恐らく、人類さえ絶えかけている世界で、前に進み続ける執念であり、ある意味場違いな崇高な精神なのかもしれない。 どこか諦念を感じる父と息子の対話に胸が痛い。 親子の愛や絆というより、様々な来るべき「終わり」を見据えた上で人間存在や善を根本的に問う作品だと思う。
1投稿日: 2022.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログなんだろ、これがピューリツァー賞を獲るはっきりした理由を読み取るだけのSF的読解コードが私に欠けているのかな?色々と既視感満載で、どうしてこれが?との思いが拭えない。 黙示録もの、という括りでいけば、アトウッドの方が深くて痛い。そうではなくて、親子もの、とか、ロードノベルとして読むには、情緒のうねりもストーリーの起伏もさほどでなし。ラストの甘さも、どうなんだろう、と。 唯一、成功してるなと思えるのは、世界観と文体のマッチング。読点をほとんど打たず、セリフに「」をつけなかった訳者さんの力量に依るところが大きいんじゃないだろうか。
0投稿日: 2022.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ災害か戦乱かわからないが、人間も動物も植物もほぼ死に絶えた世界で、南を目指して歩き続ける父と息子。道々出会う人々は簒奪者ばかりであり、過酷な旅となる。父は絶望を感じつつも息子を生かすことを最優先し、人殺しも厭わない。息子は倒れた人々に対し優しくあろうとし、食糧や衣服を与えようとする。ハッピーエンドは期待できないし、その通りに終わったが、父性を強く感じる手応えのあるストーリー。でも最後には母性に救われるんだよなあ。
1投稿日: 2022.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ空想世界ではなく現実に起きそうな未来がリアルで怖い。 食、性別、人が余裕がなくなった時がより1番怖い。 描写が想像出来てしまう。 その中で親子の絆や純真な少年がこの本の面白さ 命は平等であって平等でない 生き方、命を考えさせられる作品
1投稿日: 2022.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ全てが美しかった。 文を噛み締めるようにじっくり読み進めた。 希望も絶望もないんだろう。ただ生きるというストーリーがここまで楽しいとは。
1投稿日: 2022.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ピュリッツァー賞を受賞した世界的ベストセラー、だそうです。 自分には合わなかったな~。 舞台は何らかの原因で死滅してゆく世界。 空は暗く、寒く、食べ物がありません。 とても深刻なマッドマックスの世界、といったところでしょうか。 そこを父親と息子の2人連れが南を目指して歩きます。 凍えながら、飢えながら、ただただ歩きます。 親子が最も警戒するのは人間です。 数少ない人間たちは、強奪しあったり、殺し合ったりしているのです。 ときには文字通り食い物にされてしまうのです。 雨に打たれ、食料を探して廃墟を探しながら、靴はボロボロ、人目につかぬよう慎重に進みます。 言ってしまえば、ただそれだけの話です。 最初から暗く、そのトーンは最後まで変わりません。 文章も慣れるまで苦労します。 この作者は、読点というものをほとんど使いません。 そのため例えば 遠い過去に彼はこのすぐ近くで一羽の隼が山の青い横長の壁を背景に急降下して鶴の群れの真ん中の一羽を胸骨の竜骨突起で一撃しぐったりしたひょろ長い獲物をつかんで川まで運び秋の静かな大気の中に飛び散る薄汚い羽毛の尾を引くのを見たことがあった。(本文抜粋) なんて長ったらしい分かりづらい文に出くわします。 読点使えや~っ!! 三回も読み返したわ。 唯一読点を使うのは わかった、と少年はいった。(本文抜粋) このパターンのみです。 記号が嫌いなのか「」も使いません。 しかし、まあ、それは慣れます。 地の文はザっと読んで、気になるとこだけをしっかり読めば良いわけですから。 でもストーリーがな~……。 過酷な状況での人間とは、という話しなんでしょうが、自分にはピンときませんでした。 残念。 自分には文学作品は合わないってのが分かってるくせに、どうしてときどき手を出してしまうんだろう? ピュリッツァー賞みたいなブランドに弱いのかなー。
13投稿日: 2022.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ「バーナード嬢曰く。」で知って長らく気になっていましたが、本屋で見かけてようやく読めました。 終末世界を歩き続ける親子の物語。生きていくための描写がけっこう辛かったです。
1投稿日: 2021.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ文学ラジオ空飛び猫たち第10回紹介「世界の終わりでどう生きるか」 ダイチ 今年のコロナ禍に読みましたが、ラストあたりボロボロに泣きました。本当読んでよかったと思えた小説です。終末の世界の話なので、とにかく暗く絶望的だけど、それゆえ人間の本質的な部分を描いています。暴力的な描写も多く、残酷なシーンや状況もありますが、その中でこの小説は親子の関係や愛を描いているので、なんだか救われたような気持ちになれました。 救いがあるとかないとか関係なく人間の愛情を描いた作品です。誰かを大切にしたいと思ったことがある人には必ず胸を打つと思いますので読んでほしいです。 ミエ 作者のマッカーシーの何もかもフラットに描く文章が好きで、この小説にはまりました。旅する親子は今日この一日を乗り越えれるのか、とすごい緊迫感を感じれます。あっさりと人は死んでいくし、都合のいいことなんて起きないし、本当にマッカーシーは容赦がないと思います。そんなサバイバルな世界で、タフに生きる父親と、必死についていく優しい少年に感銘を受けました。小説から生きる力をもらえたと思っています。 真剣に生きようと思っている人に読んでほしいです。マッカーシーは親子にすごく厳しい現実を突きつけてきます。その現実に親子は向き合い、生き延びようと必死に日々を過ごします。これほどの緊張感と、同時に希望もある小説はないと思います。マッカーシーの真剣さは並のレベルではないです。 ラジオはこちらから→https://anchor.fm/lajv6cf1ikg/episodes/10-ei5rua
3投稿日: 2021.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ都合よく生き残ることができるわけだけれど、ラストで都合よく生き残れなかった数多善き人に思いが至って都合の良さに合点が行った。
0投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ雲に覆われた空、陰鬱な靄のかかる大気、灰が降り積もった地面、何らかの破滅的事象により終わった世界を、生き残った父と息子が南を目指して歩いていく。 行く先々の廃屋や廃船や地下室で偶然見つける缶詰や瓶詰の食糧で露命を繋ぐ。希望のない世界のため、生き延びられるのが良いことなのか否かについて父と同様、読者であるこちらも考えさせられる。 偶々生き残った人と巡り合えても、その人が善人とは限らない。赤ん坊の頭を切り落として串焼きにしていたりする。 徹頭徹尾暗鬱な世界観。そうなった原因が仄めかされ、途中まではそれを知りたい思いが先を読む動機になっていたのだけれど、途中からは予想される旅の終りがどう書かれるかを知りたい気持ちに切り替わった。 でも原因を知りたかった気もする……。 訳が直訳的に感じたので、もっと詩的な翻訳だとよかったかも。
1投稿日: 2021.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログポスト・アポカリプスものSFの一冊として読んだ。すごく重く、灰色な気持ちになった。ただひたすら南を目指す父と子は淡々と食料を探し、少しでも安全な場所を探し旅をしているが、彼らが通り過ぎる風景は酷いものだし、最後についても希望があると大手を振れないエンディングのような気がして、ズーンとなった...貯蓄された食物を探すだけでは安定的でないし、人間がそんなに疑心暗鬼になって少人数に分かれたままなんていうことがあるのだろうか?とかいろいろ考えていた(描かれていないだけで台頭しているグループとかはあるんだろうなあ)。世界どうなったの?って思っていたけれど、作中でそれを老人に尋ねるように、知らないまま放浪の旅に放り込まれる未来が、人類に訪れるあり得る未来なのかもしれない。読んでいて、縫合くらいは最低限サバイバル知識として頭に入れておこうかと思った..
2投稿日: 2021.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
男はまだ幼い少年をショッピングカートに乗せて灰に覆われた世界で南を目指し歩いた。少年が生まれる少し前に何らかの人災あるいは天災により世界は死に絶え、太陽は分厚いスモッグの向こうに姿を潜め木々は枯れ果て、生き残った人びとはお互いから奪い合い貪るほかなくなった。それでも父の語る〈善い者〉〈火を運ぶ者〉の物語を信じ、道で行きあう人びとに手を差し伸べようとする少年と、かつてあった世界の幻影に悩まされながら息子と共に〈明日〉に辿り着こうとする父の姿を描いたポストアポカリプスSF。 翻訳もので文体の話をするのって原文を見たわけじゃないから気が引けるんだけど、この小説はまずこの文体抜きにして語れない。句点がほとんどなく、会話文はカギカッコなし。一文が何行にも渡ることもあるが、日本語として意味が取りづらいと感じる箇所はひとつもなかった。この訳は偉業だと思う。 とにかくこの文体がすこぶるかっこいい。すぐに真似したくなる。ハードボイルド調の硬質な文体だが深層にはキリスト教神秘主義的世界観が息づいていて、闇のなかに微かな光を放って白く浮かびあがるバロック彫刻めいた美しさがある。凋落し腐乱したものが崩壊の一歩手前で奇跡的にまだ形をとどめているかのような頽廃的な美の表現は、文章自体が灰に覆われた世界のメタファーのようだ。アンナ・カヴァンの『氷』の世界を白黒反転したようなヴィジョン。物語終盤に描かれる被曝したような人びとの阿鼻叫喚図はロダンの「地獄の門」を連想させる。 SFなのだが主としてキャンプ小説というかサバイバル小説でもあって、このお父さんは防水シートと毛布を使って雪用のブーツを作ったり、エンジンオイルとガソリンでランプを作ったりできる。家捜しや悪漢と行きあったときにも頼りになるし、捨て置かれた船から使える資源のサルベージもしてくれる。固く締まった瓶の蓋をドアに挟んで開ける方法は覚えておこうと思った、壁の塗装めっちゃ剥がれるらしいけど(笑)。 それから、飢餓状態を散々描写されてからでてくる食べ物の美味しそうなこと。墓から掘り出されたかのように干からびて見えながら、切ってみるとなかに肉の豊かな風味を残していたハム。焚き火で温めた缶詰のポーク&ビーンズ、生のアミガサタケ(調べたら生食厳禁らしい)。そして白昼夢のような地下シェルターでの豪勢な食事。父がコーヒーミルで豆を挽く音で息子が目を覚ますところなど、それまでとの激しいギャップで泣き出しそうになる。 技術を操り子に伝える父性といざとなれば子のために死をも恐れぬヒロイズムの結びつきは、本書にうっすらと危険な匂いを纏わせている。母親はこの世界で子どもを育てることに絶望し姿を消した、という設定にはじめは〈男の世界〉を書くため?と少し警戒したが、物語が進むにつれこの世界では真っ先に子どもと女が襲われ、あるいは武器を持った男に捨て置かれるのだということが描かれたので納得できた。男が女を蹂躙し尽くしたあとで、相対的に弱い男たちに矛先が向いた世界なのだ。秩序が崩壊したら男が女を狩り尽くすだろうというヴィジョンにはリアリティがある。単なるマチズモではない。 一方でこの父親のヒロイズムは息子を神格化することで成り立っている。それがまたもうひとつの危うさなのだが、彼が自死も掠奪も選ばなかったのは子がいたからなのは事実だ。はじめは純粋に庇護対象だった息子に「善き者であれ」と諭され、少しずつ親子の立場が反転していく。何もない世界でも子は育ち、父が教えていないはずの言葉を話し出す。だんだんと父を包む死の影が濃くなると、「いろんな心配をしなくちゃいけないのはお前じゃないからな」「ぼくだよ、それはぼくなんだよ」という印象深い言葉が交わされる。灰色の世界に生まれ落ち、父亡き後もここで生き続けなければならない子どものどうしようもない不安。父が子を守ろうとするのと同じかそれ以上の気持ちで、子が父の死を思い案じていたことに気がつく。そして父の力強さと対比になるような彼の優しさが、ずっと父を守ってきたことも。 父の死後、子は知らない神の代わりに父に祈る。私はここに至ってやっとこの物語が徹頭徹尾宗教の話をしていたことに思いあたった。元々ポストアポカリプスSFは世界の存在意義と倫理を問い直すものであるために宗教色が強くなりやすいと思うが、『ザ・ロード』はおそらく世界崩壊前から宗教的に暮らしていた人間が、神を信じられなくなった世界で息子をキリストのように崇めながらなんとか再び信仰へコミットしようと巡礼する物語を意図的に書いている。解説で66歳のときに生まれた息子との体験から書き出されたことを知ると、父と子で完結する信仰の描き方は少しナルシスティックにも思えるけれど、読んでいるあいだはとにかく夢中で文章にのめりこんでしまう、終末SFの傑作だった。 余談。私がこの小説を知ったのは東山彰良が『ブラックライダー』のインスパイア元として挙げていたからなんだけど、本書を読むと悪い意味じゃなく『ブラックライダー』は二次創作だったんだなと腑に落ちた。『ザ・ロード』では描かれない人肉を食べる側の視点、そして少年が辿り着くカルト教団側の視点に想像力を注いで書いたのだと思う。文体はウェットな『ブラックライダー』より、ルポルタージュ設定でドライな印象の『罪の終わり』のほうが近いかな。 アメリカの未来絵図という意味ではジョン・クロウリーの『エンジン・サマー』も思い出す。そういえば本書にかち割った自販機からコカコーラを取り出して飲むシーンがあるけど、『エンジン・サマー』にもたしかゴミの山でコーラ缶を見つけるシーンがあったような。『ブラックライダー』では人名になってるし。アメリカにとってのコカコーラって何なんだろう。
4投稿日: 2020.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ素晴らしい小説 父と子の物語、sfの皮を被っていますが継承の物語、人生の物語だと感じました 読みにくいですが読んで良かったと思える小説
1投稿日: 2020.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
核戦争(推測)後の荒廃しきった地球。生き残ったわずかな人間が略奪と食人を繰り返す中、人間の尊厳を守ろうとする父子のあてどない旅路。 「絶望」の描写が手を変え品を変えこれでもか、というくらい出てきて、ただただ怖い。だがページをめくる手を止められない。どうかこれ以上悪くならないで、と祈るよ うな気持ちで先を急いでしまう。重厚な内容にしてはかつてないくらいのスピードで読み終えた。小説の世界にどっぷりはまり込んでしまい、その夜はしばらく寝付けなかっ たほど。 病に冒された父は、幼い息子を一人この世界に残すことを憂う。息子は彼にとって神の言葉そのものだ。手にした拳銃には銃弾が一発。自分にできるのか?つらく苦しい旅 路の最中、幾度となく自問自答する。 結局、彼は息子を置いて一人で旅立つことを選ぶ。どうしようもなく絶望的な極限状態にあって、彼は息子の生に希望と未来を見出す。何の根拠もないか細い祈りのような ものかもしれないけど、愚かかもしれないけど、これはきっと人間の性なのだろう。
0投稿日: 2020.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログマッカーシーのピュリッツアー賞受賞作。終末の地球を歩く父と子の姿を、悲しみに満ちているが乾いた筆致で描いた。人類は自ら招いた恐怖と絶望を超えられるのかと、少年を通して語りかける。感動作。 父親と少年が、何もかも燃え尽きた地表を南に向かって歩いている。 理由は 訳者あとがきから 舞台はおそらく近未来のアメリカで、核戦争かなにかが原因で世界は破滅している。空は常に分厚い雲に覆われ、太陽は姿を現さず、どんどん寒くなっていく、地表には灰が積もり植物は枯死死、動物の姿を見ることはほとんどない。生き残った人々は飢え、無政府状態の中で凄惨な戦いを続けている。そんな死に満ちた暗澹たる終末世界を、父親と幼い息子がショッピングカートに荷物を積んで旅をしていく。寒冷化がいよいよ進み次の冬が越せそうにないため、暖かい南をめざしているのだ。 これで状況が十分説明されている。こうなった原因は語られず、現状の荒みきった地球、わずかに生き残った人たちも既に人でなくなっている世界。 分厚い灰が積もりその細かい塵が空に舞い上がり上空で雲になり雨を降らせる。日が差さず空が白んできたことで朝かもしれないと思う。 飢えた一握りの生き残りがお互いを食う。柔らかい人の肉をむさぼる。通り過ぎた後には略奪と破壊と死だけが残されている。 父親と少年は、持ち出した食料が尽きてくると、焼け残った家や小屋をあさる。少年は常に父に付き添い話しかける。 その声はこの世の、地球の生命が尽きようとしている中で、唯一人間らしい響きを残している。だが父親は少年の魂から出る声に従うことが出来ない。少年を死なせないためには、人らしい生き方など捨てなくてはならない。タダ生き伸びるために死力を尽くしている。 生き続けるためには、敵は殺さなくてはならない、銃はそのために離さない。弾が尽きるまで。 厳寒のなか海に浮かぶ廃船にも泳いでいく、厨房に何か残ってないだろうか。 父親は、火を炊かねばならない、そうしないと少年が凍える。 少年はいつも火を(と共にあり)運んでいる、善き人であろうとしている。 父は肺臓をやられ血を吐いている。死んでも息子を守らなくてはならない。 こうして、穢れのない少年の言葉が、汚れきり腐った道程に火を灯し、それに読者は同行する。 変化のない枯れた木立と燃え尽きたかっての家の残骸、焼死し打ち捨てられた人々を越えて、日々ただ暖かいだろう南に進んで歩き続ける。 食べられそうなものならどんなものでも食べ、泥水を漉してのみ、流れている黒い水の中に入って体を洗う、そんな光景に付き添う。 話の終わりまで変化のない道筋を、憑かれたように読んでしまう。 小さな出来事におびえ、拾ったり見つけてきたボロ毛布を体に巻きつけ、やっと南の海に来た。そこは黒く汚れた波が打ち寄せていたやはり死んだ海だった。 このまま長く生きていると世界はいずれ完全に失われてしまうだろうと思った。盲いたばかりの人の世界が徐々に死んでいくように全てがゆっくりと記憶から消えていくだろうと。 旅の途中で父親が思った、そんな風景の未来が見えた。 父は命がつきそうだった。 パパと一緒にいたいよ。 それは無理だ。 お願いだから。 駄目だ。お前は火を運ばなくちゃいけない。 どうやったらいいかわからないよ。 いやわかるはずだ。 ほんとにあるの?その火って? あるんだ。 何処にあるの?どこにあるのかぼく知らないよ。 いや知ってる。それはお前の中にある。前からずっとあった。パパには見える。 ぼくも一緒に連れてってよ。それはできない。 お前が話しかけてくれたらパパも話しかける。 ぼくに聞こえるの。 ああ聞こえる。話をしているところを思い浮かべながら話すんだそうすれば聞こえる。練習しなくちゃいけないぞ。諦めちゃいけない。わかったかい? わかった。 迷子になっても見つけてくれる、善意が見つけてくれるんだ。パパは言った。 少年は生き残りの人が近づいてくるのを見た。
1投稿日: 2019.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログリドリー・スコットの『悪の法則』を観て衝撃を受けたので、脚本を書いたコーマック・マッカーシーの小説を読もうと思った。 『ザ・ロード』は、多分戦争が原因で滅び、冷えていきつつある世界を、主人公の父と息子が、寒冷化から逃げるように南を目指して旅をするという話。 終末がテーマの映画や小説は数多あるが、これほど悲惨な終末世界の描写はなかなかないのではなかろうか。 そういう状況のなかで発生する善と悪の葛藤は、物理学でいうと加速器での実験のようなもので、善悪の素因数分解を試みているようにも感じられた。
0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ大きな何か(核平気だろうか…)が起きて世界が滅んでいる世界で、父と子が生きようと足掻く話。動物も植物も殆ど死に絶えており、残った食べ物などを奪い合ったのであろう、人は互いに殺し合っている。善だ神だなんて言っている場合ではなく、なかには人肉食も行われているケースもあるのだとか。 父はそんな世界において、自分の子どもに善を説く。子どもは世界が滅んだ後(ほぼ同時のようだ)に産み落とされ、善がまだしも意味を成していた頃のことは知らない。あくまで父から教え諭されたことにより、読者にとって違和感のない「常識」を持っていることになる。弱っている人がいたら助けてあげようとか、そういうこと。 ただし、それだけでは滅びた世界を生きていけないことも同時に知っている。子は、理想と現実の狭間で苦しむことになるのだ。もちろん、世界が滅びる前……この世界だって、理想と現実という対立は存在するのだが、それが非常に顕著な物語だといえる。 終末と家族というテーマでいうと、多和田葉子『献灯使』を思い出す。3.11を強く意識させる終末世界で、親や祖父世代が子どもに対しての懺悔の気持ちを強く抱いている世界。何か教訓を掬うとすれば、次の世代への責任からあまりにも目を背けてしまった人類への警鐘だろうか。そんな小説だった。 本作では、作者の国がキリスト教圏であることが関係しているのか知らないが、善の気持ちを受け継がせようと奮闘している父の姿が印象的だ。理由の一つとして、息子を健全に育てるという父の義務を己に課すことで、全てを諦めてしまいたい願望から自分を引きはがしているのだと思う。 しかし、善もへったくれもなくなってしまった世界において、子をこうやって育てることに本当に意味はあるのだろうかと、不安になる。生存を第一に考えなければいけない世界で、子の善意は見方によっては邪魔になる。善く生きることを志向して、善意に殺されることもあるだろう。効果的な人の殺し方でも教えておいた方が、生存率は高まるのではないか。もちろん、そうした人の心とでも美称されるような心を失うなら死んだも同然だ、という考えも分からないではないが。 だから、この小説を親子の愛の物語といった切り口では読めなかった。火を運ぶという比喩・名前の示されない父子といった独特の設定からは、物語をパーソナルなものに完結させない、人類の生きる道を描き上げようという意思があるのかなと思った。 なお、メチャクチャ読みにくかった。翻訳が悪いのか原文が悪いのか知らないが、この手の文体の本は二度と読みたくない。
1投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ文明社会が何らかの原因(核戦争?天変地異?)で破壊され、焼き尽くされた後の荒廃した世界。名も無い父子が南へと旅をする。読み取れる情報は断片的で、なぜこうなったのか、どうして旅をしているのか、それを読者が想像する事でより一層この世界の異様さが浮かび上がってくる。希望の見えない父子の旅、失望、絶望を覚えながらも生きるために歩みを進める。なんとか生き延びる。一体何のために?生き延びて何になるのか。そんな中で少年の痛いまでの純真さ。父親は自分の死を悟って、どんな気持ちで息子を見ていたのだろう。ひたすらに暗く、切ない。
2投稿日: 2019.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ恐らくは、核戦争による世界の破滅後に、僅かに生き残った人間の行動を想定した、絶望の世界の物語である。父と子(廃墟の中で生まれた少年)の儚い旅路。その苦難の果てに待ち構えていたのは、父を亡くした少年の新たな旅立ちだった。〝同じ境遇に置かれたとしたら〟などと、淡い幻想を思い巡らす暇さえ許されない、恐怖と戦慄のピュリッツア-賞受賞作。
0投稿日: 2019.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ核戦争か環境破壊のような天変地異が起こり、文明が崩壊した終末世界を描いた作品。 主人公の父親と少年は、冬を越すために南へ向かう。わずかな食料と生活用具を乗せたショッピングカートと残り2発の弾丸が入ったリボルバーだけが父子を守る唯一の所持品。 父子は廃墟になった家屋から食べられそうな物を物色し、彼らと同じように生き残った者達から身を隠す。彼らに捕まれば、殺されて食われるか。 運が良ければ逃げ切れるかもしれない。 父子は何度も餓死しそうになりながらも南へ向かう。しかし、父は病を患い、長くは生きられないだろう。その時が来たら少年には手順を伝えてある。拳銃を口に咥え、思いっきり引き金を引くのだと。 動植物のほとんどは死に絶え、地上には緑はなく、灰が降り積もる色の死んだ土地が続くばかり。川は涸れ、黒く変色した液体がわずかに流れる。 わずかに残った人間は、お互いの所持品を奪い合い、負けた者は殺されその場で食べられるか、奴隷にされ、生きる食料となる。 父子は、自らを『火を運ぶ、善き者』と自認し、相手の所持品は奪っても、決して殺して人肉は食べない。しかし、父の命はまさに尽きようとしている。 まさに『マッドマックス2』や『北斗の拳』を地で行く小説である。いや、さらに悪い状況かも知れない。これほど酷い状況で生きる人間達を描いた小説は読んだことがなかった。 それでも父子は希望を捨てず、最後まで生きようとする。 自分ならば、ここまでできただろうか、たぶん一人では無理だろう。守るべき家族がいたからこそ、ここまでできるのだ。 ただ、このような世界で生きたいとは思わないし、このような世界に決してこの世界をしてはいけないのだと改めて思う。 この小説はあらゆる人に、特に世界のリーダー達に是非読んでもらいたい。自分の子供や孫にこのような経験をさせたくないのならば。 それにしても、目を覆うようなあまりにも酷い状況を美しい文体で表現するこの文章。さすがアメリカ現代文学の巨匠が、世界の終わりを放浪する父子の姿を描きあげた長篇。ピュリッツァー賞受賞作である。
7投稿日: 2019.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ怖いです。今、世界の均衡が崩れて世界大戦が起こったら、きっとこうなるな…というリアルな予想図です。 地球環境が破壊され、太陽の光は届かず、一切の動植物が死に絶えた世界で、生き残った人間達が残された食料品や文明の遺物を漁りながらサバイバルを繰り広げている。こんな世界でのサバイバルに私は絶対耐えられない……。 多くの人間達がただ生き延びる事に汲々としているなかで、主人公の父と息子は、互いの存在によって何とか理性をつなぎ止めている。正直、未来は明るくない。それでも、地球が人間の破壊の影響から回復して元の状態に戻るまでの間(戻るのかはわからないが)、何としても人間の理性をつなぎ止め、それを継承していくのだ。がんばれ人間。おろかな人間達……。
0投稿日: 2018.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ"本の雑誌40年の40冊”から。これは素晴らしい。のっけからただひたすら、淡々と父子2人の道中が描かれているだけだし、会話分も全部地続きだし、舞台も荒涼たる新世界だし、ともすれば地味なだけに陥ってしまうかもしれないところ。そこを表現の緻密さとかで緊張感に変換して、かつそれを終始維持することに成功している。漫画や映画と親和性の高い世界観だから、殺伐としているとはいえ、自分の中で映像化しやすいのかも。特に後半とか、結末が気になって仕方なく、途中で止められませんでした。コーマックの他作品たちにも是非触れてみたいです。
2投稿日: 2018.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
核戦争か何かが起きた世界、灰で覆われ、無政府状態。秩序がなく、食糧や生きるための道具を奪い合う世界。こんな中父と子どもが二人でカートを引きながら、ひたすら歩き続ける物語。こんな状態になったら自分は絶望するだろうか、それとも何か希望を見つけられるだろうか。
0投稿日: 2018.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「バーナード嬢」で気になっていて、店頭で見つけた際に購入。 句点がない文体が読みにくかった。 世界がどの程度崩壊しているのか、どこかにまともな人間のコミュニティがあるのかどうか、最後までわからないまま。一応、最後にまともそうな人間に出会ったところで終わるが、息子があとどれくらい生き延びられるのかはわからないままで、ラストをどう受け止めていいものかわからず。 父親がギリギリまで息子のために命を削り続けた姿に静かな感動がある。 ひたすら廃墟の中を進む情景と、破滅途中の断片的なエピソードが、神話的な雰囲気で、終末ものとしてとても良かった。
0投稿日: 2018.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ機会がなければ読了することはなかったかもしれない。しかし、物語を読み終えた時、読んでよかったと思った。破滅を迎えた世界を父と子が旅する物語。大岡昇平「野火」のシチュエーションやドストエフスキー「カラマーゾフの兄弟」の三男などが読んでいてよぎった。描かれているのは新しい芽生えを否定された希望のない世界。自然が完全に人にそっぽを向いた世界。もはや何も与えるものがない世界というのは大岡昇平の「野火」よりヒドイ感じがした。丁寧に描かれる世界にある限られたもの。色々な事を考えさせられた。又、色々なことを考えられる場面、世界をこの読書を通してひとつ得た気がする。
0投稿日: 2017.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ核戦争か何かでの文明崩壊後、分厚い雲に覆われた世界は寒冷化が進行して冬を越せそうにない。 父親と息子は生きるために、ひたすら南を目指す。 道中では人間性を失った人工物の数々、奪い合うために殺し合った痕跡、酷いものばかりしか目に映らない。 「私たちは善い人だ」 そう諭して、息子が目にしたことのない世界の話をして、先へと進む。 "私たちは火を運んでいる"という比喩が度々使われる。 火とはは何かの解釈が解説でも検証されているが、俺はそれを"人間性"だと考える。 幼い子供は世界を知らない。ゆえに純真無垢な存在だ。しかし、物語の世界では稀有な存在だ。 人間性を無くした悪ばかりの世界で、善たる子供は人間性という火を運ぶ。 フッと息を吹きかければ簡単に消えてしまうそれを、喪うことのないよう父親は息子に託す。 果たして父親は善なのか。息子を守るために他人が死につながる行動をすることもある。 父親が火を灯し続けていられたのは、息子に自らの火を移すため。 なれば、ラストシーンで父親はやりきったことになる。 ひたすらに陰鬱な描写が連続し、ひたすら二人が歩き続けるだけの小説だ。 緻密に嫌になるほどに文明崩壊後の世界を細かく書くことで、人間性とは何かを問いかける。
2投稿日: 2017.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017/08/18/Fri.(ブックオフにて中古で購入) 2017/08/20/Sun.〜09/07/Thu. 施川ユウキ『バーナード嬢曰く。』の第2巻を読んだ時に興味をもち、ずっと読んでみたいと思ってた一冊。 暗くて寒い世界。灰と泥にまみれた世界。人を食べるやつもいる。 なのに、物語には不思議と品格を感じる。 この読後感を上手に書き表すことはできないけど、他の小説では味わえない余韻に浸れる。
0投稿日: 2017.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2017/06/29 順番は逆だが、19XX年の様な時代。何かによって滅びたあとの世界。 南へと旅する父と子の話。 今の私達がゼロだとすると、彼らは決してゼロ以上にはならない。 父のおとぎ話を子が継承する? 食料があるときにゲットできそうならどうなるか見たかった
0投稿日: 2017.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カートを押す父と息子がひたすら道を歩く。日々の食料を求め。南へ。海へ。 憩える場所は容易く襲われてしまうから、カートに載せられるだけの荷物に絞りつつ。 核だか彗星だかの災厄ののち、世界は灰に覆われ。 荒涼。寒気。木も死に。動物もいない。そこここに炭化した死体。夜は真の闇。 滅びゆく、というか、すでに滅んだ星で、残された少数の人間は、互いに係らず、助け合わず。互いに脅えあっているのだ。 人を食べるか食べないか。略奪するかしないか。レイプ。殺人。(を怖れて妻は……。)(マッドマックス。北斗の拳。子連れ狼。バイオレンスジャック。ブラックライダー。) ふたりで生き延びるには人を助けてはいられないと父は断言する。 息子はそれをわかっていてもしかし、それでも助けてあげられないかと問う。 カタストロフィの後に生まれた子を護るために、父は鬼にもなる。このトーンに変動はない。 繰り返される「ここで待っていろ。いなくなりはしない」。不安な子供。 強盗を警戒し、残弾を気にしながら拳銃で倒す。 しかし時折り心が折れそうになり、もう生きていたくないとも思う。(が、息子に漏らしたりはしない。) とはいえ、息子は父がいなければ生きていけない、父は息子がいなければ生きる意味がない。 筋に大きな劇はない。 淡々と移動。場所の調査。食べ物の確保。他人への警戒。「善い人々」との出会いを期待しつつ。 繰り返しの中で一貫するのは、親子の語る「火を運ぶこと」。 善意。尊厳。善さ。尊さ。人間らしさ。あたたかさ。輝き。その反面、世界を滅ぼした文明でもある。つまりはプロメテウス。 ロードムービー→ロードノベル→アメリカならではのフロンティアスピリット→ウェスタン。 カギカッコのない会話・読点が排除された文体から醸されるのは、詩的、象徴的、寓意的、原初的、神話的な描写水準。 細かいところは描写されるが、全体はまったく靄に包まれたまま。 だからこそサバイバルという極めてミクロな視点を保ちながらも、抽象的で幻想的な話にも見える。ここにポエジーが生じる。 最後まで、父は絶対に息子に絶望を語らなかった。 だからこそ保たれた少年の「善さ」。世界の実相を見てしまった上での。 父は息子の肉体だけでなく魂をも守ろうとした。 本当に少年の無垢が世界を救うのかもしれない。 母を思わせる女性に抱き留められる少年の姿は、作者が描かざるを得なかった救い。 安直でどうかと考えることもできるが、最低限親として、放りっぱなしにはできなかったのでは。
1投稿日: 2017.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ荒廃した世界。灰色の世界で夜は暗く寒い。殺人者や略奪者が多く、誰も信用できない。そんな世界を父と子の二人が南へ歩いていく。 他人を信用しない、慎重な父と、純粋で他人を助けたいと思う子ども。 どちらの行動、思考にも一理あって考えさせられた。 ラストが好き。
0投稿日: 2017.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ父と子がカートに荷物を積んで荒廃した世界(「The Walking Dead」みたいな、でもゾンビはでてこないけどね)を生き抜く。 本を読んでから、映画化になっているのを知ってYouTubeで映画の予告を見た 映像化になってもなかなか良さげな感じ DVDが出てるので機会があれば見てみたい 小池昌代さんの解説がすんばらしかった 解説だけ何度も読み返した 読み応えのある解説はうれしいな ☆4.5
0投稿日: 2016.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
過酷な状況の中で人間の持つ「善さ」を体現する子供。ムイシュキン公爵のような無垢な存在。こんな子供は普通にいないが、なぜか実在感が高く、自分の子供とかわらなく感じる。 なぜラストに、父親が死んだとたんに、救う人間がでてくるのか、しばらく子供が苦悩してから出てきた方が、リアリティもあるし、救う人たちのありがたみもわかるはずなのに。
0投稿日: 2016.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代アメリカ文学のロードナラティブ。 SFとロードの融合は去年見た映画のマッドマックスを彷彿とさせられた。 この一冊に出会えてよかった。 作者についてもっと知りたいと思えた。
0投稿日: 2016.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ何らかの大災害によって滅びた後の世界を、父と息子が道に沿って歩いて旅をする話。死者の残していった食料や衣服、死んだ木々や灰の混じった水といった、死んだものたちを親子は糧にして「火を運ぶ」。鳥のように直線距離で進むのではなく、道の上をさまよいながら。 乾いた文体、カギカッコの付かない詩的な会話文、読点がほぼ排除された地の文、滅びた世界に関する詳細な描写によって、生きることが絶望であるような残酷な世界観にどっぷり浸ることができた。 私はちょうど「マッドマックス 怒りのデスロード」を見たばかりなので、この本の読後感はその映画を見たときと同じような感覚だった。 聖書や何らかの比喩には疎いのでそのあたりのメッセージ性は私には分からなかったが、少年の善性に心が潤され、滅びた世界の絶望感も心地が良かった。
0投稿日: 2015.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ廃墟を親子で彷徨い、父親が死に、また子どもが彷徨うという話である。映画化されたとあるが、日本で上映されたであろうか? 再度読んだが前に読んだことを全く覚えていなかったのはそれだけ印象が薄かったからなのだろうか。 6月にマッカーシーが死亡して、その追悼文が新聞に掲載されたので、再度読んだ。 本棚の検索ではザ・ロードやロードの検索ではヒットせずに、マッカーシーでヒットした。カタカナの本の名前では検索できないというアルゴリズムのバグがあるのかもしれないし、・が入る検索はできないのなのかもしれない。
0投稿日: 2015.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ二人のセリフは多くを語っていないが、それでこそ文字通りの意味ではなく深みに潜む本心や疑問を考えさせられる。場面設定も多くのことが捨象されている。なぜ世界は荒廃しているのか、母はどうしているのか、向かう先に何があるのか、なぜ二人は生き残っているのか。あらゆることを捨象することで二人の関係性がより浮かび上がり、二人を取り巻く世界が無限に広がる途方もなさを感じさせる。自分は無限に絶望を感じたが。
0投稿日: 2015.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ終末を迎えようとしている世界で、父親と子供が南を目指して進んでいく。ほとんど絶望しかなく、あたたかいのは親子愛だけ。ラストは涙が止まらなかった。それがどういう涙なのかは読んでみてください。いつかくるであろう終末に備えなくてはと思った。今の地球がこうならない保証はない。
0投稿日: 2015.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ終末後の世界をただひたすらさまよう、父と息子の親子二人の話。 その日を生きれるかどうかもわからない日々を送る様子が語られる。親子の会話で成り立っている物語といえる。不思議な話。最後はよかったのか救われたのかよくわからないまま結末となる。
0投稿日: 2014.09.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ父の視点。息子の視点。2つの視点で感情移入をしながら読んだ。物語が終わった時に感じたのは、一言で言い表すことができない温かなものが、父から子へと間違いなく伝えられたという確信だった。そんなすばらしい場面に立ち会った気にさせられる物語。
0投稿日: 2014.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
映画化によって話題になっていた2010年に、シンガポールの日本人向け本屋で購入。しかし、途中であまりにも読むのがつらくなって、読み終わったのは2014年・・・と言う感じで随分時間がかかった(あきらかにかかりすぎ)。 本書の舞台となるのは、おそらく核戦争により人類のほとんどが死滅してしまった後の北米大陸。主人公の男性は息子とともに、「火を届ける」という漠然とした言葉とともに、南の海岸へと向かう。すでに荒廃しきったこの世界では、飲み物や食べ物をめぐって他の人間との争いがあり、人食も行われている。そういった「枯れ切った」世界を主人公と息子はひたすら歩き続ける。 日本のゲームやファンタジーとともに育った僕は「読み進めれば、この世界がこうなってしまった」理由がわかるのでは、と期待をするのだが、その期待はエンディングまで満たされずに終わる。世界がなぜこうなったかという「大きな物語」にはいっさい触れられず、父親は病死をし、息子は道行く家族に拾われ旅を続ける・・・というのが本書の結末だ。 カテゴリとしては本書をSFに分類したが、これはかなり強引なカテゴリわけで、実際には「文学」とするのが正しいと思う。宗教的なテーマや訳文越しであっても伝わってくる美しい文章は、読者をまるでその世界で主人公と一緒に旅をしているような気分にさせてくれる。 一方でSFやミステリのようなカタルシスとは最後まで無縁の作品でもある。映画版は見ていないのだが、精神的に元気なときでないと、とてもではないが見る気にはなれない。そういう意味で読み手を強く選ぶ作品であると思う。
0投稿日: 2014.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、「天地明察」の冲方丁さんがTV番組で紹介していた1冊。SFだと思ってましたが、これは何になるんでしょうか? 何らかの原因により、消失し灰で覆われた世界を息子と二人、「火」を運びながら何かを求めて旅をします。 ここで言う「火」とは、心とか魂とか、そう言う感じのもの。太陽も霞んでいる世界は、暗くどこにあるか分からない未来。もうどこにも無いかもしれない希望を探して、息子を守りながら、ひたすら歩き続ける。 上手く表現出来ませんが、この暗いストーリーがなのに、なぜ惹きこまれるのか・・・不思議です。 2007年ピュリッツァー賞を受賞した、ベストセラーだそうです。知らなかった。 暗い絶望の中で、自分を貶める事無く、諦めない。 このレビューを書く事で、この本の良さが整理出来た気がします。
0投稿日: 2014.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の終わりを描いた小説ということだけ知っていたので、てっきりエンターテイメント小説かと思いきや、これは紛れもない純文学だった。 何らかの原因で文明が崩壊した世界を旅する親子の物語。秩序もなにもかもが崩壊した過酷な世界で生きるために淡々と旅を続けるんだけど、少年の純粋で無垢な心があまりにも痛々しい。しかし、物語のラストではもしかしたら、この少年の純粋さがこの荒廃した世界を救うのではないか?と少し感じさせることができた。 少し重たい物語だけど、文学作品としてとても優れたものだと思った。
0投稿日: 2014.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ映画「悪の法則」を見て、さらにこの作品でピュリッツアー賞受賞しているということで読んでみた。 「悪の法則」もそうだったけど、理由なんか必要無し、淡々と語られ始める究極のハードボイルド 歩き続ける父と息子。 生きていく希望もほとんどなく、息子だけが支えになっている父。 息子がいなければ、自殺しているかもしれないし、略奪者になっているかもしれない。 場面は究極だけど、自分にとっての子どもってのも、そういう所があると思う。 最後がわずかだけど希望へとつながるストーリーになっている点だけが救い。
0投稿日: 2013.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ燃え尽きた世界。灰に覆われた世界。南を、海岸を目指す少年と父親。善いもの。火を運んでいる。頭に入れたものはずっとそこに残る。
0投稿日: 2013.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ父と息子の愛、父から息子へ受け継がれていくものの話。 焼け跡以外何も無い終末世界だからこそ父と息子の関係の描写が研ぎ澄まされる。 尋常じゃない過酷な終末世界描写の中にあってすらほのぼのとしてしまう息子の可愛さに父の愛情の深さがわかる。 物語は一歩一歩旅を進める親子と同じように進みが遅い。傾斜のゆるい螺旋階段の様にループしながらちょっとずつ上に上がって行く。 何らかの災いで一瞬にして破滅してしまった世界という舞台の作りこみが凄いところにSFとしての面白さがある。「核戦争後」ではないところが、よくある世界観にならず興味を引き付けて読み進めさせる推進力にもなっている。
0投稿日: 2013.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ読んでいる間中、痛みで身が引き裂かれる思いだった。文明が崩壊した後のアメリカ、動植物は死に絶え人々は互いの肉を貪り食う世界。灰色の景色を父子は互いを支えとしながら、極限状態の道程を歩んでいく。読点を排した文体は息苦しさを掻き立てられ、括弧のない会話文はか細い吐息が音色を立てている様だ。人間が人間でいられない世界の中でも、人間であり続られる事を本作は示している…が、家族の遺品として読むには余りにも辛過ぎる内容だった。それでもラストには欠片の程の希望を感じることが出来たし、たぶん今はそれぐらいで丁度良いから。
0投稿日: 2013.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ灰ともやに包まれた死に行く世界を旅する親子の物語。 「この灰ともやに包まれている」という構造は物語自体のものでもある。 手元ははっきり見える。 しかし、遠くを見ようとすると途端にはっきりしなくなる。 たとえば、船からコンロを取り外そうとするシーンがある。 その行為は非常に細かく描写される。 しかし、この世界に何が起こったのか、それからどれだけの時間が 経過したのか、ここはどこなのかについての描写はほとんどない。 そのため、物語全体を見通すことができない。 常に目の前のことしかわからない。 親子も、小説を読んでいる私たちも。 そして、そこに作者独特の文章構造が加わる。 いわゆる地の文にそのまま会話文を入れるのだ。 少し抜粋すると 足を止めて少年を振り返った。少年は立ち止まって待った。 もう死ぬと思ってるだろう。 わかんない。 死にはしないよ。 わかった。 みたいな感じ。 読んでいると非常に不思議な感覚にとらわれる。 物語に溶け込んでいく感覚? 取り込まれていく感覚? そして、あの世界はもしかしたら、私たちの世界とそれほど離れた場所に あるのではなく、実はすぐそばにあるのではないかと感じさせられる。 なにしろ、何があったかはわからないのだ。 「彼」もそのときまでは普通の生活を送っていたはずだ。 なにかが起こり、彼はあの世界に放り込まれた。 私たちに同じ事が起きないと言い切れるだろうか。 具体的に様々な事を描きながら、同時に非常に抽象性の高い幻想的な 物語になっていると思う。 面白かったです。
1投稿日: 2013.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ何かが起こって終わりの寸前まで行ってしまった地球上、父と息子が銃を手に山や道路をただひたすらに歩いて生き延びようとする物語。 私が苦手とする緊急時ならではのヒステリックな愛の要素はなく、驚くほどたんたんと、父として平常を一度も経験したことのない息子をどのように育てるのかという苦労や温かい親子の言葉のやりとりが綴られている。 「火を運ぶもの」=人間としての大切なもの、を意味していて、それは善意だとか尊厳だとかそういうものだと思うんだけど、こんな緊急時にあんなに良い息子に育ててお父さんあっぱれです。息子がずっと火を手放さないことを祈る。
1投稿日: 2013.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ核戦争か何かにより荒廃しきった世界を、父と子が孤独に南を目指して歩き続ける。 道中、廃墟となった家々から食料などを頂戴する。 たまに遭遇する他の生存者に対しては、善なる者か悪者か慎重に探り、時に銃で脅し、時に無視し、やり過ごす。 この世の終わりを描きつつも、幼い子に託された「火」が受け継がれていくことで、新たな世界の静かで暗い始まりをも感じさせる。 物語としてはあまりおもしろくなかったのが正直なところ。
0投稿日: 2012.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
読後、悪い夢を見終わった感じがした…。 人類終末の最悪のパターンなんだろうけど、本当にありそうで。そして自分が主人公だったらこの時どうするだろう?とグルグルします。 独特の文体と暗い内容。なのに、何度か読み直したくなる一冊。
0投稿日: 2012.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ二巡目。ラストシーン手前で子供の個性がぐっと引き立ってくるように見える。これは末日以降の世界で、善の強い心が育って行く物語なのかも。マッカーシーの中でもこれほど情愛の側面が豊かな作品はなかなか無いと思う。
0投稿日: 2012.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ピュリッツァー賞を受賞し映画にもなった、終末世界を描いたSF作品。死に満ちた暗澹たる破滅後の、生き残った人々が闘争を繰り広げる世界を、暖かい南を目指して旅をする父と子の物語。極限状態で人間らしい優しさを維持できるかをテーマに、それ以上に父の子に対するあたりまえの父性愛が、そしていつかは立って一人で歩んで行かなければならない人の強さが全面に描かれる。人を殺すことも厭わず、鬼になる覚悟で息子を守る父の、子供を思うただひたすらの親の気持ちは「ダンサー・イン・ザ・ダーク」「サラエボの花」の母たちの想いに通じる。感動の親子愛という作品に留まらない、少し重くも感じられそうだが、一方的でもある子供への親の想いを感じることができた作品。
0投稿日: 2012.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログH24.3.26 どこかで暗転するのか明転するのかと思って読み進めたが、ずっと同じテンション・・ 感触や匂いなどがリアルに感じられるため、飽きはないが、ずっと重く残るものがある。 “男”と“少年”という人称が、神話的な世界観を表すのに役に立っているのかな? 少年も旅を通して成長し、男は少年を次のステップに引き渡す役目を終えたかのように息を引き取る。 あぁ、男は少年の父親ではなかったのか?このようにして、この少年(とこの少年の持つ希望)を引き渡す役目を持った男にすぎなかったのか。 旅が終わって、始まった。
0投稿日: 2012.03.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨年最後に読んだ本。どうして冬に、こう世界の終り的なものを読みたくなるのだろう。村上春樹が「退屈です」と言っていたように非常に退屈です(けなる意味ではなくて)。オチも自分は正直良く分からなかった。でも好き。そんな小説です。 若干高橋しんにマンガ化してほしいようなしてほしくないような(サイカノは好きではないですが)。
0投稿日: 2012.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ重く灰に閉ざされた終末の世界を、父と息子が生きるために歩き続ける物語。 描き出される世界は圧倒的な質量を持って読者に投げかけられ、私たちもその世界の中を父子と共に歩き体験しなければなりません。 読者に受け止めさせ、眺めさせ、判断を下させる作品でした。 すごい、です。
0投稿日: 2011.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ灰が降って荒廃した道をショッピングカートを押しながら南に向かうことになったのか、読み手である私のなぜ?という疑問ははれることがなく、とにかく父親と息子二人で必死に生き抜かなくてはと移動する話。死んでしまった者勝ちではないかと言いたくなる世界ではありますが、天使のような子どもの存在にだけ救いがあるようでした。
0投稿日: 2011.09.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ荒廃した世界で、父と子が強盗や空腹と戦いながらただただ南を目指して道を進む物語。 これ以上ないほどシンプルで無骨で、率直な作風。 一気に読める。 いまいち心に入ってこなくて☆3にしてしまったが、自分に子どもがいたらまったく受け取り方が違っていただろうと感じる。またはもっと幼ければ、逆の視点で受け取れていただろう。 なんだかものすごく半端な時期に読んでしまったせいで面白さを掴みきれていないような感触が自分の中にあって、猛省しとります。 子どもが生まれたらもう一度読もうと思う。
0投稿日: 2011.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログコーマック・マッカーシー著 ザ・ロ-ド読了。お正月休みに読んだ本年の一冊目であります。 全てが荒廃し、灰となってしまった「事後の世界」。ひたすら南を目指して歩き続ける父子の物語。「事後の世界」とは何を意味するのかについては物語では明示されていないものの、恐らく核戦争か何か人為的なキャタストロフの果てを連想させる。 「事後」数年は経過したと思われるその世界では法の秩序は既に崩壊しており、生きるために「レイプ」「人肉食」「強奪」「殺人」などあらゆる「悪」が蔓延る。日に日に輝きを薄めていく幽かな太陽はその姿を見せることは無く、風雨、雷、雪が吹きすさぶ絶望的な世界である。 自らを「火を運ぶ者たち」と称する主人公の父子は生きる為にあらゆるサバイバル術を駆使して、ひたすら南を目指して道なき道を進んでいく。「火」はさしずめ「人間の尊厳と心」を意味するのであろうか?何度も死と直面しながらも、人間としての心を失う事無く生き抜こうとする父子の姿には、残念ながら決して「希望」を感じる事はついぞ出来なかった。 「人間は何の為に生きるのであろうか?」という根源的な命題を深く考えさせられた一冊であった。我輩も日々、より快適な生活がしたい、美味しいらーめんをもっと食べたいなど、豊潤な物に溢れる贅沢な社会の中で生きている。唯「生きる」という事のみが目的となった世界では生き抜く気力が果たして生まれて来るものであろうか? 本作は現代アメリカ文学を代表する重鎮による長編SF作品でありますが、近年の東アジアを取り巻く緊張状態などを考えると、決してSFの世界と割り切る事が出来ないのではないか?とも感じたのであります。 新年に読むにはちょっと重すぎた一冊でしたかね。本作は既に映画化されて、昨年夏日本でも公開されているらしい。DVD、BDも発売されているようなので、今度是非とも映像でも味わってみたいものであります。 【Dance1988の日記】 http://d.hatena.ne.jp/Dance1988/20110102
0投稿日: 2011.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログそれでも前へ・・・。大切なものを守るものと自立していくもの。強く生きる物語だと思いました。文庫の装丁もイメージにぴったり
0投稿日: 2011.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ何もかもが灰で覆われた世界(終末思想)が舞台のとっても重い物語。暗い。 生き残った父子がひたすら暖かいであろう南を目指すという内容。 この父親はどんなに絶望的な状況の中でも、息子にだけは希望を与え続けようとする。どうしても。 父子愛に満ちた哀しい小説。
0投稿日: 2011.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ彼は既にメキシコすら目指してはいない。何もないことが分かっている先に向かって、ただひたすら生き、歩き続ける。世界を焼き尽くした火を目の当たりにしながら、それでも最後の火を消さないように消さないように守りながら。彼らの行く手には絶望が横たわっているだけなのを分かっていながら。頼りない光が見えてくる日は果たして来るのだろうか。ただ、父は言う、歩け、歩き続けよ、と。
0投稿日: 2011.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ帯巻にあったコピー「父には息子が、息子には父が全てだった。それぞれが、相手の全世界となって――。」 これで、購入しました。まだ、36ページ。
0投稿日: 2011.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ良い本だとは思うのですが、ダメでした。 荒廃した世界を旅する父と子の愛情の物語です。 そんな世界の中でさえ、純粋さを失わない子供の姿は見事だし、父親の愛情も素晴らしい。 しかし、どこか私の期待とズレてしまったのです。 何故こんな世界になってしまったのかが明かされるはず。最後には何か大きな転機が起こり、物語が大きく動くだろう。そんな事を思いながら読んでいたのです。もちろん私の勝手な期待なのですが。 物語は父親と少年のエピソードを積み重ねながら大団円に向かいます。最後にはそれなりの転機があるのですが、最後まで父と子供の愛情物語に終始します。 Amazonなんかを見るとほぼ絶賛なんですけどね、私には合わなかった。。。
0投稿日: 2011.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界が終わりを迎えた時に何が起きるか。この想像力は文化によって違うようだ。アメリカはとくに、終末思想が強い。日本ではなかなか生まれないだろう。
0投稿日: 2010.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ物語の世界観にはまると一気に読んでしまう。荒廃した世の中が舞台だが、その中で父親と息子の相互愛が一筋の光のように見え、美しく感じられた。
0投稿日: 2010.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ某ミュージシャンの影響で手にとってみた。圧倒された。 まず、世界観に文体があってる。荒廃した灰色の大地が文章からも想起される。かさついてざらついた、どんより滲む空が延々と続く世界。 暗い澱んだ世界を、ひたすら進む父と息子。息子の存在が、父にとっては「絶望の中にある一筋の希望の光」なのだろうなあ。淡々とした会話が、詩のように挟まれるのが印象的。 好みは分かれるだろうし、読むのに気力が必要だけれど、私はとても好きだ。
0投稿日: 2010.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきにあるとおりマッドマックス2、北斗の拳のような世界観からするとSFである。 しかし、犯罪が犯罪と定義されないぐらいに荒れ果てた状況下での育てる為に親子関係を描いたストーリー。非常に文学的。 何か爽快な感じはないがズシリと来る作品
0投稿日: 2010.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の方に差し掛かって帰着駅に着いた僕は駅のベンチに座り込み最後迄読まずに居られんかった。家まで待てなかった。 父親は強風の中、掻き消えそうなろうそくの火のような善という価値観を守り切ったのだと思う。
0投稿日: 2010.07.27
