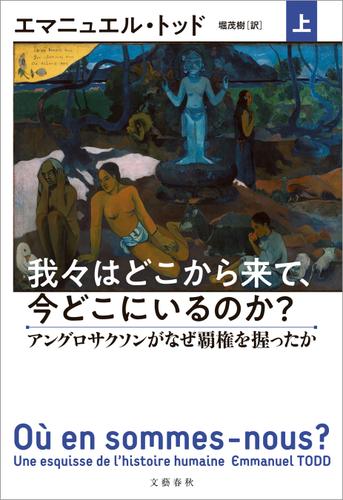
総合評価
(13件)| 2 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族構造や宗教そして教育という、我々の心理を深い次元で司る要素の分析を通して、それぞれの国の政治や経済がなぜ現在のようになっているのかを読み解く書である。無意識・下意識の階層にある何かが、目に見えるものを支配しているという考えには、大いに納得できるものがあった。 核家族か共同体家族かあるいは直系家族か、という言い回しが数多く登場する。核家族はホモ・サピエンスの原初的家族形態であり、むしろ直系家族のほうが最新なのである。ただ、絶対的な核家族は、創造的破壊が非常に得意である一方、技術や知識の継承という観点で直系家族に劣る側面がある。産業面で成功している中国・インド・日本・ドイツを観れば頷ける主張である。 ここに兄弟間の平等性・女性のステータス・父方居住かというファクターで細分化したのち、出生率・識字化のタイミングなどで国力の推移を分析することで各国の政治・経済のダイナミズムを考えていく。アメリカの創造性と野蛮性の混在の正体を暴いた10章は特に面白かった。 正直、内容理解は20パーセントほどしか進まなかった。文章自体は難解ではないが、主張を理解するのに時間がかかりそうだったため、飛ばして読まざるを得なかった。下巻は日本やドイツに触れるため、まずはここまで読み切ってしまいたい。
0投稿日: 2025.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ・家族類型 相続が自由、あるいは、平等的な同居を伴わない絶対核家族、平等核家族→英語圏 同居を伴う父方居住、母方居住、双方居住 直系家族(父方居住) 長男がほとんど相続する→日本、ドイツ 直系家族(そうしょ居住) 直系家族(母方居住) 外婚制共同体家族 男が平等に相続をし、外婚制 →中国、ロシア 内婚制共同体家族 →アラブ圏 ・核家族は人類史の原始的な形であり、社会の要請に応じて父系の共同体家族へ複雑化していった ・経済や社会システムは短期間に変わるが、家族類型は長く変わらない
0投稿日: 2025.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ過去課題本。本書がベストセラーだったときに、その流れで課題本になったと思われる。「家族制度から政治が見える」と本書は主張しているようだが、論理展開に強引な印象を受けた。
0投稿日: 2024.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログいや、むずかしくて読めない。あきらめる。前書きだけでも勉強になるかも。つまり、資本主義の罪悪はもう結果が見えてる、とか。
0投稿日: 2024.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログエマニュエル・トッドは乳幼児死亡率に着眼してソ連崩壊を予言した事で有名な歴史学者だが、その著者が、家族形態に注目し、覇権国との因果関係を探る本。序盤、核家族などの家族形態と文明の発展等の結びつきがピンと来なくて読み難い感じがしたが、識字率の解説などから一気に面白くなる。 集団が物理的、地理的条件から自然発生的に生じ、自他の区別は後付けで発生したと考えるのが無理のない解釈のように思う。地球の真反対に住む集団が繋がっているとは到底思えない。そこでは言語も風習も、恐らくは見た目も異なる。だから、元々一つだった集団が敢えて利権構造によって区別するために言語や風習を違えたというよりも、同族として認識不可能なほど差がある集団同士が、自ずと別物として認識し合う状態ができたのだろう。 ー 紀元後二〇〇年頃のことである。「ミシュナー」(ユダヤ教の口伝律法をヘブライ語で編集した文献。のちに「タルムード」の基礎を成す本文となった)に定着するかたちで、ユダヤ民族への帰属は母親から継承するという、たいへんよく知られた規則が現れた。これを根拠として、ユダヤ教が母系制へと推移したと想像するのは容易であろう。そして、その推移は、中東でどんどん拡がっていた父系制に対する反動だった。 その意味で、母系制が父系制に反動として広まったという考え方は、良くわからない。日本でも女系天皇に対する反対意見はあるが、これは今までのやり方を継続する慣性への拘り(それに対する遺伝子レベルでの論拠は後付けか)であって、それらの拘りが各国であるのは、他国を意識した結果ではないと思うが。一方で、識字率の話は説得力がある。 ー その結果のうち、ユダヤ人と非ユダヤ人のそれぞれの識字率を比較してみよう。ロシア帝国の全人口中での10歳以上の男子の識字率は28%だったが、それをユダヤ民族に限定し、読むのはイディッシュ語のヘブライ文字でもロシア語の文字でも構わないとすると、数値が65%まで上昇する。1837年以前に生まれた、当時60歳以上の人口に注目すると、原初的なユダヤ文化にもう少し近づくことができ、その不完全さや父系的な教育の偏りをも垣間見ることができる。男性の識字率は54%だったのに対し、女性のそれはわずか15%にとどまっていた。このデータが示唆する世界は、紀元後一世紀に大祭司ジョシュア・ベン・ガムラが夢見た世界に近いのではないだろうか。次章の主なテーマはドイツとプロテスタンティズムの宗教改革だが、私はそれに加えて、人類を全体として見たときの識字化プロセスにも言及するだろう。 ー それでもユダヤ教は、未分化核家族モデルの機能の仕方を変えなかったわけではない。古代ではまったくオリジナルだった禁止、すなわち堕胎の禁止と嬰児殺しの禁止を導入したのだ。旧約聖書ははっきりと出産奨励主義で、ホモ・サピエンスのプラグマティックな態度と袂を分かっている。ホモ・サピエンスのほうは、ごく自然にマルサス的(人口制限論的)で、人口と食糧のバランスでものを考え、食糧調達因難な場合には「汝、殺すなかれ」といった掟に縛られる気持ちなどほとんどなかったのだ。ユダヤ教のこの革新が古代におけるユダヤ民族の高い出生率を支え、その出生率が、ローマによる征服にも先立って、異邦への移住とディアスポラの人口増加を部分的に説明する要因になっていたと推察するのは、妥当なことだろう。 ー 文字表記は、その本質において、知識を固定する技術であり、これによって人間社会は、記憶内容の口頭伝達にともなう不確実性を免れる。長子相続は、長子相続から早晩発生することになる直系家族とともに、これまた継承の技術にほかならない。継承されるのは、君主制国家、封地、農場、工房などである。より深い部分では、そうした社会構造の諸要素にともなう、事務処理や、農業や、金加工技術などのすべてのテクニックである。したがって、文字表記と直系家族というこの二つの社会的続性の道具の間にひとつの歴史的近接性を看て取るのは、非論理的なことではない。 初期の表意文字システムの場合には、直系家族との関係はおそらく非常に緊密だ。あの種の文字を使いこなすには厳しい修練が必要なので、おそらく、直系家族の継続性と文字表記技術の獲得のあいだには必然的な関係が存在するのだろう。私がここで喚起しているのは、書記を家業とする家族内での父から息子への継承だけではない。中国の文字であり、日本でも用いられている漢字の数が、じつに数千にも上ることを思ってみようではないか。もし、継承のために考え出された家族システムもなく、その中で子供に対して働く親の強い権威もなかったとしたら、あれほど多くの文字を記憶することなど考えられただろうか。 今度は二一世紀の現在に身を置いてみよう。中国と日本の文字表記システムは今も生き延びているが、こんなことが可能だということ自体、あの両国に高いレベルの家族的・学校的規律が存在するからこそであろう。 したがって、メソポタミアで、中国で、日本で、文字表記の出現と長子相続による家族秩序の形成の間に歴史的な結びつきがあったという仮説を立てていけない理由はない。エジプトでは、長子相続がかなり早くから社会の上層階級に取り入れられたのだが、このケースなども仮説に矛盾しない。 ー 読むことの学習をひとつの技術の獲得としてしか見ないなら、われわれは間違いを犯すことになろう。今日では、次のことが分かってきている。幼児期に読むことを覚え、実際に読書に没頭すると、それによって頭脳の機能がいちじるしく拡張されるのだ。たしかに、頭のいい子は読むことを覚えるのが早い。しかし、人類史を理解するためにより重要なのは、とりわけ読むことを通して子供たちの頭がよく機能するようになるということだ。外国語の習得と同様、読む能力の獲得は思春期以前には容易で、思春期を過ぎると困難になる。人体組織の成長の決定的な局面では、識字化によって頭の構造が変わると言ってもよいくらいだ。 読むという活動が新しい人間を創造する。読むことを覚えた人間においては、世界との関係が変わる。 ー プロテスタンティズムはまた、大衆の識字化というそのオペレーションによって読み書きの出来る農民を「製造」するに到ったのだから、原初キリスト数よりもさらに古い母なる宗教、ユダヤ教の後を追い、その点ではユダヤ教を追い抜いたのであった。宗教改革は、この狭義の教育的意味において、ユダヤ人たちによってもたらされたメッセージに対して格別に忠実であった。 ー 識字化は、最初のうち、宗教的な夢や悪夢が精神に取り憑くのをむしろ後押しした。しかし、もう少しあとになると、科学革命のベースとなった。ガレリオ・ガリレイはピサの人だったけれども、近代物理学の基盤となった地域は間違いなくヨーロッパ北西部、つまり、男性の半数が読む能力を持っていた地域であった。ところで、物理学が発展すると、万物の創造主にして統制者としての神を疑問に付すことが可能になる。自然界の数学的捕捉・表現を担った立役者たちの幾人かは、自らの宗教的疑念を傲岸な客推理でコントロールしようとした。デカルトは一六四四年にラテン語で「コギト・エルゴ・スム(我思う、ゆえに我在り)」と述べたが、これは、論理上の紆余曲折を経て至高者の存在を認めることにつながる確信であった。 面白い。下巻に更に期待。
53投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ良書、歴史に関する斬新な視点を甘えてくれる ただ、分かりづらい、難しい、専門用語が多い 歴史を語る時、政治、経済、テクノロジーなどの観点から語る事が多いが、この本は家族という観点から見た歴史を語ってる 家族のあり方の変遷、それが人々の価値観や社会のあり方に与える影響 特に、イギリス/アメリカの家族や社会の特徴と、それの影響
0投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1年前に『第三次世界大戦はもう始まっている』を読んで以来、ちょっと注目している著者。 https://booklog.jp/users/yaj1102/archives/1/4166613677 ならば、ご専門の人口学、家族学による、著者の主張を拝見してみようと手に取った。図書館でもそこそこ待ちが発生してた。人気なのかな? とはいえ、本論の部分にはさほど興味はなく、やはり今の世界情勢を語った部分に目が行く。 「私がとくに強調したいのは、この戦争(=ウクライナ戦争)は政治学、経済学では的確に捉えられず、人類学的に解釈する必要がある、ということです。」 佐藤優も、この戦争は価値観の戦いだと言う。 トッド氏も、ウクライナ戦争は「奇妙な戦争」と断じ、経済的に依存しているヨーロッパとロシアが、なぜ戦わなければならないのか? 互いに相手の息の根を止めることなく戦争を続けるために、今、何が行われているのか? トッド氏は、 「それぞれの陣営は、新しい戦い方をいちいち「発明」する必要に迫られています。」 と説く。 西洋はいま、思考停止に陥りつつある。経済学が支配的なイデオロギーとなっているが、それでは物事は解決できない。資本主義の論理に対し、トッド氏は、本書で、人間の行動や社会のあり方を「政治」や「経済」より深い次元で規定している「教育」「宗教」「家族システム」の動きに注目する人類学的なアプローチで読み解こうとする。 トッド氏の視点は理解できた。今後の事態を見守ろうと思う。
1投稿日: 2023.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は「家族システムの世界史」と言える。 社会の最小単位とも言える「家族」の体系は、その地域特性の影響を受けながら「核家族」に始まり、「直系家族」に移行し、さらに「外婚制共同体家族(結婚は共同体家族の外の人間とする)」、「内婚制共同体家族(いとこ婚などを推奨する閉鎖的な形態)」に移行していくという。 つまり本書では「(いろいろなところで生まれ育ってきた)我々は(この順序に沿って)どこから来て、今どこにいて、そしてどこへ向かうのか?」について考察されている。日本人だけでなく、米国、欧州、アフリカ、ユーラシアの人々の家族体系の歴史を解説し、各地域で根を張る家族体系の特徴を土台にして経済や紛争まで語ってしまうトッドさんの想像力と説得力にいつも脱帽する。「家族システム」の歴史を紐解いたところで社会学や比較文化論の域を出ないが、弁の立つトッドさんはこのやり方でソ連崩壊やトランプ現象、ブレグジットを言い当てたことは有名だし、そのわかりやすさがトッドさんを学者の枠を超えた別格の論客に押し上げている。 そんなトッドさんは、ロシアによるウクライナ侵攻を「第三次世界大戦」と捉えてこの本で語っている。 https://booklog.jp/users/kuwataka/archives/1/4166613677
1投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族,宗教,識字化,産業,政治…見事なまでに一連のものとして,また絡み合い影響し合うものとして説明されている.まだ上巻を読み終わったところだけど,政治的,文化的,宗教的に相容れない集団が存在してしまうのは避けられない事なのかも?と. 一方で,こういった深いところ,脈々と続いて来た人類の歩みに思考が及べは,「理解は出来なくても存在を受け止める」努力は出来るようになるのかも,と希望的観測も持ちつつ,下巻へ進む…
0投稿日: 2023.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭に書いてあるが、トッドによる研究の全貌を一般の読者にも読みやすい形で示した「私にとって最も大事な本」だそうだ。全人類の歴史を、家族システムという補助線ひとつで整理しなおしてみせる手際はおみごと。経済学ばかりが重視される社会科学の現状への異議申し立ても傾聴すべきと思う。「反米を煽るものではない」と言いつつ、アメリカとドイツをディスるときの筆の冴えも面白い。 日本やドイツの直系家族が経済的な効率性に優れると言いながら産業革命がテイクオフしたのは核家族のイギリスであったり、それはそれで理由が示されるのだが、全般を通して、ああ言えばこう言う的なところも多く、ウクライナ戦争にまつわる言説も含めすべての議論を真剣に受け止めていいいかどうかは留保したいところ。
1投稿日: 2023.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログホモエコノミクスに還元されないそれぞれの地域が持つ特性を、主にそれぞれの地域の伝統的な家族構成によって描く名著だと思う。 原著執筆から5年が経ち、社会情勢が大きく変化している中でも全くそれを感じさせない内容だった。
2投稿日: 2023.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ今日までの人類の進化は、意識・下意識・無意識によって成り立っている。無意識に当たる家族と宗教の影響が興味深い。 一方で、翻訳が難解なため理解するのに苦労した。
0投稿日: 2023.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史人口学、家族人類学者のトッドらしい着眼点で、さまざまな国・地域の家族構成から、宗教や人々の経済基盤、ヒエラルキー、識字率などの統計を引きつつ、歴史をひもといていく。 上巻前半はかなり学術的で、人類学素人の私にとっては、多少”体力”の要る読書になったが、後半は宗教改革から、プロテスタンティズムや印刷技術の普及による変化、都市文明と核家族化の関係、18世紀までさかのぼっても北欧の女性の識字率が高かったことなど、従来の身近な知識で読み進められる話になってくる。 全体として、父系社会は、農耕が始まり定住して財産を蓄えるようになり、相続という行為が必要になって生まれてきたもので、実は核家族よりも新しい形態で、今我々が新しいと考えている核家族や男女平等というのは、むしろ原始的なものだったかもしれないという“反転“理論が背骨になっている。 ちょっと面白いのは、「いったいなぜアメリカなるものがわれわれの眼に、モダンであると同時に未開の自然のように映るのか、われわれの未来の姿を先取りして示してくれるほど進んでいるのに、なぜ習俗においてあれほど洗練度が低く、あれほど非文化的に見えるのか」という著者の問題設定。読み進む原動力になる、フランス人らしい視点かもしれない。
7投稿日: 2022.11.13
