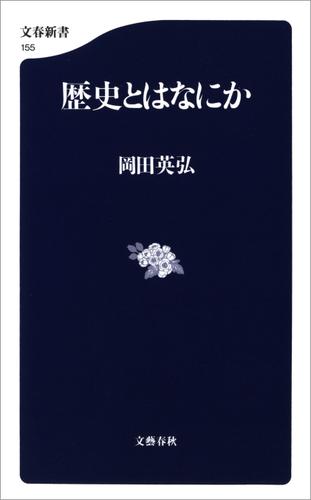
総合評価
(38件)| 13 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ★過去を現在の視点から見てはいけない★歴史のストーリーを描くのではなく、歴史とは誰がどんな狙いで書かれたのかを記す。歴史は政治権力の中心で書かれるもので、権力の正当化が歴史の使命。著者の主張の是非を判断する材料はまったく持ち合わせないが、シンプルに面白い。 ・歴史を成立させるには直進する時間の観念が必要で、輪廻転生するインド文明や一瞬一瞬がアッラーの創造にかかるイスラム文明では成立しない。 ・自前の歴史があるのは中国文明(正統という観念を記すためで、そのため現実をゆがめて変化のない世界を記す)と、地中海文明(争いがあって最後は正義が勝つ)だけ。それぞれ歴史の書き方が決まっていて、それに対抗してほかの文明が生まれる。 ・日本人が好きな3世紀の魏志倭人伝は、中国の歴史の外伝の隅に書かれた内容で、あくまで彼らの都合によるもの。邪馬台国の距離の表記もそもそも適当という。 ・8世紀の日本書紀も、当時の皇室の祖先がどういう系譜を持っていたかを語っているだけなのに、後世の人が日本民族の由来を語るものと曲解する。 ・18世紀末までは君主の位・権利・財産であり、国家はない。いま振り返るから君主の財産が国家だったかのように見えるだけ。国家という枠組みや国語は後からつくった。 ・国民国家ができたのは、君主の傭兵より国民軍が強いから。スタートはナポレオン。君主制を残したまま国民国家に衣替えしたのが立憲君主制という政治形態。 ・王家が長く続くのは、権力ではなく人格が世襲される(天皇も一例)。共和制の大統領は一貫した個性を持てない。 ・自明のように感じる国家や国民はたかだか200年の歴史しかなく、18世紀以前の歴史をその視点から叙述するのはナンセンス。 ・現代の中国の歴史は19世紀に入って皇帝の歴史を国民国家にすり替えたもと。清帝国は満州人の皇帝が満州人、モンゴル人、中国人、チベット人、イスラム教徒と均衡を保っていただけだが、国民国家としての中国の視点からは国境の内側の住民はすべて漢人であるべきとなり、少数民族の弾圧に。
0投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的に知る事になる歴史において前提になっている事を疑って素直に見直した画期的な歴史観だと思う。 確かにそうであるならば、そう言えますね。 と思うし、厳密に言えばそうかという感じ。 無理に神話と融合しない見方を内外通してやってみせる。 なるほど実在が危ういのもこれを読めば納得しやすいし、その性格を素直に考えるなら思ったよりも資料はいい加減だよなそりゃという感じ。 とても面白かった。
0投稿日: 2024.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ【文章】 とても読みやすい 【ハマり】 ★★★★・ 【気付き】 ★★★★★ 歴史とは、時間軸、空間軸を持って一個人が直接体験できる範囲を超えたもの。 歴史は、自己の正当化の武器になる。 インド文明、イスラム文明は、もともと歴史を持っていなかった。 憲法によって作られた国家アメリカでは、歴史は重要視されていない。
0投稿日: 2023.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史とは昔に起こった出来事のように考えていたがそうではないと言う、歴史は人間の住む世界の説明である。歴史を間させるには必要な要素がある。 忘れがちな要素としてためになったのは、歴史書を書いた人にはその人の立場や思想がありそれが反映されていると言うこと、もう一つは現代の国民国家のあり方民主主義が当たり前の私たちにとってこの携帯の政治がずっと続いていたかのように考えてしまうこと、今の枠組みで考えてしまうと言うことだ。 いろんなことについて考えさせられる良書である
0投稿日: 2023.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史は、真実が書かれたものよりも読みやすいもの、読者が求める神話的なものの方が好まれる。 また、書き手1人の経験等で歴史は正確に書かれないため、結局はフィクションになりがち。
0投稿日: 2022.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
歴史というものが何なのかが良くわかった。 某国の歴史がいかにデタラメなのかも。 とあるサイトで知ってAmazonで購入
0投稿日: 2022.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史とは何か。 歴史を少しでも専門的に学習した人間であれば一度は考えた事があると思う。 有名な著作にE.H.カーの著作があるが、その本とは一線画している。 しかし、個人的な感想だが、歴史とは何かの答えにはなっていないと感じる。 何が?と言われれば、それは言葉にできないのだが。 逆を言えば、その難しさ、奥の深さが歴史の楽しさなのかもしれない。
0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史の史料は、作者や作者の属している社会の好みの筋書きによって整理されている。その史料を手掛かりに歴史家の解釈でつくられているものが、我々が知らされている歴史
0投稿日: 2019.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ10.6.25 石井ブログ 【書評】歴史の創られ方が分かる本「歴史とは何か」岡田英弘 再レビュー テーマ:書評:歴史・社会分析 多読書評ブロガー石井です。 「歴史とは何か」を再度紹介します。歴史の読み解き方を教えてくれる本です。 最初の100レビューで取り上げていたのですが、今のブログのレイアウトで閲覧できないこと、文体が今と違うことなどからリライトしてお届けします。 今の世の中に当然のように存在している著者の言う「国民国家」というあり方について、19世紀に入って、戦争に強いという理由で急速に普及した形態にすぎず、もう制度的に限界に来ているという主張は新鮮でした。 歴史とはなにか (文春新書) 国民国家及び民主主義は、観念上のものであって、現実ではありません。 そのひずみは、今の社会で起きている種種の問題に結びついているのではないかと感じました。 そして最後には国民国家という基盤が終焉するのではというところまで言及されています。 経済の行き詰まりを解説した本は多数出てきていますが、歴史の推移を正面から分かりやすく解説してくれている本はなかなか出合えないのでオススメします。 【学んだこと 内容メモ抜粋】 ■イスラム文明 神の言葉は不変。人間は変わり、うつろうもの。 未来に「必ず」とつけるのは、神の意識より、自分の意識を優先させる不遜な態度。 ■中国文明 「正統」の歴史←司馬遷「史記」の歴史観 正統を証明するために事実を捻じ曲げる。 皆わかってるから国家は信頼されない。 ■日本の歴史 GHQの指導で、「神話」が削除され、考古学である縄文・弥生時代からになった。 ■世界史の時代区分は「現代」「古代」のみ マルクス主義的段階進化は存在しない ■アジア 19世紀に入ると国内史料だけの時代から、海外の史料も対象になる。 ■地球規模 18世紀末のアメリカ独立・フランス革命による「国民国家化」 日本:1868年の明治維新 ■モンゴル:世界史の誕生 ユーラシアとアジアが、13世紀、元の征服により繋がった。 モンゴルからの継承政権:中露印、アラブ諸国、中央アジア各国 モンゴルが陸を押さえた。 欧州各国は、新たな利権を求め海へ進出した。 ■君主制 嫁入りのやり取りにより、所有地は分断され、「領土」の線引きが大変。 戦争に強い:無数に多数の兵士を動員でき、自分達の「国」を守るモチベーション。 ■国民国家と民主主義 民主主義は欠陥だらけの制度。明白な「虚構」平等主義に基づいている。 ■共和制の国家 アメリカでは、大統領が変わる度に、国の「性格」が変わる。 ■君主制は人格(文化の伝統と権威)が伝承される。 国民国家が現れる19世紀までは、皆君主制か自治都市だった。 ■日本が国民国家に簡単に転換できた理由 (1) 領土が明確:四方が海。 (2)鎖国の方針を歴史的に堅持。域内に外国の領土もなかった。 (3)外国人がいないため、誰が「日本人」か明確 ■中国 日清戦争に負けて日本に追随することを決めた。 ■現代中国語 日本語を例に作る。 ■国民国家の終焉の理由 広域統合の動きが出てきたのもその一環だが、まだ序章 (1) 国民国家は観念上のもの。理想であって、現実ではない。皆が皆を所有するはない。 (2)国民国家の統合の象徴である「国語」も人工的に作り出されたもの。 フランス語もドイツ語も人工的に作り出されたもの。 (3)種族の問題:同じではない。同じ言葉を話しても違う民族だと自分で認識する。 元の【備忘録 内容メモ全体】も参考までに載せておきます。内容的には重複している所が多いです。 ・人は、今を生きており、時間を直接的に認識することはできない。 →時間の感覚や歴史は人が便宜的に創っている。文学、目指した目標、狙った効果がある。 →ヒストリーの語源は、「調査研究」byヘロドトス:最古の歴史家 →大切なのは、史料の矛盾をつきつめ、最もありそうな説得力のある解釈を作り出すこと。 →道徳的判断や功利的判断は避けなければいけない。善悪の判断は両面。 →良い歴史解釈は、意図を持って創られた歴史と利害衝突を招きやすい。 ・イスラム文明:神の言葉は不変。人間は変わり、うつろうもの。 →未来に「必ず」とつけるのは、神の意識より、自分の意識を優先させる不遜な態度。 →歴史という文化には、ローマ帝国の抗弁に対抗するために、取り入れた →本来的に持っているものではないから、交渉に弱い。 ・アメリカにとっての歴史はヨーロッパの歴史のみ、他は地域研究 →アメリカ自身にも、アメリカ研究のみ、伝記の効用は歴史より自己啓発 →アメリカは、憲法だけによって作られた国 →皆、ゼロから出発する=アメリカンドリーム ・中国文明とは、「正統」の歴史←司馬遷「史記」の歴史観 →日本にも影響している →正統を証明するために事実を捻じ曲げる。→皆わかってるから国家は信頼されない。 →中華思想:支配の権限を持たない「漢人」が悔し紛れに作った思想。 →朝貢:独立者からの贈り物のやりとりを、自分の権威を強めるためのPRに使っていた。 ・地中海文明とは、地球上で最初の歴史を書いたヘロドトス「ヒストリー」語源は「調査研究」 →二つの勢力が対立し、最後に正義は勝つ世界観←ゾロアスター・ユダヤ教の影響 →ユダヤ教が残って、自分のアイデンティティを保てたのは一神教だったから。 ・日本文明の成立事情 →日本書紀が主張する「正統史観」:中国へ対抗するため。 →創作なのだから、天皇のルーツをたどる研究はナンセンス。 →GHQの指導で、「神話」が削除され、考古学である縄文・弥生時代からになった。 →鎖国が日本のアイデンティティを作った。朝貢は独立のしるし。 →歴史認識の混乱は、明治維新から始まった。西洋の歴史に「正統史観」を当てはめた。 ・世界史の時代区分は「現代」「古代」のみ マルクス主義的段階進化は存在しない →アジア:19世紀に入ると国内史料だけの時代から、海外の史料も対象になる。 →地球規模:18世紀末のアメリカ独立・フランス革命による「国民国家化」 →日本:1868年の明治維新 ・モンゴル:世界史の誕生 ユーラシアとアジアが、13世紀、元の征服により繋がった。 →モンゴルからの継承政権:中露印、アラブ諸国、中央アジア各国 →金時代に華北で発生した資本主義経済:銅がなくて紙幣を使い、信用経済が発達した。 →アメリカが1971年に行った不換紙幣を、モンゴルは13世紀に使っていた。 →13世紀、モンゴルの取引相手だったヴィネツィアで、世界最初の銀行できる。 →モンゴルが陸を押さえた。→欧州各国は、新たな利権を求め海へ進出した。 ・「国民国家」とは何か →君主制:嫁入りのやり取りにより、所有地は分断され、「領土」の線引きが大変。 →フランス革命→市民革命→王族の領土を争い→ナポレオンが統一→「国民国家」 →戦争に強い:無数に多数の兵士を動員でき、自分達の「国」を守るモチベーション。 →爆発的に拡大したが、戦争による疲弊で、その役割に限界がきている。 ・国民国家と民主主義 →民主主義は、欠陥だらけの制度。明白な「虚構」(平等主義)に基づいている。 →共和制の国家:アメリカでは、大統領が変わる度に、国の「性格」が変わる。 →君主制:人格(文化の伝統と権威)が伝承される。 →国民国家が現れる19世紀までは、皆君主制か自治都市だった。 ・日本が国民国家に簡単に転換できた理由 (1)領土が明確:四方が海。 (2)鎖国の方針を歴史的に堅持。域内に外国の領土もなかった。 (3)外国人がいないため、誰が「日本人」か明確 →中国は、日清戦争に負けて日本に追随することを決めた。 →現代中国語→日本語を例に作った。 →日本へ来た留学生が持ち帰った革命思想→辛亥革命:清が滅ぶ →それまで政権を握れなかった漢人が支配することで中華思想が強まり →チベットの弾圧。文化を弾圧し、言葉を教えない。 →日本は鮮やかに成功しすぎた。 ・国民国家の終焉の理由 (1)国民国家は観念上のもの。理想であって、現実ではない。皆が皆を所有するはない。 (2)国民国家の統合の象徴である「国語」も人工的に作り出されたもの。 →フランス語もドイツ語も人工的に作り出されたもの。 (3)種族の問題:同じではない。同じ言葉を話しても違う民族だと自分で認識する。 →広域統合の動きが出てきたのもその一環だが、まだ序章にすぎない。 歴史を捉える上での大局観が見事にわかりやすく解説されており、歴史を学びなおしたい、世界史の流れを捉えるようなことをされたい方にオススメします。
0投稿日: 2019.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・日本書紀は、七世紀末から八世紀のはじめにかけてのあいだ、ちょうど日本国の建国の時期に、日本の建国を正当化し、天皇という世襲制の君主の正統性を裏付ける目的で編纂された。
0投稿日: 2019.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最悪の書である。民主主義を否定し天皇を中心とした立憲君主制を唱えている。この様な人が今の世にいたとは!
0投稿日: 2018.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史とは何かというのを定義した一冊。 宮脇淳子の『日本人が教えたい新しい世界史』と被る箇所も多かったが、勉強になった。
0投稿日: 2018.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆きっかけ 宮脇淳子さんの著書のレビューに夫である岡田氏のことが出てきて気になって。2017/2/27
0投稿日: 2017.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2001年刊。著者は東京外国語大学名誉教授。◆114頁以下の記述を見て、駄目だなぁ、老いたなぁと素直に感じた。文献史学のみが視野の全てを占める著者の眼から見れば、縄文時代は存在しないかのごとく。また、その前の旧石器時代、更にホモ・サピエンスの形成過程は眼中にないのだろう。◇二つの時代区分なら、文字情報の使用の前後で分けたい私の考えとは完全に乖離。◇大学受験予備校時代、日本史・世界史の双方の教官から参考文献として列挙された「倭国」。横断的な視野の重要性に気づかせてくれた著者への憧憬の時代は遠くなりにけりか。 加えて、偶然の積み重ねのみで歴史が形成されているというのも一面的な見方にすぎる。この発想は、未来の出来事が、現在とは無関係の偶然の事象により決定されることを意味し、まるで著者の説明するイスラムの歴史観そっくり。ちなみに、生物進化において、その前の体構造的な枠組みに縛られるという見解すら存する中、ランダムに発生する要因の大きな要素が、爾前の行動や決断ということを、著者は忘却している感がある。加えて、ランダム運動自体も後続が規程される理解(複雑系)もあり、うーん説得力がないなぁと感じたところ。 もっとも、文献資料分析、特に中国史のそれに限れば、やはり面白いし、詳細だなあと感じた。他の方も、中国史を語るなら、新書でもこれくらいは書かないと全然説得力がないよ、と思うほど詳しい。
0投稿日: 2017.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ東アジアで誕生日の観念が発生したのは記録にある限りでは唐の玄宗皇帝が729年、自分誕生日祝って千秋節と呼んだのが初めて。748年には天長節とかいしょうした。それ以前には誕生日を意識することは全くなかったらしい。 ムハンマドは最初はカーバではなくエルサレムの神殿 い向かって礼拝していた アメリカ本屋で、歴史コーナーにあるのは西洋やローマギリシャ。アジアやアフリカは地域研究コーナー。 アメリカに歴史はないので、交渉とかではアメリカは過去を済んだこととみなしがち。でも日本とかが過去の歴史でhsといってもらちがあかない。 劉備は蜀の皇帝と称したのではなき、漢の皇帝と称したが、漢は魏が継いだのでそこは無視された。
0投稿日: 2016.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2015/04/17:読了 繰り返し、読むべき本。 図書館で借りた本だけど、買っておこうかな 歴史学の本ではなく、歴史とはなにかという本。 時間は、人間の認識によって成立するように、 歴史は、文字によって成立する。 歴史の記述フォーマットは、長らく、ヘロドトスと司馬遷だった。 よって、歴史は、地中海を中心とする歴史記述と、中国を中心とする歴史記述があり、それ以外の地域には記述された歴史はない。
1投稿日: 2015.04.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界には「歴史のある文明」と「歴史のない文明」がある。日本文明は「反中国」をアイデンティティとして生まれた。 「歴史とは、人間の住む政界、時間と空間の両方の軸に沿って、それも一個人が直接体験できる範囲を超えた尺度で、把握し、解約し、理解し、説明し、叙述する営みのことである。インド文明は「歴史のない文明」。輪廻・転生という思想だから。イスラム文明も、基本的に「歴史のない文明」。神の意志が第一義。「歴史のない文明」アメリカは、現在と未来にしか関心がない。 「日本文明」の成立事情。国民国家とはなにか。
0投稿日: 2014.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ東アジア史の泰斗による「誤った歴史の捉え方」を切る一冊。 その根底には、多くの歴史学者すら陥っている様々な誤りに対する、著者のやるかたない憤懣があるようだ。 例えば、中国文明の歴史は「現王朝の正統性」を証立てるために書かれたものであるという大前提を見落としているがゆえに、説明不能の事態をこじつけで解釈するような羽目になっている。 その対抗文明である日本文明も、歴史書は天皇家の「正統性」を証立てるために書かれたものだった。古事記もそのように多分に政治色の強い「神話」だった。これを見落として歴史の事実と捉えてしまう愚を指摘する。 あるいは唯物史観にどっぷり浸ってしまったものの見方だったり、「国民国家」の概念は19世紀以降に出てきたものなのにその「国民」「国家」という枠組みをそれよりも過去にも当てはめてしまっていたり、といった過ちを次々と(半ば怒気を含んで)指摘していく。 著者は徹頭徹尾、よい歴史とは個人の主観や価値判断を排して、あらゆる資料を一貫した論理で説明できることだと主張する。 その著者の観念にそぐわない歴史家や歴史解釈が世の中にどれだけ多く、それゆえに「よい歴史」を書くのがいかに難しいか、歴史研究はいかに慎重に行わなければならないか、私のような素人にも伝わってくる力作である。
0投稿日: 2014.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ次のような史観が新鮮かつ納得。一度読むべき良書。 中国で作られた歴史・地中海で作られた歴史の2つがあるという。(それ以外に近代まで歴史はなかった)しかも違う性質の歴史。 そして、国民国家の時代に「誰が所有するか」をめぐって大量の概念が作られた。国の歴史もその1つ。新しく作られたものでしかない。 だから歴史は各国の都合に応じたものになっている。新に普遍的な歴史は批判を受けるはずのもの。そして、そんな普遍性を作れる歴史家は個性を追求した人になるはず。
0投稿日: 2014.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカには歴史がない。子供は親の遺産を使わず頑張る。 君主制は"人格"の踏襲。 中国は日本型の国民国家を目指し、それが少数民族の弾圧に繋がり、漢族だけにしようとしている。
0投稿日: 2014.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容が細かくなって行くと難しくて理解できなかった。しかし、歴史に関する私達の概念や思い込みの間違いを指摘し新しい歴史観を提示してくれ、総じて納得がいった。国民国家を論じるところは結構おもしろかった。
0投稿日: 2013.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ中国で最初に書かれた歴史は司馬遷が紀元前2世紀末から紀元前1世紀初めに書いた「史記」で、天命を受けた天子が天下を統治する権利を証明するためにつくられた。その後、その天命を引き継ぐ形で書かれる「正史」の枠組みが固定された。 地中海世界で歴史をつくったのは紀元前5世紀のヘロドトスで、その題名ヒストリアイは研究調査という意味だった。内容はギリシアとペルシアの戦いで、2つの勢力が対立して、最後に一方が勝って対立が解決し、歴史が完結するという歴史観が生まれた。 ローマ時代に、光明が暗黒に勝って、救世主が降誕して最後の審判が行われるというゾロアスター教が入ってきた。ユダヤ人はその救世主をマーシーアハ(メシア)と呼び、ローマの支配から解放してくれることを待ち望んだ。処刑されたイエスをメシアであると信仰したのがキリスト教。 663年の白村江の戦いに敗れ、唐軍の脅威にさらされたことによって、倭王は日本天皇と名のり、律令や戸籍を整備し、冠位・法度を施行して日本を建国するきっかけとなった。 日本書紀に登場する天皇の説話は、天智・天武天皇兄弟と、その両親の舒明・皇極(斉明)天皇の時代の親子2代の間に実際に起きた事件を下敷きに組み立てている。15代の応神天皇までの日本の天皇は架空のもの(「倭国の時代」)。 世界史がモンゴル帝国から始まった理由として、モンゴル帝国から分かれた新しい国々が現代にも継承されていること、12〜13世紀の金帝国の時代に誕生した資本主義経済(手形取引)が草原の道を通って地中海世界や西ヨーロッパに伝わったこと(13世紀にベネチアで最初の銀行ができた)、モンゴル帝国が陸上貿易を独占したため、その外側に取り残された日本と西ヨーロッパが海上貿易を始めたこと(1350年から倭寇)。 国民軍に多数の兵士を徴兵できるため戦争に強いことが、国民国家が普及した理由。ナポレオンの国民軍の強さを痛感したヨーロッパに広がった。
0投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログそれぞれの文明での「歴史」の捉え方が紹介されており、 興味深く読みました。 「歴史」は科学ではなく、文化であり、 記述者の目を通して書かれたものであるので、 その人の持つ背景を全く拭い去ることは難しいです。 そのような「歴史」を受け取っていることを認識しました。 「国民国家」や「民族」という概念は、近代成り立ったものなので、 受け取る側も、そういった枠組みのなかで過去を捉えようとすると、 見えなくなるものがある気がします。
0投稿日: 2012.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史を叙述すること、歴史家が他人の経験にどれぐらい自分を投入できるか・・・ 簡単なようでとても難しいことを考えさせられた。 歴史は普遍的な一個人の紡ぐ言葉である。 書いているものから、人格まで透けて見えてしまいそうで、私などは不安になる。
0投稿日: 2012.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史を読む・書く姿勢について、言及した本。 最近、歴史解釈が政治問題に発展するニュースを見るにつけ、非常に不快な思いをすることがある。 歴史が、イデオロギーや政治的解決、合理的とらえかたなど、歴史に対する冒涜があたりまえのように行われているからだ。 この本では、歴史に対峙するときの心得を、様々な歴史記述例を基に、説明している。 日本の歴史書(古事記・日本書紀)にも非常に辛辣なのは、残念。 もっと勉強しろってことだな、たぶん。
0投稿日: 2012.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログfacebookでの知り合いの方からの推薦で読んでみた本です。 はるか昔に読んだE.H.カーを思い出すタイトルですね。とても抽象的なだけに、かえってどんな内容だろうかと興味がわきます。著者の岡田英弘氏は、東京外国語大学名誉教授、中国・日本古代史の専門家です。 本書での著者の主張はかなり刺激的です。マルクスの唯物史観からの発展論的思考の否定は他にもみられる論ですが、それ以外にも日本の天皇制の起源・歴史の時代区分・「国民」「民族」の発生過程等々、種々のテーマに関する興味深い論考が目白押しです。
0投稿日: 2012.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局、学問とは原理を指し示し、そこへ導く営みであることがよくわかった。つまり学問の最終形態は数学と宗教に辿り着く。ザ・原理。岡田英弘の主張には鉈(なた)のような力が働いている。まさしく一刀両断という言葉が相応(ふさわ)しい。 http://sessendo.blogspot.com/2011/10/blog-post.html
0投稿日: 2011.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ納得します。全てを突き放した感じで論が進められているのに すがすがしさと気持ちよさを感じた。歴史というものを第三者的に見るなら やっぱりこうあってほしいな なんて。私はまるめこまれているだけなのかもしれないがww 一読に値します、お勧めします。同情じゃない意味でアジア(日本含む)が哀れで仕方なくて、涙出そうでした。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「歴史」というものについて考えさせらる一冊。 牽強付会的な部分も感じられるが、新しい歴史認識を与えてくれる。
0投稿日: 2011.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 世界には「歴史のある文明」と「歴史のない文明」がある。 日本文明は「反中国」をアイデンティティとして生まれた。 世界は一定の方向に発展しているのではない。 筋道のない世界に筋道のある物語を与えるのが歴史だ。 「国家」「国民」「国語」といった概念は、わずかこの一、二世紀の間に生まれたものにすぎない…などなど、一見突飛なようでいて、実は本質を鋭くついた歴史の見方・捉え方。 目からウロコの落ちるような、雄大かつ刺激的な論考である。 [ 目次 ] 第1部 歴史のある文明、歴史のない文明(歴史の定義 歴史のない文明の例 中国文明とはなにか 地中海文明とはなにか 日本文明の成立事情) 第2部 日本史はどう作られたか(神話をどう扱うべきか 「魏志倭人伝」の古代と現代 隣国と歴史を共有するむずかしさ) 第3部 現代史のとらえかた(時代区分は二つ 古代史のなかの区切り 国民国家とはなにか) [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ-my bookdarts- 歴史は、人間の住む世界の説明である 時間と空間に沿い、一個人の体験を超えて把握すること インド文明は「歴史のない文明」である 輪廻・転生という思想 もう一つの歴史の重要な機能とは、「歴史は武器である」という、その性質のことである。文明と文明の衝突の戦場では、歴史は、自分の立場を正当化する武器として威力を発揮する。
0投稿日: 2010.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろい、いろいろ目からうろこ 歴史は、常に”誰か”の目的に沿って記述される。 そのため、都合のよいことが書かれる。 そこから、事実を抜き出そうとすると、落とし穴にはまる。 日本書紀は、天智天皇、天武天皇の時代に作られた。それ以前の、歴史は創作の可能性が高い。 古事記も、同じ、日本書紀後の内容。 中国に対抗するために作られたと考えるのが妥当。 中国の歴史書も含めて、東洋の歴史は正当性を主張することが目的。 韓国の歴史も同様(700年ごろに出来た?) 西洋の歴史は変化を書き留めることが目的 世界史といえるものは、モンゴル帝国以後。 国民国家が近代の重要なテーマ。国民国家は、軍事的なメリットがあり広まった。 せいぜい、200年前の話。それ以前は、国民も国も明確ではなかった。国王ではなく君主がいた 現代の概念で過去を考えるのはナンセンス。 国民国家自体も、賞味期限が切れかけている?
0投稿日: 2010.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史に関する深い考察。 歴史=人間の住む世界を時間と空間の両方の軸に沿って、それも一個人が直接体験できる範囲を超えた尺度で、把握し、解釈し、理解し、説明し、叙述する営みのことである。 歴史の成立する前提条件は①直進する時間の概念、②時間を管理する技術、③文字で記録を作る技術、④ものごとの因果関係の思想 の四つが揃うことである。 隣国との関係で歴史を共有することは難しい。なぜなら権力の正当化が歴史の本来の使命であるからだ。
0投稿日: 2010.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ一般的に歴史とは何かというのが書かれています。歴史とはどのようなものか知りたい人は読んでみると面白いと思います
0投稿日: 2010.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学入試の論文勉強用にみっちり暗記した本。 歴史とは歴史家と事実との間の相互作用の不断の過程であり、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話なのである。 歴史を学ぶ人は必ず一度は読む本。
0投稿日: 2009.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ負け惜しみの「中華思想」とは名言ではないでしょうか。国民国家の説明がまた分かりやすかったです。これから歴史がもっと楽しめそう。
0投稿日: 2008.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログそもそも歴史ってなによ? ということが簡単な文章でつづられている。 「人は歴史にファンタジーを求めている。」 という指摘にギクリ。 いいじゃん・・・夢見たって。
0投稿日: 2008.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ作られる歴史の姿について書かれた本です。 まさに記録されていく「歴史とはなにか」について考察する本。
0投稿日: 2004.09.20
