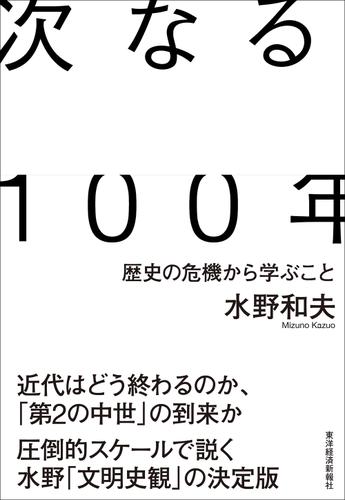
総合評価
(8件)| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ第92回ビブリオバトルinいこま「三冊屋」で紹介された本です。 2022.6.26 ①『次なる100年』水野和夫 ②『恋愛と贅沢と資本主義』ヴェルナー・ゾンバルト ③『Stereo Sound No.213』ステレオサウンド
0投稿日: 2024.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みづらい文体だが、主張は明快である。 ゼロ金利の意味とは何か、どうして実質賃金が下がるのか、中間層が没落する理由は何か。 これらの疑問が氷解した。もはや成長は幻想である。
0投稿日: 2023.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ水野和夫さんの本は新書「資本主義の終焉と歴史の危機」だけ読んだことがある。 先日、「Slowdown 減速する素晴らしき世界」を読んで、もやっと感じていたことがなんとなく書かれている気がした。 そんなときにこの本を目にして、なんとなく関連がありそうな気がして、でも高いのでとりあえず図書館で借りてみたらとんでもない厚さだった。 2週間で返さないといけないのでちょっと駆け足で読んでしまったけれど、やっぱそうだよなあという感じがした。 【なんとなく感じていること】 1)本当にこれからも順調に経済成長なんてできるのだろうか 2)そもそもだが、消費しきれないほど作っているのではないか(服とか食品) 3)企業の収益を現地にいる労働者に給料として還元せず、株主に戻しちゃったら日本から資本がどんどん流出することになるのではないか 4)お金に働かせる、というのは倫理的に誤っているのではないか 5)高度に経済成長していたのは単にその前が貧しすぎただけ、もしくは人口が急激に増えただけの、一時的なボーナスタイムだったのではないか 6)日本の文化は、タイトな国民性からもたらされる治安の良さや、誠実さによって守られており、これ以上の貧困を許すと、秩序が崩壊するのではないか。 とりあえずこんな感じだろうか。 いま、この時代に肉体を持って生きている人間が、現時点の状況を歴史的に捉えようとすると、やはりデータだけでは足りず、思想(宗教や倫理も含まれる)、芸術などの助けを十二分に借りなければできないだなあと思った。 データだけでは、抽象化は難しい。これからの100年を見据えるには、人類史全体を流れで大きく捉える必要があるんだろうな。 水野氏にこの本を書かせたのが鈴木忠志の演劇であることや、たびたび引用されるのがシェイクスピアだということを考えると、人間の思想というものは、小説、戯曲、経典、思想書、さまざまな形で表されるものの、結局は人間の社会そのものを描き出しているのかもしれない。
0投稿日: 2023.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバル化は、時の小泉政権が主張していたのとは違い、富裕層による帝国化である。これにより中間層が脱落、この過程は帝国崩壊につながる(歴史が証明)。 無限の「蒐集」古代ローマが世界帝国を目指し土地を、中世キリスト教は世界宗教を目指して無限に信者を、近代はより良い生活を目指して資本を無限に集めようとした。
0投稿日: 2023.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ大著である。 イコン、コインの次は、芸術が価値を持つ。その理由は、先進国で金利がつかなくなり、蒐集、収奪を特徴とする資本主義経済が終焉する。とのこと。 芸術が価値を持つとの提案は勇気ある。本当にそうなるのだろうか。
0投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ1000ページくらいあり長く脚注が非常に多いが過去の歴史から生まれた階級を変わることは少ない、富める人がどんどん富む社会になっている。 国際収支はゼロサムでアメリカが支配層になっている
0投稿日: 2023.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ中世の秋とGAFAを2文5行で書かれても話が飛び過ぎててついていけない。ゼロ金利は好きでなさそうだ。話そもそも本デカすぎ。電車で読めない重くて持ち運びに不便。終章が2/3くらいから始まったと思ったら、その半分は引用の注記でした。
0投稿日: 2022.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ生産性上がっても賃金が下落する原因等の記載部分等は詳細は触れてないイメージ。 生産性を何と捉えてるか? 賃金対象の属性をひとくくりにしすぎてない? 電子化等で労働力が不要になっても 日本における過去の水準(労働時間で評価し高齢管理職男性の高すぎる賃金水準)が 外国におけるそれと乖離がありすぎただけ。 →今は水準の乖離が狭まってきてるから 結果全体の賃金が下落している様に見えてるだけ。 それを踏まえこれからの100年をどう先読みするか? 具体に触れてほしい。
0投稿日: 2022.02.23
