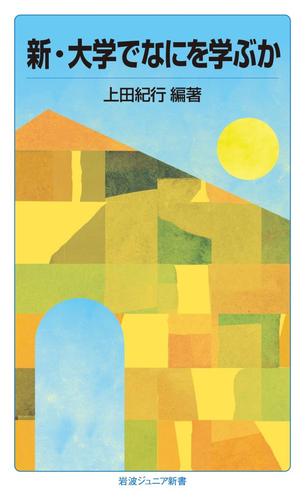
総合評価
(17件)| 2 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ同性婚通して欲しいって社会で言ったら一匹のお気持ちだもんね。それがその人の真実である事は認めるけど、それを政治に反映しちゃいけないんだよ。同性婚通して欲しいって叫んでる人はこういう政治そのものの勉強を怠ってる人なのかなと思った。大学全入時代なのにろくに勉強してない人が多すぎるんだろうな日本は。 政治にマイノリティであるLGBTの概念を取り入れてるの自体政治的には間違いだということだよね。これは。 池上 彰 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院特命教授。1950年、長野県生まれ。1973年、慶應義塾大学を卒業し、NHKに記者として入局。松江、呉での勤務を経て、東京の報道局社会部。警視庁、気象庁、文部省、宮内庁などを取材。1989年より5年間、首都圏ニュースのキャスター。1994年より2005年まで「週刊こどもニュース」の〝お父さん〟。2005年に独立。現在は名城大学、東京大学、立教大学など9つの大学で教える。 磯﨑憲一郎 東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター・リベラルアーツ研究教育院教授。1965年、千葉県生まれ。早稲田大学商学部卒業。2007年『肝心の子供』で文藝賞、2009年『終の住処』で芥川賞、2011年『赤の他人の瓜二つ』で東急文化村ドゥマゴ文学賞、2013年『往古来今』で泉鏡花賞受賞、2020年『日本蒙昧前史』で谷崎潤一郎賞受賞。他の著作に『眼と太陽』、『世紀の発見』、『電車道』、『鳥獣戯画』、『金太郎飴 磯﨑憲一郎 エッセイ・対談・評論・インタビュー2007─2019』などがある。 伊藤亜紗 東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター・リベラルアーツ研究教育院教授。マサチューセッツ工科大学(MIT)客員研究員。専門は美学、現代アート。もともと生物学者を目指していたが、大学3年次より文転。東京大学大学院人文社会系研究科基礎文化研究美学芸術学専門分野博士課程修了(文学博士)。主な著作に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』(水声社)、『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社)、『目の見えないアスリートの身体論』(潮新書)、『どもる体』(医学書院)、『記憶する体』(春秋社)、『情報環世界』(共著、NTT出版)がある。 木山 ロリンダ 東京工業大学リーダーシップ教育院副学院長・リベラルアーツ研究教育院准教授。文学・文芸を通してトラウマを乗り越える方法に興味を持ち、日本古典文学・文芸と臨床心理学を専門としているカウンセリング心理学者。二つの文化の間で育つ二人の子の母親で、アイデンティティ形成とその流動性、バイリンガル教育、国際結婚も研究の対象とする。日本における特別養子縁組の仲介について博士論文を書いた。 國分功一郎 東京大学大学院総合文化研究科・教養学部准教授。1974年、千葉県生まれ。東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。高崎経済大学、東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授を経て現職。専門は哲学・現代思想。著書に『スピノザの方法』(みすず書房)、『暇と退屈の倫理学』(朝日出版社、第2回紀伊國屋じんぶん大賞受賞 増補新版:太田出版)、『ドゥルーズの哲学原理』(岩波現代全書)、『来るべき民主主義』(幻冬舎新書)、『近代政治哲学』(ちくま新書)、『民主主義を直感するために』(晶文社)、『中動態の世界』(医学書院、第16回小林秀雄賞、第8回紀伊國屋じんぶん大賞受賞)、『いつもそばには本があった。』(共著、講談社選書メチエ)など。 多久和理実 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院講師。2010年、東京工業大学理学部物理学科卒業、2010年9月から1年間、ボローニャ大学に交換留学生として留学。2014年9月から1年間、日本学術振興会特別研究員としてガリレオ博物館に滞在。2016年、東京工業大学大学院社会理工学研究科博士課程修了。2019年、学術博士。専門は科学史。物理学を学ぶきっかけはニュートンの光の実験に興味を持ったこと。今後「ヨーロッパ各地の博物館にあるニュートンが使ったと言われるプリズムについて調べたい」。 中島岳志 東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター・リベラルアーツ研究教育院教授。1975年、大阪府生まれ。京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了。2005年『中村屋のボース』で大佛次郎論壇賞、アジア・太平洋賞大賞を受賞。著書に『秋葉原事件』、『「リベラル保守」宣言』、『血盟団事件』、『親鸞と日本主義』などがある。 中野民夫 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。1957年東京都生まれ。東京大学文学部宗教学科卒。1982年博報堂入社。7年間の営業職を経て休職・留学し、カリフォルニア統合学研究所(CIIS)で組織変革を学ぶ。以後、会社勤めの傍ら、人と人・自然・自分自身をつなぎ直すワークショップを実践。2012年に早期退職、同志社大学教授を経て、2015年秋から東京工業大学の教育改革に加わる。専門はコミュニケーション論。主著に『ワークショップ』、『ファシリテーション革命』、『学び合う場のつくり方』など。 西田亮介 東京工業大学リーダーシップ教育院・リベラルアーツ研究教育院准教授。社会学者。1983年京都府生まれ。博士(政策・メディア)。慶應義塾大学総合政策学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。同後期博士課程単位取得退学。同助教(有期・研究奨励Ⅱ)、立命館大学大学院特別招聘准教授等を経て、2015年9月東京工業大学着任。著書に『メディアと自民党』(角川新書)、『情報武装する政治』(KADOKAWA)など。 林 直亨 早稲田大学スポーツ科学学術院教授。1970年東京都生まれ。専門は応用生理学、健康科学。1992年早稲田大学人間科学部卒業。早稲田大学人間科学研究科修士課程修了。1999年博士(医学・大阪大学)取得。1995年大阪大学助手、1999年から1年間カリフォルニア大学デービス校訪問研究員。2004年九州大学助教授・准教授。2013年東京工業大学教授。2021年から現職。 山崎太郎 東京工業大学科学技術創成研究院未来の人類研究センター・リベラルアーツ研究教育院教授。1961年東京都生まれ。東京大学文学部独語独文学科修士課程修了。専門はドイツ文学およびドイツのオペラ。リヒャルト・ワーグナーの楽劇を主な研究対象として、テクスト解読・演出分析・書簡研究など様々な方向からアプローチを重ねている。主な著書に『《ニーベルングの指環》教養講座』(アルテスパブリッシング)、訳書に『ヴァーグナー大事典』(監修・共訳、平凡社)など。 室田真男 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。東京工業大学第5類に入学、同大学大学院理工学研究科博士課程を修了(工学博士)。株式会社東芝研究開発センターに6年間勤務。その後、東京工業大学に戻り現在に至る。専門は教育工学。現在は、大学院生が学士課程学生の学びをサポートするGSAプログラムのリーダーを務める。 弓山達也 東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授。1963年奈良県生まれ。法政大学、大正大学大学院で学び、博士(文学)。大正大学教授、エトヴェシュ・ロラーンド大学客員教授などを経て、2015年より現職。専門は宗教学。主な著書は『天啓のゆくえ』(日本地域社会研究所)、『東日本大震災後の宗教とコミュニティ』(共編著、ハーベスト社)、『いのち 教育 スピリチュアリティ』(共編著、大正大学出版会)など。 「そういった方には申し訳ないのですが、私はこの本の役割はそのようなものではないと考えています。というのも、何よりもまず、そのような情報であれば、わざわざ本を手に取らなくても簡単にインターネットで入手できるからです。それは四〇年前では考えられないことでしたが、いまでは日常の風景になっています。もはや本がガイドの役割を果たす必要はないのです。むしろ本は、そうしたガイドブック的情報に溢れたインターネット空間ではなかなか手に入れることのできない何かを提供しなければなりません。それはなんでしょうか。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「私は現在、理系の学生を相手に文学の授業を行っているが、文系の、文学部よりも、理系の方が、変わった切り口で小説を読み解いたり、私も余り読んだことのないような不思議な短篇を書いてくる学生が多いように感じている。これは恐らく、文学部の学生が知らず知らず刷り込まれてしまっている、文学に対する盲目的な、不要なリスペクトが、理系の学生にはないからのような気がする。文学、小説に対する知識や周辺情報が増えれば増えるほど、小説本体にまっさらな気持ちで向かうことは難しくなる、知識が邪魔をして、型に嵌まった読み方しかできなくなってしまうのだ。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「福田は、政治は「九十九匹」を救うためにあると言います。しかし、残りの「迷える一匹」を、政治が救うことはできないとも言います。そして、その「一匹」を救うことこそ、文学の仕事だと言うのです。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「 福田は、政治に対して「一匹」を救おうとしてはならないと警告します。なぜならば、その「迷える一匹」を政治が救済しようとすると、他者の心の問題に政治が介入することになるからです。 政治は心を支配してはならない。常に異なる他者間の利害調整と合意形成に注力しなければならない。政治が他者の心を満たそうとすると、そこに全体主義やファシズムが忍び寄ってきます。福田は、そのような政治を断固として拒否し、政治の領分を限定しました。そして、政治の手からこぼれた「一匹」の心を救うことにこそ、文学の使命があると言いました。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「しかし、私たちは、あることを機に安定した日常を失い、唐突に「迷える一匹」になってしまう存在です。大切な人が突然亡くなった時、信頼していた相手に裏切られた時、人間不信に陥った時……。私たちの目の前は真っ暗になり、手にしてきた世俗的価値(お金や資格、実学的知識、地位、名誉など)は役に立たないものになります。私たちはすべて「九十九匹」であり「一匹」でもある存在です。 これからの人生、何度か大きな挫折や悩みがやって来ると思います。根源的な苦悩や危機に直面した時、残念ながら理工系の専門知識や実学はあまり役に立ちません。しかし、学生時代に触れた哲学書や小説、詩の一節、映画のワンシーン、音楽などが生きる支えになることがあります。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「これからの人生、何度か大きな挫折や悩みがやって来ると思います。根源的な苦悩や危機に直面した時、残念ながら理工系の専門知識や実学はあまり役に立ちません。しかし、学生時代に触れた哲学書や小説、詩の一節、映画のワンシーン、音楽などが生きる支えになることがあります。 リベラルアーツは平穏な日常においては、特に役に立つことはありません。立身出世にもそれほど役に立ちません。お金も儲かりません。しかし、何らかの形で人生の前提が崩れた時、リベラルアーツ教育で得た「教養」が意味を持ちます。年齢を重ねた教員が、口をそろえて「学生時代に多くのものに触れてほしい」「様々な経験を積んでほしい」と言うのはそのためです。専門知識とリベラルアーツは、役に立つ位相が異なるのです。専門には専門の「場所」(トポス)があり、教養には教養の「場所」があるのです。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「解らなくても何の問題もないので、気になった文学者、芸術家、思想家、哲学者、批評家、学者がいれば、その著書や作品に触れてください。ややこしそうな名作映画もみておいてください。ライブハウスで音楽を聴き、美術館で芸術を鑑賞しておいてください。旅にも出てほしい。歌舞伎もみてほしい。文楽も。現代演劇も。解らなくてもいい。解ることには大した意味はありません。所詮、今の自分に「解る」程度のものですから。 しかし、「解らないけどすごいもの」「うまく言語化できないけど心を動かされたもの」に触れていると、「解る」以上の感触が残ります。何らかの引っ掛かりが残ります。それが重要です。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「 大学入学のときに考えているよりも、遥かに人生は長いということかもしれません。花形産業の所在も変わっていくし、自分のしたいことも変わる、大切なものすら変わりうるなら、何が正解かを模索する必要があります。 尺度が変わるなら、失敗も正解かもしれませんし、正解も失敗かもしれない。思った以上によくわからないのです。それに耐える力はやはり経験的に、試行錯誤のなかで磨くほかなさそうです。人生は振り返るには短すぎるし、ただ後悔するには長過ぎると感じます。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「途中で休職して留学し、 30代で修士課程で学んだ。多くの出会いがあり、それを元にプライベートで様々なワークショップをやるようになり、本も書いたりし始めたが、会社勤めは続けた。入社から 30年にもなる頃、ふとしたきっかけから早期退職して大学の教員になった。今やるべきと思えることを一生懸命やっていると、ふとした瞬間に、新たな扉が開く。嫌だなと思っていると長引くが、夢中になってやっていると、思わぬ展開が訪れる。こんな人生を生きたい、と目標を掲げてめざすより、「今ここ」を大切にしていると、人生が私を通して生き始める。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「では授業に限定されない主体的学びをどう始めればよいのか? 平凡な答になりますが、迷える大学生にまずなすべきこととして何よりも強くお勧めしたいのは本を読むこと、徹底して読書の習慣を身につけることです。 理由の一つは、本を読むことを通して、今後どのような知的作業においても必要になる言葉の感覚がおのずと磨かれてゆくからです。 この世界でどのような仕事に就こうと、人間の営みのよすがとなるのは言語であり、日本の社会においては、それはまず何よりも日本語の運用能力ということになります。自分で何かを突き詰めて考える際にも、人間は基本的に言葉を用いて、考えを煮詰め、絞り込んでゆくものです。そして自分の考え、意見を世の中に発信する際にも、その媒体となるのは言葉なのです。研究者が書く論文や学会での発表、会社での会議やプレゼンテーションの資料、あるいはビジネスで自分が売ろうとしている商品のよさを説明するとき。このように言葉を使わなければ成り立たない状況は、文系・理系を問わず、あらゆる仕事で現出します。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「大学院生になってから私が新しく追加した行動パターンの一つに、観劇と映画鑑賞がある。私は凝り性のようで、二〇一九年の記録を見ると劇場に四三回、映画館に一二回行っていて、歴史ものの DVDを五一枚買っている(正直に数字を書くと仕事をサボっていると疑われそうだ)。学部時代の私は人混みが苦手で、書物と授業以外から情報を得ることの意味が理解できなかった。当時、科学史を担当していた故・梶雅範先生が授業中に熱心に歴史映画を勧めているのをいつも白けた顔で聞き流していた。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「映画館に足を踏み入れるようになったのは、修士課程で交換留学生としてイタリアに滞在していた時だった。高校で理数科に進学して以来、「みんな科学が好きで当たり前」という環境で甘やかされて生きてきた私は、留学して初めて、「いきなり科学の話を振っても会話が成立しない」という現実に直面した。ある日、人懐っこいルームメイトに映画に誘われて、「原作を読んだからいい」と断ったつもりだったのに映画館に連行されてしまった。そうしたら案外、映像を観るのは新鮮だったし、感想を言い合うのも面白かった(私はテレビやゲームを禁止する家庭で育ったため、そもそも映像を観ることに慣れていなかった)。そして、共通の話題として使える映画を便利なツールとして認識するようになった。少なくとも、いきなり「好きな数式は何ですか?」と訊く前に、「好きな食べ物」とか「好きな映画」くらいは話題に出そうと配慮するようになった。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著 「理屈をこねくり回して文句ばかり言っていた私を説得してくれたのは、古典の中の言葉だった。歴史というふるいに掛けられながら何百年間も読み継がれてきた言葉は、きっとこれからも時代や条件を超えて普遍的な価値を持ち続けるに違いない。現在でも愛され続けている昔の言葉に出会うと、あたかも物理学で基本法則を知ったときのような気持ちになることがある。」 —『新・大学でなにを学ぶか (岩波ジュニア新書)』上田 紀行著
0投稿日: 2025.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学に合格してから、早一ヶ月が経過した。合格したときのワクワクや大学生活が始まる事への喜びは最早薄れ、日々に忙殺されている。さて、大学は何のために行き、何を学ぶかという本書の問いは、答えが一つに定まることはないと思う。私は、大学で色々な挑戦をして、これまで見えなかった新しい世界を見てみたいと思う。単位を取るということも確かに大事であるが、それ以上に学びに没頭したい。
0投稿日: 2024.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログたくさん本を読めば納得できることがたくさんあるが、受動的な教育を受けてきた高校を卒業したばかりの学生が読んでも難しいかもしれない。大学卒業時に自分が大学を通してやってきたことが正しかったのか、確認するために読むといいと思う。
0投稿日: 2024.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大学で何を学ぶか、学べるのか、学ぶべきなのか、という点に焦点を当てた本。 各章で異なる教授が、自身の経験に即して考えを述べてくれる。 中には参考になるものも多く、私が言語化できなかった一般の大学生に対するモヤモヤをストレートに言語化してくれている方もいて流石だと感じた。 特に学びと海の羅針盤と教養はどのような時に役立つのか、試行錯誤から学ぶの三つが印象に残った。 小説などの本を読むことを通じて、社会について学び、学んだことから得た疑問を解決することで・・・と言ったループの中で自分の興味があるものを見つけること、社会の中で辛い時、1%のひつじになってしまうときにこそよくわからないけど感動した文学作品が活きること、「役に立つから」「正しいから」学ぶのか、尺度が変わる世界と自分の中で選択することの難しさがあり、自分が納得できる選択をする必要があること。 この三つだけでも本書から学び取り、胸に留めておきたいと思う。 私自身は大学卒業間近に読んでしまい、読めば読むほど自分が「してこなかった」ことについて解説がなされ悔しく思った。私のような学生を少しでも減らすため、大学1,2年生の後輩に嫌われない程度にそれとなくおすすめしようと思う。
0投稿日: 2024.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ東工大のリベラルアーツ研究教育院の13人の先生方が「大学でなにを学ぶか」また、リベラルアーツ(教養)とは何か、という問いに答えている。 13人もの先生の話なので、一つ一つが短くて読みやすく、入学式での校長先生のお話のような感じだったが、次の4月から大学生の私にとってはとてもためになることばかりだった。 教養の重要性について熱弁している先生もいれば、読者に寄り添ってやる気を引き出してくれる先生や、自らの大学生活、さらには大学教員生活での経験をたっぷり書いている先生など同じテーマだが十人十色で、面白い本だなと感じた。 すでに2度読んだが、何度でも読み返したくなる良い本だと思った。
0投稿日: 2023.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ東京工業大学のリベラルアーツ研究教育院で教育に携わる先生方13人からの大学での学びに関するアドバイスです。
0投稿日: 2021.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB29741523
0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学で学ぶ意義を十分考えてきた一般人ならあまり目新しいことはない、というか「大学は答えを出すことではない勉強をするのだ」系の話に圧倒的に偏っているのだが、伊藤亜紗『女子学生たちへ』と室田真男『「リーダーシップのある専門家」になるために』は割と切り口が違うので面白い。 特に伊藤亜紗の、「世界は書き込み可能である」というのはとてもとても大事なメッセージだと思う。一人ひとりの小さな書き込みが世界の見方の標準をアップデートしていくということ、大人でも分かっていない人多いと思うので。 要読→『リーダーシップ教育のフロンティア(研究編/実践編)』(北大路書房)
1投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本経済新聞連載コラム「池上彰の大岡山通信」 18歳プラス”読書で視野を広げる”という記事の中で紹介されていた本。 池上彰氏をはじめ、13名もの著名人、大学教授の方々がそれぞれの考えを学生たちに語り掛けるように書かれている。学者としての姿勢を貫きつつも、決して上から目線ではなく、学生たちの自主性を喚起させるかのように書かれている姿勢に好感が持てる。リベラルアーツについて考える良い機会になった。いずれにしても、学生側の学ぶ姿勢も大事ではあるが、大学側もより魅力的な教育機関になることを切に希望する。
1投稿日: 2021.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ東工大で教鞭を取っている研究者たちの 若者へのメッセージ。 理系トップ大学の先生方が リベラルアーツを勧めている。 でも、これって実は難しい。 私も大学時代は、やっと好きなことだけできる! と思って、文学系の講義ばかり取ってたなあ。 他の分野は最低限だけ取って。 今なら、もっと幅広に学ぼうと思うのに。 でも、今の自分がそう思える人間になったのは、 大学時代に好きなことばっかりやってたからだとも思う。 生徒にも、視野を広くしろと指導するけど、 高校のうちに分からなくても良いと思っている。 いつか彼らが自分で気付く時のための種蒔きを していると思っている。
0投稿日: 2021.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生までは、先生や親の言う通りにしておけば「良い子」として評価してもらえる。しかし、社会に出ると、その「良い子」は「言われたことしかできない、創造力がない人間」となり、仕事ができないと評価される。 私は経験からこのように思ってきた。 では、大学で何を学べは良いのか。 本書の先生方の答えをまとめると、「自ら考え、問う」ことである。 学費は高いが、学問以外にも、自分を見つめなおし成長できる時間を与えてくれるのが大学だと感じた。
0投稿日: 2021.02.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
大変革期のVUCA(Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous)な社会では「定型業務の専門家」ではなく「適応力のある専門家」が必要だ。この混迷期に適合した専門家は、具体的知識(クイズ的知識)ではない、より高次な知識(メタ知識)を身につけた人のことで、アクティブラーニング(既存の知識を整理しなおす学習活動)を繰り返し行うことで育成される。 定型業務の専門家−−<知識のメタ化>−−>適応力のある専門家−−<リベラルアーツ教育>−−>リーダーシップのある専門家 『「リーダーシップのある専門家」になるために』(室田真男)より要約
0投稿日: 2020.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログなんとなく大学に行き何となく大学生活を送る学生が多いが、何のために大学に行き何を学びたいかを考えれば、より学生生活が豊かになる。
0投稿日: 2020.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ國分功一郎みたいな有名な先生が多数原稿を寄せているので読み比べて批評する精神も養えるし、漫然と偏差値が妥当な大学に進学しようとせずはっきり目標を持って進路を選ぶきっかけになる。
1投稿日: 2020.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ・この本を一言で表すと リベラルアーツとはなにか、大学生活の有効な時間の使い方を教えてくれる本 ・読み終わって感じたこと 大学は受け身的に学ぶ場ではなく、対話や学びたい学問の意思決定など主体性が必要である。 ・こういう人におすすめ これから大学生になる人。 なんとなく大学進学を進めようとしている人。
0投稿日: 2020.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルに惹きつけられた。 大学教員たちの考えを知ることで、学ぶ意味について知れると思った。 また、今後の大学生活を見つめ直す良い機会を与えてくれると思った。
0投稿日: 2020.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ今年度、本格的にリベラルアーツの授業を受け持つことで、予備知識を入れておくために講読。リベラルアーツっぽいことを講義する自信はあったものの、あくまで自己流だから、専門家・経験者のご意見を拝聴できた。 結論を先に述べると、教育する側として、既に理解している章もあれば、再発見できた章もあった。前者だと、池上彰「自ら問いを立てること」、國分功一郎「問いを発する存在になる」などは、普段の専攻教育科目でも発しているとおり。対照的に、後者の章としては、中島岳志「教養はどのような時に役立つのか」が、これまで頭の中でぼんやりと考えながら教えていた理想を、文章で具現化してくれていたうえで、非常に有益だった。20世紀の批評家・劇作家である福田恆存のメッセージ、すなわち「「99匹」のための実学、「1匹」のための教養」を事例としたのが、本章および本書の主題を明らかにするために、的を射ていた。リベラルアーツで得た「教養」というのは、「何らかの形で人生の前提が崩れた時」にこそ意味を持つものであり、大きな躓きを経験した時、「引っ掛かりのインデックス」が多いほど、危機に強い人間になる(68-69頁)。この点を、まだそれほど大きな躓きをしていない大学生に伝授できることこそ、リベラルアーツの授業に意味が出てこよう。 他方で、有用だったとは言い切れないが、いかにもリベラルでおもしろかったのが、中野民夫「僕は大学時代、何よりも旅から学んだ。」と、多久和理実「「リベラルアーツなんてやりたくない」という人へ」。これだけぶっ飛んだ大学生活を送れる余裕を、現代の大学生にも持ってもらえると、本書の役割も大きかったと言えるのではないだろうか。
1投稿日: 2020.03.28
