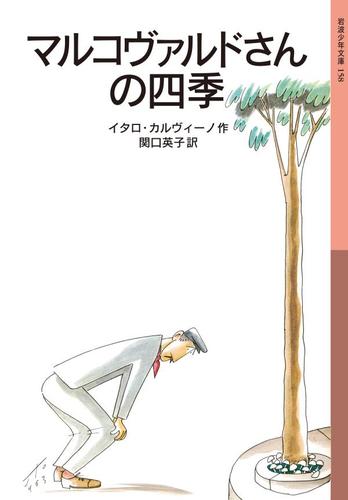
総合評価
(21件)| 4 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ『遠くから吹いてくる風は、都会に思いがけないおみやげを運んでくるものです。もっとも、それに気づくのは、よその土地の花粉でくしゃみを連発してしまう花粉症の人のように、感じやすい心を持った、ほんのひとにぎりの人たちだけですが』―『都会のキノコ』 「『見えない都市』を歩く」の文章に誘われて読む。岩波少年文庫の一冊。けれど、『この本は、子どもの本なのでしょうか? 若者むけの本? それとも、大人むけの本? これまで見てきたとおり、さまざまな側面がつねに糸のようによりあわさっているといえるでしょう』、と、作家自らが解説する通り、事は決して単純ではない。もちろん、子どもの思考が単純だと言っている訳ではなく、ともするとありがちな勧善懲悪、白黒のはっきりとした物語ではない、という意味である。と、和田忠彦先生も書いていたので読んでみたのではあるけれど。 イタロ・カルヴィーノの一冊と言えば「見えない都市」かも知れないけれど、個人的には「冬の夜ひとりの旅人が」がお気に入り。どことなく多和田葉子の「容疑者の夜行列車」と重なる印象があるのだけれど、全体としてはエーコの小説を読んでいるのかなと思わせるくらいに凝った仕掛けがある一冊。もちろん空想科学小説的なカルヴィーノの小説も好きだけれど、そちらの仕掛けは何となく虚構感が強くて素直には読み解けない。一方、冬の夜ひとりの旅人が、や、見えない都市、は哲学的な思考に嵌まって脳がぐるぐるとする感じがとても良い。その対比の軸で考えると本書は哲学的な方の分類へ傾くのだけれど、何かもっと素朴なことを言っている印象に塗されてカルヴィーノの本当に言いたいことが見えにくい。 足掛け10年を費やして書いた一冊ということで、そこには何等か通底するこだわりのようなものがあるだろうとも思うのだけれど、全体の印象としては日刊新聞の四コマ漫画のような風刺の匂いこそするけれど、何かを強烈に否定している訳ではないし文明社会を批判している訳でもない。自然を愛する一見純朴そうなマルコヴァルドさんにしても、絵に描いたような子だくさんの貧乏生活を営む青色労働者だけれど、小賢しいことを考えたり、小さな悪事を躊躇なくしてみたりと簡単に肯定も否定もできない人物として描かれている。ではそんなあくせくと働き生活に汲々としている人物を見てくすりと笑っていればいいのかと言うと、如何にも都市生活の流れに上手く乗っている人々との対比の中では思わず擁護したくなる人物でもあったりするので、何となく読んでいて落ち着かない。例えば、そんな風に左右に揺さぶられるような感覚は、実は冒頭引用したこの本の始まりの文章の中に既に見出せるとも言えるのだけれど。 わざわざそんな人物とその家族の暮らしを春夏秋冬の繰り返しの中で描いてみせるのだから、作家にはきっと狙いがあったのに違いない。恐らく一番大切なことは自分たちが生きている今、自分たちを取り巻く環境や様々な人々の思惑、のようなものから目を逸らさずに、一つひとつ考える、ということなんだろう。それがカルヴィーノの言いたかったことなのかな、と思う。
4投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ話の内容自体はごく単純だけどシビアな表現で書かれた文章です。気分転換に気軽に楽しめるかと思って読み始めたら、意外と考えさせられることの多い短編集だった。 作者による解説によると「産業社会」というあまい夢だけでなく、「いなかの生活」というあまい夢も、攻撃の的となっているそうで、「昔にもどる」ことができないだけでなく、その「昔」自体が、じっさいには存在したこともなく、幻想にすぎないとのこと。 マルコヴァルドさんの自然に対する愛着は、都会に住む人だけが持つもの、都会で自分のことを「よそ者」と感じているマルコヴァルドさんこそ、ほんものの都会人、という作者の言葉にすごく納得できた。
0投稿日: 2023.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ笑えるというか「こんなことしていいのかよw」という話が多かった。ラスト2話が怖い。中之条ガーデンの森の図書館で読んだ。
0投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「この本は、子どもの本なのでしょうか?若者むけの本?それとも、大人むけの本?」 ー作者による解説より 「マルコヴァルドさんの四季」というタイトルと表紙を見て、どんな内容のお話だと思いましたか? 私はマルコヴァルドさんという男性が四季おりおりの情景の中で何か素敵なものを見つけ、小さな幸福とふれあう物語を想像しました。 …これが遠からずも当たらず。 この本はマルコヴァルドさんとその一家が過ごす四季×5年分の20話を収めた短編集。 マルコヴァルドさんは、イタリアのどこか知らないけど都会の街で8人家族を養う大黒柱。 そしてどんな仕事をしているのかさっぱり分からないけど、低賃金労働者で家計は苦しい。 ひもじくて野生で生えてるキノコを採りまくろうとしたり、寒さに震えながら薪を買うお金がないから森で薪を調達してきたり、スーパーで他の客がパンパンにカートに商品を詰め込んでいるのが心底羨ましくて買う気はないけどカートを品物でパンパンにしてみたり。 そんなこんなで田舎から出てきたマルコヴァルドさんは、田舎の自然に思いを馳せ、都会の汚らしさにため息をつきながらも、その街で家族と暮らしていきます。 さて、その短編一話一話の展開なのですが、どれも一話ごとに起承転結がしっかりしていて皮肉と哀愁とちょっとした希望に富み、面白いのです。 ただ悲しいかな、物語の最初に街の中でマルコヴァルドさんが小さな幸せや生きがいを見つけることは、読む前の想像通りなのですが、ラストはいつも悲しい結末に突き落とされ、こちらは読みながら呆然とします。 …ええっ!?ここみんなで笑ってハッピーエンドじゃないんだ!!? 救いようがないとまではいかないけど、ちょっとつらい。 割と毎回、そんな感じ。シビアな終わり方も。 どんな展開でそうなるのかは読んでのお楽しみということにして…。 この、何かいいことを見つける→なんやかんや盛り上がりの展開がある→切ないラスト、という展開は、どうやら作者のカルヴィーノが意図的に織り成していたらしい。 完全に術中にハマる。 けれどあまり悲壮感なくページをめくり読み進めてしまうのは、マルコヴァルドさん含めマルコヴァルドさんの子どもたちがめちゃくちゃ逞しくて、次みつけた希望に目を輝かせられるガッツがあるから。 そしていつもマルコヴァルドさんが幸せだ、素敵だと思い焦点を当てるのは、街中のネオンでも喧騒でもなく、植木鉢でぐんと背を伸ばしている植物や、星が輝く夜空、きれいでおいしい空気。 そんなマルコヴァルドさんの感性は、「都会の暮らしにふさわしくない目」と解説などで表現されています。 なるほど、ふさわしくない。 たしかにそうかも。 でもそれと合わせて印象深かったのは、田舎から出てきたばかりのマルコヴァルドさんには都会の街の風景がキラキラして見えたということ。 これも対比として表現しているのかな。 個人の感想だけど、マルコヴァルドさんはちょっとなよっとした感じがあるけど、その子どもたちはめちゃくちゃパワフル。 自分たちは食うに困る生活を送っているのに、裕福だけど日々をつまらなさそうに送っている男の子を見て「恵まれない子どもだ」と感じるというタフネス。 一連の物語で輝いて主人公然としていたのは、案外子どもたちの方なのかも。 あとはこれが書かれたのは1950〜60年代初期というのに、古びた感じが一切しない。 つい去年書かれたばかりですよと言われても納得してしまいそうな新鮮さ。 マルコヴァルドさんが過ごす四季は、はちゃめちゃな展開もあるけれど、今の私たちの生活と照らし合わせて共感を呼ぶものだと思いました。 なんだかついまた読みたくなる、そんな本。 ちなみに特に好きだなーと思ったのが、 「高速道路ぞいの森」「牛とすごした夏休み」「毒入りウサギ」「月と《ニャック》」「けむりと風とシャボンの泡」「がんこなネコたちの住む庭」「サンタクロースの子どもたち」 です。 以下備忘録がてら目次をば。 春 都会のキノコ 夏 別荘は公園のベンチ 秋 町のハト 冬 雪に消えた町 春 ハチ療法 夏 土曜の午後、太陽と、砂と、まどろみと 秋 お弁当箱 冬 高速道路ぞいの森 春 おいしい空気 夏 牛とすごした夏休み 秋 毒入りウサギ 冬 まちがった停留所 春 川のいちばん青いところ 夏 月と《ニャック》 秋 雨と葉っぱ 冬 スーパーマーケットへ行ったマルコヴァルドさん 春 けむりと風とシャボンの泡 夏 都会に残ったマルコヴァルドさん 秋 がんこなネコたちの住む庭 冬 サンタクロースの子どもたち 作者による解説 訳者あとがき
11投稿日: 2022.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『梨の子ペリーナ』の再話者となっていたイタリア民話編纂の巨匠イタロ・カルヴィーノ氏の手掛けた児童書。 ズバーブ商会の倉庫の人夫として働くマルコヴァルドさん。 思いついた妙案を熟慮せずに行動に移してしまい、いつも期待していたのとはちょっと違う結末(どちらかというと失敗)にたどり着いてしまう。 妻とたくさんの子どもらを抱え、かつかつな暮らしを送りながらも自然を愛でる心に溢れ、人並みな欲はあるけれど後先見ずに突き進んで窮状を脱せない様は返って善良さが滲み出ていてにくめない。 そんなマルコヴァルドさんの春夏秋冬季節にひとつのエピソードを5周繰り返す形での連作短編集。 比較的あっさりとはしているが、へんてこエピソード達の間に、「おいおい。。。」といった呆れや忍び笑いあり、人間の心の浅ましさを垣間見るものあり、ときには一抹の切なさを感じるものありと玉手箱的作品。 挿絵がいい感じ。
28投稿日: 2022.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ期待以上におもしろかった! おもしろさの方向性で言えば、「サザエさん」のようなおもしろさだ。 登場人物たちの思考や行動が容易に予想できて、その結果も予想できてしまう。 「あ~あ、またあんなことして、もう、サザエは。」みたいな。 この本では、マルコヴァルドさんの春夏秋冬に関する短いお話がたくさん収録されていて、四季が何周もする。 四季が何周もするのに、マルコヴァルドさんは懲りない。まったく懲りない。 毎回、「マルコヴァルドさんか家族がなにかを見つける・思いつく→大喜びでそれにくいつく→うまくいかずにがっかりする」という展開だ。 個人的にとくに愉快だったのは、 スーパーの話(家族でスーパーに行ったけどお金がなくて何も買えないから、カートを押して買わない商品を入れることを楽しむ・・・) 洗剤サンプルの話(こども達が洗剤サンプルを大量にあつめて売ろうとしたが・・・) バスを乗り過ごす話(マルコヴァルドさんが知らない停留所で降りてしまい、目的のルートに戻るために四苦八苦・・・)
4投稿日: 2022.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログマルコヴァルドさんの四季のタイトル通りマルコヴァルドさんが四季を過ごす話。身近なものから季節の変化を感じとる感性が素敵。
0投稿日: 2021.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ちょっぴりズレてるマルコヴァルドさんの素敵な日々。 都会の中であくせく働き、四季の移り変わりに心を寄せる。マルコヴァルドさんを紹介するとそういう人なのだが、それはこの物語の魅力とはちょっと違う。 マルコヴァルドさんは、都会の中の小さな自然を見つけては喜び、しかし物語はちょっとビターな方向に転がっていく。公園のベンチを別荘と洒落込んでも光や音や臭いのせいで眠れない。キノコを見つけたら食あたり。スーパーマーケットやネオンサインに振り回される。 でもマルコヴァルドさんは挫けない。子沢山で家計は苦しく、いつも思ったようにはいかないけど、マルコヴァルドさんはブツブツ言いながらも楽しそうだ。 生きるってこういうことなんじゃないかと、便利さに染まりきって疑問にも思わない自分を振り返る。
0投稿日: 2021.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログちょっとシュールな現代童話、といった印象。ただただ現代童話にありがちなシニカルさに偏ってばかりではなく、ひねりを効かせた笑いあり、都会ならではの物悲しさあり、「意味怖」的な話もあり…それらが豊かな描写で描き出される。後半には、今に通ずる社会問題を取り上げた話もあり、物語とは別のところでドキリとしたり…。幅広い年代で、それぞれの視点で読める良書だと思う。
0投稿日: 2020.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然を愛でることが得意(というより現実逃避が上手い?)な貧乏子沢山のマルコヴァルドさん 児童文学の顔しながらそのじつ随所に散りばめられた皮肉とブラックユーモアに大人も楽しめるお話たち 一話が短いし繋がりもほとんどないので気が向いたときに一話、また一話と気軽に読みすすめられる
1投稿日: 2020.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.8 ユーモアの中にも悲哀があり、ほっこりするかと思えばかわされ。現実と別世界のあいまいな感じ。世の中のバカらしさ。世知辛い。でも一生懸命。
0投稿日: 2020.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ都会のまんなかに暮らしながらも、心うばわれるのは、季節のおとずれや生きものの気配。大家族を養うため、家と会社のあいだを行き来するマルコヴァルドさんのとっぴな行動とユーモラスな空想の世界が、現代社会のありようを映しだします。
0投稿日: 2016.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログカルヴィーノの作品は邦訳あるものは殆ど全部読んでたつもりだった。もしかしてカルヴィーノのファンと言っていいかもしれない。幾つかのものは再読すらしているから。「くもの巣の小道」は自分の楽しみのために、「冬の夜一人の旅人が」は若い友人に勧めるために。 しかしこれは未読だった。半世紀以上も馬齢を重ねていれば大概の小説とインド映画の筋は忘れてしまうのだが、児童向小説は比較的記憶から抜け落ちることがない。そしてこの「マルコヴァウドさんの四季」は児童向小説なのである。 子供のために書かれたからと言って、決して楽しい小説ではない。主人公のマルコヴァルドさんはトリーノを思わす工業都市に暮らす労働者だが、かれと4人の家族が惹き起こす騒動に語り手は決して同情的ではない。かれらの愚行に対する冷ややかな距離感が、全篇に独自のペーソスを行き渡らせている。 面白いのは、マルコヴァルド一家の愚行が、ほとんどの場合食べ物に対する欲望によって惹き起こされていることである。飢餓がかれらを愚行に走らせているのではない。かれらはそれなりには満ち足りているのだが、終始美味いものへの欲求があり、それが虚栄心を刺激してやまないのである。 この作品は20の短篇から成っており、5つごとに春夏秋冬に振り分けられているが、それらが厳密に時系列上に並んでいるわけではない。たぶんこの区分は上記のような「美食への渇望」を導入するために設けられたものであろう。 しかしこの小説では美食が事細かに描写されるわけではない。欲望の対象となる「美味いもの」は漠然とフンギのフリッターとかチェルヴェッラとか(チェルヴェッラというのは豚のセルヴェッソから作った腸詰めのこと)ウサギのローストとか書かれているだけである。マルコヴァルド一家がこれらにありつくことは決してないからである。 カルヴィーノには左翼的傾向があるからこの中に資本主義批判を読み取る者があっても無理ないことに違いない。しかし食いしん坊の間では消費への欲求は容易に美食への渇望へと置換される。カルヴィーノもまた自らの(胃の)中に同様の変換装置を共有していたのであろう。だからこそこれらの物語はかほども悲しいのである。同じ胃の持ち主である私にはそれがよく分かる。
0投稿日: 2015.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ思っていたのと違って、すごく考えさせられる内容だった。 小さい頃読んでいたら、純粋に楽しい話で、裏の世界は見えなかったと思うけど、色々考えてしまうあたり、自分が大人になってしまったんだなーと思って、少し寂しくもあり・・・ でも、いい作家を知れてよかった!
1投稿日: 2015.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ50年ほど前に書かれたイタリアの姿。でも現在にもいまだよくある光景がそこにある。時代差を感じる部分は、マルコヴァルドさんの貧しさくらいか。職を持っている人がなかなか食べていけないほど今の先進国は深刻ではないのではないかと思うくらいか。都市のなかで視点を変えて暮らすほのぼのとした一面があって良書であった。
0投稿日: 2014.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログファンタジー以外の児童書は滅多に読まないのだけれど、 児童文学作家の先生が描写がすごい本として挙げていて、読んでみた。 裏表紙の解説を読んで、抒情的なもっとウェットな内容を想像していたけれどとんでもない。 都会の中の自然や、季節のうつろいや音・色・香りなどに対する描写は確かに素晴らしい。 でもそれ以上に現代社会への皮肉が壮絶にこめられていて、読んでいて始終にやにやしてしまう。 子供と大人で楽しみ方が全く変わる作品だと思う。 マルコヴァルドさんやその一家が結構悪いことをするので (それらもコミカルにユーモアたっぷりに描かれていて大変面白いが) なかなか日本では出せない作品だなあと感じる。 他の方も書かれていたけど、これを少年文庫にいれる岩波はすごいと思った。その内容の普遍性と言い、描写の美しさと言い、実はかなり文学性の高い作品だと思う。 表紙・挿絵もとても合っていて素敵な本。
1投稿日: 2014.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
まずはこの表紙の腰をかがめたおっさんの何とも言えないとぼけた表情が◎です。 で、この表紙の絵やら本をパラパラとめくった時に目に入る挿絵を見る限りではどれもこれもどことなく風刺的 & おとぼけ風の印象を持ち、ほのぼの~としていつつもちょっぴりピりっと風刺が効いたお話、例えて言えば新聞なんかに掲載されている4コマ漫画的な物語を連想するわけです。 ところがどっこい、これが読んでみるとちょっと違うんですよね~。 物語のタイトルにもなっているマルコヴァルドさんはとある町(都会と言うべきか?)で会社勤めをしている中年の男性です。 会社勤めと言ってもいわゆる「ホワイトカラー系」ではなく「ブルーカラー系」の労働者です。 当然のことながら会社の廊下を風をきって颯爽と歩き、高収入を得ているタイプではなく、ま、はっきり言ってしまえば貧乏暮しを余儀なくされているおじさんです。 そしてこのマルコヴァルドさん、「貧乏子だくさん」の言葉通り、6人のお子さんを抱え、最初は半地階みたいな部屋に、次には屋根裏部屋に住むようなファッショナブルという言葉とは無縁の生活をし、言ってみればギリギリの生活を送っている生活者です。 借金まみれで家賃の滞納は当たり前、日々の食事もギリギリという生活ぶりらしい・・・・。 周りには豊かなものがいっぱいあるにも関わらず、それとは無縁の生活を送っていて、そのことに全く傷ついていないわけではないものの、基本的には「現代風」と呼ばれるものに関しては根っこの部分では興味を持っていない、ちょっと超然とした人物です。 かなりの夢想家で、四季折々の風物を愛でる溢れんばかりの心を持っているのですが、それが裏目に出て都会生活者としては失格と言えるようなドタバタ喜劇(悲劇?)を演じてしまう・・・・・そんな人物。 物語はそんなマルコヴァルドさんの「脱線物語」が20編(春夏秋冬 5回り分≒5年分)描かれています。 自然を愛する(それも観光としての自然ではなく、本来地球上に人間と共存している自然物をあるがままの存在として愛おしく思う)と言うと、現代では「人間性の回復」という言葉と一緒に語られることが多いわけだけど、マルコヴァルドさんのドタバタぶりを見ていると、単なる変人でもあり、「困ったちゃん」でもありというあたりが、この物語の最大の風刺部分なのではないかしら?? と言うのもね、この物語。 言ってみればある1つのパターンが20編全てで貫かれているんですよ。 四季折々の風物の描写 ここは瑞々しい文章で時に詩的で時に音楽的。 何とも言えない風情を醸し出します。 ↓ マルコヴァルドさんが自然に触発され「変な行動」に走る 「気持ちは分からないじゃないけど・・・」と思わせられる、でも「都会人としては常識はずれ」な行動に呆気にとられます。 ↓ 想像以上に話が大きくなってしまいやれやれ・・・・・ 「ホント困った人だねぇ」と思いつつも、彼の努力(?)はいつも報われず、そんなマルコヴァルドさんのことをカラカラとは笑えなくて、そこに何かしらの「哀しみ」みたいなものを感じます。 というパターンです。 著者のカルヴィーノも解説文の中で、このマルコヴァルドさんの物語のことをこんな風にまとめています。 大都会のまんなかで、マルコヴァルドさんは、 1. 身のまわりのできごとや、動物や植物など生きもののかすかな気配に、季節のおとずれを感じとる。 2. 自然のままの姿にもどることを夢見る。 3. 最後には、決まってがっかりさせられる。 そしてそんな物語20編を読了した時にふと思うのは、これってかなりデフォルメされてはいるけれど、現代の日本にも通じる部分がある物語だよなぁ・・・・・ということです。 つまり、マルコヴァルドさんは、都会の暮らしにどこか居心地の悪さを感じていて、自然への憧れを持った人物なわけです。 でも、自然に帰ろうとすると必ず失敗してしまう可愛そうな人でもあります。 そんなマルコヴァルドさんの姿に垣間見えるのは「都会人というのは、マルコヴァルドさんと同じように、田舎に憧れてはいるけれど、実際には田舎では暮らせない人」のことを言うのかもしれない・・・・・という現実だったりするわけです。 「夏、別荘は公園のベンチ」を読むと、自然に憧れるマルコヴァルドさんが、都会生活の中で手に入れられる自然というのは結局のところ「都会の真ん中の公園」、つまりは人工的に作られた自然でしかないことが描かれています。 そんな姿に都会生活に疲れはじめた頃、「六義園」とか「新宿御苑」とか「後楽園」を徘徊していた我が身がダブリます。 又、「別の夏、牛とすごした夏休み」を読むと、都会の労働者が皆、同じような時刻に一斉に目覚まし時計でたたき起こされ、寝ぼけ眼のまま朝食をかっこみ、満員電車に揺られて同じ方向に向かって民族の大移動を始め、「相手のわき腹をひじでおしあいながら」前へ前へと進んでいく様子が描写されます。 これを読んでいる時、KiKi は随分昔、新宿駅で感じた「こんなに多くの人が脇目も振らず同じ方向にまるでベルト・コンベアに乗せられた部品の如くに動いているのって、ひょっとしたら変なことなんじゃないか?」という想いを、そして、その延長線上に今のLothlórien_山小舎生活があることを思い出させられました。 都市生活、文明社会、資本主義社会、拝金主義等々を揶揄しながらも、そこに何とも言えない優しいまなざしを注いでいるカルヴィーノの文章に、ある種の達観を感じつつ、「人間が生きている現代」「都会の中にもある自然」を感じ、一つ一つの短編をじっくりと味わうことのできた読書でした。 良書だと思います。 もっともこれ、子供向きの本かどうかはちょっとビミョーなところかもしれません。 少なくともさわやかな読後感、未来への希望というよりは、人生の現実・悲哀みたいなものがかなり表に出ちゃっているので・・・・・。 でも、この年齢になった KiKi が読むと「自然」と「文明」の狭間の中で、飄々ともがいている(って変な日本語ですけど)マルコヴァルドさんの姿に、何とはなしに親近感を覚えてしまうんですよね~。 マルコヴァルドさん、都会で暮らしていた時代には決してお友達になれそうもなかった人物だけど、今の KiKi ならそれなりに仲良くできるかも・・・・・・(?)しれません。
1投稿日: 2012.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこないだ読んだ『マルコヴァルドさんの四季』は安藤美紀夫訳だった。ふと、訳者違いの版違いが出てるのを見つけて、図書館で借りてきて、またマルコヴァルドさんの話を読む。この新版は関口英子訳。 表紙カバーに使われている絵は違うが、イラストはかわらずセルジョ・トーファノ。 新版には、作者のカルヴィーノ自身による解説もおさめられていて、それを読んで、マルコヴァルドさんのお話は最初に書かれたものが1952年(60年前!)で、最後のは1963年に書かれたということも知る。もう半世紀前のイタリアで書かれた話が、どこか今の日本社会を思わせる。 ▼マルコヴァルドさんは、数多くの失敗を経験しながらも、けっして悲観的になることはありません。彼に敵意をいだいているようにも見える世界のなかで、自分らしさを感じることのできる世界につながるぬけ道を見つけようという心を忘れないのです。なにがあってもあきらめず、ふたたび挑戦する心の準備が、いつだってできています。 …(中略)… 世の中のできごとや状況にたいしては、ものすごく批判的なまなざしをむけながら、人情にあふれた人びとや、あらゆる生命のきざしにたいしては好意にみちたまなざしをむける…そんな、身のまわりの世界をながめるときのマルコヴァルドさんのまなざしにこそ、この本の教訓があるといえるのかもしれません。(pp.271-272、作者による解説) おもしろいところはいろいろあるが、もう一度読んでもおもしろかったのは「がんこなネコたちの住む庭」の秋の話。昼休みのあとの時間つぶしに、ネコのあとをつけて歩くマルコヴァルドさん。ネコの目を通していろいろな場所を観察すると、「見なれたはずの会社のまわりの風景に、いつもとちがったライトがあたっているように」感じられる。おまけにマルコヴァルドさんは、ネコの背丈になって、つまりはよつんばいになって、ネコのあとをついて歩いたりするのだ。 イタリアの大都会の真ん中に住んでるというマルコヴァルドさんは、ぎんぎんに都会的なものには目もくれず(まったく目に入らないらしい)、しかし、木の枝で黄色くなった葉っぱや、屋根瓦にひっかかっている鳥の羽根、馬の背にまとわりつくアブ、テーブルにあいた木くい虫のANA、歩道にはりついているイチジクの皮…などは見逃さない。 都会の野蛮人のようなマルコヴァルドさんの話を読んでると、マルコヴァルドさんとはちょっと違うけれど、『隅田川のエジソン』とか、『ゼロから始める都市型狩猟採集生活』なんかを、むらむらとまた読みたくなるのだった。 (7/8了)
0投稿日: 2012.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり昔に読んで、児童書にしては暗い本だと思っていたが、今再び読み返すと、その暗い部分の意味がよく分かるだけになおさらやりきれない気持ちになる。文学的にはもっと高い評価をしてもいいと思うが、一筋の希望も見えない話は、やはり面白いとは言い難いので星は3つにしておく。もう少しユーモアのある風刺なら救われるのに…。しかし、カルヴィーノは大好き。
0投稿日: 2012.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ子だくさんで、半地階に住み、会社と家との往復で生活に疲れきっているようなマルコヴァルドさん。そんなくたびれた中年男にも自然の四季折々はいくばくかの潤いをもたらしてくれる。真面目な気持ちで読んでいると、ずっこけてしまう。それはないだろうというオチが待っている。しかし・・・これって子どもの読む本かなぁ、首を傾げたくなる。大人の私にはそこそこ楽しめるけれど。
2投稿日: 2011.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ馴染んでいたせいか、前に出されたときの訳者によるものの再版でなくて、少しがっかりしましたが、マルコヴァルドさんを通して見る少し不思議な世界……おすすめです。
1投稿日: 2009.07.13
