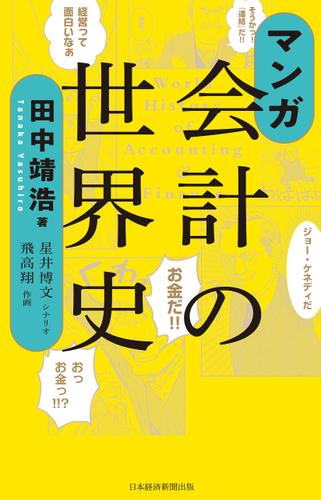
総合評価
(18件)| 3 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログさらっと読めて、大雑把に会計の歴史を把握できる。 複雑な会計事務に取りかかる前に、そもそもなぜこんな仕組みが必要だったのかという視点があったほうが良いと思う。 かなり大胆で大味なまとめ方をしている。
0投稿日: 2025.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ会計の世界史は、会計というわかりづらい考え方に、それが生まれた背景、経緯を伝えることで、会計に輪郭を与える。 マンガで大枠の流れを伝え、解説で中身を補う。 なお、本書は世界史であって、会計手法を理解するためではない。 簡単に読めるので、会計を覚えてもらいたい人への、ちょっとしたエピソードを仕入れる気持ちでどうぞ。
0投稿日: 2025.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ簿記をほんの少し勉強したことがあるくらいで、会計にあまり興味があるわけじゃなかったけど、面白かった。歴史漫画のように楽しめた。 名前は聞いたことあるけど、何をした人かわからない人たちがたくさん出てきた。
0投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。マッキンゼーの創始者は、教授だったんだ。地味な会計学の。コストより利益、過去より未来。財務会計が守りで、管理会計が攻めの会計。
0投稿日: 2024.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ会計に興味はあったのですがどれも難しそうな本ばかりでした。 本書は漫画ということで読んでみました。 株式会社の成り立ちや、減価償却などなど 会計の歴史を漫画で学べて面白かったです。簿記の勉強でも原価計算とか減価償却は出てくるのですが、この漫画を読んで成り立ち込で勉強するとより理解しやすくなると思いました!
0投稿日: 2024.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ分かりやすくまとまっていておすすめ。 聞いたことのある言葉、なんとなく知っている言葉でも、それが生まれた背景知識を知ることができるし、歴史という流れとしてなんとなく知っている出来事も「会計」としてシンプルに繋げてくれているので理解を深めることができる。 歴史も苦手、会計も苦手という人にとっても比較的抵抗感を無くすことができる本。
0投稿日: 2024.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在の「会計」がどんな背景でどう成り立ったか?を漫画でわかりやすく解説した本。会計と聞くと難しいイメージしかなかったけど、すべての誕生には歴史的な意味があったこと、なぜ重要かということがわかってよかった。これを読んだから決算書が読めるようになる、というものではないが、会計が苦手と思っている人には興味を持つきっかけになると思う。
0投稿日: 2024.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログお手軽に理解したいと漫画を手に取ったが、元の本の面白みがなくなり(当たり前だが)、ちょっと残念だった。
0投稿日: 2024.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画がとってもわかりやすかったです。 「会計」と聞くとどうしても難しいように感じてしまうので、この、漫画+ちょっと説明、な作品はとってもありがたいな。と思いました。 この本を読んでもうちょっと興味が湧いたので、文字だけの方もまた読もうと思います。
1投稿日: 2023.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログさらっと短時間で読めて、ビズネス史と会計の繋がりが分かる。 マンガではない、元の本も読みたくなる。 中高生に読ませたい。
0投稿日: 2023.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ前に『会計の世界史』を購入してずっと未読のまま。 しかし、春から社会人になるにあたって今簿記の勉強をしています。 簿記の勉強は特に面白みはなく、そんな時に『会計の世界史』って買ってたなと思い出しました。 その前に漫画版を読んでおこうと思ってこちらも拝読。 今現在の会計がどのように変化してきたのかが分かりました。何事にもはじめはお金がかかるし、そのお金の管理が信頼を集めることになる。 株式会社ができたり証券会社ができたり、それらの起源は読んでいて面白かった。 また、歴史の教科書じゃちょっとしか触れられていない蒸気機関車の周りの話や世界恐慌後の経済の話は非常に興味深かった。 経済や会計に興味を持てば、企業や経済の未来も少しは理解できるかな。
0投稿日: 2023.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ全ての事象には因果関係がある。 簿記という一見無味乾燥の学問も、さまざまなストーリーを経て確立されてきた。 本書ではそのポイントがわかる。1時間程度で読了可能。簿記を学んでいる方こそ、お勧めできる一冊と思う。目的を知ってこそ、そこに意義が生まれ、意欲が生まれるはずだ。 メモ 簿記→イタリアの為替手形 減価償却→蒸気機関車 株式会社→鉄道 ガバナンス、CPA、ディスクロージャー→ケネディ 狭義の株主と広義の株主(潜在株主) 現金主義から発生主義へ、不正増 管理会計→会計の過去から未来への転換 国際会計(IFRS)→アメリカだと黒字、イギリスだと黒字
0投稿日: 2022.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ簿記(帳簿)の誕生イタリア ゴジモ•デ•メディチ フィレンツェの銀行業 帳簿管理の導入 この繁栄によりフィレンツェルネサンス芸術が発展 ルカ•パチョーリの書籍スンマよってヨーロッパに簿記広がる メディチ銀行破綻後の混乱によりルネサンス凋落 ダヴィンチはパリへ流浪 そのためルーブル美術館にモナリザがある 株式会社と証券取引所の誕生 16世紀スペインの支配下にあったオランダ 活版印刷によりプロテスタント勢力が増しカトリックから独立 宗教に寛容ユダヤ人やカトリックも集まり経済の中心地に 世界初の株式会社オランダ東インド会社(VOC)誕生 所有と経営の分離 証券取引所の誕生 世界初のバブル崩壊 チューリップバブル発生 会計士と監査の誕生 1830年リバプール蒸気機関車が誕生 減価償却の必要性、現金主義から発生主義へ 発生主義によりデロイト、プライス、ウォーターハウスなどイギリスにて若き会計士と監査登場 連結と原価計算の誕生 19世紀後半 アメリカにて鉄道建設ラッシュと鉄道投資ブームが起こり、ヨーロッパの投資家が安全性分析(経営分析)を勉強 鉄道会社の乱立により激しい価格競争と景気の波が企業を襲う 単位当たり固定費を安くするために大量生産を行い供給過剰そして販売価格の下落を招く 乗っ取り屋の登場、石油業界ではロックフェラー、鉄道業界ではJ•P•モルガン 所有権を収めつつ経営再建させる手法はモルガニゼーションと呼ばれる、持株会社と連結決算の始まり アンドリュー•カーネギー さくらんぼの逸話 標準化、分業、機械化により原価計算に意味が生まれる。原価計算を駆使して鉄鋼会社を拡大 J•P•モルガンと手を組みUSスチールを設立史上初の10億ドル企業 1888年 カール•ベンツ 自動車は誕生当時、魔女の車といわれ様々な嫌がらせを受ける。開発を諦めようとしてところ、夫人と2人の息子が自動車の凄さを証明する為父に黙って200kmの世界初長距離ドライブに出かけ成功する。 道中で見つかった様々な改良点を修正しミュンヘン産業博覧会で金メダル受賞 1913年 ヘンリー•フォード 食肉加工場でみたベルトコンベアシステムを導入しT型フォードの大量生産が実現 大量生産+低価格販売という手法がその他の製造業にも広がりアメリカのモノづくりがヨーロッパを追い抜く程に成長、第一次世界大戦の勝利も重なりNY証券取引所は活気づく ディスクロージャー制度の誕生 しかし1929年10月24日暗黒の木曜日発生 ジョー•ケネディ(ジョン•F•ケネディの父) 銀行検査官の立場とインサイダー情報を活用し大恐慌の中財産を増やす 大統領選挙に目をつけルーズベルトに多額の献金 当選したルーズベルトはケネディを米国証券取引委員会初代長官の任命し ルーズベルト曰く泥棒を捕まえるには泥棒が一番 大恐慌によって失われた市場の信頼を取り戻す為 昔の悪友を説得しながら投資家保護制度の改革を行う US基準づくり、CPA監査制度、ディスクロージャー制度(決算情報の公開)、インサイダー取引の禁止 管理会計の誕生 シカゴ大学 会計学教授 ジェームズ•マッキンゼー 過去実績(原価計算)ではなく未来の計画(予算管理) シカゴ大学の管理会計講座は評判を呼び全米に広がる。有名人となったマッキンゼーは自らの名を付したコンサルティング会社を立ち上げ世界で最も名を知られた会計教授となる ファイナンスの誕生 マーカス•ゴールドマン 将来CF(企業価値)の見積りと割引計算のノウハウを持ち、友人のリーマン• ブラザーズとともに割安な会社を買収しIPOするという手法でゴールドマン・サックスは有名となっていく GE 家電製品の割賦販売を始め多角化 事業ごとの投資効率によって評価する ピエール•デュポンのデュポン公式(ROI=利益率×回転率)
0投稿日: 2022.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ読了しました。 ■なぜ手に取ったのか 著者の大ファンで買わずにいられなく手にした本です ■何が語られていたのか マンガで著者の「会計の世界史」がわかりやすく書かれていました。 私は原作を読んでいますので、内容自体について把握しております。 しかし、会計をマンガで読んだことはありません! 登場人物の個性がしっかりキャラクターに埋め込まれ活き活きと描かれており 一気に読んでしまいました。 原作同様ですが、会計・監査・ファイナンスなど端的かつ分かりやすく、 ストーリー仕立てで描かれており、裏のテーマである「父子の物語」も しっかり表現されていたので、原作同様、読み応えのある者になりました。 ■何を学んだのか 当時の考え方、見ていたものがマンガなので絵で表現されており、 リアルに人と物事のつながりついて感じることができました。 ■どう活かすのか 改めて原作を読みたくなる気持ちにさせてくれる本でした。 ■どんな人にお勧めなのか 会計リテラシーをつけたいと思っている人、会計、経理にアレルギーがある人 など経理、会計の入門書をさがしている人にお勧めの本です。
0投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ書籍版読了後におさらいとして読むのも良い。会計の歴史をマンガで簡単におさらいできる。最後に出てくる予算管理の内容がよく分からなかったので、別途勉強し直したい。
0投稿日: 2022.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ会計に関わる仕事をしていてある程度は理解していますが、歴史と絡めて読むのはとても面白かったです。 漫画が多いのでサクサク読めました。
0投稿日: 2022.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ国際会計基準、未だに日本はこの基準を巡って右往左往し、先送りしている。先日も細かい話だが、電子帳簿保存法を2年先送りしたばかりだ。そういえば皇室議論も見事に先送りされた。何も決められない国、日本。 フランクリン・ルーズベルト大統領は、インサイダー取引で私腹を肥やしまくった悪党ジョー・ケネディを証券取引委員会の初代長官に任命。不正をしまくり、悪事の方法を知り尽くしたケネディは、会計基準・監査制度・ディスクロージャー制度・インサイダー取引禁止等の華々しい成果を上げた。 そして会計は自分達の会社の状況を知る為の私的なものから、投資家のための公的な性格へと変化した。 そしてITにより証券市場はグローバルな性質を特段に高め、国際会計基準が重要となった。 日本は未だに鎖国状態というか、取り残された市場となってしまうが、いったいどう考えているのだろうか。
0投稿日: 2022.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ会計の歴史がイタリアから始まるところが面白いと思った(とても陽気でどんぶり会計のイメージがあったため)。 大きな産業ができると必要とされる会計も変わり、今の形になったことがよくわかった。でもやっぱり複雑化した今の会計はかなり難しいなぁと感じた。
0投稿日: 2022.01.01
