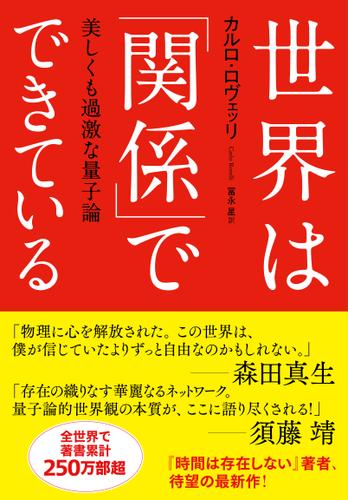
総合評価
(44件)| 12 | ||
| 8 | ||
| 16 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ「時間は存在しない」「ブラックホールは白くなる」に続きロヴェッリのこの本を読んだ。量子論についての本で科学と哲学とが相半ばする内容は2冊と同じなのだが、もともと捉えづらい量子論について書いているせいか、この本が一番飲み込みにくかった気がする。しかしつまらないというわけではなく、数多の刺激に富む良い著作であるとは思う。我々自身もこの物理学が捉えようとする世界の網の目の中に組み込まれている。
0投稿日: 2025.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ引寄せの本で量子力学を知って、もっと詳しく知れるのかなと読んでみたけど、引寄せの解説とはちがった。むずかしくて、なんのこっちゃわからなかった。
1投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ愛の力で結びつき 争いの力で引き離される その無限の繰り返しで 世界の万象は造られている ____エンペドクレス(本書 169Pの参照人物) 万物は流転する。世界は関係で出来ている。以上。 ………ではあまりに短いので、もう少し。 実際、エンペドクレスの理念から、正義と邪悪を、命を、生きることを問うた、私が最も愛する名作・装甲悪鬼村正という作品においても、浦夢という人物の会話が大変に示唆的に描かれていました。浦夢は、エンペドクレスの、万物が造られる関係性の理解を、最も世界を理解した人物であると評価していました。 戦争に勝つための政治的な理由で、形而上学は、哲学は、対立者の善意を認めてしまう危険思想として排除され、あるいは物理的な研究による兵器開発を遅らせてしまう邪魔者として封殺されてきたことが、歴史的な偉人の紹介によって明らかになったのも感慨深かったです。 いつの世も、そうした忖度と、真実を見いだしたい好奇心との狭間で、人間らしく、生きてきたのだなと、その苦労と、ささやかで偉大な幸福をら心から尊敬しています。まさしく、関係という言葉が世界を現すなら、「人《間》」と、我々のことを指して呼ぶのは、なんとも味わい深く、運命的な力を感じてしまいます。 成り立ちを思えば、物理とは、むしろ唯物的な視点よりも、哲学的な視点で愛し、親しまれた時間の方が、ずっと、ずっと永かったのだと、伝わってきました。想えば、私が影響を受けてきた脚本家・小説家・漫画家、表現をする人たちの作品というのは、大変に、私たちが生活する物理的な、あるいは関係に生じる心の機微に精通してありながらも、どこか形而上学的な、哲学的なものを多く含めておりました。元長柾木さんなどは特に、世界の観測について大いに評価された人ですが、主な著作といえば、まさかのアダルトゲームですよ。笑笑 ※猫撫ディストーション 今回の読書に影響され、アレクサンドル・ボグダーノフ氏には強い興味を催されましたので、今後、いろいろと彼にまつわる著作を読んでみます。素晴らしい哲学書を読ませていただき、ありがとうございました。 この本が気になるけれど難しそうと思ったあなた。 理系の前提知識は一切不要です。 それでいて、理系で学びたい、学問の先にあるものを、手に取るように知ることが出来る、面白すぎる一冊です。 是非とも、図書館などを頼って、読んでみてくださいませ。 ここまで私の感想を読んでくださったあなたに感謝を。ありがとうございます。 あなたのこれからの日々が、あかるく、やさしく、おだやかなものになりますように。 量子にときめくこの心から、祈りをこめて。
0投稿日: 2025.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ生命化学系の大学生である私にとって、量子論との出会いは量子化学だった。本書を読んで量子論の始まりには行列力学と波動力学という二大巨頭があったことを知った。またシュレディンガーの波動方程式は量子の不連続性をなくしたいという思いが含まれていたようだ。式を追うだけでは把握しきれない科学者のドラマや気持ちを本書では描き切っている。 そして量子論を解釈するため、著者はナーガールジュナ(龍樹)に行きつく。龍樹によればいかなる視点も別の視点との関係性抜きでは存在しえないという。量子論の結果が古代の仏教哲学と呼応しているようにみえるところが面白い。 本もまた、他の本との繋がりが本質的であるといえるかもしれない。この本を読んでいるときも、かつて読んだ本や読んでいないが知っている本が頭の中を巡った。さらに本それ自体を完璧に読むことはできず、読み手の経験により読み方が異なるという立場から、本もまた絶対的なものでなく読み手との関係性により成り立っているといえる。
0投稿日: 2025.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ属性は対象物のうちにあるのではなく、対象物との関係性にある。 対象物ハイビスカス他の対象物との関係においてのみその属性を有する。 もはや物理学を超えて哲学にてなっている。 何物もそれ自体では存在しない、別の何かとの関係においてのみ存在する。 この本は量子力学の本のはずだが、生物の進化論にまで話が及ぶ。 さらには、チャーマーズの脳のハードプロブレムにまで話は及ぶ。
0投稿日: 2025.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
量子力学が分かりにくい。ニュートン力学など従来の考えではとうてい納得いかない。 多くの人の共通した認識ではなかろうか。本書もこの観点、筆者も通った道から説明をしている。そもそもこの導入が罠である。もっとも私達の多くはこの文脈からしかのみこの山を登れない。この山は様々な状態を内包している。しかしそこにはすぐには気づかない。 第五章にて、ボーアの直感をあらゆる自然現象に拡張した記述として以下を挙げている。 ― 以前は、あらゆる対象物の属性は、たとえその対象物と、ほかの対象物との相互作用を無視したとしても定まると考えられていたが、量子力学は、その相互作用が現象と不可分であることを示している。どんな現象であろうと、明瞭に記述するには、その現象が発現する相互作用に関係するすべての対象物を含める必要がある。 ― ニュートン力学を是としているがそもそもそれが間違いである。工学を学んだ者なら誰でも知っている。つまり、ニュートン力学通りの実験は行えない。必ず誤差が生じる。つまり、ニュートン力学はある可能性を無視した理想でしかない。重力による落下を考える。観測系に含まれるのは、空気抵抗だけではない。そもそも重力は私たちに一定に働いていない。近くに重力物があれば相互作用してしまう。 本書では外側から見る観察者もいないとしている。つまり物理学とは常に一人称である。内側から外側を記述しているに過ぎないという。 これもしんであるあ。たまたま、一人称でも三人称でも同じに結果になる。それがニュートン力学という認識である。つまり、特殊解のはずのそれを一般的であるとし、そこから普遍して考えるからおかしなことになる。 私たちのコミュニケーションはうまくいかないことが多い。それは自分が正しい。もしくは、自分のものの見方を、他者もしていると勘違いしている時に生じる。 絶対はない。全ては相対的である。ただし、同じ系での相互作用を経験している別の存在とは、同様な知見を持っている可能性は高い。よって相互作用する中で、互いの認識を合わせられる可能性は高まる。ある程度の合意のが生じることで、語り合う、という相互作用が生じる。 これはヴィトゲンシュタインの言うところの言語ゲームに他ならない。 私たちは本書を簡易に理解する方法がある。ニュートン力学などに依拠する認知や理解は、世界を楽に認知するための方便である。確かに近似はするが正解では無い。 より小さいものの理解は、観測するための系の影響が無視できない。様々な実験の不可思議さは、その実験が世界の在りようのいったんをたまたま極端な形で提示しているのに過ぎない。 世界は不確定かつ確率的にしか観測できない。エンタングルメントは生じる。その事実があるに過ぎない。 問題は特殊解であるニュートン力学的な理想で記述しようとする無謀さである。 そう考えると、一切皆苦。空。等の仏教世界も量子力学の世界を解釈するのに使われるのも納得である。
0投稿日: 2024.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ『世界は「関係」でできている』――つまり縁起(えんぎ)である。量子力学が仏教に迫る様は、古い経典をありがたがって読むだけの既成仏教に鞭を振るう。しかも悟りから遠ざかった僧侶どもが語る縁起は概念に過ぎず、量子力学の観測やデータには遠く及ばない。 https://sessendo.hatenablog.jp/entry/2024/07/29/140116
0投稿日: 2024.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すごく読みやすくて面白かったー!といいつつ、量子論の本は何冊読んでも強固としてある「自我」や「主観」といったものを相対化しきれていないところもあり、科学者たちが持っている「ほんとうに、信じられない。こんなことを、信じろというのか?これじゃあまるで…現実が…存在しないみたいじゃないか」という恐怖感には直面していない。 序章の「深淵をのぞき込む」 …だが、これぞまさに科学なのだ。科学とは、世界を概念化する新たな方法を探ること。時には、過激なまでに新しいやり方で。それは、自分の考えに絶えず疑問を投げかける力であり、反抗的で批判的な世親による独創的な力ー自分自身の概念の基盤を変えることができ、この世界をまったくのゼロから設計し直せる力ーなのだ。たとえわたしたちが量子論のまありの奇妙さに戸惑ったとしても、この理論は現実を理解する新たな視点を開いてくれる。そこから見える現実は、空間に粒子があるという素朴な唯物論の描像より精妙だ。現実は、対象物ではなく関係からなっているのだ。…(p11) 序文で既にワクワクしてしまった。SF小説を開くようなワクワク。 第1部「奇妙に美しい内側を垣間見る」 第2部「極端な思いつきを集めた奇妙な動物画集」 ・「重ね合わせ」ー有名な思考実験「シュレーディンガーの猫」(p62)。猫は、「起きている猫」と「寝ている猫」の「量子的重ね合わせ」の状態にあること…→「観察者」がいるということはどういうことなのか?人間がいるということではなく、世界の物理系全てが観察者たりえるのか ・観察者自身も観察される可能性があるということが重要である(p78)→人間も自然の一部であるという思考。多かれ少なかれ自然の中の生命には意識があるものもあり、その中でたまたまある「私」という存在のちっぽけさ、それは「無」であると考えること、まだ私には少しジャンプが必要だが、なんとなく分かるような気がする。 「みなさんにとっては現実、でもわたしにとっては現実でない事柄とは?」 …わたしたちが観察しているこの世界は、絶えず相互に作用しあっている。それは、濃密な相互作用の網なのだ。…わたしたちが「現実」と呼んでいるものは、互いに作用し合う存在の広大な網なのである。そこにはわたしたちも含まれていて、それらの存在は、互いに作用し合うことによって立ち現れる。わたしたちは、この網について論じているのだ。(p84-5) ・「事実は相対的である」…ある対象物にとって現実であるような事実が、常にほかの対象物にとっても現実であるとは限らない(p89)→これは「人によって真実は異なるよね」という話ではなく、事実自体が異なるというラディカルな結論なので、ぞわぞわしてしまった。そうしたら一体私が見ているものは、誰とも共有できず、私は孤独な存在なのだろうか?と ・こうして世界は粉々になり、さまざまな視点の戯れとなって、大局的な唯一の視点の存在は、許され無くなる。それはさまざまな視点の世界、さまざまな発現の世界であって、確たる属性を持った実態や、一意的な事実の世界ではない。属性は対象物のうちにあるのではなく、対象物の間にかかる橋なのだ。対象物は、ほかの対象物との関係においてのみその属性を有し、橋とは橋が出合う節(ノード)になっている。この世界はさまざまな視点のゲーム、互いが互いの反射としてしか存在しない鏡の戯れなのだ。この幻のような量子の世界が、わたしたちの世界なのである。(p96-7) 「現実を織りなす関係の網」 ・二つの対象物の全体としての属性は、三つ目の対象物との関係においてのみ存在する。二つの対象物が相関しているという言いまわしは、三つ目の対象物に関する事柄を表しているのだ。相関は、相関する二つの対象物が、いずれも第三の対象物と相互作用するときに発現するのであって、第三の対象物はそれを確認することができる。…二つの対象物の相関はそれらの対象物の属性であって、およそ属性なるものの例に漏れず、さらなる第三の対象物との関係においてのみ存在する。 エンタングルメントは、二人で踊るダンスではなく、三人で踊るダンスなのである。(p105) 第3部「立ち現れる相手なくして、明瞭な記述はない」 ・いかなる視点も別の視点と依存しあうときにのみ存在するのであって、究極の実在は金輪際存在しない、と。これはナーガールジュナの視点自体にいえることで、空でさえも本質を持たない。(p155)…わたしたちは、イメージのイメージでしかない。自分たちを含む現実は薄くもろいベールでしかなく、その向こうには…何もないのである(p158-9) ・何かを理解しようとするときに確かさを求めるのは、人間が犯す最大の過ちの一つだ、とわたしは思う。知の探究を育むのは確かさではなく、根源的な確かさの不在なのだ。…哲学的にも方法論的にも、知の冒険の碇をおろすことができるもっとも基本的な、あるいは最終的な定点は存在しない。 「自然にとっては、すでに解決済みの問いだ」 ロヴェッリお得意の直感に寄り添ってくれる有難い章笑。それでも心が存在しているということはどう説明できるのか? ・…けれどもこの言葉(意味)の守備範囲がここまで広がったのは、わたしたちの種の生物的文化的な歴史を経たからで、そもそもの始まりは、何か物理学に根ざしたものなのだ。その何かに、わたしたちのきわめて複雑な神経系や社会や言語野文化の明瞭な表現やつながりが付け加わってきたわけで、その何かは、妥当な相対情報なのだ。…意味や志向性は、至るところに存在する相関の特別な例でしかない。わたしたちの心的生活における意味の世界と物理世界はつながっている。ともに、関係なのだ。(p174-5) ・精神(心)の本質に関する見解は、一般に、三つしかないとされている。第一に、精神の現実と無生物の現実はまるで違うとする二元論。第二に、物質的な現実は精神のなかにしか存在しないとする観念論。そして最後に、精神的な現象はすべて物質の動きに還元できるとする素朴唯物論。…だがじつは、ほかにも選択肢はある。対象物の属性が別の対象物との相互作用によって生じるとすると、心的な現象と物理的な現象の隔たりはかなり小さくなる。物理的な変数も、心の哲学者たちのいう「クオリア」ー「赤が見える」といった基礎的な心的現象ーも、概ね複雑な自然現象と見なすことができるのだ。(p182) ・何かを感じる「わたし」が、心的過程の統合された総体でないとしたら、いったい何なのか。自分のことを考えるとき、わたしたちは確かに統一されていると感じる。だがその統一感は、自分の身体が統合されているということと、心的過程の意識と呼ばれている部分が一度に一つのことしか行わないというありようによって正当化されているにすぎない。この問題に登場する「わたし」は形而上学的過ちの残滓であって、過程と存在物とを取り違えるというよくある間違いの結果なのだ。…わたしたちは確かに、これが「わたし」だ、という独立した実体を直感している。だがそれをいえば、かつてわたしたちは嵐の後ろにはユピテルがいると直感していたわけで…。…精神の本質に興味を持つ人間にとって内観は最悪の研究手段であり、自分自身の思い込みを探しまわって、その思い込みに溺れることになる。(p184) ・わたしたちは関係を基盤とする視点に立つことで、主観/客観、物質/精神の二元論からも、実在/思考や脳/意識の二項対立を克服することはできないという主張からも、遠ざかる。自分たちの体内で展開する過程、さらにはその過程と外の世界との関係を解明することができたとしたら、その後に理解すべき何が残るのか。わたしたちの意識の現象学とは、まさに、ニューロンが運ぶ信号のなかに含まれる妥当な情報の鏡のゲームで、それらの過程に割り振られた名前以外の何ものでもないのだが…。(p187) 「でも、それはほんとうに可能なのか」ーシェイクスピアの『テンペスト』から始まる… ・…わたしたちがあたりを見渡すとき、じつは「観察」はしていない。では何をしているかというと、(誤解や偏見を含めて)自分たちが知っていることにもとづくこの世界の像を夢見ているのだ。そして無意識に、この世界とその像の間に不一致がないかどうかを精査し、必要ならその像を修正する。言い換えればわたしたちは、外界を再構成した像を見ているわけではなく、自分が予期し、把握した情報にもとづいて修正を施した像を見ているのだ。(p191-2) ・十九世紀フランスの哲学者イポリット・テーヌの言葉を借りれば、「知覚された外部とは、外部の事物と調和することが裏付けされた内側の夢なのだ。また「幻覚」を誤った知覚と呼ぶのではなく、知覚された外部を「確認された幻覚」と呼ぶべき」なのだ(p192) 原題及び英語タイトルが『ヘルゴラント島』というのがオシャレ…だけど日本語版はこれで良いと思います笑。 また、原注にない参考図書として挙げられているのは、朝永振一郎『量子力学I,II』、吉田伸夫『明快量子重力理論入門』、木田元『マッハとニーチェ』、中村元『龍樹』など…
2投稿日: 2024.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログすべてはタイトルに集約されるように、物事は関係において成立し、私が生きているか死んでいるかそれ自体はわからない。相手との関係においてのみ成立するということ。 また、今この瞬間の私の行動がこの世界、今後の時代に少なからず影響を与えている。
0投稿日: 2024.04.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ物性研の所内者、柏地区共通事務センター職員の方のみ借りることができます。 東大OPACには登録されていません。 貸出:物性研図書室にある借用証へ記入してください 返却:物性研図書室へ返却してください
0投稿日: 2024.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる物が他との関係において観測される事象ということだろうか。モノからコトへみたいな。ナーガールジュナの空の思想が少しだけイメージできた気がした。 ただ、文章はちょっと文学的すぎるかもしれない。物理的な内容にあまり突っ込まず雰囲気だけ書いてある感じ。やや冗長で、この内容なら半分以下のページ数で説明できるのではと思った。
0投稿日: 2023.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ自然はわたしたちの形而上学的な偏見よりもはるかに豊かなのだ。自然のほうが、わたしたちよりずっと豊かな想像力をもっている
1投稿日: 2023.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログレビューはブログにて https://ameblo.jp/w92-3/entry-12801503549.html
1投稿日: 2023.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログシュレディンガー、ボーア、アインシュタイン、ドブロイ、パウリ…等、20世紀前半の科学者が量子力学をめぐって大発見をした。流れるように進む学問。 その熱気が伝わる内容、および 量子力学の基礎について関係性で説明する内容。 前者はよく書けている、後者は難解。 読了70分
0投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ『時間は存在しない』の、ループ量子重力理論の研究者カルロ・ロヴェッリの本。 量子力学の発端の、生き生きとした歴史を示す導入は読みやすいが、第2章後半から、この世界構造は何なのか、という量子論にとって避けられない根源的な問いへの思索となり、難解になっていく。ここからは読者を選ぶように思われる。 量子力学は情報理論だ、関係だ、「空」だと言われても、それが物理事象とうまく接続できない読者としては、わかった気になるようでならないようで、著者の思索に振り回されて困惑する。世界の本質の思索において、物理は哲学と無縁ではいられない、と頭でわかってはいても。それでも、思想の網を広く持つことが重要だ、という物理学者の主張に触れる点では興味深い。第三部の生命や脳についての議論はやや踏み込みすぎる気もするが、シュレディンガーなどを踏まえると、それも物理学の思想の到達点ではあるのかもしれない。 この本で知った知見として、量子論の記述する現実は、相対性理論の示すように相対的なものだ、「間主観性」だ、ということ。これをカギに、今後の量子論の本に触れていきたい。
0投稿日: 2023.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中までだが、量子論の考え方と、すべては関係によって成り立つ考え方は、唯識やスピノザなどともつながると思ったが、思考したり語るにはまだまだ聞き齧っただけでは歯が立たない。
0投稿日: 2022.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学的な面もあり興味深い本なのですが、わたしには少しレベルが高かったかなと… 個人的には、『時間は存在しない』の方が楽しめました。
0投稿日: 2022.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ量子力学の知見から、世界のすべてが「関係」としてだけ現れる/存在するという洞察、さらにそこから世界の一部である我々の意識/実存、または意識の中での意味の在りようが描き出される。 非常にスリリングに感じた。内容が自分の考えにとてもあっている、納得できるということからかもしれない。 書籍にもあるが、哲学で多く論じられている実在論とはややレイヤが違い一概に比較できないとも思うが、あらゆる実在が相対的(関係)であるという著者の考えは、実在の理解として、とても納得できる。 さらに著者は、相対的といったときの我々の存在については、意識は世界の一部であり、ただただ自然であるという。分かっていると言いたいが、「自分の存在」の特別さを探してしまう気持ちを、まだ捨てきれないでいると感じる。 また、著者は言う、量子力学から考えた自分の考えは、仏教の「空(縁)」につながると。 ここで、我執を断つことは仏教のめざすものの一つであったなと思い、自分の気持ちに納得する。 改めて考えると、おそらく自分は、我執を含む執着から離れたいと思いから本を選び読んでいるのだとおもう、だから、本書をスリリングに感じたのかもしれない。 ・量子力学から考えるに、すべての物の属性は関係を持った時にだけ立ち現れる(2者間の関係のみ。3者の場合は、2者間の関係を位置?変換することで共有できる)。 ・意味もダーウィズム的な進化論から物理的な相互関係から基礎づけられる(超越的なものはない)。 ・意識は自然の一部であり複雑な相互関係といえる(超越的なものはない)
0投稿日: 2022.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学で「意識」の説明を試みたパートあり ■四章 現実を織りなす関係の網 量子物理学を、系が互いについて持っている情報の理論と捉えることが可能 対象物の属性を二つの対象物の相関の確立、あるいはむしろ片方の対象物がもう片方について有する情報、と見なすことができる。 111 ○ 165 わたしたちが心的生活を送るには、ニューロン、感覚器官、肉体、脳で起きる複雑な情報処理が必要だ。 基礎となっている各系に「原意識」があると考えなくても、凍りついた「単純な物質」を迂回することはできる。互いの関係によって定まる変数とその相関という観点に立てば、この世界をはるかに上手に記述できる、ということを認めさえすればよい。 心的な現象も、物理的な現象も、物理的な世界の部分同士が相互作用することで生み出されたもの。
0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログHelgoland https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000818812021.html
0投稿日: 2022.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ相互作用のネットワークの節を素粒子と呼んでいるに過ぎない、そう考えれば素粒子の不可思議な振る舞いが理解できるのか? あまりに哲学的に過ぎて理解できない。 物質的世界と精神的世界が同じ?分からない。
0投稿日: 2022.09.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の頃、自分以外の全ては統一された意識下の登場人物で、本当はこの世界の真の住人ではなく、実験用のモルモットである自分を取り巻く役者か何かだと感じた事があった。その頃、父の古漫画で手塚治虫のSFミックスに『赤の他人』という作品を読み、主人公が同様の妄想に取り憑かれ、不意に皿を割る事で役者を欺こうとするシーンに共感した事をよく覚えている。少し時が経ち、トゥルーマンショーという映画を見た。どれも彼我を極端に隔絶した妄想症、あるいはそれを利用した表現である。 これを素朴実在論というのか、独我論というのか、哲学の領域においてもハッキリした呼び名は分からない。最近では映画にちなんでトゥルーマンショー妄想などという、精神障害に分類されるらしい。哲学と精神症は紙一重という事だろう。非日常に取り憑かれる不都合は、いつだって病人扱いで排除だ。 本著は、量子論から関係性を問うもので、シュレーディンガーの猫などを読んでいると、私はどうしても上述の妄想論を思い出してしまうのだ。オブザーバルであって初めて定義される世界。しかし、量子論については、専門性が高く、やはりよく分からなかったというのが正直な感想。分からないから、既知の範囲で解釈しようとこじ付けてしまうのだろう。まさに、関係性による思考処理という事かも知れない。そしてこれら諸々の詭弁は、哲学でも精神症でも、まして量子論とも異なる、牽強付会、ご都合主義から神の境地に帰着する。気楽なものだ。 他人は我が世界の為に存在するという都合よい関係性が、解釈に留まらず、その支配欲を叶える仮想世界への入り口に誘う。やがて人間は、現実世界の関係性を失い、仮想世界で一代限りの神になる。この時、量子論はどうプログラムされるのか。そう考えると、既に現世はバーチャルなのかも知れない。
1投稿日: 2022.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ【まとめ】 1 行列力学 ハイゼンベルクの理論は、電子の運動を記述するのは諦めて、自分たちが観察し測定できるものだけ、つまり、電子が放つ光だけを記述する。すべての基礎に、オブザーバブル(観測可能量)を据える。 原子内部の電子に関してわたしたちに観察できるのは、電子が放つ光――ポーアの仮説によれば電子がある軌道から別の軌道へ飛躍するときに出す光である。一つの飛躍には、電子が飛び出す軌道と飛び込む軌道の二つの軌道が関係している。したがって、一つ一つの観察結果を、飛び出す軌道を行とし、飛び込む軌道を列とする表の各項に対応させることができる。 位置、速度、エネルギーといった電子の運動を記述するすべての量を、数ではなく数の表で表す、というのがハイゼンベルクの着想だった。電子の位置は、xというただ一つの値ではなく、Xというあり得るすべての位置からなる表で表されており、表の項が示すそれぞれの位置が、あり得る飛躍に対応している。使う方程式はこれまでと同じで、(位置、速度、軌道のエネルギー振動数などの)通常の量をこのような表で置き換えればよい、というのがこの新しい理論の考え方なのだ。 ハイゼンベルクの発見に続き、シュレーディンガーが電子は「粒子ではなく波である」という理論を発表する。ψ(波動関数)の発見である。 しかし、ハイゼンベルクはその理論に齟齬があることに気づく。波は、遅かれ早かれ広がって空間に拡散する。しかし電子は広がらない。どこかに到達するときは、必ず丸ごと一点に到達する。原子から電子が一つ放たれたとしよう。シュレーディンガーの方程式によれば、ψという波は空間の至るところに一様に拡散するはずだ。しかし、現実は一点に到着している。 ここに新たな理論を付け加えたのがボルンだ。 ボルンの理解によると、空間の一点におけるシュレーディンガーの波動関数ψの値は、その点で電子が観測される確率と関係がある。ある原子が粒子検知器に取り囲まれていて、その原子が電子を一つ放出したとすると、検知器がある場所における値は、ほかならぬその検知器が電子を探知する確率を規定する。つまりシュレーディンガーの波動関数は、実体ある何かを表しているのではなく、実際に何かが起きる確率を与える計算手段、ちょうど明日の天気を告げる天気予報のようなものなのだ。 じきに明らかになったのだが、ゲッチンゲンの行列力学についても、これと同じことがいえる。行列の数学はあくまで確率を予測するのであって、正確な数値を与えるわけではない。ハイゼンベルクの形にしろ、シュレーディンガーの形にしろ、量子論は確実に起きることではなく、確率を予測するのである。 観測、確率に続く量子論の第三の着想は、「粒状性」である。わたしたちが暮らすこの物理的な空間は、きわめて小さな規模では粒状であって、プランク定数が、基本的な「空間の量子」の寸法を決めている。 XP-PX = ih Xという文字は粒子の位置を表し、Pという文字はその速度と質量をかけたもの(専門用語では運動量)を表している。iという文字は-1の平方根を表す数学の記号で、hはプランク定数を2πで割った値である。 2 量子の世界の奇妙な振る舞い ・量子重ね合わせ 光子からなる光線をプリズムによって2つに分割(左経路と右経路)し、それを一つにし、また分かれて2つの検知器(上検知器と下検知器)に到達するような実験器具をつくる。2つある経路のうちのいずれか(左か右)を手で遮ると、光子の半数は下の検知器に到達し、残りの半数は上の検知器に達する。ところが二本の経路をともに開放しておくと、すべての光子が下の検知器に到達し、上の検知器には一つも引っかからない。 これが「量子重ね合わせ」で、一つの光子が「左も右も両方」通っている。いわば、左を通るという状況(配位)と右を通るという状況(配位)、これら二つの配位の量子的な重ね合わせなのだ。そしてその結果、光子はもはや上の検知器に向かわなくなる。二つある経路のいずれか片方だけを通っていたときは、上にも向かっていたのにだ。 しかもそれだけでなく、光子が二本の経路のどちらかを辿るか「観察」するだけで、干渉が消え、上と下両方の検知器に検知されるのだ。 3 実体は存在せず、そこには「関係」があるのみ 観測者は、測定機器と同じように自然の一部である。そのとき量子論は、自然の一部が別の一部に対してどのように立ち現れるかを記述する。光子、石、木、人間といったさまざまな物体は、絶えず相互に作用しあい、一つ一つの対象物は、その相互作用のありようそのものである。 したがって、対象物の属性と、それらの属性が発現する際の相互作用、さらにはそれらの属性が発現する相手とを分離することはできない。さらに、対象物が相互作用していないときにもその属性が備わっていると考えることは余計であって、誤った印象を与えかねない。なぜなら、存在しないものについて語ることになるからだ。 相互作用なくして、属性はない。すべてのものは、なにか別のものへの作用の仕方だけで成り立っている。 では、観測者とは違う、対象者自身についてはどうだろうか? みなさん自身がシュレディンガーの猫であったとする。みなさんにとっては、毒ガスは発せられたか発せられなかったかであり、自分自身は生きているか死んでいるかのどちらかだ。わたしにとっては、みなさんは生きても死んでもいない。つまり「量子的重ね合わせが存在する」。 関係論的な視点から見ると、この二つはともに正しいといえる。なぜならそれぞれの状態は、みなさんとわたしという異なる観察者との相互作用に関係しているからだ。 ここから導かれるのは、ある対象物にとって現実であるような事実が、常にほかの対象物にとっても現実では限らないということだ。 そこにあるのは、明確な属性を持つ互いに独立した実体ではなく、ほかとの関係においてのみ、さらには相互作用したときに限って属性や特徴を持つ存在だ。 量子論は、物理的な世界を確固たる属性を持つ対象物の集まりと捉える視点から、関係の網と捉える視点へと私たちを誘う。対象物は、その関係の網の結び目なのである。 4 量子もつれ 量子的な重ね合わせの状態にある一対のもつれた光子をウィーンと北京に一つずつ送ると、奇妙なことが起きる。たとえば二つの光子は、両方とも赤であるような状態と、両方とも青であるような状態の重ね合わせになっているかもしれない。さらにそれぞれの光子は、観察された瞬間に、赤か青かが判明する。ところが片方が青だということがわかると、遠くにあるもう片方もまた青なのだ。なぜ、両方とも同じ色になるのか。そこが問題だ。 その答えを知るには、対象物の属性は別の対象物との関係においてのみ存在する、ということを思い出せばよい。北京で光子の色を測定すると、北京との関係での色が決まる。しかしそれは、ウィーンとの関係での色ではない。そしてまた、その逆も正しい。二ヶ所で測定が行われるその瞬間に二つの光子の色を目にする物理的な対象物は存在しないのだから、その二つの結果が同じかどうかを問うことには意味がない。二つの光子の色が同じであるという現象が発現する(つまり二つの光子と同時に相互作用する)相手が存在しない以上、無意味なのだ。 二つの対象物が相関しているという言いまわしは、三つ目の対象物に関する事柄を表しているのだ。相関は、相関する二つの対象物が、いずれも第三の対象物と相互作用するときに発現するのであって、第三の対象物はそれを確認することができる。 何ものもそれ自体では存在しないとすると、あらゆるものは別の何かに依存する形で、別の何かとの関係においてのみ存在することになる。ナーガールジュナは、独立した存在があり得ないということを、「空」(シューニャター)という専門用語で表している。事物は、自立的な存在でないという意味で「空」なのだ。事物はほかのもののおかげで、ほかのものの働きとして、ほかのものとの関係で、ほかのものの視点から、存在する。
20投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログカルロ・ロヴェッリ「世界は「関係」でできている」読了。ドイツのヘルゴラント島で若きハイゼルベルグが到達した不確定性原理。またボグダーノフの組織化。古典物理の世界観が、好奇心と反抗と変化から生まれた思索による量子力学等の登場で一気に変わってしまった感覚を読んでいて感じる事ができた。
2投稿日: 2022.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系量子論渉猟 量子論の読み物を相変わらず手に取ってしまうのである。 もちろん多分一生わからないままでおわるのだが、何冊も読んでいると、さながら巨大な塔の内部をゆっくり螺旋階段でのぼっていくように、気づけばだいぶ高いところにきたなーなんて気分にはなれる、それが量子論文系読書の醍醐味であろう。 さて、本書の議論の出発点は、うちの娘が苦労している元素周期表、さらに言えば電子が核の周りを回るその数と動きである。電子が増えたり減ったりして性質が変わる、その働きはどのように説明できるのか。 そうこうしているうちに、電子の動きは観察しているかどうかで変わってくる、という、お前ら自然界レベルで人の目気にしてどうする的な世界に入っていく。 これがまあまたいつものように、ある物質は観察されるまで定まらない、という不確定性原理というやつで、シュレージンガーの猫の例えの学び直しに時間を費やし、そして徒労感を得る。 そこにそれがあるのは観察したからだ、という理屈は、それでは観察される前はどうなっていたのか、なぜ観察している私がその物質に影響を与えるなんてことがあり得るのか、という当たり前の疑問につながっていく。 観察の数だけ少しずつ世界が層のように増えていく、つまりこの世は無限のパラレルワールドだから。たまたま観察したときの確率、いわばサイコロによって世の中は決まってくるから。 さまざまな仮説が大まじめに物理学者によって論じられ、しかし相対性理論との整合性のある理屈を誰も見つけられず、論争は未だ決着していない。 そんなことはサイエンティストではなく哲学者の領分では、という疑問を抱えているうちに実は物理学は哲学そのものだ、なぜなら物とは何か、を考えるのがこの学問の役割なのだから、という地平に辿り着く。 ならばと古今東西の哲学にヒントを探せば、原始仏教、ナーガールジュナの「万物に実体はなくすべては関係性によって決まる」が、思考の補助線としてはもっとも当てはまりがいいということに著者は気がつく。 うむ。 しかしこれだけ理論的支柱が曖昧模糊としているのに量子コンピュータはまあそれなりに実用化の道を突き進んでいるというのが私にはいまだにようわからんのであった。
15投稿日: 2022.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「時間は存在しない」という著作で、私を混乱に陥れた理論物理学者カルロ・ロヴェッリの初学者向け量子物理学の入門書。 著者が序文に記している「私はこの本を、なによりもまず量子物理学にはなじまが薄いが、それでも量子力学がどんなもので何を意味しているかをできる限り理解したいと考えている人々に向けてまとめた。」という意図は成功していると思う。 言葉で書いてある部分を拾いながら、それを理解しようと努力することはできた。 ただ、数式が出てくると、私はその意味を理解しようという努力をスキップした。 見えても理解できないものはあるのだ。 ただ、なんとなく、マルチバースの考え方は、空想だけでなく、現実に理論的に考えても良いものだという気がしてきた。 量子力学での新しい発見には、ぼんやりした空想から生まれてきているものもあるようだ。 本書の狙いであるその深淵をのぞき込む淵には、私も立つことができたような気がする。
0投稿日: 2022.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
科学的素養をそこまで必要としない量子論の本という触れ込みで読んでみた。確かにエピソード重点で読みやすい部分もあったが、数式や未知数が出てきた瞬間にわかったふりしかできなくなった。観測による確定とか関係性しか存在しないとか実にむつかしい哲学の話で、この辺は訳者あとがきの言う通り。 直感に反するというだけで話が受け入れがたくなるのは、注記で批判されていた本そのままの態度で反省すべきかと思うが、それも引用されていた英作家ダグラス・アダムズの「重力井戸の底で火の玉の周りをまわって生きている人間の視野がどれだけ歪んでいるかは明確」という言を受けてみればなるほど納得。また人は目でものを見ず、脳の予期と異なるものがあるときだけ情報がフィードバックされるという話も面白かった。 つまるところ本筋はふわっとした理解しかできなかったので枝葉末節ばっかり見ていた気がする。『時間は存在しない』も読んでみるべきかどうか。
0投稿日: 2022.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本は、「時間は存在しない」の著者でもあるカルロさんの量子論について考察された本です。 科学の本というよりは、哲学的な本で、私には、めちゃくちゃ難しく、苦労しました(笑) 量子論の摩訶不思議な世界が描かれており、頭が、混乱しますが、とてもいい刺激になりました。 ぜひぜひ読んでみてください。
12投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界は対象によってできているのではなく,関係によって対象が存在しているというコペルニクス的転換によって量子論を解釈する関係論的解釈に基づいている。本書は物理学の範疇を華麗に抜け出し、哲学、心理学、生物学の範囲を駆け抜けてゆく。関係論的解釈によって二元論など先入観に囚われた世界を新たな記述によって再解釈し、観測することが可能になる。
2投稿日: 2022.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログまたもや素晴らしい本に出会った。量子論という理系的な内容を、学問的な専門知識と卓越した詩的な文章能力を両立させて面白くかつ美しく教えてくれる本だ。完全に自分の好みのツボ。生物学の福岡伸一さんや数学のサイモンシンさんのファンならば絶対に読んだほうが良い。 数か月前に、同じ著者の「時間は存在しない」を手に取ったが、それは全くとしていいほど自分に響かなかったが、おそらくそれは自分の不勉強のためだろう。再度チャレンジしてみたいと思う。
4投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログつい最近「実在とは何か(アダム・ベッカー著)」という、主に哲学の立場からコペンハーゲン解釈の論理実証主義的な実在否定論を批判する本を読んだが、この本はそれとは全く正反対の立場に立つ。つまり自然主義の見地から「世界はそこに内在する自然の一部と他の一部の相互作用の網の目によって成り立っている」とし、事実の総体としての「実在」を否定するのである。どちらの見方にも説得力と疑問点がありどちらが正しいと断ずることはもちろんできないが、短期間に全く正反対の立場に接することは知識の整理になるし、独断への落ち込みを避ける最も有効な手段だと思う。 本書の導入部分はシュレーディンガーの波動関数〈ψ(プサイ)〉に対する物理学界の解釈論だ。ψを「確率」として扱うマックス・ボルンらの主流派に抗してこれを事実の総体としての世界にどうにかして位置付けようとする非主流派の理論(ボームの〈パイロット波理論〉、エヴェレットの〈多世界的解釈〉等)を、著者はバッサリ切り捨てる。そして、世界を〈関係=相互作用=属性〉の観点から再構成し、①事物の属性が生じるのは世界の一部と他の一部との間に相互作用が存在するからであり、また②すべての事実は相対的である、とのコペルニクス的転回を提示する。 この論に従えば、「測定状況依存性」の問題はある世界の一部と他の一部の相互作用の問題に回収することができ、何ら不思議な現象ではなくなる。そもそも相関関係にない観測者に対しては、すべての現象はエンタングルメントとしてしか提示されない。測定という形で相互関係に立った瞬間、その現象から具体的な属性が提示されるのだ。ただしその属性は観測者との間でしか妥当せず、異なる系に立つ観測者がその属性に同意するには、観測者同士が相関して共通認識を持つ必要がある(〈間主観性〉)。 そして、量子物理学の2つの公準から「ある対象の情報を最大限集めても情報の総体は確定不能」と言う命題が導出されることから、「究極の〈本質〉は存在しない」という、伝統的実在論の否定に至るのだ。ここで興味深いのは、論理実証主義の旗頭であったエルンスト・マッハに影響された、ロシア革命期の思想家アレクサンドル・ボグターノフなる人物が舞台廻しとして登場することだ。彼は、マルクスやエンゲルスと通底する相対的経験主義に立ち、「現在の物質概念も知識の歩みの途中段階であり、経験と概念の組織化により継続的に知識を得ることが必要である」と主張してレーニンの史的唯物論批判を繰り広げたのだが、これが上記の量子物理学の公準から導かれる確定不能性と相似形をなすのである。「歴史も情報も、先行して獲得された経験の総体からは決してその未来が確定できない。だからこそ世界の表象から既知の事実と異なる情報を検出し、知識の更新を図る必要がある。これが歴史と量子論に共通する本質だ」というわけだ。量子論と共産主義世界における論争とのシンクロに驚かされると同時に、物理学者でありながらロシア思想史にも造詣の深い著者の博識ぶりに深い感銘を受けた。 無論、どうしても得心の行かない部分はある。例えば、本書で触れられる〈ハードプロブレム(デヴィッド・チャーマーズ)〉がこれで解決できた、と著者は言うが、本当にそうだろうか。「すべての物理現象は三人称的でなく一人称的であるから、一人称的な心的現象も物理現象の範疇に含めてよい」と言うのが著者の主張だが、それはやはり安易なショートカット(主観的意識経験の物理科学的記述を経ることなくいきなり主観を物理現象としてカテゴライズしてしまう)と言わざるを得ないように思う。本書で槍玉に挙げられているトマス・ネーゲルは、まさにこの主観的経験の物理的記述の困難性を指摘したのであって、これに正面から挑まないままいきなり「主観的経験はすぐれて物理的現象」とするのは意図的な論点ずらしのように思えてしまうのだ。 そしてもう一つは、実在性の否定にどうしてもポストモダン的なニヒリズムの匂いがしてしまうこと。「哲学が科学に従うべきであって、その逆ではない」とは自然主義の文脈でよく見られる言説だが、少なくともこれまでは実在の探求こそが科学パラダイム獲得の歴史の下支えだったのではないのか。それともやはり僕のこのような見方自体が、すでに古典物理学のドグマに絡め取られたものなのだろうか。 とはいえ、著者の考察は簡潔で論旨が分かりやすく、説得力に富むのは間違いない。有名な「シュレーディンガーの猫」や「エンタングルメント」を用いた間主観性の説明も懇切丁寧で、少なくとも上述した「実在とは何か」との比較では、著者の主張の方に同意する向きが多いのではないかと思う。また、本書第3部以降の自然主義・科学哲学的考察は日本の研究者も同様の著書を多く出しており(e.g. 戸山田和久「哲学入門」「恐怖の哲学」etc.)、僕同様馴染みが多く共感できる読者も多そうだ。
3投稿日: 2022.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルからポピュラーサイエンス的な量子力学解説と言った趣向の本かと思ったが途中から、これはちょっと違うなと思い始め、最後にかけては哲学というか文学というか様々な分野を統合して世界への認識を改めていくような割と革命的な世界の見方を提示してくれる。世界の見方が変わる本。 作者カルロ・ロヴェッリのヨーロッパの哲人的なさまざまな分野での深い教養とそれを魅力的に語る言葉の翻訳を通しても伝わる素晴らしい文章が非常に魅力的。 シェイクスピアの引用から始まる最終章が白眉。
2投稿日: 2022.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
新聞の書評を読んで面白そうだったので読んでみたけど、量子については1mmも理解できなかった。現代物理学は哲学という認識は得た。 冨永星さんが翻訳を担当された「素数の音楽」を読んだ時も思ったけど、この解明に関わってきた人物たちのエピソードが破天荒で面白すぎる。ボグダーノフが初めて口にした言葉が生後18か月の「パパはばかだ!」に笑ってしまった。
1投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ量子論を、その歴史と思想の観点から書いた本。 ハイゼンベルクやシュレーディンガーだけではなく、レーニンやナーガールジュナまで登場する。 原書は文学的にも美しい文章らしいけれど、日本語訳はそうでもない。
1投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「量子重力理論」の研究を専門とする著者が、量子物理学が生まれた背景や、古典物理学の常識を覆すその特徴的な概念、さらには量子論を事物の「関係性」から捉えるアプローチを解説した一冊。 著者は、量子論の基本概念である「量子飛躍」が、単純な方程式ではなく、観測された結果のみを用いて、確率論を前提とした「行列」によって記述された経緯や、量子論に特有な、対象物は「ここ」にも「あそこ」にも存在する「量子重ね合わせ」の状態にあり、我々が目にするのは「量子干渉」がもたらす一つの状態だけであるという考え方、さらにそれを発展させると、「観測」とは我々が対象物を世界の外側から見ているのではなく、我々自身と対象物との相互作用であるという「関係論」に行き着くと主張する。 「この世界が属性を持つ実体で構成されているという見方を飛び越えて、あらゆるものを関係という観点から考える」べきだという著者の「過激な結論」は、本書後半でナーガールジュナという古代インド哲学者の「空(くう)」の概念との対比をふまえ、これまで絶対と思われていたものが相対であったという発見が、心的世界と物理的世界の境界を消し、双方とも自然現象として捉えるという地点にまで昇華される。難解な内容ではあるが、物理学のイメージが(良い意味で)変わることは間違いない。
3投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作の「時間は存在しない」が相当面白かったので期待して読んだのだが、前作ほどのインパクトはなかった。 前作は時間とは何かというシンプルそうで難しい問題に焦点があたっていたので読みやすかったが、今回は量子力学の歴史から始まり、何について議論を展開したいのか少し読者を置いていってしまった印象。 ただし、知的好奇心をくすぐるには十分な内容で、読んでいて新しい世界が開けるような感覚もあった。
1投稿日: 2022.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者はループ量子重力理論の人で、内容は哲学というか宗教というか、そういうものだった。 古典力学だと多体問題にならなければ、わりと明瞭な世界で、精神性など入り込む余地はあまりないように思う。 一方、量子力学になると途端に曖昧でぼやけた確率の世界になる。そういう点で、哲学とか宗教とかと重なる部分が出てくるのだろう。 量子力学の振る舞いと人の営みとのアナロジーがいろいろと語られている。それはそれで面白く、なるほどなあと思うところが多くある。が、だからといってそれ以上のものはない。量子力学を持ち出さなくても語れるところではある。 著者はとても賢い人で、哲学や宗教などについても造形が深いと思う。本書で触れられていることを(物理方面は問題ないが)私はあまり知らないし理解も浅いと思う。それぞれ本を読んでみたいなあ、読まなくては、と感じた。
1投稿日: 2022.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ【はじめに】 カルロ・ロヴェッリは以前『すごい物理学講義』と『時間は存在しない』を読んでいた。『すごい物理学講義』は著者が重力と量子力学を統合する究極の理論として追究するループ量子重力理論の一般向け解説であり、『時間は存在しない』は時間の矢がなぜ流れるのかをエントロピーの観点から考察したものである。いずれも、非常に抽象度が高く難しい理論を、一般向けにとても分かりやすく興味を惹くように書かれていた。 本書は、世界は空間と粒子の前にそれらも含めてまずは「関係」から生まれくる、とする考えを量子力学の理論から説明し、その上で生物の志向性とわれわれが認識する「意味」も同じく関係から生まれてくるという著者の考え方を示したものである。 なお原題は、ハイゼンベルグがすべての始まりとなる量子行列力学の構想を得た場所であるヘルゴランド島から取られている。自分は一般論として原題を尊重するべきだという考えを持っているが、邦題で付けられた『世界は関係でできている』の方が、さすがに内容を的確に示しているし、分かりやすく、また売りやすいだろう。 【概要】 本書の構成は、以下の三部構成となる。第一部はイントロダクションで、第二部と第三部がメインとなる。 第一部の量子力学の誕生期のエピソードとして、ハイゼンベルグによる量子力学の構想とそれに続くシュレディンガーの波動方程式の話に触れられる。時代を画することとなったハイゼンベルグの論文の最初には「もっぱらオブザーバブルな量の間の関係のみに依拠する量子力学の理論に基礎を与えることが、この論文の目的である」と書かれている。この「オブザーバブルな量の間の関係」という概念がこの本の鍵となる。 第二部は、量子力学の解釈に関する章となる。いわゆるコペンハーゲン解釈の先にある「量子論は、自然の一部が別の一部に対してどのように立ち現れるかを記述する」 ― これが量子論の「関係論的(Relational)解釈」と呼ばれるものの紹介である。量子もつれや光の量子実験など量子力学から導かれるが人間の直観には反する事象がいくつか紹介される。本書の対象となる読者が科学者ではなく一般向けであることから数学的な厳密な理論はほとんどない。しかしいくつかの量子力学の結論の結果、著者としては「この世界が属性を持つ実体で構成されているという見方を飛び越えて、あらゆるものを関係という観点から考えるしかない」と結論つけるのである。基本的に相互作用から切り離された孤立した実体というものや状態というものはない。対象物の属性は、他の対象物に対してのみそのような属性として存在する。量子力学におけるこの考え方を「状況依存性(Contextuality)」と呼ぶ。 ここから導出される著者の結論の中に、多世界宇宙論の否定がある。なぜなら多世界の前提として、世界を独立した事実とみなし、外部の独立した観察者を前提としているからだ。量子力学の観点からは独立した事実というものはなく、相互作用したときに発生する関係のみが世界なのだ。「事物の総体には「外側」がない。外側からの視点は、存在しない視点なのだ」と説くのだ。 続く第三部は、第二部を受けた形で、われわれに生物にとって「意味」や「志向性」がどのようにして生まれるのかを語る。新しい第三部の冒頭に、唐突にマッハの思想を受け、組織化という概念を推し進めた旧ソ連のボルダーノフや、空の概念を論じたナーガールジュナ(龍樹)の話が置かれる。その後、心的現象もまた量子の世界のように何か実体や土台があるのではなく、関係性があって初めて実体や属性が現れるというように論を進める。 著者は、最終的に相関情報と進化論を世界に共通する原則として措定する。そして、次のように宣言する。 「意味や志向性は、至るところに存在する相関の特別な例でしかない。わたしたちの心的生活における意味の世界と物理世界はつながっている。ともに、関係なのだ」 【所感】 第二部の終りに著者は次のように書いている。 「思うに、わたしたちは科学に哲学を順応させるべきなのであって、その逆ではない」 その通りであると思う。「われ思うゆえにわれあり」と宣言したデカルトが起源とも呼ばれる現象学や実存主義などの西洋哲学も量子力学や宇宙論に順応されるべきであるし、精神分析や心理学も含めた哲学全体も脳神経科学の観点に順応されるべきである。ここで著者が試みている「世界」の把握に関してもその通りである。その意味でマルクス・ガブリエルのような哲学に関しても科学に順応させるべきであるからこそ、彼の哲学観には個人的に違和感を持っている。この観点で著者の試みはひとつの試みとして重要だとは思う。まず量子力学によって開かれた状況依存性の議論はとても納得感がある。エントロピーとしての情報と進化論によるエントロピー増加に対抗する動力についての考察も、その重要な二つの理論の交差点に生物があるという構造論もその通りだと思う。 一方で、量子力学の関係性が存在に先立つという概念を、「意味」や「志向性」のレイヤにも適用する論に関しては個人的には正しさを欠いている部分があるのではと感じた。量子の世界と同様に、相互作用によって心的現象が生じ、相互作用がない孤立した心的現象というものはないというのはアナロジー・比喩としては有効であるように思われる。しかし、そのロジックは、あくまでアナロジーとして成立しているだけであって、量子の世界の構造がそうであるから心的世界の構造が同様であることを証明するものではない。この点は重要であるように思う。 著者は「心の働き方を量子力学を用いて説明する試みは、まったく説得力に欠けている」と書いている。これもまたその通りである。心の作用、特に自由意志の存在、を量子力学の不確定性理論やコペンハーゲン解釈をもとにして説明しようとする理論は明白なレイヤ侵害によって失敗している。しかしながら、同じく量子力学の状況依存性の議論から心的現象を説明することもまた説得力に欠けるように思われるのである。 「この世界に関するわたしの知識は、まさに意味ある情報を作り出す相互作用の結果の一例にほかならない。それは、外側の世界とわたしの記憶の相関なのだ」と書くときに、その正しさの根拠として量子の世界を持ち出すこともまた論理的な誠実さに欠けるように思う。 「過程や出来事、ひいては関係論的な属性や関係が織りなす世界の観点に立つと、物理的現象と心的現象の隔たりも、それほど深刻には見えなくなる。なぜならどちらも、相互作用が織りなす複雑な構造から生じる自然現象と見なせるようになるからだ」 どちらも相互作用が織りなす自然現象であるかもしれない。繰り返しだが、ただ心的現象がそうであることを、物理的現象がそうであることが保証しないと認識するべきなのだ。また、そうであるがゆえに、量子の世界が関係から出来上がっていることによって、何か心的現象が説明されることはないのではないのか。 もちろん、量子力学的世界観は、世界をどのように把握するのかに関する哲学的思考にとって欠くことができないものであると思う。ただし、心的現象に関してはそこから演繹することは何か重要なステップを飛ばしてしまっているように感じる。 ---- 【カルロ・ロヴェッリの本】 『すごい物理学講義』 (カルロ・ロヴェッリ)のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4309467059 『時間は存在しない』 (カルロ・ロヴェッリ)のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4140817909 【量子力学黎明期の本】 『そして世界に不確定性がもたらされた―ハイゼンベルクの物理学革命』のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4152088648 『量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突』のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4105064312 【量子もつれの本】 『量子力学の反常識と素粒子の自由意志』のレビュー https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4000295799 『宇宙は「もつれ」でできている 「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』 https://booklog.jp/users/sawataku/archives/1/4062579812
13投稿日: 2022.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログなんか、面白いんだけど、理解できないところも多く、だけど面白いと感じる、面白い本。 原題は「Helgoland」で、これは量子力学の発祥に関連がある島の名前である。 この島から始まる量子物理学の系譜から始まり、不確定性、量子もつれ、相対情報などの話に至る。途中、レーニンとボグダーノフの議論や、ナーガールジュナの空の概念まで入ってくるのが、面白い。 日本語版のタイトルである「世界は「関係」でできている」は本書の内容を端的に表しており、結論としてはこのタイトルに尽きる。 以前、仏教関係の書籍を読んでいた時に、物体を見るときに、我々の目に光子が飛び込んでくるのと同時に、我々も見る対象に影響を与えているという趣旨の話があった記憶があるのだが、相互作用により世界が形作られているという話と頭の中でリンクした。 書籍の最後の方では、心理世界と物理世界の関連についても話が及んだが、この辺はほぼ内容についていけず。 全体としては、同じ著者の「時間は存在しない」よりは理解できた気がする。 何度か読み直してみると少しづつ理解が進むかもしれないので本棚に入れておこうと。 本論とは関係ないのだが、脳が見るときの信号の流れも興味深かった。目に光が入り、信号が脳に達すると思われがちだが、実際には脳から目に向かって信号が出ているとか。脳は先に予想される映像を描き、目から入ってくる情報と整合させ、両者に違いがる場合、その違いの分を補正して「見て」いるらしい。 文章の誤字脱字に気づかないことがあるが、脳の中では予測の段階で誤字脱字がない映像を描いているのかもしれない。その映像で意味的に問題がなければそのまま理解してしまうのかも。 また、同じ文章を読むにしても、ディスプレイに映されたそれと、紙面に印刷されたそれでは誤字に気づく頻度が異なる気がする(数えたことはないが)。どちらも脳が予測してから差を補正するということに違いはないのだろうが、ディスプレイに移った情報の方がより予測との差を認識しづらいということなのかもしれない。 文章を読む行為について、脳がどこまでを予測して、補正してということを行っているかも興味が湧くところ。文章が目に入る段階で、字面を予測しているとしても、意識上ではその場で意味を認識はしていない。でも無意識の部分ではなんとなく意味を認識していて、ちゃんと意味が通る文章か予測を始めているのだろうか。 「プルーストとイカ」をもう一回読んでみたくなった。
3投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界の見方が少し変わるとても面白い本だった。 量子力学の専門的な話と言うよりも、「世界について理解する」というような哲学的な本であった。 ただ、序盤の量子力学の解説に関しては少し背景知識がないと理解が難しい。 とはいえ文系の私でも理解出来て、楽しめたので、わかりやすい本だと思う。 古典物理学では説明不可能な量子現象に対する解釈として「関係」という概念を用いて説明している。そして、その考え方が哲学的にも特異でなく、先例のある考え方であることを解説している。 題名のような過激さは本の中にはない。表紙のデザインとタイトルだけだろう。 非常に読んで楽しかった。
2投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
奇妙に美しい内側を垣間見る 極端な思いつきを集めた奇妙な動物画集 みなさんにとっては現実、でもわたしにとっては現実でない事柄とは? 現実を織りなす関係の網 立ち現れる相手なくして、明瞭な記述はない 「自然にとっては、すでに解決済みの問いだ」;でも、それはほんとうに可能なのか
0投稿日: 2021.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ量子理論の本かとおもいきや、ゴリゴリの哲学本だった。 量子の理解不能な振る舞い(観察の有無で結果が変わる)についての解釈はまだ結論が出ておらず、いろいろあるみたいだが、この本の解釈は面白いし、分かりやすかった。 その解釈の説明が前半を占め、後半はその解釈を踏まえて、この世界をどう捉えるかという哲学的な話になっていく。 そこからはかなり難しかった。 何となく分かったような分からんような感じだったが、物理学と哲学の近さは感じた。
0投稿日: 2021.12.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ量子論は確率、観測可能、粒状性 位置や速度は「行列」で示される 量子 重ね合わせ どちらでもない状態 ハイゼンベルグの「観測」オブザーベイション 観察によって手持ちの情報が変わる 二つの物理的対象物のすべての総合作用を「観測」と見なすことができる。 あらゆる対象物のあらゆる属性が速度のように相対的 量子もつれ エンタングルメント 遠く離れた二つの対象物が同じ振る舞いとなる 第三の対象物との関係 ナーガールジュナの「空」 独立した存在がありえない ≒量子力学論 究極の実態の追求 ⇔ 相互依存と偶発的な出来事の世界 意味とは、生命の外側と内側の妥当な「相対情報」 概念の更新 脳は見えそうなものを予期し、自分の予測に反する情報の入力、確認をしている
0投稿日: 2021.12.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ解説竹内氏の「ルネサンス的な知性による本」まさにその通り!! 量子物理学のテーマからこんな哲学の話につながっていくとは思わなかった。たしかに世界の真理を解き明かそうとする学問という根っこは同じか。 竹内薫氏の解説、冨永星氏の訳者あとがきから読んでもいいかもしれない。本文で迷子にならないようガイドになってくれる感じ。 正直、量子物理学の現象の詳細やら過去の物理学者のアレコレは斜め読みですっ飛ばしていたが(とはいえシュレーディンガーのスキャンダラスな私生活には思わず目をみはる)、哲学的思索へとつながっていく流れに引き込まれていき、じっくり読み耽ってしまった。 量子物理学では、対象物と測定装置との相互作用を無視することができない。絶対かと思える実験結果も、あくまでその観測者の視点で像を結んだ見え方にすぎない。それは観測者と対象との「関係」によって実現されたもの。現象とは、この世界の一つの部分からほかの部分への働きかけなのだ。 ほかの要素との関係において他の要素のありようが決まる、というのは、受精卵から細胞が分化していくときに隣の細胞がどの組織になるかによって自分も何の組織になるか決まる…「細胞は空気が読める!」という話と既視感を覚えた。出典は福岡伸一氏。『動的平衡』だったか? 絶対不変の現実は存在せず、ほかの視点と相互に関係することで、その事象への理解が深まっていく。 真実はいつも一つ?それはどうかな?? 人がものを見るとき、目から脳に信号が送られて像を結んでいるのではなく、実際は脳から目へ信号の大部分が送られている。脳はすでに知っていることに基づいて見えそうなものを予期し、予測した像を作る。そして予測と違いがある場合に限って、目から脳に信号が送られる。それがもっとも効率的なやり方だから。 色眼鏡をかけてものを見ると、予測との違いを脳は受け取らないんじゃないだろうか。それが認知バイアス。 ダイヤの原石を磨けるのはダイヤモンドだけ。テーゼとアンチテーゼからのアウフヘーベン。多様性の中で生み出されたアイディアはよりイノベーティブ。 自分だけの視点、あるいは同質的な視点ばかりでものを考えるのではなく、異なる視点と交わることでより高みへ行ける。ダイバーシティの重要性とはそういうことだろうと思い至った。著者がそんなことを伝えたいのかはわからないが! 最後の最後、シェイクスピア『テンペスト』からのプロスペロの一節の引用が沁み入る。いやはや、著者の教養には恐れ入る。
2投稿日: 2021.12.07
