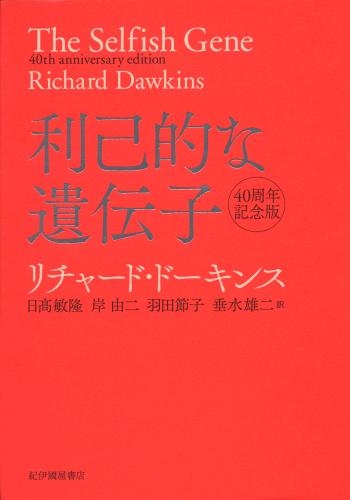
総合評価
(61件)| 22 | ||
| 24 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ若干冗長で長いけど、我々生物は遺伝子の乗り物であり、個体の生物としてではなく遺伝子としてどのように自分を未来に残していくかだけが真に重要な事だと強く説得してくれる。 人間の社会的行動の全てでこのような未来に向かう遺伝子のパワーで動いている側面が感じられるようになる。一度読むと世界の見方が変わる本。
0投稿日: 2025.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の体は遺伝子のヴィークルで、遺伝子が増殖するように進化する。遺伝子自体に感情はないが、まるで利己的な遺伝子があるかのように進化はすすむ。群れのために自分を犠牲にする人間や生物の利他的行動も、遺伝子の観点からみれば、おのれが増殖するためには良い行動になっている(そうなるようなDNAを持つヴィークルが生き残る)。母が自分を犠牲にして子供を助けるのは自分の遺伝子を将来に届けるため。はちが外敵を針で刺して絶命するのは、繁殖能力のない己を犠牲にして自分の遺伝子を持つ女王バチにつくすため。情報を後世に拡散させるものは遺伝子だけとは限らず、自己複製子は文化でもおこる。非遺伝的に継承される芸術・習慣・技術などなど、これをミームと名付ける。今から50年近くも前に書かれた本なのに、内容はしっくりくる。 ヴィークルを一旦リセットして(死なせて)、次の世代につなぐ際、遺伝子を複製&ちょっとだけ改変して環境変化に備える(いろいろな複製遺伝子のうち、環境変化に耐えたものだけが生き残る)という仕組みはとてもレジリエンス度が高い。自分の心と行動は遺伝子に左右されていると言われると、不満・不安を感じる人も多くいるかと思うが、遺伝子に感情があるわけではなく、結果的に生存率の高い遺伝子が残っていると考えるとしっくりくる。自分の行動を左右する遺伝子も、生存率が高かったからこそ現時点で自分というヴィークルの中で生き残っているのだ。 AI時代となり、複製と進化はコンピューターコード・アルゴリズムで起こっている。DNAよりも進化が速いこれらのミームの登場は、新たな生命?を予感させる。遺伝子との違いは生まれ変わるという概念が薄いこと。AI自身で全てのコードを一旦書き換える(生まれ変わる)、AIの世代交代が起こった時こそ、AIが人間を追い越すシンギュラリティ―と言える感じた。 それにしても、文章が冗長で通読するのに疲れたので星は3つ・・・・
0投稿日: 2025.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ・リチャード・ドーキンスによる、利己的遺伝子論に関する本。進化論を遺伝子を中心に解釈した有名な科学史の本。生物は、個のレベルで見ると一見利他的に見えるような行動をとるが、これは自らの遺伝子の生存に有利に働くからであり、遺伝子のレベルで見ると利己的である。 ・進化の過程を見ると、「生物は遺伝子のための生存機械=生物という形態は遺伝子が勝ち残っていくための防御のようなもの。」「この生存機会は多数の遺伝子を含んだ「乗り物」のようなもので、遺伝子は生存機械を乗り捨てて生きながら、自らのコピーを広げている。」 ・私の利他的に見える優しい行動も、遺伝子レベルで見ると生存に有利だからという利己的な行動だったのだ! 結構好きな考え方
0投稿日: 2025.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間をはじめとする生物普遍の問題である「なぜ世の中から争いがなくならないのか」などの問題を動物や人間社会でみられる親子の対立と保護、雌雄の争い、攻撃やなわばり行動などがなぜ進化したかを説き明かします。 読み終えたことは読み終えたわけですが。正直、現在に至るまで本質的なところはあんまりよく解ってないです。 大きな理由の一つといたしましては、中学時代から理科の勉強が苦手となり、高校に進学して以降は、生物の勉強をサボりにサボっていた果てに地学を選択し(そこでも全く成績は振るわなかった)後遺症のひとつが、まさかこういう形で噴出してくるとは思いもよりませんでした。 しかし、「なぜ世の中から争いがなくならないのか「なぜ男は浮気をするのか」―などなどのここで書かれている諸問題というのは人間に限らず生物にととってはおそらく今後も普遍的なものであると思いますので、もう少し生物の本を色々読んでから本書を読み返してみようと思います。 本書は40周年記念版ということで前版からの変更点がありまして ・ドーキンスによる「40周年記念版へのあとがき」追加 ・岸由二による「40周年記念版への訳者あとがき」追加 ・古くなった表現、表記を変更 ・装幀と本文レイアウトを刷新 とのことです。 時間に余裕のある方は僕の無念を引き継いで本書を読破されることを陰ながら祈っております。
5投稿日: 2025.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ紀伊國屋書店 増補改題『生物=生存機械論』 (科学選書 9)版を遺伝に興味があった学生時代に読了。相対性理論を初めて学んだ時のような衝撃をよく覚えている。
0投稿日: 2025.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言葉というものは私たちが自由に使う道具にすぎず、またたとえ、「生きている」というような言葉が辞書にあるからといって、その言葉が現実世界における何か明確なものを指しているとは限らない。人間の苦難は、こういったことを理解していない人があまりに多いために生じているのだ。 メイナード=スミスが提唱している重要な概念は、「進化的に安定な戦略(ESS|Evolutionary Stable Strategy)」と呼ばれるもので、もとを辿れば、W・D・ハミルトンとR・H・マッカーサーの着想に基づいている。「戦略」というのは、あらかじめプログラムされている行動指針だ。戦略の一例としては、「相手を攻撃しろ、彼が逃げたら追いかけろ、押収してきたら逃げるのだ!」などというものがある。理解してもらいたいのは、この戦略を個体が意識的に用いていると考えているわけではないということだ。私たちは動物を、筋肉の制御についてあらかじめプログラムされたコンピュータを持つロボット生存機械だ、と考えてきたことを思い出してほしい。この戦略を一組の単純な命令として言葉で表すことは、これについて考えていくうえでは便利な方法である。あるはっきりとわからないメカニズムによって、動物はあたかもこれらの命令に従っているかのように振る舞うのだ。 進化的に安定な戦略、すなわちESSは、個体群の大部分のメンバーがそれを採用すると、別の代替戦略に取って代わられることのない戦略だと定義できる。これは微妙かつ重要な概念である。別の言いかたをすれば、個体にとって最善の戦略は、個体群の大部分が行っていることによって決まる、ということになる。個体群の残りの部分は、それぞれ自分の成功の最大化を目指す個体で成り立っているので、残っていくのは、いったん進化したらどんな異常個体によっても改善できないような戦略だけだ。環境に何か大きな変化が起こると、短いながら進化的に不安定な期間が生じ、おそらく個体群内に変動が見られることさえある。しかし、いったんESSに到達すれば、それがそのまま残る。淘汰はこの戦略から外れたものを罰するだろう。 この概念を攻撃にあてはめるために、メイナード=スミスの一番単純な仮定的例の一つを考察してみよう。ある種の個体群には、「タカ派」型と「ハト派」型という二種類の戦略しかないものとする(この名は世間の慣用的用法に従っただけで、この名を提供している鳥の習性とは何の関係もない。じつは、ハトはかなり攻撃的な鳥だ)。私たちの仮定的個体群の個体は、すべてタカ派かハト派のどちらかに属するものとする。タカ派の個体は常にできるかぎり激しく際限なく戦い、ひどく傷ついたときしか引き下がらない。ハト派の個体はただ、もったいぶった、規定どおりのやりかたでおどしをかけるだけで、誰をも傷付けない。タカ派の個体とハト派の個体が戦うと、ハト派は一目散に逃げるので、けがをすることはない。タカ派の個体どうしが闘うと、彼らは、片方が大けがをするか、あるいは死ぬまで戦い続ける。ハト派とハト派が出会った場合は、どちらもけがをすることはない。彼らは長い間互いにポーズを取り続け、ついにはどちらかが飽きるか、これ以上気にするのはよそうと決心するかして、やめる。当面のところ、ある個体は特定のライバルがタカ派かハト派かを前もって知る手立てはないものと仮定しておこう。彼はライバルと闘ってみて初めてそれを知るだけで、手がかりとなるような、特定の個体との過去の戦いを覚えていないものとする。 さて、まったく任意の約束事として、闘う両者に「得点」を付けることにする。たとえば、勝者には五〇点、敗者には〇点、重傷者にはマイナス一〇〇点、長い戦いによる時間の浪費にはマイナス一〇点としよう。これらの特典は、遺伝子の生存という通貨に直接換算できるものと考えていい。高い得点を得ている個体、つまり高い平均「得点(pay-off)」を受けている個体は、遺伝子プール内に多数の遺伝子を残す個体である。この実際の数値はかなり広い範囲内でどのようにとっても分析に差し支えない性質のものだが、私たちがこの問題を考えるうえでは役に立つ。 重要なのは、タカ派がハト派と闘ったときにハト派に勝つかどうかが問題なのではないという点だ。その答えはすでにわかっている。いつでもタカ派が勝つに決まっている。私たちが知りたいのは、タカ派型とハト派型のどちらが進化的に安定な戦略(ESS)なのかだ。もし片方がESSで他方がそうないのであれば、ESSの戦略のほうが進化すると考えなければならない。二つのESSが共存することも理論的にはありうる。もし、個体群の大勢を占める戦略がたまたまタカ派型だろうとハト派型だろうと、ある個体にとって最善の戦略は先例にならうというものだったら、このことが言える。この場合、個体群は二つの安定状態のどちらでもいいから、たまたま先に到達したほうに固執することになるだろう。しかし、次に述べるように、じつは、タカ派型とハト派型という二つの戦略はどちらもそれ自体では、進化的に安定的ではない。したがって、どちらかが進化すると期待するわけにはいかない。このことを示すには、平均得点を計算する必要がある。 全員ハト派から成る個体群があるとしよう。彼らは闘っても、誰も傷付かない。おそらくその争いは長い儀式的な試合、あるいはにらみ合いであって、どちらかが引き下がった時点で決着がつく。このとき勝者は、闘って資源を手に入れたので五〇点を得るが、にらみ合いに長い時間をかけたのでマイナス一〇点の罰金を払うため、結局四〇点になる。敗者もやはり時間を浪費したので一〇点引かれる。平均すると、ハト派の個体はいずれも争いの半数に勝ち、半数に負けるものと考えられる。したがって、一戦あたりの彼の得点はプラス四〇とマイナス一〇の平均、プラス一五点となる。というわけで、ハト派型の個体群中のハト派個体はすべてたいへんうまくやっているように思われる。 ところが今、この個体群にタカ派型の突然変異個体が現れたとしよう。彼はここでは唯一のタカ派型個体なので、闘う相手はすべてハト派だ。タカ派は必ずハト派に勝つので、彼はすべての戦いでプラス五〇点を獲得し、これが彼の平均得点となる。彼は、正味一五点しかないハト派に比べて莫大な利益を享受する。その結果、タカ派の遺伝子は、その個体群内で急速に広まるだろう。しかし、そうなるとタカ派の各個体は、もはや出会ったライバルがすべてハト派であることを期待するわけにはいかなくなる。極端な例を挙げるなら、タカ派の遺伝子が首尾良く広まって、個体群全体がタカ派になった場合、今度はすべての戦いがタカ派同士の戦いになるはずだ。今や、事情は一変する。タカ派の個体どうしが出会うと、片方がけがをするのでマイナス一〇〇点となり、勝者はプラス五〇点を取る。タカ派個体群の各個体は戦いの半数に勝ち、半数に負けると考えられる。したがって、一戦あたりの平均得点は、プラス五〇とマイナス一〇〇の平均、すなわちマイナス二五点となる。ここで、タカ派の個体群内にハト派が一個体いるとしてみよう。確かに彼はすべての闘いに負けるが、その一方でけっしてけがをすることはない。タカ派個体群内のタカ派個体の平均得点がマイナス二五点になるのに対して、彼の平均得点は、タカ派個体群内ではゼロだ。したがって、ハト派の遺伝子はその個体群内に広まる傾向がある。 この話の語り口からすると、あたかも個体群内にたえず振動があるように思われるかもしれない。タカ派の遺伝子は圧勝して優勢を占める。すると大半がタカ派になる結果、ハト派の遺伝子が有利になり数を増やしていく。やがてハト派が多くなると、またタカ派の遺伝子が栄え始める、という具合に。しかし、このような振動の起こる必要はない。どこかに、タカ派とハト派の安定した比率が存在するのだ。私たちが用いている任意の得点システムから計算してみると、安定した比率は、ハト派が十二分の五、タカ派が十二分の七となることがわかる。この安定した比率に達すると、タカ派の平均得点とハト派の平均得点がちょうど等しくなる。このため、淘汰が一方より他方に有利に働くことはなくなる。もし個体群内のタカ派の数が次第に上り始め、その比が十二分の七以上になると、ハト派が余分の利益を受け始め、その比率がもとに戻って、安定状態になる。安定した性比が五〇対五〇であるのと同様に、この仮定的例では、タカ派対ハト派の比が七対五だ。どちらの場合も安定点付近で振動があったとしても、それは非常に大きなものになることはない。 表面的には、これは群淘汰説(グループ・セレクション)にいくぶん似ているように思われるかもしれないが、実際にはまったく違う。群淘汰説に似ているように見えるのは、この説明が、個体群には安定な平衡状態というものがあって、それを乱すと、またその点まで戻ろうとする傾向があると考えることを可能にするからだ。だが、ESSは群淘汰よりはるかに微妙な概念である。それは、ある集団が他の集団より成功するかどうかには関係がない。このことは、私たちの仮説的例の任意得点システムと使うとうまく説明できる。タカ派十二分の七、ハト派十二分の五から成る安定した個体群内のある個体の平均得点は、六・二五となることがわかる。これは、その個体がタカ派でおハト派でもそうだ。ところで、この六・二五というのはハト派個体群内のハト派個体の平均得点(一五)よりずっと低い。全員がハト派になることに同意しさえすれば、どの個体も有利になるはずだ。単純な群淘汰説によれば、全員がハト派になることに同意した集団はいずれも、ESS比にとどまっているライバル集団より成功するはずだ(じつは、全員ハト派になろうという申し合わせをした集団は、成功する可能性が最も高い集団ではない。タカ派六分の一とハト派六分の五からなる集団では、一戦あたりの平均得点が一六・六六である。これが考えられるもののなかで最もうまくいく申し合わせだが、当面の目的からすれば無視できる。全員ハト派で、各個体が一五点の平均得点を持つ集団は、すべての個体にとって、ESS集団よりはるかに良い)。したがって、群淘汰説は、全員ハト派の申し合わせに向かって進化する、と予言することだろう。なぜなら、タカ派が十二分の七の割合で含まれている群れは、それよりうまくいかないはずだからだ。しかし、申し合わせにつきものの難点は、長期にわたって全員の利益をはかるという申し合わせでさえ、裏切りを免れないことである。たしかにどの個体も、ESS集団にいるより、全員ハト派の集団にいるほうが有利だ。しかし残念ながら、ハト派の申し合わせをした集団に生まれた一個体のタカ派はあまりにもめぐまれているために、タカ派の進化を食い止めることができない。こういうわけで、この申し合わせ集団は裏切りによって内部から崩壊していく運命に縛られている。それにひきかえ、ESSは安定している。なぜならESSがそれに加わっている個体にとってとくに有利だからではなくて、たんに内部からの裏切りを食い止める力を持っているからである。 人間では、各個人の利益をはかる申し合わせをしたり協定を結んだりすることは、たとえそれがESSという意味で安定していなくても可能だ。だがこれができるのは、個人全員が意識的に将来の見通しを立て、その協定の規約に従うことが自分の長期的利益につながることを見抜けるからにほかならない。人間の協定ですら、その協定を破れば短期間に大儲けできるため、そうしたいという誘惑が常に優勢になる危険をはらんでいる。この最も良い例は価格協定だろう。ガソリンの価格を人為的に高値に決めれば、ガソリン業者は全員が長期間利益をむさぼれる。長期にわたる高い利益を意識的に見込んで結託した価格協定集団は、相当長い期間生き延びるはずだ。ところが、遅かれ早かれ、自分だけ値下げをして早く大儲けをしたいという誘惑に負ける者が現れる。するとたちまち、その近隣の業者が真似をし、値下げの波が国じゅうに広がる。すると、ガソリン業者以外の私たちには残念なことだが、彼らの将来への意識的な配慮が再び頭をもたげ、新たな価格協定が結ばれる。このように、意識的に見通しを立てる才能に恵まれた種である人間においてさえ、長期的利益に基づく協定ないし申し合わせは、内部からの崩壊の瀬戸際でたえず動揺を続けている。まして、せめぎ合う遺伝子によって支配されている野生動物では、集団の利益や申し合わせの戦略が進化するとはとても思えない。したがって、進化的に安定な戦略という方式がいたるところに見られると考えなければならないだろう。 私たちの仮説的例では、ある一つの個体は、タカ派かハト派のどちらかだという単純な仮定をした。そして結局、タカ派とハト派の進化的に安定な比率に収束した。実際にこれは、タカ派の遺伝子とハト派の遺伝子の安定した比率が遺伝子プール内に確立されるということだ。遺伝子用語ではこの状態を安定多型(stable polymorphism)と呼ぶ。けれど数学的には、多型を考えなくても次のようにしてまったく等しいESSが達成されうる。どの個体もがそれぞれの争いにおいてタカ派のようにもハト派のようにも振る舞えるのであれば、全個体がおなじ確率で、つまり私たちの例で言えば十二分の七の割合でタカ派のように振る舞うようなESSが達成される。実際にはこれは、各個体が、そのときにタカ派のように振る舞うべきか、ハト派のように振る舞うべきかを(ランダムにではあるが、七対五の割合でタカ派のほうに多く)決断して、それぞれの争いを始めるということだ。ここできわめて重要なのは、この決断がタカ派のほうに傾いているとはいえ、どの争いの際にもライバルには自分の相手がどう振る舞おうとしているかを推定する手立てがないという意味でランダムでなければならない、という点である。たとえば、続けて七回の争いにタカ派を演じ、次に続けて五回ハト派を演じ、以下同様というのはだめだ。どの個体かがこのような単純な順序を取ったとしたら、そのライバルはすぐさまこの順序を飲み込んで利用するだろう。単純な順序の戦略をとる相手を利用する方法は、彼がハト派を演じようとしていることがわかったときにだけ、彼に対してタカ派を演じることだ。 もちろん、タカ派とハト派の話はあまりにも単純である。これは、自然界で実際に起こらないが、自然界で起こることを理解するうえで役立つ「モデル」だ。モデルには、このモデルのようにごく単純だが、にもかかわらずある点を理解するうえで、あるいはあるアイディアを得るうえで役に立つものがある。単純なモデルはさらに精巧にすることもできるし、次第に複雑にしていくこともできる。何もかもうまくいけば、モデルは複雑になるほど実世界に似てくる。タカ派とハト派のモデルと発展させる手はじめは、さらにいくつかの戦略を付け加えることだ。可能性のある戦略は、タカ派型とハト派型だけではない。メイナード=スミスとプライスが導入したさらに複雑な戦略を、「報復派」型と呼ぶ。 報復派はどの闘いでも、最初はハト派のように振る舞う。つまり、タカ派のように徹底した激しい攻撃をしかけず、規定通りの威嚇試合をする。しかし、相手が攻撃をしかけてきた場合は報復する。言い換えれば、報復派は、タカ派に攻撃されたときにはタカ派のように振る舞い、ハト派に出会ったときにはハト派のように振る舞う。別の報復派に出会った場合は、ハト派のように振る舞う。報復派は、条件戦略者である。その行動は相手の行動によって決まる。 もう一つの条件戦略者を、「あばれん坊派」と呼ぶ。あばれん坊派は、誰かが攻撃してくるまでは誰にでもタカ派のように振る舞う。反撃に遭うとただちに逃げ出す。さらにまた別の条件戦略者は「試し報復派」である。試し報復派は基本的には報復派に似ているが、ときおり争いをちょっと実験的にエスカレートさせてみる。そして相手が反撃に出なかったら、このタカ派型の行動を続ける。けれどもし反撃されたら、ハト派型のように規定通りの威嚇に戻る。攻撃を受けた場合は、普通の報復派とまったく同じように報復する。 コンピュータによるシミュレーションで、これまでに挙げた五つの戦略者すべてを自由に振る舞わせると、報復派だけが進化的に安定であることがわかる。試し報復派は、ほぼ安定だ。ハト派は、その個体群がタカ派とあばれん坊派の侵略を許すので、安定でない。報復派の個体群は、報復派自身よりうまくやる戦略が他にないため、どの戦略者にも侵されない。しかしハト派は、報復派の個体群内では同じくらいうまくやれる。つまり他の条件が同じであれば、ハト派の数がゆっくり増えていくことになる。ところがハト派の数がかなりの程度まで増えると、試し報復派が(ついでに言うなら、タカ派とあばれん坊派も)有利になり始める。というのは、彼らはハト派に対する対処の仕方が報復派よりうまいからだ。試し報復派自身は、タカ派やあばれん坊派と違って、ほぼESSだと言える。試し報復派の個体群内で彼らよりうまくやれるのは他の戦略のうちで報復派だけだし、この戦略とていくぶんましにすぎないという意味においてである。したがって、報復派と試し報復派の混ざったものが、恐らくこの二者間の静かな振動を保ちながら、少数派のハト派の数の振動と関連しつつ優勢を占めていく。この場合もやはり、どの個体も常にある決まった戦略を取るという多型を想定する必要はない。各個体は報復派、試し報復派、およびハト派が複雑に入り混じった行動を取ることができるはずだ。 この理論上の結論は、大部分の野生動物の世界で実際に起こっていることとかけ離れてはいない。動物の攻撃の「グローブをはめたこぶし」的側面についてはある程度説明した。もちろん詳細は、勝利やけがや、時間の浪費に与えられる「点数」の正確さにかかっている。ゾウやアザラシの場合、勝利に対する報酬は、雌の大ハーレムをほぼ独占できる権利である。ゆえに、勝利の得点は非常に高くしておかなければならない。闘いが激しいのも、重傷を負う確率が高いのもあまり不思議ではない。時間の損失というコストは、けがによるコストと勝利の利益に比べておそらく小さいと考えなければなるまい。他方、寒い地方に住む小鳥にとっては、時間の浪費というコストは何物にも代え難い大きな損失だろう。育雛期のシジュウカラは三〇秒に一回の頻度で獲物をつかまえる必要がある。まさに日中の一秒一秒が貴重なのだ。タカ派対タカ派の闘いで使われる比較的短い時間でさえ、こうした小鳥たちにとってはおそらくけがの危険以上に深刻なものだ。残念ながら、現在、自然界の諸現象のコストと利益(ベネフィット)に実際の数値をあてはめるには、あまりにもわかっていることが少な過ぎる。私たちは、自分で勝手に決めた数値から簡単に結論を引き出さないよう注意する必要がある。重要な一般的結論は、ESSが進化する傾向があること、ESSが集団の申し合わせによって達成されうる最適条件と同じではないこと、そして常識は誤解を招く場合あることだ。 メイナード=スミスが考えたもう一つの戦争ゲームは「持久戦」である。これはけっして危険な闘いをしない種、おそらくまずけがなどしそうもない、鎧に覆われた種に見られるものと考えられる。このような種では争いはすべて儀式的姿勢によって解決される。争いは常に、どちらかが引き下がることで終わる。勝つためにしなければならないのは、相手が背を向けるまで自分の陣地に踏みとどまり、敵をにらみつけていることなのだ。威嚇に無限に時間をかけていられる余裕のある動物など、明らかにいない。ほかにするべき大事なことがいくらでもある。彼が争っている資源は価値があるかもしれないが、無限に価値があるわけではない。それは、しかるべき時間に値するにすぎず、競売(オークション)の場合と同様に、各個体はその資源にはしかるべき額しか費やさない覚悟をしている。時間はこの二人の競りの通貨だ。 これらの個体はみな、ある資源、たとえば雌が、どれだけの時間に値するかを、あらかじめ正確に算定するものと考えよう。少しだけ長く続ける覚悟をした突然変異個体は常に勝つはずだ。したがって、決まった競り値を守るという戦略は不安定である。たとえ資源の価値がきわめて正確に推定され、全個体が正しい値をつけたとしても、この戦略は不安定だ。この時間を最大化する戦略によって競りをする二個体は、ちょうど同じ瞬間に諦め、どちらも資源を手に入れ損なうに違いない! この場合、争いで時間を無駄にするよりは、最初からさっさと権利を諦めるほうが、個体にとっては得策なのだ。持久戦と実際の競りとの大きな違いは、要するに、持久戦では競争者がどちらも犠牲を払うが、利益を得るのは片方だけという点である。したがって、踏みとどまる時間を最大化しようとする戦略を取る個体群内では、最初から諦めるという戦略が成功し、個体群内で広がるだろう。そうなると今度は、すぐに諦めずに数秒待って諦める個体に利益が生じ始める。この戦略は、現在個体群内で優勢を占めている即時退却派に対して演じられたときには有利に違いない。そこで淘汰は、諦める時間を次第に引き伸ばす方向に働き、いずれそれは、争われている資源の真の経済的な価値によって許される最大値に再び近づくことになるだろう。 私たちはここでも、数式でなく言葉を使って、あたかも個体群がもろもろの戦略をめぐる振動を示すかのように描写してきた。が、数学的分析によれば、この場合もやはり、その描写は正しくないことがわかる。ある進化的に安定的な戦略があって、それは数学の式で表せるが、それと同じことを言葉で表すとこうなる。各個体が持久戦を続ける時間は予言できない。それはどんな場合にも、すなわち資源の真価を平均する以外には予言できない。たとえば、資源が実際には五分間のディスプレイ(誇示)を続けることもあれば、五分以下しか続けない場合もあるし、また、きっかり五分間続けることもある。ポイントは、彼がその場合どれくらいの時間続けるつもりなのかを相手が知るすべはない、ということだ。 持久戦では、諦めかけているときにそれを相手に悟られないようにすることがなにより重要なのは明白だ。ひげをちょっと動かしたりして、敗北を認めようかと考え始めていることをうっかり匂わしたほうは、とたんに不利になる。たとえば、ひげを動かすことが、一分後に退却することの確かな兆しだとすれば、ごく単純な勝利の戦略が描ける。「相手のひげが動いたら、当初の計画がどうであろうとも、一分間待つがいい。相手のひげがまだ動かず、しかもどのみち諦めるつもりだった時間までにあと一分足らずしかない場合には、即刻諦めてそれ以上時間を無駄にするのをよしたほうがいい。自分のひげはけっして動かさないことだ」。こういうわけで、自然淘汰は、ひげを動かすことやその他、その後の行動を露呈してしまうようなしぐさをただちに罰するだろう。ポーカーフェイスが進化するはずだ。 まったくのでたらめを言うよりポーカーフェイスの方が良いのはなぜか? やはり、嘘をつくことが安定ではないからだ。大部分の個体が、持久戦でほんとうに長時間がんばるつもりがあるときしか頸の毛を逆立たせない場合を考えてみよう。相手の裏をかく計略が進化するに違いない。つまり、相手が毛を逆立てたらただちに諦めるという作戦だ。だがここで、嘘つきが進化し始める。実際に長時間がんばるつもりのない個体がいつでも毛を逆立てることによって、勝利を容易にすばやくものにするだろう。こうして、嘘つきの遺伝子が広がっていくのだ。やがて嘘つきが大勢を占めると、淘汰は今度はそれを見破って挑戦する個体に有利に働く。このため、嘘つきは再び数が減る。持久戦では、嘘をつくことは真実を語ることより進化的に安定だとは言えない。ポーカーフェイスは進化的に安定である。ついに降伏するとしてもそれは突如としてなされ、予測不能だ。 私たちがこれまで検討してきたのは、メイナード=スミスが「対照的」争いと呼んでいるものばかりだ。つまり、競争者どうしが、闘いの戦略以外のあらゆる点でまったく同一だと仮定されていることである。タカ派とハト派は同じ強さであり、武器や鎧で同じように武装しており、勝利によって得るものも同じと仮定されている。これはモデルを利用するには都合の良い仮定だが、あまり現実的ではない。そこでパーカーとメイナード=スミスは、非対称的な争いを考えてみた。たとえば、もし戦闘能力や体の大きさが個体によって異なり、各個体が自分との比較のうえで相手がどれくらい大きいかを計ることができたとしたら、このことが、そこに生じるESSに影響をおよぼすだろうか? おそらく影響を及ぼすはずだ。 非対称的な争いは、主に三つ考えられる。第一は、今述べたように、体の大きさか戦闘能力が個体によって異なる場合。第二は、勝利によって得ようとしている報酬が個体によって異なる場合である。たとえば、どうがんばっても老い先の短い老雄は、前途に膨大な生殖生活を控えた若雄と違って、たとえ傷ついても失うものが少ない立場にあるだろう。 第三に、これはこの説の一風変わった結論だが、まったく任意の、一見関係なさそうに見える非対称がESSを生み出す可能性がるというものだ。そのように非対称のおかげで、急速に争いの決着がつくことがあるからだ。たとえば、競争者の一報がたまたま他方より先に争いの場に到着している場合は、たいていこれにあてはまる。彼らをそれぞれ「先住者」「侵入者」と呼ぶことにしよう。議論の都合上、先住者や侵入者であることには、一般的な利益はないものと仮定する。のちに述べるように、この仮定が実際には正しくないと思われる理由があるが、これは重要ではない。重要なのは、たとえ先住者が晋遊舎より有利だと考える一般的な理由がなくても、この非対称それ自体によって決まるあるESSが進化するという点である。単純なたとえとしては、人間が大騒ぎをしたりせずに、コインを投げてあっさりもめごとの決着をつけるのがこれにあたる。 条件戦略、すなわち「自分が先住者であれば攻撃し、侵入者であれば退却せよ」というのがESSになるのかもしれない。また、非対称が任意だという仮定があるので、「先住者であれば退却し、侵入者であれば攻撃せよ」という逆の戦略が安定となる可能性もある。ある個体群においてこの二つのESSのうちどちらが採用されるかは、どちらが先に大勢を占めるかにかかっている。大部分の個体がこの二つの条件戦略の片方を取るようになると、それから外れた異常個体は罰を受ける。したがって、定義からすればそれがESSなのだ。 たとえば、全個体が「先住者が勝ち、侵入者が逃げる」戦略を取るとしよう。これは、彼らが闘いの半分に勝ち、半分に負けることを意味している。彼らはまったくの無傷で、時間も無駄にしない。なぜなら、すべての争いが任意の規定によってただちに解決されるからだ。さてここで新たに突然変異の反逆者が現れたとしよう。彼は常に攻撃し、一向に退かない純粋なタカ派型戦略を取るものとする。相手が侵入者の場合には、彼は勝つだろう。相手が先住者であれば、負傷という大きな危険を冒すことになる。平均すると、彼はたびたびけがをするばかりでなく、めったに争いに勝てない。だが、何か偶然の出来事によって、この逆の規定に従う個体が大勢を占めるようになった場合を考えてみよう。そのとき、彼らの戦略は安定した規範になり、これから外れたものは罰を受ける。もしかすると、ある個体群を何世代にもわたって観察すれば、ときおりある安定状態から別の安定状態へ突如移り変わるのが見られるかもしれない。 しかし、実生活においては、真に任意の非対称というものはおそらく存在しない。たとえば、先住者は侵入者より、実際に有利な立場だろう。彼らはその土地の地形をよく知っている。また、先住者がずっとそこにいたのに対して、侵入者は戦場に赴いてきたのだから、息を切らしているかもしれない。自然界で二つの安定状態のうち「先住者が勝ち、侵入者が退く」状態のほうがより可能性が高いことには、もっと深い理由がある。つまり、「侵入者が勝ち、先住者が退く」という逆の戦略は、自己崩壊を招く傾向を本来的に持っているのだ。メイナード=スミスはこれを逆説的戦略と呼んでいる。この逆説的ESSの状態にある個体群では、個体は常に先住者と見られないようにと努めているはずだ。つまりどんな出会いにおいて、常に侵入者であろうと努めているに違いない。彼らがそれをやり遂げるには、たえまなく、他に何の意味もなく動きまわるしかない。その時間とエネルギーの損失は別としても、この進化傾向は「先住者」という範疇を自然と消滅させていくことになる。「先住者が勝ち、侵入者が退く」というもう一方の安定状態にある個体群では、先住者になろうと努める個体に有利に自然淘汰が働く。各個体にとっては、これは、ある区域に踏みとどまり、できるだけそこを離れず、そこを「守ろう」とすることだ。今ではよく知られているように、こうした行動は自然界に一般的に見られ、「なわばりの防衛」と呼ばれている。 この型の行動的非対称で私が知っている最も見事な実例に、偉大なる動物行動学者(エソロジスト)のニコ・ティンバーゲンが、彼ならではの巧妙で単純明快な実験によって示したものがある。彼は、雄のトゲウオが二匹入った水槽を持っていた。魚はそれぞれ水槽の反対側の隅に巣をかまえ、自分の巣のまわりのなわばりを「守って」いた。ティンバーゲンはこの二匹の魚をそれぞれ大きなガラスの試験管に入れて、この二本の試験官を並べて持ち、魚たちが試験管を通して闘おうとするのを観察した。するとたいへん興味深い結果が得られた。二本の試験官を雄Aの巣に近づけると、Aが攻撃姿勢を取り、雄Bが退却しようとした。だが試験管を雄Bのなわばりに移動させると、形勢が逆転した。ティンバーゲンは、単に日本の試験官を水槽の一端から他端へ動かすだけで、どちらの雄が攻撃し、どちらの雄が退却するかを指示することができた。どちらの雄も明らかに単純な条件戦略を、つまり「先住者であれば攻撃し、侵入者であれば退却する」という戦略を取っていたのである。 生物学者はよく、なわばり行動の生物学的「利点」は何かを問う。これにはさまざまな示唆がなされており、そのなかのいくつかについてはのちほど述べる。だがいまや、この質問そのものが無用かもしれないということがわかってきた。なわばり「防衛」とは単に、二個体とある一定の地域との関係を決める、到着時刻の非対称ゆえに生じたESSにすぎないかもしれないのだ。 任意でない非対称のうちもっとも重要なものは、体の大きさと一般的な戦闘能力だろう。体の大きいことは必ずしも闘いに勝つために最も重要な要件とは言えないが、やはりその一つではある。闘う二者の大きいほうが常に勝つのであれば、そして各個体が、自分が相手より大きいか小さいかを確実に知っているのであれば、何らかの意味のある戦略は、ただ一つしかない。すなわち、「相手が自分より大きければ逃げろ。自分より小さい奴にはけんかをふっかけろ」。大きさの重要性がそれほど確実でないとなると、ことは少々ややこしくなる。体の大きいことがわずかでも有利であれば、今述べた戦略はまだ安定である。だが負傷の危険が大きいとなると、第二の「逆説的戦略」も考えられる。すなわち、「自分より大きい奴にけんかをふっかけ、小さい奴から逃げろ!」というものだ。この戦略が安定となる理由は以下のとおり。全員が逆説的戦略を取る個体群では誰もけがをしない。これはあらゆる争いにおいて、関係者の一方、つまり体の大きいほうが常に逃げるからだ。ここに、小さい相手をいじめるという「常識的」戦略を取る平均的大きさの突然変異が現れると、その個体は出会った相手の半数と激しい争いを演じることになる。これは、彼が自分より小さい相手に出会うと攻撃を仕掛け、その小さい個体は逆説的戦略を取っているので激しく応戦してくるからだ。常識的戦略派は逆説的戦略派より勝つ確率は高いが、なお、負けて大けがをする危険も十分にある。個体群の大部分が逆説的戦略を取っているので、常識的戦略者はどの逆説的戦略個体よりもけがをする可能性が高い。 逆説的戦略はたとえ安定だったとしても、おそらくこれは学問的に興味深いにすぎない。逆説派が常識派より高い得点を挙げられるのは、彼らが数のうえで、常識派にはるかにまさっているときに限られるからだ。そもそもこの状態が最初にいかに生じるかを想像するのは難しい。たとえそれが生じたとしても、個体群内の逆説派に対する常識派の割合がほんの少し増すだけでもう一つのESS、すなわち常識派のESSの「誘因域」に入り込んでしまうだろう。誘因域というのは、この場合なら常識派が有利になるような個体群比率の集合と定義される領域である。つまり、ある個体群がこの誘因域に達すると、常識的戦略の安定点に向かっていやおうなく引き込まれるのだ。自然界に逆説的ESSの例を見つけるのは心動かされるものの、ほんとうにそれを期待できるのかどうかははなはだあやしい(私は少々早まったようだ。この文を書いたあとで、私はメイナード=スミス教授から、J・W・バージェスがメキシコ産の社会性のクモOecobius civitasの行動について次のように書いていることを聞いた。「このクモは何かに妨害されて隠れ場所から追い出されると、岩の上をつっ走り、身を隠すことのできる空いた割れ目が見つからないと、同種の別の個体の隠れ場所に逃げ込む。侵入者が入ってきたときに、そこに先住者のクモがいると、そのクモは侵入者を攻撃しないで逃げ出し、新たに自分の隠れ場所を探す。このため、いったん最初のクモが追い出されると、次々と巣の持ち主の入れ替えが起こり、それが数分も続いて、しばしば、その集団の大部分の個体が自分の住処からよその住処に移らされることになる」おれは一五二頁に述べた意味で逆説的である)。 もし動物が過去の闘いのことを記憶していたらどうか? それは、その記憶が個別的なものか、一般的なものかによって異なる。コオロギは過去の闘いで起こったことについて一般的な記憶を持っている。最近多くの闘いで勝ったコオロギはタカ派的になる。最近負け気味のコオロギはハト派的になる。これはR・D・アレグザンダーによって見事に示された。彼は模型のコオロギを使って本物のコオロギを奇襲した。この処置を加えたあとでは、そのコオロギは他の本物のコオロギとの闘いに負けやすくなった。各々のコオロギは、自分の個体群内の平均的個体の戦闘能力と比較しての自分の闘いに負けやすくなった。各々のコオロギは、自分の個体群内の平均的個体の戦闘能力と比較しての自分の戦闘能力を、たえず評価しなおしているものと考えられる。過去の闘いの記憶を用いるコオロギのような動物が、ある時間密集した集団を成して過ごすと、ある種の順位制が発達するようだ。観察者は各個体を順番に並べることができる。順位の低い個体は順位の高い個体に降伏する傾向がある。個体どうしが互いに認知しあっていると考える必要はない。勝つことに慣れた個体はますます勝つようになり、負けぐせのついた個体は決まって負けるようになるというのが現象のすべてである。はじめはまったくでたらめに勝ったり負けたりしていても、おのずとある順位に分かれていく傾向があるのだ。これには、集団内の激しい争いを次第に減らしていく効果がある。 以上のような現象は、「一種の順位制」とでも言わなければなるまい。というのは、順位制という言葉を、個体の認知がなされている場合にしか使わない人が多いからだ。その場合には、過去の闘いの記憶は一般的というより個別的である。コオロギは互いに相手を個体として認知してはいないが、ニワトリやサルは認知している。あるサルにとって過去に自分を負かしたことのあるサルは、将来も自分を負かす可能性が高いだろう。この場合、個体にとって最高の戦略は、以前に自分を負かしたことのある個体に対しては、比較的ハト派に振る舞うことだ。以前に出会ったことのない一群のニワトリを引き合わせると、普通はやたらにけんかが起こる。だが時が経つと、やがてけんかは下火になる。しかし、それはコオロギの場合と同じ理由からではない。ニワトリの場合には、各個体が別の個体に対する「自分の地位を学ぶ」からだ。これはたまたま集団全体にとっても都合が良い。その証拠として注目されているのは、順位が確立していて激しい闘いがめったに怒らないニワトリの集団ではたえずメンバーが入れ替わっていて、その結果しょっちゅうけんかしている集団よりも産卵率がはるかに高いことだ。生物学者はよく、順位制の生物学的利点ないし「機能」は集団内の公然の攻撃を減らすことにあるという。しかし、これは説明のしかたとしては正しくない。順位制それ自体は、進化的な意味で「機能」を持っているとは言えない。なぜなら、それは集団の特性であって、個体の特性ではないからだ。集団レベルで見たときに順位制の形で現れる個体の行動パターンには、機能があると言えるかもしれない。しかし、「機能」という言葉をまったく捨てて、個体認知と記憶という二つの条件を加味した非対称な争いにおけるESSという点からこの問題を考えたほうが、はるかに良い。 以上、同種の個体間の争いについて考えてきたが、種間の争いについてはどうか? はじめに述べたように、異種のメンバーは同種のメンバーに比べると、それほど直接的な競争相手ではない。このため、異種間に資源をめぐる争いがおこることは少ないと考えられるし、この予想には確証がある。たとえば、ロビンは他のロビンに対してなわばりを守るが、シジュウカラに対しては防衛しない。ある森の数羽のロビンのなわばりを地図上に示し、その上に数羽のシジュウカラのなわばり地図を重ねて描いてみると、この二種のなわばりはまったく無規則に重なっている。彼らは別々の惑星に住んでいるようなものなのだ。 だが、ある場合には、別種の個体間の利害がかなり激しく衝突する。たとえば、ライオンはアンテロープの体を食べたがるが、アンテロープは自分の体についてまったく別の計画をいだいている。これは、普通は資源をめぐる争いとは認められないが、論理的に言えば、なぜ認められないのか理解し難い。この場合の資源は肉だ。ライオンの遺伝子は自分の生存機械の食物として肉を「ほしがっている」。アンテロープの遺伝子は自分の生存機械のために働く筋肉や機関としてその肉を必要としている。この二つの肉の用途が互いに相容れないため、利害の衝突が起こる。 自首のメンバーもやはり肉で出来ている。では、なぜ共食いが比較的まれなのか? ユリカモメの例で述べたように、おとなはときおり自種の子どもを食べる。だが、おとなの肉小銃が、自種の他のおとなの個体を食べようと積極的に追いまわすことはありえない。なぜないのか? 私たちはまだ、進化の「種にとっての善」という見かたから考えるくせが抜けないので、「ライオンはなぜほかのライオンを狩らないのか?」というようなまったく妥当な質問を忘れがちだ。もうひとつ、めったに訊かれないタイプの鋭い質問を以下に記す。「アンテロープはなぜ反撃しないでライオンから逃げるのか?」 ライオンがライオンを狩らないのは、そうすることが、彼らにとってESSではないからだ。共食い戦略は、先の例のタカ派型戦略と同じ理由で不安定である。報復の危険があまりに大きいのだ。だがこのことは、異種間の争いにはあまりあてはまらないように見える。獲物の動物がたいてい報復せずに逃げるのはそのためだ。これはおそらく、別種の二個体間の相互作用においては、同種のメンバー間の場合より大きな非対称が組み込まれているという事実に根ざしている。争いに大きな非対称がある場合には、ESSは常にその非対称に依存した条件戦略となるようである。別種間の争いでは利用できる非対称がたくさんあるため、「小さければ逃げろ、大きければ攻撃しろ」といったたぐいの戦略がたいへん進化しやすい。ライオンとアンテロープは、争いにもともと存在する非対称が絶えず増大するように強調してきた進化的放散によって、一種の安定状態に達している。彼らはそれぞれ、追いかける手腕と逃げる術策において、高度に熟練するに至っている。ライオンに「立ち向かう」戦略を取る突然変異のアンテロープは、地平のかなたに姿を消しつつあるライバルのアンテロープよりうまくいかないはずだ。 私たちは、ESS概念の発明を、ダーウィン以来の進化論における最も重要な進歩の一つとして振り返るようになるだろう。この概念は利害の衝突のあるところならどこでもあてはまる。つまりそれは、ほとんどあらゆる場面に通用する。動物行動の研究者は、「社会組織」と呼ばれるものについては、ほとんどあらゆる場面に通用する。動物行動の研究者は、「社会組織」と呼ばれるものについて語るのが習慣になっている。社会組織は、自らの生物学的「利点」を備えた独自の実体として扱われることがあまりに多い。これまでに挙げた例で言えば、「順位制」がそれに当たる。生物学者が社会組織について述べた数々の説の背後には、かならず群淘汰主義者の仮説が隠されていることを私は疑わない。メイナード=スミスのESSの概念こそ、独立した利己的な単位の集まりがどのようにして単一の組織された全体に似てくるようになるかを、初めてはっきりと教えてくれるだろう。このことは種内の社会組織ばかりでなく、多くの種から成る「生態系」や「コミュニティ」についても言えると思う。ESSの概念は、いずれ生態学に革命をもたらすはずだと私は期待している。 この概念は、第3章で述べた、良いチームワークを必要とするボートの選手(体内の遺伝子にあたる)の例で生じた問題にも適用できる。遺伝子は、それ単独で「優れたもの」としてではなく、遺伝子プール内の他の遺伝子を背景にして働く際に優れたものとして淘汰に残る。優れた遺伝子は他の遺伝子と両立し、補足し合って、何世代にもわたって体を共有していくものでなければならない。植物をすりつぶす葉の遺伝子は、草食動物の遺伝子プール内では優れた遺伝子だが、肉食動物の遺伝子プール内では悪い遺伝子だ。 両立しうる一組の遺伝子は、一つの単位としてまとめて淘汰にかけられるものと考えることができる。第3章のチョウの擬態の例の場合には、まさにそうなっていたように見える。しかし、ESS概念の素晴らしさは、純粋に独立の遺伝子のレベルの淘汰によって、同じような結果がもたらされることを理解させてくれる点だ。遺伝子どうしは同じ染色体上で連鎖している必要はない。 ボート選手の例は、じつはこの点を説明するのには適さない。この点に最も迫れるのは、次のような例である。実際にレースに勝つには、クルーの選手どうしが言葉を交わして、自分たちの活動を調整することが大事だとしよう。さらに、コーチが自由にできる選手プールでは、ある選手は英語しか話せず、ある選手はドイツ語しか話せないものとしよう。イギリス人が常にドイツ人より漕ぐのがうまかったり、へただったりするということはない。だが、コミュニケーションが重要なので、混合のクルーは、イギリス人やドイツ人ばかりで統一されたクルーのボートにはなかなか勝てない。 コーチにはこのことがわからない。彼はただ、自分の選手をでたらめに混ぜて、勝ったボートに乗っていた選手に点を与え、負けたボートに乗っていた選手から点を引く。ところが、彼が自由にできる選手プールにたまたまイギリス人が多いと、ボートに乗り込むドイツ人はコミュニケーションを妨げるため、そのボートが負ける原因になりがちだ。反対に、選手プールにたまたまドイツ人のほうが多いと、イギリス人が、その乗り込んだボートを負けさせる原因となる傾向がある。総合的に最良のクルーができあがるのは、二つの安定状態の一つになるとき――つまり、全員がイギリス人か全員がドイツ人であって、混ざっていない状態だ。それは表面的には、あたかもコーチが言語別のグループを単位として選んでいるかのように見える。だが、彼はそうしているわけではない。彼は、レースに勝つ外見上の能力で一人一人の選手を選んでいるにすぎない。ある選手がレースに勝つ傾向は、たまたま候補者のプールに他のどの選手がいるかによる。少数派の候補は、自動的に罰を受けるが、それは漕ぐのがへたなためではなくて、単に彼らが少数派なためにすぎない。同様に、遺伝子が互いに両立できるために選択されるという事実があるからといって、チョウの例に見られたように、遺伝子の集団が単位として選ばれていると考えなければならない理由は必ずしもない。単一の遺伝子という低レベルの淘汰が、もっと高いレベルでの淘汰という印象を与えることもある。 この例では、淘汰は単なる適合性を選んでいる。さらに興味深いのは、互いに補い合う遺伝子が選ばれる場合だ。たとえて言うなら、理想的にバランスの取れたクルーは、右利き四人と左利き四人から成るものとする。この場合もまたコーチはこの事実を知らず、やみくもに選手の「成績」を基準にして選ぶものと仮定しよう。ところが、選手プールにはたまたま右利きが多く、左利きの選手はみな、どちらかというと有利な状態にある。すなわち、彼は自分の乗っているボートを勝たせる傾向があるので、優秀な選手に見える。反対に、左利きの多いプールでは右利きが有利なはずだ。これはハト派の個体群内で成功するタカ派の個体や、タカ派の個体群内で成功するハト派の個体の場合と同様のこと。違うのは、ハト派とタカ派の例は個体間の、つまり利己的な機械間の相互作用の話だが、この場合は体内の遺伝子間の相互作用の話だという点である。 コーチがやみくもに「優れた」選手を選んでいっても、いずれは左利き四人と右利き四人から成る理想的なクルーができあがる。それは、あたかも彼がバランスの取れた一揃いの単位として彼らをそっくり選んだかのように見える。しかし私の考えでは、彼は一つ下のレベルで、つまり個々の候補のレベルで選択していると考えたほうが、明快ですっきりする。左利き四人右利き四人という進化的に安定な状態(ここでは「戦略」という言葉は誤解を招きやすい)は、単に、外見上の成績に基づいた低レベルでの淘汰の結果としてもたらされるものだ。 遺伝子プールは、遺伝子の長期的な環境である。遺伝子プール内で生き残ったものであれば、何であれそれが「優れた」遺伝子だ。これは理論ではない。観察された事実ですらない。同語反復になってしまう。興味深い問題は、遺伝子が優れているというのは、有能な生存機械、すなわち体を作る能力のことだと書いた。しかしいまや、この見解には以下に述べるようなただし書きを付ける必要がある。遺伝子プールは進化的に安定な遺伝子のセット、すなわちどんな新遺伝子にも侵入されることのない遺伝子プールと定義される状態に達するだろう。突然変異や組み換えや移入によって生じる新しい遺伝子は、大部分が自然淘汰によって罰を受け、進化的に安定なセットが復元される。ときおり、ある新しい遺伝子がそのセットに侵入することに成功し、遺伝子プール内に広がっていくのに成功することもある。すると、不安的な過渡期を経て、やがて、新たな進化的に安定な組み合わせに落ち着く――ほんのちょっとだけ進化が起こったのだ。攻撃の戦略の例で述べたように、個体群には二つ以上の代替可能な安定点があり、ときおり一方から他方への突然の飛躍が起こることがある。進化とは、たえまない上昇ではなくて、むしろ安定した水準から安定した水準への不連続な前進の繰り返しであるらしい。あたかも、その個体群全体は一個の自動調節単位のように振る舞っているかに見えるだろう。しかし、これは錯覚だ。それは実際には、単一の遺伝子のレベルで起こる淘汰によって生じている。遺伝子は「成績」で選ばれる。だがこの成績は、進化的に安定なセット、すなわち現在の遺伝子プールという背景のなかでの振る舞いに基づいて判定される。 メイナード=スミスは、まるごとの個体のあいだに見られる攻撃的相互作用に焦点を合わせることによって、事態をきわめてはっきりさせることができた。タカ派とハト派の体の安定な割合を考えるのはやさしい。体は大きな物体であって、目で見ることができるからだ。しかし、別々の体に宿る遺伝子間のこのような相互作用は氷山の一角にすぎない。進化的に安定なセットのなかの、つまり遺伝子プール内での遺伝子の重要な相互作用の大部分は、個々の体のなかで行われる。これらの相互作用を目で見るのは難しい。それらは細胞内で、とりわけ発生中の胚の細胞内で起こっているからだ。よく統合された体が存在するのは、それが利己的な遺伝子の進化的に安定したセットの産物だからである。 ともあれ、この本の主要なテーマである動物個体間の相互作用のレベルに話を戻さなければならない。攻撃を理解するには、個々の動物を独立した利己的な機械と見なすと都合が良かった。しかしこのモデルは、関係する個体どうしが、兄弟姉妹、いとこどうし、親子といった近親者の場合にはあてはめられない。なぜなら、近親個体どうしが彼らの遺伝子のかなりの部分を共有しているからだ。それゆえ、個々の利己的な遺伝子の忠誠心は、別々の体に分配されている。これについては次章で説明する。 メイナード=スミスの分析法に従って、ここでも「戦略」という言葉は、やみくもに動く無意識的な行動プログラムを指している。ここで雌の二つの戦略を、「恥じらい」型と「尻軽」戦略、雄の二つの戦略を「誠実」型と「浮気」戦略と呼ぶことにしよう。これら四型の行動規律は以下のとおりである。恥じらい型の雌は、雄が数週間にわたる長くて高価な求愛をしなければ彼と交尾しない。尻軽型の雌は、誰とでもただちに交尾する。誠実型の雄は長期間求愛を続ける忍耐力があり、交尾後も雌のもとに留まって子育てを助ける。浮気型の雄は、雌がただちに交尾に応じなければたちまちしびれを切らせ、その雌を棄てて別の雌を探しに行く。交尾後は雌のもとに留まって良き父親役を演ずることはなく、新しい雌を求めて去ってしまう。ハト派とタカ派の分析例と同様、考えられる戦略は何もこの四型には限られないが、これららの戦略の挙動を追ってみることは問題の解明に役立つはずだ。 メイナード=スミスに従って、それぞれの代価と利得に仮説的数値を与えておくことにしよう。一般的な扱いをしようと思ったら、それらに代数的な記号を与えておくべきなのだが、数値を使った方が理解しやすいだろう。子どもが無事に育った場合、それぞれの親の得る遺伝的利得を(+)15単位としよう。子どもを育てるための代価、すなわち食物、世話に要する時間、子を守るために親の冒す危険のすべてを合算したものは(-)20単位とする。代価は親が支払わなければならないものなので、負の数で表現する。長い求愛で時間を浪費する代価も負になり、この代価を(-)3単位としておこう。 今、恥じらい型の雌と誠実型の雄だけで構成される集団を考えてみる。理想的な単婚社会だ。いずれの夫婦においても、子ども一頭を育てるごとに雌雄はともに同じ平均利得、すなわち(+)15単位を手に入れる。子育ての代価(-)20は等分に分担されるので、雌雄はそれぞれについて平均(+)10単位が引かれる。長い求愛に費やされた時間の代価(-)3単位がさらに雌雄それぞれに課されるので、雌雄それぞれについての最終的な平均利得は(+)2単位(+15-10-3+2=2)となる。 さて、この集団に尻軽型の雌が一頭入り込んだとしよう。彼女の成績は抜群だ。長い求愛にふけることがないので、その分の代価を払う必要がないからだ。集団内の雄はすべて誠実型だから、誰と交尾しても相手は子煩悩な父親になると期待できる。子ども一頭当たりの彼女の利得は(+)5単位(+10-10+5)となり、恥じらい型のライバルより3単位も成績が良い。そこで尻軽型の遺伝子は集団内に広がり始める。 尻軽型の雌が大成功を収めて集団内で優勢になると、雄側に事態の変化が起こってくる。これまでは、誠実型の雄の独壇場だった。しかしここで浮気型の雄が集団中に登場すると、彼は誠実型のライバルより良い成績を上げ始めるのだ。もし集団中の雌がすべて尻軽型であれば、浮気型の雄の成績はじつに目覚ましいものとなる。子どもが一頭無事に育てば彼は(+)15単位を手に入れ、しかも代価のほうは二種類とも支払う必要がないからだ。この代価のないことが彼に与える主要な利益は、そのおかげで彼が気ままに雌を棄てて新しい雌と交尾できる点にある。不運な妻たちは、いずれも子育てに孤軍奮闘しなければならない。求愛時間の浪費のための代価を払う必要がないとはいえ、彼女は子育てのための代価(-)20単位をすべて自分で払う必要があるのだ。尻軽型の雌が浮気型の雄に遭遇した場合、彼女の利得はさし引き(-)5単位(+15-20=-5)になってしまう。一方、浮気雄はそれによって(+)15単位も手に
0投稿日: 2025.04.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆信州大学附属図書館の所蔵はこちらです☆ https://www-lib.shinshu-u.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BB25562930
0投稿日: 2025.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ朝日新聞globe+に生物学者の方が「生命進化の歴史は利他的な助け合い」との記事を寄稿。頭に浮かんだのが、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」。積読から開放。 この著書により心が震わされた箇所が複数ある。 まず、ドーキンスは前提として進化に基づいた道徳を主張するつもりではない。「氏か育ちか」論争における何らかの立場を主張するものではない。人間の行動やその他の動物の行動の詳細を記載したものではない。と断り、”遺伝子の利己性”と呼ぶ基本法則によって、個体の利己主義と個体の利他主義がいかに説明されるかを示してくれる。 遺伝子の利己性理論は遺伝子プールの考え方を根底とする。すなわちありとあらゆる物質の素が原始スープの中で雷や太陽光などの化学反応によって突然変異をおこす。必要な物質を奪い合い消費しまくるので、どこかで行き詰まるが、また安定した状態から、突然変異により新たな安定的な物質が生まれる。その環境に適応した物質が急増していく理論(今のところ自分で説明できる範囲) ×群淘汰 ×個体淘汰 ◯遺伝子淘汰進化論的アプローチ 進化的に安定な戦略ESS(エボリュジョナリー ステーブル ストラテジー) 著者は否定するが世界のスタートがどこか、ヨガの世界とつながって見える。 自己複製子が自然淘汰に打ち勝つ3大要因 →長生き、多産性、正確さ コイルの不滅 遺伝子結合体はもろいが遺伝子は何代も続く 有性生植 減数分裂 46個の染色体をもつ細胞→23個の染色体をもつ生植細胞になる 混合のメカニズム 精子(又は卵子)の製造中に、各父方の染色体の一部が物理的に離れて、母方の染色体のちょうどそれにあたる部分と入れ替わるつまりその精子には父母の(うまれる子供にとっては祖父母の)遺伝情報が含まれる。 「交叉」 染色体の一部を交換する過程の事 =不滅の遺伝子 100億年生きてる この先も生き続ける 何代も受け継いできた遺伝子。一人じゃない。なんて幸運なんだ!(←震えポイント) 私たちは遺伝子の生存機械として生きている。 自然淘汰による進化というダーウィンの進化論に納得がいくのは、単純なものが複雑なものに変わりうる方法を、すなわち、無秩序な原始が自ら集まっていっそう複雑なパターンを成しついには人間を作り出した方法を示してくれるからとする。 意識とは、事実上の決定権を持つ生存機械が、究極的な主人である遺伝子から解放されるという進化傾向の極地だと考えることができる。 私たちは子どもたちに利他主義を教え込まなければならない。子どもたちの生物学的本性の一部に、利他主義が組み込まれていることを期待することは出来ない。 具体的な淘汰の例をいつくも出しながらすすみ、 終盤にあらたな概念「ミーム」を生み出す。(←いまのミームってここから来てたのか!) ミーム(新たな自己複製子)=人間をめぐる特異性の「文化」。言語は、非遺伝的な手段によって「進化」するように思われ、しかもその速度は、遺伝的進化より格段に速い。 人間の脳は、ミームの住みつくコンピューターである。 この考えは歴史学者ハラリなど他分野の学問にも影響を与えていそう。 この「ミーム」と最終章「遺伝子の長い腕」まで読むと、現存する全ての物質が一つにつながった。(←震えポイント) ドーキンスは「遺伝子の効果は個体の身体の形や行動だけでなく、環境に及ぶ」ことを指して「延長された表現型」と呼ぶ。ビーバーのダムや寄生虫が操る宿主行動のように、遺伝子の“影響”が個体外にも現れる、と考えたのだが、それの終着点がAIだとするのは行き過ぎた考えだろうか。 表面的にしかわからずパッと見とイメージで勘違いされ叩かれる”利己的な”の凄みを知り古典的名著とされる理由がわかった。 ブワーって羅列備忘録として書いたが もう一度冒頭の記事を読んでこよう。 うん、やはりちょっとズレていた。
12投稿日: 2025.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
遺伝子とは何だろうか。DNA?生命の設計図?子どもが親に似ている理由?どれも正しいが、ドーキンスの洞察はその先を行く。彼に言わせれば、遺伝子こそが生命の本質で、私たちの身体は遺伝子の乗り物に過ぎない。 異星人であれ、コンピューターの中の生き物であれ、生命が生命的であるためには遺伝子が必要だ。しかも、その遺伝子は利己的に振る舞う。遺伝子のなかに利己的なものがいるという意味ではない。遺伝子である以上、利己的である必要があるのだ。 40年を経てもなお斬新な視点。生命や進化に興味のある人は必読の書。
1投稿日: 2025.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ最も基本的な単位は遺伝子 遺伝子は外部にも影響を及ぼす 利他的な行動は翻れば至極利己的になる(種全体からの視点なら)
0投稿日: 2025.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログリチャードドーキンス先生の名著。 面白いが和訳されたためなのか文が難解で読みにくい。 1/3ぐらい読んだ。
0投稿日: 2025.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれが1970年代に書かれていたなんて、今まで読んでいなかったのが恥ずかしい。 ミトコンドリアは元々別の生物だったのを取り込んだ説は、たしか生物の授業で聞いた覚えがある。現代人にとっては全く突拍子のない話ではない。 生物は遺伝子にとって生存機械(乗り物)であり、その生き残りのために行動し、生殖している。遺伝子は都度命令を下す支配的な指揮官ではなく、太古の昔から情報を淘汰し組み替えてきたベテランプログラマーだ、というお話。 ※この本で何度も出てくる「淘汰」は弱いものが削がれるのではなく、必要なものが残っていく意味合い(最後の解説で「だよねー」となった)。 親から子への美しい無償の愛も、遺伝子の近縁度を考えると論理的に説明できる。母の愛と父の愛が異なるのも、母の遺伝子は必ず50%受け継がれているが、父の遺伝子はもしかしたら別の男性の遺伝子の可能性もなくはないためだ。 先日の贈与の本然り、利他的な行動や感情の意味が知りたいお年頃の私には、これまた興味深い本だった。やっぱ利己的やん!これはかなりしっくりきた。いいねいいね。母方の叔父は今もほんとに優しいんだよね。 DNA鑑定をしたら、父の愛も母の愛に近いものに変わるのかな?鑑定できる未来は遺伝子さんのプログラム外かもしれない。追加調査求む。 真理とは方程式だ。遺伝子とその距離を考えることで、人間に限らぬ生物の行動原理がわかるなんてめちゃくちゃ面白い。 そしてさらに面白いのが、その方程式だけではまだまだ人間の脳や感情には説明がつかない部分があること! 人間とは何か。人間が人間であるうちは、一生答えには辿りつけないかもしれない。第三の人類かAIが解き明かしてくれるかな。
4投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024年12月31日、グラビティの「みつける」に投稿されてた画像がこの本だった。「Amazonとかで本を買うやん?表紙しかわからんやん?いざ届いたら、分厚くて驚くことない?」
0投稿日: 2024.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ想像以上の密度だったが、題材に加え文章も非常に面白いため飽きずに読み通せた。素晴らしいの一言。 本書のことは、既に今まで読んできた色々な本の中で参照・引用されていて、そのマスターピースぶりは理解していたが、読んでみて改めて多くの刺激を貰えた。 社会には多くの対立がある。 その原因は「大衆vs大衆」の構図であれば宗教や領有権の対立であったりするし、クローズアップすれば人と人との意見のすれ違い、例えば夫婦喧嘩だったりもする。 そういった多くの対立の根源が、遺伝子における飽くなき戦いの延長上にあることを知れる。 私の興味の深い分野でいえば、男女間の思考の違いを理解するのに非常に役立った。 男としては、結婚したパートナーのことが嫌いでなくても、他の異性に対し身体的関係性を持ちたいと思うことが自然だ。 ゴシップニュースを見ても、妊娠・出産期の、妻がまさに命の瀬戸際のような状態にあるタイミングですら夫が不倫をするという例に事欠かない。 また、子供に対する愛がないわけではないのに、母親と父親の間には温度差があったりもする。 こういった、同じ人間であるというにはあまりにも対照的な男女間の思考・感情の違いというものが解明される。 人間の平等における議論をするのであれば、本書を抜きにしては話が進まないと言ってすらいいだろう。これは男女平等はもちろん、人種差別問題であったり、更に広げれば格差問題にも応用が利きそうだ。 また、信仰・宗教に関する論議でも、この知見がベースにあるかどうかで話が180度変わるに違いない。遺伝子学なしで宗教を論じるのは、生産性皆無の不毛な机上の空論になってしまうように思う。それくらい、本書は世界に対する大きなインパクトがある。 ダーウィンの『種の起源』のように、私が知らないだけで、実際には多くの知見がグラデーション状に登場しているのだろうが、本書を読んだ私としては、本を読んだ以前以後でラインを引けるくらいの大きな変化があったように思う。『資本論』、『銃、病原菌、鉄』、『ホーキング、宇宙を語る』のように。
2投稿日: 2024.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ数年前に読了。 今の自分を形づくる大切な「教科書」です。 生物にのめり込むきっかけにもなったし、今の進路に行き着いたのも思い返せば本書かもしれません。
4投稿日: 2024.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分はどこまで自分なのだろう? と思いながら最終章を読み進めていたら 「自分はどこまで自分なのだろう?」と思っているのは何なんだ?と何ともいえない気持ちになった。 哲学的な問いに科学で迫る名著でした。
0投稿日: 2024.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しいので完全には理解できてないが、この本のおかげでジャレドダイヤモンドの本が読みやすくなったのは間違いない
0投稿日: 2024.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ序盤の遺伝の話は、あぁこういうのあったなぁと高校の生物思い出した。 生物が遺伝子の生存機械という考えは、非常に興味深く感じた。 その後の攻撃や家族計画、世代間の争い、雄と雌の争いなど、実際の生物の具体例をもとに説明があり、理解に役立った。しかし、難しかった、、ちゃんと読まないと理解できないね(読んでも理解できないところもたくさんあるが) あまり考えたことがなく、触れない分野を学べたことがよく、人間の生物学的な本質の見方がすこしわかり、楽しかった。 ただ、本が分厚い、気合い入れて読まないとダメだった、、笑
0投稿日: 2024.08.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ久々のヒット❗ 原始の化学物質のスープの中で自己を複製するものが登場し、複製ミスで多様化し、より複製して増殖しやすい形質の物質が増加する競争状態となり、他の物質を取り込むものやそれから守るための防壁を設けるものが現れ、ついには現在のような複雑かつ大規模に連携し合うシステムとしての生物に進化したが、進化の本質は偶然と環境による遺伝子間の意思なき競争であり、その単位は生物個体ではなく遺伝子であるとする。 そして、生命の本質は、遺伝子のような自己複製子であり、他にもミーム(人間の思考や文化や芸術や発言)などが、生存と複製と適者生存が適用される自己複製子として存在しているとする。 他にもいろいろあるように感じた。例えばゲームのクリア方法なんかも。 個体の生存ではなく遺伝子の増加こそが進化というレースの報酬として機能しているというのは目から鱗。
0投稿日: 2024.07.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ進化学が大好きで関連書を色々と読んでいたが、この有名な本を今まで「読まず嫌い」で来てしまっていた。有名すぎるために他の進化学の本で内容が取り上げられることが多く読んだつもりになっていた部分が大きいが、「極端な遺伝子還元主義」として批判的に扱われていたことに影響されていた部分もあると思う。 しかし今回ちゃんと読んでみて、思っていたよりも遥かに学術的な内容で、しっかりと読みごたえがある本だった。 この本の初版の時代に作者が「進化は遺伝子を単位として起こる」と主張したことは一般社会にも大きな影響があったと思う。 50年近くたった今でも進化がどうやって起こるのかということについて、まだまだわからない部分が多い。 進化の単位が「個体」か「遺伝子」かという争点自体が古い考え方になり、現代では進化がどうやって起こるのかという問題についてはもっとこみいった複雑な要素があるとわかってきている。 (例えば、ゲノムの水平移動、レトロトランスポゾン、ゲノム重複、細胞内共生、寄生体や腸内細菌叢の影響などなど) 今のこの流れに至るまで、ドーキンスが当時この本を出版した意義はとても大きかったと思う。 今回は進化学が好きなのにずっと避けていた本を生きているうちに読めて良かったし、内容も思ったより専門的で面白かった。今読んでも価値のある本だと思う。
0投稿日: 2023.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺伝子が自己利益を追う?生物学の常識を覆す刺激的な冒険へ!(吉田亘克先生) 日本大学図書館生産工学部分館OPAC https://citlib.nihon-u.ac.jp/opac/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=1000274341&opkey=B169881694713507&start=1&totalnum=1&listnum=0&place=&list_disp=20&list_sort=0&cmode=0&chk_st=0&check=0
0投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物を知る、人間を知るのとても興味深い本。 「自己複製子」と「ヴィークル」、「ミーム」という考え方に驚嘆した。
1投稿日: 2023.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わって、なんでもっと早く読まなかったんだろうかと思った。 自然淘汰の単位を種や群れではなく、遺伝子という視点からとらえて説明した歴史的な名著。 生物の行動や進化を遺伝子が生き残るという視点でとらえて、納得のいく説明をしてくれている。 よく本書に対して、道徳や倫理への冒涜かのようや批判を聞いたことがあるけれど、 そもそも、本書は道徳に対してなんらかの意見を加えるものではないことは、筆者自身が冒頭をはじめて、繰り返し述べられている。 本書の妙は、道徳とは関係のないところで、遺伝子の視点から人間を含めたすべての生物の進化を見ているところにあると思う。 本書を読み終えて思うのは、進化という歴史の中で、遺伝子がバリエーションを持って、様々な環境を経て、その中で生き残ってきた今があることのすばらしさだと思う。 生物学だけでなく、ゲーム理論からの影響を受けて、利他性の説明をしている章や、今やネットでは普通に使われる「ミーム」という言葉を提案している章など、社会科学とのつながりもある本なので、本当に読んでいておもしろかった。 読みやすい本なので、読んだことのない人は、抵抗を持たずに読んでほしい。
2投稿日: 2023.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わらなかった… 抽象的な書き回しで先に進めなかった。 人生の一冊になるよう、再チャレンジをいつかしよう。
1投稿日: 2023.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ視点が広がり、ものの見方が変わりました。 人生でコレ一冊といった本に巡り合えた幸せを感じています。 ドーキンス博士ありがとう。他の著書も読んで理解を深めたいとおもいました。 しばらく経ってからまた咀嚼するため読もうと思います。
1投稿日: 2022.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺伝子は自己複製子であり、私たちはその生存機械だという彼の主張は、頭の中で理解できても、なかなか腹落ちしない。限りない豊饒な生物多様性をこの理論で説明ができるのかもしれない。だが、人間は・・?私も単なる自己複製子が乗っている生存機械に過ぎないのか・・?遺伝学的にはそうなのかもしれないが、複製することなど二の次三の次で日々の生活に明け暮れている僕はいったい・・。やはり生存機械を中心に思考をめぐらす自分がここにいることに気づく。
1投稿日: 2022.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログうーむ。結局のところ、生命とは何か?って事が主題なのかな。そして、それは自己複製子であると言う事を長々と説明して来たと… 人だったり、鳥だったり、虫を例にして観察の記録やら、ゲーム理論を用いて説明が続きますが、人や鳥や虫の観察記録については、NHKスペシャルの様々な特集やらで今となっては、概要レベルでは周知のものが多いと思われ、個人的にはなんか聞いたことあるような話と言う感覚。(この本が出版された頃で、ここまで網羅的なものが存在しなかったのがこの本の凄さなのかも知れない) 生物と言う観点では「ボトルネックのある生活環を持つヴィークル」という言い方とか、西洋哲学では、スタートがあって終わりがあると言うベースの考え方がある中で、こう言う言い回しが新鮮だったのかもしれない? 東洋哲学では、円と言うか、ここで言う環にあたるのか、生と死が繰り返されて生命は続いていくと言った考え方があるけど、ベーシックな考え方の違いとかが評価を分けることもあるし… この本を読むべき人ってどんな人なんだろうかと考えてしまう… 学者にでもなろうとしている人向けなのだろうか。少なくとも、サラリーマンは除外して良い感じがする。この本だけで理解した気になれることはまずないので、周辺知識を補うための多数の本を読まないと行けない本と言う感じ。私が読んできた本の中にはあまり無かったのかも知れない。 40周年記念版への後書とかいれて、500ページ近い分量な上に、前半通じて難解な言い回しとかが多くて、難儀しました。
3投稿日: 2022.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にとっては難解だった。他の方のレビューを見ると理解されてる人が多そうなので、自身の読解力のなさに辟易する。また読み返せば理解できるかもしれないが、根気がない。しかし、要所要所理解できたところもあり、特に囚人のジレンマなどのあたりは面白く読むことができた。我々は結局、遺伝子のコントロール下に置かれているということなのかな。
0投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログわたしも含めて生き物はみんな遺伝子生産機械で、かつ遺伝子の乗り物。そう考えると日常のイライラや面倒なことがどうでもよくなる。気持ちが軽くなる。
0投稿日: 2022.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり抽象的で難解な内容だったが、生物の行動に対する理解が深まっていくのを実感した。特に雄と雌の対立についての章は、人間の恋愛についての示唆にも富んだ興味深い内容だった。人間の遺伝子的な決定論を理解できたことで、癒しの効果も感じた
0投稿日: 2022.06.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ開始: 2022/6/15 終了: 2022/6/28 感想 遺伝子中心の見方を提供しつつもそこから脱却しようとする人間の理性(脳)の可能性を教えられた。ゲーム理論、文化的側面にも話が広がり面白かった。
0投稿日: 2022.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022.02.26 昨年『自己組織化と進化の理論』を読んで以来、生物学についての興味を一層強くしたので、名著である本書を手に取った。 正直、読んだ後で世界の見え方が変わる。遺伝子の目線で生物の進化を説明することの明快さ。そして分かりやすさ。 血縁関係者間の遺伝子共有度の考え方、蟻は受精卵は全てメスになることなど、自然の凄さ、これらがプログラムされているという事実は驚愕だ。 そして、進化的に安定な戦略(ESS)。生存戦略を単純なパターン化して説明する明快さ。面白い。 なにより最も勉強になったのは、「囚人のジレンマ」を例にESSを説明する部分。 ある環境におけるESSは「やられたらやり返す」型である。これは妬みを持ち続けるのではなく、一度やり返したら過去を忘れてあげるのがポイント、という事実がかなり刺さった。人間は妬みを持ち続けてしまいがちで、これが泥沼化する要因である。「やられたらやり返す。でも一度きりだ」というのはこれからの人生で役に立ちそう。 この「囚人のジレンマ」、私とあなたの間でパイを奪い合うゲームではなく、胴元からいくらポイントを得るかというゲームであるというのが、青天の霹靂というか、これまでの対峙の概念をひっくり返される。離婚の調停が例として語られたように、泥沼化することで利得を得る第三者がいる。目の前の相手に囚われて、相手からいかに奪い取るかに思考を持っていかれがちだが、本当にすべきことは相手と協力して胴元からいかに奪い取れるかということなのだ。 この本を読み終わる頃にロシアによるウクライナ侵攻が始まってしまった。攻められてしまった時には、ESSではやり返さないといけないということになる。頭で分かっていても悲しい決断になる。 戦争とは本当に残酷である。 色々考えさせられる。 #戦争反対
1投稿日: 2022.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ長い本ですが、ずっと面白く、そこまで時間をかけず読み終わりました。 印象に残ったのは、生物は皆利己的な遺伝子によって支配されながら生きているが、だからといって我々がそのように生きる「べき」だというのは全くの間違いだということです。むしろだからこそ、我々は利他性を身につけていかなければならないというのは説得力のある言葉でした。そして、利他性を持っているのが結局得になるようですしね。
1投稿日: 2022.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログたまたま手にとった、2021年のニュートン9月号に紹介されていたので、読んでみた。門外漢にもわかりやすく書いてくれたみたいだが、むずかしい!読めないところは、申し訳ないが、飛ばして読んだ。 極論にはなろうが、自己複製することが目的であると考えると、肩の荷がおりるような気持ちになる。 人間や動物、植物の行動を解読するための一考になる。無知な私にとっては、かなり斬新で新鮮な考えを与えてくれる、貴重な本であった。
0投稿日: 2022.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ40年前、大きな衝撃を与え、独自の視点で生物の進化を捉えた作品 今となっては比較的この本で示された考え方が浸透されてきた感じがあるので、衝撃があるとは言い難い 生物学にあまり詳しくない人が読めば新鮮に感じ、詳しい人が読めばこの考え方の元となる理論や思考を辿ることで納得感が深まっていく 著者の主張が一貫しているため、わかりやすくはなっているが長文でじっくりとその主張が繰り返されるため、途中で飽きが来てしまうのでのんびり読むのが良い ライオンの話やミームの話は特に興味深かった
0投稿日: 2021.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物の個体は、自己を複製し存続するために動くという点で利己的な遺伝子によって動かされている。 文化伝達の単位のミームは、DNAよりも早く伝播する。 人間が持ち得る新しい自己複製子
0投稿日: 2021.07.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・生物とは、遺伝子が自らを外敵から守るために築き上げた「生存機械」 ・「ミーム」は文化的伝達の単位であり、遺伝子のように、自己複製を繰り返していく性質を持つ。 ・遺伝子は、自分自身のコピーに対しては、他の体にいる場合であっても援助を惜しまない。個体レベルで見たら他人を助けたり、子供を助ける行動も、遺伝子レベルで見たら生存のための戦略
0投稿日: 2021.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ遺伝子が存続しやすい環境を維持発展するよう生物はプログラミングされており、それこそが生物の究極的な生きる目的
1投稿日: 2021.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はリチャード・ドーキンス博士の古典的名著。 生物の遺伝子がどのように進化していったかが論じられている。 数年前に一度手に取ったのだが、その時はあまりに自分の知識のなさとじっくりと読める時間がなかったために挫折した。 しかし、今回は以前比べ多少の知識武装(笑)をし、年末年始の休みを利用して、時間もそこそこあったので読了することができた。 このような学術書というのは、年数が経つとその理論や主張が時代遅れとなったり、新しい理論が生まれ、主張が間違っていたことが判明するなどしてほぼ古い物は読まれなくなるのだが、本書は題名でも分かるように40年以上前に書かれたもので、その主張はまだ色あせていない。 数多く学者からも引用されている本書である。 遺伝子学の基本書として読んでおいて損はなかった。
27投稿日: 2021.01.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ30年前に話題になっていたけど読むことがなかったなと、本屋で手に取ると40周年記念とある。あれおかしいなと思いつつ購入して正月に読書に耽った。何となく概要を知っているつもりだったが、読んでみると誤解していることも多くて、今読んでも全く色褪せないというか新鮮な驚きが沢山あった。ただ丁寧に論説していく内容なので、隙間時間で読めるような本ではないようだ。だが多様な遺伝子か発生したと思われる原初の生命スープを創造するとなんだか壮大な歴史の旅に出たような不思議な気持ちになった。全ての章を読み終わり訳者後書きを読むと最初の謎が解けた。日本で出版された当初は全く違うタイトルで、10年後に原題の通りのタイトルで出版すると一気に世間で話題になったとのこと。なんかスッキリした。
0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史的名著とされるが、ちょっと情報が古い部分がある。著者もあとがきで触れているが。 「実証」の不可能な進化論について、遺伝子の自己複製という基本原理から思考を組み立てて、鮮やかに論じて見せる。ただし、「利己的」という言葉すら比喩であるということは理解しておくべし。
0投稿日: 2020.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログかつてのベストセラーが40周年記念版として蘇る。 藤井太洋氏が紹介されていたのを見て、読みたくなり、図書館で手に取る。 かなり分厚くて読み始めは躊躇していた。 私たち生き物がどのようにプログラムされているのか、どうすれば子孫を残せるかという命題を賭けてありとあらゆる戦略が用意されて試され続けてきた結果が今なのだ。目の前の小さな不幸に一喜一憂しているのがバカらしくなる。コロナ騒ぎも宇宙や地球の営みの中では、通過儀礼なのだろう。ヒトの多くはいつまでも傲り過ぎに気づけないままなのだろう。
0投稿日: 2020.11.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人間は、遺伝子の乗り物にすぎない❗」 衝撃的で、めちゃ面白いです。 ぜひぜひ、読んでみてください。
2投稿日: 2020.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020.8.4 読了 人間の生存戦略的なモノをマクロ的に知りたいと思って読み始めたが、、、、クソ長い。 辞書ぐらいあるページ数を蛇のように論が展開する中で読まされた感じ笑 論文をまとめてある形だから昆虫や他の動物に対する数多くの考察がなされていて面白いとは思うが話の脱線が半端ない。 ダラダラ読む読み物としては充分楽しめるはず。 内容については、人間という自己複製の器の観点から論じてある部分が非常に明快だった。 自分がどう生きるか的な部分には関わりはないが、「人間って結局こうだよなー」的な部分の諦観は得られるのではないだろうか。 ゆっくりした時に読み直したい。
0投稿日: 2020.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『利己的な遺伝子』要約 ■要点1 生物は利他的に見える行動をとることがあるが、それが自らの遺伝子の生存に有利に働くからである。 ■要点2 生物とは、遺伝子が自らを外的から守るために築き上げた「生存機械」に他ならない。 ■要点3 生存機械は、多様の遺伝子を含んだ「乗り物」のようなものだ。遺伝子は生存機械を乗り捨てて行きながら、自らのコピーを次々と広めていく。 ■要点4 「ミーム」は文化的伝達の単位であり、遺伝子のように自己複製を繰り返していく性質を持つ。 ■要点5 将来を予測する能力を持つ人間だけが、利己的な自己複製子に立ち向かうことができる。
0投稿日: 2020.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかったが、読むことができてよかったと思う本だった。遺伝子レベルで見ると、なぜ利己的な遺伝子なのかということがわかった。 家族や同族に対する生存機械の行動が、利己的な遺伝子によるものだと納得するなど、この視点から見るといろいろなものが説明できる。
0投稿日: 2020.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
なんとなく、タイトルが気になり読んでみた。1回だけだと輪郭もつかめなかった。タイトルに引っ張られて読んだほうがいいのか、どうか。
1投稿日: 2020.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる人にとって必読書だと思う。 ヒトを含む生物がどうしてそういう行動を取るのか、理解する助けにもなる。 例えば、男性は女性と違って必ず浮気をするものだとよく言われるが、必ずしもそういうわけではないということも理解できるようになると思う。
0投稿日: 2020.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ旧版を読んだことがあるので2回目. 生物は遺伝子の乗り物. その遺伝子が繁栄することと,その乗り物である生物が生存したり幸福であったりすることは全くの別問題. (遺伝子目線では自死を選んだ方が,自分と同じ遺伝子を一定割合持つ母親や兄弟を生きながらえさせた方が繁栄する) しかし人間という乗り物は発達した脳という機関により運転手に背くことができる(=避妊具の使用)
0投稿日: 2020.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日進月歩の新発見が続く進化と遺伝に関し,40年も前の本がいまなお再版され続け影響力を保っているという単純な事実が驚きである。 自然淘汰とはいったい何なのかについて,ベースの部分で気づきを与えてくれる本。 各論では,最初の自己複製子は現存するDNAとは限らないこと,アリやハチのような社会性生物の議論,裏切り者に関する議論がおもしろかった。
0投稿日: 2020.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ生物は生存機械に他ならないって結構ショッキングです。利他的な行動は遺伝子の生存に有利だから。 現在の遺伝学者はどういう見解なんだろう。
0投稿日: 2020.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ生き物っていうのは遺伝子を運ぶための乗り物なんだと。そして人が利他的に振る舞うのも、そうした方が自分の遺伝子を残しやすいからなんだと。 ドーキンスも人が悪いよね。まるで『人間は遺伝子のためだけに生きている』みたいな書き方するんだもん(よく読めば違うことはわかるけど)。 はじめて読んだときはショックだったけど、示唆を与えてくれた重要な本。
1投稿日: 2019.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ利己的な遺伝子 40周年記念版。リチャード・ドーキンス先生の著書。人間同士の対立やいざこざ、周りに対して攻撃的言動をしてしまう理由には利己的な遺伝子からくる本能がある。自分勝手が利己的、攻撃的な自分や他人の存在が嫌になった時には、利己的な遺伝子を読んでみると利己的な人が利己的である理由に納得して諦めがつく。利己的な遺伝子、時代を超えて色褪せない一冊です。
0投稿日: 2019.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
むちゃくちゃ時間かかって読んだ。遺伝子レベルで考えると不思議なことがいっぱい。そして抗えないことも。とにかく今生命をもらっているありがたさに感謝しないといけないな。
0投稿日: 2019.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ"遺伝子"が後世に残り続けることを望んでいるという説は新鮮だった。生物個体は遺伝子の乗り物に過ぎないと。わかりやすい例示、シミュレーションで簡単に納得させられてしまう。途中遺伝子に対抗できるものとしてミーム(文化)の存在を説いていたのも良かった。なお前置きと後書き(◯周年記念の一筆とかなんとか)は助長。ともあれ40年もこの本の内容が支持されてきたというのは本当にすごいことだ。
0投稿日: 2019.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の教養講座で紹介され、懐かしく思って読む。 女だからこうとか男だからこうというのも、生物学的には根拠があると思うと少し気楽になる。
0投稿日: 2019.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ名前も概要も知っているけど読んだことの無かった本。進化を考える時は「個体」ではなく、「遺伝子」を単位にして考えなくてはならない。 我々がつい個体を単位として考えてしまうのは、人間は個体の境界がはっきりしているからではないかと思う。これが植物のように接木ができると、個体にそれほど意味はないことが分かる。あくまでも遺伝子がどのように増えるかが大事なのだ。 「生命の目的は子孫を増やすこと」を比喩などではなく、心から言っている人をこの本で叩きたい。40年の重みを喰らえ。
4投稿日: 2018.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ生命とは、遺伝子の運搬機械であるー。この本は、ダーウィンの『種の起源』と並んで世界に大きなインパクトを与えた生物学の本と言っても差し支えないだろう。ドライでデジタルでどこまでいっても利己性だけが支配する
0投稿日: 2018.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
協調性は強い筋肉を持つのと同じぐらいチームを強くする 第2、第3の遺伝子があるから変化に対応して生き残る 未来を予言する方法、シミュレーション 有性生殖は生き残る遺伝子数を最大にするため 私たち動物が宇宙における最も複雑で完璧にデザインされた機械。
0投稿日: 2018.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ『利己的な遺伝子』ようやく読み終えた。AI・BI時代を見据え、幸福や労働の再定義が求められるなか、生物個体としての法則や大局的理論を抑える上で、この歴史的古典は避けられない。群淘汰、遺伝子淘汰を説明した、さまざまな動物の行動事例は息を飲む。 ウェストワールド パレートの法則
0投稿日: 2018.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「英国史上最も影響力のある科学書」の第1位に選ばれた古典の40周年記念版。古典ながら色あせないのは、生物学におよばず人文・社会科学思想に広く影響を与えたからだろう。これまでの批評を踏まえた解説があるため、だいぶ理解しやすくなった。文系の人ほど読むべき。
0投稿日: 2018.04.18
