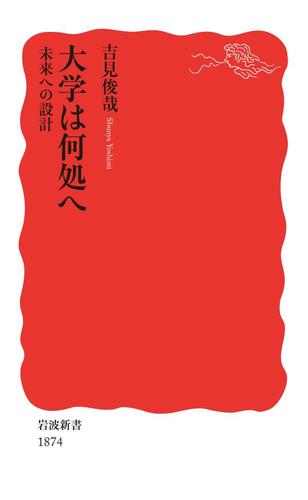
総合評価
(24件)| 5 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学論に関する骨太な新書。これより先に出版された『大学とは何か』も持っているのだが、『大学とは何か』は世界における大学の成り立ちや歴史についての内容が多く、積んでしまっていた。本書『大学は何処へ』も買っただけで放置していたのだが、Audibleにあるのを見つけて視聴。出版は2021年で、コロナ禍における大学運営についての記載があったが、コロナ禍が明けた今読んでも十分興味深い内容だった。様々な歴史的失敗やボタンの掛け違い、あるいは日本に深く根付いている年度の区切りの問題など、もはや大学だけではどうにもできなさそうな状況ではあるが、糸口を見つけていかなければいけないだとは思う。順番は逆になってしまったが、『大学とは何か』もきちんと読みたいと思える内容だった。
0投稿日: 2025.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ客観的に日本の教育制度と大学の位置付けを再考できる機会となった。小中高、高専、短大、大学、大学院。また年齢と教育制度が絡みついてしまっている日本社会の課題を感じるところ。
0投稿日: 2025.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログわが国における大学および学制(6・3・3・4)の発祥から説いて、日本の「大学」は大学=ユニバーシティではなく、国家エリート養成するために西洋の近代知を輸入するための機関として設置されている、というところに着地していると思う。コロナ禍での作品だけにオンラインの可能性(これも下手すると大学を殺してしまう?)や2020年はじめに議論されていた9月入学についても検討されている。ところで、大学でよくきく企業でもないのに「学長=社長」、国家でもないのに「教職員=主権者」アナロジーで大学改革を進めるのは百害あって一利なしというのはその通りだと思いました。
0投稿日: 2025.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ個々の大学ではなく、日本の大学制度を俯瞰的に論じた本。 お説ごもっともな部分もあるのだが、大学生が総じて優秀で、人間は老いても知的好奇心が衰えず勤勉である事が前提となっている。 東大で学び、東大で教鞭を取ってきた筆者のキャリアならばそう考えるのも無理はないかも知れないけれど、誰もが何度も学び直してセカンドキャリア、サードキャリアを構築できるわけではないし、構築したいわけでもない。 筆者が憂えているのは『エリート教育』の未来であって、その設計図の中に日本の大半の大学は含まれていない。いや、そもそも“日本の大学“は『大学』ですらなく、似て非なるものと断じている。 氏が夢見る、21世紀版にリニューアルされた『中世ヨーロッパスタイルの大学の再来』はロマンチシズムに溢れており、その成果を見てみたくはなる。『エリート教育』は決して悪いものではない。高等教育は彼らこそ享受すべきものだと思う。しかし、現状で溢れかえる大学の問題は、普通の人々の問題なのだ。
5投稿日: 2024.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の成り立ちを明らかにした後,その過程で生じた齟齬,オンライン化,9月入学の是非,日本の大学の均質性,を考えた上で,日本の大学の将来像を模索する.日本人の民族的価値観念や思想哲学に基づいた,新たな大学像を構築するのか否かに依るため,民族としての成熟度が問われる.現在の日本の大学が均一化しているならば,日本民族やその文明が疲弊停滞している証左だろう.
0投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ■企業経営の手法を大学運営に移入しようとしたことで、マネジメントが重要だという思想に主力教員が振り回されて時間を磨り潰しており、研究も教育も下降線だ。 ■専門教育はもちろん必要だが、その前段階としてヒトとしてのポテンシャルを上げる機会となる横断的な学びの経験が大事だ。しかし現在の日本のパンキョウは専門教育に隷属してしまい、主体的な教養教育はできていない。 ■コロナで広まったオンラインだが、マス教育をITに載せるだけでは大学自身の自己否定につながるだけ。練りこまれた共通教材はマス・リモートで活用し、より深い専門的な教育は少人数のゼミナール・実験教室方式でなければならない。前者の間は学生は「街に出て、世界に出て」知の実践的足腰を鍛えるようにしてもいい。 ・・というようなことを書いている(と思う)。
1投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
文理の格差は大学の法人化にある P.59 東京帝大 第二工学部 P.62 …今日の私立工業大学の中核[例えば東京都市・工学院・芝浦工業]は、この戦後末期の工学系大拡張の副産物として生まれているのだ。 中でも東海大は大規模総合大学に発展した P.63 …明治学院、青山学院、関東学院の三つの「学院」が一校への統合を迫られている。 …ミッション系ではない私学、たとえば明治大学や中央大学、立命館大学では、むしろこれをチャンスとばかりに工業専門学校を開設し、それが戦後、それぞれの大学において大規模な工学部に発展することになる。 P.68 …大綱化のなかで大学の「教養」と「専門」の敷居を取っ払ったことが教養教育の弱体化を招いた P.70 もともと明治期に帝大に入学したのは社会のごく一部の知的上層であり、そうであるがゆえに「学術の蘊奥うんおう」を探究するという目的が一定のリアリティをもって受け止められていた。しかし、大正期以降の高等教育の大衆化のなかで、大学の役割は学問を究めることよりも、真に有用な職業人を育てることに変化したと同窓会は考えていた。 …旧帝大で、戦後になって総合大学化に向けた拡張が促されていった 東工大のリベラルアーツ教育の先駆け P.150 九月入学 Spring once againは大阪市の公立高校に通う二人の学生が起こした。 高専の可能性 カレッジ型教育 金沢工業 グーテンベルクの銀河系
0投稿日: 2022.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の「大学」が劣化している。その一番の原因は、国民の無関心、誤解、保守的思考…。 結局のところ「大学」を真に改革するには、日本の社会自体を改革しないといけない。しかし世間は社会の改革に乗り気ではない。だから日本の「大学」は、経済とともに国際競争から取り残されていく。 そもそも、「大学とは何か」から始めなければ、改革は「ボタンの掛け違い」のまま悪化の位置図をたどる。それを歴史的経緯と並べて示したのが本書である。 これを読んだ読者は、では何をすれば今日の窮地を改善させることができるのだろう…ただただ、途方に暮れてしまう。 だが本書にはヒントもある。社会人も再び「大学」という場で学ぶ、ということだ。 終身雇用制度も綻び、セカンドキャリアなどが当たり前の時代になってきた。最先端の研究も十数年前より格段に進んだ。人生100年時代ともいわれるようになった。二十歳前後で学んだ知識だけでは、到底かなわない。 各個人が学ぶことをやめないこと。 これが、日本の「大学」および日本社会を発展させる一番の方法である、と感じた。
0投稿日: 2021.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の未来像を論じる。 コロナの影響もあり、大勢が一堂に会する機会に制限が設けられる。オンデマンドや双方向の遠隔授業が導入される。そんな状況が大学の窮状を浮かび上がらせた。 とはいえ著者の考える大学の理想像に同意できない。欧米や戦前のシステムを評価しすぎだ。大衆化された大学の役割はむずかしい。どうしたって大学によって役割は変わるはずだし、役割に応じた出口も必要になる。この役割に応じた出口が日本には用意されていない。それだけ社会が大学に期待していないわけだ。
0投稿日: 2021.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06860112
0投稿日: 2021.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【大学で何をするか、何をしたいか】 私はもう社会人になるため、私自身に活かせるかは分からない。 しかし、大学の教育がどうあるべきか以前よりも視野広く考えられたと思う。 特に今後のオンライン時代は、ミネルバ大学のような例は参考になる。 ・日本人の興味は大学ではなく、大学入試にある 就職までのつなぎとしてのみ見られる。 →中身の薄さ ・ミネルバ大学はキャンパスを持たず、学生が4年間で複数の都市を移動し寮に住む。現地の企業やNPOと連携し、多様な環境に実際に触れることで、より実践的な議論をおこなう。 →机上の空論ではなく、経験をもとに考える ・大学での学び →少人数での議論 オンラインでも十分可能。オンデマンド型の配信講義は学生の知識向上には繋がるが、質は低い。 →オンラインではゼミなど、ワークを積極的に取り入れる。配信講義は少なめに ・日本人のSNSに対する信頼は世界と比較しても極端に低い。Twitterの匿名率も高い。 しかし、人々はネットでの承認を求め、正義に同調する。 →SNSは実態のない世界である可能性を踏まえる。 今後は実名のサービスが有力になる(?)
0投稿日: 2021.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍で大学は大変。学生もだが教員も対応に四苦八苦。 大学はどうなっていくのかを、中世からの大学の成り立ち、世界と日本の大学の違いや、コロナ禍以前からのオンライン化した大学の事例、9月入学の考察など多様な切り口で解き明かしてくれます。 難読な部類ですが、筋道の通った論説はさすがで納得がいきます。 今このコロナ禍の状況が、新しい第三世代の大学への一歩だ、という主張に光が見える気がしました。茨の道ではありますが。
1投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログコロナ禍で、ほとんどがオンライン授業に切り替わった、大学の授業。 大学は窮状に立たされており、10年後には何校が残るかわからない。根本的な原因と、ポストコロナ時代の大学のあり方について。
0投稿日: 2021.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ欧州的ユニバーシティと奈良時代から官僚育成のために作られた日本的「大学」はイコールではない。中世旅する知識人のネットワークとして始まった学会。旅する知識人の集積場所、つまり多様性、独立独歩のユニバーシティ。 その違いがよくわかりました。 その分析を基に、21世紀ポストコロナの大学こそ、中世ユニバーシティをベンチマークにするべきではないか?と言う問いかけにとても共感しました。 校舎がなく、4年間半年毎に学生全員が世界を移動しながら学び続けるミネルバ大学。 経済に国境が無くなった社会を反映するには、大学も移動し続けるのは理にかなっていると思います。高城剛さんが「アイデアの質と量は歩いた距離に比例する」と言ってました。また誰か忘れましたが「旅をしないと本は書けない」と言う言葉もみたことがあります。 やはり、芭蕉のように漂泊してこそ、新しい知識が生まれるのではないかと思いました。
3投稿日: 2021.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログExcellent!さすが東大教授の大学論、Quality秀逸! 日本の大学の①現状②経緯③世界の位置低下④入試至上主義 コロナ禍で本質の問題が顕在化 ①国家主導の画一化 個性化に逆行 ②民間経営手法の導入 大学の喪失 ③④⑤
0投稿日: 2021.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログリンダ・グラットンの「LIFE SHIFT」を読んでからずっと、100年生活に「学び」をもう一度、組み込みたい(はやりのリカレント教育?)という気持ちがむくむく沸き上がっている自分にとっては、タイミンググッドな新書でした。一方で大学人というインナーサークルからの大学改革についての分析なので、悔恨、逡巡、もやもや満載です。章立てが序章「大学の第二の死とは何かーコロナ・パンデミックのなかで」第一章「大学はもう疲れ果てているー疲弊の根源を遡る」第二章「どれほどボタンの掛け違いを重ねてきたのかー歴史の中に埋め込まれていた現在」第三章「キャンパスは本当に必要なのかーオンライン化の先へ」第四章「九月入学は危機打開の切り札かーグローバル化の先へ」第五章「日本の大学はなぜこれほど均質なのかー少子高齢化の先へ」第六章「大学という主体は存在するのかー自由な時間という希少資源」終章「ポストコロナ時代の大学とは何かー封鎖と接触の世界史のなかで」ということで、もう大変です。がんばれ吉見先生、っていいたくなります。しかし、この閉塞感の中でも希望の光は見いだせていて、MOOCとかミネルバ大学とか、いこうぜ、ピリオドの向こうへ、といった輝きを感じました。いずれにしてもリベラルアーツの裾野の広さと専門研究のの深さの再構築で、やっぱり「学び」は人間を人間足らしめるものだと再確認しました。さて、自分のリカレントはどうする?先ずは、遡りで「大学とは何か」を読むところからか…
0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ東大のことが多いので東大生は自分の大学のこととして読むことが望ましいが、他の国立大学については参考程度である。ただし、東工大については意外と詳しく書いてあるので、東工大生はその部分だけ拾い読みでもいい。 あまり他書で扱っていない高専と金沢工大についても書いてあるので、高専についておおよそ知っておくためには読むといい。しかし高専が年間300万円の授業料を必要としていたとは思わず、授業料や寮費は無料だと思っていたので、これだけを知るためにも読むといいかもしれない。
0投稿日: 2021.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の危機をつまびらかにする、大学人だからこそ書けた、必読の書。政治家も、企業人も、大学改革に適当なことをいう前に、まずは正しい現状認識をお願いしたい。して、大学人は、自由な時間を取り戻しつつ、ポストコロナの大学の在り方を構想しよう。
0投稿日: 2021.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2021/7/17 メトロ書店御影クラッセ店にて購入。 2021/7/26〜8/4 これまでも大学の在り方について、著作を発表している吉見氏の本。コロナで遠隔授業が主体となった大学の、今後を、明治期以来の日本の大学の位置付けから読み解く。非常に 勉強になった。
0投稿日: 2021.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
コロナ禍で、これまで遅々として進まなかった大学のオンライン化は一気に進んだ。ポストコロナ時代の大学はどうあるべきなのか、ということから始まり、大学の歴史から昨今の大学改革の悪影響が語られ、最後は、国民国家の大学ではなく、新しい地球人を育成するような大学に、日本の大学の一握りでもなれるかと問いかけて終わる。 大学改革は研究者にとって一番大事な"時間"が蔑ろにされて、外からの論理、圧力で進められてきた結果、今のような研究力も低下し、多くの博士号取得者が非常勤職に甘んじているという指摘は、予算やポストの再配分だけでなく、「自由な時間」をどのように実現していくか、若手教員のキャリアパス、学生の学びについても、大学や国を越えた流動性を実現することが大事だというのはよくわかるが、まさに、言うは易し、行うは難し。 大学の成り立ちや、高専のポテンシャルなど、色々参考になることが多かった。
7投稿日: 2021.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログamazonの本ランキングでは眉唾ものの本が跋扈する中で、筆者の確実な知識基盤のもと新しい刺激をくれる「岩波新書」の1冊。 岩波新書の特徴として文献や人物が多く取り上げられることが挙げられ、ページをめくるうちに混乱してくる本も多々あるが、本作では章ごとに区切られていて、理解しやすかった。 大学の歴史から、その定義する重要性はたまた将来の大学のあり方など数多くの論点があり、一度読んだだけで全て把握することは困難。 ただ、確かな知識と経験から考察した未来像は本当にワクワクしてくる!!大学に3回入学、3回卒業すべきだって!?とんでもない衝撃を受けた。 大学の成り立ちが少しわからなかったので、精読と関連書籍を漁ってみる
0投稿日: 2021.07.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2020年のコロナ禍が一挙にオンライン授業を進展させ、大学は大きく変革させられたことから始まる。実は海外に比べて遅れていた日本の教育の現状が著者によって深刻な実態として心に迫ってくる。日本の失われた20年というのは経済、政治以上に教育において進んでおり、これは長く続く未来への深刻な影響が心配される。日本学生の海外留学者が減る一方で米国の大学へは中国、インド、韓国、台湾の学生たちが激増しているとは何と恐ろしい実態だろうか。それは若者たち自身の問題ではなく、日本の教育システムに問題があるという著者の深刻な問題告発である。日本の大学問題は入試改革ばかりに注目が集まるということは異常な姿なのだろう。そして大学の改革についての今後の方向性を著者が真剣な姿勢から可能性を示唆してくれている。
0投稿日: 2021.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ失礼であることは重々承知なのだけど、読み始めてしばらくして、おじいちゃんから話を聞いている気分になった。 理工系の大学が戦時中に国から必要とされて数を増やしていき、戦後に新制大学になった話や、戦前の高等学校と戦後の高校の違い、金沢の高専の話なんかは読んでいて興味が湧いたけれど、大学教員のタイプ分けやその比率はなんの根拠があるのだろう?著者の実感? これからは大学に生涯で三回行く時代だ、という話も現実味がない。少子化が進む一方の日本で大学が栄えていくには一人が何度も大学に行くのが理想だし、学び直しができる社会は理想だけれど若い世代を中心とした貧困の実態をご存知か?と思ってしまった。 別の段落で非正規の割合とかについても言及されていたから知らないわけじゃないだろうけどなんだかな…という気持ち。 相性がいまいちだったのか、恐らく単に私の理解力不足のせいなのだろうけれど、中弛みして読み進まず、最後は無理やり読み切ったけれどあまり頭に入らなかった。
0投稿日: 2021.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログあとがきで著者は書く。「日本の「大学」は、実は大学=ユニバーシティではなかったのだ! 」。つまりそういうことである。明治維新、戦後の学制改革を経て、そして現在も永遠と続く「大学改革」は結局日本の「大学」を大学=ユニバーシティとして機能させることにはならなかった。むしろ大学=ユニバーシティから遠ざけることになった。その歴史を辿る。 オンラインを最大限に生かしたミネルヴァ大学のあり方も、日本の大学が多分今後も強化していくであろうオンライン化と似て非なるものである。現在もそうだが、日本の大学のオンライン化は学生をアパートの個室に閉じ込め、時間も空間も個別化するものであり、ネミルヴァ大学のキャンパスはないが全寮制である・・・とは全く異なるものである。 著者は言う、「第三世代の大学の使命とは、世界哲学や世界人文学、様々なリベラルアーツ的な知を通じて自由な地球市民を育てていくことだ」と。多分その通りである。 そして、そのために日本の大学は何をしなければならないか。著者はいくつかの方向性を出すが・・・・おそらく著者自身はそれができるかとどうかについて懐疑的であるように私には思える。 日本の社会のこれまでと今を見る限り、それを知れば知るほど絶望的になる。「世界哲学や世界人文学、様々なリベラルアーツ的な知」を失ったかのように見える為政者にこの変革は可能なんだろうか?
0投稿日: 2021.05.23
