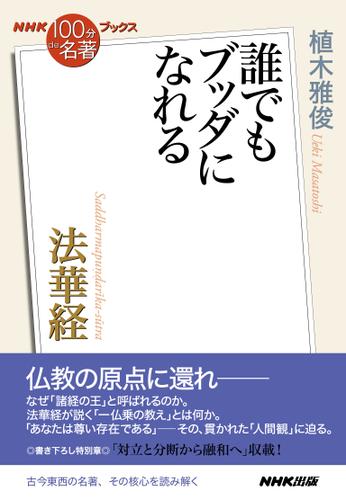
総合評価
(5件)| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. 菩薩の概念の変遷 - 菩薩の定義: 最初は「覚りを得る人」としての意味が強調され、釈迦の教えを受け継ぐ存在としての位置づけ。 - 大乗仏教の影響: 大乗仏教が興起することにより、菩薩は「覚りを求める人」として、すべての人に開かれた存在と解釈されるようになった。 2. 小乗仏教と大乗仏教の共存 - 共存の時代: 小乗仏教(上座部仏教)と大乗仏教が同時期に存在し、互いに影響を与え合った。 - 批判と融合: 大乗仏教側から小乗仏教への批判が見られる一方で、両者の対立を超えた融合を目指す動きもあった。 3. 仏教の変容 - 釈尊滅後の変化: 釈尊滅後500年の間に、仏教の教義や実践方法が大きく変化した。 - 修行の難易度: 初期の経典では即時成仏の可能性が強調されていたが、後の部派仏教では極めて長い修行が必要とされることが一般的になった。 4. 法華経の教え - 平等思想の回復: 法華経によって、すべての人が平等に成仏可能であるという思想が強調された。 - 三乗の融合: 声聞、独覚、菩薩の三者を融合させ、全ての人に成仏の道を開くことが教えられた。 5. 社会的な平等 - カースト制度の批判: 釈尊は、出自による差別を否定し、行動によって人間の価値が決まると説いた。 - 人間の尊厳: すべての人間は、行動や生き方によって尊厳を持つべきであるという考えが根底にある。 6. 多様性の尊重 - 差別相と平等相の関係: 多様性を受け入れるためには、普遍的な視点に立つことが重要である。 - 法華経の実践モデル: 常不軽菩薩の行動を通じて、対立や分断を乗り越えるための実践の在り方が示された。 7. 現代への示唆 - 平和の実現: 現代の対立や差別を乗り越えるためには、仏教の平等思想が重要な役割を果たすと指摘されている。 - 社会的な教化の必要性: 一般民衆を教化し、仏教の教えを広めるための努力が求められる。
0投稿日: 2025.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ原始仏教から小乗、大乗、法華経の流れ、その中で法華経が意図したものが分かりやすく説明されていた。初めは共感しながら読んだが、後半は知っている内容が多かった。
0投稿日: 2024.09.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ宗教についてなので内容は難しかった。 でも、100分de名著で扱ったものなので 概要を学ぶ上でわかりやすかった。 経典とは、なにか説法集や 生きるための指南書みたいなものだと 浅く思っていたけれど、 仏教の変遷とその在り方への批判、 よりよい在り方を目指した戒めも含めた もりもりの内容なのだと理解できた。 これは、著者の地道な深い翻訳や研究と 丁寧な解説のおかげだと思う。 「般若心経」を勉強したことがあり 仏教的な視点については 理解できていると思っていたけれど、 それどころではない多くの学びがあった。 仏教に貫かれている平等思想には 深い感銘を受けた。 地涌の菩薩や常不軽菩薩の話が 興味深かった。 特別章として追加されているところは 今を生きる私たちにとって学びが大きい。 仏教は、二元論に陥らない凄さを持っている。 現代、様々な分野で対立と争いを見るが、 たとえ強者と弱者が入れ替わっても その問題は解決はしない。 それらを分断してみる視点から退き 高次元からまるごと受け入れる姿勢が 仏教なのだと感じた。 多様性を個性の対立にせず 同じ土地と水に育つ 草木の様相の違いとみることができれば 互いの共感も生まれ 融和も可能なのかもしれない。 仏教の生まれたインドでは、 差別・階級の意識が根強く 仏教が根づいていないことは残念だ。 中国や日本へ渡り、時代や支配者により 解釈や理解が変わりつつも 現代にこの思想が残ってくれたことに 感謝したい。 ブッダの教えには普遍性があり あらゆる人間に向けられた包容力がある。 唯一無二の思想のように感じる。
0投稿日: 2024.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔からいまいち捉えどころがない印象の法華経。昔から「法華経はほめる言葉ばかりで中身が何もない」とも言われていたようである。そもそも法華経は何のために書かれたものかを理解することが必要だろう。下記記載がわかりやすかった。”小乗には小乗の、大乗には大乗の差別思想がありました。そこで、両者の差別思想と対立を克服し、普遍的平等思想を打ち出すという課題を受けて成立したのが法華経なのです。”
0投稿日: 2023.07.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ初期仏教の小乗と大乗の対立の中、それを乗り越えるために編まれたという法華経を誰がどのようにして広めていくのかというのが法華経の内容のあらましで、二重構造のようになってブッダへの道を説いているという。それは常不軽菩薩のように何物にも軽んじず軽んぜらず、真の自己の尊さに目覚め、それによって他者も同等であると認めることができるということが、人間がもつ差別への拘泥と他者への攻撃性の無意味さを教えてくれていると思えた。
2投稿日: 2021.08.31
