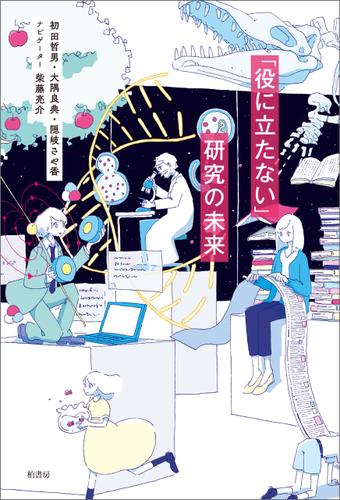
総合評価
(18件)| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系の存在意義を考えるために読んだ。理系の学問でも、研究資金獲得競争に邁進せざるを得ずに有用性という観点に合致する分野に研究領域が収束しているという指摘になるほどと思わされた。ノーベル賞受賞者の、「楽しいと思える研究をする研究者が増え、研究の多様性があることが大切」という言葉は「それって何の役に立つんですか?」という社会における日常的な問いかけを見直すという示唆を与えてくれる。科学史の専門家から提示された、貴族的な国家と民主主義国家での学問・芸術保護のスタンスの違いは斬新な視点であり、歴史上繰り返される衆愚政治や近代の大衆社会における孤独・閉塞感などの民主主義国家のマイナスな特質を考えさせられる観点であった。
0投稿日: 2025.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ物性研の所内者、柏地区共通事務センター職員の方のみ借りることができます。 東大OPACには登録されていません。 貸出:物性研図書室にある借用証へ記入してください 返却:物性研図書室へ返却してください
0投稿日: 2024.02.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ研究というと、「病気の治療に役立つ」とか「暮らしが便利になる」とか、そういう役に立つか立たないかで語られがち。 基礎研究や学術研究を「役に立つか立たないか」ではなくて、知的好奇心や探究心を満たすものでもいいじゃないか。 国は役に立つ研究を選び、そこに研究費を投じる。それでいいの?と思ったけれど、政治を憂いてもしかたないので、民間の団体が研究費用を支援する必要がある。そして、研究者ではない一般の人にも科学の楽しさを伝えて、「推し研究」を支援できる社会になっていけたらいいなと思った。
0投稿日: 2022.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログみなさんには「推し研究者」はいますか?" という出だしから始まる本書。残念ながら私には一人も思いつかない。 どうして市民と研究者の間にこうも隔たりがあるのか。科学の面白さはどう伝える?基礎研究はこれからどう支えるべきか?そもそも「役に立つ」とは? それぞれ違う立場から科学、基礎研究、これからについて語っている。ナビゲーターの方も学術系クラウドファンディングサイトの方で、質問の内容が具体的で、文系の私にも大変興味深い内容だった。 説明責任の一つに「研究者の日常を伝える」のもありではないか、というのも面白いなあと思った。 あと無理して「〇〇に役に立つ」をゴールにしなければいけない、というのはおかしいのではないか。自分の「知りたい」をもっと突き詰めてほしいし、それを支える仕組みを作ろうと奮闘している4人の姿が垣間見えた。 オススメ度: ★★★★☆ ノブ(図書館職員) 所蔵情報: 品川図書館 407/H42
0投稿日: 2022.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ役に立たない科学が役に立つ:物質の安定 知識・使えば使うほど増える資源 物理学 基礎研究の本質・ゼロイチ 4つの常識 ディラック方程式の ヒッグス論文 役に立たない知識の有用 人間の精神を解放 選択と集中・ゼロイチと両立しない すべては好奇心から始まる―ごみ溜めから生まれたノーベル賞 選択と集中は何をもたらしたのか:国家戦略とマネジメントの話の混同 企業の意識 説明責任 目標設定が低くなる悪循環 内にこもったフレクスナー・外に出たアインシュタイン アウトリーチ活動 これからの基礎研究
0投稿日: 2022.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ研究にはお金がかかり、資金は足りないけど、根本的な解決には見えない壁があるんだーというもやもやがリアルに伝わってきました わたしは研究とか、そういうのは難しくて途中の大隈さんのお話とかもついていけなくなりそうなくらい縁遠いと思いました でも、プレスリリースとかみてみよ!って思いました、本文にも合った通り「思い立ったら行動」ですね あと、知識は唯一、使えば使うほど増える資源という表現は知らなかったので、とても良い言葉だなと思いました
0投稿日: 2022.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
役に立たないとされがちな基礎研究について議論された座談会のまとめ。 そもそも役に立つとは何かということ(線引きは不明瞭・恣意的 と理解した)、基礎研究は多様性を認めてこそ将来応用につながるような研究が生まれること(選択と集中はそぐわない)、研究内容に加えて研究者の人となりや生活ぶりを紹介するようなサイエンスコミュニケーションもあるといいこと、市民のニーズにあった研究という視点(シチズンサイエンスや当事者研究)など、盛りだくさんだった。 子供への理科教育は等しく必要としても、大人に対しては、研究にそれほど興味のない層に無理に届けなくてもいいのでは、という提案もあった。そういう視点は大事なように思った。
0投稿日: 2022.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「何の役に立つの?」「勉強して何の意味があるの?」世間、政府にとどまらず、この流れが子供達にも起こって来ていると感じる。自分の頭で考える「楽しむ」ことの大切さを伝えられる人に私はなりたい。
0投稿日: 2022.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ役に立つ立たない、お金になるならない、そんな物差しで研究を測るな!そんな当たり前なことが当たり前でなくなっている世の中を嘆く。お金有り余っているところは有り余ってるみたいなのに。
0投稿日: 2022.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこの研究は何の役に立つのか? この質問の裏には何かの役に立たない研究は意味がない、という意味が込められている。 しかし歴史の中でなんの役に立つのかわからない研究が多くの科学技術の発展に役立っている。 考えてみれば身体トレーニングもやっている時はそれが何に役立つのかわからないものも多い。 でも、そうやって身体の動きを少しずつ理解することで思わぬ発見もある。 研究という姿勢は短期的なものでインスタントな結果を求めるのではなく長期的な展望で取り組まないといけないですね。
0投稿日: 2021.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「研究」に対して、役に立つ・立たない、といった場合、その話している人の頭の中がそれぞれ違うので、話自体が噛み合っていないことも多い。そんな中で、異なる分野の研究者、ここでは数理学、生物学(ノーベル賞の大隅先生!)、人文学の3名の研究者が講演後、座談会形式で課題と具体的な取り組みを話し合っている本。 ナビゲーターは、研究者を応援するクラウドファンディングを経営しているとのこと。基礎研究は、選択と集中と相性が悪く、説明責任を果たす上でも相性が悪い。一方で、説明責任自体は、果たすべきだが、何を説明すべきか、まったく関心がない人にどのように説明するかの工夫や方向性をしっかり議論すべきというのは、とても納得。 役に立つ/立たない、説明がつく/つかないの文脈でいくと、世の中には、説明がつかないけど成り立っているものがあり、例えば、地方のお祭りなんかがそう。その土地ならではのお祭りがあって、地元の人が大事にしていて、じゃあ、その価値はどこにあるかというと誰も「説明責任」は果たしていない。若い人も楽しんで参加しているという現状は、感情面としてアタッチしているということ。逆に言うと、感情面で納得がいっていないときに、「説明責任を果たしてほしい、他者に対して自分が納得できるようにしてほしい、それによってお金を出すことを納得したい」という問題が起きているのだ、という指摘はとても鋭いと思いました。役割として説明責任は果たすべきだが、○○の役に立つとウソに近いようなことは止め、一方で純粋に頑張っている人を応援したくなるような感情を醸成できると基礎研究の環境が良くなると感じました。 他に科学と技術を分けて考えるべきであるということ、国の果たす役割の重要性、一般市民が”推し研究者”を応援できる体制など、示唆に富む話が多数あるとともに読みやすさもあり、基礎研究、引いては好奇心が原動力になって研究に取り組める環境を構築できるような活動を継続して欲しいと思いました。
0投稿日: 2021.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
研究は、全てが役に立つわけではないし、研究している時点で役に立つかはわからない。そのため、役に立たないと思われている研究でも支援をしなければ、将来有益になる研究も潰されてしまうかもしれないし、研究の種が撒かれなくなってしまい、研究が先細りしてしまう。目先の利益だけを追求するのではなく、中長期的な研究支援をするべきだと思う。
0投稿日: 2021.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎研究を「役に立つもの」と思う風潮がおかしい、興味があるものをそのまま突き進めれば良いではないか。面白いから研究をやりました で良いではないか。 研究は芸術と同様に文化であって目的がうんぬんではない。研究者は世間に面白さをアピールするのも仕事である。 刺さった。自分の研究に悩んだ時にまた読みたい。
0投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ人を動かす原動力はいろいろあると思うんですけど、研究については、「好奇心」とか「探求心・探究心」とか「興味・関心」であることが望ましいのだと思います。 ただ、世界的に、また、とくに日本では、それらを支えられるだけの土壌や理解、文化が乏しくなってきているように思いますし、その状態を危惧しているのが、本書の関係者だと思います。 一方で、その危惧を払拭するための動きがあるのも事実。 たとえば、この本においてナビゲーターを務めている柴藤氏は、そのような動きを支えている人の一人。 自分もいつかは、柴藤氏のような活動をしたいな、と思っていますので、そこに向けて、いろいろと作戦を考えていきたいと思います。
0投稿日: 2021.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログもともとトークイベントがあって,ぞれを書籍化したものらしい。 そういうわけで読みやすいが,内容は薄味。 科学,とくに基礎研究は「役に立たない」と言われがちだけど,でも,大事だし,とにかくおもしろいんですよ,という話。
0投稿日: 2021.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
知識は使えば使うほど増えていく資源 違う分野の相互作用が大切 基礎研究=原理の追求:縦糸 × 普遍性(論理体系)の探求:横糸 科学の発展は循環的 波及効果が大きいため、長期的視点が必要 多様性から選択 有用性以前に精神の自由 ゼロを一にするには「選択と集中」は使えない。 古代ギリシャローマの 有用性=ユーティリティ=公共での役割 自分にどう関係するのかを主張する民主的な社会は 高尚な学問に冷たい 説明責任 =感情的アプローチ 公的財源のなかのパイの奪い合い →アカデミアと企業の協業のプラットフォーム 一回は失敗してみる心の余裕
0投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
この本から学んだこと ・日本の科学技術における方針は「選択と集中」であるが、これによって基礎研究がおろそかになっている。 ・基礎研究は役に立つかが先行するのもではない。研究者が好奇心をもってやっていたことが、後で役立つものだった、という順番。 ・研究者が自分から研究を発信していき、それを面白いと思った人がお金を出す仕組みが重要。 ・基礎研究は「0から1」を作り出すこと。技術開発や応用研究など、目標地点のあるものでは効果を発揮するが、基礎研究においては目標を立てられないので効果を発揮しない。
0投稿日: 2021.05.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ3人の異なる分野の研究者が、それぞれ微妙に異なる立場から「役に立たない」研究について論じている。 3人それぞれの講演等の中から印象に残ったことを書き記しておく。 まず、理論物理学者の初田さんは、基礎科学の重要性を一般社会や政府に対して理解してもらうためには、科学者自身のアウトリーチ活動をより多様に、効果的に展開していくべきだと主張している。ADKと組んだ独自のアウトリーチの取組み(クリエイターと協力してプロトタイプを作っていくというもの)も紹介していて、興味深い。 次に、分子細胞生物学者の大隅さんは、自身が、当初全く引用されない分野だったオートファジーの研究を続けてきた経験から、安易に「役に立つ」分野を研究するのではなく、自分が本当におもしろいと思える分野を見つけることの重要性を説く。また、大隅さんは自身の財団を立ち上げ、研究者視点での「おもしろい研究」にファンディングしているなど、国の政策とは一定の距離を置いて基礎研究の支援を行っている。 最後に、科学史家の隠岐さんは、「役に立つ」というのは政治的な言葉(説得のための言葉)であり、決して検証のための言葉でないことを指摘している。「有用性」が持ち出されるのは、それが未来に関する言葉だからだ、という主張はなかなか興味深い。また、隠岐さんは、今般の科学技術基本法改正によって人文社会科学がいわゆる科学研究に位置付けられることになったことについて、人文社会系研究者が安易に「動員」されないようにと、警鐘を鳴らしている。「社会のため」と言ったときの「社会」とは何を指すのかが曖昧なまま動員されると非人道的な結果に繋がりかねないという指摘はもっともであり、まさに人文社会系研究者はその点に留意しながら研究をすべきなのでは、と感じた。
2投稿日: 2021.05.03
