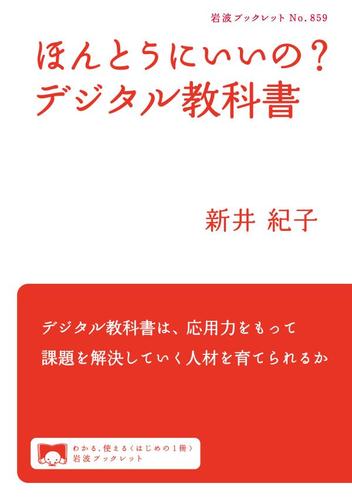
総合評価
(19件)| 4 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ私にしてみれば珍しい岩波である。 会社の同僚に「読んでみますか?」と薦められた本。 ブログで仕事の事は書かないようにしているが、実は教育関係の仕事をしており、とあるデジタル教科書も手伝ったりしているのだ。 もう3年前、当時の総務大臣であった原口氏が、原口ビジョンの中で、2015年までにデジタル教科書を全ての小中学校全生徒に配備するなどとブチあげたものだから、一気に「デジタル教科書」に注目が集まった。 この本は、というか新井紀子氏はどちらかというと懐疑的なスタンスで、この本をまとめている。 デジタル教科書って一口に言っても、子供たちが使う「児童生徒用」と、教師が使う「指導者用」が有ります。 「指導者用」は、すでに全ての教室に配備されたデジタルテレビや、プロジェクター、電子黒板などを利用し、教科書を大写しにして使うもの。 現在の一斉授業形態の中でも比較的すんなり利用できるものですが、「児童生徒用」となると個人持ちハードウェアやネットワークの事もあり、そう簡単にはいきませんし、そもそも現在の教科書がデジタルになる必要があるのかと、私自身も懐疑的ではあります。 原口ビジョンのような総務省が掲げる経済活性化のための材料として「教育」をそんな場に出して欲しくないですもんね。 でも、「デジタル教科書」と言えば一般的には、「児童生徒用」を指すようですが、この本も「児童生徒用」の事を中心に書かれています。 ま、興味がございましたらお勧めです。 60ページ程度の本なので二時間もあれば、読み終わっちゃいますし、すごく読みやすく書かれています。 さて、岩波書店。 私は、岩波系の本をほとんど読みませんが、実は先日、仕事の関係で岩波の論壇誌『世界』から取材がありました。 小中の情報教育についてページを設けるんだそうで。 どんな取材だろうと期待してたんですが、単に会社の沿革や雑談で終わってしまいました。 もっと本質に突っ込んでくるかと構えてたんだけど、ちょっと肩すかしを食らってしまったな。。。 個人的な意見ならいくらでも言えるけど、公の立場を思うと何にも言えなくなっちゃうんだけどね。
0投稿日: 2023.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
デジタル教科書でできること、したほうが良いことを整理する必要がある。 目標は「便利」だけでなく「教育」のはずだから。 そのために、何がしたくて、そのために何が効果的かを考えなくてはならない。
2投稿日: 2022.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル教科書の導入に対して、否定的な考えをしっかり書いてある本です。 (否定的な本であるという意味ではありません) 今後は慎重に、そして積極的に導入を進めたいと思います。
0投稿日: 2022.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ約50年前に通っていた学習塾には、定年後の小学校の先生がいらっしゃった。丁寧に教えて下さった。国語の先生は、主語と述語、修飾語の見分けられるように、また算数の先生は文章題の文が誤解なく読み解けるように、時間をかけて教えて下さった。先生がたの教える技術と時間と根気、それらを支える熱意と愛情を今思い出します。 新井紀子さんは、そういうことの重要性を、説得力のある文章で語っています。共感するところが多いです。
0投稿日: 2020.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログブログ書いた↓ http://sansho.hatenablog.com/entry/2013/06/04/001611
0投稿日: 2018.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル化が教育的に効果があるとは言い難いことを、科学的かつコンパクトに論じている。 最後の筆者の言葉に、教員としての使命を果たせているかと問われている気がして武者震いする思いだった。 「人を育てることには常に膨大なコストと予測不可能性が伴う。…不完全で非効率でしかない人間を、手塩にかけて育てることによってイノベーションが起きる可能性を待つ、その寛容さこそが今、社会に問われている。」
0投稿日: 2018.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018.3.24市立図書館 デジタル教科書がどのようなものであるのか、急に導入・移行が進められようとしている理由は何であるのか、その流れは教育的に妥当なのかどうか、コンパクトに解説。移行を提言しているのが文科省ではなく総務省であり、教育的効果よりむしろネットワーク整備をすすめるための方便として利用されているに過ぎないこと、デジタルメディアの可能性や利点も認めつつ、一律にデジタル化することへの危惧がわかりやすく伝わってくる。
0投稿日: 2018.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログAIの到来に備えて小中学生は何を学ぶ必要があるのか?問題解決能力のその先は? 2012年の本だが、AIなど技術革新があれば解決出来る部分もある。技術の進歩を注視しつつ、デジタルコンテンツのメリットを最大化出来る部分から導入を進め、適用範囲を広げていくことになるのではないか。著者の主張は、技術的な部分がボトルネックとなることもあって、否定的なものが散見されるが、逆に技術革新によるデジタルコンテンツの可能性を強く感じさせる。 ティーチングとコーチング 特徴量を見出せなくなる危険性 過去に例がないようなことには対応できない
0投稿日: 2016.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル教科書を議論する上での叩き台として、枠組みをきれいに整理してある。何より、(はっきりとは言わないが)反対派の筆者がデジタルデバイスを使い倒している側の人間であるところに説得力がある。”デジタルの弱みは「面積」”、”ハイパーリンクは理解を助けるか”など、具体的で説得力のある論旨が展開されるのは気持ちがいい。引用文献にもおもしろそうなものが多く、うすいうすい岩波ブックレットの中では、濃密でかなりお買い得の本である。
0投稿日: 2013.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ総務省が、インフラ整備のために進めているデジタル教科書。筆者は、紙の教科書から全面的にデジタル教科書に代わるのなら、効率で経費削減以外にはメリットはないだろうと述べている。知識技能の定着にはある程度効果はあるものの、思考力判断力を身につけるのには工夫が必要であるだろう。
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログICT技術を使った公教育がどう変化して、 そのメリット、デメリットがわかりやすく書いてある。 印象的なポイントは、 教育ソフトが消費者用(バナー広告などのため)につくられる傾向があること。 ネットワークを各地に張り巡らす光の道構想というものがあったこと。
1投稿日: 2013.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログデジタル教科書について、教育の効果の面から今までの実証的な研究を踏まえたいい本である。さらに教育を経済成長の道具にしてはいけないと主張している。教員養成の学生にとっては必読の本である。
0投稿日: 2013.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログたしかに小学生にデジタル教科書っていうより高校生のほうが導入には難易度が下がりそう。 筆者はデジタル教科書に懐疑的みたいだけど、全部を入れ替えって方針がまずいんだろう。デジタルランドセルってやつだ。この教科はデジタルっていう方法なら実行可能かな? ハイパーリンクも横線がひいてあるから見るかどうかを選択しないといけないんであって気になったらクリックしたら見れるというタイプなら気にならないと思う。 マルチウィンドウが必要になる授業にはまあ低学年には無理だろうな。 サーバーは学校にでっかいバックアップ機能のHDを置いて毎晩アップデートし、そこからwifi通してダウンロードもしくは閲覧という形なら実現可能か? 出来るための課題をひとつひとつこなすしかないんだろう。 まずは電子書籍のシェアがどの程度広がるか様子を見てからの導入でも遅くなさそう。
0投稿日: 2013.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業視点が如何に多いか、ネットワークの会社として考えなければならない点も多いと感じました。巷でもてはやされているよりも、道具としては効果が限定的なものだと理解しないと危ないですね。
1投稿日: 2013.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ普及しつつあるデジタル教科書は本当によいのか。著者が考察しています。著者はどちらかというと懐疑的なスタンスです。僕もです(^^)
0投稿日: 2013.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログお題目を結構クリティカルに解釈して書かれている。「へえ〜、なるほどね」と思えることが多くて、それでいて奇抜なアイディアにも映らず正論。これは目から鱗です。 薄いし、一気に読めます。お勧め。
0投稿日: 2013.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ - Hardware:モニタ画面の限界(一覧性)、眼への負担不明 - Software:ハイパーリンクの功罪(情報増は理解を深化させるか?)、ワーキングメモリ分散による集中力低下 - Contents:即時フィードバックが強み→スキナー箱的学習には向いてる。が、それでいいんだっけ?テイラーメイド(学習履歴からの適切な学習過程の統計的計算、って本当?効用と限界) - Network:学習効果よりも光の道ありきで生まれた議論では?クラウド化の必要性? という話。
0投稿日: 2013.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ本屋でちらっと見かけ、前を通り過ぎかけて…ん?と思って2歩戻り、衝動買いしてきた。 受験終わったら読む。
0投稿日: 2013.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ小中学校のデジタル教科書化についてまとめられた本。 コスト面、性能面、学習の質等。あくまでも現実的で冷静な目で調査されている。 現時点では最もわかりやすいハードルはコストである。 義務教育の教科書予算は一人当たり4000円ほどだそうで、 コンテンツ代としては同等もしくは印刷コストを抑えて安くなるかもしれないが、 デバイスはそれほど安くないし耐久性にも課題がある。 学習効果についても、単純に今以上の効果を期待するのは難しい。 一枚に収まってしまえば並べて俯瞰的に使用することはできなくなるし、 ハイパーリンクが便利とはいっても、闇雲に適用すれば情報量増加により、課題によっては理解度・効率は悪くなる。 デジタルのメリットもいくつも挙げられていたが、 技術的にもコスト的にも即座に導入できるような要素は少ない。 デジタルツールは今後も発展を続けるだろうし、小学生を含めた一人ひとりに普及するのも遠くないかもしれない、しかしそれは紙ではない、あくまで別のツールなのである。 何より大事なのは学習である。デジタル/アナログの相互に偏見を持つこと無く、冷静な判断をし続けたい。
0投稿日: 2012.12.16
