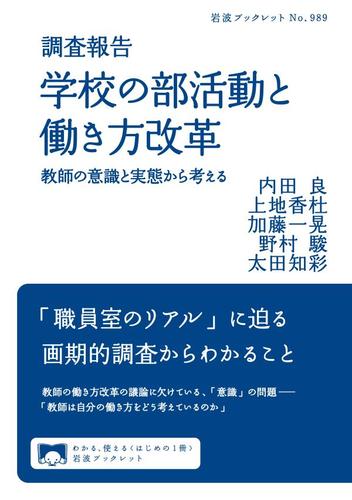
総合評価
(2件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログP.40 本性の検討で明らかになった知見は、次の四点である。 ①働き方に対する意識については、八割を超える教員が、「仕事が忙しい」と感じる一方で、「仕事にやりがいと感じる」と答えていた。働き方に対する意識の均質性・共通性が指摘できる。 ②部活動に対する意識については、部活動顧問に対するストレスと楽しさをめぐって、教員集団が大きく三つに分化していた。意識の面での多様性が指摘できる。 ③誰が部活動にポジティブな意味づけをしているのか、またネガティブな意味づけをしているのかを調査した結果、前者には若手教員と男性教員が、後者には年配教員があてはまることが分かった。教員の置かれている状況によって部活動に対する意識が異なっていると推察される。 ④部活動に対してポジティブな意味づけをする教員に着目し、その理由を検討したところ、生徒および教員自身に対して何らかの積極的意義があると見なされていることが分かった。 部活動に積極的な意義を見出し、主体的に関与しようとする教員と、部活動に異議を見出すことなく、より多くのストレスを感じながら関与させられている教員に二分されているのである。前者には若手教員と男性教員が、後者には年配教員と女性教員が位置付けられる。しかも、後者に比べて、前者の方が部活動立会時間が長くなっており、客観的には多忙な状況にある。 P.48 教科別担当部活動(グラフ) 体育:運動部95.4%, 文化部1.5%, 担当していない3.2% 音楽:運動部11%, 文化部86.2%, 担当していない2.8% 美術:運動部36.6%, 文化部60.2%, 担当していない3.3% 技家:運動部65.6%, 文化部26.9%, 担当していない7.5% 外国語:運動部75.4%, 文化部18.2%, 担当していない6.4% 社会:運動部88.0%, 文化部8.5%, 担当していない3.6% 理科:運動部78.8%, 文化部17.8%, 担当していない3.4% 数学:運動部84.4%, 文化部10.7%, 担当していない4.9% 国語:運動部75.7%, 文化部18.9%, 担当していない5.4% 担当教科と部活動指導に感じるストレスの関係 比較的割合が多いのは、外国語科や技術家庭科、音楽科、家庭科の教員で、約7割が部活動指導にストレスを感じている。(=比較的女性教員が多い科目だから必然的にそうなるのでは?加えて、参考文献のタイトルを見るだけでは調査対象の学校種別がわからないけれど、中学・高校で男女比がまったく異なるから結果も変わってくるだろうな~)。その他教科でも、ストレスを感じる教員のほうが多数派である。保健体育課は例外で、ストレスを感じない教員のほうが多い。 週当たり部活動立会時間の平均値(分) 体育:750分/ 46% 音楽:670分/ 67% 美術:450分/ 56% 技家:560分/ 68% 外国語:580分/ 70% 社会:680分/ 59% 理科:610分/ 62% 数学:620分/ 63% 国語:590分/ 66% P.55 顧問をする競技・活動を中高生時代に経験したことがあるか 経験あり:42.5% 経験なし:57.5% P.58 2015年12月、「部活動問題対策プロジェクト」というウェブサイトが立ち上げられ、「教師に部活の顧問をする・しないの選択権を!」という署名活動が行われた。2018年8月現在で3万4000筆あまりの賛同を集めている。 文科省は、2017年度から「部活動指導員」を制度化した。部活動指導員は、「学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、技術的な指導に従事する」とされている。これまでの外部指導員は、顧問の教員と連携・協力する立場であり、普段の指導や大会引率は顧問の教員が主導する必要があったのに対し、部活動指導員は自らが顧問として日常な指導や大会引率を行うことができる。(現実は、顧問+部活動指導員になり、顧問の負担減にはなっていない気がする。) しかし、部活動を外部委託する取り組みは、依然として一部の自治体にとどまっている。それは、部活動を外部委託できるだけの予算や人材を確保することのできる自治体が少ないためであろう。また、部活動指導員の任用にかかる費用は、国から補助が出るとはいえ、都道府県と市町村が、それぞれ費用の三分の一を負担することになっている。そのため、多くの自治体では、予算を理由に部活動指導員の制度を利用しないことが懸念されている。今行われている部活動を教員以外の人材に担ってもらおうとすると、こうした財政的な問題に直面してしまう。 では、お金がない以上、現状維持もやむを得ないのだろうか。運動部活動研究者の中沢は、そう考えるのは早計だ、と指摘する。氏は、そのような考え方は二つの大事なことを忘れているという。 ひとつは、そのような多額の予算を必要とする仕事を、すでに教員が担っているという事実である。もうひとつは、外部委託の議論が、今の部活動の規模を維持する前提で進められていることである。部活動を外部委託して教員の負担を減らすのが財政的に難しいのならば、部活動の規模縮小も、選択肢に入れるべきだろう。そこで次に、どれくらい部活動規模を縮小すれば、教員の負担を減らすことができるのかを考えたい。 P.68 多忙化に関する情報共有(グラフ) 多忙化について同僚と話をした:あった93.7%, なかった6.3% 多忙化のニュースを見聞きした:あった98.7%, なかった1.29% (後者についてなかったと回答した教員は、現場に立つ人間として意識が低すぎないか…?) 自分の働き方は現状のままでよい(グラフ) とても思う5.1%, どちらかといえば思う27.0%, どちらかといえば思わない43.4%, 全く思わない24.5% 仕事が忙しい:とても思う55.4%, どちらかといえば思う37.0%, どちらかといえば思わない6.6%, 全く思わない1.0% 自分よりも忙しい教員がいる:とても思う74.1%, どちらかといえば思う18.3%, どちらかといえば思わない5.7%, 全く思わない1.9% ほかのきょいんよりも早く帰るのは申し訳ない:とても思う17.7%, どちらかといえば思う43.0%, どちらかといえば思わない24.1%, 全く思わない15.3% 同僚という集団を基盤としている教員にとって、「忙しさ」を相対化させる相手が常に存在している。そのため、自らも忙しい状況でありながら、「自分よりも忙しい」人を参照することで、自らの「忙しさ」を過小評価していく。「多忙を呼び込む」教員文化を指摘しているが、教員たちは自分より忙しい教員の存在を認識することで、実際には自らも十分に多忙であるにもかかわらず、「さらに忙しい状態」に自らを呼び込んでいる可能性がある。 肌感的に当たり前のことをデータで出すって大切。
2投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ主に部活動を中心とした、働き方改革の資料集です。 様々な立場に立って、働き方改革を考えなければならないなと感じました。
0投稿日: 2022.01.30
