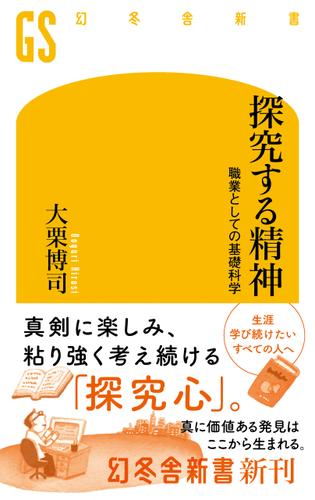
総合評価
(27件)| 12 | ||
| 11 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ大栗博士の著書はいつも新しい発見があって楽しい。 凡夫の戯言として、科学は森羅万象の仕組みの解明、法則性の発見が原点であるが、人間を遥かに超越する高次な生命体(がいたとしたら)も同じ結論となるのだろうか。例えば物の数え方は人間のルールであり、そのルールに基づく数学も別生命体にとっても畢竟同じ数学になるのか。大栗博士とも共著のある佐々木閑先生の「科学するブッダ」は科学の人間化がテーマでしたが、その辺りは私の浅薄な知識では読み取れず。はたまた我々の科学はあくまでも人間原理であって、その考え自体が誤りなのか
0投稿日: 2025.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ【琉大OPACリンク】 https://opac.lib.u-ryukyu.ac.jp/opc/recordID/catalog.bib/BC06491129
0投稿日: 2025.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ科学者として生きてきた筆者の体験から導き出された科学との向き合い方、またそこに至るまでに参考にしてきた書籍や人物の言葉が綴られている。 科学の歴史を知れるだけでなく、学ぶ意義やその方針を考える参考になった。
0投稿日: 2025.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本の雑誌・研究者本特集から。名を成した先生の来し方を自ら振り返りつつ、都度出合った書を紹介していくという、ブックガイド的ニュアンスも大きい一冊。
0投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ感銘深い内容であり、著者が類稀なる才能の持ち主であることが伝わってくる。理論物理学者でありながら、知的関心の分野の幅広さと、その深さに驚きを持ちながら読み進めた。才能ゆえに、学問を探究する上で恵まれたコースを歩み、日本に閉じこもることなく、文字通り世界を股にかけた活躍は爽快でもある。素粒子論の究極の理論と思われている超弦理論に早くから刮目し、取り組んでいた先見の明は素晴らしい。基礎科学は地図のない旅に例えられるが、正しい方向に進んでいるのか、果たしてゴールはあるのか、不透明ななかを手探りで進むが、10年先、20年先で成果が見えることがあり、比類なき精神力とともに粘り強さが求められる。短期的な成果を追い求めがちな昨今の日本が真摯に考えるべきヒントが本書にはある。研究費支給の判定に、目的や実現可能性だけで判断すると、将来の大樹の芽をつむことになる。欧米では、研究者自身の探究心が優れているか、遂行する能力にたけているか、人にお金をつける、という発想がある。集中力の例えとして、数学者の例があげられているが、含蓄ある内容なので以下に再掲する。数学を考えながらいつのまにか眠り、朝目が覚めた時にはすでに数学の世界に入っていなければいけない。常人の理解を超越した世界である。
8投稿日: 2024.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ地図を持たない旅人である研究者にとって、探究心こそ現時点で持ち合わせる最上のコンパス。 にしてもものすんごい経歴。ジリ貧の研究者が読んだらたぶん病む(でも嫌味な感じは全く無く、ただただ尊敬。日本人でこれだけ活躍されている研究者がいると思うとやっぱり誇らしい)。
1投稿日: 2024.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学者の方がどのように物理に興味を持って、どのように研究を進めていったかについて自伝的に振り返ってます。 正直なところ読んだ感想は、自分には学者は無理でしたごめんなさいという感じで、好奇心は合ってもここまでは頑張れないなぁと思ってしまって(集中力が続かないことには自信があります、私)。 ただこういう突き詰めて考えることのできる人に突き詰めて考えることのできる環境を提供することは大事だと思います。
1投稿日: 2023.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ1.基礎科学の研究者 2.その研究に社会的・経済的価値を見出すイノベーター 3.このような研究やイノベーションを支援するプロデューサー
0投稿日: 2023.07.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ学問のプロである学者の人の半生が書かれた本。多くの気づきと納得があった。 僕は自己啓発本として読んだ。学ぶとはどういう事なのかについて、理解を深められたと思う。自分は今何をすべきなのか、考える材料になった。
1投稿日: 2023.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学者の思考法 岐阜の商店街で育った少年時代の話が面白い 両親が働く店の奥で勉強。商店街の中にある本屋に行ったり。 ●考える材料 自分の頭で考えるためには、その材料である知識も重要です。知識が乏しくては自分の考えを豊かに広げることができません。 57 ●先人の教え 東島清 自らの知的好奇心に忠実であれ 佐々木閑との対談 「どんなものでも機能が発揮できるときが幸せなのだ」 アリストテレス『形而上学』 すべての人間は、生まれつき、知ることを欲する。 トマス・アクィナス『真理について』 人間の究極目標は、宇宙とその諸原因の全秩序が霊魂に書き記されること
0投稿日: 2022.10.31 powered by ブクログ
powered by ブクログブルーバックス「南部陽一郎物語」を読んで、積読本だった本書を手に取りました。がんの転移の可能性を指摘されたタイミングで、ずっと避けていま研究人生の回顧録を執筆したとのこと。結局、転移もなく、この本が生まれたのは若い世代にとっては幸運でした。物理を学ぶ学生だけではなく、まだ進むべき道を見つけていない若者にとっても良書だと思います。まさに、書名通りの「探究する精神」が小学生の時から発現し、その知的好奇心が研究人生をドライブして来たことが、丁寧に書かれています。知的好奇心の道標が、本であり大栗博司版「ぼくはこんな本を読んできた」になっています。最初に通った近所の本屋さんの名前が「自由書房」っていうのもいいよなぁ…もちろん物理学の名著、大著もありますが、最近出版された新書などでの気づきもいろいろ引用してあって、人生まるまる「自由書房」で自らを放牧している感じ。素敵です。著者は物理学が統一理論に向けてぐいぐい前進したいた時代の学者で、しかも数理連携の重要性の推進役の一人であることも含めて、物理学の「日の当たる道」が眩しく見えます。この新書を読んだのか4月の天気のいい朝、窓から日差しの溢れる電車の中で。はるか昔の新学期のワクワク感が蘇りました。
0投稿日: 2022.04.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ300ページ程で読み応えがある。好みの小説のようにワクワク楽しみながら読めるものでも無いが、表題を構成する各単語の意味を納得出来る形で平易に書かれている。小学生が読むのは辛いだろうが、内容的には小・中学生から読んでみて欲しい書物。未だ小さな子を持つ親にも読んで欲しい。
0投稿日: 2022.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ超弦理論の話は研究者時代の話であるが、小学生時代から大学生、大学院生、大学での職について書かれている。したがって科学に興味があってもなくても自分の生活と科学の関係を考えることに役立つ。 それよりも、本文で紹介される本が特殊な本ではなく、誰でもが一度は聞いたことがある有名な本で、しかもそれが文庫として紹介されている。わずか83冊であるが、これだけを読むだけでもだいぶ考えることが増えるであろう。 京大の下宿に1000冊の本があり、大学院を卒業する前には5000冊になったと書かれている。 本もかなり吟味されてここで引用されているので、いんようされた本を読む価値は十分にある。 今、1000冊の本が下宿にある学部生はどのくらいいるであろうか。1つの本棚に100冊の本が入るとしたら、本棚10個分である。 20年間で2000冊いかない私の読書が恥ずかしいばかりである。
0投稿日: 2021.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこういう自身の修養ヒストリーのエッセイを書くのは、湯川秀樹『旅人』以来、物理学者のたしなみになっているのかな。 興味の赴くまま一生懸命やっているうちに、現在に至っております、という率直な述懐。
2投稿日: 2021.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ前半は(大それたことですが)自分の人生に照らし合わせつつ、最後の章は基礎科学の大切さについて今年のノーベル賞受賞者の言葉も思い出しながら読みました。数学や物理などの理学の結果を、工学に進んだ自分は日々応用させてもらっているので、感謝しかないです。本書を読んで、知的好奇心に基づいた大学での研究に戻りたいな、と少し思いました。
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ海外経験も多く、そこからの指摘が良い。 理系の人なんだけど、高校国語の新学習指導要領にも言及をしていて、視野が広い。というか、やはり文系・理系と分けているような時代(他国ではとっくにそうなっている)では無いんだろうね。 お金の使い方でもそう。卒業生から学校への寄付、それを運用して、研究基金などにする。 日本もやればできること、いっぱいあると思う。
0投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者自身の研究者としての自伝をベースに、どうやって人生において真理を探求していったかが描かれている。世界的な研究者が研究者同士の交流を通じてどのように研究を行っていたか伺い知れる一冊。また著者のアメリカの大学での経験をもとにして、世界トップレベルの研究所ではどのように大学運営や研究のマネジメントが進められているかも議論されている。
0投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ超ひも理論の分野で成功している物理学者の自伝を追いながら、基礎科学の重要性を再確認するテーマ。事業仕分けの蓮舫でなくても、読んで学べることは多い。一番のハイライトとしては、天才少年がどのようなことに興味を持ち、どのような本との出会いがあったかを具体的に見れる点。やはり読書はとても重要。 アメリカの一流大学の研究者でも、突出した天才は稀だが探究を長く続ける体力には眼を見張るものがあるとのこと。 個人を尊重する自由な気風でこそイノベーションが生まれるのであれば、民主国家に豊かな国が多いことの裏付けと言えるのか。専制的な抑圧の国では限界があるのか
2投稿日: 2021.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ小学生時代の書店での放牧経験が大栗先生の基礎となった。僕自身、高校1年の時に近所にジュンク堂ができ、毎日のように通った。そこで、昔から好きだった小説の世界を広げることができたし、建築の世界に触れるきっかけになった。当時は、背伸びをして大人の世界を覗いている感覚が嬉しくて本を読んでいたと思う。ただ、動機はどうあれ、新たな世界に触れるきっかけに、書店の役割は大きかった。子供にも、放牧を経験させたい。 本書の1部は、大栗先生の本紹介のようでもあり、メモが捗った。 リベラルアーツ(特にコミュニケーション面)に対する意見、価値合理的な研究に対する意見には大いに同意。(「人にお金をつける」研究支援制度は面白い) 僕自身は、課題発見・解決を生業としているが、そんな近視眼的な目線だけでは、社会は面白くない。探究心を自由に炸裂させる或る種の利己的な目線も大事にしたい。
0投稿日: 2021.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ人にお金をつけるという研究支援制度はたしかに大切。また人を見る目は経営者にあると考える。意思決定時にその知見を活かせるといい。この人は違うなという提案でも良い。
0投稿日: 2021.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「重力とは何か」や「強い力と弱い力」を書いた大栗さんの新作。基礎科学の研究者である著者の半生を描くと同時に、哲学の時代からの科学の歴史を描いている。 私も企業の一研究員である中で、心に残ったのは「自身の知的好奇心に忠実であれ」ということと、「ミッションを大事にすること」の2つ。 私が感じたことは本の内容とは少し違うかもしれないが、自分が面白いと感じたことが一番意欲が湧くし、素直な気持ちで取り組めるということ。しかし一方で、好奇心の持ったもの全てに手を出していては時間が足りない。そんな時に、自身の軸=ミッションに沿ったものを選ぶべきであると思う。 特に、ミッションに沿うことは組織運営を考える上でも重要と思う。マネジメントの役職に就いた際にはぜひ意識していきたい。
1投稿日: 2021.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ安宅和人オススメだったので読んだ。物理学者の本で、そんな世界もあるのかと興味深くはあったが、文系な私にとっては、のめりこむほどではなく、途中でやめた。 他の物理学者も書いているけど、朝永振一郎はエッセイがうまくて、その紹介がよかった。 朝永の方をよんでみようかな
0投稿日: 2021.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
全体としては色々勉強になった。前半は著者の幼少期いかに天才的な子どもであったかみたいな少々自慢とも取られかねない記述が続くので、人によってはチクチクするかもしれない。後半に行くにつれて著者の研究とか人間関係への姿勢とか、参考文献なども色々出てくるので色々参考になることが多くなる。すごくいい本なんだけど個人的には進路選択のところで東大も行けたけどあえて京大にしましたみたいな記述は余計だと思った。十分優秀な人なんだから別にあえて東大を引き合いに出す必要なかった気がする。
0投稿日: 2021.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ大栗先生の半生をとおして、探究する精神とはなにかを伝えてくれる。基礎科学は夢やロマン、好奇心が駆動力だが、応用科学にとっても並列して重要であることがわかる。 本書で紹介された様々な文献も読んでみたい。 歴史をひもときながら、日本という国を、世界の視点で考えている。 欧米の大学、研究事情も伺えて、一気に読み終えた。
0投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大栗先生の研究人生と研究観をまとめた本.先生がどのような気持ちで研究生活を送っておられるかが書かれている. ポアンカレの大きなインパクトのある研究と限定的なインパクトの研究との比較に始まり,基礎研究を中心としながらも研究応用やプロモーションにも言及されている.理系の人だけでなく文系の人にもお勧めしたい一冊である.
0投稿日: 2021.05.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ自伝的内容だが、子供の頃のエピソードをはじめ研究者になるまでの探求する心の成長がよくわかります。 大栗先生が大学院でつけるべき3つの力として以下を述べてます。 「問題を見つける力」 「問題を解く力」 「粘り強く考える力」 粘り強く考える力という点において研究者の人達は答えがでるかどうかわからない問題でも何十年も費やすのだから脱帽です。 「探求する精神」について深く学ぶことが出来る本でした。 良書です。
1投稿日: 2021.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ「はじめに」を読んでビックリ。癌の手術をしていたんですね。幸い転移はなかったとあります。一安心です。最初の3分の2は著者の半生が描かれています。いくつかのエピソードは、他の著書にも書かれていることですが、初出のエピソードもたくさん載ってます。高等研究所の研究員として採用されたときに嬉しさのあまり後方宙返りしたとか、大学に入学するまでに読んだ本(ハイレベルです)とか、東大ではなく京大を選んだ理由とか、勉強した受験参考書とか、京大から東大に移る経緯とか。 後半の3分の1は、基礎科学を研究することの意義について書かれています。おそらく、本書で一番伝えたいことなのだと思います。また、大栗先生は研究者として一流なだけでなく、組織のオーガナイザーとしても優秀な方であることが分かりました。それだからこそ、米国の物理学会で成功をおさめることができたのでしょう。
1投稿日: 2021.03.29
