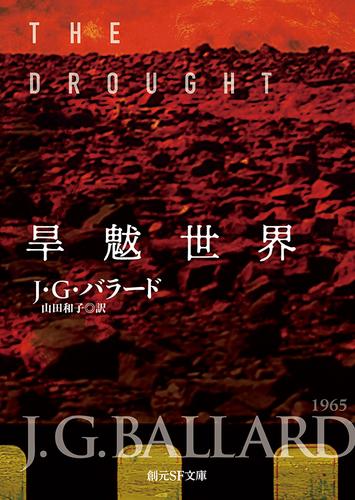
総合評価
(5件)| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
古典と呼ぶほどではないが65年発表というわりに古さは全くない。現在の肌感覚とシンクロする部分があり、極端な世界観にも関わらず現代的で違和感がなく自然に感じる。 まず感じたのは状況と心情の説明がいつもよりしっかりしていることで、今まで読んだ中では最も具体性があり分かりやすかった。 それは新訳のせいもあるだろうし、手堅く焦点の定まった文体で好感が持てる。 社会病理学的実験を試みる後期の作風に移行した後に書き直したものだと思ったが違うようだ。最初から意識が時代を先んじているということだろう。 現代の預言者という謳い文句に最も相応しい作品ではないだろうか。 ほぼ同時期発表の結晶世界が外から内にある中心点を目指し収縮していったのとは対照的に、本作はスケール大きめな空間の中でダイナミックに時間と場所が切り替わる構成になっている。人物も多彩で、それぞれに世界観があり世界崩壊後の暗澹たる終末を描いているわりに暗さがあまりない。ストーリーも結晶世界では夜型の不健康さが目立っていたが、主に早朝、昼間をメインに進行するのでわりと健康的だ。キャサリンとフィリップ・ジョーダンという著者にしては珍しく比較的まともな(置かれた状況に対して諦めていないという意味で)キャラを投入していて、それに加えクィルター夫人のコミカルさも手伝い、暗く重くなりがちな内容に一定の光度の維持と軽さを与えている。 時折カオティックにはなるが絶望的な急降下というわけではなく、全体的には緩やかに傾斜した斜面を下方に向かって滑り落ちていくような印象だ。 不条理な末期的世界との辻褄を合わすかの如く個性の誇張が肥大化しているような終盤の展開は、よくある低予算の安っぽいアニメのようだ。漫画やアニメというのは特に意味はなく、人は何故そんなものを楽しんでいるのかと言えば、現実が歪み崩壊して本能的な感覚が極端な形になった像に識閾下で反応しているからではないのかとふと考えた。それらから言葉や文字を抜いたら何も有意義な意味は無い不可解な絵の羅列か奇怪な人形劇になる。それが後半に描かれている非論理的な躁鬱の楽園のような世界なのかもしれない。 第一章前半部の各エピソードが独立性をもっていて、著者の他の作品の補足説明になっていることもポイント高い。(個人の見解) 著者のエッセンスがバランスよく分配配置してある代表作と言っていいだろう。 題材が著者の得意とするインフラ停止なので悪いわけがなく、それを中心に様々なテーマが描かれている。 主人公は悪化する環境から人々が続々退避して過疎となって行く土地に残り続け何かを期待しているが、その荒廃へのある種の安堵感はブラックな職場がブラックすぎて次々人材が抜け、逆にブラックさが無くなってくるような感じか、あるいは破綻寸前の業務が無意味となった会社で遊んでいるような状況に似ている。 荒廃して行く土地にあえて残り続けている人々に一目置いているが、その場所から離れたとたんに同僚意識がなくなり関心を失うというのもよくわかる感覚だ。 主人公は出ていくつもりだと言いながら全く出ていく気配がない。そのモラトリアムを享受している様は、まるで就職を拒む引きこもりのようである。とはいえ職業はいつもの医者でいざとなれば行動するし自分の責務をこなすのだが、人間関係も含め問題を棚上げにして最後の最後まで自ら決断を下さない様は、先延ばし癖というおおよそ真っ先に批難されるだろう欠点に斬新な光を当てている。 てっきり最後まで移動せず出る出る詐欺だろうと思ったが、突発的な出来事からあっさり旅立つ。物事が変るきっかけなんてそんなものだし自然な流れだと感じた。 そのシーンの叙述もすごい。普通このような物語が大きく転換する場面では、希望を感じさせる前向きな描写にすると思うのだが、〈心が真空に近付いていく〉などとまるで工場で死んだ目をしてライン作業をしている時の精神状態みたいなテンションの下がることを書いている。こんなのを少年ジャンプなどでやったら即打ち切りだろう。 様々な見方が出来ると思うが、この物語は労働からの解放を描いていると解釈するとかなり分かりやすくなる。 実際、著者はヴァーミリオン・サンズの序文で未来の労働について言及していたりするしこじつけとも言えないだろう。 セツルメント参加を逡巡するところなど、特にその本質が顕著で、入所を打診して断られる場面は、実務とは無関係の非合理な理由で落とされる面接と同じだ。 けっきょく貨幣が水に交代しただけで社会が崩壊しても別の新たな社会が登場し、その社会に適応するには正常だった世界と同じように自我を犠牲にしなければならない。 労働の本質とは義務という正義を根拠にした自我の取引、増減であり、現代の諸問題の核心もほぼそれに収束すると言っていいだろう。自我をどこまで差し出すか、あるいは満たすか減らすかで未来の運命は決まり、限度を超えると裁判沙汰になったり最悪は自死を選んだり、週刊文春にスクープされる著名人のように他人の自我の破壊を引き起こし引退を余儀なくされる。考えてみればシンプルな作用なのだが著者以外こういう本質的な面を指摘する者を見たことがない。あるいは大抵の人々にとって取るに足らない事なのかもしれない。 著者はアバンギャルドな前衛アート的な文脈で語られることが多いと思うが、極めて現実的な視点を土台に作品を作り上げていて、決して奇をてらっただけの作家とは違うことがよくわかる作品となっている。 旱魃と言われても日本では水害の方が問題になることが多くあまりピンとこないが、世界的には深刻な問題だ。当然最終的には水資源の奪い合いになり危機に際した人間性が露出するが、しかしその状況に主人公は期待を抱いている様子が描かれる。確かに水が乾いて行くという状況にはどこか清々しさや一種の満足感がある。 生命の源、活動の根幹を成す水の減少とともに様々な事物の関係性が解消されそれらの本来の役割も失われていく。 その様相を描くことに実際的な役に立つ意義があるのかと言えば、ないだろう。しかし、その社会という縛りから解放された状態こそが人の奥底に眠る理想的な観念のようなものではないだろうか? バラードの作品に感心するのは普段は無視して無いことにしているが確実に存在する意識を追求しているからだ。それはまともな人間なら下らないと白眼視するようなことなのだが、それを真面目に描こうとしている極めて希有な作家だ。 最近、不確実性というワードをよくきくが、それは今まで当然のことだった物事が通用しなくなる、つまり常識が信じられなくなりどう対処すればいいのか不透明になってきているということだと思うが、結局世の中に当然というものはなく不確実なままの常識で辛うじて支えている状態の日常があるだけだと言える。確実と言える時は自分がそれを知っていて実行できるか、過去の体験や既出の事実だけで、それ以外に唯一確実なのは自分の存在だけであり、社会というのは少しの亀裂で不安定になる程度の確実性で機能していて、その中に放り込まれた微小で確実な自我が不確実な常識の支配によってバラバラにされる場なのだろう。作中のビーチなどまさに不確実性の塊であり、不透明で混迷した世の中で非常識について考えることは有効かもしれない。 常識という概念は明確に定義できず日々更新される大量の情報によって成立している。そんな曖昧な概念を正義として目標を設定し義務が発生する。 しかしあまりに情報過多で複雑になりすぎ情報の精度や価値の喪失に怯えているのが今の世の中だと思う。 湖と河が干上がり底が見え土地との境界が無くなり全てが一体化してしまえば底の意味もなくなる。それまで世界を構成する条件や基準になっていた存在は、砂漠に捨てられている空き缶と同じゴミと化し元の存在の情報価値は意味をなさなくなる。水の消滅は情報の消滅であり、必要最低限の物と関係性だけが存在する。これはほとんどの情報は整理するまでもなく人を不自由にさせる余計な荷物になるだけで実は不要なものだと伝えているのではないだろうか。 主人公のランサムはこの状況を受け入れたなどと言いながら最後には楽園から一人旅立つが、ラストシーンが表現しているのは、極限まで情報を削ぎ落した本来あるべき世界の姿なのかもしれない。 バラードは時代の方が遅れて来るほど現実を追求した作家であるという認識がより明確となる作品だった。よくわからないがポストモダンとはこういうことだろう。
0投稿日: 2025.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ旱魃世界 人類の愚かな振舞いにより、海からの水の恵みが途絶えた世界。 湖は干からび川は流れを止め、生き物は死に向かい、陸地は砂漠化していく。 人は海水を蒸留して得るわずかな水と引き換えに、愚かにも、更に塩で海を浸食していく。 連想されるのはマッカーシー「ザ・ロード」でありマルセル・セロー「極北」であり、映画「マッドマックス」や「風の谷のナウシカ」だろうけど、水を求めて南へ向かう姿は、なぜかスタインベック「怒りの葡萄」をイメージしてしまう。 主人公が「意識の中に携えてきた内なる景観(イナーランドスケープ)の周辺領域を越える旅」とは、なんだったのか……最後まで読んでも捉えることは難しい。 初めの頃に書かれていたハウスボートの中に飾った「雑誌から切り抜いたイヴ・タンキーの『緩慢な日々』の写真」が、最終章のタイトルとされていること……うーん、わかりません。
1投稿日: 2024.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログあっという間に暑い夏はすぎて秋。酷暑をふりかえりつつ、タイトルからして暑そうなバラードの作品を読む。燃える世界の改訂版の位置付けとのことですが、読みやすさも違う し、意味合いも違う文脈が多くなったような気がします。特にラストシーンなどかなり違うのではないでしょうか。これ翻訳の違いなのでしょうか?原文が変わったのでしょうか? 読んだからといってこれからの人生が何か変わるかといえば何も変わらないですが、なんといってもバラードの魅力はそのシュール・リアリズムの絵画のようなビジュアルにも訴える強烈なイメージでしょう。この印象は一生残ります。「沈んだ世界」も再読してみよう。
2投稿日: 2021.09.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ原題「The Drought」のとおり、干上がった終末世界が描かれる。「結晶世界」の前に書かれたもの。「結晶世界」だといずれすべて結晶となってしまうのか、という静かな結晶化の世界という気がしたが、ここでは旱魃に抗うが、でも受け入れてもいる、しかしのたうち回っている騒々しさを感じる世界。 バラードはシュルレアリズム絵画が好きだということだが、文中にも主人公ランサムの部屋にはタンギーの絵があり、その絵が今いる旱魃世界だとしばしば連想する、と出てくる。自分もタンギーの絵が好きなのだが、旱魃の世界はちょっと連想しなかった。ただ、灰色のバックにすべっとした石が描いてある絵は、時間が止まったような感じがして、それが干からびて砂漠化した世界を想像するかも。確かにこの旱魃世界では砂に埋もれて行くのだ。 絶景写真集で出てきたアフリカの鉱物採集町の砂に埋もれた廃墟を思い出した。しかもこの旱魃世界になった原因は過去50年にわたって生成された莫大な量の工業廃棄物のせいで海面に膜ができて水蒸気ができなくなった、ということになっているのだ。 またバラードは第二次世界大戦中の上海租界に育ち日本軍の捕虜施設にも入ったという。その戦争中の混沌とした上海での生活もこの旱魃世界に反映されているのかな、などとも感じた。自伝もでているようなので読んでみたくなった。 雨が降らずに旱魃にさらされた土地に住む医者ランサムの逃避?生活。海にそそぐ川、湖沿いの街に住むランサムを中心に、建築家の友人や動物園を営む女性、川で生活する若者といった者たちが旱魃世界で営む生活。海を求めて住んでいた川を下るが・・ しかし旱魃の海岸にに10年も住んでいたのだ。もっと遠くへ行くには力尽きたのか、とかそういうことはあまり考えず、この暑さの中で旱魃世界を読むという、この空気感を味わえばいいのかな。 原題:The Drought 旱魃 1965年に改題改変されイギリスで出版。 ※The Burning World (燃える世界)が1964年にアメリカで初出版。 1965年発表 2021.3.19初版 2021.4.16購入 21.8.6読了
1投稿日: 2021.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
突如現れた謎の有機物によって世界中の海洋の表面が覆われ、海水の蒸発が阻害されて水の循環が機能しなくなった世界。湖も河川も次々に干上がり、水を求める人々が海岸地帯へと避難していく中、医師ランサムは湖に係留したハウスボートの中で、色々と理屈をつけながらぐずぐずと内陸部に留まり続けていた。彼を見捨てて愛人と海へ向かう妻を見送り、不思議な安寧を感じながら町に留まる彼の周囲に見え隠れする、同様に海への避難を良しとしない独自の価値観に囚われた人々・・・絶望的な状況の中、次第に暴力に満ちていく町で、ランサムが選択した行動とは? バラードの「破滅三部作」のひとつ、「燃える世界」の改稿版。鴨は「燃える世界」未読ですが、かなり印象が異なるそうです。 鴨は「破滅三部作」の他2篇「沈んだ世界」「結晶世界」を読了しており、この2作との印象の違いに、何よりも驚きました。極めてリアル。海水面の上昇によって人類の生活圏が急速に狭まりつつも、熱帯性の動植物の暴力的な生命力に満ち溢れた「沈んだ世界」、万物が結晶化して活動を停止させ、静かに緩慢に滅びていくという”作り話”そのものの「結晶世界」と比して、旱魃で地上の水分が干上がり、水を求めて海辺に殺到する人々の姿(でも海水をそのまま飲むことはできないので、必然的に暴力的な争奪戦が発生して・・・)という、バラード作品にはまずあり得ないと言っても良いぐらい現実的で絶望的でヒリヒリした舞台設定は、眼からウロコでした。バラード、普通にリアルな作品も書けるのね・・・。 ただ、リアルな舞台設定とは言ってもそれはあくまでもバラード作品における比較論の話であって、バラードが描きたかったのはやはりいつも通り、滅亡そのものではなく、滅亡の風景の中を彷徨する人間精神の変容だったのだろうと鴨は思います。その観点でも、主人公ランサムの行動の意味がある程度合理的に理解できるこの作品は、他の作品とは一線を画すると感じました。 最後の最後のあの1行は、どういう意味なんでしょうね。普通に読めば、死の淵に瀕したランサムが最後に見た幻覚、と捉えるのが順当かもしれません。が、幻視者バラードが読者に見せつけた”救いの光景”なのかもしれません。どちらとも決めつけずに、良いお酒を飲んだ時のような心地よい酩酊感を持って読了したい作品ですね。
6投稿日: 2021.06.15
