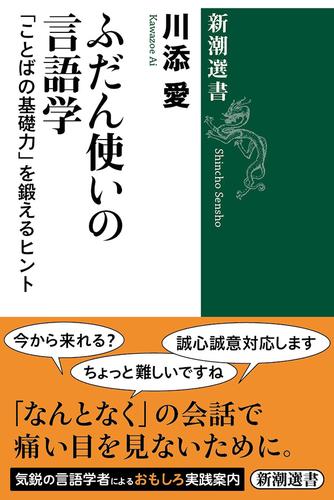
総合評価
(31件)| 6 | ||
| 13 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ- 「君のことも大事にするから」- 背景的な意味 - つまり君以外にも大事にする人物が存在する。これが背景的な意味 - 「今から来れる?」言外の意味を意識する - お願い、命令の意味を言外に含んでいる - 後から取り消せるという意味で背景的な意味とは異なる - 「来れる?でも、単に聞いてるだけで恋って意味ではないよ」が成り立つ - 「海賊王に俺はなる」 - かきまぜ現象 - 「が」「に」「を」などが比較的自由な語順で現れることを「かきまぜ現象(scrambling)」と呼び「かきまぜ文」と呼ぶ - A.この土地は東京ドームが二つ入る広さだ。 - B.?この土地は、二つの東京ドームが入る広さだ。 - 「二つの東京ドーム」にはそれらが現実にあるかのような「実在感」がある。 - このスペシャル感に関する違いは言葉で表すのが難しく、言語学でも長年考えられている問題だ。 - 副助詞 - 「は」は、それまでの文脈ですでに登場しているものに付く - 「が」は、それまでの文脈には現れておらず、新たに登場するものに付く - A.あっ!あそこに狸がいるよ! - B.?あっ!あそこに狸はいるよ! - A.誰が買ってきたの?私が買ってきました - B.?誰が買ってきたの?私は買ってきました - 格助詞 - 「が・の交替」 - A.将棋の強いおじさん - B.南国の強い風 - a.将棋が強いおじさん - b.?南国が強い風 - 「[将棋の強い]おじさん」と「南国の[強い風]」の違い - 似たような語の並びだが**構造が異なる** - 普段の言葉を振り返る - 私は自分の使おうとしている言い回しに自信がないとき、国立国語研究所の提供する『現代日本語書き言葉均衡コーパス』の検索サービス「少納言」(https://shonagon.ninjal.ac.jp)で検索することがある - 「言葉の乱れ」問題 - IT黎明期には「パソコンを立ち上げる」も奇妙と言われた - 「とても」は、かつては「とても太刀打ちできない」「とてもそんな気になれない」のように否定と一緒に使われる用法しかなかった
0投稿日: 2025.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログおもしろいのは知っていた。でも、他に読みたい本も多く、購入するまでには至っていなかった。BSテレビ東京の「あの本、読みました?」で「日本語界隈」が紹介されていた。これは読んでみたいと思った。で、図書館にリクエストした。しかし、なかなか届かない。どうやら他にも頼んでいる人がいたようだ。で、ぶらぶらと図書館の棚を見ていたら、本書を見つけた。ここのところずっと小説を読んでいたので気分転換に読みだした。いやあ、おもしろい。最初に出てくる問題。「良い宿がいっぱいでさ」僕は何の気もなく宿がいっぱいあると思ってしまった。ふん?と考えると、確かに満室であるともとれる。「あなたのせいで負けたんじゃない」励ましている?むっちゃディスってる?(ディスるって初めて使った)確かにこれは気をつけないといけない。同じことばでも違う意味を持っていたりすると誤解を生む可能性があるというわけだ。助詞の「が」と「は」の使い方はいつも気になる。「日本語練習帳」か他の日本語の本か何かで読んだのだと思うが、初出かどうかの違いだとか説明を読んでも、結局雰囲気だけで使い分けている。そう、本書の中でも雰囲気や気分によって判断するところが多かったように思う。ことばを置き換えてみるとちょっと変だよねえとか、ここ否定にするとなんか変な感じがするよねえとか。ということで、理論言語学者はもっときちんと説明しているのかもしれないが、専門用語とかは分からないので、まあ雰囲気で判断するよりない。これ、でも、僕が日本に生まれてずっと日本語を使っているからということであって、外国語として日本語を学ぶときはまた別だよな、とも思う。ということで、外国人が日本語をマスターするのは難しいよな、と思ったりするわけだが、漢字が大変なだけであって、しゃべるのはそれほどでもないとも聞く。うーん、どうなんだろう。日本語を教える機会もこれから出てくるかもしれない。ちゃんと勉強しないとだな。ところで、同音異義語が多いことがダジャレを生んでいるとどこかで読んだことがある。それが落語のオチなんかにも使われる。ことばを上手に使って、上手に楽しめばよいのかな。
0投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログKindleで読んだので、マーカーひきまくり。 同じ言葉や文でも、人によって解釈や感じ方が違うことがある、ということを改めて考えさせられました。 理論言語学、おもしろそう!と思いましたが、「言語を科学的に研究する分野」だとのことで、特に第3章のテストは、ほぼ感覚のみで生きている私には向いてない気がしました。 あいまいな表現には極力気をつけようと思うとともに、言葉のあいまいさが、お笑いや小説の面白さにつながるのかな、とも思いました。
7投稿日: 2025.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の書きっぷりに慣れてきたこともあって、こんなに分かりやすい新潮選書は初めてかも。 「無意識の言語知識」がいかに豊富で、無意識であるだけにそれの使い方に自覚的でないことに気付かされる。 格助詞と副助詞の使い分けなんて、どうしてできるのか分からないし、人に説明できない。 まだまだ勉強しなくちゃだな。
1投稿日: 2024.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ川添さんの本は、「言語学バーリトゥード1」 に次いで2冊目。同じ言語学に関する内容でも、 「バーリトゥード1」は、話題が身近でサクサク 読めたが、こちらは、沢山の例題を用いて、 言葉の違和感について読み進める 学術書のようで、少し趣きが異なるが、 実用的で有益な内容だった。 私達が普段、無意識に使っている言葉の使い方 や、曖昧さが、思いがけない誤解を与えたり、 トラブルに発展する場合がある。 主語が大きい場合は、特に注意が必要。 形容するかたまりが、長くなると、曖昧になり、 誤解を招きやすい。 誘導尋問のかわし方など。 日常で役に立つ言葉の使い方が、他にも 沢山解説されている。 個人的には、特に相手のぼんやりとした言葉を 自分が都合よく受け取っていないか反省。 普段、無意識に使っている自分の言葉の使い方 には、個人の癖があるが、意識して見直す 必要があると思った
11投稿日: 2024.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログプロレス好きということで知った川添先生の言語学入門書。 普段使っている日本語の曖昧性はどこから来ていて、どうやったらそれを避けることができるかが説明されている。人の文を読んで私自身感じることが多い違和感の正体が少し理解できた気がする。そういう文を書きがち、話しがちな人に読んで欲しいと思うが、概してそういう人は本を読まないのよね。 具体例は忘れたが、高校の英文和訳の授業で、意味が伝えづらい文の語順を入れ替えることで見事に問題を解決した友人のことを今でも憶えているので、私自身こういう理論が好きなんだろうと思う。 「最強のニーチェ」と同様、最後にご自身の背景が述べられており、グッときた。
0投稿日: 2024.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ありそうでなかった言語学ドリル」(カバーの紹介文より)ではない。強いていうなら、「言語学で使われる分析テスト」という括りで、分析手法の一部を紹介した点は珍しいかもしれない。註釈で、論文を含む参考文献が多少豊富に提示されている点も好印象。 理論言語学者が、専門とその関連分野から日常に役立ちそうな項目を「いいとこ取り」して解説。一般的な言葉の使い方のヒントを伝える。 理論言語学者とは、たとえるなら「〜に鑑みて」が「〜を鑑みて」になりつつあるのはなぜだろうと考える人たち。「に」が正しいと考えたり指摘したりするわけではない。 自分にとって新しい情報はほぼなかったように思うが、「少納言」という検索サービスは初めて知った。試しに「〜に鑑みて」と「〜を鑑みて」の用例を調べると22件vs16件。一番古い用例は「に」1978年、「を」1995年とあるので、やはり「を」の方が新しめの使い方なんだな〜と楽しめる。
1投稿日: 2024.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語を【自然現象】として観察し、「それらの現象が存在するのは、私たちの無意識の知識がこうなっているからだ」という仮説を立て、それに従って理論を作り、現象を説明しようとする理論言語学の本。 人が何年も母国語を使うと無意識の知識が備わってくることは、外国語を学んでいると実感しますが、言葉が【自然現象】だという発想はなるほど確かに。 超難しい日本語を、母国語だから無意識レベルで使ってるけど、それでもややこしい間違いはよくあります。そんな日常遣いで発生する日本語の違和感を、置き換えたり何かに当てはめてみたりしながら根気よく解きほぐしていく。言語学者って根気強いのね、私は途中我慢できなくて読み飛ばしちゃいました。
0投稿日: 2024.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本人が当たり前に獲得している日本語の微妙な難しさの理由が分かる本。 外国人が日本語を習得するのはそりゃ大変だわって納得。でもまぁ読んだからって言葉巧みな話術が身につくわけではなさそうだ。
0投稿日: 2023.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログあまり自分向けではなかった ふだんぜんぜん意識せず使ってるけど日本語って難しい SNSなどで違和感ある文章読むと何がおかしいんだろうと考えるようになった
0投稿日: 2023.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ普段意識をしない言葉使いや、言語化して説明が難しい話し言葉、書き言葉を丁寧に解説された良書。専門的な内容を一般の人にわかり易く伝えて頂くことに徹してあり、文章1つ1つが極めて丁寧に記述されている。後段に「言語の難しさはその知識が個人的なものであると同時に公共的なものである点」との視点には大いに感服した。著者の1ファンとしては短い「あとがき」からも本書に対する好意が増した。
0投稿日: 2023.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ尊敬する翻訳者さんの紹介で購入。言葉遣いの「違和感」を明解に説明してくれる良書。わかっていたはずの「正しい言い回し」がなぜ正しいのかが理論的に分析され、すっきりと腑に落ちる。日本語を書くこと、話すことを仕事にしているすべての方におすすめできる本。
0投稿日: 2023.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ理論言語学の知見から日常の会話のちょっとした違和感を読み解くきっかけを与えてくれる。 例題とそれに対応するメソッドを組み合わせてしかも豊富に提示してくれていて興味が尽きない読中感。 情報量が多くて少し頭を使うが、筆者の言語学を一般の人たちにも親しみを持ってもらいたいという気概がびしびし伝わって気持ちがいい。 それぞれの方法の説明は割愛しますが、筆者のような引き込む力のない文章では退屈させると思うので、是非読んでみて欲しい。そう思うのです。
1投稿日: 2023.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言語学バーリ・トゥード: Round 1 AIは「絶対に押すなよ」を理解できるか』を読んで面白かったので、本書も読んでみた。 東大出版会の前者に比べて、本書は学術的な新書という印象。面白さよりも、きっちり知りたいという人にオススメ。
0投稿日: 2023.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の経験では、言語学の本は以下のパターンがある。 ①真面目な人が、真面目になって書いた ②真面目な人が、面白いと思って書いた ③面白い人が、真面目になって書いた ④面白い人が、面白いと思って書いた 川添氏の④を読んだ後に、この③を読んだので、諸所の表現から④を思い出してしまい、①にも読めそうな③なのに④にも読めるという現象が起こった。これでも門外漢にはだいぶ敷居が高いようにも感じるので、④にあたるバーリトゥードを読んでからこの本を読むのが適切かもしれない。 何にせよ、言語学的アプローチがわかりやすく書いてあったので、言葉を生業にする方にも大変有用に思う。
0投稿日: 2023.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早く読んでおけばよかった言語学の本。「背景的な意味」「会話的含み」「ゼロ代名詞」「かきまぜ文」などの提示の方法が新鮮で、どれも納得させられた。置き換えテストでの「二つの東京ドーム」のツッコミと、他人との意見の不一致での「タピる」が特によかった。「笑えない冗談」のあたりも、やはり言葉の持つ背景的意味の怖さを解き明かしてくれている。全編を通して掲載されている例文やテストのクオリティが高く、解説もたいへんわかりやすい。付箋33枚!
0投稿日: 2022.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語話者だと会話する時には深く考えずに喋っている言葉だけど、科学的に分析すると複雑なんだなと。そして日本語は曖昧な部分が多いのだなと。だから忖度とかに慣れきって、会話だけでなくあちこちで忖度されるのかなぁと思ったりして。
1投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の図書館で川添愛さんの本はないかと検索したところ、この本を見つけたので、借りて読んでみました。 会社の後輩で、言葉の「曖昧性」に対してとっても無頓着(に見える)な人がいるのですが、この本を読みながら「その人に読ませたい」と強く思いました。 それはさておき、「言葉は自然現象」であるとか、「人によって言葉の使い方・解釈が異なる」という前提は、忘れがちだけれども大切な考え方だと思いました。 また、文の適切さの「テスト」という考えは、目からウロコでした。 とりあえず、この本を読む限りでは、自分自身の言葉の使い方については、ある程度、妥当なものであることがわかりましたが、言語学については、まったく知識が足りないことを痛感しました。 ということで、この本の参考文献を参考に、他の言語学の本にも触れてみたいと思います。
0投稿日: 2022.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ第一章:無意識の知識を眺める:意味編、第二章:無意識の知識を眺める:文法編、第三章:言葉を分析する、第四章:普段の言葉を振りかえる。理論言語学は、私たちの頭の中にある言語に関する知識を研究対象としてるという。言語の知識とは文法のことかと考えたけど、本書を読み進むうち、それだけではないことが分かってくる。学校で長いこと国語の勉強をしてきたけど、文法に強くもならないし、漢字も今ではもう忘れているものが多いありさまである。でも、日本語の知識は様々な形態で頭の中に蓄積されていたのだと思う。本文の文例で、それはちょっと不自然だぞ、とか、そうは言わないな、などと感じるのはその蓄積の賜物なのだろう。ところが、その知識をこれだと取り出すことは難しい。本書を読んで初めてそういった知識の上で日本語を使っているのだということが分かった。
0投稿日: 2022.08.13 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜSNSで炎上が起きるのか、その傾向と対策の書としても読めるが、ことばの演習課題がきっちり提供されているので、数学や物理の教科書に取組むような覚悟がいる。
0投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語の難しさを言語学の観点から説明されていて興味深かったが、素人の私は内容が膨大すぎてちょっと飽きてしまった
0投稿日: 2022.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログふだん何気なく使っている「言葉」。そうして何気なく使っているのに、うまく使いこなせなくて困る「言葉」。なぜ使えるのに使いこなすのは難しいのか。 まえがきによればこの本は『理論言語学の入門書ではない』とのことだが、無意識な言葉の操作というのはどういうことかを言語学の観点から解きほぐす内容となっている。 この本の意図するところは『自分の中の「無意識の知識」を意識し、その中にみられる傾向や法則性をつかむことだ。そうすることで、「他人が自分の言葉をこのように解釈するかもしれない」とか、「自分のこの言い方は不自然に聞こえるかもしれない」などといったことに気づく機会が増える。そうなれば、別の言い方を考えたり、用例を調べたり、他人の意見を参考にしたりする機会も増え、状況に合った「最適解」が見つかる可能性が高くなる。」 つまり「正しい言葉」を学んでマウントを取る、ということではなく、より謙虚に言葉と向かい合うきっかけを作ることを意図している。「言葉と向かい合う」ためのヒントとして、ふだん使いの言葉の要素を理論的に分析し、一般的に自然に正確に伝わりやすい言葉・文章とはどういうことか、が考察されており、興味深い。 意味とはなにか、文法とはどういうことか、その無意識にうまく解釈を重ねていく自然言語の奥深い世界に触れると、人工知能における”ふだん使い”に耐えられる言語処理の困難さにも気づかされる。
1投稿日: 2022.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて、”母国語”と言うのは、すごいものだな、と思った。 言語学の本を読んだ後で、この感想とは、自分の語彙の無さに呆れてしまうが、でもやっぱり、すごいのだ。 著者が理論言語学の研究対象が『私たちの無意識の言語知識である』とおっしゃっているのだが、この”無意識”と言うのが、日本語を母語としていない人にとって、いかに難解であるか。本書の中で、沢山、具体例が上がっており、それを改めて著者の解説とともに読むと、こんな曖昧なこと・膨大な量を、日々の会話で瞬時に判断していたなんて、と驚くのだ。 ・・・とここで一旦ブレイクし、面白かった具体例など、かなり長文で記入し、更新をかけたらエラーになって追記した部分が全部消えた(涙)さすがに再度書く気にはなれず断念。再読の機会があれば、また気になったところを書き残すこととしたい。
2投稿日: 2022.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ『言語学バーリ・トゥード』が面白かったので読んでみた。しっかり言語学の内容もあるのに言語学を一切知らなくても簡単に理解できるようになっている。言語学界隈はやっぱり怖いなぁ。笑主語の大きさに注意
2投稿日: 2021.12.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者Twitter: @zoeai https://twitter.com/zoeai 文春オンライン(2021.12.3): #1「俺は海賊王になる」と「海賊王に俺はなる」の違いとは? 言語学者が分析する『ONE PIECE』の名台詞にみる“文章術” https://bunshun.jp/articles/-/50090 #2「全然オッケー」は日本語としておかしい? 気鋭の言語学者が抱く“言葉の乱れ”問題についての“違和感” https://bunshun.jp/articles/-/50091
2投稿日: 2021.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ数多くの例題があり、楽しみながら日本語の感覚を確認できた.*や?の付いた文は著者の通りの違和感を持てたので、良しとしよう.「置き換えテスト」や「入れ替えテスト」を活用して、更に感覚を磨きたい.p213で紹介のあった「少納言」は早速活用を始めている.
2投稿日: 2021.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学とタイトルにつく本を何冊か読んでみて、いまだに言語学という広い範囲に何が含まれているのかつかみきれていないのだけれど、この本は言語学の中でも理論言語学のエッセンスを集めた本のよう。 川添愛さんの著書はこれまでにも何冊か読んでいるけれど、わかりやすく平易に説明する技術に長けた方だなと感じる。 この本も、これまでのものより専門的な本なのかなと思っていたら読みやすいので一気に読めてしまい、あまりに駆け足で読み進めてしまったので、きちんと理解できているのだろうか…?と首を捻りながらページを捲ると、第4章に出てくる総復習的な練習問題で「わかるぞ…!」と、意外としっかり内容を理解できていたと達成感を得られる。まるで進○ゼミのような本。予想外に実用的で驚いた。 「ふだん使いの言語学」というタイトルが表すとおり、日常的に言葉を扱う場面で役に立つ知識を中心としてまとめられており、専門書というよりは実用書のような手触り。作文技術に特化した本というわけでもないのできっぱり実用書的な内容を求めるひとには物足りないだろうけれど、言葉のしくみや理論の解説が多めなので言葉遊びが好きな人間には考えたり想像したりしながら読み進められて楽しい。 言語学の学習者ではないので、どの程度専門的な分野に触れられているのかはわからないのだけれども、専門外の人間にとって興味を持ちやすい部分が厳選されている気がする。 これを足掛かりにもう少し詳しく言語について掘り下げたいなと知識の扉を開く入り口としてちょうど良いかも知れない。
3投稿日: 2021.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ理論言語学を修めた著者が、日本語を書く上で歪み捩れのないわかりやすい文を書くにはどうするべきかを解説してくれる。 でも、意味の取り違えのないわかりやすい日本語を書くなら本多勝一の日本語の作文技術をお勧めする。彼の主義主張には賛同しないが、この作文技術は読む価値がある。
2投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本語って、 面倒くさい。 でも、面白い。 自分の文章を添削される時、 相手が何を直せと言ってるのか分からない人は、 読んでみるといいのではないかと思う。
2投稿日: 2021.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ川添さんの本2冊目、これも非常に面白かった。挙げられている例文が尽く面白く、都度ハッとさせられる。私達がもつ当たり前に脳内で(都合よく)変換する脳内母国語スキル!中学生くらいの文法のテキストにもいいと思った。
2投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終えてみるとタイトルの「ふだん使い」がすとんとくる。著者と同様、言語学徒として学んだことが日頃の言語活動になにかと役に立っている立場なので、一般読者としての評価・感想はむずかしいが、入門書としてはよみやすくわかりやすく、高校生、大学生のあいだに(つまり社会人になる前には)一度はであっておいてほしい「(理論)言語学」のおいしいトピックがぎっしり詰まっていた。 言葉(空気にように当たり前にあやつれる母語)がわかったりつたわったりするしくみを意識してじっくり学んだり、自他の言葉遣いの異同をどのように捉えればいいか考えたりする機会は、現況では高校までの国語や英語、大学の語学のクラスでもほとんどないけれど、言語学を学べば学ぶほど、こういうちょっとした知識抜きでコミュニケーションや語学に困難を感じたり失敗したりしているなんてほんとにもったいないなと思ってしまうので、こういう本がたくさんの人に読まれてほしいけれど、どうやって布教すれば伝わるんだろう…(選書を手に取る層は読書人口の中でもかなり限られてしまいそうだし…)
7投稿日: 2021.02.09
