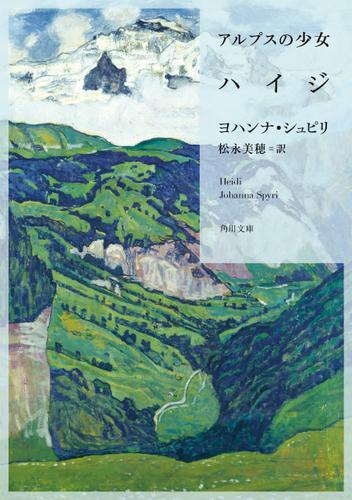
総合評価
(6件)| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀に書かれた小説。アニメのオープニング、断片的なシーンは覚えているが全体のストーリーは全く記憶していなかったのだが、原作の面白さを聞いて読んでみた。病弱なクララが山の生活で健康を取り戻していくというハイライトだけでなく、偏屈なお爺さんが再びコミュニティの一員となっていくなど、大人になっても人は変わることができるというストーリー。一貫して勤勉を美徳とするプロテスタント的な価値観が書かれている。篤い信仰は金銭的にも報われるというオチもあり。ハッピーエンドになるとわかっていて読めるので良い娯楽だった。 ーーーー 19世紀のスイスは既に中立国となっていたが、お爺さんは若い頃には傭兵として出稼ぎに行き、その息子も死因はわからないが他国で亡くなっている。羊飼いのペーターはおそらく6年生ぐらい、ハイジは3年生くらいだが、2人とも小学校に行かずに文盲。ペーターのお父さんはおそらく出稼ぎで不在、おばあちゃんとお母さんの現金収入はペーターが世話する羊のミルク程度かと思われる。 一方で、フランクフルトのゼーゼマン家(クララの家)は複数の使用人が暮らし、主人のゼーゼマンの職場はパリ。職種は不明だが汎欧州のスパンの事業を行っている。 ハイジは天真爛漫で良い子だけど、それ以上に羊飼いのペーターの無学ぶりとことばを知らないが故か、もともと境界知能児なのかが心配になる。ハイジのおかげでペーターがやっとアルファベットが読めるようになることは救いだ。
3投稿日: 2025.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログNHKでアルプスの少女ハイジの作者、ヨハンナ・シュピリの特集番組があり、それを見て本書を手に取りました。私自身子供時代にアニメで見たことはありましたが、本書でやっと本当の原作に触れたことになります。本書は大人が手にとっても全然問題ない水準だと思います。ぜひ大人も本書を読んでほしいと思いました。 アニメでは、ハイジ、ペーター、クララという子供たちの交流が中心になっている印象を受けますが、本書を読んで改めて実感したのは、クララという少女が周りの大人たちを幸せにしていく存在だということです。おじいさんを改心させるだけでなく、羊飼いのペーターのおばあさんや、クララのお父さん、おばあさん、さらにフランクフルトに住むお医者さんの心さえも癒すのです。 スイスの美しい自然と神様への祈り、その中心にはハイジという存在がいます。大都市フランクフルトに連れていかれたハイジは活力を失います。しかしアルムの大自然に戻ったハイジは、まるでアルムの小屋の裏にある巨大なもみの木のように、まわりを元気にするマザーツリーのような存在になるのです。さらにいえば、ハイジは読者の心すらもきれいにしてくれると言ってもよいでしょう。本を読んでこんなにすがすがしい気持ちになったのは久しぶりでした。
1投稿日: 2025.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
終盤の、ハイジの後見人が2人もできたとか、わたしにもハイジへの権利を与えていただければ、わたしの晩年にはあの子が面倒を見てくれて、そばにいれくれるかもしれませんとかですごく冷めた
0投稿日: 2024.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ近年翻訳された版。改めて大人向け完全版として読んでみて、再度発見も。基本的なストーリー理解がアニメベースなので、違うところも発見しながら。
0投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもたちだけではない。大人たちの、喪失から立ち直る成長物語でもある、あらゆる人に勇気をくれる物語。 宮崎駿の日本アニメ版ハイジを見て感銘を受け、ながらく原作の方も読んでみたいと思っていた。 できるだけ、子ども向けに内容を編集・省略されたものではなく、できるだけ原作に近いものを。 本書は、ブクログのあらすじにある通り、大人にこそ読んでほしい素晴らしい物語である。 主人公のハイジの、持ち前の明るさだけでなく、フランクフルトでの苦しい時期を経て、その苦しみの中でも得ることができた教養や価値観を元にさらに成長し、周りを癒し、そして周りの子どもたちだけでなく大人たちも、ハイジとともに悲しみの中でも前を向いて歩けるようになっていく… それら全ての物語が、登場する人々が愛おしく思えてくる。 訳がとても読みやすく、スラスラ一気に読めてしまった。キリスト教の考えに基づいた、私たちの生きる日々を支えてくれる名言だらけだ。けれど説教くさくなりすぎず、ポカポカと読みながら明るい気持ちにさせてくれる描写の仕方もとても素敵で、飽きがこない。 他の訳も読んでみたい。 けれど、一番最初に読んだハイジが、本書で良かった。 以下備忘録がてら目次をば。 そして目次の下に、日本版アニメハイジと本書ハイジの内容の違いや印象に残ったところの感想を書く。 ネタバレにもなるのでご注意ください。 目次 ◆第1部 ハイジの修業と遍歴の時代 アルムのおじいさん/おじいさんのところで/牧場で/おばあさんのところで/二人のお客さんと、それに続く事件/まったく別の生活と、たくさんの新しいこと/ロッテンマイヤーさんの落ち着かない日々/ご主人が帰ってきて耳にした、前代未聞のことがら/おばあさま/ハイジの喜びと悲しみ/ゼーゼマン家の幽霊/アルムへ帰る旅/日曜日、教会の鐘が鳴るとき ◆第2部 ハイジは習ったことを役立てられる 旅行の準備/アルムへのお客さま/恩返し/デルフリ村の冬/まだまだ冬は続く/遠くのお友達が動き出す/アルムでのそれからの日々/誰も予想しなかったこと/お別れしても、また会える さて、なんせハイジに関してはアニメから入り、アニメのハイジが大好きになり本書を手に取ることになったので、アニメと本書の内容を比較しながら感想を書いていきます。 おおまかな感想としては、子どもに見てもらうため、かなりアニメにはオリジナルエピソードを盛り込んだのだなぁという印象。その差が面白い。 アニメ見たのが数年前なので記憶違いがあったらごめんなさい。 ・アニメのハイジの、とても特徴的な赤い丸いほっぺは、原作の描写の通りにキャラデザに落とし込んだ結果なんだ〜!と分かり嬉しくなった。 ハイジの容姿は黒髪の癖っ毛の巻き髪に黒い目、真っ赤な林檎のようなほっぺと説明されている。言われてみればアニメにも癖っ毛な感じが表現されているかも。 ハイジが楽しそうだとこちらも嬉しくなり、フランクフルトでハイジが悲しむことすら禁じられふさぎ込んでいく姿は、アニメでも本書でも見ていてとてもつらい。 ちなみにロッテンマイヤーがデーテ(ハイジのおばさん)から聞き出したハイジの洗礼名であるアーデルハイトは、ハイジのお母さんと同じ名前であるとのこと。 アニメではなかったが、本書では序盤の方に、ハイジの母アーデルハイトも夢遊病になったことがあり、アルムで暮らす前、ハイジがアルムの環境に耐えられず夢遊病になるのではないかと危惧される場面もあった。 しかしハイジをむりやりフランクフルトへ誘拐していったデーテよ…デーテの描写や性格はアニメとほとんど変わらず。 最初にハイジに何枚も服を着込ませていたのも本書と一緒。 ・アルムのおじいさんは「おんじ」とアニメでは呼ばれていたが本書ではその描写はなく。分かりやすく呼ぶためのアニメのオリジナル呼称なのか、アニメを作成する際参考にした訳でおんじと呼ばれていたのか。 またアルムのおじいさんは、アニメでは描写を省略されていたが、傭兵として出稼ぎに行っていた過去がある。クララの介護がすんなりできたのも、事前準備だけでなく、傭兵時代の経験がもとになっている。 ハイジが帰ってきた後、アニメではなかったハイジがおじいさんに絵本を読み聞かせする描写があり、その話の内容におじいさんは自分の人生を重ね、自分の態度を改め教会に行き、村の人たちと積極的に交流を持とうと決意し、村の人たちも喜んで歓迎する描写がある。泣いた。 ・クララがハイジをフランクフルトに引き留めようと縋り付く描写はアニメほどなかった。一度か二度くらい? というかフランクフルトでのクララとハイジの交流の様子は必要最低限といった感じ。 ハイジが帰った後アルムへの旅が先送りになった時も、最初は嘆き悲しむも父ゼーゼマンの説得を受け前向きに療養に励む描写も。 そしてアルムにとうとうやってきた時。 アニメではクララをどうやってアルムの山の上に過ごさせるか(特に車椅子問題)、みなかなり頭を悩ませていたが、本書ではそのような議論はなく、おじいさんが70歳にしてクララを片手で抱えるなど、割とあっさり解決。 よくテレビで言われる名言、「クララが立った!」という台詞は本書にはなかった。 アニメではそういう簡潔で印象的なセリフが必要で考え出された台詞だろうか。この台詞の代わりに、小説という媒体での素晴らしい表現でクララが立つことができ、歩くことができるようになるまでの描写は泣きどころである。 クララが歩けないのは心身症であるという話をよく聞くが、本書ではアニメほどクララが立つことを恐れる描写はなく、おじいさんが「ちょっと立ってみようか」と初めて声をかけた時にもすんなり「わかった、立ってみる」と立つ努力をしようとする。 アニメを見ると確かに心身症かもしれないなと分かりやすく思えるが(大袈裟なほどクララが立つことを怖がっている描写が多いので)、本書を読みながら、原作者はどういう意図であったのだろうと、本当に心身症のつもりで書いたのかが少し気になるところ。 またこの話題に関しては論文があった気がするので、どのハイジを論拠に心身症と判断できるとしたのか読んでみようかな。 ちなみにクララがブロンドの髪だと描写されていたのは、おばあさんに歩く姿を見せた時の一度のみ。 ・山羊飼いのペーターの、食べ物にありついた時のニーッと幸せそうに笑う表情の描写は、まさにアニメ通り笑 本書を読んでいると、とても素朴で素直な少年であることがわかる。 アニメと違うのは、最後までクララとハイジ、ペーターが三人一緒に仲良く遊ぶシーンはほとんど全くないこと。クララが立てるようにハイジとペーターが二人で肩をかすシーンくらいだろうか。 またアニメと全く違うところが他にもあり、アニメではクララの車椅子が風で飛ばされおじゃんになっていたが、本書ではクララにヤキモチを焼いたペーターが車椅子を突き落とし粉々にしたというところ。 アニメでもクララに最初は打ち解けず拗ねるシーンはあったが、車椅子を壊す展開よりはさっと仲良くなって三人が楽しそうにしているところを見せたかったのだろうか。 ちなみに本書では車椅子を壊した後、ハイジや村の人々など周囲の発言により、ペーターはやっと自分がしたことがとても悪いことだと気づき、自分の悪事という名の影にひどく怯えつづける。 自業自得とはいえかなりその様子は気の毒であるが、おじいさんやクララのおばあさんなどに励まされ、改心した。このペーターの悪いことをしたことを悔い、成長していく場面はとてもいい話だと思う。 もちろん、ハイジに教えられながら字を覚え読むことができるようになったところも(その教材として使われたABCの歌が脅し文句のオンパレードで笑ってしまった)。 ・フランクフルトのゼーゼマンさんのお屋敷の使用人たちは、良くも悪くもコミカルで面白い。 印象としてはほとんどアニメ通りなのだが、彼ら、本書ではアニメよりもへっぴり腰である。 ゼバスティアン(アニメではたしかセバスチャンだった気がする。子どもが呼びやすいように英語読みにした?)が、ハイジがやってきてから度々起こすロッテンマイヤーのアクションに、影で笑い転げる様子などまさにアニメ通り。本書でも読みながら笑いすぎだよ!笑と思わずツッコミたくなるほど。 お屋敷の使用人では、ゼバスティアンだけがハイジが日に日にふさぎ込んでいくのをつらい思いで見守っている。 ティネッテの性格の悪さもアニメ通り。 ロッテンマイヤーも大体アニメ通りのふるまいと性格。ただアニメではお前までクララに付いてアルムに来るんかい!とツッコミを入れたくなるくらいクララに対して過保護な描写があったが、原作ではそこまでの描写はない。代わりにハイジをこんな目に合わせて!とゼーゼマンに叱られる描写もない。 アニメのロッテンマイヤーはなんだかんだアルムまでやってくるガッツはあったが、本書ではゼバスティアンがハイジを返す時に訪れたアルムの話を聞いて(ちなみにこのゼバスティアンもふもとの駅で別れただけでアルムまで行ってはいないのである)、最初からアルムへの同行拒否。 アニメでは、あれでもロッテンマイヤーを愛情のかけ方を間違えただけのちょっと可哀想な人ポジションで少しでも愛着を持ってもらおうとしてあの登場頻度になったのだろうか。 ・アニメから入った身としては意外だったのが、ハイジを夢遊病と診断しアルムに返すよう強く促してくれたお医者さん先生の物語である。 本書では、フランクフルトでの先生とハイジの接点はごく少なかったがゆえ、先生が視察を兼ねてアルムに訪れた時、ハイジが自分を覚えて慕ってくれることに驚く先生の描写がある。 またアニメでは省かれていたが、先生はハイジが帰った後、立て続けに妻と娘を亡くし、かなりやつれてしまっていた。 けれどアルムにやってきて、ハイジに慰められ、おじいさんと仲良くなり、アルムが大好きになり帰っていく。物語の最後では、デルフリの村でおじいさんの冬の住居の隣に、引退後先生が終の住処としてやってくる話もあり、おじいさんの今後も、ハイジの今後も希望に満ちた終わり方をするのだ。 本書ではアニメ以上に大活躍・愛おしく思える人物として描かれている人である。 彼の喪失ゆえの悲しみから立ち直る姿は、その時にかけたハイジの言葉は、さまざまな迷える大人たちに響くものだろう。 ・あとは細かい違いやアニメで省略されていた話になるが… ヤギのユキちゃんは本書ではユキピョンと呼ばれている。ユキピョンが売られて食べられるかもという話はアニメオリジナルのものであり、本書でそんな悲しい展開はないので安心してほしい。 クララと一緒にアルムにやってきたのは、アニメではロッテンマイヤーだが、本書ではクララのおばあさんである。馬に跨るなど逞しい姿を見せる。 アニメほど奇天烈な印象はないが(おばあさんが屋敷から帰るときの目眩しのサプライズパーティーもアニメオリジナルの話)、明るく擦れていない、それでいて良い意味で信心深い性格はアニメ通りである。 ハイジに文字を読めるようにしてくれたのがおばあさんなのも本書も一緒。 ただアルムに似た絵が飾ってある秘密の部屋は本書にはない。アルムに似た絵は本書では絵本の中に描かれており、おばあさんはそれをハイジにプレゼントする。泣ける。 学校にハイジやペーターが行くシーンは本書にもあるが、ごくわずかである。 アニメのようにそりすべり競争なども、他の村の子どもたちの描写も本書には一切ない。 他にもいろいろあるが、ひとまずこの辺だろうか。 他の訳も読んで、訳の違いも見ていきたいがいつになるやら。 原作も、原作をもとに子ども向けに膨らませていったアニメのストーリーも、どちらも違って完成度が高い…と比較してみて改めて思った。
21投稿日: 2023.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ「100分de名著」で取り上げられていたこと、WOWOWでアニメを久しぶりに全部見たことで新発見があり、原作も読みたくなった。 昔の訳で読んだ覚えが在るが、何となく古い言い回しで挫折した気がするので、躊躇していた。忘れた頃、この文庫を見つけたら、「100分de名著」に出ていた方の訳だった。 訳が素晴らしい。すんなり読めました。 アニメではいろいろストーリーが付け足され、変更してるところもあったんですね。 いくつになっても、人は変われる!と希望が持てました。大人こそ読んで欲しい。
18投稿日: 2021.10.02
