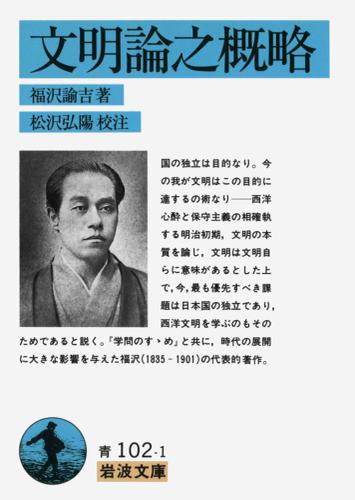
総合評価
(21件)| 5 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、日本が西洋に対して後進国であるという当時漠然と共有されていた認識に対して、文明という概念を提出し、問題の所在を剔抉して見せた。黒船が強力なのは明らかであるが、しかしそれだけをもってして黒船を持たない日本が遅れているというのも何か違和感が伴う。そこで、文明という尺度によって、何が西洋をして黒船を生み出したのかを図式化してみせたのである。それはとりもなおさず、外圧に苦しむ日本がとるべき道を示すことに違いない。ここで著者が誠実で用意周到であったのは、西洋を到達点とするような尺度として文明を示さなかったことにある。黒船のような優れた技術を生み出した西洋の文明は確かに日本よりは進んでいるが、日本はそれに追いつくにとどまらず、追い越してさらに先へ進むことも可能なのである。つまり、著者は本書を著した時点で既に西洋目標としていない。西洋の体現している比較的進んだ文明の本質を解明することで、西洋のその先の文明を目指していたのである。 西洋文明の限界を知っている我々としては、後知恵として、著者の目指した世界を著者と同じ路線で突き進むことの危険性を指摘することはできる。しかし、その本質を見出すという作業は、今日の行き詰まりの原因をより具体的に見いだし、問題の解決策を模索するためには、われわれにとっても必要な準備作業である。本書は今日なおその価値を失っていないといえる。 一方で、本書は漢学者や国学者に向けての西洋学案内という側面もあったようである。著者の議論は、政治学から初めて倫理学、史学に進み、最後には簡略ながら具体的な政策提言を行っている。西洋学の初学者を想定して書かれているだけあって丁寧な議論が展開され、具体例をふんだんに示しながら東洋学との比較が詳細に行われている。とはいえ、本書冒頭から、それも傍論として、国民国家の概念や国家の正統性についてかなり突っ込んだ議論を紹介しており、これだけでも当時の人々、それも西洋学の素養のない読者がどれだけ本書を理解できたのかかなり怪しいところである。さらに続けて、統計に基づいた社会科学、計測可能な体系的教育論、宗教と倫理の峻別、西洋的な近代化の歴史理論など、懇切丁寧に解説しているとは言え、読者の理解をはるかに上回るであろう議論が展開される。当時どれだけこの書が正しく理解されたかは別として、今日の視点からは、著者が文明というものを表層的な最新技術や洗練された生活様式ではなく、そうしたものを可能にする経済基盤や国民に根付いた思考様式であると理解していたことがよくわかる。 当時の知的水準からすると、はるかに高い水準で議論を展開している本書ではあるが、これだけ痛烈に東洋学をやっつけておきながら、東洋学者を西洋学振興の味方に付けようという意図があったというのであるから笑ってしまう。批判される側としては、こみ上げる怒りを抑えるだけでもやっとのことであったのではなかろうか。とはいえ、誠実な読者はこれだけ広範にわたる最新学説を展開されて舌を巻いたであろうことは想像に難くない(実際のところその議論のほとんどはギゾーに追っているようだがその当否は今後の課題としたい)。
0投稿日: 2025.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本に足りないのは実学。数理学や近代科学。人は生まれながらの貴賎の差はないが、実学を学べば地位の高い人・裕福な人になる。実学を学ばなければ、地位の低い人・貧しい人になる▼国を守る。国のために命を捨てる。自由独立を守る。国民のわずかがこうした気概を持っているだけでは独立は守れない。国民ひとりひとりが独立自尊の精神を持たねばならない。「日本人は日本国をもってわが本国と思い、その本国の土地は他人の土地にあらず、わが国人の土地なれば、本国のためを思うことわが家を思うがごとし。国のためには財を失うのみならず、一命をも抛(なげう)ちて惜しむに足らず。これすなわち報国の大義なり」『学問のすすめ』1872 日本では被治者は治者の奴隷だという発想がある。政府に任せきり、国の事に関与しない態度。日本には政府はあるが、国民(ネーション)がまだない。まず精神的な態度を身に着けるべき▼儒教は徳による統治ばかりで、体制の維持に利用されてきた。停滞の原因だ。違う意見を持つ多くの人が、さまざまな事柄に関して議論する自由の気風を制限してきた。また、儒教は能力のある者を抑圧する身分制度を正当化してきた▼明治維新が起こったのは人民に、知恵の力が育ってきていたからだ。ペリー来航はきっかけに過ぎない。中国と違い、武士が天皇から権力を奪ったことも、自由の気風が生まれる遠因になった。『文明論之概略』1875 祭祀(まつり)と政治(まつりごと)を明確に分けるべき。政治は損得勘定にかかわるものであり政党がすべきこと。天皇は自ら政治に当たるべきではなく、民心融和の中心にならねばならぬ。天皇は党派によらない権威であるからこそ、危機に際して国民の一体化を容易にする。天皇は国民統合、歴史伝統の象徴であり、直接に政治権力を行使しないことにこそ意味がある。『帝室論』1882 (以前から支援していた金玉均による朝鮮近代化が西太后に潰された甲申政変1884の翌年) 中国や朝鮮は儒教思想に染まったままだ。日本はこれらの地域と共にアジアを興そうと考えることなく、西洋文明国と行動を共にすべきだ。『脱亜論』1885 ********************* ※大坂(堂島)生まれ。適塾(現大阪大学, 緒方洪庵)に学ぶ。
0投稿日: 2022.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ全編を通じて、権力の偏重と行政の無責任さ、学者の見識外れ、民衆の政治的関心の低さなどを嘆じる義憤が、通奏低音のように流れている。やむにやまれぬ思いで、一気に書かれたものであろうと推察する。 今から1世紀半近くの昔に書かれたものであるが、その訴えるところはいささかも古びてはいない。つまりは、この国の基本的なところは、明治の初め頃と何も変わってはいないということなのである。
0投稿日: 2022.01.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ文明を進めて独立を得る。文明とは、社会を人為的に操作する度合い?そのためには、規則や制度を整えるだけではなく、人民1人1人の独立の気風が必要。
0投稿日: 2021.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ解説によると「福沢の生涯最高の傑作」との事。福沢が日本近現代最高の思想家であるとするならば、本書は日本近現代最高の思想書という事になるのかもしれない。福沢の思考方法には今読んでも唸らされる点が多々あるし、現代人でもコレに匹敵するモノを書ける人間はいないだろう。約150年前にコレを書いたというのは凄いとしかいいようがない。が、この時代・このタイミングだからこそ書けたのかもしれないとも言える。ただし、本書は出版当時はあまり読まれず、読まれるようになったのは1930年代と1950年代以降のようであるが。 文語体で少々読みにくく、内容をしっかり理解できているのか覚束ないのが難点ではあるが、その辺は注釈書や現代語訳で補いながら原文を読む事により、著者の息遣いを感じる事が有益に思える。
0投稿日: 2021.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ当時としては飛び抜けて開明的だったと思うが、今も読むべき古典なのかどうかは疑問だ。 ただ、明治の初め(出版は明治8年)に、日本のこれまでの歴史とその本質はまだしも、西欧の歴史と科学・技術の本質をこれだけ深く捉えていたかと思うと驚きを禁じ得ない。 内容よりも、その姿勢を学ぶべきだろう。クリティカルライティング(orシンキング)の見本だ。 ・P224:日本の宗旨には、古今、その宗教はあれども自立の宗政なるものあるを聞かず。
1投稿日: 2018.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ幕末から明治にかけて世界の中の日本の置かれた状況を冷徹に分析し、日本の植民地化を防ぎ国の独立を守るためにこそ西洋の文明を取り入れる必要があることを、論理的、体系的に、かつ相当の危機感をもって書かれた警醒の書。福沢は、内に憂国の思いを持ちながらも決して原理主義、絶対主義に堕することなく、全ての物事を相対的に比較衡量して、常に目的のための最適な手段を考えるリアリストである。単なる西洋かぶれの思想家ではないことがよく分かった。
0投稿日: 2018.03.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代語ではないので 読み辛いといえばそうなのだけど 著者に出来る限り近い言葉に触れた方が 真意が伝わり易いと感じる。
0投稿日: 2017.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ福沢諭吉の主著。ギゾー、バックルなどの文明史論を取り入れつつ、西洋文明と日本文明を対照させ、西洋文明に学ぶ必要を説く。明治8(1875)年刊。 本書の主張は明白である。西洋文明を目的とすべし、というのがそれだ。はたして今日の日本は、様々な点で西洋化された国となった。では、福沢の願いは叶ったといえるか。否であろう。本書刊行の70年後に日本は独立を失うことになったし、また現在の日本にしたって、福沢が指摘した問題点をどれほど克服したといえるだろうか。そもそも福沢が西洋に学ぶべしとしたその第一は精神(気風)である。が、現実の西洋化はもっぱら文物・技術・制度の面で行われてきた。今日、日本が直面している様々な問題に分け入っていくと、「結局、日本の文化が…」「日本人ってのは○○だから…」みたいな話になって終わることが多い。つまりは日本人の精神、気質や気風が問題となっているのであり、福沢が出した宿題がそのままになっているといえる。 また、本書は日本が西洋近代というものに直面して間もないころに書かれたものである。福沢は西洋と対面するその最前線にいた人物であるから、本書の記述からも福沢が抱いていた危機意識・緊張感といったものを垣間見ることができる。昨今の政治的議論の弛緩ぶりを想うとき、思考のスタイルといった点でも、本書から学べることは多そうである。 ――――――――――― 『文明論之概略』は古い本なので、21世紀人たる私たちが読むにはいくらか障害がある(文体とか)。そこでお勧めしたいのが丸山眞男『「文明論之概略」を読む(上・中・下)』(岩波新書)との併読である。まさに「精読」といった感じの解説本であり、福沢の思想のより深い理解へと私たちを導いてくれるだろう。ただ、このプランは文庫1冊プラス新書3冊で、読み通すのが少々大変ではある。そこでより簡便なルートとして斎藤孝による現代語訳がちくま文庫から出ている。未読なので訳の出来不出来等のコメントはできないが、近代の古典の現代語訳という試みは評価したい。古典は多くの人に対して開かれてあるべきだ。
0投稿日: 2017.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本経済新聞社 小サイズに変更 中サイズに変更 大サイズに変更 印刷 リーダーの本棚最善選択する知的強靱さ 慶応義塾長 清家篤氏 2015/6/7付日本経済新聞 朝刊 「知的な強靱(きょうじん)さ」を感じさせる著書に引き付けられる。 座右の書は福沢諭吉の『文明論之概略』だと言うと、立場上そう言うのだと思われるかもしれません。しかしこの本は大学院生のときに、日本の計量経済学の先駆者の一人である小尾恵一郎教授(当時)から勧められて読んで以来、本当に座右に置いています。最初は「説教くさい本ならすぐに閉じよう」とやや消極的に読み始めましたが、読み出したらやめられず一気に読了しました。 自分の価値観と合致していた本なのでしょう。あらゆる事柄を相対的にとらえるべきだという福沢の考えが、冒頭の「軽重、長短、善悪、是非等の字は相対したる考えより生じたるものなり」によく表れています。何か一つのことを絶対視する思想とは全く異なる立場です。この本の核心は、徳(モラル)と智(ち)(インテレクト)をさらに私のそれと公のそれとで私徳(律儀(りちぎ)などを意味する言葉)、私智(事物を理解し工夫する力)、公徳(公平などを意味)、そして公智(物事の軽重大小を判断する力)の4つに分け、最も大切なのは公智であると説くところです。相対的な価値の中から、その時々で最善のものを選択するということで、知的強靭さを必要とします。絶対的な価値を唱え続けるよりずっと難しいことです。 知的強靭さを感じる本を読むと、自分も少し強くなれそうな気になります。感銘を受けた猪木武徳著『戦後世界経済史』に「可能性と蓋然性は異なる」との一文があります。何でも起こりうる「可能性」と、実際に起きる見込みである「蓋然性」の違いをデータと論理によって判別すべきだと指摘しています。 研究活動の合間を縫い、余暇に読む本は実在の人物を題材にした作品が多い。 一つの価値を絶対視する考え方が苦手なのは父の影響もあるかもしれません。建築家だった父は大学卒業と同時に海軍に入隊しました。どう見ても軍隊には不向きで、実際、軍隊はこりごりだったようですが、一方で妙に海軍びいきでもありました。それが不思議でしたが、大学生のときに阿川弘之の『暗い波濤(はとう)』を読んで少し理解できました。戦争や旧日本軍の愚かしさを知りつつも、自分の任務をなんとか果たそうとする学徒兵の姿が描かれています。いかにも軍人風の説教をする参謀に「私ら、軍人が商売とちがうんです。偉い人に勲章もらわすために死にに行くんやないですよ」と学徒兵がたんかを切る場面が象徴的です。その後、しばらく阿川作品にはまり、山本五十六、米内光政、井上成美の3部作も読みました。やはり惹(ひ)かれたのは、あまりすっきりしないようにも見える『米内光政』です。 厳しい状況の下で、物事の軽重大小を判断し、相対的に少しでもマシな選択をするのは決してすっきりしたものとはなりません。米内が日米開戦直前に参内し、このままではジリ貧だから開戦すべしという論に対し、「ジリ貧を避けようとしてドカ貧になりませんように」と言上したあたりに、公智を感じます。実は陸軍軍人の中にも、保阪正康の『破綻―陸軍省軍務局と日米開戦』の描く石井秋穂のように最後まで開戦を避けようと努力した人もいました。懸命に戦争回避策を考えた「理性派」「寡黙な人たち」が、大言壮語して開戦を主張する「感情派」「放言癖」の人たちに悩まされる姿を保阪はビビッドに描いています。 誠実な生き方を記した書にも共感する。 仕事ぶりにとどまらず、人生の歩みとしても、誠実で淡々とした生き方を描いた本に引かれます。吉村昭の綿密な取材調査に基づいた一連の小説は愛読書ですが、その仕事や生活ぶりが彷彿(ほうふつ)されるようなエッセー『わたしの流儀』、『私の好きな悪い癖』なども好きです。マルクス・アウレーリウスの『自省録』はローマ皇帝の生き方を記した本です。彼が父について書いた「彼にたいする喝采やあらゆる追従をさしとめたこと。(略)大衆にこびようともせず、あらゆることにおいてまじめで着実で、決して卑俗に堕さず、新奇をてらいもしなかったこと。(略)人生を快適なものにするすべてのもの(略)がある時にはなんら技巧を弄することもなくたのしみ、無い時には、別に欲しいとも思わなかったこと」は今日でもリーダーの生き方の模範だと思います。 (聞き手は編集委員 前田裕之) 【私の読書遍歴】 《座右の書》 『文明論之概略』(福沢諭吉著、岩波文庫ほか) 《その他愛読書など》 (1)『戦後世界経済史』(猪木武徳著、中公新書)。「市場化」をキーワードに世界経済の半世紀にわたる変化を検証。 (2)『暗い波濤』(上・下、阿川弘之著、新潮社) (3)『米内光政』(阿川弘之著、新潮文庫)。米内をよく知る人たちの証言を調べ上げ、様々な資料を活用して「内面がわかりにくい人物」とされた米内の実像に迫っている。 (4)『破綻―陸軍省軍務局と日米開戦』(保阪正康著、講談社) (5)『わたしの流儀』(吉村昭著、新潮社)。日常生活での様々な発見や小説の題名のつけ方など著者の人間性があふれる随筆集。 (6)『私の好きな悪い癖』(吉村昭著、講談社) (7)『自省録』(マルクス・アウレーリウス著、神谷美恵子訳、岩波文庫)。皇帝の公務の傍らで、折に触れて浮かぶ感慨や思想などを断片的に書き留めた書。 せいけ・あつし 1978年慶応義塾大学経済学部卒業。92年同大学商学部教授。2009年5月から現職。専門は労働経済学。『雇用再生』など著書多数。
0投稿日: 2015.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
日本国の独立と外国交際について説く。そのための文明。 読むのにやたら時間がかかった。次読むとしたら現代文訳かな。 特に前半は例え・比喩が冗漫。削れば半分以下の厚さになりそう。この時代の本には珍しくもないけど。 智徳を4つに分けて説明しているのは面白い。 「ただこの改革を好む者は、藩中にて門閥なき者か、または門閥あるも常に志を得ずして不平を抱く者か、または無位無禄にして民間に難居する貧書生か……概してこれをいえば、改革の乱を好む者は智力ありて銭なき人なり」(109頁)。 読書の技法(佐藤優)に同様の指摘有。 「甚だしきは昔の小児の言行を録して今の大人の手本と為し、この手本に従わざる者を名けて不順粗暴と唱るが如きは、知徳の行わるべき時代と場所とを誤りて……」(188頁)。 まさに。この本にも当てはまるけど。
0投稿日: 2014.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2013.06.05読了)(2007.11.12購入) 「「文明論之概略」を読む」丸山真男著、全三巻を読んだので、原文にも目を通しておこうと読み始めたのですが、とても読んだという情況ではなく、一通り目を通した、というところです。通常1時間に40頁ぐらい読めるのですが、この本は、1時間に20頁というペースで、なかなか大変でした。これから読もうという方は、現代語訳も出ているようなので、そちらを読むことをお勧めいたします。 解題で、津田左右吉さんが各章の内容を要約しているので、拝借しておきます。 第一章は、ものごとの利害得失を考えるには、その本位(規準または基本というほどの意義であろう)を定めることが必要であることを述べたものである。 第二章では、今の西洋は文明の域に進んでいるが、日本はまだそこまでいっていないから、西洋の文明を学ぶべきだと言っている。 第三章は文明の本質を考えたものであって、まづ文明は人の生活のあらゆることがらに関するものであることを説き、次に文明の根本は智徳の進歩であるといっている。 第四章から第七章までは智徳についての考察であって、文明は国民一般の知徳の働きの総合せられたもの、すなわち人民全体の気風の現れ、であるので、それが文明の精神である、したがって智徳の与かるところの治乱興廃も、この気風によって生ずるので、一二の英雄などの力ではないという。 第八章は西洋の文明の由来を論じ、第九章はこれに対して日本の文明の由来を考えて、西洋ではいろいろの思想が並存しているのに、日本ではなにごとも政治的権力に支配せられているので、それがために文明が進歩しなかった、と言っている。 第十章に於いて、強い調子で日本の独立を論じている。外国との交際を盛んにすることによって独立の気象を練磨すると共に、日本を文明の域に進めることの外には無い。 【目次】 凡例 緒言 巻之一 第一章「議論の本意を定る事」 第二章「西洋の文明を目的とする事」 第三章「文明の本旨を論ず」 巻之二 第四章「一国人民の智徳を論ず」 第五章「前論の続」 巻之三 第六章「智徳の弁」 巻之四 第七章「智徳の行はる可き時代と場所とを論ず」 第八章「西洋文明の由来」 巻之五 第九章「日本文明の由来」 巻之六 第十章「自国の独立を論ず」 解題 津田左右吉 後記 富田正文 諭吉を理解するために 遠山茂樹 ●お互いを知ることが大事(20頁) 交際は、或は商売にても又は学問にても、甚しきは遊芸酒宴或は公事訴訟喧嘩戦争にても、唯人と人と相接して其心に思うところを言行に発露するの機会となる者あれば、大いに双方の人情を和らげ、所謂両眼を開いて他の所長を見るを得べし。人民の会議、社友の演説、道路の便利、出版の自由等、都て此類のことに就いて識者の眼を着する由縁も、この人民の交際を助るがために殊に之を重んずるものなり。 ●異端妄説(22頁) 古来文明の進歩、其初は皆所謂異端妄説に起らざるものなし。「アダム・スミス」が始て経済の論を説きしときは世人皆これを妄説として駁したるに非ずや。「ガリレヲ」が地道の論を唱えしときは異端と称して罪せたるに非ずや。異説争論年又年を重ね、世間通常の群民は恰も智者の鞭撻を受て知らず識らず其範囲に入り、今日の文明に至ては学校の童子と雖ども経済地道の論を怪しむ者なし。 ●西洋文明(24頁) 今世界の文明を論ずるに、欧羅巴諸国並に亜米利加の合衆国を以て最上の文明国と為し、土耳古、支那、日本等、亜細亜の諸国を以て半開の国と称し、阿弗利加及び墺太利亜等を目して野蛮の国と云い、この名称を以て世界の通論となし ●太平安楽(26頁) 今後数千百年にして世界人民の知徳大に進み太平安楽の極度に至ることあらば、今の西洋諸国の有様を見て愍然たる野蛮の歎を為すこともある可し。是に由てこれを観れば文明には限りなきものにて、今の西洋諸国を以て満足可きに非ざるなり。 ●順序(31頁) 欧羅巴の文明を求るには難を先にして易を後にし、先ず人心を改革して次で政令に及ぼし、終に有形の物に至る可し。 ●統計学(74頁) 広く実際に就て詮索するの法を、西洋の語にて「スタチスチク」と名く。 ●時勢(84頁) 政権の王室を去るは他より是を奪うたるに非ず、積年の勢に由て王室自らその権柄を捨て他をして之を拾わしめたるなり。 ●改革の乱(96頁) 改革の乱を好む者は智力ありて銭なき人なり。古今の歴史を見てこれを知る可し。 ●国と国(238頁) 国と国との交際に至ては唯二箇条あるのみ。云く、平時は物を売買して互いに利を争い、事あれば武器を持って相殺すなり。 ●サンドイッチ島(253頁) 「サンドウィッチ」島は千七百七十八年英の「カピタン・コック」の発見せし所にて、その開化は近傍の諸島に比して最も速やかなるものと称せり。しかるに発見のとき人口三、四十万なりしもの、千八百二十三年に至て僅に十四万口を残したりと云う。 ●国の独立を(258頁) 目的を定めて文明に進むの一事あるのみ。其目的とは何ぞや。内外の区別を明にして我本国の独立を保つことなり。 ☆関連図書(既読) 「福澤諭吉」西部邁著、文芸春秋、1999.12.10 「「文明論之概略」を読む(上)」丸山真男著、岩波新書、1986.01.20 「「文明論之概略」を読む(中)」丸山真男著、岩波新書、1986.03.27 「「文明論之概略」を読む(下)」丸山真男著、岩波新書、1986.11.20 「福沢諭吉「学問のすすめ」」福沢諭吉著・佐藤きむ訳、角川ソフィア文庫、2006.02.25 「福沢諭吉『学問のすゝめ』」齋藤孝著、NHK出版、2011.07.01 (2013年6月6日・記) (「BOOK」データベースより)amazon 国の独立は目的なり、今の我が文明はこの目的に達するの術なり。西洋心酔と保守主義の相確執する明治初期、文明の本質を論じ、文明は文明自らに意味があるとした上で、今、最も優先すべき課題は日本国の独立であり、西洋文明を学ぶのもそのためであると説く。『学問のすゝめ』と共に、時代の展開に大きな影響を与えた福沢(1835‐1901)の代表的著作。
0投稿日: 2013.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一回読んだだけでは内容が濃すぎて、消化しきれない感が残りました。 今も当時も日本の本質的な問題は変わらっていないようだし、また、その本質を指摘してるからこそ未だに読み継がれてるかと思います。
0投稿日: 2013.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ昔の人がどんなに真剣にDevelopmentというものを考えていたかわかる本。福沢諭吉は脱亜欧論とかいろいろ色眼鏡でみられているが、じっくり読んでみると、現在の日本にもつながる名著だと思う。
0投稿日: 2013.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間をかけて読了。幾度も幾度も立ち止まり、線をひきながら読んだ。 ここで広く全般にふれレビューとするならば、福沢が真に願うところと、それに関する在野の在り方について書いておきたい。 福沢は、学問する人でありながら、日本の独立のためには、自身と同じく学問する人間を増やさねばならない、在野の人として野辺の隅々まで学問をいきわたらさねばならないと考えていた。だから彼は政治にも象牙の塔にも入らず、在野人たる着流しの姿で、しかしながら高尚にみえる学問を続けたのだ。酒を飲めど、本をくる手は止まらない。その姿が広まるべきだった。慶應義塾の人間は今一度、学問の普遍こそ独立の普遍であると、見直すべきだ。 憂国の原因として福沢が挙げていた外国との付き合いにも、今でこそ読む価値がある一冊『文明論之概略』である。福沢は本当に、学問をする人間と下民とを分断していたのか。学問を嫌悪して、関係ないさと嘘吹いて、悔しい顔一つもせずに福沢の発破を流してしまうことが続いている日本では、哀しいことに『文明論之概略』が名著でありつづけるだろう。
0投稿日: 2013.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ言わずと知れた福沢諭吉の代表作。 本書の内容は多岐に渡るが、彼がもっとも言いたかったことは「国体を保持するために、国民一人ひとりが合理的な思考(文明)を獲得しなければならない」というシンプルなものであるように思う。 すでに効用(実)がなくなっているのに古い習慣(名)に囚われ、思考停止に陥っている(=惑溺)例として、儒学者・漢学者・国学者が批判の槍玉に挙げられる。中でも孔子・孟子は相変わらず目の敵にされており、「そこまで言わなくても」と思ってしまうほど。読み進めている際、ふと「白猫であれ黒猫であれ、鼠を捕るのが良い猫である」という鄧小平の言葉を思い出した。 もちろん、本書は素朴な文明礼賛ではない。福沢も「国の独立が目的であり、国民の文明はその手段である」と言い切っており、ここが意外とポイントのような気がする。 占いやスピリチュアルがいまだに流行る現代の日本。我々の精神は未だ文明からは程遠いと言うことができそうだ。 ところで、135ページに「巧言令色、銭を貪る者は、論語を講ずる人の内にあり」という件があるが、今をときめく経営者が何人も浮かんでしまうのは私だけだろうか。
0投稿日: 2012.11.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ消費増税先伸ばしのニュースをみて、日本の政治が理解できなくなったので、文明開化の時代に遡って政治、社会の思想や背景を知ろうと手に取った。 実学の祖として有名な福沢諭吉だが、彼の思想は、今のグローバリストを量産すべしという胡散臭い議論とは全く別だった。 何のために外に目を向けるのか。 その目的は、新たな視点を取り入れて価値判断の基準を増やすことで、日本の社会問題をひとつでもふたつでも解決するためであるという自分の認識を確認した。 備忘録:文明とは人の安楽と品位の向上であり、それをもたらすのは国全体における智徳である。
0投稿日: 2011.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ「学問のすすめ」よりも内容的にも若干難しいが、それよりも文章がぐっと難しい。なぜか「べからず」という語尾が頻発し、「その権威なかるべからず」などと、我々にあまりなじみのない言い回しなだけに、ぱっと見て肯定なのか否定なのか戸惑ったり。 しかし内容はなかなか豊かで、当時の日本人にしてはよく先まで見通して考えていたもんだなあ、と感心するしかない。 丸山真男が指摘していたように、確かに相対主義的な思考法が随所にあらわれているのも、面白い。 儒教の被支配者的な限界など、興味深い指摘が豊富だ。 日本(やアジア)は西洋に遅れている、という当時の切迫した思いは、しかし現在人類学的な観点から見ると、必ずしもそうとは言い切れないのだが、単に西洋を真似するのではなく、その本質に学んでさらに未来の文明にまで進もう、という意気込みはさすがだと思う。
0投稿日: 2011.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ福沢は一国の発展段階をその国民一般の持つ学問的知識の水準により決まるとし,一国が野蛮の状態からより文明化された状態に移行するために,国民一人ひとりが学問を修め知識を増し組織から独立し自分の足で立つことを説きました. この本は現代においても我々一人ひとりがいかにして生きるべきかを示してくれています.
0投稿日: 2010.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ《4コマ図解・読書録゛(ログ)》No.31 http://archive.mag2.com/0000255083/20080731232000000.html 福沢諭吉【著】 『文明論の概略』
0投稿日: 2009.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログあの福沢諭吉の著書,あなたは読んだことがあるだろうか。おそらく(というか,私がだが),国語か社会科の教科書で『学問のすすめ』の一節を読んだくらいではないだろうか。今,法政大学の「地理学」の講義で使っている教科書,西川長夫『地球時代の民族=文化理論』のなかで,本書が大々的に取り上げられている。ということで,先日古書店で,この岩波文庫版を手に入れたので読んでみることにした。 本書の初版は明治8(1875)年に,和紙木版で6巻本として発行された。もちろん,この岩波文庫版はその6巻を全て1冊に含んでいるが,当時は活字ではなく,木版画だ。その2年後に洋紙活版刷一冊本が刊行されたというから,まさに日本が近代化する過程に生まれた出版物であり,著書であるといえる。 日本の近代化とは,鎖国の江戸時代の終焉であり,明治維新があり,廃藩置県など日本の制度がまるっきり入れ替わった時期であり,それをわたしたちは「文明開化」と呼んでいる。しかし,「文明」ということばは日本語にはなかったのだ。もちろん,文化という言葉とともに,過去に年号として文明の語は使われたことがあるが,わたしたちの時代の昭和や平成が日常用語として用いられることがないように,文明という語は単に中国の古典から借りてきた言葉にすぎない。意味など伴わない象徴的な言葉であった。 すなわち,「文明」という語は文明開化という現象のなかでヨーロッパから輸入された言葉であると同時に,ヨーロッパからさまざまな政治制度や経済体系,生活様式を輸入することを,その言葉を用いて文明開化と呼んだわけである。すなわち,文明とはこの時代の最大のキーワードであった。だから,その言葉を普及させるために,当時最もすぐれた知識人であった福沢諭吉がその言葉を普及させるために本書を書かなくてはならなかったのだ。 日本の政治制度や経済体系に関して,本書ではJ.S.ミルの『代議政治論』や『自由論』,『経済学原理』が多用されているが,その他にバックルの『英国文明史』とギゾーの『ヨーロッパ文明史』からヨーロッパ文明について学んでいる。当時からもちろん,ヨーロッパの著作をそのまま翻訳するということはあったが,部分的に翻訳したものを引用文だと明示することなく,自分の文章であるかのように用いることが多くあったようである。本書もそんな感じで,上の2著からの引用分は数多い。もちろん,本文だけ読んだだけではそれには気づかないだろうが,ご丁寧にこの岩波文庫版ではいちいち注釈を入れている。 すなわち,この本はヨーロッパの文明化の過程を概観し,日本に明治維新以前にあった文明の歴史を辿り,両者を比較することで,日本が今後ありうべき姿を探求するという目的がある。もちろん,その具体的なところは『学問のすすめ』のような他の著作がありますが,その前提となるのが本書。 いやあ,それにしても難しかった。木版画版の1ページ分の写真が掲載されていますが,カタカナによるおくり仮名を平仮名に直し,漢字にはとても丁寧に読み仮名がふってありますが,基本的には現代語訳にはなっていない。特に,日本の文明史の箇所は英語を読むより大変だ。でも,現代と違って,こうした歴史を記述するのは大変だと思う。 しかし,全体的な論調は,日本は今のままでは駄目で,文明化=欧化であり,ヨーロッパに近づくことこそが日本国の独立である,という主張はかなり極端のように思えるが,そのくらい強い主張だからこそ重要な論として受け入れられたのだろうか(あ,といっても,本書は他の福沢の著書と比べて当時はあまり読まれなかったらしい)。 ともかく,やはりこういう読書は新鮮です。
0投稿日: 2008.12.27
