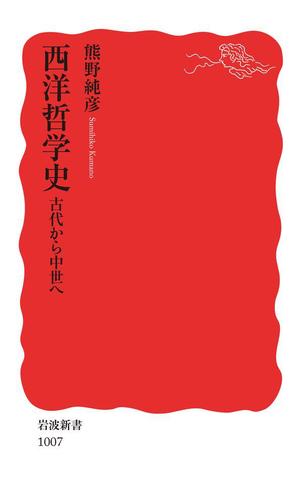
総合評価
(31件)| 6 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学をきちんと勉強してみようと思いまずこちらに…しかしながら哲学初心者にはもっと基礎的知識が必要だったかも。 ただ、今ある哲学がさまざまな流れ、曲折を経ているのだということがよく分かったので他の易しい哲学書を読みつつ続編に臨みたい感じ。
2投稿日: 2025.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログある程度哲学史一般に触れたことのある人向けの解説書というレベル。 かく言う私も、古代から中世は勉強不足+神が前提にあったり是非を問うたりとで腹落ちがどうしてもできず半端な理解にとどまってしまった。不甲斐なし。 本書の魅力は、著者もまえがきに述べているように哲学者の原著テキストを積極的に掲載して説明を進めているところ。原著なのでそのまま理解しようとすると難解ではあるが、その直後に解説を加えてくれるし何より哲学者の息遣いが感じられて思考の懐が深まった感覚。 とはいえ、ここの哲学者の主張と連関は掴みきれず。。『哲学史入門』シリーズの古代-中世の部分再読と、ネオ高等遊民の入門書必読だな。精進いたします。
0投稿日: 2025.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学史の勉強がしたいと思い、2冊目にこの本を手に取りました。きっと理解できると面白いのだと思いますが、初学者の私にはまだ難しかったです。ある程度、他で哲学史の知識をある程度身に付けてから読んだ方がいいと思います。
0投稿日: 2023.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ「哲学とは、人間の経験と思考をめぐって、その可能性と限界を見さだめようとするものであること」であるとしているが、前半のギリシア哲学の部分は興味深く読めるのでいいとしても、後半の中世哲学の部分はキリスト教の影響が大きく、一般的にはあまり扱われない領域に関する記述も多いので、ある程度の素養がないと結構難解で読み進めるのが大変かもしれない。
0投稿日: 2023.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもわかりやすく、哲学史の流れを書いている。 哲学史の入り口にちょうどいい。 ただ、熊野さんは分かりやすさより文章への自己満足感に走った印象もある。 途中、ところどころページ数の制限に苦しんでいるような箇所もあるけど、この新書の目的を考えると致し方ない。
0投稿日: 2023.04.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ【オンライン読書会開催!】 読書会コミュニティ「猫町倶楽部」の課題作品です ■2022年11月11日(金)20:30 〜 22:15 https://nekomachi-club.com/events/ca6b7e19cca8 ■2022年11月27日(日)17:30 〜 19:15 https://nekomachi-club.com/events/87fecd27ea09
0投稿日: 2022.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
-2007.03.12 良書である。著者独特の語り口がいい。 -やわらかな叙述のなかに哲学者たちの魅力的な原テクストを多数散りばめつつ、「思考する」ことそのものへと読者を誘う新鮮な哲学史入門-と、扉にうたわれるように、採り上げられた先哲者たちの思考を、著者一流の受容を通して、静謐な佇まいながらしっかりと伝わってくる。 岩波新書の上下巻、「古代から中世へ」、「近代から現代へ」とそれぞれ副題された哲学史は、著者自らがいうように「確実に哲学そのもの」となりえていると思われる。折にふれ再読を誘われる書。その章立ての構成を記しておこう。 「古代から中世へ」 1-哲学の資源へ 「いっさいのものは神々に充ちている」-タレス、アナクシマンドロス、アナクシメネス 2-ハルモニアへ 「世界には音階があり、対立するものの調和が支配している」-ピタゴラスとその学派、ヘラクレイトス、クセノファネス 3-存在の思考へ 「あるならば、生まれず、滅びない」-パルメニデス、エレアのゼノン、メリッソス 4-四大と原子論 「世界は愛憎に満ち、無は有におとらず存在する」-エンペドクレス、アナクサゴラス、デモクリトス 5-知者と愛知者 「私がしたがうのは神に対してであって、諸君にではない」-ソフィストたち、ソクラテス、ディオゲネス 6-イデアと世界 「かれらはさまざまなものの影だけを真の存在とみとめている」-プラトン 7-自然のロゴス 「すべての人間は、生まれつき知ることを欲する」-アリストテレス 8-生と死の技法 「今日のこの日が、あたかも最期の日であるかのように」-ストア派の哲学者群像 9-古代の懐疑論 「懐疑主義とは、現象と思考を対置する能力である」-メガラ派、アカデメイア派、ピュロン主義 10-一者の思考へ 「一を分有するものはすべて一であるとともに、一ではない」-フィロン、プロティノス、プロクロス 11-神という真理 「きみ自身のうちに帰れ、真理は人間の内部に宿る」-アウグスティヌス 12-一、善、永遠 「存在することと存在するものとはことなる」-ボエティウス 13-神性への道程 「神はその卓越性のゆえに、いみじくも無と呼ばれる」-偽ディオニソス、エリウゲナ、アンセルムス 14-哲学と神学と 「神が存在することは、五つの道によって証明される」-トマス.アクィナス 15-神の絶対性へ 「存在は神にも、一義的に語られ、神にはすべてが現前する」-スコトゥス、オッカム、デカルト
0投稿日: 2022.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ初学者向けにしては難解なテクスト。同時に重厚さも備わっている。 アリストテレス以降は非常に読みやすく感じたが,アリストテレスの提示した論理学的知見が現代に浸透していること,また近代哲学が極めてアリストテレスの影響を濃く受けていることが理由かもしれない。 トマスの解説部などは,原文を読まないと理解が追いつかないような側面もある。 とは言え,原典のテクストにも当たりながら,西洋哲学の軌跡が端的にまとめられており,なるほど名著と言えるだろう。
0投稿日: 2021.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログデカルトまでのギリシャ・ローマ世界における思想について、通史的にざっと知識を整理しようと購入したが、そのような実用的な用いられ方を拒むような著者の文体にあえなく返り討ちにあい、結局2度3度と読み返すことに。「世界と、世界をめぐる経験のすべてがそこに結晶しているような一語を語りだすためには、幾重にも錯綜したことばのすじみちを辿りなおさねばならない。そのとき哲学的思考が抱え込む困惑は、日常の風景を反転させ、世界の相貌を一変させる一行を探りあぐねる詩人の困惑と、全く同質のものであるはずである(p.30)」。本書で哲学者の思索をなぞる著者のことば自体もまさにこのような詩的な響きを帯びており、どの文章にも安易な読み飛ばしを阻む深みが潜んでいる。 以下覚え書き。 第1章 イオニア学派、ミレトス派 タレス 自然(ピュシス)に目を向け、世界の原理(アルケー、始まり)を問う アルケー=水 アナクシマンドロス 自然=反復と循環、アルケー=無限なもの(アペイロン) アネクシメネス 無限なもの=アエール/プネウマ(空気) 第2章 ピタゴラス 輪廻(身体という牢獄からの魂の解放)→身体を超えた秩序(ロゴス) 魂(プシュケー)、知性(ヌース)によるロゴスの知覚 →「数こそが原理」 どれでもなく、どれでもあるもの(e.g.直角三角形) 数が生むハルモニア(調和) ヘラクレイトス アルケー=常に消滅しながら生成しているもの(e.g.炎) 「万物は流れる(パンタ・レイ)」 ロゴス=相反・対立するものの両立(=調和) クセノファネス 神は非物体的な一者、不動でなければならない 第3章 エレア学派 パルメニデス 存在だけがあり、無はあり得ない では、あるものとは?→それ自体は生成も消滅もしないもの(他のものは「ない」) エレアのゼノン 「多」と「動」の否定 多・動は有限(現にある数だけある)かつ無限(間に別のものがある)→矛盾(帰謬法) カントのアンチノミー(無限と不定の混同を批判)への影響 アリストテレスの反論「無限の分割は有限時間内で可能(分割の場合は時間も無限…一対一対応)」X「際限」 メリッソス 空虚はあらぬものだが、運動のためには退去する場所として空虚が必要(古代原子論へ) 第4章 エレア派への回答 「何かが変化したというためには、変化しないものが必要(アルケーは変化しないとすれば多と動も生じない)」 エンペドクレス 元になるものは不変、その結びつき方が変化する アナクサゴラス 生成は混合であり、消滅は分離である(生成も消滅もなく、常に同一のまま存在し続ける e.g. 種子) デモクリトス あらぬものもある(「あらぬもの=空虚におけるあるもの」の運動→現象と感覚における差異を生ずる) エピクロス 原子は性質を持たない(性質=ノモスは変化するが、原子は変化しない)→では、差異はどのように生ずるか? プラトン 虚偽や誤謬は「ある」の反義であり、これらがあるならば「あらぬ」もある →「あらぬ」=「ではない(差異を生成)」cf. サルトル「無化」 第5章 ソフィストたち 神話的思考への啓蒙 プロタゴラス 人間の感覚への「あらわれ」が全てのものの尺度 → では存在とは異なる「あらわれ」とは何か? ゴルギアス 存在は人間に捉えられず、捉えられたとしてもそれを表現することはできない ソクラテス 「アポリア(行き止まり)」→無知の知(無知ゆえに知を愛し求める=フィロ・ソフォス→philosophy) 対話術「エレンコス」においても答えを与えない(知らないから) シノぺのディオゲネス 小ソクラテス学派(キュニコス学派(犬儒派)) プラトニズムへの反感 第6章 プラトン イデア…当のものごとが、「それ」によってまさにそのものごとである、そのもののこと 目に見えないイデア=エイドス(すがた、形相)への希求…愛知者 「探求のアポリア」知らないものをなぜ探究できるのか →「想起説(アナムネーシス)」…潜在的には全てを知っている、学ぶ=想起する 「等しさ」と「等しいもの」は違うものなのに、「等しいもの」から「等しさ」を直感するのはなぜか?→「等しさ」が「等しいもの」のうちに「現前」→イデアのみが真に、永遠に存在する 諸事物とイデアの共通項は?(アリストテレス「第三人間」) 「一」と「多」変化する事物を超えて真なる存在であるイデアを思考 第7章 アリストテレス プラトンのイデア…自然=神の技術、イデアを参照し想像する → 秩序(ロゴス)は世界の外部に存在 → 自然それ自体のうちにロゴスが求められるべきでは? 自然的存在…自らの運動と停止の原理を持つ 技術が自然を模倣する 自然=生長するものの生長、運動の原理、存在者の存在の始源 四原因説 質料のみでは実体は得られず、形相(何であるか、エイドス=ロゴス)が必要 質量が形相を可能性として含む=可能態、質料が形相を伴う=現実態 製作行為=質料に潜在する形相を顕在化する技術、自然の比(ロゴス)に従う 1. 自然がロゴスを内在=目的論的な自然像 2. 徳(エートス)…働きそれ自体が目的となるような人間の素質 「形而上学」…自然学を超える(メタ)学=存在論、実体とは何か 第一の実体:個物 第二の実体:種(エイドス=形相)…実体の本質 現実態にある形相…可能態にある形相にとっての「目的」 全ての存在者にとっての目的=「純粋形相」=「神」 運動は永続的でなくてはならない(永続的でないなら運動開始前と終局後に何らかの変化があることになる) →「第一の動者」はそれ自体永続的であり、かつ運動してはならない 動かされず動かす「不動の動者」…愛されるものが愛するものを動かすように動かす 神的なものの「観想」→最高の至福 第8章 ストア派の論理学 タブラ・ラサ…経験論へ 真実:表象と対象との一致(しかし、対象との対応により真理を定義するのは循環論では?→真アカデメイア派の古代懐疑論へ) 意味と指示の区別(明けの明星と宵の明星の指示対象は同一だが意味は異なる) 質料と形相の区別(アリストテレス)の受容 「神」=全ての質料に浸透するロゴス、理性それ自身 ストアの決定論…因果関係による順序と連鎖(ロゴス=宿命=神) 自然と調和して生きる→国家を超えた「世界市民(コスモポリテース)」 アパティア(無感動)…感情に流されてはならない、全ては自然に従う →現在こそが永遠、現在が最後の瞬間であるかのように生きる 第9章 古代懐疑論(ピュロン主義) セクストス・エンペイリコス 感覚的なものへの疑い(エレア派に起源…パルメニデス「思いなし」、古代原子論者「ノモス」) 判断中止(エポケー)により、独断論者の「体系」を批判 メガラのエウクレイデス パルメニデスの「一つの同じもの」とソクラテスの善の結合 ディオドロス 活動こそが能力を表す、現実的なもののみが可能的である(cf. アリストテレス「現実/可能態) パイドン(エリス派) アルケシラオス(新アカデメイア学派) ストア派の循環論(真の表象と偽の表象を隔てる基準があるとする)を批判 ピュロン主義者たち 表象と思考を対置し、判断中止へ至る方策=「トロポス(いい回し)」 「トロポイ(感覚の仕方)」は相対的→一旦判断を停止(アポリア)する必要 批判的合理主義(演繹的体系の無根拠性を指摘)の原型 第10章 新プラトン主義 フィロン 二段階創造説…「思考される世界」「感覚される世界」 神は「エイコーン(神の似姿、一性)」を範型として人間を創造 プロティノス 存在=一性(一つでなければ存在できない、多による一の分有) 多を形作る一を、一としているもの→三つの原理(「一者」「たましい」「知性」) たましいが身体を一つのものにし、知性はたましいの活動を規制する プロクロス 一者は存在に先立ち、他のものの存在の源となる「第一の原因」であり「善」 第11章 アウグスティヌス 感覚への懐疑論(新アカデメイア派)への反論…真なるものの認識は如何にして可能か 「感覚する私(=欺かれる私)」は確実に存在している(デカルト方法的懐疑との類似) 自ら存在し、自らの存在を知り、自らを愛することは感覚による表象(=欺き)を介しない 確実・真なるものは人間の内面に存在、理性による判断が真理(一性)を捉える 内面における「神」という絶対的外部性があるからこそ、完全・真なるものが認識できる 時間の経過で散り散りになる「私」を統合しているのは「神=永遠の現在」である 第12章 ボエティウス 「三位一体論」…たましいと身体が「一つ」cf. プロティノス 普遍論争の原点 「存在=単に在ること(存在の文有、偶有性)」と「存在者=本質的に在ること(実体)」の差異 アリストテレスの「善」…分有ではなく、実体により「善」なるもの=「神」 単純なもの、一なるもの、善なるものでは「存在」=「存在者」 「存在そのもの」である「神」から流出する「善」により、存在者は「善」となる 「永遠」=無限の生命の、全体的で同時的な完全なる所有 第13章 偽ディオニュソス 「神」=闇に隠れるもの 無知により到達可能(神秘主義) エリウゲナ 「神」=「創造し創造されないもの」かつ「創造せず創造されないもの」=存在を超えた「無」 スピノザの先駆? アンセルムス スコラ哲学 さまざまな善を可能にする「共通な或るもの」=「最高の存在者」 神の存在証明:それより大なるものを考えることができないものでも考えることができる!=実在しているはず(カントの反論:完全であっても存在するとは限らない、「存在する」はものに関わる述語ではない) 第14章 トマス・アクィナス アリストテレスをラテン世界に逆輸入したラテン・アヴェロイスト「二重真理」批判 - 「可能知性(全ての人間が持つ単一の知性。アリストテレス「能動知性(身体の形相であるたましいに作用)」に対置される)」批判…全ての人が同一であるのは自由意志の否定であり不合理 - 「世界の永遠性(アリストテレスも主張)」批判 スコラ哲学的な存在証明の非自明さを指摘 「五つの道」による神の存在証明①第一動者②始動因③必然性④秩序⑤目的因 第三の道…偶然的世界が存する以上、必然的な神もまた存在せねばならない a世界の存在、b世界の本質(=偶然性)、c神の存在、d神の本質(=必然性)のとき、 a:b=c:d(存在の類比)という比によって、経験的地平から神が証明される 世界は神を出発点とした被造物=世界は神の存在を「分有」する 神だけが「自存する存在そのもの」であり、他の一切の存在者は神から流出(=創造)される 第15章 神の絶対性へ スコトゥス 「存在」の一義性…同一主語について同時に肯定と否定がされ得ない述語 「存在」はカテゴリーに先立って有限/無限の両者に適用される「超越概念」 神に適用されれば無限、被造物に適用されれば有限→神と被造物を介在 オッカム 「神の予定」予定に反することができなければ全能ではなく、予定に反するとき全知でない 神は未来の事柄について確定した知を有する=神にとっては全てが現前する、一切が現在 永遠とは全体の現前、神の予定=未来の未確定な事柄についての確定された知 偏在する神 デカルト 無から一切を創造する神 人間が法則を必然と感じるのは神が絶対性を人間に植え付けたから
1投稿日: 2021.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログうむ、入門書にしては難しい!笑 ただ根気強く読んでいくと輪郭くらいは見えてくる。「ヨーロッパ哲学の伝統はプラトン哲学の脚注だ」という言葉の意味もよく分かる。プラトンだけではなく、アリストテレスも全編にわたって顔を出してくる。 個人的な本書の立ち位置としては哲学史の輪郭を把握して個々の哲学者にアプローチしようと思う。その後はまた本書に帰るかも知れない。 哲学はマクロ→ミクロ→マクロの勉強でいこうかな。 余談だが、アウグスティヌスの『告白』は高校生の頃から存在は知っているが初めて読もうと思わせてくれた。
0投稿日: 2020.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学で哲学かじったつもりだったけど近代以降が中心だったから、ここに出てくるなんちゃらティウスみたいなひとたちがことごとく初耳だった。
0投稿日: 2020.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学者の原体験をベースにするというコンセプトは面白いが、この著者の他のもだけど、知識不足だと読みづらいので、はじめてでこれに入るのはおすすめできない ただ、一つ一つの議論が丁寧になぞってあるので、じっくり読むと結構面白い。
0投稿日: 2020.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学の始原からデカルトに至るまでの歴史を丁寧に辿った一冊。 一つ一つのエピソードは控えめに抑え、全体の流れを重視した構成。 西洋の哲学が辿ってきた歴史が、とても分かり易くまとまっている。 一つ一つの章は短くコンパクトにまとめられているが、その内容に不足は感じない。 それぞれの章を構成する際に、思想の核を為している重要な言葉を取り上げることで、その章が何を表しているのかを適切に表している。 さらに、専門的で難解な用語をあえて廃する事によって、読み進む際の困難さが軽減されている。 時代の背景、哲人たちの言葉、脈々と流れる時間。 それらを、必要最低限の表現によって、見事に纏め上げた一冊だと思う。 「哲学」というものが辿ってきた歴史を見渡すことが出来る良書。 それにしても、西洋に於ける哲学というものは、どこまでも神学、宗教の影がちらつくのだなとしみじみ思った。 政治においても宗教が及ぼす影響というのは計り知れないものがあるし、科学にしても同様。 「神」というものの存在感が、向こうでは絶対的に強いのだと改めて感じた。 その呪縛に囚われず、もっと「自然」な思考が可能であった東洋哲学の歴史との対比が読んでみたい。
1投稿日: 2018.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代・中世の哲学史を新書一冊で概観できる本です。 続編である『西洋哲学史 近代から現代へ』のほうを先に読んだのですが、そちらでは随所に著者自身の見解が示されていたのに対して、本書はおおむねオーソドックスな紹介になっているように感じました。 ちょっと残念に思ったのは、本書と続編のあいだに挟まれるルネサンス期の哲学がスルーされてしまっていることでしょうか。新書サイズにもかかわらず、一般にはあまりなじみのない古代懐疑論や新プラトン主義などにもページを割いて解説しているだけに、一通りの解説がほしかったように思います。
0投稿日: 2018.03.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ院試の対策をするにあたって、全体の流れをつかむのに使用した。専門書というわけでもないので、哲学史をおおまかに知りたいという人にとっては十分だろうと思う。詳しめに知りたいという人にとってはさすがに足りない。哲学者ごとの専門書か、古代なら古代、中世なら中世で詳しく論じられているものを読むべきだろう。内容は薄いわりに非常によくまとまっているのだが、レトリックに酔った部分が散見されるのでマイナス1点。
0投稿日: 2017.02.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ本社は古代から中世にかけての西洋哲学をまとめたものである。一般の西洋哲学史の本は、人物名とその人が唱えた概念を一文でまとめた形で纏められているものが多いが、本書は歴史のコンテクストを追いながら、それぞれの人物の思想について、具体的かつ論理的に説明しており、とても面白かった。説明してある内容はそれなりに分かりにくいものだと思うのだが、著者の日本語は大変良質で、ゆえに見事なまでにコンパクトかつ分かりやすく説明していたため、理解しやすかったように思える。
0投稿日: 2016.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、ついていけなかったな、、、 ひとえに当方の能力不足に起因するのだろうが、まえがきで風呂敷を広げた著者に期待し過ぎた面もある。 あと哲学書によくあるのだが、文章が流麗でない(というかわざと小難しく書いているような気もしなくもない)。 いずれにせよ当方が顔を洗って出直してこいということでしょう。
1投稿日: 2013.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ他書との違いを3点挙げている。 1哲学者の思考と経験を追体験可能 2誌好結果のみでなく、論理的道跡をたどる 3哲学者のテクスト引用 登場する哲学者の半分は名も知らぬ、異人たちであった。 テクスト引用は、重要なのか?疑問。哲学者個人の経験的流れを追うために、重要結果が明晰に分かりづらい。すでに各哲人の足跡を知っている人にはおもしろいのかもしれない。 ソフォス?フィロ?フィロソフォス?
0投稿日: 2013.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学者って「哲学書」を呼んで育っているんだなあと改めて実感。その人がどのような文脈(社会的状況、宗教)で、どの文章(哲学書)を、どのように読んだか(聞いたか)を考える哲学史的視座は重要。 ただ、本書でもいうように(?)それだけでは語り尽くせないその人「特有の思考」というものがあって、それを感じることができるかどうかだよなあ。 古代、中世の人は「有(ある)、無し(ない)、有限・無限」について考えを深めていたようだ。
0投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学者について何も知らない状態だったが、歴史背景と共に西洋哲学が如何に発展していったかがなんとなく掴めた。 そして自分の無知っぷりも思い知ったよソクラテスさん!
0投稿日: 2013.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学の黎明たるミレトス学派から、後期スコラ哲学に至るまでの思考の歴史をまとめた哲学史。「哲学とは哲学史であるとはいえないかもしれませんけれども、哲学史は確実に哲学そのものです」という著者の言葉が実感できる簡潔にして重厚な内容。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際の講義のほうが、クオリティが高いか(オールドスタイルな講義だけれども)。流れるような文体で統一されているので、これを足がかりにして人物や概念をじっくりと検討するのが、かえって難しい。それでも、ぶれのない解釈の提出は非常にありがたい。
0投稿日: 2011.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は15章で構成されており、それぞれが対応する哲学の歴史的変遷、どのような思想が論じられていたかを具体的な哲学者や学派を通して説明されている。 大まかにそれぞれの哲学者がどのような思想を持っていたか知るのには適しているが、細部まで説明がなされているわけではないので、よく知りたいならば本書で紹介されている哲学者の著書を読むべきだ。 西洋哲学への入門書として、また歴史的変遷を見直す一つの手段として非常に有効であると言える。
0投稿日: 2010.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ頑張りました。まだ近現代読んでませんが。もう納得しようがしまいがとりあえず読み進めました。難しかったし訳わからんところもいっぱいでしたが、楽しかった。
0投稿日: 2010.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ『西洋哲学史』(熊野純彦、2006年、岩波新書) 本書は、自然哲学の祖とされるタレスの時代の哲学者から、トマス・アクィナスからデカルトの時代の神学論争までをその範囲とし、15章にわたり各章20ページ弱でそれぞれ解説している。 古代から中世までとは言え、新書ですべての範囲を理解できるかといわれたら、それは難解なのではないか。まして、たとえばソクラテスの思想を本書一冊でカバーできるはずがない。 しかし、本書は西洋哲学の歴史を辿ることが目的。古代の哲学者がどのように人生、真理、世界、神について考え、発展させてきたのかという思想の流れを追うには良書と言えるのではないか。 (2010年5月22日 大学院生)
0投稿日: 2010.05.22 powered by ブクログ
powered by ブクログいっさいのものは神々に充ちている。 世界には音階があり、対立するものの調和が支配している。 私が従うのは神に対してであって諸君にではない。 すべての人間は生まれつき、知ることを欲する。 君自身のうちに還れ、心理は人間の内部に宿る。 存在することと存在するものとは異なる。 神はその卓越性のゆえに、いみじくも無と呼ばれる。 存在は神にも一義的に語られ、神にはすべてが現前する。
1投稿日: 2010.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ新書であるため、持ち運びが可能という点で気に入った。 有名哲学者達の思想をざっと知る分にはいいのではないか。 アウグスティヌスに関する11章の3つの部分が非常に興味深かった。 P167L6〜L10 「友人や恋人、一般に愛する者の存在には、「関係」という一語には尽きないなにかがあるのではないだろうか。愛する者は「もうひとりの」「他の」私というよりも、私の存在の一部である。私の存在は、愛する者と切りはなすことができない。だれかを愛するとき私は、じぶんの存在を、むしろ、自身の外部に有している。すくなくともじぶんが存在することの意味を、自己の外部にもっているように思われる。」 P169L9〜L14 「アウグスティヌスはまだ愛することを知らなかったけれども、「愛することを愛して、愛の対象をもとめていた」。「愛し、愛されることが、私には甘美であり、愛する者の身体を享受することは、なおさらに、甘美であった」のである。アウグスティヌスはやがてひとりの女性と同棲し、十八歳のときに一児の父となる。「情欲でむすばれた場合、子は親の意に反して生まれるのではあるけれども、生まれた以上は愛さずにはいられない」。」 P170L4〜L5 「肉欲に囚われていたアウグスティヌスはべつの女性とも関係をもち、「痛みはやわらいだようでもあったが、よりいっそう絶望的なものともなった」。」
0投稿日: 2008.10.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋哲学の流れを、時の哲学者の思考過程を再構成するという独特の方法で紹介した著書の、上巻に相当する本です。 収録されている時代は紀元前500年から紀元1500年ごろまでの、実におよそ2,000年間。ソクラテスよりはるか昔のタレスやピタゴラス、プラトンやアリストテレスを経て、アウグスティヌス、トマス、デカルトまでを網羅しています。登場する総勢30人以上の哲学者に偏りや過不足がないのかどうか、正直さっぱりわからないのですが、たぶんこれ以上の事柄を紹介されていたら、おそらく私の頭がパンクしていたでしょう。新書に詰め込める情報量の限界を見せてもらう思いでした。久々に、読んでいて頭が痛くなるという体験をさせてもらいました。中学時代にホーキングの本を読んで以来でしょうか。 読んでいると、哲学というのはどうして難しいのか、という問題が何度も頭をよぎります。私たちの感覚を超えた世界を捉えるとき、たとえば神話のように、混沌とした内容をそのまま提示されると、案外読み手としては楽に飲み込むことができる。しかし、その混沌とした世界に人間の作った思考秩序を導入しようとすると、それはとたんに理解不能度を増してしまう。私には哲学的思考が、どうも後者の典型なのではないかと思えました。哲学がアブラハムの諸宗教と出会ったあたりから、ようやく理解しやすくなったように感じられたのは、土台にある世界観が秩序付けられた結果なのかもしれません。 存在と不在、一と多、有限と無限、神と人・・・哲学のテーマは2項対立のオンパレードです。このような考え方は、否定語(=not)が他の単語から独立した、屈折語を使う西洋人に独自の発想だったのかもしれない。だとすれば、否定語(=ない)が文の付属物のように扱われる膠着語を話す日本人には、いっそう理解しにくいものかもしれない、などなど。考えることはあまたありました。 しかし、本書の形式である「哲学者の思考過程の再構成」が、果たして入門書としての本書の性格にどれほど寄与したのか、はなはだ疑問です。確かにこの方法は、名前だけの羅列よりもずっと実のあるものだったかもしれない。けれど、原典を多く引用し、哲学者のじかの思考を本書に吹入しようとしたのは、少し欲張りすぎではなかったでしょうか。結果として、思考の過程よりも結果が多く書かれている原典によって、かえって理解のしづらい構成になってしまった気がします。また、通史というのであれば、哲学者同士のつながりを(物理的交流やテーマの流れを問わず)もっと整理した形で提示してほしかったなあと思います。 後半は愚痴のようになってしまいましたが、デカルトまで到達した哲学史の旅が、本書の続編にどうつながっていくのかとても楽しみです。 (2008年6月 読了)
0投稿日: 2008.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ西洋哲学史の概論書。ただ、入門書にしては少し難しいように感じました。前半部分は楽しく読めましたが、後になるにつれて分かりづらくなっていきます。ある程度、歴史や思想・哲学の知識が必要な気がします。
0投稿日: 2007.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログやっと読み終われた…という感じ。 最初のほうの記述がとてつもなく私好みの文だったのですが、途中は鳴りをひそめていた気がします。 自然から神に至るあたり、実感に欠けてくるのが問題なんですかねぇ。神って言われると、ウッてなってしまいます。 でも新書にしては細かくて面白かった。特に前半がいい!
0投稿日: 2007.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログタレスに始まり中世へ・・・。なんとやわらかで滑らかな語り口!熊野先生の講義を受けたことあるのですが、彼の喋りの独特の空気がそのまま文字になっていて感動した。引き込まれるなあ。
0投稿日: 2006.11.12
