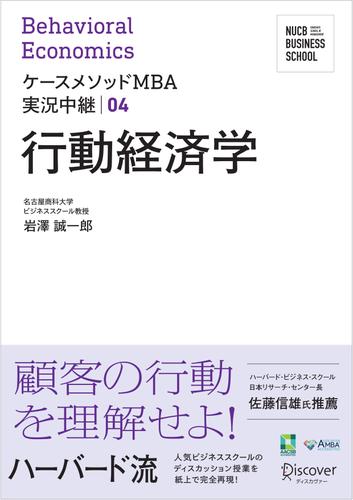
総合評価
(6件)| 4 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログケースメソッドで実際に講義を受けているようなやり取り、出題…と、とても面白かった。 行動経済学がいかに日常的に取り入れられているのかがよくわかる。 自分のビジネスに落とし込んで考えやすい。
0投稿日: 2025.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容がとても面白く、論理的に書かれていたので理解しやすかった。 人が選択をする時に直感による選択(本書ではシステム1)と、分析による選択(システム2)を行っている。そして、ビジネスサイドではこれらの選択システムに注視した策を打つ必要があるという内容。 本書では、ユーザー目線と企業目線での議論展開がされており、それぞれがwin-winになるようどうすべきか?が書かれていた。 日頃何気なく使っている様々なサービスも心理学の応用だと考えると、とても面白い。
0投稿日: 2025.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ行動経済学の講義をライブ方式で記載されているので、非常にわかりやすい内容でした。 名古屋商科大学の授業のエッセンスが詰まった非常良い本です。 授業を文字起こししてるので、読んでから授業を受けると、授業の良さ著しく低下するので、 名古屋商科大学ビジネススクールに入学したいと思っている人は授業終了後の復習に使うといいかもしれません
0投稿日: 2023.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客がシステム1に動かされているとき、ビジネスはどのようにそれをマネジメントすべきか? ①ビジネスとしては、顧客のシステム1を知ろうとしなければいけないということ。 ②顧客がシステム1で動いている際には、顧客のシステム1へのアプローチが必要だということ。 ③顧客の自由と尊厳を大事にしようということ。 特に②については、 システム2(分析・推論)による説得の前に、相手のシステム1(速い脳、知覚・感情・直感)をほぐし、説得を受け入れる素地をつくる必要がある。その基本はEmpathize、すなわち、相手の感情に入り込んで理解すること。良き理解者としてふるまうこと。そして、よき理解者であるというメッセージを相手に伝えること。傾聴すること、うなづくこと、賛意を示すこと、理解を示すこと。具体的なやり方はいろいろでしょうが、このプロセスに時間をかけ、仲良くなり、信頼されないことには、意味のある論理のコミュニケーションを始めることができないでしよう。
1投稿日: 2021.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
行動経済学について、実際の授業をベースにした構成がとられており、リアリティがあった。 脳の中で「知覚」、「感情」、「直観」といったことにより最初に動かされるシステムを「システム1」と呼び、これは努力しなくても、自動的に素早く立ち上がる。 一方、もうひとつの部分は分析や推論といった脳の活動に伴って動くもので、「システム2」と呼ばれる。これの立ち上げには労力が必要で、集中してコントロールしていないと動かない、しかもゆっくりとしか立ち上がらないという特徴がある。 人は、「システム1」によって判断し、「システム2」に至る前に意思決定しがちなため、非合理的な意思決定をとってしまうというもの。本書では具体的な事例が6ケース、取り上げられている。 印象に残ったのは毎月分配型投資信託をケースに取り上げた事例。「毎月分配型」、「年率20%」など、とても魅力的な語句を並べて、顧客のシステム1に働きかけるような商品パンフレットが例として掲載されていた。 私はこの業界にいなければ、話上手な営業マンに、魅力的な語句を並べられ、おすすめですよ。と言われれば、システム2を立ち上げることなく、購買していたのではないかと思料。 手数料稼ぎを目的に、あえて、システム1に頼った、システム2を立ち上がらせないためのセールスが積極的に行われていたとすると、残念な気持ちとなった。
1投稿日: 2021.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ専門書でありながら、とても面白く、分かりやすかった。 人のシステム1はバイアスだらけで、まともに判断してる気になっていることに、時折差し込まれているクイズを通して実感した。ビジネスケースもとても面白かったし、考えさせられた。 人って面白いな、と思いつつ、人を相手にビジネスする際にこの行動経済学的知見は必須だと感じた
2投稿日: 2020.10.04
