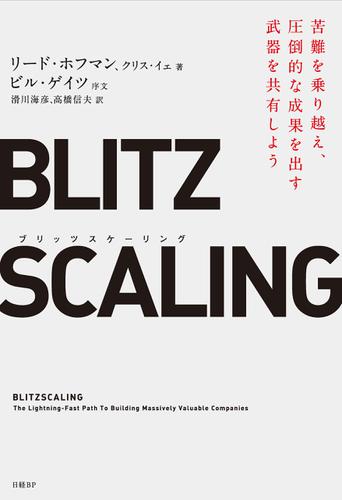
総合評価
(15件)| 2 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ昨今のIT企業、Amazon、uberなどの類を見ない急成長(ブリッツスケーリング)の要因、リスク、方法を解説した本。 想定読者はブリッツスケーリングを目指すスタートアップ企業や大企業だが、読み物としても純粋面白い。しかし、ブリッツスケーリングは一般的な成長ではなく、amazon に代表されるような圧倒的な成長を意味するので、ここまでスケーリングさせたいと思っている人がいるのかは疑問がある。 日本でもシリコンバレーや深圳のようなブリッツスケーリング生み出したい人には必読書だろうが、果たしてそんな人はいるんだろうか。 個人的には、なぜ昨今の企業ユーザー数獲得に躍起になるのかが腹落ちでき、読む価値があった。 2025/7/28追記 『「価値」こそがすべて!ハーバードビジネススクール教授の戦略講義』(2023年 東洋経済新報社)ではネットワーク効果を狙ったブリッツスケーリングには欠陥があることを示している。たった3年で異なる研究結果が出てくるのもまた面白い。
0投稿日: 2025.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップや事業スケールを目指すフェーズにおいて、とるべき打ち手、特に組織や経営のあり方について解説されている。打ち手については、少しリスキーな方法論であると感じるところもあり(リスクを取らねば大きなリターンが無いのも事実だが…)現実の経営では、ファイナンスや資金調達、コスト完了も含めたリスクへのバランスの取り方も併せて理解する必要があると感じた。
0投稿日: 2023.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログペイパルマフィアにしてリンクトインの創業者であるリード・ホフマン氏の著書。大物が書いてある補正でありがたく読了したが、正直同じことを繰り返したり当たり前のことを言っていたりで、読んでいて苦痛の方が大きかった。 一方で稀代の起業家の思考・視野が丸ごと文書化されたような内容で、彼のビジネスの視点や思考を追体験できた意味ではよかった。 ブリッツスケーリングという概念自体は日本のスタートアップ界隈ですで当たり前になっているので、あえて提唱者から丁寧に説明される必要は特になかった。 【総評】 ブリッツスケーリングとは、現代の成功したスタートアップが取り入れている、アグレッシブな成長戦略のこと。本書ではその構成要素が解説されているが、個人的には、本書でブリッツスケーリングを特効薬のように扱っているのが非常に気になった。本書は成功したスタートアップが「ブリッツスケーリングできた」要因となる共通マインドやその仕組みを紹介しているだけである。それを「ブリッツスケーリング」というメソッドを考えたかのように紹介しているのにはモヤモヤが残る。 でも改めて振り返ってみると、ちゃんと教科書っぽく並べられている(かつリーンスタートアップとかよりも事例が多い)ので時々読む分にはいい本な気がしてきた(星3→4に昇格させました) 【学び】 ・ブリッツスケーリングのための重要なテクニックは以下の3つ。 ①ビジネスモデルのイノベーション →急速な成長を遂げる革新的なビジネスモデルは不可欠。 ビジネスは単純に顧客を獲得して、サービスを提供し、売上げを立てることに尽きる。 自分のビジネスのルールがライバルと同じなら、Asset勝負になってしまう。ちなみにテクノロジーが新しければいいというものではなくて、ウーバーやエアビーは前例のない新しいテクノロジーを導入したわけではなく、ビジネスモデルが新しかった。 ②戦略のイノベーション →急激な成長を達成するために何をして、何をしてはならないのかをはっきりさせる。ウーバーはどんなサービスより早くタクシーに乗れることを追求し、その体験ができる人を増やすことを成長戦略とした。 「ムダ」ともいえる多額の初期投資によって、保守的なライバルよりも決定的な規模に到達できたのがウーバーでありメルカリ。→これは人生のマーケティングにおいても同じだと思う。 ③経営のイノベーション 人材不足やアラが目立つプロダクトにも我慢してタクトを奮っていく ・成長の最大化は 大きい市場を見つける→多くのユーザーに届けられる(ディストリビューション)→粗利が稼げる(利益率が高い)→成長投資してネットワーク効果がきいて好循環 というロジックで行われる。 「スタートアップの多くはディストリビューションの重要性を過小評価している」ドリュー・ハウストン(ドロップボックスCEO) 「モバイル時代になるとアプリストアは「たまたまいいものに行き当たる」というセレンディピティを排除してしまう」(本文) →つまり、自社プロダクトがいいものだからと言って勝手に広まることはほとんどないから、広告宣伝を頑張らないといけない。その有効な方法が「既存ネットワークの活用」と「バイラル性」である。 消費者は粗利率は気にしない(プロダクトの価格と自分にとっての便益のみ気にする)ので、粗利率は高い方がいい。 ・でも「PMFできてないこと」と「事業スケーリングの限界(例:オペレーションの拡張に物理的限界があるとかインフラがパンクしたとか)」が成長の最大化を阻むので、それを気にするべし。 ・リードホフマンの「自分磨き」について ー創業者は自分を「学習マシン」にする必要がある ーイーロン・マスクは「巨人の方に乗る(賢い人と話し彼らの成功と失敗から学ぶ)」を意識している。ホフマンも本を読むだけではなく専門家に話をして補うことにしている。 →教養としての人脈の話と同じだった。 ー反省とFeedBackのための時間を残しておく。ToDoリストの無限ループに陥り、重要なことを見失わないようにする。FaceBookのマークとシェリルは、月朝と金夜に必ず顔を合わせて議論する。 「私は自分に投資することを自分本位だと感じていた。自分は働いているべきだと思っていた。(中略)しかし、ほかの起業家と過ごす時間をもっともつべきだった。ヨガか瞑想をすべきだった。例えば仕事を離れてでも、自分自身を磨くことが会社のためになることを私は理解していなかった。」リード・ヘイスティングス(ネットフリックスCEO) 「他の起業家と話すこと。有名な起業家だけでなく自分より1年、2年、5年先をいく人たちと話す。そういう人たちからは、他とは大きく異なる重要な物事を学べる。長期的視点に立つ感覚は非常に大事だ。フェーズが変わるごとに、状況は静かに変わっていくからだ。」ドリュー・ハウストン(ドロップボックス) ・ブリッツスケーリング時代に我々が認識しておかないといけないこと ー急速に変化する世界で生き残るには、不確実性を不可避と受け入れるしかない・不確実性を自らの優位性に変えていくべきだ ーこの時代において専門家は存在しない。 「ライバルに比べて学習曲線を登るのがわずかに速いというだけで、巨大な価値を築くチャンスが生まれる」 「変化こそが唯一の不変のものという世界にあっては「常に学ぶ」ことこそ適応への最良の道だ」 ー常に最初に反応する者になる必要がある。 新しいテクノロジーやトレンドが現れたとき、われわれは往々にして自分の居場所を見失い、思考を麻痺させてしまう。これでは行動せずに変化を眺めているだけになる。 不確実さを物ともせずに行動する人が巨大なチャンスを得る! 「ブリッツスケーリングを実行する際の不安感は、よりよい未来をできるだけ速く手に入れるためには小さな代償だろう」 【印象的なフレーズと感想】 「会社がブリッツスケーリングしているとき、リーダーはたとえ確信の度合いが100パーセントにはるか届かない場合でも、とにかく決断を下し、断固としてその決断を守り抜くべきだ。ライバルに先駆けて動くためなら、間違った決断をして、その結果、大損害を被るリスクを受け入れねばならない。」 →大企業にはない精神なので意識したいし、言語化してくれてありがたい。「良い戦略、悪い戦略」の選択と集中の話に似ている。これらは往々にして「決断を下すための自信・知識・経験・情報」が足りず実現しないことが多いので、それらを得る方法を考えなければならない。 「トップクラスの人材は市場に大きな影響を与えたいので、リーダー企業で働きたがる。同時にスケールアップに成功した宇宙ロケット的な企業に参加することは、経済的に非常に有利だ。一般的な初期段階のスタートアップに加わるよりもはるかにリスクが少なく、成長の確実性が高い。」 →その通り。自分の能力を過信して簡単に成長が始まってないスタートアップにいくのは愚策 「みんなが好きなプロダクトをつくれ。すごい人材をみつけろ。それ以外?それ以外に仕事なんかない。まやかしだ。」ブライアン・チェスキー(AirBnb創業者) 「基本的な定義に焦点を当てるべきだ。企業のビジネスモデルは、プロダクトの生産、販売、サポートによってどのように金銭的な利益を生み出すのか示さなければならない」アンドレア・オバンズ(ハーバードビジネスレビュー) 「意見で決めるなら、私の意見が常に勝つ。しかし、データは意見に勝つ。だからデータを持ってこい」ジェフ・ベゾス(Amazon)
0投稿日: 2022.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップの急成長に必要な考え方や方策、そして様々な企業の事例とともに紹介されている。 変化が激しく、何が正解か分からない世界においては、スピードこそ命。そして、学び続け、タイミングを逃さずにスケーリングする。スケーリングするために、豊富な資金をいかに獲得して、競争優位性を保てる状態にするのか、似たビジネスモデルとの短期決戦をいかに乗り切るのか。 起業家にとっては、参考になることが多いと感じたが、しがないサラリーマンには、遠い世界のことが書かれているように感じてしまった。
0投稿日: 2021.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ少し興味があり、買ってみたが、なかなか進まなかったです。今まで読んだ本で一番進まなかったかもです。ビジネス本だが、世界、立場、業界、全てに置いてあまりにも自分とのギャプがあり過ぎて正直ちんぷんかんぷん。言いたい事はわかるところもあり、しかも知ってる企業も出てくるのだか、何故か進まなかった。全部繰り返しの文章に見えてくる。 それとも、おそらく自分は、訳本が苦手なのかも。
1投稿日: 2021.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログスタートアップが急成長するための戦略「ブリッツスケーリング」。効率性よりもスピードを重視する、この戦略の本質や仕組みについて解説した書籍。 スタートアップがある程度の成功を収めると、次はキラープロダクトや大規模な市場が必要となる。そうした、スケールアップの段階に最速で至るための経路が、ブリッツスケーリングによる急激な成長。 ブリッツスケーリングの基礎となる要素は、次の3つ。 ①攻めの要素と同時に守りの要素がある 市場に奇襲をかけるといった攻勢の要素と、ライバルが追い付けないスピードで前進するという防御の要素をもつ。 ②先に規模を拡大した会社が、競争優位を得る 最初にスケールアップした企業に、人材と資金が集中する。 ③巨大な利点がある一方、リスクも大きい 急速な成長は、様々な問題を引き起こす可能性がある。 ブリッツスケーリングを成功させる上で、最も基本となるのは、急成長できるビジネスモデルを設計すること。優れたビジネスモデルは、次の4つの成長要因が最大化されている。 ①市場規模 巨大企業を目指すなら、小さすぎる市場にかかわらない。 ②ディストリビューション 費用のかからない、独創的な流通・販売方法を考え出す。 ③粗利益率の高さ 利益率の高さは投資家にとって魅力的で、投資を促す。 ④ネットワーク効果 ネットワークのサービスのユーザーが増加し、スケールが拡大することで利益が増し、「1人勝ち」状態となる。
0投稿日: 2021.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ・ブリッツスケーリングには攻めの要素と同時に守りの要素がある。ライバルがついてこられないスピードで前進することで、相手はこちらの動きの対応に集中せざるを得ない。彼らがこうした悪循環に陥ると、我々を脅かすような新たな戦略を打ち出すための時間も失われる。ブリッツスケーリングは自分に強みがある場所を戦場として選べるようになる ・マーケットの両側でプロモーションに力を入れ他社を引き離す。ウーバーならばドライバーと乗客にインセンティブを出すことで素早く決定的な規模に到達した ・モバイルファースト時代になると、ゲームは別として、「たまたま」アプリをインストールするユーザなどほとんどいない ・既存ユーザの維持にも力を入れるべき。 ・サービスのユーザー数または利用料の増加がネットワークの効用を増大させるなら、そのサービスにはプラスのネットワーク効果が働いている。(ファックスやFacebook) ・5種類のネットワーク効果 1)直接的ネットワーク効果:使用量が増えると、価値が直接的に高まる(SNS) 2)間接的ネットワーク効果:使用量が増えると、補完材の消費を促し、間接的にプロダクトの価値が高まる(スマホユーザのAndroidなど) 3)双方向ネットワーク効果:あるユーザグループによって使用量が増えると、別の補完的なユーザグループの価値を高める(Air BnBなどのMarketplaceサービス) 4)ローカルネットワーク効果:一部のユーザグループの使用量が増えると接続ユーザの価値が高まる(一部の電話放題かけ放題サービスなど) 5)互換性と標準規格:あるプロダクトの仕様が増えると、それと互換性のあるプロダクトが有利となる ・優れた考えに巡り合うことがめったにないのは、才能の欠乏というより勇気の欠乏からきている ・ゼネラリストは組織の「幹細胞」と考えるとよい。人の身体には、必要に応じて様々なタイプの細胞に変化する能力を持つ幹細胞が少数存在する。大きな組織では、必要に応じて様々な機能を果たせる人が必要となる。 ・アマゾン上の質問回答機能は、顧客にメールを送り質問した結果得られた回答をベースに採択された ・指標は情報に簡単にアクセスできて根拠がわかりやすいことが重要 ・何をしないかを決めることは、何をするかを決めるのと同じくらい重要だ ・私は皆のためにルールを変えようとしているのか、自分だけが逃れようとしているのか ・自分の学びを考え、自分を磨く時間を取れば、手本として会社全体に学びの文化を広められる ・計画錯誤とは、ベストケースのシナリオに基づいて計画を立てること、そしてもっとよく考えるべきなのに計画通りの結果を想定してしまうこと ・変化がずっと重要 ・小さなリスクでも、将来体系的な問題に変わる恐れがある問題は放置してはいけない。すぐに行動できない場合でも、後で必ず対応すると約束すべきだ。そうすれば将来そのリスクが体系的になったときにうろたえずに済む ・不確実性に立ち向かうためには、安定性が必要だ。何もかもが変化する世界では、人は何か確実なものを求める。嵐の中でこそ冷静さと確固たる指導力を保つことが重要となる
1投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ企業成長の過程の事例集。企業のステージにおいて、やるべき施策、組織が変わってくる。 グローバルでのシェアを取りにいっている企業たちの思考や戦略が知れるという意味でも、読み物としても、とても面白い。
0投稿日: 2021.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログスピードと不確実が安定に取って変わる時代において必要となるブリッツスケーリングの考え方についてが事例とともに解説される。ブリッツスケーリングを進める際には企業規模による各ステージにおいてマネージメントの方法や必要な人材も変わってくる。企業カルチャーの変更さえあるかも知れず、その際の考え方、進め方が語られる。 自分は安定の時代におけるレガシー企業の働き方にしか馴染みはないが、ブリッツスケーリングの考え方は日常の業務にも活かしていける、むしろ取り入れなければこれからは難しくなるだろうとも感じた。
0投稿日: 2021.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログうーん、内容的には他書で議論されていることが多く、あまり目新しさがなかったです。また、ホフマンの実体験に基づく生々しい現実、というよりは、コンサルが書いた感じの事例羅列っぽくなっていて、面白さがあまり感じられませんでした。
1投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ【読んだ本の感想とメモ】 ■ブリッツスケーリング pmfの後の非効率であるが競争の中での不確実性に最も有効な素早い意思決定を伴ったスケーリング 採用、マネジメント、ファイナンス、オペレーションあらゆる箇所に成長痛が伴う モデルの革新、グロースの革新、経営の革新が必要であった。 それはすべて、誰もがやらないことをやり、やっているはずのことをやらないリスクを段階的に意思決定することである。スケールすることをしながら、スケールしないことをするとても矛盾した営みかもしれない。 もちろん、マーケットの成長や、エコノミクスの不成立がある場合は推奨されない諸刃の剣なのだ。
0投稿日: 2020.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ効率を度外視しとにかくスピードを出す。歩留まりよりも前進。それがブリッツスケーリングだ、という話だが、読み進めていくと「あれ?」という瞬間が出てくる。 例えばAppleの戦略、あれは選択と集中ではないのだろうか、と。 効率うんぬんというより「直感に反する、スケーリングにおいて重要な意思決定と行動」、それがブリッツスケーリングの骨子なのかもしれないと自分なりに腹落ちさせた。 カルチャーを大事にする。evilにならない。 意思決定プロセスの周辺領域は驚くほどオーソドックスだ。 Nokiaの例に顕著だが、ブリッツスケーリングしたスタートアップに凋落させられるというのは現実に起こりうることだ。 ただ、結局のところブリッツスケーリングとはなんなのかという点が抽象的かつ広範に過ぎるのではないかと感じた。
0投稿日: 2020.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の興味関心の方向の問題なのか、他の人がいうような衝撃や魅力を感じられず... これを参考にできるほど、自分の事業的なレベルや経験、悩みが至っていないということな気がするな。
0投稿日: 2020.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://www.silkroadin.com/2020/04/blitzscaling.html タイトルにはこう書かれています。 「苦難を乗り越え、圧倒的な成果を出す武器を共有しよう。」 本書はブリッツスケーリングの行使によって成果を出すことをメインテーマに、 ブリッツスケーリングの取り扱いについて書かれた本となっております。 「ブリッツスケーリング」とはブリッツクリークによって企業を急成長させるという造語だ。(引用 BLITZSCALING、リード ホフマン、クリス イェ/日経BP) 詳しくは本書を読んで頂くことで明らかになりますが、少し内容をご紹介致します。 先の見通しがつかない現代ですが、変化するということだけは確実です。 何が起きるか分からないからこそ効率よりスピードを重視する。 意思決定の速さ、リスクと不安を伴うタフな決断がわたしたちには必要です。 これはハイリスクハイリターンな戦略でしょうか。 慎重すぎることや決断が遅れることもまたひとつのリスクです。 熟考を重ねた良いアイデアや、効率的な手法も結果が出なければ意味がないからです。 成果を出すために、素早く動く。 いつの時代もスピードは重要です。スピード重視の考え方は昔から存在しています。 現代においてもスピードこそ成果を出すための武器であるとわたしたちは確信します。 スピード重視の成長戦略。 BLITZSCALING 苦難を乗り越え圧倒的な成果を出す武器を共有しよう リード ホフマン、クリス イェ/日経BP ぜひご覧ください。
1投稿日: 2020.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログリードホフマンにしか書けない本 最近読んだ本の中で、一番衝撃的な本だった 僕が、エアビーを知った時には、圧倒的な企業だったが、そこに至るまでには、財務リスクをとり、事業のリスクをとり、様々なリスクを取ることによって、あれほどの企業になっている事を知れた。なかなか外には出ない情報だと思われるが、リードホフマンだから書けたものだと思う。 スケールに関して、いくつもの事例があったが、それと並行して驚いたのが、カルチャーの大切さを語っていた事だ。カルチャーにフィットしてない人材は、どれだけ能力が高くても厳しいという文があり、これはアカツキの塩田さんも言っていたため、自分の中での大きな戒めになった。 素晴らしい本だったので、スタートアップの多くの人にオススメ。
0投稿日: 2020.03.15
