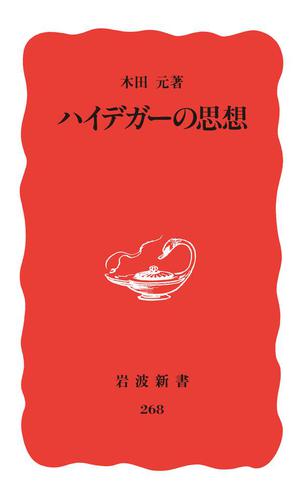
総合評価
(26件)| 7 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
↓僕なりの理解 現存在は、現存在自身をも含む存在を存在者たらしめ、世界を構築する意識的な現場である。存在は無意識で知覚され、存在者は意識で認識される。この存在了解=存在投企は、自然現象的に起こる出来事であり、現存在はあくまでその座として出来事を眺める。その意味で、存在は現存在に先立つ。 ソクラテス以降の哲学は、存在を本質存在(-である)と事実存在(-がある)に分節し、ニーチェは存在を力への意志と永劫回帰で捉え直し、哲学は極地に至る。個体は、この混沌と秩序を志向する力としての二つの存在が拮抗し、その結果として表現される存在者である、ということだろう。しかし存在は、本来分節していない自然(ピユシス)なものであり、哲学の外部にある。名詞的な現前として分節する(非本来的時間性)のではなく、動詞的な瞬間として捉える(本来的時間性)ことでしか、形而上学を乗り越え実存を捉えることはできない。言葉は無意識(存在)の表出のひとつだが、あくまで意識的なものである。形而上学、つまり存在忘却、故郷喪失の時代にいる我々にできることは、思索や詩や芸術を通して、失われた存在を追想しつつ待つことである。 作品を端緒として、クローズアップされ分節され再構成された存在者を見ることで、その背景にあるコミュニズム的世界が開かれ、現れ出る。この世界を含んだ存在者をソクラテス以前のギリシア人は自然(ピユシス)と呼んだ。ある作品=被制作物=存在者(神殿)を通じて、それまで混沌であったところに世界の明るみ=ピユシス(太陽、潮騒、生物たち)が開かれる。その現成と同時に、暗みにある故郷とも呼ぶべき基底としての大地が初めて姿を現す。ここで、世界と大地は闘争の関係にある。つまり、大地=混沌と闘争しながら存在者が存在者として立ち現れ、それらの相互作用から世界が開かれるという無意識の過程こそが真理の実現態であり、芸術作品は、形而上学の外部にある、この自然(ピユシス)な存在と無意識の深みにある感性との交響を、増幅し具象化して追想させる存在論的機能をもつ。
0投稿日: 2025.04.27 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの「存在」の解明に焦点を当てた解説書。存在とは何かと聞かれたときに「存在とは~である」と答えるのは、「である」という言葉を使用しているという点で自己撞着に陥っているという難しさがある。ハイデガーの唯一の著作に当たる「存在と時間」にもある通り、ハイデガーはそれを時間に求めた。ハイデガーは存在は現存在と呼ばれる、過去と未来の概念を持つ者によって了解されることで生じると考察する。これはハイデガー以前の、「存在は制作されることにより生じる」という視点を解体することで生じる。ハイデガー以前の哲学の考え方では、神の存在を仮定しないと人間の存在を規定できないという欠点があるが、ハイデガーのそれはその部分を克服している。 全体的な感想としては、幅広い哲学的教養がないと全体の理解は難しいと感じた。浅学故、中後半の、各哲学者をどのようにハイデガーがとらえたかを記載した部分は正直理解ができなかった。
0投稿日: 2024.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ハイデガー関連の書籍初挑戦。にしては、木田元著作のものを選ぶのは無謀だったかな、と読み終えた後の理解度を鑑みて少し後悔している自分がいる。 そうはいっても、諸学者向けの網羅的な作品としてではなく、ハイデガーの「存在の思索」に思い切って焦点を絞った作品として自分の心づもりを変換すれば大変興味深い読書体験ということができる。本書の内容を要約するには力及ばず、なので付箋をした過去の自分を信じ引用箇所にコメントするに届め、個人的なおさらいとさせていただこう。 <存在了解>という用語の説明。<存在企投>という用語に言い換えているが、観念的な話でどうもふわふわとして腑に落ちない難解さがあるな。 P83:<存在企投>とは、現存在がいわば<存在> という視点を投射し、そこに身を置くことだと考えればよい。つまり、<存在>とは現存在によって投射され設定される一つの視点のようなものであり、現存在がみずから設定したその視点に身を置くとき、その視界に現れてくるすべてのものが<存在者>として見えてくる、ということである。 ハイデガー流の「現象学」の定義。私はもちろん、現象学に対しても学びが足りないので、へーそうゆうものかという程度の感想で不甲斐ない。 P99:<存在>というものがけっして存在者に属する何かではなく、人間において正起するある働きだということを原理的に解き明かし、その働きを体系的に解明することが現象学の使命だと言っているのである。 アリストテレスとプラトンの存在概念を対比させながら、その二つの起源的な根源的存在を解き明かさねばならないというののがハイデガーの主張だと理解。プラトン・アリストテレス解釈のまとめとしては以下の引用か。 P124:古代・中世・近代にわたる伝統的存在論のうわべの多様性が解体され、そこにはプラトン/アリストテレスのもので形成された<存在>概念がさまざまに歪曲されながらも一貫して受け継がれていること、そしてそれが<存在=現前性=被制作性>という存在概念であることがみごとに明らかにされる。 前期の<存在了解>から後期の<存在の生起>への「思索の転回」。「存在」というものが現存在(人間)が主体か、自然が主体かの重心の変化かなと理解。 P143:この転回を、<現存在が存在を規定する>と考える立場から<存在が現存在を規定する>と考える立場への転回ということができるのかもしれない。 ハイデガーによるプラトンの存在論への評価。繰り返しになるが、これ以降本書内でアリストテレスと対比されている。 P164-165:つまり、存在を自然として捉える立場と、存在をイデアとして捉える立場は、<存在する>ということを<発言し現れ出る>ことと見る点では違いはないのだが、ただその視線を向ける先が違うのである。前者はあくまで現れ出て存続しつつあるその動きに目を向けるのに対し、後者はすでに現れ出たものが外からをそれを注視する働きに対しおのれを提示するその姿だけに目を向け、これを超自然的存在に高めてしまう。こうして、後者の視線のもとでは、。その目撃される存在の外観によって示されるその「何であるか」、つまり<本質存在>が表立ってきて、それに対して、それから取り残されたものとして<事実存在>が区別される。 プラトン/アリストテレスの存在観の対比を端的に述べている個所。ここから始原の単純な存在=自然としての存在が押しやられ、忘却されてしまう「故郷喪失」という時代が今なのだとうまとめかな。 P173:つまり<被制作性>と同義である。ただ、その際プラトンは、その作品がいかなる<外観>を提示し、<それが何であるか>にもっぱら目をとめ、つまりはその制作を導いてきた<イデア>の現前性に優越的な存在を認めたのに対し、アリストテレスは、あくまで個物が作品として眼前に現れ出ているその現前性、<それがある>としての現前性、<現実態>としての現前性を第一義的なものと見るのである。 後の章で技術・芸術論に踏み込んでいるが、ここはより詳細な説明を求むかな。著者本人も概略だけを説明するに留めるてきなことで、簡便なものにまとめているので。
4投稿日: 2023.01.29 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの存在論や哲学観の全体像がよくわかる。カント、ヘーゲル、ニーチェ、フッサールなどの関係性や影響も時系列ごとに綺麗に整理されていて読みやすい。
0投稿日: 2022.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ技術論については、紙幅の制約と、著者の理解不足により、ここでは取り上げることができなかった、とある。残念。
0投稿日: 2021.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
最近、木田元の哲学書をいくつか漁り読みしたので、木田元のハイデガーへの思い入れと「存在と時間」の解釈について大分わかってきたので、それを補強するための適書。形而上学を否定するハイデガーの企てには恐れ入るが、そもそも形而上学ってリアルな人生において何の意味があるかが分かっていない自分には理解できない。まあヨーロッパに生まれ育たないと理解できないようなので、日本人である私にはわからなくて当然なのでしょう。哲学は所詮は、時代・場所・文化に深く根ざしているものなのだから。
0投稿日: 2019.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの言う「存在」とは何か。本書はそれを丁寧に説き明かしてくれる。その説明の中で「世界内存在」という概念についてわかりやすい解説が行われている。これらを杖にもう少しハイデガーの思想について勉強していこうと思う。
0投稿日: 2015.11.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ存在、という驚異。 これは人間に固有のものである。 特定の環境に依存せず、複数の環境をメタ的な視点で再構築する能力、そしてそれは存在ということなる。 そしてその存在というものは、自らの意思ではなく、超越した力により存在する。 「神秘的なのは、世界がいかに存在するかではなく、世界が存在するということである」と述べたのは、ウィトゲンシュタインであり、ライプニッツの「なぜ何もないのではなく、何かが存在するのか」という問い。
0投稿日: 2015.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ大船図書館で読む。この図書館は狭いですね。非常に読みやすい本です。この人が、売れっ子である理由がわかります。図書館ではなく、購入してじっくり読む必要がある。
0投稿日: 2014.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
存在論とは哲学そのものであり、それを考え続けることが哲学だが、例えば本書後半にあるように芸術にその試行を転用してみたりするとまた面白さと深みが倍増する。 ゴッホの絵画や神殿建築に寄せられたことばのきらめきは感動的である。 ラディカルに問い続けること。光は闇を背景としてしか存在しない。
0投稿日: 2014.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ウィトゲンシュタイン「神秘的なのは、世界がいかにあるかではなく、世界があるということである」『論理哲学論考』p78 【3つの命題】p82 ①現存在が存在を了解するときにのみ、存在はある(エス・ギブト) ②存在は了解のうちにある(エス・ギブト) ③現存在が存在するかぎりでのみ、存在は<ある>(エス・ギブト) <世界開材性>とか<世界内存在>というのは、人間がそうした<世界>という構造を構成し、それに適応しながら生きる生き方、存在の仕方を指すと考えてよい。このような高次の機能によって、現存在が現に与えられている環境から身を引き離すその事態を、ハイデガーは<超越>と呼んでいる。現存在は、<生物学的環境>から<世界>へと超越するのである。p86 ハイデガー「あらゆる存在者のうちひとり人間だけが、存在の声によって呼びかけられ、<存在者が存在する>という驚異のなかの驚異を経験する」p89 <存在=現前性=被制作性>というアリストテレス以来の伝統的存在概念は、ハイデガーの考えでは、非本来的な時間性を場としておこなわれる存在了解に由来する。p139 ハイデガー「ピュシスとはギリシア人にとって存在者そのものと存在者の全体を名指す最初の本質的な名称である。ギリシア人にとって存在者とは、おのずから無為にして萌えあがり現れきたり、そしておのれへと還帰し消え去ってゆくものであり、萌えあがり現れてきたっておのれへと還帰してゆきながら場を占めているものなのである」『ニーチェ』p156 ハイデガー「<力への意志>という名称は、存在者がその<本質><仕組み>から見て何であるかを告げており、<等しきものの永劫回帰>という名称は、そうした本質をもつ存在者が全体としていかにあらねばならないかを告げているのである」p182 【存在が言葉になる】 すべてに先立ってまず<ある>のは、存在である。思考は、人間の本質へにのこの存在の関わりを仕上げるのである。思考がこの関わりをつくり出したり惹き起こしたりするわけではない。思考はこの関わりを、存在からゆだねられたものとして、存在に捧げるだけのことである。この捧げるということの意味は、思考のうちで存在が言葉となって現れるということにほかならない。言葉こそ存在の住居である。言葉というこの宿りに住みつくのが人間なのである。思索する者たちと詩作する者たちは、この宿りの番人である。彼らがおこなう見張りとは、彼らが語ることによって存在の明るみを言葉にもたらし言葉のうちに保存するというふうにして、その明るみを仕上げることにほかならない。『<ヒューマニズム>についての書簡』p201
0投稿日: 2013.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの本当のところを知るには少々物足りないかもしれないが、新書なので内容としては十分だった。変にポップでもなく、きちんと読めたのは好感的。他の読書案内もあって、参考にしたい。
0投稿日: 2013.06.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読もう読もうと思いつつも、難解で近寄りがたいハイデガー。この本は大変分かりやすかった。存在の見方をひっくり返すハイデガーの考えが平易な言葉で読みとかれている。 存在は、〈それが何であるかということ〉「本質存在」と、〈それがあるということ〉「事実存在」とに区別される。その区別とともに形而上学としての存在の歴史がはじまるのである。 哲学史全体にわたったハイデガーの思想を考えることをと通して、哲学の根本問題について語られている。アリストテレスやプラトン、ソクラテス以前の哲学者たちの思想を理解するのにも役立つ。
0投稿日: 2013.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーは20世紀最大の哲学者として、またきわめて難解な思想家として名高い。一方ナチスへの協力者として、その言動は厳しく糾弾されてきた。ここでは主著『存在と時間』の精緻な解読を通じて、ハイデガーの存在論や哲学史観の全貌を描く。と同時にその作業を通じて、なぜナチスに加担したのか、その理由をさぐり、思想の核心に迫る。
0投稿日: 2012.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログハイデガーの入門書。主著である『存在と時間』を中心にその人生や周辺人物の記述も交えて解説。非常に難解なハイデガーのテクストも木田元氏にかかればここまでわかりやすくなるのか、と思えてしまうほど咀嚼されている。 実際に記述が信頼できるかは私が判断できるところではないが、これを手引きにハイデガーの著作を読んでいけば自ずとわかってくるだろう
0投稿日: 2011.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログとかく難解と言われるハイデガーの著作。もともと日本語で訳すことができるのかどうかさえも疑わしいハイデガーだが、木田先生特有の言葉で綴るハイデガーのエッセンスは、おそらく他の追随を許さないほどの見事な解釈とわかりやすさである。木田先生は日本を代表する知性だとあらためて思う。
0投稿日: 2011.12.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書はハイデガーの生い立ちや哲学史観の紹介、主著「存在と時間」の解読、ナチズムへの傾倒と戦後の様子を分析することを通じて、彼の思想変遷を明らかにしようとする試みである。 そのため哲学門外漢であり、主著の「存在と時間」に関心を抱くのみである私にとっては、本書中盤の哲学史観に関する記述が少々骨の折れるものであった。 不勉強が祟ったか・・・要再読である。
0投稿日: 2011.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 主著『存在と時間』の精緻な解読を通じて、ハイデガーの存在論や哲学史観の全貌を描く。 と同時にその作業を通じて、なぜナチスに加担したのか、その理由をさぐり、思想の核心に迫る。 [ 目次 ] 序章 一つの肖像 第1章 思想の形成 第2章 『存在と時間』 第3章 存在への問い 第4章 ハイデガーの哲学史観 第5章 『存在と時間』の挫折 第6章 形而上学の克服 第7章 ハイデガーとナチズム 第8章 後期の思索?言語論と芸術論 終章 描き残したこと ハイデガー略年譜 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終わってから時間が経ってしまったので記憶がぼけてしまったり、理解が間違ってるかもしれないのでご了承を。哲学に疎い自分でも読めるように分かりやすく解説されてる本だった。同時代の人たち、詩人や哲学者との関係について紹介し、またナチスとの関連についても解説されている。当時は第一次大戦に敗北した極限的な状況だった。 ハイデガーの有名な著書「存在と時間」。この本は発表された当時、人々に大きい影響を与えたらしい。戦争中であったのでそういうことに敏感な人が多かったのだろう。 僕がハイデガーを勉強しようと思ったきっかけは、存在とはいったいなんなんだろうって疑問から。自分のことに自信がもてなくて、自分は一体なんなんだろうって悩んだりしてて、そういうことを教えてくれるものはないかなと思って。 でも、ハイデガーは、人間のあり方はどうあるべきか?ということを考えていたのではなく、むしろ「存在」とはなにかを探っていたのだという。表現が難しいのだが、「~デアル」と「~ガアル」の違いだとこの本では述べている。 難しく言うと、事実存在と本質存在の違いだという。哲学史上、いろいろな考えの哲学者がいたが、プラトン的な考え方とアリストテレス的な考え方がある。プラトンとしては、なにか純粋的な概念があり、それをもとにしてモノが存在する、と考えていた。アリストテレスは、なにかモノが先にあり、それがしめす性質があるという考え方だ。ハイデガーによるとモノは被制作物であるという。なにか純粋的な概念な概念があり、その概念をもとにだして創りだしたのがモノだと。英語のcreatureはcreateから来ているように。そして、一見相反するようだが、アリストテレスも実はこの考え方だといっている。しかし、こういった事実存在と本質存在という区別化は本当の自然(ピュシス)を忘却してしまうことであるらしい。ピュシスは英語のnatureに相当する単語らしい。natureといえば、自然であるが、nature of …という用例だと~の本質という意味にもなるように、本質という意味が近いのかもしれない。ハイデガーはこの形而上学の存在の区別の克服を目指していたが解決できなかったらしい。ちょっと自分の理解が怪しい範囲になってきたのでここまでで… あと、後期の芸術論についても述べてあった。思索とはつまり創造すること、createすることで、芸術の本質とはそういうことだということが書いてあった。芸術作品の中に世界をcreateすることが本質だと。詩作も思索であるとかだじゃれっぽいことを言ってたり(違 ここらへんも誤解してるかも こうまとめてみると、ハイデガーの思想をとてもわかりやすく解説してあるいい本だったけど、自分の中でちゃんと噛み砕けてないなあと痛感。またの機会に借りなおしてよもうかな。
0投稿日: 2011.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログすべてに先立ってまず<ある>のは、存在である。思考は、人間の本質へのこの存在の関わりを仕上げるのである。思考がこの関わりをつくり出したり惹き起こしたりするわけではない。思考はこの関わりを、存在からゆだねられたものとして、存在に捧げるだけのことである。この捧げるということの意味は、思考のうちで存在が言葉となって現れるということにほかならない。言葉こそが存在の住居である。 ・・・・・・『ハイデガーの思想』202頁 本著は、ハイデガーの未完の著作『存在と時間』を中心に語られている。 ソクラテスとプラトンによって、存在が「本質存在」と「事実存在」とに分断された。それによって、哲学を哲学たらしめてきた。が、それ故に、その枠を超えて存在を問う術をなくしてしまっている。より根源的な『存在』の存在を問うべきではないか。・・・と、解釈してみようと思う。 また、前半部分の記述ではあるが。人は時間性を持って、世界を認識している。人間は、現在<いま>を認識するとき、瞬間的、断片的な状態のみを認識しているわけではない。現在に至るまでの過去と、現在から派生するであろう未来を、合成した世界「時間性を持った場」を認識し、次の行動基準としているのだという。この世界観はおもしろいと感じた。 本著には多くの哲学者が登場する。中心人物には解説が添えられているが、やはり各哲学者の知識がなければ、読み解くのは難しいのだろうと思う。 ソクラテス、プラトン、アリストテレス、デカルト、カント、ヘーゲル、ショーペンハウエル、ニーチェ、ヤスパース、フッサール、サルトル、ウィトゲンシュタイン・・・などだ。 少なくともニーチェ以前の哲学者への知識があったほうが、そしてその知識が深ければ深いほど、ハイデガーの着眼点に驚かされるのではないかと思う。
0投稿日: 2010.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ『ナトルプ報告』の紹介を含めて、ハイデガーの「存在の歴史」に対する見方を、たいへんわかりやすく解説している。 同じ著者による『ハイデガー』(岩波書店「20世紀思想家文庫」、および「岩波現代文庫」)に比べると記述があっさりしていて、手に取りやすい。 あえて難点をあげると、『芸術作品の起源』についての解説はちょっと残念。ハイデガー自身に語らせるのもいいが、著者自身のもう少し踏み込んだ解説が聞きたかった。
0投稿日: 2010.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ2010.10.6 存在とは何か? 「我思う、故にわれ在り」の在るとは何か。 存在は、現存在が存在了解するうちにある。 世界内存在。(人間は、時間軸のズレのおかげで、環境から身をはがし、より高次に構造化する) 本質存在と事実存在。
0投稿日: 2010.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ第六章 形而上学の克服 ヘラクレイトスらのプレ-ソクラテスの思索:自然哲学;生成されたものとしての自然ではなく、生成する自然(natura naturans)についての驚き この自ら生産するピュシスとしての存在は、本質存在と事実存在へと分かれておらず、原初の単純さを保持している。/ 「存在とは何であるか?」という形而上学の問いは本質存在と事実存在を分離せしめる。そして、この分離自体が形而上学の成立の条件である。 第一章 思想の形成 「いわゆる存在者レベルでの神への信仰は、結局のところ神を見失うことではなかろうか」p45 第三章 存在への問い ウィトゲンシュタイン:「神秘的なのは、世界がいかにあるかではなくて、世界があるというそのことである」(論考)p78 「私はハイデガーが存在と不安について考えていることを、十分に考えることができる。人間には、言語の限界へ向かって突進しようとする衝動がある」p79 「この体験を記述する最善の方法と私が信ずるのは、私がこの経験をするとき私は世界の存在に驚く、ということである。その場合私は、<何かが存在するとはなんと不思議なことだろう>とか、<世界が存在するとはなんと不思議なことだろう>といった言い方をしたくなる」(倫理学講和)/ 「不安の無の明るい夜の中で、存在者としての存在者の根源的な開示がはじめて生起する」(形而上学とは何か) 第八章 後期の思索―言語論と芸術論― 「詩人とは、真剣に酒神を歌うことによって、逃げ去った神々の痕跡を感じ取り、その痕跡の上にとどまり、自分と同類の死すべき者たちに転回への道筋をつけてやる者たちのことである」p207
0投稿日: 2010.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこの数百年間で最も偉大な哲学者と呼ばれる 「ハイデガー」というドイツの哲学者のことを書いた本。 主に「存在と時間」と「ハイデガーがナチスに加担したこと」などについて 公正な視線で書かれてある、非常に読み応えのある本。
0投稿日: 2008.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ比較的わかりやすい哲学書だと思ったので、☆4つ。 理解しているかと言われれば、生返事しかできないが、〔存在と時間〕について納得できたような気がする。 理解するのに時間がかかるから途中で切り上げ。 また、手にとろうかな。
0投稿日: 2008.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は「存在と時間」を読みたくて東北大学の哲学科に進んで以来、半世紀以上ハイデガーを読み続け研究を重ね続け斯界の泰斗と目されてきたけれど、その割にまとまったハイデガー本が少ないのですね。批判的に捕らえている部分がかなりあるせいか。 これは初心者用に易しく書かれているとはいえ、思想的射程は深く広い。
0投稿日: 2007.02.28
