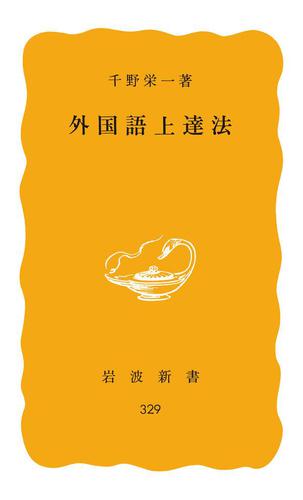
総合評価
(87件)| 31 | ||
| 34 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を使って商談をするのは結構キツくて、時々修羅場を迎える。一対一なら身振り手振りとスマホを駆使して誤魔化すが、用意していたナレーション付きのプレゼンに対しアドリブを求められた時、頼り切っていた通訳代わりの方が欠席で自力で対応せざるを得ない時など。 何とかならんかと思うが、こればかりは地道な努力をするしかない。自然な翻訳ガジェットが普及してくれれば良いのだが、まだその時は来ていないらしい。 そんなあなた(私のこと)に、この一冊! 何が響くかはその人次第だと思うが、私に響いた二点を紹介してみたい。響いたと言っても、慰められた、勇気を貰ったという感じに近い。 一つは、母国語でも語彙は完全じゃなくて、幾つになっても読書では知らない言葉に出会うし、日々、新たな言葉も生まれてくるよねーという話。だから、もう〝ある程度“で飛び込んでしまえ。それと文法なんて正確じゃなくて良い。 もう一つは、「必要なシーン」だけ乗り切れればいいだろ、という話。これだ!つまり、その国で美容室に行くなら美容室用のシナリオを覚えてしまう。商談なら商談のシミュレーションを。今ならそれをAIに自然な感じに訳して読ませる事もできるし。 ということで、この本のおかげで完璧主義に向けた地道な努力から遠ざかった気はするが、プレッシャーからは随分解放されたのである。
75投稿日: 2025.09.21 powered by ブクログ
powered by ブクログミラン・クンデラの『存在の耐えられない軽さ』の翻訳等でも知られる千野栄一氏の語学指南書。初版以来これまでに何十回も増刷を重ねていることからも窺われるように、本書は非常に多くの読者を惹き付けてきた歴史的名著であり、歳月による風化を乗り越え、なおもずっと輝きを失うことのない新書の金字塔である。 筆者が何度も、語学の「語彙」や「文法」の重要性について語るのは勿論のこと、個人的に甚く感銘を受けたのは、そもそも言語習得において何よりも大切なことは「時間」と「お金」だと言い切っている箇所。それも、かなり序盤でこの命題を提出しているところに目を瞠った。巷間では、「語学の勉強において、大切なのは〜〜〜だ」といった言説が非常に多い。その「〜〜〜」の部分は、論者によって千差万別。先の「文法学習」を真っ先に挙げる人間もいれば、「音読」を唱える者もいよう。はたまた「英文解釈こそが全てだ」と嘯く専門家さえいる。あるいは、もっと抽象的な水準で――もはや当たり前のレベルで――「復習が大切だ」と改めて(?)声高に主張する輩も存在する。 こんな調子で、(時として低次元の)言語学習についての虎の巻が世に氾濫する中、この千野氏の著作は――あたかもどこ吹く風と言わんばかりに――そもそも「時間」と「お金」を費やせば費やすほど、語学は上達すると言ってのける。これは意外な盲点で、蓋し慧眼。そもそも我々は「大前提」から考えることを久しく忘れてはいなかったか?先に挙げた語学学習に関する百家争鳴の意見(「文法」・「音読」「英文解釈」そこに「シャドーイング」等を加えてもいい)は、改めて検討してみるに、どれも所詮は「具体的な勉強法」に過ぎず、そもそもこれらに対して「時間」と「お金」を割かなければ、上達するはずがないのだ。そして逆に、誰しも費用と手間暇を充分にかけ学習すれば、否が応でもその語学力は磨かれる。至って簡単な話だが、極めて大事な指摘である。 そして個人的な見解だが、語学の勉強において最も「時間」と「お金」が必要とされる学習法――本書の論旨に従えば、最も学習効果が高いもの――とは、とどのつまり「留学」に他ならない。外国語に最も長い時間触れることができ、さらに費用も高くつく。皮肉に聞こえるが、これが現実だし、言語習得に関しては、これが一番の近道であることは否定し得ないだろう。本書を読んで、作者の主張・意図(「まずは、語彙と文法をしっかり勉強しよう!」)とは別に、以上のような事をふと考えてしまった。さように、語学の勉強とはシンプルに見えるも、非常に奥が深いものなのだ。
1投稿日: 2025.05.14 powered by ブクログ
powered by ブクログSNSで紹介されているのを見て、興味があったので読んでみた。 切れ味のある皮肉(であり事実)を交えながら進んでいく話がとても面白く、一気に読めた。 こうしたほうがいいんだろうなぁ……とぼんやり考えていたことが、確信に変わったような感じがする。 ■実行に移したいこと ・少しずつでも毎日定期的に繰り返す。 (1日に6時間ずつ4日やるより、2時間ずつ12日したほうがいい) ・この外国語で単語を何語覚えるのかを定める。 単語の習得にいくつかの関門を設け、それをゴールと見立て、突破したときに盛大にお祝いをする。 ・外国語の理解をよりよくするために、その外国語を支えている文化、歴史、社会など様々な分野の知識・情報を得る。 ■心に残った言葉 ・語彙の習得はどの言語でも同じだけ時間がかかり、日本であろうと留学先の外国であろうと、意識して覚えない限りどうにもならない。「外国語は好きなんだけど、単語が覚えられなくてね」という人は、自分が勤勉でないことを告白しているのである。(P50) ・[会話上達において困難の]第一は、完璧主義者がよく陥る、間違いをしないために黙ってしまうことである。[略]何もしなければ誤りを犯すことはないが、黙っていては会話は上達しない。会話では「あやまりは人の常」の精神が大切なのである。(P168) ・言語はそれだけで単独に使われるのではなく、必ず何かある状況の中で使われる。この状況は、いろいろな情報を言語に与える。従ってこの状況がよく分かっていれば、その言語の理解が容易になる。そして、その言語が伝えている内容が具体的に把握されれば、その言語の理解がより容易になることは自明のことである。ここに、レアリアが大切な理由がある。(P184,185)
1投稿日: 2024.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ858 千野栄一 1932年東京に生まれる。東京外国語大学ロシア語科、東京大学言語学科を卒業。1957年から9年間プラハに在住。カレル大学スラブ学科を卒業する。東京外国語大学名誉教授・和光大学教授。訳書は「しりたがりやのこいぬ」シリーズ、『ロボット』など多数。2002年、没。 神様が公平だと思うもう一つのことは、短期間に急激に習得した語学は短期間に急激に忘れるが、長い時間をかけて習得した語学は忘れるのに長い時間がかかるという事実である。 「覚えなければいけないのは、たったの二つ。語彙と文法」 これまた実に明快な答であった。なんだと思われる人もいるかも知れないが、すべての外国語の学習に際して絶対に必要なのは、この二つである。単語(言語学では、単に「語」という)とは何かを厳密に定義するのは非常に困難であるが、それはまあここではそれ以上追求しないとして、単語のない言語はないし、その単語を組み合せて文を作る規則を持たない言語はない。すなわち、何語を学ぶにしても、この二つを避けて通るわけにはいかない。 絶えず辞書を引かなければならない外国語学習がいかに悲惨なものであるかは、多くの人が痛いほど経験しているところである。それだから、単語を覚えるという努力を着実に続けられる人は、ひとたびこの困難を乗り越えたときの楽しみを知っているか、それを想像できる人である。一つの外国語をモノにした人は次の外国語の習得でも成功率が高いことが、その一証拠といえよう。 語彙の習得が文法の習得と違う大きな特徴は、言語による難易がないことである。語彙の習得はどの言語でも同じだけ時間がかかり、日本であろうと留学先の外国であろうと、意識して覚えない限りどうにもならない。「外国語は好きなんだけど、単語が覚えられなくてね」という人は、自分が勤勉でないことを告白しているのである。そして、この自称〝記憶力の悪い〟人がひとたび天皇賞となると、舌をかみそうな馬の名前だけでなく、馬の血統、経歴、所属 厩舎 名から、 重馬場 での対応能力、さらに騎手の性質までそらんじているのだから、記憶力が悪いということに同意するわけにはいかない。必要なのは超満員の電車の中でも○や△や◎の記号の意味するところを必死で学習するその熱意で、単語の習得にはそれがないことが問題なのである。そして、あんな込んだ電車の中ででも赤鉛筆を使って大事なポイントを区別するという効果的学習を、単語の習得に際しては使わないということである。 この千語を覚えるのに、辞書を引いて覚えるのはむだである。辞書を使うのはもっと後のことで、この段階ではすでに訳のついている単語を覚えればいい。この千語は、どれでもいいという訳ではない。この単語の選び方についてはすこし先で述べるが、もしよい教科書なり自習書なら、そこにこの千語が含まれていなければならない。必要なことは単語を覚えることで、辞書を引くことではない。そして、その単語の記憶を確実にするのには、それを書くことをおすすめする。この段階では、理屈なしに覚えるだけである。そのエネルギーとしては、どうしてもその言語をモノにしたいという衝動力を使い、そのエネルギーの燃えつきる前に千語を突破することである。従って、この千語習得の時間は短くなければならず、そこで十分に時間のとれるときに新しい言語を学び始めるよう計画をセットする必要がある。 もし千語をモノにできれば、その言語の単語の構成がなんとなく分かるようになり、千五百にするには最初の千語の半分よりはるかに少ないエネルギーで足りるようになる。そして千五百語覚えさえすれば、もう失速することはない。ただし、この千語なり千五百語を覚えるというのは確実に覚えることで、なんとなく霧の中にあるような覚え方は意味がない。確実な五百語は不確実な二千語より、その言語を習得するのに有効である。 小説や詩を楽しみ、会話もでき、その言語で手紙も論文も書けるというようになるには最低四〜五千の語が必要になり、その学習には三〜四年は必要である。この五千語をさらに六千語、七千語、八千語……にすることは、その道のプロ以外必要ではない。いくら覚えてもきりがない単語の学習には、目安が必要である。使いもしない語を無理して覚えるのは、ナンセンスとしかいいようがない。もし、辞書を引き引きその言語で書かれたテキストを読みたいというのであれば、二〜三千語で足りる。ここまで覚えれば、その言語に関しては一応の〝上がり〟である。 単語習得の第二のポイントは、その言語をどれだけできるようにするかによって習得する単語の数を定め、それを突破したらお祝いすることで、一つ一つの目的の達成に喜びを味わい、その実感を次のエネルギーに転じていくことである。 言語学の知識が教えるところでは、言語により差があるとはいえ、大体どの言語のテキスト(書かれた資料)でも、テキストの九〇パーセントは三千の語を使用することでできている。すなわち、三千語覚えれば、テキストの九〇パーセントは理解できることになる。そして、残りの一〇パーセントの語は辞書で引けばいい。これならもう絶望的ではない。頻度数の順で五千番から六千番までの千語を覚えても、全体の理解範囲はほんの数パーセント上がるだけであるが、頻度数の高い単語を千覚えることは、理解できる範囲をぐっと拡げることになる。そのもっとも重要なのが、最初の千語なのである。 「コナン・ドイルの『まだらの紐』を読むといいよ、面白いのでつい英文でも読んでしまうから」という外国語習得のヒントは、テキストが面白いことは大事だという点では評価するが、一生に二度と出会わないインドの蛇の名前のたぐいが多くでてくるという点ではよくない。何年に一度しかお目にかからない語を外国語で覚えるなんていうことは、記憶の負担になっても、得るところはほとんどない。 読者の方々はあまり意識していないであろうが、日本語を読んでいるときでも、分からない単語はいつも出て来ている。しかし、必要がないときは飛ばして読んでいるのである。新聞のスミからスミまで読んで、その中に分からない単語が一〇以下の人なんて、永年新聞の編集にたずさわっているベテラン記者か、新聞社を受験しようとしている大学生ぐらいである。 チェコ語にはそれを表わすうまい表現がある。Čím více kdo zná jazyků, tím vícekrát je člověkem.──いくつもの言語を知れば知るだけ、その分だけ人間は大きくなる。
0投稿日: 2024.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ古い本なので辞書についてなど、内容が古い箇所もあるが、語学学習についての本なので現在でも問題なく通用する内容だった。 特に最後の「レアリア」については大いに納得した。 レアリアというのは、「現実的な知識や情報」のことである。それらを知らなければ、いくら語学が出来ても誤訳をしたり誤解をしたりし兼ねない。 また、様々な知識(レアリア)の獲得が語学習得に有利だというのは、学生時代よりも記憶力は悪くなったけれど、レアリアが増えたおかげかある面では昔よりすんなりと英語を理解できるという実感を持っているので、目から鱗とともに大いに納得した。
2投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学者でチェコ語の専門家でもある著者による外国語学習法の指南書。 86年発行のもはや古典と呼べる一冊で、内容も確かに外国語学習の真髄が書かれているのだろうと思う。 しかし王道ゆえに内容に意外性はなく、本書に手を伸ばす程度には外国語、ひいては勉強と曲がりなりにも向き合ってきた人間ならば、この本の内容はどれも、キチンと意識できているかは別として「こうするのが正しいんだろうな」と漠然と思ってはいたことに尽きる。 近ごろのハウツー本のように「今までの英語学習が180°変わる!」などと安易に謳わずに本質だけを控えめに述べているのはいいが、ネットなどで語学のコツが溢れる現在あえてこの本を読む理由があったかは疑問。 ただ私のような読者を想定してか、巻末に「本書を通して外国語学習法の知識をつけるのではなく、外国語を身につけてくれ」というようなことが書かれていた。図星。 ともあれ非常に読みやすいし、著者自身や友人の体験談を交えた語り口は面白いので、語学のモチベーションを上げるにはまあちょうどいいかも。
0投稿日: 2022.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ語学を覚える時に大切なことは、語彙と文法。これが基本中の基本。語彙は、まず1000語を目指してやるべき。
0投稿日: 2022.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生や高校生に読んでもらいたい本。 三単現のsより、なぜ語学を学んでいるか考えることが重要。その通りですよね。
1投稿日: 2022.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログスラヴ語学で有名な千野栄一さんがずいぶん前に書き下ろした、外国語学習のためのコツや方法論などを惜しみなく(むしろ赤裸々に?)新書です。千野さん自身も様々な外国語学習をするにあたりたいへん苦労し、また、いわゆる「天才」と呼べるような大学者たちから教えを受けており、書いてある外国語学習法は非常に説得力があるものになっています。 本書の構成は一見学問としての体系とは異なる雰囲気がありますが、一学習者としてはわかりやすい順序になっています。すなわち、最初になぜ外国語を学ぶのかという目的をもとに目標を決定し、必要なものを用意し、それをもとに学習を進めるためのある程度具体的な方法を提示し、最後にアドバンストなことが書いてあります。2021年の感覚からすると「もっと今では便利な教材が普通にあるのにな」と感じる部分もありますが、本書の出版年を意識しながら読めば十分脳内修正しながら読めるものと思います。 近年急速に発達しているという聞く第二言語習得理論の研究結果を直接的に利用しているわけではないため100%真に受けることはできないのかもしれませんが、少なくともこうした方法で多くの学者・学生たちが外国語を身に着けてきた実績は本物であること疑いありません。本書はそうした学習指南書のうち、長年評価され読み継がれたものの一つとして安心して読むことができる書籍の一つであると感じました。
0投稿日: 2021.10.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ語彙・文法の章は参考になる。後はやや冗長か。 結局はよく使われる部分にフォーカスし、ひたすら繰り返し学習せよという話。使えるレベルで言語習得しようと思うと、そりゃそうだよなーという内容を改めてちゃんと教えてくれる。
0投稿日: 2021.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログラストの1/3がどうしても眠くなってしまって読み進められなかったので諦めました。 最初の方の章では自分の経験や考え方とリンクするところがあって面白かったし、読みやすかったです。 語学の勉強が好きなのですが、その一方で単語の暗記が生まれてこの方ずっと嫌いで、でも先生が作中でおっしゃっているようにそれをやらないことには語学はお話にならないので自分に鞭打ってボキャを増やしたいです。。はぁ。。
2投稿日: 2021.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語上達に必要なモノ 答え:お金と時間 まさに真理。 “外国人に日本語を教え、その代わりに外国語を学ぶというのはよく聞くが、そうやって外国語に上達した人に会ったことがないのは、お金を使ったことがないからであろう” 1985年に書かれてますが、今読んでも充分に学ぶことがあります。巷には色々な外国語学習のメゾットはありますが、これ読めば全て解決するような気がします。 ◯外国語上達のポイント なぜこの外国語を習うのか、という意識が明確であること。 まずは、やみくもに千個単語を覚える。そして、三千語覚えれば、テキストの90パーセントは理解できる。 発音は初めが大事。最初に間違えると矯正がほぼ不可能。発音は個人差が激しい。
0投稿日: 2021.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強ってやみくもにするものではないと思っています。絶対的に覚えなければならないもの。きちんと把握しなければならない規則。そして、思考する。やみくもにならないための指針と基準。それらに則ってできればこんなに楽なことはありません。 この書では、母語ではない言葉、外国語を学ぶときのための指針を提示してくれています。しかも、ご自身の経験と根拠を示しながら。 あ・・・間違ってはいないんだ、と自信につながる一冊でした。
0投稿日: 2020.07.19 powered by ブクログ
powered by ブクログやみくもに語学を勉強せず、目的を持て。 これが本書で最も大事な部分だと個人的には思う。 何のためにその言語を学ぶのか? それが分からず勉強しているのは、弁護士を目指してるのに、保育士の専門学校に進学するみたいな話なわけで。 語学に限らず、何事にも言えること。 収穫としては、「音声学を学び、軽視しがちな語彙を重視し、惹きつけられる先生から学び、金を払え。学びはじめはまず1000語。そして何より継続。」といったところか。 所々時代錯誤を感じる学習法は否めないが、版を重ねているだけある普遍的な内容だったなと思う。
2投稿日: 2020.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログただやみくもに外国語習得を開始するのではなく、戦略を立て、無駄のない努力をしたいところである。本書は、過去の自分の方法ではダメだったのだと気付かせてくれた。早速スマホで単語帳アプリをダウンロードし、1000語の暗記から始めている。また、友人にお金を払い、毎週一回一時間半の授業をしてもらうように依頼した。生涯をかけて、5カ国語を楽しめるようになるのが目標だ。 以下、本書より抜粋。 「言語の習得にぜひ必要なものはお金と時間であり、覚えなければ外国語が習得できない二つの項目は語彙と文法で、習得のための三つの大切な道具はよい教科書と、よい先生と、よい辞書ということになる。」 「もし、辞書を引き引きその言語で書かれたテキストを読みたいというのであれば、二~三千語で足りる。ここまで覚えれば、その言語に関しては一応の”上がり”である。」 「もし、あなたが学習しようとしている言語に語の頻度数を示す資料があったら、それは絶対に見る必要がある。」 「外国語の習得に際して、語彙に関してはこれまであまり無視されていたので、もっと関心を持つ必要があり、語彙の習得にもっと計画的に時間をかけることが絶対に必要である。」 「一冊の学習書の中の変化表を全部切り抜いてビッシリ貼り直すと、大体10頁内外になる。(言語により異なる)もし読者の方がモノにしようと思っている外国語の骨組みが、10頁を完璧にモノにすればできると分かれば、誰にでも勇気がわいてくるに違いない。」 「先生は各人に小さなノートを用意させ、それを単語帳にする。毎時間の最初に、その時間で扱う文法事項の手短な説明があり、ごく少数の語彙が与えられてから授業が始まる。授業の圧倒的大部分の時間は、母語から外国語への翻訳にあてられる。まず語彙を覚えるための易しい短文が繰り返し当てられ、新出の語彙が覚えられたのが確認されると、その日の文法事項がその作文の中に組み込まれてくる。学生が単語でつっかえると、すぐ小さなノートにその単語を書き加えることを要求し、更に、その語が入ったいくつかの分を訳させる。そのノートの単語は学期が深まるについれて一人一人で違ってくるので、やがて学生を当てるとき一人一人からノートを提出させ、それを見ながら作文が要求される。」-ブラジミール・トグネル先生の授業方法 「先生は授業の最初の日に葉書程度の大きさの紙に、氏名・専攻・住所・電話を書いて提出させ、これがその後の授業で重要な役割を果たした。まず出席をとって、欠席の人のカードを抜き、その裏面にその日付をつける。そして残りのカードをよく切り、裏返しにしてから、授業では順に当てていかれた。一巡するとよくカードを切り、学生に自分の順番を予測させないようにし、しかも皆が公平に当たるよう配慮して、質問の難易で学生にひいきのないように、裏にしたカードをめくるまで誰に当たるかわからないようにふせておき、そして質問に答えられない学生がいると、カードにどの変化ができなかったかを記入して、次の週には必ずそれを復習させるのである。」-ヨゼフ・クルツ先生の授業方法 「繰り返しは忘却の特効薬である」
13投稿日: 2020.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習に関して当たり前の事が書かれています。 外国語の学習は、 1 強い意志 2 お金 3時間 が必要だよと。 ただ現代における外国語の学習環境は、 情報革命以後、かなり変わった。 一言で言えば、キャリアにおける外国語学習は、 終了したと思う。その代わり、より趣味的な要素が強くなるだろうと思う。 AI技術の応用で自動翻訳が凄まじい勢いで、 発達しているが、それと外国語学習の有無は、 同列的に考えてはいけない。 あくまで、外国語学習は、外国語を通じて、 異文化に触れ、異文化を背景に持つ人たちと触れ、 考え方の幅が広がり、そして自分をより深く知ることにほかならない訳だからだ。
1投稿日: 2019.12.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ数えてみると購入してから今までに6回も読んでいるが、語学に関するエッセイでは最高の本。何度読み返しても新鮮でおもしろい。
4投稿日: 2019.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ポリグロットである著者の作品。言語学習の才能はないがここまでできるようになったという著者の背景を振り返ることで、言語学習の門は誰にでも開かれているということを教えてくれています。 他の言語学習の本にも書かれていますが、やはり繰り返すことが一番重要なのだと再認識させてくれます。さらに、お金と時間を惜しまないことも重要だと書かれています。最近では無料で勉強できるアプリなどいろいろな教材が溢れていますが、やはりきちんとした教材でないとデタラメなことを書かれているなと感じることはあります。出版されている教材でも怪しいのはありますが。。。 英語に限らずですが、他の言語を学習していると、日本語の発音は種類が少なく不利になると感じますが、日本語にしかない発音もあるのは知りませんでした。たしかに言われてみれば、外国語で同じような発音はないなーと新しい発見もありました。 そういえば某番組で、ロシア語は格変化が多少違っても通じるよ、といったことを聞いたことがありますが、ここに書かれていることとは真反対でしたね。
0投稿日: 2019.07.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ"外国語を身につけるための心構えと、学習の際に気にかけるべきことが端的にまとめられた良書。 なぜ、その言語を学ぶのか目的と目標を明確にしなさい。 そして、何より必要なものは、お金と時間。その言語の語彙と文法を学ぶこと。 最低3年から4年、語彙数は4000語~5000語覚える必要がある。 語彙を覚えるのも戦略的に、使用頻度が高いものから目的に応じて範囲を広げていく。 学習書は薄く、頻度の高い優しい語彙から練習を繰り返すようなものが理想。 やっぱり、英語から・・・時間管理といかに習慣にするかがカギ。"
0投稿日: 2018.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ【感想】 別の本で佐藤優が称賛していたので購入。 30年以上前に出版されたにも関わらず、非常に読みやすい本でした。 まぁ30年も経って学習ツールは大きく変わったが、本質は今も昔も変わらないだろう。 外国語の習得に必要なものは「目的と目標」「語彙」「文法」「学習書」「教師」「辞書」「発音」「会話」「文化や歴史」。 とりわけ重要なのは「目的」で、次いで「語彙」と「発音」なのだろうと読んでいて思った。 やっぱり、明確な必要性がないと切羽詰まって勉強しないから、なかなか習得できないでしょうねー。 個人的に英語が必要不可欠な環境ではないし。今後そうなるかも明確ではない。 習得するに越した事はないにしても、実践する場がなかったら時間と費用の無駄になりかねない。 そもそも、こういった本を読んでいるだけでは画餅で終わるどころか、習得に大してそもそも高いハードルを感じてしまう・・・ 趣味程度で取り掛かるのは考えが甘すぎるのか? まぁ、そのあたりの費用対効果を考えた上で取り組もう。 TOEIC高得点GETという目標を元に頑張ってみるか。 【内容まとめ】 1.「何故この外国語を習うのか」という意識が明白である事が絶対に必要である。 外国語がモノにならない人は、目的意識の不足がその原因である。 2.数多く外国語ができる人がいても、その中で読み書き話せると三拍子揃ってできる言語は1つか2つで、3つという人は少ない。 3.覚えなければいけないのは、語彙と文法 文法は骨と神経、語彙(単語)は血肉。 血や肉がなければ、人間ではなく骸骨にすぎない。 4.まず、よく使う千の単語を覚える。 千の単語を覚えるのは、その言語を学ぶための入門許可証こようなものであり、これを手にしてようやく助走成功するようなものである。 5.「発音」は、外国語を学ぶための重要な前提。 外国人は文法上のミスのある文の方が、ひどい発音で話された文よりもむしろ理解ができる。 【引用】 外国語コンプレックスに悩む一学生は、どこようにして英・独・仏・チェコ語をはじめとする数々のことばをモノにしていったか。 辞書・学習書の選び方、発音・語彙・会話の身につけ方、文法の面白さなど、習得のためのコツを著者の体験と達人達の知恵をちりばめて語る。 ・目的と目標 ・語彙 ・文法 ・学習書 ・教師 ・辞書 ・発音 ・会話 ・文化や歴史 p6 才能の差は確かにある。 しかし、ある言語を習得できるかどうかは、その習得の方法により多くの事が依存している。 p20 外国語を習うとき、なんでこの外国語を習うのかという意識が明白である事が絶対に必要である。 外国語がモノにならない人は、目的意識の不足がその原因である。 p26 ごく稀にしか起こらないハイジャックのインタビューのために全スチュワーデスにその分野の応答ができるように英語教育するというのは全くと言っていいほど無駄である。 人間の能力には限界があって、寿命も限られているのであるから、必要なだけの英語が出来ればよく、それで十分なのである。 p29 色々と数多く外国語ができる人がいても、その中で読み書き話せると三拍子揃ってできる言語は1つか2つで、3つという人は少ない。 p38 ・上達に必要なのは、お金と時間 人間はそもそもケチなので、お金を払うとそれを無駄にすまいという気が起こり、その時間が無駄にならないようにと予習・復習をするものである。 また、習得には繰り返しが必要なため、どうしても時間が必要になってくる。 p41 ・覚えなければいけないのは、語彙と文法 まずは単語を覚えなければいけない。 いい教科書、いい教師、いい辞書。 文法は骨と神経、語彙(単語)は血肉。 血や肉がなければ、人間ではなく骸骨にすぎない。 単語を覚えるおいう作業は単純であり、ゴールがなく、面白くない。 それにも関わらず、単語を覚えなくては習得に支障をきたす。 この矛盾を解決しなければならないのが外国語の学習である。 p51 ・まず千の単語を覚える。 千の単語を覚えるのは、その言語を学ぶための入門許可証こようなものであり、これを手にしてようやく助走成功するようなものである。 この段階では、理屈なしにただ覚えるだけである。 →まずは頻度の高い単語から。 何年に一度しかお目にかからない語を覚えるなんて、記憶の負担になっても、得るところはほとんのない。 p95 ・語学書は薄くなければいけない。 1冊読み終えればその言語が完璧に習得されるなんて本はない。 また、ありあまる時間をすべて外国語習得にのみ捧げるというのも現実的ではない。 従って、大きな本は駄目なのである。 語学書は薄くなければならない。とりわけ、初歩の学習書はそうでなければならない。 p108 まず第一に、語学教師はその語学がよくできていなければならない。 →語彙、文法、発音。知らない事ははっきりと「知らない」と明言できる。 第二に、教え方が上手であるということ。 限られた知識であっても、それを整然と教えられる人の方が役に立つ。 第三は、教える事に対する熱意や、先生の個人的な魅力。 この先生についていかないと損をするというような気持ちにさせる全人格。 p144 ・「発音」は、外国語を学ぶための重要な前提。 外国人は文法上のミスのある文の方が、ひどい発音で話された文よりもむしろ理解ができる。 p199 ・繰り返しは忘却の特効薬 外国語の習得は始めたら規則正しく、たとえ短い時間でも毎日することが大切。
11投稿日: 2018.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を学ぶ方法に関するエッセイといったところ。「外国語」なので、英語に限っておらず、むしろそれ以外の言語についても語られていて、面白い。 イメージ的に大昔の本かと思ったら、1986年ということで、意外と最近だと思ったのは、そういう年齢だからか。 何よりも単語、まずは単語。その上で文法かな。 (108)
0投稿日: 2018.10.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ語学が苦手と称する著者が外国語を習得する方法を解説したもの。 ・何の目的で学ぶのかを決めること。(全て完璧になる必要はない。) ・上達に必要なのは時間と金。 ・少しでも繰り返す。 ・発音は音声学の知識が役立つ。 今更だが、役立つアドバイスだと思った。
0投稿日: 2018.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学者である著者が、みずからの体験を紹介しつつ、外国語学習の要諦について語った本です。 古い本ですが、本書で紹介されている外国語学習のコツは、こんにちでも参考になるところは少なくないと思います。また、著者自身の体験だけでなく、語学の達人とされる人びとの驚異的なエピソードなども紹介されており、上品なユーモアがあっておもしろく読めました。
0投稿日: 2018.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ語学を学ぶのにどこまで自分に必要なのかを見極める事が 大事と言うのには納得。 (例えばウェイターは注文の取り方や接客に必要なフレーズに特化すれば容易に多言語をマスターできる。) 勉強は目的意識と計画が大事!
0投稿日: 2018.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1986とは思えないくらい古風な文体。 外国語上達には、お金と時間が必要、語彙と文法を覚える。よい教科書と良い教師と良い辞書が必要。 外国語学習はスタートダッシュ。欲望から衝動まで待つ。まず1000語確実に覚える。4-5000語が当面目標。辞書引き引きでよいなら2-3000語。>今学期終わったら1000語単語帳片づける。来季始まるまでに。 文法を10P分にまとめる。それを暗記する。 p115各課の単語20と簡単な文法事項。それを使った作文。できなかったところ記録。反復練習。 よい辞書。探している語が出ている。その語に自分の読んでいるテキストに合う訳が出てkる。訳のほかにも必要とする文法事項が手出来る。熟語が出ている。よい用例が上がっている。読みやすい。引きやすい。持ち運び便利。安い。前書きを読んで選ぶ。頻度数への配慮、当該語を母語とする人のチェック、読みやすく使いやすく、訳語の日本語がこなれている。辞書は多いほど良い。 発音。最初が肝心。だいたいキモがある。それを区別するには。>うーん。できないとこやるしかないんだけれド。 会話。些かの軽薄さと内容。レアリア。現実的な知識と情報。 外国語学習は短時間でも毎日。
0投稿日: 2018.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者自身の体験談以上に、かつて接した語学教育者や学習者の武勇伝が載っていて、なかなかインパクトがあった。学ぶ事について纏めると、初めは日本語で書かれた簡単な本を使い、必須単語を徹底して覚え、あとは必要に応じて辞書を引きながらやっていく、ということで、それだけみれば通り一遍の語学書と同じなのだが、出てくる人たちが篦棒な猛者ばかりで、道無き道を進み切り開いた人達の情熱に驚いた。
0投稿日: 2018.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
千野栄一『外国語上達法』1986 明解でいい本だなと思う。「第二言語習得論」といわれる科学的アプローチが流行(?)のようだが、この本とあわせれば、いろいろと得るところがあると思う。著者はスラブ語の専門家でロシア語史をやっているうちに、チェコ語とかクロアチア語などをマスターした人で、チェコ語の話がよくでてくる。今のような便利なもんがなく、日本語の辞書もない時代に、難しい言葉をマスターした人々のことがいっぱいでてきて、とにかく示唆に富んでいて面白かった。 ・語彙(最初の1000語はガリガリやる。論文が書けるようになるには4000〜5000語が必要で3〜4年はかかる。とにかく単語集をみているだけでドイツ語を習得したチェコ人がおったらしい) ・文法 チェコの英語学者マテジウス(失明してベッドの上で業績をのこした人らしい)の理論が面白かった。言語は基本、既知から未知を示すもんである。英語では受身と不定冠詞が未知を扱うらしい。不定冠詞というと、なんかボンヤリしているとしか思わなかったが、不定だからこそ未知の新しい情報だということ。 例) I am a student. わたし[目の前にいる既知の者]→〔まだ知らないだろうけど〕学生なのよ。 ・教師の項目には、①教える言語ができること、②教え方がうまいこと、③人格的な魅力があることというのが「いい教師」の条件だそうだが、熱意があればカバーもできるといっている。 クロアチア語やロシア語の教授方法が面白かった。毎回とにかく20語くらいで文法項目をマスターする。学生にノートを作らせ、できないところを書かせ、教師がノートをあつめて、できないところをくり返し何度もあてる。少ない項目を確実にできるようにしていくというもの。「オーダーメイド授業」とか「学習者中心アプローチ」とかいうけど、1960年代にもすぐれた教師はやっていたんだなと思う。 ・レアリア 現代では「現物教材」と訳されて、レストランのメニューなどを指すが、本来はギリシア・ラテンなどの古典を読むのに必要な知識のこと。これを読んで、「漢文にもこれあるわ」と思った。たとえば、「鼎」(かなえ)が三本足の器であることを知らないと、「鼎立」とか「鼎談」とかが分からないというようなこと。レアリアを英語に訳すと、thought and lifeというらしい。 このほかにも、辞書や学習書、発音や会話などについても書いてあります。
0投稿日: 2017.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書によれば、外国語の学び方は、語彙と文法を重視する、である。3000語、覚えればよいのである。 そして、語学が目的になってしまっている人は、手段で語学を学ぶ人より挫折しやすい、ということである。
0投稿日: 2017.11.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版が86年で、16年時点で47刷に達していことからも、良書と期待して手に取った。 1語でも語彙を増やすに時間をつかうべきかと思った。が、それでもなお読みたかったし、200ページに収まってる内容は、移動時間を殺すのに都合が良かった。 読み終えて思うのは、非母語を難なく扱えるようになった人は、賢く謙虚で、でも自信のある人だなと。しかし問題はぼくの中国語である。良い自習書もあり、先生もおり、なんなら中国語がつかえる国にすんでいるのに、この体たらく。 この本に照らし合わせると、発音無視しすぎ・覚えるべき基本語彙がみえてない・ゴール設定できてない。ってことに、耳が痛すぎる。
0投稿日: 2017.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典的名著。 個人的なことだが、自分も第二外国語を学習中である。 本書にあった「語彙と文法」は、まさに実感。 とにかく、刺激と再認識させられる知見が多い。 名著。
0投稿日: 2017.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
外国語を習得しようとする場合、何語を何の目的で学ぶかをはっきり決めてかからないといけない、というのが第一の主張である。日本ではまず最初、英語がその候補に選ばれるわけだが、この場合でも英語の自分に持つ意味をよく考えなくてはならない。 次に、習得したいと思う外国語が決まったら、その外国語をどの程度習得するつもりかの見通しをつけなくてはならない。読み書き話すという三つができるようになるには、言語の難易の差によって3年から5年が必要になってくる。(p.31) 最近ソビエトで出たロシア語の初歩の本を見ていたときのことである。「これは魚ですか、鳥ですか」という疑問文があり、一瞬「ロシア人よお前もか」と思った。ところがその横に挿絵がついていて、展覧会で一枚の絵の前に立った見物人が抽象画をさしながら画家に聞いている場面が描かれていたので、思わず笑わされてしまったし、「……ですか、それとも……ですか」という構文を一緒に覚えさせられてしまった。(p.102) 会話というものは自分が相手の人に伝えたいことを伝え、相手の人が伝えたいと思っていることを聞くことであって、自分がたまたまその外国で知っている句を使ってみることではない。ここに、会話集や会話学校のもたらす危険がある。(p.172) そもそも言語というものは、それ自身が目的ではなく、伝達を始めとする幾つかの機能を果たすために存在している。すなわち言語は「自目的」的ではなく、「他目的」的なものである。そして、言語はそれだけで単独に使われるのではなく、必ず何かある状況の中で使われる。この状況は、いろいろな情報を言語に与える。従ってこの状況がよく分かっていれば、その言語の理解が容易になる。そして、その言語が伝えている内容が具体的に把握されれば、その言語の理解がより容易になることは自明のことである。ここに、レアリアが大切な理由がある。(pp.184-185) シェークスピアについての評論を読む場合、シェークスピアを読んだことがあるかないかはその理解に大きな差が出てこないわけにはいかないし、機械を扱ったことのない人が機械のことを聞いても読んでも分からないところのあるのはそのためである。自分の知らない内容について聞いたり読んだりしたとき、その理解が大変であることは母語でも同じだとはいえ、それが外国語ともなれば余計に困難の度が加わることとなる。(p.192)
0投稿日: 2017.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語上達のtips(コツ)が分かる。 外国語学習の導入にもモチベーションアップにも最適。 出版年は古いが、内容は色褪せない。
0投稿日: 2016.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ身も蓋もないことも多々書いてあるけど、外国語に限らず勉強の基本みたいなことも学べる、かな。高校1年生のときに初めて読んだんだけど、今でも折に触れて手に取っちゃうな。
0投稿日: 2016.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ1年前からドイツ語を勉強しているが、まったく身についているという自覚がなく、いまだに簡単な文しか話せない。 この本では、外国語をマスターするには時間がかかるとは書かれているが、効果的に勉強する方法はあると書かれており、それを実践すればもう少し上達するだろうと思わされる。 後書きには本書に何度も登場する、イジー・トマン博士のことばが述べられており、(この本を読んだ時間を無駄にしないために)「今日のうちに、ここに述べられたことの一つでも応用する気になってください」というもの。千野先生が教えてくれた方法を今日から実践したいと思う。まずは単語を真剣に覚えよう。
0投稿日: 2016.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログさきに種田先生の本読んじゃったから少し、見劣りしたかな、、、、 たぶん相性の問題なのかなと思うのだけど、あんまりこれを読んで、語学学習が面白いだろうとは思えなかった。 でも、レアリアの項とか、1項ずつまとめを書いてくれたとことか、会話の項はとてもよかった! 発音の項は耳が痛かった
0投稿日: 2016.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ千野 栄一(ちの えいいち、1932年2月7日 - 2002年3月19日)は、日本の言語学者。東京外国語大学名誉教授、和光大学学長。言語学、およびチェコ語を中心としたスラブ語学が専門。 (ウィキペディアより引用。2016/2/8) 言語学者が著した語学勉強法を紹介する一冊。 語学を勉強したことがある者なら一度は言われたことがあるであろう事柄が、章立てて構成されている。 語学の基本として語彙と文法を押さえること、毎日こつこつと続けることが、語学修得への一番の近道である。 本書の肝は以上であるが、どのような単語から覚えるべきか、文法を押さえることがなぜ重要なのか、また他に重要な要素があるのか気になる方はぜひ本書を手に取って頂きたい。 書いてあることを実践する覚悟があるならば、読んだ時間は決して無駄にならないはずだ。
0投稿日: 2016.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ`` 「外国語は好きなんだけど、単語が覚えられなくてね」という人は、自分が勤勉でないことを告白しているのである。 `` という部分にうっときました。語彙は大事。
0投稿日: 2015.12.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ「英語」ではなく、あくまで「外国語」の上達法について、簡潔にして正鵠を射た記述がなされています。 「レアリア」等の他にはない画期的な視点で書かれた章もありますし、内容もさほど多すぎないので、サクッと読むことのできるおすすめの本です。
0投稿日: 2015.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
佐藤優さんが知性とは何かで紹介していたので読みました。 外国語学習において語彙と文法、そして継続的な学習が大切だと書いてあり、改めて英語学習の必要性を感じました。 外国語上達法 千野栄一 1:はじめに 「語学の取得というのは、まるで水をしゃくっているのようなものです。絶えずしゃくってないと、水がなくなって胃s舞います。水がどんどんもれるからといって、しゃくうのをやめるとザルははぜてしまう」 忘れることを恐れるな。 2:目的と目標 必要とするだけの量だけ学習する 何語を何の目的で学ぶのかはっきりさせる。 3:必要なもの 外国語上達に必要なもの お金と時間 外国語の習得には、記憶が重要な役割を演じており、記憶には繰り返しが大切でそのためには時間が必要である。ある外国語を習得しようと決心し、具体的な目標に向かってスタートした時は半年はがむしゃらに頑張る。 短期間で急激に習得したものは、短期間に急激に忘れるが、長期間で覚えたものは忘れるのにも時間がかかる。 覚えるのは語彙と文法 4:語彙 言語を人間に例えれば骨や神経は文法であり、語彙は血であり、肉である。骨や神経がだめんら、その人間はうまく動かないが、血やにくがなければ人間ではなく残骸にすぎない。 繰り返しが学習の母 5:文法 文法は補助手段であってそれ自体が学習の目的となってはいけない。 6:学習書 初歩の語学の自習書なり、教科書は薄くなければならない。語学の習得のためにはこれだけ、澄んだ。ここまでわかった。一つの山を越えたということを絶えず確認して、次のエネルギーを呼び覚ますことが必要である。 やみくもに語彙を覚える時期では教科書に載っている単語の訳を覚えることに徹する。 7:教師 8:辞書 9:発音 10:会話 人は努力する限り過つものである。 ファウスト ゲーテ 会話というものは自分が相手の人に伝えたいことを伝え、相手の人が伝えたいと思っていることを聞くことであって、自分がたまたまその外国語で知っている句を使ってみることではない。 会話をすることによって知識や考えを深めるために話をするのであって日本語の会話と大差ないのである。 11:レアリア 外国語を学ぶということは外国の文化を学ぶということ 言語が周囲の状況から切り離されておらず、その状況の与えるいろいろのあ情報とともに使用される限り、それらの周囲の状況が与える譲歩を間違いなくキャッチすることはその言語を理解する上で大切である。 外国語の背景を知ること。 12:まとめ 学習法で大切なのはお金をかけること。定期的に繰り返すこと。 繰り返しは忘却の特効薬である。 「馬を水辺に連れて行くのはやさしいが、水を飲ませることは難しい」
0投稿日: 2015.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログレアリアというキーワードがあることを知った。英文の内容を理解するときに、関連知識があるとわかりやすいと感じていたが、レアリアとはその関連知識の一般的な呼び方である。レアリアのことを書いてある章には、いくつかのおもしろい例が載っていた。外国語で書かれた文章の舞台である国々での当たり前のこと(これもレアリア)についての知識がないと、誤訳をしたり、翻訳に大変苦労をしたりするということであった。
0投稿日: 2015.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習の指南書。語学習得は繰り返し継続することが大切と説かれている。文法の必要性、参考書・辞書・教師の選び方は学習に役に立つ。ユニークなのは発音のために音声学を学ぶ方法だ。そこまでやるのかと驚いたが、正しい発音を手にいれるためには必要な回り道かもしれない。
0投稿日: 2015.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ内容としては、正直平凡であったかな。 私は今現在スペイン語を学んでいて、卒業論文の材料と語学を伸ばすための手がかりとして手に取った。もう少し早い時期に読んでいればもっと役に立ったと思う。これから新しい言語(英語以外)を学ぶ人にとってはとてもいい本である。 p,51ラテン語の格言より Repetuìtiō est māter studiōrum. (繰り返しは学習の母である)
0投稿日: 2014.04.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言語学(特にマイナー言語)が専門の方なら ご存知の千野氏の著書。 英語ペラペーラな先輩から 進められて、拝読。 話せない私には、 わかってるから、 言わないで!といった 感じでした。 レビューは気が向いたら。
0投稿日: 2014.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習の古典名著を今更ながら読みました。 内容は完結で非常に読みやすく、巷に溢れる英語学習本に書いてあることは全て網羅されていると言っても過言ではないと思います。
0投稿日: 2014.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
20年近く昔に書かれた本なので、今とはずいぶん状況が違うが参考になる。 初学者の時から立派な辞書は要らない。語彙は大切。独習書は語彙がしっかりしてるのがいい。 学びたい外国語をどこまでマスターするかを決める。 今はCD付の独習書があるしインターネットで動画は見られるので昔の情報も手段もなかった時代の人たちは凄い。けど昔の人のほうが楽しそうなのはなんでなんだろう。
0投稿日: 2013.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ斎藤兆史『英語達人列伝』は 達人の伝記のコンピレーションといったところでしたが、 本書は「達人」による一般人のための勉強法となっています。 さまざまな勉強法について、種々のエピソードを織り交ぜて紹介しています。 見た目は岩波新書(黄)と堅そうな印象を与える本書ですが、 なかみは初学者向きの内容となっています。 目的意識、そして語彙と文法が大切というのは、 本書を読み返すたびに改めて思うことです。 自分の語学力の伸びに合わせて、 気分転換がてら何度も読み返してはいかがでしょうか。
0投稿日: 2013.10.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてある内容は、一般的なことだけれども、そこに出てくる登場人物がとても面白いと思う。 エッセイのような感じで、読みやすい。昔の本だけれど、今の学習にも繋がるような内容もあって、参考になる。
0投稿日: 2013.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初の2章が最も印象的だった。目的意識がなによりも重要というのがよくわかった。 “必要でない言語を単に教養のためとかいって三つも四つもやることは、人生での大きなむだ以外の何物でもない。”
0投稿日: 2013.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ書いてあることは奇をてらうものでもなんでもなく,語をしっかりと覚えておくことに始まる非常にオーソドックスで真面目なことです。でも,その背後にwill powerと目的の明確化がないと,ただただ時間を食うだけです。 ***** 外国語を習うとき,なんでこの外国語を習うのか,という意識が明白であることが絶対に必要である。この反対の例が“教養のための外国語”とやらで,こんな気持でフランス語やドイツ語を学ばれては,フランス語やドイツ語が迷惑である。フカフカしたじゅうたんの上で,数々の教育機器に恵まれ,ネイティブ・スピーカーのいい先生のいるカルチャー・センターで,よい教科書と,よい辞書があってもうまくこれらの外国語がものにならない人は,目的意識の不足がその原因である。(p.20) 大学生というのは,本来時間はあるがお金のない人たちであり,社会人というのは,いささかお金があるが時間のない人たちである。このことからも明白であるように,資本主義というのは時間をお金にかえる制度なのである。(p.39) 語彙の習得が分布の習得と違う大きな特徴は,言語による難易がないことである。語彙の習得はどの言語でも同じだけ時間がかかり,日本であろうと留学先の外国であろうと,意識して覚えない限りどうにもならない。「外国語は好きなんだけど,単語が覚えられなくてね」という人は,自分が勤勉でないことを告白しているのである。そして,この自称“記憶力の悪い”人がひとたび天皇賞となると,舌をかみそうな馬の名前だけでなく,馬の血統,経歴,所属厩舎名から,重馬場での対応能力,さらに騎手の性質までそらんじているのだから,記憶録が悪いということに同意するわけにはいかない。必要なのは超満員の電車の中でも〇や△や◎の記号の意味するところを必死で学習するその熱意で,単語の習得にはそれがないことが問題なのである。そして,あんな込んだ電車の中ででも赤鉛筆を使って大事なポイントを区別するという効果的学習を,単語の習得に際しては使わないということである。(pp.50-51) ある外国語を習得したいという欲望が生まれてきたとき,まずその欲望がどうしてもそうしたいという衝動に変わるまで待つのが第一の作戦である。そして,その衝動により,まず何はともあれ,やみくもに千の単語を覚えることが必要である。この千語はその言語を学ぶための入門許可証のようなものであり,これを手にすれば助走成功で,離陸が無事に済んだとみなしていい。もしこの段階で失敗したときは,あきらめた方がいい。翼や車輪が壊れたままで飛び上がろうとするのは,どだい無理というものである。ただ,同じ言語を二度目にもう一度アタックするのは最初のときよりつらいことは,知っておく必要がある。一度始めて中断した場合は,それまでに学んだ知識は二度目のとき役立たないのみか,かえって妨害になる。(p.52) もし千語をモノにできれば,その言語の単語の構成がなんとなく分かるようになり,千五百にするには最初の千語の半分よりはるかに少ないエネルギーで足りるようになる。そして千五百語覚えさえすれば,もう失速することはない。ただし,この千語なり千五百語を覚えるというのは確実に覚えることで,なんとなく霧の中にあるような覚え方は意味がない。確実な五百語は不確実な二千語より,その言語を習得するのに有効である。(p.53)
0投稿日: 2013.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ言語学者である筆者が、外国語上達法について、辞書、学習書の選び方、発音、語彙、会話、文法など、習得のためのコツを披露。。目的と目標をはっきりさせて、情熱を持って学習することが重要。
0投稿日: 2013.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログバスケで怪我したので久々の読書 外国語上達法を読んだ 結局、大切なのは人間性であり、意欲である気がした。 外国語が話せても、話に中身がなければ意味がない。 どんな状況であっても、意欲があれば勉強出来る。 大切なのは学習の目的を明確にすること。 そしてどの程度学習するかの見通しをつけること。 反復練習、忘れることを恐れないこと。 その言語の使われている国の文化や歴史、背景を知ることも大事。 言語学習には想像力も大事であると思う。 ”人間の能力には限界があって寿命も限られているのであるから、必要なだけの語学が出来ればよく、それで十分なのである。 覚えなければいけないのは、語彙と文法 必要なものはお金と時間 よい教科書と、先生と、辞書 単語を覚えるという努力を着実に続けられる人は、ひとたびこの困難を乗り越えたときの楽しみを知っているか、それを想像できる人。 必要な千語をまず覚えること。 変化表を覚えること。 会話を上達させるには「いささかの軽薄さと内容」が必要 外国語を話すには文法的に間違える恐れがあるが、あやまちは人の常という覚悟をもち話すこと。 そして会話の命はその内容。会話によって新しいことをしり、考えさせられ、喜びを得るからこそ話をするのである。 文化、歴史、社会を知ること。 風俗や習慣をよく観察し、興味を持ち、学んでいくこと。 それが外国語の理解を助ける。 あくなき繰り返しをすること。 大切なのは、短時間ものすごく集中することにより、学習を規則的に継続すること。 そして目的をはっきりとさせ、意欲を高めること、その意欲をもって実行すること。 繰り返しは学習の母である。 Repetição é mãe de estudo. 人は間違いを重ねることで学んでいく 外国語を習得することで、その人の視野は複眼的になり、物事の違った面が見えてくる。 そして、ほかの人の持たない情報も得られることになる。 いくつもの言語を知れば知るだけ、その分だけ人間は大きくなる。
0投稿日: 2012.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこの本が出版された頃に一度読んだ。そのときは読んだだけで終わってしまった。だからまだ外国語をモノにしてない。 現在、英語に再チャレンジ中。
0投稿日: 2012.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の千野さんは既にお亡くなりになっていることもあり、少々古い部分はあるものの、ほとんどは2012年現在も通用する。ことあるごとに読み直している本。
0投稿日: 2012.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ英語だけでなく、外国語全般の学習方法のエッセンスがつまった名著。語学に少しでも興味があればぜひ一読して欲しい本。私はこの本を読んで、語学の勉強法に対する認識が大きく変わった。 中身は言われてみれば当然の事ばかり書いてあるが、それが語学上達にとって必要不可欠であり、近道などない事が思い知らされる。地道な努力が一番の上達のコツなのだ。 「自分は語学の才能がない」と評する千野先生だが、自身の苦労なされたエピソードや他に出来る人のお話は、読んでいて引き込まれるものがある。
1投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
言語学においては名の知られている千野栄一先生の著書。世代としては現代より一世代前になるんだろうけど、さすがスラブ語研究についてはひとかどの権威だけあって、ご自身の外国語習得の経験を開陳しつつ、洋書にチェコ語やロシア語など、スラブ諸語の知識を垣間見ることができます。 千野先生はスラブ系の言語が専門ですが、外国語を学ぶにあたって何が大切なのか、どこに気をつければいいのかというところに関しては、何の言語であってもそれほど大きな違いはないんだな、ということが、この本から理解できます。 初刊が1986年ですが、まだ十分に読むに値する助言が多く含まれていると思います。それほどページ数も多くなく、さらっと読めるので、これから先、英語以外に何か一つ言葉を増やしてみようかな、という時には、一つの参考として読むのも好いかと思われます。
0投稿日: 2012.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習のエッセンスが詰まった本。 ちまたにあふれる「聞き流すだけで身に付く」とか、「絶対勉強するな」といったうたい文句がどれだけ薄っぺらいものかがわかる。 これを読んでモチベーションがわかないなら、語学の習得は諦めた方がいい。 ふと巻末を見ると1986年に第1刷、2011年に第41刷とある。25年の時の洗礼を受けてなお、外国語学習者に読まれ続ける名著。
0投稿日: 2012.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
語学における「文法」の大切さと「発音」を間違えると、riceがliceに聞こえてしまい、とんでもない勘違いを引き起こす…とかいう話は面白いです。 他にも興味深いことは書いてありますが、これから外国語をやる人・現在外国語を勉強中の人・そうでない人も一読してみる価値はあると思います。 だいたいの外国語の文法も集約すれば10ページほどに収まるので、10ページを突貫工事でやり通せば、その語学の骨格がつかめる…と聞くとやる気が出てくるのでは?
0投稿日: 2012.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語とはこう勉強すべし!というのが分かりやすく書かれている。 というか、書かれているのは当たり前のことなのだ。 金と時間をかけるべし。 金がかかれば惜しんで勉強する。 時間をかけて反復すべし。 よいテキストとはこんなのである。 よい先生に出会いましょう。 などなど。 でも、これができないからこそ語学は身につかない。 あたりまえだけど、できないこと。 こうして明快に文章化してくれると、なんだかすっきりしていて、やる気がでてくる。 もう少し、頑張ってみようかな、と思わせてくれた1冊。
0投稿日: 2012.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
25年も前の本だとは思えないのですが・・・。「目標を決める」「レタリア」が大切という外国語学習法以外の部分が一番為になりました。著者は外国語の勉強が苦手とする部分が共感でき、とても読みやすかったです。 英語の勉強やる気なかったのに、コレを読むともう少し・・と思ってしまったw 目標については学校の授業ってだけじゃ、そら身につかんわなー。学校で英語教える前に、先生にこれ、読ませてくれ。
0投稿日: 2012.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ語学上達の基本をおさえつつ、意外と盲点となっているところもさりげなく教えてくれる、語学フリーク必読の一冊。 その言語習得の目的をはっきりさせることで到達点が決まり、それにより「語学の無間地獄」に落ちないで済みます。 そして、辞書はそのまえがきと凡例を必ず読まなくては編者が報われないこと、その言語の背景たるレアリアを身につけることでそのことばが立体視できるようになることが述べられています。 このあたりは、私にとっては新しい発見でした。 折に触れ読み返したい内容です。
0投稿日: 2012.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ高校生の時に買ってから、もう何十回読んだかわからない名著。新書だが、自分はエッセイだと思って読んでいる。少なくとも『実用書』ではない。本気で外国語を身に付けようと思って実践したことがある人にだけ、「うんうん、その通り!」と思わせてくれる。だから「手軽に外国語を身に付けたい」という御仁にはわかっていただかなくていい本。
0投稿日: 2011.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ今ちょうど中国語学び出して2週間経ったので、モチベーション維持のために読んでみた。古いけど、書かれていることは古びていない。お金と時間をかけ、単語をしっかり覚え、復習をかかさない。単純だけど、これが言語習得の王道には違いない。コツコツやっていこう。
0投稿日: 2011.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習を因数分解し、その解を求めた書。 決してエビデンスには満ちていないが、体験からにじみ出た言葉にどこも、すんなり納得。 語学で何をするのか決めよ。 そして、まずは千語を究めよ。 論より証拠を教えられた思いがする。
0投稿日: 2011.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ上達に「楽」は不要。必要なのは語彙と文法、時間と金。 ということを、実に明快に解き明かしている。 うすうす感じていたことだったが、目からうろこ、目の前の濃い霧が晴れた感じがする。 こういうのを「名著」というのだろうなぁ。
0投稿日: 2011.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 外国語コンプレックスに悩む一学生は、どのようにして英・独・仏・チェコ語をはじめとする数々のことばをモノにしていったか。 辞書・学習書の選び方、発音・語彙・会話の身につけ方、文法の面白さなど、習得のためのコツを、著者の体験と達人たちの知恵をちりばめて語る。 言語学の最新の成果に裏づけられた外国語入門書の決定版。 [ 目次 ] [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログまず単語を1000は覚えること。 次に基本文法を学ぶ。 その際、テキスト、辞書、先生をしっかり選ぶ事。 時間をかけることは絶対必要。
0投稿日: 2011.05.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版1986年というかなり前の本ではありますが、数々の語学学習の本で引用されている基本書のようなので、私も気になって読んでみました。外国語習得に必要とされる普遍的な法則がわかりやすくかかれており、ロングセラーになっているのがわかった気がします。 ただ筆者が「私は語学が苦手である」というスタンスから始まっているのですが、読んでいるうちに、その努力のすごさに圧倒されて、これは苦手とは言わないのではないかなと思いました。
0投稿日: 2011.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カレル・チャペックやミラン・クンデラの翻訳でもおなじみのチェコ文学者による外国語学習法。経験談や先行する類書からの引用を交えた「ありがたいお話」として面白い。今は第二言語習得に関する専門的な研究が進んでいることもあるし、わざわざこの本を引っ張り出してくる必要性は正直ないと思うけれど、ただ面白さという一点に関して言えば、本書の一人勝ちでしょう。 特に「レアリア」辺りからの、著者自身の高揚がそのまま投影された文章が素晴らしい。無意識下の情熱が文体に変形を加える、その瞬間の高揚。小説だったらクライマックスに相当するほどの文章の煽動力がここにはあります。なんていうか、それだけでも、読んで良かった。 この人の訳した小説が好きだ、なんて人は、読んでみても、いいんじゃないでしょうか。
0投稿日: 2011.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を学ぶのに簡単な方法なんてありません。 地道にコツコツ。 自分が何の為にその言語を学習するかが明確になっていると 伸びも早い。 辞書の選び方、文法、発音等項目ごとに分けられているので、 読みやすい。 1986年に発行されているが、基本な言語学習法は今も変わりません。当たり前のことを書いてありますが、もう1度言語学習を改めて考えさせられる本です。
0投稿日: 2011.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を勉強する上で必要なことがコンパクトにまとめられてて、しかも読みやすくて分かりやすい、すごくいい本だった。無駄なく必要な事柄を述べ、しかもそれらの選び方を詳細に解説してある。エピソードも多くて、読み物としても面白い。良い教師については、チャットなりスカイプなりがある今だからこそ実践的だと思った。 ・ある外国語を学ぶ目的は?目標は?読めればいいのか、必要なフレーズを書くだけ話すだけなのか。そこをはっきりさせないといけない。 ・読み書き話しの三拍子が揃うのは超難しい。そこだけが外国語学習目的じゃない。 ・勉強の必要があるのは語彙と文法。 ・必要なものは良い教科書、良い辞書、良い教師。 ・良い教科書とは、薄い教科書。 ・活用や変化が多い屈折的言語は文章丸覚えが効果的。 ・会話はとにかく話して、間違って習得する。 ・レアリアがないと、言語だけではお話にならない。 ・S先生は神。
0投稿日: 2011.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログまず文章が面白い。「使わない外国語を習得しても、力を維持するための復習の時間が無駄」(要約)ってのが目からウロコ。大切なのはどこ(論文を読める・書ける・日常会話ができるなど)をゴールとするのか。文法も語彙も大切。
0投稿日: 2011.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ多くの語学に触れてきた著者が発見した言語習得の普遍的なコツを、分かりやすく紹介してくれる。 言語習得の認識の改善から細かい習得方法まで書いてあり、非常に重宝した。 しかし、結局は本人のモチベーションと用意し得る環境に依る部分が大きいことを考えると、 とどのつまり言語習得は本人が必要になった時に必死で行えばよく、この本のような方法論はあまり役に立たないのではないか とも思う。
0投稿日: 2010.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログわがバイブルに認定しよう。ちなみに、著書は、クンデラの「存在の耐えられない軽さ」の翻訳もされている。
0投稿日: 2010.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ○2010/06/14 前回の新書よりもさらに読みやすい…。同じ教科の課題で購入。こうサクサク読めるのが続くとどんどん新書に手を出したくなってしまう。言葉を専門にしている人はやっぱり言葉に対して丁寧になるんだろうか。 各章まとめてあって言いたいことが分かりやすい。英語ってものをならってきたから、多言語を学ぶ上でのあるある体験談なんかも踏まえつつ読めるしおもしろい。 ただ、これを自分が教える側に立って思ってね、と言われてしまうとすごく厳しいものが(笑)精進…?
0投稿日: 2010.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこれいいよ的なことをネットでよく見るので、こういう本あまり好きじゃないんですけど(英会話熱煽ってる的な)、読んでみた。忘れた頃に図書館から入荷連絡。 あったりまえ〜のことが書いてあったよ〜だからいいんだよね。 初心者なのにいきなりペーパーバックで英語にふれろ、とか映画をみまくれ!じゃなくて。でもこの先生の時代には両方とも手にするのは無理だったからしゃーないか。 ひとまず基本を覚えて、それをハンドルできるようになれと。 やっぱり中高の英語教育というのは、それに沿っていて(内容つまらんけど)、ナットク。そして大人になって、作業=カネに換算するようになってからは、それができなくなっちゃうんだよね。反復って大人になるとむずかしいよね〜 でも自分が思ってたことと先生の言ってることはだいたい一緒だった。自分に必要な語学力を得ることを考えろ、とか。しょせん外国人なんだから、ネイティヴ並みなんて無理っすからねー ひとまず、中1の時に、発音記号から単語を書くテストを毎回やってくれた高橋ピグモン先生と、帰国子女日本語教育校だった小中で発音のよい同級生に囲まれたことを感謝します(って別に私の発音がいいわけじゃない、恐怖心がないだけ)
0投稿日: 2010.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ当然のことを当然のように書いてるが、意外に響く本。語学を始める時、つらい時に読むと頑張る気が起きてくる。不思議な力がこめられている。
0投稿日: 2010.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログTOEICに備え読んでみる。 語学を始めるぞ、って時に読むべき本だった。 内容はごくごくまっとう、かつコツコツと頑張らねば、という気にさせるもの。奇をてらった、というか、目から鱗のメソッドがあるわけではない。 語り口が優しく、上品かつユーモラス。 少し前の、堅苦しくない知識層(って表現が適当かわからないが)の紳士って感じ。むしろ英国紳士って感じ。 ゴールの設定、および理由の有無は多いに語学学習に影響すると。大変耳の痛いお言葉。
0投稿日: 2010.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を習得する際のコツとは何か。とても斬新で奇をてらったものが書いてあるというわけではないが、どのコツも納得させられるものである。文体も読みやすい。
0投稿日: 2010.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語を学ぶにはコツがある。それを意識して勉強すれば必ずうまく勉強できる。 中学の時から私は日本語を外国語として勉強してきた。日本語は韓国語と発音や文法が非常に似ていて勉強しやすかった。でも、中国国内で何年間日本語勉強したってなかなか話せない。書いたり、読んだりするのは良かったが、会話ができなかった。その時から私は将来日本への留学を決意した。せっかく覚えた日本語なのに使えず忘れてしまうと思って・・・日本に来たら上達が早かった。自分もびっくりするほど。日本語を話す条件が整っていることと昔から勉強してきて基礎知識が丈夫だったからだと思う。まだ、この本に書いているように文法や単語などは長く使わないとわすれるから常に本を読むこと、外国語は短期間でうまくなるのは無理なので長い間の勉強が必要だということも大事だ。
0投稿日: 2009.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ[コメント] 「勉強法」佐藤優 [関連リンク] 外国語学習について新書を読んでみた - 鰤端末鉄野菜 Brittys Wake: http://d.hatena.ne.jp/Britty/20090328/p1
0投稿日: 2009.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ外国語学習者を勇気付ける言語学者の千野栄一・故東京外国語大学教授のエッセイ風著書。千野氏は、スラヴ語を中心とする言語学者でロシア語やチェコ語等を専門にしているようだが、言語学的分析の対象はグルジア語等へも向かっており、また当然比較的学習の容易なドイツ語やフランス語も学習経験があるようなので、英語以外のマイノリティ言語(千野氏に言わせれば、フランス語、ドイツ語、ロシア語はこれに該当しない)を学習しようとする者にも参考になる本である。書いてある事は、当たり前と言えば当たり前の事だが、それでも読んでよかったと思わせる内容と言えるだろう。
0投稿日: 2009.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ充分語学に堪能であろう著者が、更に神様のように尊敬する先生に尋ねると「上達に必要なのは、お金と時間」だといわれた…。チェコの国民的作家であるカレル・チャぺックを紹介しても名高い千野栄一氏が、外国語を学んで上達するには・・・を実際的かつ軽妙に述べた名著では。
0投稿日: 2008.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ語り口が軽妙(なんて月並みな表現)。千野先生を敬愛して已まない人を知っているけど、なるほど愛すべき先生かもね。
0投稿日: 2008.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「外国語を学ぶにはコツがある。それを意識して学習すれば、必ず外国語がモノになる」という一貫した主張を裏付けるエピソードとともに、具体的な勉強法が項目別に紹介されている。「目的を持つこと」や「継続の大切さ」、「文法の大切さ」といった正道を行く学習法がいかに大切であるかということを改めて実感させられるとともに、「語彙の選択」、「辞書の選択」、「教師のあるべき姿」、「レアリア(言語の背景にある文化や社会、歴史)の大切さ」について教えてくれる、語学の学習者にとっては必読の1冊。個人的には「まず語彙を1000語覚えてそれで無理ならその言語は諦めろ」というアドバイスが印象的だった。 ちなみに千野先生は外大のチェコ語科を作った人で、言語学ではすごい有名な人らしい。「月刊言語」で、千野先生が「言語類型論」について書かれた短い文章を読んだことがあるが、とても面白く読めた。本書も1章の長さがあまり長くなく、とても読みやすい。
0投稿日: 2008.07.23 powered by ブクログ
powered by ブクログワラをもつかむ思いでこの本をつかみました。 挿話が多く、ときには話が脱線することもあるのですが、語彙、文法、学習書、教師、辞書、発音、会話、レアリア、といった語学学習に必要な要素を、それぞれの章において明快に結論を出していることが最大の良さでしょう。 私がこの本を読んで、語学学習、とくに自習するための学習書を選ぶ上で必要と考えたことを箇条書きすると、 1 分厚くなく、薄めであること。 2 各課に分かれていること 3 各課では、そこで学ぶべき文法項目が明記されていて、その文法項目に関する例文を和訳(英訳)する練習問題があり、その後和文(英文)を当該言語に翻訳する練習問題がある。 4 各課ごとに新出の単語の表が、訳とともに付されていて、巻末に本に登場するすべての語彙のグロッサリーがある。 5 単語は当該言語で頻出する1000〜2000語が網羅的に収録されている。その頻出分析は、学問的な研究成果によるものである。 6 易しい内容から難しい内容へ、と進むようになっており、決して重要文法項目順ではないこと。 7 大切な文法項目や単語は、何度もその後の課でブラッシュアップできるよう二度三度と出てくるようになっている。 8 例文は実際に使われる文章、かつ興味を引くようなものである。 9 発音の項目がおろそかにされていない。発音記号を使って詳しく説明してあること。 10 CDが付されていて、例文を網羅的に収録している。 この本を読んで、少しずつ自分の学んでいる言語が近くなってくるのを感じられるようになりました。
0投稿日: 2008.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ千野先生の著作を初めて読みました。ユーモアのある語り口。実際の講義はどんなものだったんだろう? 内容はもちろん二重丸です。外国語学習への意欲が増しました。
0投稿日: 2007.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ動機と目標をはっきり持つことが大切。語学上達のためにはお金も労力も時間も必要。当たり前のこと。そうだなぁと再確認。
0投稿日: 2006.07.22
