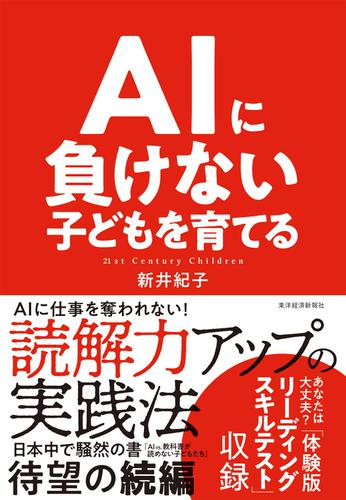
総合評価
(178件)| 76 | ||
| 65 | ||
| 22 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間のAIに対する優位性を明らかにしようとしたら、人間の「読めなさ」を晒す結果になってしまったというRST(リーディングスキルテスト)を通して、読解力の大切さとそれを身につけるための提案がされている。文章が非常に分かりやすく、著者の信念と確信がひしひしと伝わってくる。迫力と説得力があり、一気読みした。 体験版の成績はそこそこだったが、「◯◯と◯◯のワードが来たら答えは△△」とか、「理屈が理解できないから暗記」は、高校の時やってたなあー。穴埋めワークシートの弊害やルビを振ることの無意味さなど、気付かされることも多々あった。 小学校の低.中.高学年ごとの授業方法の提案がされており、このように段階的に進めていければ苦労しないのだが…… という現場の実情はある。しかしながら、穴埋めワークシートや、自ら桁を揃えなくてもよいような筆算ワークシートの弊害を理解し、使用を少しでも減らしていこうという意識をもって授業する事には、すぐにでも取りかかりたい。読めている人には「読めない」がどういう事か分からないが、これが分かれば、ドリル学習よりもやらなければいけない事が見えてくる。 これだけ科学的なデータが示されているにも関わらず、それが国の教育施策に生かされているのかというのが大いに疑問。一人一台端末を配布するよりも、真の生きる力に直結する読解力を育成する方に議論を進めてほしい。
0投稿日: 2025.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ係り受け解析 照応解決 同義文判定 推論 イメージ同定 具体例同定 コピー機を多用することで写すことができない子がふえた 文の意味を正しく理解できていない子がふえた 論理的な説明ができるようにする 記事から感想を書く 正しく伝えよう 言葉のとおりに図形を並べよう 偽定量を探せ
0投稿日: 2025.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ単語はわかっていても文が読めない、多くの方は自覚せず生活している。そんな衝撃的な現実を突きつけられます。 それを踏まえて、読解力のない大人がいかにして子供を学ばせるのか、さらにどんな要素を重視すべきかが分かります。
11投稿日: 2025.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」続編! 「基礎的•汎用的読解力を身につけて中学校、そして高校を卒業させることこそが21世紀の公教育の果たすべき役割の『一丁目一番地』」と主張しています。 本書でいう読めるとはAI読み(キーワードの群として読ん)でいくのではなく、「意味を理解して読む」ことです。 そんな当たり前のことと思ってしまいがちですが、これまた子どもも大人も読めない人が一定数(約3人に1人)いるのです。体験版RST(リーディングスキルテスト)もついているので、ぜひやってみてください。かくいう私も正答率は100%ではありませんでした。 そして、その要因の一つに近年の学校教育の動向をあげています。 学習支援や話し合い活動の時間確保のための穴埋めプリントを増やした結果、プリント頼みでノートが取れず、文章の意味を考える機会を奪い、教科書が読めない生徒を増やした可能性があると。 また、人間は怠ける天才であり、いつまでも補助輪つきでは生徒が伸びなくなる。面倒であっても難しいことから逃避しないように、卒業まで心がけてやる必要があるとも。 そして、合理的配慮で行われることの多いルビつきに関しても言及していました。ルビによって読み方(音)はわかっても「読んでわかる」ことにはならないようです。 そんな中で筆者は親、学校、個人でできること提言しています。 詳細が気になる方は、ぜひ手に取ってみてください。
7投稿日: 2025.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「AIvs教科書が読めない子どもたち」の続編。リーディングスキルテスト体験版と解説、今の学校教育の課題、意味がわかって読めるための授業提案などがまとめられていた。学校で多用する穴埋めプリントはキーワードを暗記すれば大体正解してしまうことや、黒板の文章の意味を理解しながらノートに書き出す訓練ができていないことなど、今の学校教育は大丈夫なのかと思う。小学校で意味がわかって読めるようになっていないと中学校以降の学習や社会に出た後苦労するんだろうなと思う。電子黒板よりも読解力が身につく授業をやってほしいと思った。
0投稿日: 2025.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ2回目の読了。 1回目は、前作「AI vs 教科書が読めない子供たち」を読んで間も無くの頃に読んだせいか、読み急いでしまった感があった(スピードを上げてキーワード読みをしちゃダメだって、新井先生も言ってるのにね)。 今回は、そうならないように、ゆっくりと読んだ。 そしたらまあ、面白い面白い。 RST(リーディングスキルテスト)は、答えが問題文の中に書いており、しかも問題文は短文なので、「日本語の意味をとらえて短文を読めれば必ず解ける」、にも関わらず、(AIのように)キーワードを拾うような読み方では決して解けない、そんなテストである。 ※この本には紙面上で行える「RST体験版」が収録されているので、それだけでもやってみてほしい。30分かかりません。僕は2問間違えました。 序盤は、このRSTがいかに綿密に考えられ、いかに科学的に検証され、いかに画期的であるかを、ていねいに分かりやすく説明している(AI自然言語処理のトップ国際会議で使われているSQuADやGLUEなどのベンチマークがいかに怪しいかも)。 後半は、どのようにしてリーディングスキルを向上させるかという実務的な話(デジタル教科書とか電子黒板はいらない、とか)。幼児期、小学校低学年、中学年、高学年それぞれでの教育のポイントや、モデル授業の様子は非常に興味深い。 全編を通して、新井先生の文章が非常に平易で、かつ、深みを失わないことに感動を覚える。 「リーディングスキルを上げると、文章を書けるようになるし、プレゼンも上手くなる」と書いた筆者の説明が分かりにくいとお話にならないのだが、「この先生がそういうなら、そうなのかも」「この人のようになりたい」と思わせるに十二分な筆力である。 まえがきに書いてあったが、文筆業をされている方が「近年あまりに理不尽かつ不可解な非難が多くて議論にならない。よほど悪意があるのかと思って」いたが、新井先生の本を読んで「『もしかするとそういう人たちは文章を読めていないのかもしれない』と思い始めた」と。 なるほど、そういうこともあるのかもしれない。 かつて宗教改革の前後で印刷技術の発展と識字率の向上が同時期に起こったことを考えても、「当たり前を疑う」とか「自分で考える」とか、外部からではなく体の内側から知を取り出すにはまず、「母語が正しく読める」ことが肝要であろう。 さて、うちの子たちは大丈夫かしら。 RST受けさせてみようかな。 嫌がるかなあ。
3投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
・キーワードの丸覚え(≒AI読み)では、新しい知識を得るための文章を正確に理解することができない。 ・特に数学は、初出の言葉とその定義を理解できなければ理解することができない。 RSTで判定するスキル ①係受け解析‥主語、述語、目的語などの文の基本構造を把握する力 ②照応解決‥指示代名詞が指すものや省略された主語、目的語を把握する力 ③同義文判定‥二文の意味が同一であるかを正しく判定する力 ④推論‥基本的な知識と常識を動員して文の意味を理解する力 ⑤イメージ同定‥文章を図やグラフと比べて内容が一致しているかを認識する力 ⑥具体例同定‥言葉の定義を読んでそれと合致する具体例を認識する能力。辞書由来の問題群と理数系の教科書由来の問題群に分けられる ・中高生以上では、RSTの能力値と学年に相関関係はほとんどない。 ・高校のRSTの平均値と高校の偏差値、その高校の旧帝大などへの進学には高い相関性がある。 ・穴埋めプリントの利用により、AI読みが加速する。 ・板書を書き写すには文節や文の単位で覚えられるようになる必要がある。理解できない内容は板書するのに極端に時間がかかる。 ・実験や調理実習の手順書を読んでその通りに実行し、そこで起こったことを文章で表現することも重要。 ーーー これまで文系科目の成績は良く、理系科目が苦手なのは、数量把握が苦手だからだと思っていたが、見事に⑥の理数系だけの得点が低かった。自信のあった国語力が足りず、実は教科書が読めていなかったと知ってショックだったが、簿記やビジ法などの資格もパターンで記憶しすぐに忘れることを繰り返していたため身に付かなかったのだと感じた。 「公立学校の復権が地方創生のカギ」「おわりに」では不覚にも目頭が熱くなった。都市の富裕層しか権限層になれないのはおかしい(意訳)という新井氏の怒りと、それを原動力とした行動に心動かされた。 本は図書館で借りたが、絶対自腹で購入し新井氏の取り組みを応援したい。
1投稿日: 2024.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ難解な単語は少なく、とても分かりやすいです。 そして本書では、実際にRSTリーディングスキルテストを体験できるようになっています。 しかも、小4対象のリーディングスキルを身に付ける授業の例まで載っています。 テスト自体を繰り返してリーディングスキルを身に付けようとする事は間違い! 読解力だけど、数学の“集合と論理”の思考もすごく必要。 著者の新井紀子氏の物事へ懐疑的に向き合う姿勢は、これからの情報過多の時代において、参考にしていきたいです。
5投稿日: 2024.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2024年6月10日読了。東大合格を目標とする「東大ロボ」開発プロジェクトを率いたAI研究者の著者による、話題を呼んだ前著に続く本。「AIは人間の認識能力に及ばないが、昨今の人間の振る舞いは劣化版AIそのものではないのか」という問題提起から、「人間ならではの認識能力・論理的思考力を図るテスト」を考案したというあたり、同じような主張を延々と繰り返し続けるそこらの学者とは一味違う。26問の小テストを自分も受けてみたが典型的な前高後低型、日本語が読めていない自分に空恐ろしくなった…。明確にコミュニケーションするために、「定義」とか「指示代名詞が指し示すものの理解」とか、国語力や読解力は重要だな…と思った。そういう意味では受験勉強も悪くない。AIに置き換えられないよう、自分もインプット偏重にならず思考を続けていかねば。
1投稿日: 2024.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ前書も衝撃的でしたが、本書もまた面白く、考えさせられました。大変興味深く拝読した、と思っていますが、私はきちんと「読めて」いるんでしょうか? ははは。 正確に説明する=プログラミング教育の基本。 ほほぅ。 今年度施行の共通テストから、情報が必須になるからレベルを落としてでも現役合格!と言い張って第一志望に合格した娘は、もしかして浪人して情報を学んだ方が良かったのかも? 体験版紙バージョンRST、具体例同定がボッロボロでした。笑ってしまうくらいに。定義にいちいち照らすのが面倒で、楽に逃げた結果なのかなー。 よく噛んでゆっくり食べよう、ぐらい気乗りしない、よく読んでゆっくり考えよう。急がば回れなんだろうけどな。
0投稿日: 2024.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分には読む力があると思い上がっていることに気づけた。早く読むことよりゆっくりでもちゃんと読む練習をしていくと決意できた。
0投稿日: 2024.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ半分以上はご本人が考案されたRSTのお話で、個々の家庭というより、学校教育の現場に対する提案が主。ただ、個人の家庭でも参考になることは多いです。 ここまでの物を作り上げるのにかなりの労力をかけられたのだなと感心します。
5投稿日: 2024.03.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作の『教科書が読めない子どもたち』はセンセーショナルでしたが、今作は、大きく頷く内容でした。話し合いや協同学習やICT に舵を切った弊害について問題提起をしています。 国語科の教員として深く考えさせられました。
1投稿日: 2024.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ前回に引き続き良い本だった。簡易版RST試験の自身の結果にはショックを受けたが、自身の苦手とすることが見えてきてよかった。どう対応すればいいかはわからないが(本書にもそこまで詳しくは載っていない)、まずは一文一文確実に意味を理解する習慣を身に付けたい。
0投稿日: 2023.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著「AIvs教科書が読めない子どもたち」で世間に大きな衝撃を与えた著者がAI共生時代の教育論を提案。 日常生活における文章の流し読み・テスト対策としての暗記頼りへの慣れに警鐘を鳴らし、文章の構成・言葉の定義をしっかり読み解く読解力の涵養が重要。 読解力を基礎とした論理的思考力の鍛錬・正確に説明するスキルなしに文理融合・STEM教育の未来はない。 著書内で紹介されたリーディングスキルテストは分量・時間ともに決して膨大な量ではないが、普段文章を真剣に読んでいない現れなのか、非常に疲れた。 公務員試験を受験した方に共感してもらえればと思うが、何となく公務員試験の一部問題はリーディングスキルテストに通づるものがあり、実は文書読解力を測るうえでとても優れた試験なのではないか。
1投稿日: 2023.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログRST(リーディングスキルテスト)の体験版が受けられると言うことだったので読んでみました。 散々な結果でした。 それはさておき、こういうふうに「読解力」を分解して、何がどれくらいできないのかが判るととてもよいですね。 対策しやすいです。 AIに負けない、ということと、読解力を高める、ということが直結するかどうかはどうかなと思いましたが、読解力が低いと、騙されたり、損したりは多いと思うのでぜひ高めたいです。 学校の主に国語の教員向けに書かれている感じでした。 授業案なども載っています。
0投稿日: 2023.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ高3で教師を目指す受験生なのですが 凄くためになる本で読む度なるほどと思うことが多々ありました。読解力を身につけるにはどうしたらいいのかまで書いてありこれからに生かせる本だなと思います
0投稿日: 2023.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
前著で明らかにされなかった、読解力が低下している原因について、まず学校教育において電子黒板や穴埋めプリントの活用によって板書をノートに写す作業が減ったことにあるとしている。ノートに取ることは一見非効率で無駄な作業に思われるが、文章の意味を理解せずにはスムーズに写すことができないのだという。文字単位や画数ごとに写している場合には、文章が理解できていない可能性が高い。 もう一つは、スマホの普及によって幼児が接する大人たちがSNSやゲームに集中する時間を増やし、大人同士の会話を聞く時間や自分に話しかけてくれる時間を劇的に減らしていること。 双方とも、機械や技術による生活の変化、しばしば効率化と肯定的に捉えられるものに、人間から何らかの基礎的なスキルを奪い去る側面があるということ。 単調で退屈に思われる手作業、人間同士の意味を持った会話は、見かけ上AIに取って代わられることがあっても、人間とAIとではその行う作業の本質的な部分が全く異なる。 人間は集中することができ、意味を理解し、欲求を持ち、また全力で怠けようとする。穴埋めプリントのような、意味を理解せずキーワード検索で終えるような作業こそが、AIが得意とする作業。 読解力を向上させるために幼児期の教育方針として挙げられている中には、手を動かすこと、関心を持って自ら取り組むこと、集中してやり遂げることなど、モンテッソーリ教育とも共通するものが多いと感じた。 加えて大人の関わり方が重要な幼児期。生活の中で繰り返す食事や入浴、着替えなどにも手を動かす大切な動作や自然現象を学ぶ要素がたくさんある。忙しさにかまけてこれらを疎かにせず、また子どもに向き合い、関心を持って見つめる視線の先に気付いてあげられるよう、過ごしていきたいと感じた。
0投稿日: 2023.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
リーディングスキルテストの結果をもとにした、読解力の育み方に関する本。 穴埋め式プリントを多用する暗記になりがちで読解力が付かないため、文章の要約や読み込みなどをコツコツ続けることが読解力の養成に繋がるとのこと。
0投稿日: 2023.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著から引き続き読ませて頂いた。読解力を上げることの重要性や上げるためには近道は無いことがよく分かる内容であった。小学校での教育方針はぜひとも科学的な根拠に基づき大幅に見直しをかけて頂きたい。
0投稿日: 2023.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ妻と子どもと丁寧に会話し、子どもの学校の教科書を子どもと一緒に丁寧に読んで、日々体験することや世の中の出来事について丁寧に考えを述べ合おうと思った。 それと、読んで書いて聞いて伝える、見たままを分かりやすく書く、説明する、表現する、そのようなことがとても大事だなと思った。 ドリルは完全ではないということも新鮮だった。
0投稿日: 2023.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、学力レベルに相関する読解力の重要性を説き、小中高生の読解力が低迷する教育現場の問題点を指摘し、その解決策を提案する内容である。 タイトルにあるAIの解説、及び本書の軸であるRSTについては説明が簡易的であるため著者の前著「AIvs教科書の読めない子供たち」を先に読了することを勧める。 筆者は数学者らしく、主張の前後には必ず理由が分かりやすく記してあるため、説得力がある。 読解力は、教科書の理解はもちろんのこと、新聞や新書などの読解や文章(プログラミング言語含む)の作成にも必須のスキルであることから、義務教育(遅くとも高等教育)の段階で習得するべきスキルであると感じた。我が子にも読解力が身に付くよう、意識してコミュニケーションを取りたいと思う。 読解力の重要性を知り子供たちの学力レベルが上がるよう、本書はぜひ教育現場や子育て世帯のリビングに置いていただき、次世代の国民の力が上がるよう願う。
0投稿日: 2023.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の読解力を計れるのが面白かった。 著者があらゆる批判と向き合い、論理的に反論していくのもかっこいい。 AIに負けない力とはなんぞや、は前作「AI vs 教科書の読めない子供たち」を参照。 本作は読解力をいかに強化するかに特化。 地道に「意味」と向き合うしかないんだなぁ。
0投稿日: 2023.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ基礎的な読む力は子供から大人まで必須のスキルだと思う。 流し読みの癖を減らすなどできることをしていきたい。
0投稿日: 2023.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログRSTのテストがついている、とのことで紙で購入。 満点ではなかったが概ね想定通りの点数でした。 読解力を上げるには近道などはなく、地道に深く読み込んで理解するしかないということに納得しました。
1投稿日: 2023.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ新井紀子さんの本はこれで2冊目である。 前作のAI vs教科書が読めない子どもたちがとても面白かったため、図書館で新井紀子さんの本を見つけ、すぐに手に取った。 この本の中には、リーディングスキルテストがあり、実際に自分で解くことができる。 文章をしっかりと読むことの大切さ、自分自身がどれぐらい読めていないかも知ることができた。 リーディングスキルがどうすれば身につくかの正確な答えはないが、読めていないことに気づくことこそが、第一歩だと思った。 全教職員に読んでほしいと思った
0投稿日: 2023.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ皆の感想を見てると結構テストの出来がいい人が多い印象だった。 自分は全然だめだったからヤバいと思わされた。 確かに小、中学生の時は暗記で点が取れたから論理で解かずにきてしまった。 本も早く読むことだけが正義ではない。 ついつい早く読むことが、凄いと思い読んでしまい、結果何も残らないということもあった。 これからは、「ゆっくり、丁寧に」を意識して本を読みたいと思えた。 あとは、物事の本質を捉えて考えることが大切でさらに間違いという経験をどれだけ積めるかが大事。
0投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の経験と照らし合わせても腑に落ちる読解力に対する指摘だった。RSTを実際にやってみてちゃんと文章を読めてないクセが少なからずあることを痛感させられた、確かに数学の定義文は今でも苦手だ。そして意味をしっかり理解することは、自分自身の考えを上手に出力できることに繋がる。ここで提唱されている教育を子供の頃から実践すれば、確かに人生を大きく変える結果が伴う。
0投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022年の下半期は、お絵描きAIの「Midjourney」とチャットボットAIの「ChatGPT」が一般公開されて話題となった。「Midjourney」に描かせた絵画が芸術コンペ(米国コロンビア州)で1位となり、短編SFで有名な星新一の賞でもAIを活用した作品が一般部門で優秀賞となった。特定範囲におけるAIの能力(「弱いAI」とも呼ぶ)は人間を超え始めたと言えそうだ。そんなタイミングだからこそ、積読だった本書を手にとった。 本書は「東大ロボ・プロジェクト」で「出題者の意図を理解できない東ロボ君(偏差値57.1)に8割の学生が負けた」という問題に対処するために開発したRSTという30分程の読解力テストについての解説。 RSTの類型は6つ。 ・<係り受け解析>文の基礎構造を把握できているかどうか。文法問題と言える。 ・<照応解決>代名詞などが指す内容を認識しているかどうか。 ・<同義文判定>2文の意味が同一かどうか判定する問題。 ・<推論>日常生活から得られる常識を動員して文の意味を理解できるかどうか。 ・<イメージ同定>文と非言語情報を正しく対応付けられるかどうか。 ・<具体例同定>定義を読んでそれと合致する具体例を認識できるかどうか。 どれも文脈を共有して議論を発展させていく上で必須となる能力。中学生以上は当たり前に備わっていると思うと大間違いらしい。音感と同じで、できる人には当たり前だが、一定数できない人が居るとのこと。正直、本書で説かれている言語能力のハードルを超えたとしても、バカの壁であったり、認知バイアス、心理的安全性の欠如など、コミュニケーションを阻害する要因はいくつもある。そしてこれらのどれかひとつでも絡む状況においては、AIに敵わなくなってくる可能性が高いと僕は感じている。人間にとってなかなか望み薄な戦いな気がしてならない。
0投稿日: 2022.12.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想 読書をしない子供達。読解できないならしたいわけがない。どうすれば読解力を向上させられるか。教育が槍玉に挙げられるがそれだけで十分か。
0投稿日: 2022.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログAI…シリーズ第「AIに負けない子どもを育てる」 前作が面白かったため、第2弾も読んでみることにした。 前作では、AIは全知全能の神のようなものではなく、シンギュラリティなど起きない。AIにはない”読解力”で人間は生き残っていくべきだが、実はその”読解力”が悲惨な状況になっていてい…という内容だった。 第2弾は完全にAIからは離れて、そのやばい”読解力”をどう向上させていけば良いかということが中心に書かれていた。 汎用的読解力を測るRSTのサンプル的なテストもありまずは自身もやってみた。 私は「具体的同定(辞書)」という項目が圧倒的に弱く、他は合格点以上という結果だった。 読解力を上げるには、子供の時から「意味を考える癖」をつけるというのが方策として示されていたが、現状学校や試験ではその力を向上させる仕組みになっていないということが問題視されていた。 読解力に問題がある、つまりそもそも教科書が読めていないという点に気づき始めた教育者も多くなってきているようであるが、教育会全体の流れを変えるにはもう少し時間がかかるだろう。とりあえず自分自身、そして自身の子どもにおいての教育についてはこの点を十分に考慮していきたいと感じた。
5投稿日: 2022.10.08 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://kinoden.kinokuniya.co.jp/shizuoka_university/bookdetail/p/KP00025114/
0投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログAI VS.教科書が読めない子どもたちの続編。リーディングスキルテストの体験ができ、また子育てに関して参考になる情報も多い。具体的なアドバイスが述べられた第9章は秀逸(当然、読解力についての定義と著者の主張を把握したうえで読む必要はある)。 第2章 読めるとは何だろう 日本で育った日本人は、(読み障害がなければ)ほぼ全員が読み書きできるようになる。しかし、家庭や地域によって語彙量に相当の差が出るほか、本や教科書の読み方、板書の捉え方に決定的な差 = 機能語の部分を正確に読む子とそうでない子の差が出てくることが問題。後者は教科書を読んでもぼんやりとしか意味が分からず、暗記やドリルに頼るようになる。文を読むときに(機能語を無視して)キーワードの群として文章を捉えるようになり―著者はこれを「AI読み」と呼ぶ―この方法では新しい知識(例えば数学で出てくる"定義")を学ぶこと、特に学年が上がり学習内容が抽象的になればなるほど、理解を深めることが難しくなる。日本語として単語をとらえることは出来ても、文章の意味を理解することができていないから。 一例として、「誰もが、誰かをねたんでいる」という文章を、意味を変えずに受け身型にするとどうなるかという例題が出てくる。自分は当然のように「誰もが、誰かにねたまれている」だろうと考えたが、著者の思うつぼ。ツイッターでも7000人以上の回答者のうち半分以上が同様に答えたそうだが、図を描いてみると分かる通り、前者は「誰にもねたまれていない人が存在する」のに対して、後者は「全ての人が誰かしらにねたまれている」意味になってしまい、同義ではない。この問題の(自然な)受動態文は「ない」というのが正解だそう。こんな問題一つでも、自分がいかに"読めていない"かを痛感した。 知らなかったが2022年度から高校の現代文は「文学国語」と「論理国語」の選択制になるそうで、長く続いた文学班長から、事実について書かれた文章を正確に読んだり書いたりできることにも重きを置かれるようになるそうだ。 第3~5章はリーディングスキルテストの実践、解説、間違い方のタイプ別分析 第6章 リーディングスキルテストでわかること 35分のテストでそんなに正確に読解力が判定できるのかとよく問われるが、視力検査に似ていると言えばわかりやすい。0.8を指して間違ったら1.0を指して、正解したら0.9を指して、というイメージ。通常の筆記試験のようにどの問題が出るか予め決まっているのではなく、受験者の回答に応じて難易度を変えた問題が出され、それを繰り返すことで、正答率が半々程度になる問題の難易度が、受験者が正確に読むことができる「限界だろう」と判断している。 「入試が暗記を求めるから暗記をする」のではなく、「入試は読解力を求めているのに、読解力が不足している生徒は(AIと同じように)暗記に走らざるを得ない」 日本のような「公平で統制が取れた教育制度と極めて厳格な大学入試制度を維持している国」は他にほとんど存在しない。例えばRSTの問題分類の一つ「推論」では、ある程度の常識を求める出題がある。日本で生まれ育った人にとっては当たり前のことでも、例えば州や学校によって「進化論に極力触れない」教育を受けるようなアメリカでは、テストとして成り立たないだろう。RSTの成績が州によって異なったとして、それが移民割合のせいなのか、所得の差か、教科書のせいか、教員の質か、統制の取れない条件があまりに多すぎて、日本ほどくっきりとした(例えば高校の偏差値とRSTの平均読解能力値が高い相関をもつような)結果は得られないという。 第7章 リーディングスキルは上げられるのか まず第一に、RSTは達成度テストではなく、100点を目指すものではない。RSTのドリルを作って毎日生徒に解かせるという学校が出てきたが、それは完全に間違っている。人間は、同じことを何度も練習させられると、多くの場合「楽だけど非本質的な」解き方を会得する。幸か不幸かそれで結果が向上したとしても、RSTの本来の目的からずれてしまう。 アクティブラーニングという言葉が流行しているが、著者によれば日本はアクティブラーニング先進国。1980年代、90年代、日本の学力があまりに高いので、世界各国の教育関係者が盛んに視察に来て、班活動に注目したという。班活動 = グループ学習であり、一人ひとりが意見を言い合い議論するという意味で、アクティブラーニングだと言える。 ある研究授業で、4年生の多くが2Bの鉛筆を使っていることが気になって聞いてみたところ、アクティブラーニングでは黒板の文章を写す時間はとらないのだそう。いろいろな自治体のワークシートやプリントを集めて気づいたのは、文章を書かせるよりも、穴埋め形式のものが圧倒的に多いということ。文章を「文章として」読まなくても、キーワードを埋めていけば学習できた気になってしまう。そのキーワードだけ覚えれば、真の理解はしていなくても、テストでそれなりの点を取れてしまう。そのまま中学生になり、高校生になり、ノートが取れない大学生になる。 計算ドリル、特にあらかじめ桁がそろえて書いてある筆算ドリルは使いすぎてはいけない。問題だけが書いてあって、ノートにそれを写して、それを筆算させる方が良い。「桁をきちんと合わせないこと」「繰り上がりや繰り下がりを正しい箇所に書かないこと」が筆算の初期のつまづきの多くであり、これが何も考えずに上手くいくようなドリルを使っていては、真っ白な計算用紙で自力で計算することは出来なくなる。「自転車の補助輪」は最初は必要だが、どこかで外さなければならない。伸びなくなる。 小学生で重要なのは、筆算の桁をそろえること、板書をある程度の速さでノートに写すこと、手順書通りに実験をしてその結果を見た通りに記録すること、点に合わせて定規を押さえて線を引くこと、指に力を入れすぎないようにしながらコンパスで円を描くこと。意味を理解すること、自分をコントロールすることであり、AIと根本的に違うところ。その積み重ねで、リーディングスキルは(大人ですら)上げることは可能だという。 人間は怠ける天才。怠ける天才だからこそ、遠い川から水を運ぶのではなく、井戸を発明し、水道を引いた。抽象概念を理解し、操作(推論)することは、多くの生徒にとって暗記やキーワード検索よりも面倒くさく、難しい。怠けがちになる。だからこそ、抽象概念を操作することから逃避しないよう、目にかけてやる必要がある。現代社会で生き残るうえで、意味を理解しながら抽象概念操作ができることは圧倒的なパワーを意味するから。 第8章は読解力を意識した授業の例。 第9章 意味がわかって読む子供に育てるために 全文写したいが少しだけ抜粋。 ※幼児期:社会(文字、数、貨幣、移動手段、調理など)に関心をもつようになったら、ごっこ遊びができる環境を作ったり、広告や駅名を読んだり、(電子マネーではなく)貨幣で何かを買ったり、簡単な調理を一緒にしたりする機会を増やす。 ※低学年:小学生は高学年に至るまで、発達の分散が相当に大きい。何かできないとか、標準以下であると保護者は「自分の育て方が…」とすぐに落ち込むが、睡眠・食事・排便に気を付けていて、ネットやゲームに依存させず、十分に体を動かしていて、日々母語で話しかけているなら、親ができるのはそれくらいだと大らかに構えた方がいい。 ※中学年:20世紀には、登下校の時間に「昨日は何をして、どんなテレビを見たか。どんな番組でどう面白かったか」話す機会が豊富にあった。いまはリアルタイムに情報を共有できるスマートフォンの普及により、背景知識が異なる人に何かを説明するという機会が激減した。リンクをシェアすれば済んでしまうから。その補完として、家庭ではネットワークをオフにして、学校であったできごとに興味をもって子供の話に耳を傾け、客観的に説明する機会を作りたい。
0投稿日: 2022.08.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画「二月の勝者」を通読後、 子どもの通塾や中学受験について思案していた私へのアンサーが、本書にありました。 塾にお金と時間を使わなくても、しっかりした読解力があれば自学自習が可能であり、その力さえあれば本人の意志に応じた道が拓けるであろう、という結論に至りました。 自学自習ができれば、営利目的の組織の力を借りなくとも、「教科書と代表的な問題集と参考書、そして5年分の過去問題集だけ手に入れれば」旧帝大程度は入れるように学校教育は設計されているとのこと。 (ほんまかいな……?) 意味がわかって読める子を育てるために、筆者のアドバイスを実践したい! …中学受験をして、私立の難関中高一貫に入れば、最も効率よく(楽に)難関大に受かるかもしれない。けれども大切なのは、効率では決してないのでした。 以下は、メモです。 読解力というものは、あらゆる科目において重要なスキルだが、今、日本中でこの力が低下しているらしい。 読解力は、高校の偏差値と正の相関がある。 板書をノートに写すことの意義。穴埋めプリントのワナ。 暗記でテストを乗り切ることの危うさ。 タブレット端末の導入で圧倒的に書く量が減るとしたら、それはどうしたらいいかな、、
1投稿日: 2022.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著の続きで、RSTについて詳しく書かれた本。 AIに負けず、人間が人間らしく成長していけるように、自分自身の学びや、子供の学びを工夫していきたい。
0投稿日: 2022.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログrstのトライアル版が収められててそれだけでもかなりお得。教育に関する多くの良書の中でも、この方はかなり実働伴ってて迫力が凄い。 抽象と具体の相互の行き来が私は無自覚に得意なタイプなんだと思った。無自覚だから、この本を読まなければこのテーマ自体、認識を持てなかった。 多くの人の「無自覚」(=いつまでも建設的な議論にならない。)を、データをもとに淡々と「なぜ問題なのか」「どうすれば良いのか」論じる本。気の緩むところは一切ないのに面白かった。
0投稿日: 2022.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ本文中に出てくる阿部謹也さんの「君たちはノートを写す、ということなど極めて退屈で無意味な作業だと思うのだろう。だが、皮肉なことに、君たちが侮る作業を機械に頼ることによって、実は君たち自身の質を低下させていることに気づいていない。」に、今までの自分の考え方が間違っていたということに気づき、はっとさせられた。またテストでは自分は前高後低型だった。言葉の定義とそれを理解する力が必要だとわかった。普段の生活の中で文の意味を正確に理解することを心がけようと思う。
0投稿日: 2022.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ読解力を計るRST(試験)の内容や読解力向上のヒントが具体的に書かれていて良かった。 そして、前著で、自分は読解力あるだろうと勝手に思っていたが、自分の読解力の無さを認識できた。 確かに、読み飛ばしたり、ちょっと意味が分からないなーと思いつつ読んだりしていたなと気づけた。 読解力向上の為、少なくとも丁寧に読むことを心掛けていきたいと思った。(本当は読んだ内容を要約したり、自分や他人の文章を評価・修正する方が為になるかもしれないが、、、) また、読書の多寡や好き嫌いが読解力に関係しないと言うのは驚きでした。
0投稿日: 2022.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ続編を読みました! 読解力を培う授業の具体的解説や、読解力のある子供を育てるための要諦もまとめられており、大満足の一冊。 RST(リーディングスキルテスト)の体験版も収録されており、自身の読解力をテストできます。 読解力は一人で獲得できるわけではありません。即ち、自身の資質というよりも、生育環境によるところが大きい。 そのため、読解力が劣る人を個人の「自己責任」として放置するのではなく、日本社会全体の問題と捉えることがまず重要。 そして、教育の仕組みを見直し、企業や社会全体の生産性向上につなげることが今の日本の課題である。 このあたり特に納得でした! 私もRST体験版にトライしてみました。 すべて10点満点(=上位1%未満)とはいかず悔しかったですが… 平均的ビジネスパーソン以上の点は獲得。 義務教育を終えるまでに、「読解力」を身につけないと、書籍を読んで自ら理解して学ぶということもままならなくなるというのは恐ろしいことですね。
0投稿日: 2022.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作に比べ、内容があるようでない感じがした。 どうも私凄いでしょという圧を感じて読むのがしんどかったです…。
0投稿日: 2021.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ前回の著作の続編。 どうしたら、読解力がつくかを書いてあった。 しかしながら、その方法は難しい。 教育現場がどう対応していくのか。 家庭がどう対応しなければならないのか。 よく考えさせられた。
0投稿日: 2021.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2021/10/22 読了 前作では読解力の低い人では、AIに仕事を奪われる可能性が高い、という内容だった。 今回は「どのような教育をしたら読解力のある子供に育つか」、「今からでも読解力を伸ばすためにはどうしたらいいか」という内容が主軸であった。 読解力判定テスト(RST)の体験版も載せてあり、自身の読解力を客観的に判断できる。 なお、大人の場合は「精読」で読解力が上がりそうとのこと。 最近手を出してない、科学系の新書等で精読の練習をしていこうと思う。
0投稿日: 2021.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著からの続きとして「ではどうするか」という部分を教育の観点でフォーカスすると解法としては確かに難しいとわかる。
0投稿日: 2021.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作「AI vs. 教科書が読めない子どもたち」の課題、どうすれば読解力を上げられるかに試行錯誤しながら取り組んでおられる様子。やはり一朝一夕で上がるものではないのか。大人になってからメキメキと読解力を付けられた方の体験談のように、地道にコツコツと意味がわかるまで精読するしかないのでは。私自身仕事で校正をすることがあり、この文章はどこにかかるかなどを考えることが増えたおかげで、読解力が以前より上がった気がしている。さらに英米語学科だったため、英語で言うSVOCを意識して読むだけでも校正の仕事は楽になった。 読解力を測るテスト・RSTの体験版もあるので、読解力に自信のある人もない人もぜひやってみてほしい。理数系の問題でよく間違えたのは、高校時代数学が校内で下から2位だったからと言い訳したかったのに、本書を読むとさせてくれない。ぐうの音も出ないとはこのこと。
1投稿日: 2021.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校教育にITを導入している学校は進んでいると思っていた。 ITを駆使して最先端の教育をすることがいいことだと思っていた。 もちろん使い方しだいではあるが、この本を呼んでそんな考え方が変わった。 人間は楽をする生き物である。ITの進化で効率ばかりを追い求めてしまうが、人間はそんなに早くものごとを処理できる能力はないのかもしれない。 情報過多な昨今は特に、じっくり考えて、何を言っているのかをちゃんと理解する必要があるのだろう。
1投稿日: 2021.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の読解力のなさに打ちのめされつつも、その力のを伸ばしたいと思えるインセンティブをもらった。今まで漫然と「子どもの読解力を伸ばすのって大切だよなあ」ぐらいにしか考えてこれなかった頭に、光明が差し込んだ気がする。読むとはどういうことか。読めないとはどういうことか。どんな力が必要で、どんなトレーニングが考え得るか。想像するだけでワクワクするし、まだまだ子どもを伸ばす可能性が広がっていることにドキドキする。今だから、国語が全ての教科を支えている、と断言できる。
0投稿日: 2021.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著も読み、読解力を実際につけるにはどうすればよいのか?について知りたかったので読んでみた。 リーディングスキルテストのサンプルを受けることができ、自分のレベルを大体知ることができ、参考になった。 読解力がないと、教科書を理解することはできないし、テストの問題も勘違いしてしまったり、進学先に大きな影響を及ぼす。 子供には是非読解力をつけてほしいので、多くの語彙を使って話しかけたり、絵本を読んであげたり、できることを行っていきたい。 少し残念だったのは、「大人が読解力を身につける方法を明らかにする」と、記載されていたが、あまり具体的な方法が記載されていなかったこと。
0投稿日: 2021.08.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ「AI vs 教科書が読めない子どもたち」が読みたいと思ったが、何となくタイトル的にこちらが面白そうと思ってこちらから読んでみた。 RSTについては批判もあるようだが、こういうテストで自分の現状を知るということは重要だと感じた。 結果は個人的にはショックだったが(もうちょっとできてるかと思った)、甘んじて受け入れたい。 個人的に示唆に富んでいると感じたのは「読解力がないために暗記に走る」という指摘。いわゆる学歴社会というものに対してかねてから私が感じていた違和感はこれだったのかと、非常に腹落ちした。と同時に、子供たちに戒めていかなければならないことも思う。 どちらかというと学校の先生向けの記載が多いなか、最後あたりには大人になってからの読解力の伸ばし方についても触れられていたが、読解力は一朝一夕に身につくものではなく、日々の努力の積み重ねしかないというもの。期待した人には拍子抜けする内容かもしれないが、個人的には納得。筋トレと同じで、特効薬はないということなのだろう。 著者の見解はところどころ極端なところがあり、また自身の活動の宣伝といった内容も見受けられるが、総じて同意できる内容だった。今回スキップしてしまった前著の「AI vs 教科書が読めない子どもたち」も読んでみようと思った。
1投稿日: 2021.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ「AI vs 教科書が読めない子どもたち」の 続編です。 著者は科学者のようではありますが、本書 は教育学的な内容です。 要は、読解力を向上させることが教育の原 点であり、それをどのようにして実施して 行くか、が焦点になっています。 「なんだよ、今時の小・中学生は教科書に 書いてあることもきちんと理解できないの かよ」と思った人は、本書に載っている小 テストをやってみてください。 文章を読んで理解する、という行為がどれ 程大変であるのかが実感できます。 そして、読解力の重要性は十分に認識され ているにもかかわらず、それを教育の現場 に反映させることが出来ない行政の仕組み にも呆れてしまいます。 教育の本質を考えさせられる一冊です。
2投稿日: 2021.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りた本でざっと読了。著者の主張する内容も分かるし、真っ当なことを言ってるとは思う。課題はこれらの主張を教育現場(特に国語の授業)においてどのようにして具現化するか。 短文を正確に読むことが大事なのはとてもよく分かるが、実際教壇に立つと、ストーリー性のある教材に比べて生徒を惹きつけることが難しい。もちろん教員側の工夫次第であると思うが、教材自体の面白さも伴う必要がある。その意味ではどこかのページに書かれていた、無味乾燥な文章と併せてそのテーマと連動したストーリー性のある文章も読ませる、という方法はいいかもしれない。 親切な穴埋めプリントよりノートに書かせた方がよいというのは賛成。プリントを作るイコール良い先生、という等式は本当に成り立つのか、甚だ疑問。あえてノートテイクさせてるのに、プリント作った方がなんとなく手間がかかってる感じがして高評価が得られる、というのは問題だと思うんだけど。 ゆっくりでも正確に読むというのは確かに大切。これまでまとめたような本書の内容を、さりげなく生徒に伝えられるような授業が理想なんだろうな…。
0投稿日: 2021.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ新井紀子先生の「AI vs.教科書を読めない子どもたち」の続編。 今回は、どうしたら読解力をあげられるか、今の指導のどこが問題点かなども取り上げられている。 我が子が小学生の時、プリントの宿題が多かったのを思い出す。自分の時は、ひたすら漢字を書いたり、問題をノートに写したり大変だったのに、プリントはいいなぁと羨ましく感じていた。しかし、そのプリントが読解力低下の一因になっているとは!?何事も便利になるのはプラス面だけでなく、必ずマイナス面もあるのだと気付かされた。 読解力をアップさせる授業案を載っていて、ただ単元を教えるだけではなく、うまく仕掛けを散りばめられている。しかし、その仕掛けを考えるのは大変そうだ。きちんと読解力について理解していなければそういう授業は組み立てられない。 本書に出ていた、学校や市区に住んでいる子ども達は、今後良い授業を受けられるのかと思うと羨ましい限りだ。 本書の中でも書かれていたが、実際に子どもたちが勉強している様子をじっくり見ていると、一人一人の子どもがどのくらい力があるかはよく分かる。それなのに、多くの先生が、ある子どもが勉強に必要な基礎力がないことに気づいていなかったり、授業を理解出来ていない子を意図せず置き去りにしてしまったりするのは、先生の責任だけではなく、先生の数が少ないことも大きな原因じゃないかと思う。 授業を工夫することと同時に、子ども一人一人を見てあげられる先生の目を増やすことも必要だ。 リーディングスキルテスト体験版は楽しかった。うっかり勘違いしたような、読み落としたような気もする。でも、集中出来ていないこと=なんとなくわかったで解答してしまうことなのだ。私も読解力を鍛えねば。
1投稿日: 2021.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作に比較すると新しい見識が少なかった。 また著者独自の様々な認識が個人的には合わなかった。例えば子育てに対する考え方など。 バギーを使うことに関して否定的な著者ではあったが、それも果たしてどうだろうか。著者が子育てをした頃とは社会情勢は変わっており、子育ての方法も変わっている。本書では筆者は盛んに専門家の技術を馬鹿にしてはいけないと言うようなことを喧伝してはいたが、それは子育ておいても同様であると考える。著者は子育ての知識をアップデートできていない。それなのに子育てと言うわかりやすい、コメントしやすいことに関して意見を述べすぎている。 ネットに対して敵視しすぎているのも減点。著者の専門外である。
0投稿日: 2021.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ああ、確かにキーワード拾いしてる子ってあるあるだ。プリントが効いてたのか。論理読みはしんどいはず。頭を明け渡す行為だし。推論が苦手だと数学弱い、は確かにそうかもね。記述式の訂正の話は確かに納得。フェアで民主的な教育p303。p280からだけでもいいかも。
0投稿日: 2021.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作は未読。読解力に板書が有効のようだけれど、発達障害で特に書くことに難がある息子には難しい。ただ小学校中学年まで発達の偏りを見過ごされていたのはそれまで穴埋めプリントメインの授業だったということかもなと思った。 本書に載っているリーディングスキルテストを私が受けてみたところ、文と図表が対応しているか見極める力と、理数系の定義を理解する力が低いことがわかった。息子に関しては専門家の指導に任せるとして、まずは私の読解力をあげるために本の要約などを習慣づけたい。
0投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後まで興味深く読みました。 子供だけじゃなく大人にも問われる読解力の大切さをリーディングスキルテストを通して教えてくれる本。 小学校教育でドリルの穴埋めのようなキーワード暗記などが多くなり、自ら板書することも減っていることへ問題提起がすごくハッとさせられました。 たしかにドリル専用のノートを配布され、答えを書くのみの方法になっている小学校の宿題をみて、今はすごいなぁなんて感心していましたが、自分自身で板書し、文を理解して論理的に問題を解くことの大切さを気付かされました。 具体的な解決方法はないが、第9章を参考に子供へ関わっていきたいと思った。
0投稿日: 2021.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ借りたもの。 前著『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』( https://booklog.jp/item/1/4492762396 )で言及されなかった、AIにとって替わられない人材となるために、読解力を養う教育方法について。 個人的に興味深かったのは、人材育成云々よりも、冒頭に寄せられた意見で、文筆業をされている方たちから‘「物を書いて世に問うのだから批判さるのは覚悟している。けれども近年あまりに理不尽活不可解な非難が多くて議論にならない。よほど悪意があるのかと思っていたが、この本を読んで、『もしかするとそういう人たちは文章を読めていないのかもしれない』と思い始めた」(p.1)’というのが興味深かった。 私の場合、練習問題の中で、読む時に「こういう話か?」と構えて読んでしまい、短い文章で主語が省略されている時に読み間違えていた。 読解力とは、(相手の立場や書き手の思考などを)想像する力であり、自分の持っている知識を総動員し、かつ新しい知識を得てすり合わせる、更新する柔軟性であることを改めて思う。 AIに替わられない云々以前に、昨今言われるイノベーションを興す、デザイン思考的発想の根幹だった。 前著で紹介された東大ロボ――確率と統計を駆使したAI技術――では、東大に合格できなかった。理数系は解けても、意味を理解していないAI技術では、国語などが解けなかった。 では、そのAI技術に足りないベンチマークを「答えが書いてあるのに解くのが難しい不思議なテスト」リーディングスキルテスト(RST)の体験版も掲載。それらが検証するのは以下。 〈係り受け解析〉……文章の基本構造(主語・述語・目的語など)を把握する力 〈照応解決〉……指示代名詞が指すものや、省略された主語や目的語を把握する力 〈同義文判定〉……2つの文の意味が同一かどうかを判定する力 〈推論〉……小学6年生までに学校で習う基本的知識と日常生活から得られる常識を動員して文の意味を理解する、論理的に判断する力 〈イメージ同定〉……文章を図やグラフと比べて、内容が一致しているかどうか、文と非言語情報を正しく対応づける力 〈具体例同定〉……言葉の定義を読んでそれと合致する具体例を認識する力 そして上記RSTの得点から見える、理解力の傾向があるという。 理数系が苦手?〈前高後低型〉 自力でもっと伸ばせる〈全分野そこそこ型〉 中学生平均レベル〈全低型〉 知識で解いてしまう〈前低後高型〉:はずれ値① 読解力ばっちり〈すべて10点満点型〉:あずれ値② 後半は、それらを踏まえて弱点を知りどんなことに気を付けたら良いか、学習を促すかを記載。 それに基づくアクティブラーニングの方法など。 前著で不安にされた、“「推論」が正しくできない人ばかりが集まってグループディスカッションをすると「空気」に流され誤った回答を「正しい」と思ってしまう”事に対して、教師(進行役)がその場の人々の学力に合った指導・誘導をするように忠告。 小学生高学年までの、読解力を揚げる指導方法についてを紹介。 …次第に、日本の学校教育の問題点への言及になってゆく。中には国語教科書における執筆者のジェンダー論まで。 また、大学入試の予備校指導の一環で、確実に“点を取らせる”指導傾向があることを問題視。 理系も文系も分野が異なるが、根底にあるのはどちらも「物事を論理的に捉える」が本質だったはず。 どちらが優位であるというのはお門違いなのをしみじみ思う。
0投稿日: 2021.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ「AI vs 教科書が読めない子どもたち」と同時購入。 前作からハマりにハマって一夜読みしてしまった。 教育に関心がある自分にとっては、読解力の最重要性やAIに負けない能力の育て方が面白く、とても興味深かった。 前作を読んで「ほなどうしたら読解力ってあがるねん」と藁にもすがる思いでこの本を手に取り、ほかの評論的な本にはないくらい、多くの対策案が打ち出されていてスッキリした。「リーディングスキルテスト」の体験版が著書内に組み込まれており、実際に体験することで、自身のレベルや傾向、対策ルートが見えてくる。 このテストも本当に面白く、集中力をありったけ注いでも自信が持てない答えばかり。 特に印象的だったのは「マイノリティを認める」授業というもの。大多数が、その答えになるのではなく、少数派をも受け入れていく、それも答えになるんだという新発見と自己肯定感を得られる授業のあり方に大賛成。 はっきりと危機感を覚えるし、言語だけでなく、算数も理科も社会もみんな読解力だと理解ができる。
12投稿日: 2021.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログリーリングスキルテストのPR本かと思いきや、国語教育の在り方や公立学校の復権など「ふむふむ、なるほど」と共感。是非多くの学校関係者に手にしてほしい。AIに惹かれて手にしたが、そこは残念!?
1投稿日: 2021.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
AIを前提として再編される2030年代を生き残るために、正確に評価するためのベンチマークとしての大学入試にチャレンジした東ロボ。確率と統計から深層学習するには、同じ形式で、単純で一貫性が担保され、広範囲に難易度が分布している問題が数千必要。質の良いベンチマークの構築が課題。そうして開発したReading Skills Test. ①係受解析 ②照応解決 ③同義文判定 ④推論 ⑤イメージ同定 ⑥具体例同定 読めるとは、識字、語彙、構文の把握、機能語の正確性。キーワード群で理解しようとするAI読みでは、抽象度が上がると正確に読むのが難しい。暗記量と正確さではAIが勝る。係り受けや文の構造を解析し、意味を理解する論理国語の必要性。暗記よりも論理で考える体験を。読解力が上がり、自学自習ができれば、的確な文を書け、生産性が上がり、自己肯定感も高まる。 この本では、RSTのサンプルテストを受験し、自分の読解タイプの分析が可能。試験の内容や妥当性、活用法を述べた本。
1投稿日: 2021.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作の後半の内容がより深く、進化していた。 リーディングスキルテストの結果からタイプ別診断ができたり、小中学校での授業の提案があったり、前作で不安を覚えた人への具体的なアプローチがあったのがよかった。 現代の日本人は読解力がない、と言うのは簡単かもしれないけど、その打開策をここまで提示できるのは著者が日々教育の現場に関わっているからだろう。 ただの評論家なら批評だけして終わっていると思うので。。
0投稿日: 2021.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで、私は文章を読めてきたのでしょうか?本書を読み、サンプルテストを実施してみると、きちんと理解できていない文書がいくつかあることがわかります。 子供が学ぶ上で、どのような方法でアプローチすれば、読解力向上につながるかまで提案しています。大人なあなたも結構読めていないかもしれませんよ。 読むということは、どういうことなのか答えられますか? 私は、識字=読むだと思っていました。でも、これだけでは文書の意味を理解できることにはなっていないこともあるのです。気になった方は、本書を読んでみましょう。 本書に記載されているテストを受けた私の結果は(通勤電車で実施しました)前高後低型でした。 係り受け、照応解決、同義判定6点以上、推論、イメージ同定、具体例同定のうち2つ以上が3点以下。理数系が苦手で情報量過多で論理力不足なのだそうだ。だいぶ改善してきてはいるものの、若かりし頃の自分はまさに論理力不足だったと思うなぁ。 ゆっくりでも、正確に理解することを心がけるというような、実際に読解力向上を経験した大人の体験談も第10章にあるので参考になります。 読解力が向上することで、仕事の質も格段に向上することは、直感的にわかりますよね。日本の国力にもつながる基本的な能力と言える「読む」という行為の大切さがよくわかりました。
1投稿日: 2021.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』続編。 リーディングスキルテスト(RST)の紹介と、実際のテストの体験版。読解力を高めるための授業の対案と、子ども達への接し方(育て方)。これが正解かどうか、科学的に証明はされない(それはその通りだ)けれども、統計的に見て、効果があるのでは?というスタンス。こういう部分が、とても信頼できる。 個人的に印象深かったのは、板書の必要性の説明。なるほど、な。反対に大人の読解力はあがるのか?についての体験談は、申し訳ないが、特殊な例すぎて参考にはならなかった。 RST、我が子の学校でも実施してほしいな、と思った。
0投稿日: 2021.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上司の勧めで前作とこちらを読了。 前作ではいかに現代人の読解力が低下しているかを論理立てて説明されていた。以前後輩に指示をしたところ指示通りできなかったことがあり、読解力不足により意味を理解していなかったのかもしれないとハッとした。しかしながら前作では解決策は示されていなかった。 本作では読解力を測るリーディングスキルテスト体験版を経たタイプ別診断、子供の教育方法、大人の読解力改善方法などが示されており、前作より充実した内容に感じた。印象に残った点は以下の通り。 ・現代の授業は穴埋めプリントが中心であり、板書する機会が減っていることが読解力低下の原因になっていることが想定される ・公立小学校は多様なバッググラウンドの子供が集まっており、多様性を知るには良い環境 ・少子化、地方の衰退などの社会課題を解決するには、「多様な人材」が必要。親の年収が1500万を超え、「就学援助」や「無母語児」に接したことがなく、最も近いコンビニまで10キロ以上あり、過疎のため鉄道が廃止された地域などは見たことも聞いたこともないようなエリート集団に、この国の複雑な課題を解決できる気はしない。 ・読書は速読よりも、一文一文丁寧に意味を理解して読む深読をすべき。地道に続けることにより、大人でも読解力はあげられる。
0投稿日: 2021.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ読解力をつけるためには、どうしたらいいのか、想定されたアドバイスがあってよかった。子育てする上でも参考になるかも。 自分もテストで間違えたりしたので、速読しちゃってちゃんと読めてないんだろうな。一語一語丁寧に文章が読めるように、気をつけていきたい。
0投稿日: 2021.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ☆読解力はその人の能力を決める 教科書を読めていますか?という質問に多くの人は「はい」と答える。しかし実は「読めてる気」になっている場合がほとんどだ。自分も時々さらっと文章を流し読みして分かった気になる事があり、高校の時も教科書もしっかり読み切ることが出来ていなかったと気がついた。それにより、受験も暗記に時間を費やしてしまっていたのかもしれない。RST(リーディングスキルテスト)は自分の読解における苦手分野を教えてくれる。RSTによって読解力を早い段階で測り、自分にあった読解力向上方を実践して行くことで、今まで読めなかった文章や書けなかった物が自分の力で出来るようになる。そして「読んだ気になっている」を防ぐ。それは勉強だけでなく仕事の幅を広げることにも繋がる。読解力不足は子供だけでなく、大人にも言える。そして、大人になっても読解力は上げられることが分かっている。1度RSTを受験して自分の読解力を知り、これからの自分のインプット・アウトプット、将来の仕事に活かしていきたい。
0投稿日: 2021.02.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ全ての教員と親は読んだ方がいい ◆前作「AI vs教科書を読めない子どもたち」を読んだ後に読みました。AIにはできない能力=読解力を養うための、具体的な教育の方法が提案されており、納得できます。 •文を速く読むのではなくて、正確に読むことが読解力をあげる練習となる •小学校を卒業するまでに板書をリアルタイム写せるようにする •穴埋めプリントはなるべく使わない。穴埋めプリントは小学校の内に卒業する ◆かなり具体的な授業の進め方の提案がされており、私もこういう授業を受けたかったなと思うものでした。今教育に関わる方たちにはぜひとも取り入れてもらいたいです。そして保護者も、こういう視点で教育を進めるんだと、同じ認識を持っていたいです。 ◆私は幼児の親ですが、小学生以上のお子さんを持つ方の方がすぐに実践できそう。「幼児でした方がいいこと」については、他の育児本と同じようなことが書いてありました。今はこれでいいんだなと安心しました。(絵本を繰り返し読む、自然に接する時間を持つ、など) ◆自己顕示がすごいというようなレビューを見たのですが、たしかにそんな感じの文章もありますが、面白いな〜と思って読んでいました。特に不快ではなかったです。
0投稿日: 2021.01.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ文筆行をしていると、近年あまりにも理不尽かつ不可解な非難が多くて議論にならない。「もしかしてそういう人は文章が正しく読めていないのかもしれない」と最近思い始めた。 語彙は、生活環境に大きく影響してくると言われる。 日本の子供の相対的貧困率は7人に1人に達した。一人親の家庭に限定すると5割を越えている。 貧困により、高学歴家庭と貧困家庭で育った子供は日常聞く語数の差がのべ3000万語と言われている。小学校低学年は学校よりも家庭で過ごす時間の方が長いので、この語彙格差は学校教育ではなかなか埋まらない。 自覚と時間と心の余裕がある親とそうでない親では、母語のシャワーを浴びさせる機会格差があり、その格差は広がる一方である。 そのために「ゼロ歳から保育園に通う権利、すべての小学生は学童保育に通う権利」を与えた方がいいと私は考える。 日本の制度には悪い面だけではなくいい面もある。それは6歳から近所の公立小学校に通うことである。公立小学校は社会の縮図であり、世の中の多様な背景や異なる能力が人にはあることを学ぶ。 これは非常にいい影響を子供に与える。 私たちは社会という一つの船に乗っているので、読解力が劣る人を「自己責任」として放置すると企業や社会全体の生産性が上がらず、その人々がAIに代替され低賃金の職を奪い合うようになったら、格差拡大や人口減少がさらに進み日本は持続可能ではなくなる。 海外はさらに深刻で、日本は世界でも稀に見る「よく読める国民」と言われているのである。 この本で取り上げられているRSTテストは読解力を図るために作られたものである。 大企業が新人研修や採用の時に使い、暗記やAOで高偏差値の大学に入った実は読解力の低い人材を避けるためにも利用されている。これは今後増えていくことが容易に想像できる。 試しにRSTテストを受けて、点数があまりよくなかった人(小中学生だけでなく、大人にも多い)はAI読み(語彙を繋げて読むだけ)」をしている可能性がある。 政府は毎年25万人(全体の4分の1)のAI人材を輩出しようとしているが、シンプルな文章の差さえ読み分けられない人が、AIに勝てるわけもない(暗記などはAIの得意分野のため)。 RSTは正しい文章が読めずにいる生徒を早期に発見し、どんな教科書も正しく読めるようにする事を保証する公教育の目指すべき取り組みである。 ではどんな人が読解力に乏しいのか? ひとつの特徴は文字を書くスピードである。書く人が遅い人は語単位で写すことができず、文字単位で写しているからである。 また教育会にも問題はある。現在コピー機やワークシートの多用により多くの子供が書くという大切な行為が欠如している。 それにより文章の意味を考える機会を奪っているのである。 「意味がわかって読める」ために特に幼児期に以下のことを意識するといい。 ①身近な大人同士の長い会話を聞く機会を増やすこと ②同世代(少し年上も)の子供と接する機会を確保すること ③身近な大人が繰り返し(特にこれが大事)絵本を読み聞かせること 小学校低学年~高学年は省略 人間の最も優れているところは意味を理解できることと怠ける天才であることだ。外界や身近な大人に高い関心を持つ幼少期に機会を与えれば小学校低学年までの学習内容はそれほど難しくない。この時期までに暗記という成功体験をなるべく積ませないことが、その後の成長に大きく影響してくる。 多くの子供が基礎的・凡庸的読解力を身につけ、塾や年収での格差を失くし、地方の公立高校が名高い大学に入学できるようになることがこの日本のより良い未来のための糸口なのである。 就学支援・無母語児に接したことがなく、コンビニまで10キロ以上あり、過疎のため鉄道が廃止された地域などみたことも聞いたこともないエリート集団がこの国の複雑な課題を解決できるとは思えない。 大人が読解力を身に付けるための魔法のような処方箋はないが、普段の生活の中でゆっくりでも正確に意味を理解しようと心がけることがまず第一歩である。 そして読解力向上により、①仕事の質(文章を書くスピード)、②仕事の幅(馴染みのない文章も正確に意味を読み取れる)、③発表する際の心理的ハードル(どの文なら相手に伝わるかわかるため)の3つのメリットがある。 一人一人が基礎的・凡庸的読解力を身に付け、AIと共に共存する世界が来ることを私は願う。
0投稿日: 2021.01.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書に収録されている体験版RSTを本気で解いてみたが、理数系が苦手の「前高後低型」だった。私自身は数学が苦手であるが、その理由は「読解力の無さ」にあるのかもしれない。 特に「定義」の読み取りが苦手だったので、定義の文章は意識的に時間をかけて読むなど、対策をしなければならないと思う。
0投稿日: 2020.12.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの国語力をつけるにはどうすれば良いか?と言う思いでこの本を手に取ったが、読み進めるうちに自分の読解力は大丈夫なのかと言う視点になった。案の定、RST体験のテスト結果は思ったより良くなかった。RSTで問われるような問題がスムーズに解けないとあらゆる学問や日常生活で苦労することを実感し、今後子どもの読解力を養うにはどうすれば良いか考えるきっかけになった。
0投稿日: 2020.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログAIに負けないためにどうしたら良いのかという視点で読み進めていたけれど、AIに勝つこと以上に日本人のなかでの読解力の差が大きいことに驚いた。 自分自身、文章を書くのが苦手なのだけれど、それも読解力と相関することを知った。 文章を読み進めるときにAIと同じようなキーワード読みをするのだけれど、決して早く読めるから良いわけでもなかった。「てにをは」や係受けなどを認識せずに、自分の頭の中で勝手に組み立てていただけで、真に書いてある意図を組みとることをサボっていただけだった。 早く情報を手に入れたいときはキーワード読みでも仕方ないけれど、自分の読解力をあげるためにも一文一文ゆっくり読む時間もあえて作っていきたい。 個人的な話はこれくらいにして、本書でも書かれていたが、この読解力を磨く訓練は小学校でも中学校でも教わっていないことが多いため、能力のばらつきが大きい。 学校教育で教えられないのに、社会生活において非常に重要なこの能力を、どうやったら高められるか? それを本気で考えて向き合っている著者の思いと熱量に心から共感した。 会社でおこるコミュニケーションエラーも、このリーディングスキルのなさが原因なのかもしれないので、ぜひ会社内でも検討していきたい。
0投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読解力が身についていないことで苦労する人たちがいる。 身につける方法は少し例示されているが、今後の研究に期待したい。 しかし、読解力を計るためのRSTなのに、何度も受験させれば読解力が身に付くと勘違いしている教育者のくだりで絶望した。 そりゃこんなのが指導者では読解力は身につかんだろう。
0投稿日: 2020.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいろいろ批判はありますが、読解力を育てるにはどうしたら良いか、というところまで少し分かった気がしました。続編に期待したいです。
0投稿日: 2020.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作に引き続き本当に読んでよかったと思わされる一冊でした。また、RSTは自分自身で解いてみて、思いのほか間違えてしまうところが多く、ショックを受けました。 現在指導している生徒たちの中にもリーディングスキルが低いと言わざるを得ない子たちが多いです。 そのことに対して常日頃から悩み、結果として穴埋めプリントや書き写し、暗記に近い教材を提供してしまっていましたが、今後は考えを改め、彼らに対して問題文をどのように読むのか指導しなければいけないと痛感しました。 一方、終盤部分で、新井さんが菅原さんに対して、読み方を開陳していただけ。と明らかにされ、反省されていた部分を読み、自分もそうなってはならない。と思い至りました。 幸い私は読解力の部分で悩まされることは無かったので、「読めない」という状態があまりわかりません。 まずはゆっくりと一文一文、何が書いてあるのかを生徒に対して詳らかにしつつ問題に取り組む。焦る気持ちが出てくる時期ではあるものの、彼らのこれからを考えればそうは言っていられない。まずは着実に”文章を読む”ということを指導していくことこそが今後の私の使命だと改めて感じました。 また、そのためには教育の科学研究所、そして新井さんの更なる研究の発展に期待し、可能であらば何かしらでお力になれればと思っております。とても良い一冊でした。
0投稿日: 2020.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ続編! RSTテストを実際にやってみた。 思ったよりできたが、これが解けない人が多く、教科書をきちんと読めない子供達も数多くいることがわかった。 読解力をつけるための実践が幼小中と載ってるので、是非実践して読解力あげてほしいと思った。 もちろん大人が読解力を上げる方法も載っている。
4投稿日: 2020.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読む力をつけるためには、教える方も学ぶ方も、手間と時間をかける必要があるということがよく理解できた。プレゼン用ソフトで作った資料を配付して、スクリーンとプロジェクターを使って説明するというスタイルは、とくに小学校には向いていないということだろう。 「おわりに」に、著者の生き方がはっきり書いてある。 この本は、明日から知り合いに勧めよう。
0投稿日: 2020.11.11 powered by ブクログ
powered by ブクログAIの限界 AIに深層学習させるため、読解力を問うようなベンチマークを構築するのは容易ではない。 AIが得意とするのはパターンマッチや知識。逆に、常識に基づく推論やイメージ同定(図やグラフと文の整合性を問う問題)、具体例同定は苦手。 ところが、このAIが苦手とする問題は、人間も苦手ということが分かった。 文脈、行間を正確に把握するためには、文の構造を正しく把握したり、「機能語」という、「と」「のとき」「に」などの言葉を理解しなければならない。 この機能語が読めないと、教科書の意味を理解できない。 大企業ホワイトカラーは、係り受け、照応解決、同義文判定6点以上、推論、イメージ同定、具体例同定が低い。 一行一行確実に読まずに、単語を拾い読みするタイプ。論理と定義を理解する力が不十分。 この読解力テストと、高校の偏差値に強い相関関係があることが分かった。事実を正確に読む能力が、複雑な大学受験のテストの出来にも直結している。 しかし、東大を毎年数百人排出する高校でさえ、具体例同定は50%しか正解していない。 基礎的・汎用的読解力が身についているか否かで、大学受験の難易度が変わる。入試は読解力を求めているのに、読解力が不足している人は、(AIと同じように)暗記に走らざるを得ないのだ。 日本の小学校は世界一生徒の意見を聞き、班活動をしているアクティブラーニング先進国。 しかし、何故アクティブラーニング先進国で、教科書を読めずに卒業する子が増えているのか? それは、「一人も取りこぼさずに学ばせるため、の仕組みづくり」のせいである。端的に言えば、アクティブラーニング教育のせいである。 科学分野においては正解は一つしかない。それを間違ったときに、「みんな違ってみんないい」として片付けてはいけない。本来であれば、「間違えても恥ずかしくない、間違えを繰り返して正解にたどり着くことはいいこと」という教育をしなければならない。 また、アクティブラーニングの影響で黒板を書写させる割合が減り、穴埋めプリントの配布やパワポが増えた。これにより、「単語や重要箇所をピンポイントで覚える」勉強が、子供の読解力と文章力を妨げている。 国語の目的は、「生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと」であり、小説を読んで作者の気持ちに答えたり、語彙力を身につけることではない。 【子供のリーディングスキルを向上させるためには】 母国語のシャワーと、豊かな自然からの学び、言葉と論理で説明できる能力、が必要。大切なのは、暗記のほうが楽だからといって、暗記に逃げないこと。 【Edtech】 AIは、生徒の間違え方に応じて、ドリルの問題や穴埋め問題を最適化することができるが、AIは文章題や証明は採点できない。相対や客観や抽象を理解できない生徒に、それが何を意味するかをAIは教えられない。 教育✕テクノロジーは、授業データの分析、外国語の子どもへの翻訳程度に留めるべき。 地地方公立出身者という多様な人材を確保し、地方に問題を抱えた日本を再生するためにも、基礎的読解力を上げ、地頭の底上げをしなければならない。 【大人が読解力を上げるために】 早く読まない。ゆっくり、正確に意味を理解しようと心がける。 【まとめ】 ①AIが苦手とするのは推論・同定といった「読解力」だが、それは人間も苦手とする分野 AIは正誤判定問題が得意である。それは、文中に書かれた単語と問題文を見比べ、相関関係が強ければ〇、と機械的に判断しているからだ。これは、深層学習によるパターン分析の結果として正解しているにすぎない。問題に応えられても、意味を理解しているわけではないのだ。 そのため、図やグラフを見て、「それが意味するところ」を答えさせる問題は大の苦手である。同様に、文外における一般常識に照らし合わせて、文脈を読むことも苦手とする。 しかし、意味問題が苦手なのは人間も同じであった。人間の回答方法が「AI化している」という事実が明らかになったのだ。 ②意味問題を苦手な人間が多い理由は、文の構造を把握できていないから 意味問題を解くうえで大切なことは、文の構造や、「と」「のとき」「に」などの機能語をきちんと理解しているかである。 これが身についていなければ、短文・長文における修飾語-被修飾語の対応箇所や、意味段落のつながりが理解できなくなる。 そして、この構造把握を理解できない人が多く、これが教科書を読めないことにつながっているのだ。 教科書が読めないということは、物事を考える上での土台が出来ていないということである。こうした子ども達が大人になったとき、ビジネスシーンにおいてメールや仕様書が理解できない人間になってしまう。 ③読解力を向上させるためには、国語のカリキュラムの見直しが必要 人生を送るうえで必要不可欠な「読解力」を向上させるには、小学・中学教育において「文の書き写し」や、「文の構造を論理的に把握できること」が大切になる。 昨今、アクティブラーニングの浸透によって、グループディスカッションなどの議論型教育が、授業に取り入れられるようになった。同時に、時間の節約のために板書をさせる回数が減り、穴埋めプリントを配布することが増えた。 穴埋めプリントは、文の構造把握の妨げになる。単語と答えを短絡的に結びつけることにつながり、「暗記」によって得点を取ろうとすることを助長するからだ。 大切なのは、正しい意味の構造を、順序立てて表現できるようになることである。 そのためには、聞かれている文の意味と答えが合致する理由を、言葉と論理で説明できる能力が必要になるのだ。 感想 文中で一番衝撃的だったのは、この現象を引き起こした原因の一端が、アクティブラーニングにあったことだ。 一義的な答えよりも多種多様な考えのほうが大切という思想は、アイデアの創発フェイズにおいては有用であるだろう。 では、そのアイデアを出すための基礎能力はどうすればいいのか? 物事を考えるうえでは、どうしても基本的な読解力が身についていなければならない。アイデアは天から降ってくるものではなく、地の知識と推論から帰納・演繹的に導かれるものであるからだ。 アクティブ・ラーニングでは、多様なアイデアを重んじるために、グループディスカッションを行うことが多い。しかし裏を返せば、その場の空気感やフィーリングに合わせて、自分の答えを調整することにもつながる。彼らに本当に必要なのは創発ではなく、問題認識を正しく理解し、論理的に記述できる能力なのだ。 教育現場においては、「自分で考えられない段階の子どもがいる」ということを、意識しなければならない。そうした子たちに確実に読解力を身に着けるための学習システムを、指導要領の土台に置かなければならないのだ。
0投稿日: 2020.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2020/09/04:読了 リーディングスキルテスト(RST)が何なのか、どうしてこういうものを作ったのか、がよく分かった。 ・問題を作ること自体が、大切なノウハウ ・設問の書き方自体で、回答率が違ってくる ・短文の問題がかなり蓄積されており、それ自体が資産 などなど、興味深い内容であった。 リーディングスキルを扱うのであれば、持っておくべきホンダと思った。
0投稿日: 2020.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作に続いてとても勉強になった。 読解力が重要であるということには強く同意。 AIには読解力は無理だと思う。
0投稿日: 2020.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど、と思うところが多くあった。 特に著者が「電子黒板もデジタル教科書も小学校では無理に入れなくてよいと考えています。特にEdTechには反対です。」と書いている点も印象的だ。 読解力とは何か、何に由来して鍛えられるのかについての議論は説得力もあり、参考になるところが多かった。
0投稿日: 2020.08.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ教科書を読めているかは、自分自身では分からないことに驚かされた。私も作者の指摘のとおり日本の国語教育において文学作品に偏重していると感じていた。 自分自身を振り返ってみると、新入社員になりたての頃、文章を書くのに時間がかかり、苦手であったことを思い出した。学校教育において、理工系の教科書の読み方や文章の書き方をもっと重視して欲しい。
0投稿日: 2020.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ読解力を伸ばすにはどうしたらよいか、ということが、 前作の『教科書を読めない子供たち』よりも詳細に書かれている。 黒板を写すことがなくなってきたことの弊害が読解力低下につながっているのでは、という見解は面白い。
0投稿日: 2020.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構衝撃でした。字が読めて語彙量があっても、文章を正しく「読めて」いない人が(私も含めて)結構いるという事実。 この本で「読解力」を測れるRST(リーディングスキルテスト)の簡易版を受けることができ、自分の読解力が測れるのは良いです。また、子供を持つ親にもおすすめです。知っていて損はない知識です。 特に、キーワードから判断する穴埋め問題では「読解力」は身につかないこと、ノートの板書が実は効果があることなども驚きであった。 この本を読んで自分なりの次のアクションとしては、本の感想などを要約してアウトプットすること。子供との会話時間を増やそうと思いました。
1投稿日: 2020.08.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読むことが疎かになり過ぎている。 読むために、じっくり考え理解して読む。 そのサイクルを自分のペースで回していく事が大切。
0投稿日: 2020.07.30 powered by ブクログ
powered by ブクログAIが正しく読めないことがある。 それは同義文判定、推論、イメージ同定、具体例同定などである。 ところがAIにとって難しい事は多くの小中高生生にとっても難しく、また大人にも難しいことがわかった。 正しく読むと言う事はなかなか難しいことである。 意味がわかっているためには、幼児のうちから母語のシャワーをあげたり、インターネットから切り離されてリアルなテレビの世界と接したり、歩いたり走ったり子供と喧嘩したり仲直りしたりする機会である。 社会の多様性を知ることも子供にとっては大切である。
0投稿日: 2020.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ前著『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』と比較して、どうしたら読解力が上がるのかに紙面の多くを割かれており、今回の書籍ではAIそのものについてはあまり触れられていなかった。 読解力と偏差値に相関があったのは驚くべき事実だと思う。 本書の中にある、リーディングスキルテストを受けてみて、結果はそんなに悪くなかったので、安心していたが、実際のテストでは約30分程で答えなければならないということで、私の場合、実際にはもっと時間が掛かったのと、あれだけの分量の問題に回答するのにヘトヘトになってしまった。 私自身の読解力を憂えたが、大人になってからでも読解力を向上させることができるという文面に救われた。 読解力向上の為に、じっくり意味を理解しながら噛み砕いて文章を読むことを今後はもっと意識していきたいと思った。 ただ、私の場合、人よりも読むスピードが遅いので、いかに読解力を向上させつつ、読むスピードを上げることができるかが分かるとより良いなと思った。 読解力向上に近道はないと思うので、地道にやっていこうと思う。
0投稿日: 2020.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ実践的ではないが AIに負けないために必要な能力について 漠然としたイメージはできた。 著者の提案する望ましい教育については アイデアの羅列の段階と見受ける。 今後、コンセプトを先鋭化して アイデアを体系的に整理して 具体的な教育方法に落とし込んで頂けたらありがたい。
0投稿日: 2020.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ【文章】 とても読み易い 【ハマり】 ★★★★・ 【気付き】 ★★★★・ 文章を読む能力を身につける鍵は学校教育にある。 現代の学生の文章を読む能力が低いのは、学校教育の質が低下したせいなのか、それとも、測定する前の時代から学生の文章を読む能力は低いままだったのか。 もし、後者だったなら、これまでは文章を読む能力が不十分であっても、それなりにやってこれていたということか。 今後、システムが自動化していくにつれ、これまでのようにいかなくなる時代がくるのかもしれない。
0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ読解力向上のために、どうしたらよいのか? 小学校や中学校だけでなく、自分はどんな読み能力が有るのか?無いのか? RST(リーディングスキルテスト)でそれを明らかにする。 で、成人読者を想定した「体験版」をやってみた。 いや別に簡単じゃん、と、、。答え合わせして吃驚。 照応、推論、図形イメージは高得点を出せたが、 文の基本構造把握力はビジネスマンとして、かろうじて合格。 具体例同定(言葉の定義と合致する具体例を認識)は惨憺たる有様。 いや、これは当たってる。 間違いも、よくやるよなあ、こういう間違いって感じ。 自分の強味と弱点がよくわかる。 実に優れたテストだと認識した。 すいません、それ以外は飛ばしました。
7投稿日: 2020.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分も、読解力が壊滅的なのかもしれない。 そう思うと、この本を読まずにはいられなくなります。 著者の中にあるお試し版のRST(リーディングスキルテスト)は、かなり面白いです。 本著では、「では、どうしたら読解力を高められるか」まで解説されており、著者の考えや、RSTの傾向を踏まえた課題などが丁寧に説明されています。 特に、オセロを用いた講座は、「どうしたら正確に物事を伝えられるか」について、非常にわかりやすく設計されていて感動しました。
0投稿日: 2020.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ前書『AI VS. 教科書が読めない子供たち』から1年半。今後の教育はこうであって欲しいという著者の思い、そして、大人でも必要とするリーディングスキルについて詳しく書かれている。特に、現代の教育では、穴埋めプリント学習で、生徒のリーディングスキルが向上に繋がらないものばかりで、教科書の内容を理解して読めていない生徒が多い。また、偏差値とリーディングスキルは正の相関があり、大人でも思いあたる節がいくつも書かれている。私もリーディングスキルテストを解いてみたが、思った以上に文章を読めていないことを痛感した。教育者だけではなく、ビジネスマンにも役立つ内容がてんこ盛りの一冊。
0投稿日: 2020.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログAIを進化させて大学受験で東大に挑むプロジェクト。 そこから派生して出てきたのがこのリーディングスキルテストだ。 つまり、いくらAIを進化させても、大学受験で超えられない壁が見つかった。 これがいわゆる「文章の理解」だったりするのだ。 AIは決して文章を理解している訳ではない。 やっていることは「●●の言葉の後には××が来る」などの文字羅列を統計的に解析しているだけだ。 だから、決して意味を理解している訳ではない。 この事で逆に筆者は気が付いた。 「人間は本当に文章を理解しているのか?」 そこで生まれたのがまさに「読解力」(リーディングスキルテスト=RST)の概念だ。 人間は言葉の意味と問題文を理解し、思考し、回答する。 そして「そもそも問題文を正しく読めてない人が案外多い」ことに気が付いてしまう。 もちろん自分は東大の教授なのだから、RST値も高いだろう。 自分は当たり前でも、偏差値的に低い学校や、小中学生ではどうなのか? とにかく問題文が理解できないという状況を脱しないと、問題そのものを解くことは絶対に出来ないのだから、学力など上がるはずもない。 これは社会人になっても全く同じことだ。 基本的な読解力がなければ、契約書も読めなければ、そもそもメールのやりとりも出来ない。 今の会社の社員で、メールの文章がメチャクチャな人がいる。 ちゃんと読もうとすると何が書いてあるのかサッパリ分からない。 (もちろんサラッと読んでも、文章がメチャクチャで理解出来ない) 文章が読めない人が、文章を書ける訳がない。 それも結構な役職の人がこれだから、衝撃の事実なのだ。 基本的なコミュニケーションのズレが生じているのも、これらが原因なのだろう。 とにかく「文章を正しくきちんと読む」こと。 本当に大事なスキルなのだ。 (2019/9/15)
0投稿日: 2020.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ2016年に出版され話題となった前作「AIvs教科書を読めない子供たち」の続編。自分は前作は読んでいないが、それでも十分にAI開発の現状と、作者が考える現在の教育に対する危機感を共有できる。 著者の新井紀子さんは「ロボットは東大に入れるか」プロジェクトのディレクターで、このプロジェクトの存在自体は自分も知っていたし、そのAIが中堅私大に合格できる成績を出したというニュースまでは聞いていた。 著者はAI研究の中で、AIにとって今しばらくは不可能で人間にこそ利点がある能力が"読解力"であると気づいたのだろう、そしてその読解力を調査してみたところ、全国の学生たちの読解力が驚くほどに低かったことを発見した。(おそらくここまでが前作の内容?) そこで著者は、読解力を測る指標の作成に乗り出す、それが本書で説明されているRST(リーディングスキルテスト)である。本書には、そのテストの体験版が載せてあり、問題の意図、そして点数と人物のファイリングについて説明されており非常に面白い。 またこのテストを受けた高校生のスコアと学校の偏差値に強い相関があるというのはとても興味深い。 後半に載っている著者が考える読解力を高めるための教育論も含蓄があり多くの方に一読をオススメする。
0投稿日: 2020.05.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書にはRST(リーディングスキルテスト)の体験版が収録されており、試しにやってみるといくつか誤答してしまいました。先入観や思い込みを捨てて注意深く読むように心がけたいです。 本書では、児童生徒の読解力低下の背景として、穴埋めプリントの多用が指摘されていました。穴埋めプリントは学習補助的に使用することとし、小学生のうちにそれを「卒業」させるべきである、また、板書をしっかりと書き写す力を身に付けさせるべきとのこと。 日本史は世間では暗記科目とされているけど、私自身は高校生の頃、必死に暗記した記憶はなく、ただひたすら教科書を読み、それで高得点を取ることができていました。やはり「文章で理解」しようと努めたことがとても良かったのだと思います。しかし、いまの私の授業はまさに「要点プリント」という名の穴埋めプリントに頼っており、生徒たちは歴史を「単語で暗記」してしまっているように感じます。今後は生徒たちにしっかりと教科書を読ませることを意識して、その要旨をノートに記述させたり、口頭で説明させたりするような活動を重視していきたいと考えています。
1投稿日: 2020.05.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ「推論が苦手だと、考えるのではなく、経験と空気に頼る」 「読み方がわかると読んでわかるは似て非なる」 「テクノロジーによって人がある種のスキルを失うとき、その喪失は社会現象として一気に起こる」
0投稿日: 2020.05.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ勉強になる。そして自分もちゃんと読めているのか、こうしてレビューを書こうにもとっても不安! 小中学校が現在どんな授業をしているのか、全然知らなかったので穴埋めプリントが多いということにもびっくり。授業形式が変わっているんじゃ保護者個人で打てる手は少ないよなぁ。 大学時代、板書をデジカメで写して満足気にしていたクラスメートもいたが、確かに彼の成績は特別良くなかったはず。正確な板書の大切さはいま大学に通う学生たちにも広く周知すべきなのでは。 スマホさわる時間を改めて見直して、子供に話しかけたり公園に連れて行く時間を増やそう。とりあえず私に出来ることはそれくらいかなぁ。
0投稿日: 2020.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ一作目のインパクトはない。3時間で読めた。 読解問題が載っているのだが、常識にとらわれず=社会言語学的に普通の読み方をせずに読まなければならない問題と、常識を使って読まなければならない問題があって、困る。一方の基準からは正確な書き方ができていない問題文が存在することになる。とても賢くて、確実に正しい問題を作っていて、曖昧性がなく、難しい問題となっていると、そう信じている人が作成した問題だと考えると問題はうまく解けるだろう。 で、逐語的に意味をとりながら読むことはAIにはできない読みなのだろうか。タイトルにうたうなら、逐次その確認をしてほしかった。 後半の教育論には根拠は示されず、教育学、教育方法学、教育心理学の成果は引用されず、自分の認識で書いていた。電子書籍版には引用文献、参考文献の欄がそもそもないのだけど、これでよいのだろうか。 ただ、著者のつくったnet commonsを便利に使わせてもらっていたのに気づけてよかった。
0投稿日: 2020.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ子育て世代に最後の方だけでも読んで欲しい。 教員は読んだ方がいい。 (教材準備でついやってしまうことも書いてある)
2投稿日: 2020.04.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ私は本を読むのが遅い。 声に出して読んでいる感じ。 というか、頭の中で誰かが読んでいる声を一字一句もらさず聞いている感じだ。 速く読みたくて速読のトレーニングをしたこともある。 しかし、自分には合わないとあきらめた。 正直に言うと合わないのではなく、どうしても速読ができなかったのだがそれで良かったようだ。 本書のリーディングスキルテストは70点満点の62点だった(予想外の出来)。 ゆっくりでも正確に読むことが大切であることを再認識した。 本書は読解力を付けるために、幼児期、小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、で何に気を付けどのように導いていけば良いかを具体的に示している。 個人的にかなり納得できる内容なので、幼小中学校の先生にはぜひ読んで実践して貰いたいと思う。 子育て中の人にもお勧めです。 タイトルのAIに負ける負けないは関係なく自力を身につけるのに役に立つに違いありません。 4歳までは読解力以前の知育だと考えますので、池谷裕二さんの「パパは脳研究者 子どもを育てる脳科学」なんかも併せて読むと参考になるかと思います。
23投稿日: 2020.04.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
待望の第二弾。 第一弾ではAIの限界、でも子供が教科書を読めておらず、このままではAIでは及ばない領域に人間も及ばなくなってしまう、という衝撃な内容を学んだ。 第二弾は第一弾を受けて、じゃあどうすればAIに負けない読解力の高い子供を育てられるか、という内容で非常に興味深く読ませて頂きました。 オセロの課題は早速家で子供(小学校低学年)にやってみました。大変興味を示していました。 また、主語+述語、にどんどん形容詞や副詞を足して行く遊びなどはドライブ中の退屈な時間にも有効です。 最後に小学校低学年からのおすすめの教育方針も丁寧にまとめてくださっており、しっかり学んで実践したいと思いました。
0投稿日: 2020.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの能力を高めるだけの本だと思っていたら、リーディングスキルテストRSTの説明で読解力を養うための本であった。 How to ではない。テストの作成方法についても丁寧に書かれているので、論文でテストを作成しようとする学生にも役立つ。 それだけではなく、小学校での学習の例が3つあるので、教育実習にも役立つであろう。 大人の読解力の育成についても菅原氏の説明があるので、ゆっくりとリーディングテストについて丁寧に学習することで、読解力もつくであろう。試みにこの本にあるテストについて解説を読みながら丁寧に読んでみるといい。 小学校低学年中学年高学年の読解力の育て方を書いていたので中学校高等学校でも書かれることを望む。ただし高校での国語の分析もしている。これは高校の国語の教員免許の問題点もある。免許が開放性のために、文学部では時代ごとの古典の専門家が大学教員になっているために、読解についての単位が非常に少ないこともその原因のひとつであり、文芸ばかりが重視される傾向があろう。 最後はedumapについて書かれているので、学校で使えるであろう。
0投稿日: 2020.04.09
