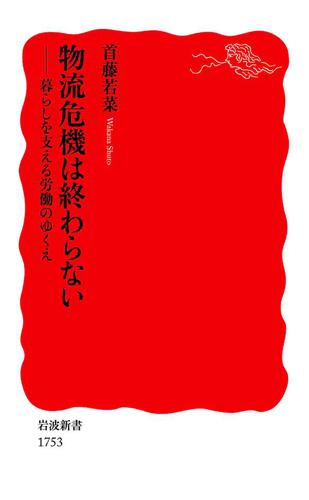
総合評価
(17件)| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ヤマトの残業代未払い・過剰労働問題を切り口に、物流の要ともいえるラストワンマイルを担うトラックドライバー人手不足および労働環境の実態について語られている。 論調としては具体的な解決策を提示するのではなく、現状の労働環境に至った原因の分析に重点が置かれている。 物流関係に携わる身として、荷主の身勝手さの腹立たしくなる気持ちは痛いほどわかる。彼らは自己中心的である、と正直感情的にならざるを得ない。 とはいえ、ビジネスの世界である。本書で述べられているような紆余曲折を経て定着した商慣行を矯正すること、そして決して無関係ではない消費者の行動意識の変革が求められていると筆者は考えている。 商慣行の矯正については、労働者の待遇を向上させること、もしくは労働量を減少させることで「適正な労働内容」に至りうるとしている。そこで、「運賃=対顧客(荷主)」を上げることは独禁法に抵触するので、「賃金=対労働者」の向上を業界企業全体で取り計らわれるべきとしている。 そして通販利用をはじめとした消費者は、物流の当事者意識を持つべきである。その先に業界ひいては社会全体を巻き込んだ「物流におけるワークルール」を構築していくべきと、筆者は締めくくっている。
1投稿日: 2024.08.22 powered by ブクログ
powered by ブクログよく聞くけど知らなかった問題。本書を読んで問題の所在がよく分かった。最近の本だと思ったら2017年発行だった。この本で指摘している問題をさいきんのTVでも取り上げていて唖然としている。
0投稿日: 2024.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
物流危機は終わらない ー暮らしを支える労働のゆくえ 首藤若菜氏による著作。 2018年12月20日第1刷発行。 著者は1973年東京都生まれ。 1996年大妻女子大学社会情報学部卒。 2001年日本女子大学大学院人間生活学研究科博士課程単位取得退学。 2002年「ブルーカラー職種における男女混合職化の研究」で学術博士。 2000年山形大学人文学部講師、2006年助教授、 2007年日本女子大学家政学部講師、2010年准教授、 2011年立教大学経済学部准教授をへて、2018年教授 夫は中北浩爾。労働経済学。 現在、立教大学経済学部教授 著書 『統合される男女の職場』 (勁草書房、2003年、社会政策学会奨励賞受賞、冲永賞受賞) 『グローバル化のなかの労使関係―自動車産業の国際的再編への戦略』 (ミネルヴァ書房、2017年、労働関係図書優秀賞受賞、社会政策学会奨励賞受賞) 学者である著者が、現場の第一線で働く人、企業へのインタビューも行った上で、物流危機の背景、今後に関してデータも踏まえて論じている。 ヒアリングを徹底して行ったからこそ机上の空論では無いリアリティを感じた。 私自身も物流センターでの勤務をしているからこそ痛感することもあったし、ドライバーの勤務の過酷さ、問題に関して改めて認識することが出来た。 単に学術論文を書くだけでは無く、新書の形でわかるように世の中に訴える事ができる学者というのは実はかなり少数派だ。 その意味でも首藤若菜さんにはこれからも学術論文だけではなく 良い本を世の中へ発信して貰いたい。 (全く論文を書かない、研究はしない、教育にも力が入っていないという駄目教授はかなりの数にのぼる) 第5章で指摘するように、過酷な労働を改善させる第1歩は他者の労働に対して無関心、無責任でいてはいけない。 社会的なつながりを認識し、働く者の負担を知り、そのコストを分かち合うこと。 適切なワークルールを作り守らせること(これが役所、公務員の仕事) 個人的には再配達には料金を取るように変える事が必須ではないかと思う。 人口減少社会に対して適切な規制を行う必要があると思う。 再配達無料から有料になることでコンビニ配達利用や宅配ボックス利用の促進を図る事が出来ると思う。 労働者、生活者、有権者の為のワークルールを作るという発想が乏しかった我が国日本ではある。 しかしこの数年働き方改革が曲りなりにも進んだ。 この方向性は正しい。 何でもかんでも市場丸投げ主義が正しいのではない。 ただ今の日本の役所、公務員は行うべきワークルール作りが不十分だ。 (というか霞が関の働き方そのものが過酷そのものだ) 世の中に必要ない不必要な資格試験の団体を作ったり天下り団体を作るのではなく 本来必要としている政策を実現して貰いたい。 印象に残った点を列挙していくと (ヤマト運輸で)2016年度上期には、人員の大幅増強策が打たれた。 年度初めから、中途社員の大規模な募集が始まり、新卒採用の枠が第二新卒(学校を卒業後就業していない者および数年のうちに転職を志す者)にまで広げられた。 特に人手が足りていない地域では、募集時の給料を引き上げることも決まった。 さらに求職者の目にとまりやすくするため、募集・採用のウェブサイトが一新され、従業員が知人を紹介する社員紹介制度も導入された。 (中略)ヤマトホールディングスの有価証券報告書によれば、デリバリー事業の従業員は、2013年の14万7350人から、2014年には16万2383人まで増員されている。 高卒の新卒採用者数も、2013年までは年間150~180人程度だったが、 2014年には347人に増え、2016年はさらに471人と、以前の3倍程度の水準を記録している。 高卒者は、入社後に運転免許を取得してもらうが、大型免許の取得には3年以上の 運転経験が必要となるので、即戦力にはならない。 そのため、トラック業界では中途採用がこれまで主流だった。 しかし、中途採用で人を採用しにくい状況が続く中、ヤマト運輸では長く働いてもらえる労働者を確保するためにも、社内で育成していく方針を立て、高卒者の採用拡大に踏み切った。 だが罪の意識は、日々の忙しさにかき消されていった。 ヤマト・ショックから約1年が経過しようとしていた2017年末、内閣府はある世論調査の結果を発表した。 それによると、約9割の人が再配達を利用したことがあり、 7割以上の人は再配達を問題だと考えている。 けれども、7割近くの人が、コンビニ受け取りや宅配ボックスへの配達など、再配達削減に向けた方法を「いずれも利用したことがない」と回答した (内閣府『再配達問題に関する世論調査』2017年12月) そもそもヤマト運輸の旧来のビジネスモデルは、ドライバーの担当区域あたりの個数を増やし効率を高めることで、収益を上げることにあった。 ドライバーも人間である以上、一定時間内に配達できる個数には自ずと限度がある。 荷物の密度がいくら増していったとしても、労働生産性(労働者一人が時間あたりに 生み出す付加価値)は無限に上がっていくわけではない。 実際ある段階からは、コスト削減効果が明らかに逓減していたという。 モノの運搬や管理を「物流」と呼ぶ。国内で年間に輸送される貨物量は約47億トンにのぼり、このうち91%がトラックによって運ばれている。 国の基準により、貨物輸送時の連続運転は4時間までと定められている。 4時間続けて運転したら、30分以上の休憩を取ることが義務づけられているのだ。 「4時間ごとにタイミングよく休憩できる場所があるわけではない」 「深夜のパーキングエリアやサービスエリアは、どこも満車状態。休憩したくても、できない」といった設備上の制約から、休憩できない との声も聞かれる。 今日、長距離ドライバーで4時間を超えて連続運転している割合は32.7%にのぼる。 つまり3人に1人が、休憩時間のルールを守っていない。 こうした実態が生まれる主たる理由は、 ①時間が足りないこと ②運賃が低いことの2つにある。 だが、現実には多くのドライバーが、パレットに積まれた荷物を手荷役でトラックにバラ積みし、それを輸送して、到着時には平積みされた荷物を再び手荷役でパレットに積み直している。 なぜパレットによる運搬が広がらないのだろうか。 前出の日本物流団体連合会の調査によれば、「荷主が積載量を多くしたいから」 ということが、最大の理由である。 繰り返しになるが、ドライバーの仕事は、本来、貨物を運搬することである。 しかし貨物搬送の前と後には、必ず荷役作業が発生する。 それらは「附帯業務」と呼ばれる。 この附帯業務を誰が担うのかが明確にされないままに、 多くの物流現場が回っている。 もう1つのサービス労働が「手待ち(荷待ち)時間」である。 長距離ドライバーたちは、一度トラックに乗れば、極めて長時間にわたり 働き続け、数日間は自宅に戻れない。 「家に帰れないことが、一番つらい」と話すドライバーが少なくない。 トラック運送事業者数は、1990年に4万72社だったのが、 2007年には6万3122社まで増えた。 2008年から減少に転じたものの、その後はほぼ横ばいで推移している。 つまり事業者数は、物流二法施行後の約15年間で1.5倍に増加し、 その水準のまま現在に至る。 物流二法→貨物自動車運送事業法と貨物運送取扱事業法 今日、トラック業界は、従業員数が50人以下の事業者が全体の90.9%を占める。 宅配便に限っていえば、ヤマト運輸が宅急便を始めた1970年代は、多くの企業が参入し、厳しい競争が繰り広げられた。 しかしその後、淘汰が進み、今日ではヤマト運輸、佐川急便、日本郵便の上位三社で9割以上のシェアを占めている。 宅配便ビジネスは、幅広い配送ネットワークを構築することで、輸送コストを引き下げることができる。 そのため、全国各地に巨大ターミナルを設け、高速自動仕分け機を導入し多数のトラックを保有できる企業が勝ち残ってきた。 いわゆる「規模の経済」が働きやすいのである。 それゆえ宅配便は、大量のドライバーを抱えるという意味で労働集約的でありながら、装置産業的な特性も持つ。 他方、一般貨物は、主に法人を相手とし、一台のトラックに1社の荷物を積載する「貸切輸送」が典型的である。 ターミナルを利用せず、1台のトラックに貨物を混載して輸送する方式もみられる。 こうした輸送方式では、トラックとドライバーさせそろえば、スポットで仕事を請け負うことも可能であり、参入障壁は極めて低い。 その結果、物流二法施行後、事業者数が急増した。 つまり一般貨物については、規模の経済が機能しにくく、 価格競争に陥りやすい。 日本郵便の存在が、運賃を据え置く方向に作用してきた。(中略) 現在、ヤマト運輸の宅急便、佐川急便の飛脚宅配便、日本郵便のゆうパックの基本運賃を見ると、大きさや重さによって違いがあるため厳密な比較はできないものの、概ねヤマト運輸と佐川急便が同水準であるのに対し、日本郵便は若干安く設定されている。こうした状況のもと、ヤマト運輸や佐川急便は、日本郵便に顧客を奪われることを懸念して、運賃の値上げに踏み切れなかったと考えられる。 ただでさえ競争が厳しい宅配便市場の中に、こうした公共的性格を有する 日本郵便が参入していることをヤマト運輸は、以前から問題視してきた。 ヤマト運輸の関係者は、「佐川さんはいいんですよ。民間企業同士が闘うのであれば、互いに赤字になれば潰れるわけで、正面切って経営努力で勝負することができます。今回みたいに価格競争になって、 採算が合わない水準にまで(価格が)落ちれば、互いに撤退するか、値上げを求めるかだけです。でもね、何年も赤字を垂れ流しながらも決して潰れない企業と闘ったら、どの企業だって負けちゃいますよ」と苦々しく語る。 本来、市場が持つ「公正な競争による淘汰」という機能が働かないのであれば、 別の方法で公正な市場を形成しなければならない。 公正な競争を保障するために、例えば、各職場の労働条件を監督指導する労働基準監督官を大幅に増員し、事業所の監視を強化するといった施策も考えうる。 現実に労働基準監督官は、少しずつ増員されている。 だが厳しい財政状況のもと、十分な監視を可能とするほどの人員増は現実性を持ちにくい。 それよりも現実的で、より効果的な施策は、社会保険の加入や労働時間などのワークルールを遵守しうる規模の事業者のみに参入を制限することである。 物流が止まった例 2018年5月のブラジルでのトラック運転手と業界団体が燃料価格の高騰に講義して、全国規模のストライキと抗議デモを起こした。 小規模事業者がひしめき合うなかで、他社と異なる付加価値をつけようとしても それが難しい。より多くの荷物を、より早く運ぼうしても、道路交通法の積載制限や速度制限を遵守して運行する限り、自ずと限界がある。 つまりサービスの差別化がしづらく、技術特性を発揮しにくいのである。 そのことが運送会社の交渉力を弱め、荷主に対して従属的な性格を生み出してきた。 なぜ若者はトラックドライバーになりたがらなくなったのか。 これには若者の「車離れ」といった変化も関係するが、それ以上に労働条件の相対的低下が影響していると思われる。 かつてトラックドライバーは「きついが、稼げる」仕事と言われていた。 それが、若者にとって魅力となってきた。 だが1990年代後半から賃金が低下していく。 今日、トラックドライバーの賃金(所定内給与)は、平均男性の7割ほどである。 労働時間が長いという意味で「きつい」ことは変わらないまま、「稼げない」仕事になってしまった。 若年層の参入減には、トラックドライバーのキャリアの変化も関係している。 かつては、20~30代にトラックドライバーとして働き、そこで身につけた技能を活かして、40~50代にバスドライバーに転職し、さらに60代でタクシードライバーに転換するキャリア・パターンがあった。 そうした道を歩めば、平均に近い生涯賃金を獲得することができた。 ところが、トラックドライバーの賃金水準が下がっていった時期に、バスドライバーの賃金はそれ以上に下落した。 例えば、50代前半のバスドライバーの年収は、1990年では600万円を超えていたが、 今日(2017年)では500万円を下回り、大型トラックの年収とあまり変わらない。 その結果、もはや運転職を渡り歩きながら、一般的な賃金水準を得るキャリアを描けなくなった。 要するに、同じ時期にトラックだけではなく、バスやタクシーといった他の運転職の賃金水準も低下していった。 それゆえ、運転職としてのキャリア展望を見出しにくくなり、若年労働者を惹きつけることが難しくなったと考えられる。
0投稿日: 2021.12.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ●日々の生活を快適に過ごすためには物流の存在は欠かせない。 今や送料無料が当たり前に根付いているが、なぜそんなことが可能なのか。それはドライバーたちの過剰労働として転嫁されているからだ。本書は物流業界が抱える問題を鋭く指摘したものとなっている。
0投稿日: 2020.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
総務省の労働力調査での男性の年間就業時間は2232時間、長時間労働が問題になっている教員は2459時間、トラックドライバーは2684時間(いずれも2017年)。政府が進めている働き方改革の時間外労働の上限規制も、運送業は建設業ととともに、「5年後の施行」と猶予期間が設けられるとともに「年960時間」、一般労働者よりも240時間長く設定されている。「荷主に対する指導の徹底と取引環境の改善が必要」とのトラック協会等の意向が踏まえられたもの。長時間労働はトラック業界の常識も一般の非常識。賃金もかつての相対的な優位性は、もはやなく、若年層の成り手がなくなりつつある。 ドライバーの仕事は、本来貨物を運搬すること。しかし、貨物搬送の前と後には必ず「附帯業務」と言われる荷役作業がある。荷積みや荷卸しだけでなく、仕分けや棚入れ、ラベル貼り、検品、資材・廃材の回収、場合によれば商品の陳列作業もある。業務契約がないにも関わらず荷主優位の商慣行が蔓延し、サービスとして提供され、その負担をドライバーが担っている。納品場所での長時間待機が余儀なくされる場合もあれば、所定納品時間との関係で休憩時間の取得ができない場合もある。これらトラックドライバーには責任のない「無償のサービス労働」の是正が進まないと、ドライバーの労働時間の実質的短縮は実現できない。 これらのサービスの実施の背景には、業界の過当競争がある。1990年施行された物流二法で規制緩和が進み、事業者数はその後15年で1.5倍に増加。貨物輸送量が増えない中で、トンキロ当たり運賃が大きく低下。ジャストインタイム、少量多頻度納品等のサービス水準のアップの中で、積載率は1990年の49.3%から2015年には36.3%まで低下。ドライバー数が増加しない中で、事業者数が増加し、何層にもわたる下請け構造の中で、車両10両以下・従業員10名以下の事業者数が増加。零細性の強い産業特性が過当競争を助長し、実勢運賃の下落と杜撰な労務管理をもたらしてきた。 かつてドライバーの平均年齢は38歳強と男性労働者の平均より若かった。それが2001年に逆転し、2016年の大型ドライバーの平均は47.7歳と5歳弱高く、一般より高齢化が進んだ。有効求人倍率は2.33倍も、宅配便ドライバーはネット通販で需要が増えたことによる人出不足、大型・中型を中心とする貨物トラックは成り手が減ったことによる人出不足と、背景が違う。配達員の新規求職者数は0.76も、貨物自動車運転者は0.38。かつ新規求職者の2人に1人は45歳以上。従事する男性の84.4%が中卒・高卒者。高校を卒業して就職するものの率は1990年には35.2%も2016年には17.9%。若年労働力人口の減少に加え、中卒・高卒労働力の不足が、成り手の不足に拍車をかけている。女性の就業者数が極めて少ないのも大きな特徴。 かつてドライバーは「きついが稼げる仕事」だった。ただ、今日は所定内給与は平均男性の7割ほど。求人側が提示する賃金(求人賃金)の最高額が、求職者が望む賃金(求職賃金)の平均賃金額に達していない。20代前半の賃金は一般労働者より高いものの、かつては30代半ばまで優位だったのが20代後半で追いぬかれる状況。生涯賃金の獲得の展望もない。 トラック協会の調査では「収入が増えるなら、本当はもっと働きたい」と答える長距離ドライバーは58.6%もいる。「労働時間が短くなれば賃金が減ってしまう」と考えているから。一方「収入が増えたとしてもこれ以上は働きたくない」と答えるドライバーも37.9%と増加傾向。厚労省の「雇用動向調査」では、2000年代前半まで仕事を辞める理由は、労働時間・休日よりも給与の割合が高かったが、労働時間を上げる比率が徐々に高くなり、2010年代に入り労働時間・休日の方が上回るようになっている。賃金より労働時間を重視するようになりつつあり、それが転職行動にも表れている。共働き家庭の増加といった社会構造の変化がある。 ボストンコンサルティング・グループは、荷物増、積載効率の悪化、労働環境改善(超過労働時間50%削減)等で、2027年には、96万人のドライバー需要に対し72万人と24万人の不足と想定。物流業界はまさに「絶滅危惧業界」。 業界の構造的な問題は、是正は容易ではない。しかし、構造の是正へと進まないと物流危機は終わらない。「この業界では経済的規制の緩和が優先され、社会的規制の確保が後回しにされてきた。業界自体の存続が危ぶまれる中、社会的規制を機能させるため、経済的規制を強化することが考えなければならない」との著者の指摘は問題の核心をついている。 労使関係の研究者が、物流の現場で起きていることを労働問題としてとらえなおし、労使関係の観点から「物流危機」をもたらした原因を明らかにし、その解決策を考える。物流危機の背景を理解するために、読んでおくべき書。著者はまだ40代、今後の活躍に大いに期待。
0投稿日: 2020.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ20191019 中央図書館 物流を支えるのは形式的には「インフラ」だが、実際には「人」であるドライバーだ。インフラの痛みに対して、消費者は残酷になれるものである。
0投稿日: 2019.10.19 powered by ブクログ
powered by ブクログどのようにして現在のような物流危機が生じているかの経緯がよくわかったが、一方で今後どうなりそうかについてはあまり示唆が得られなかった
0投稿日: 2019.08.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ物流危機が叫ばれる昨今。 本書では、なぜそのような危機に陥っているのか構造的に解明している。 事業者のみが悪いわけではなく 荷主のみに責務があるわけでもない。 我々一般消費者もその負のスパイラルに加担している、ということを訴えかけるメッセージが 構造を解き明かしていく中で随所に現れる。 物流に限らず、過当競争に陥り表面上のサービスが向上し、かつ価格が下落するという現象の先には破局しかない。 他人事とせず社会の一員として問題と向き合うべき、そう考えさせられる。
0投稿日: 2019.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログドライバーは大変な仕事だ…。 「効率的な生産システムや商品管理の裏で、トラック業界は一手に非効率を引き受けてきた。」 便利な暮らしに慣れ過ぎている日本人の意識の低さも問題だと思う。ほっときゃ解決されるだろうなんて他人事でいるのもおかしい。 ブラジルのようなストが起こったら本当に大混乱になるし、幼い子供を育てている身としては命の危機になってもおかしくない。一刻も早くドライバーの待遇改善をして、まわりまわって皆が働きやすい世の中にすべき。
0投稿日: 2019.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ物流危機に関する主に労務面からの解説になっている。 小規模会社が多く、荷主との力関係で料金があげられず、そのしわ寄せがドライバーの賃金に来ているようだ。 小規模会社では労組もなく、賃上げは難しい。産別労組でない日本では、非正規中心のサービス産業では労組もなく、雇用者側の言いなりになるしかない。 日本では生産性が低いと言われるが、その解決には料金の引き上げによる賃金の改善が必要で、日本人の作業性が低いわけでは決してない。 要はサービスに見合ったお金を払っていないことが問題で、高級レストラン並みのサービスを要求するなら、それなりの金を払うことが必要。ファミレスの値段なら、それなりのサービスしか受けられないのが当然と思わないと、従業員はやってられない。
0投稿日: 2019.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ労使関係の専門家が、現在の「物流危機」をもたらした原因を労働の観点から明らかにしている。ドライバーの過酷な労働環境や運送会社の苦労を再認識した。
0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ公開されている統計データを基に物流業界で働く人が置かれている状況が分かってよかった。もう一歩、例えばデータを年代別に見るとか、インタビュー結果を入れるとか、著者独自の切り込んだ分析があると良かった。
0投稿日: 2019.03.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ消費者としての我々が低価格や利便性を追求し過ぎて労働者としての我々を苦しめる関係について、改めて考えさせられた。 トーマス・フリードマンの『フラット化する世界』にも同様のことが書かれていたことを思い出した。。。
0投稿日: 2019.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ「私たちが得ている「安さ」や「早さ」が、働く者の長時間労働や過労死と引き換えに存在するならば、それは果たして社会的公正に適うのか?」こういった問題意識を持たなくては働く人の環境は変わらないと思いました。
0投稿日: 2019.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ労働組合や労使関係の専門家による運送業の問題に関する本。なんとなく論理が発散していて、説得力が低いと思う。運送業の実態は、統計データやアンケート結果、聞き取りなどで行われているが、人手不足と言いながらも、少ない荷物を奪い合っている状況とも書かれており、矛盾点が見受けられる。聞き取りもドライバーや作業員に対し行われており、業界の実態をどの程度反映しているのかが不明。また、解決策も、国の力で強制的に運賃や賃金を上げるとか、労組の活性化であるとか、規制の強化などが主であり、根本的な経済理論からはかけ離れている。運賃や賃金が低すぎるというのであれば、なぜそうなっているのかを示さなければ、解決できない。なぜ生産性が低いのかも同様。料金は、顧客と企業との契約で決定されるのであって、物流でも基本は需要と供給で決まることに変わりない。それに基づかないのであれば、まずそれはなぜなのかを追求すべき。荷下ろしなどの不当サービスも同じ。労働と賃金が不釣合いならば、市場原理では是正の方向に自然と動くはず。不法であれば罰すればよく、不適当レベルであっても市場から退場となるなど生き残れない。そのあたりを明らかにしないと、業界の方向性は見えてこない。生き残りのために真剣に努力をしていない企業は倒産するのが原理であって、著者はただ、淘汰されるべき弱小企業の生き残り策を述べているように思えた。 「トラック業界では、延着(荷物の到着が遅れること)は、絶対に許されないことであり、ドライバーにとってこれほど恥ずかしいことはないと考えられている」p59 「(パレットを使いたがらない理由)積載量が減るから。パレットが戻らないと困る。(荷主は)必要性を感じない」p64 「(日本郵便)何年も赤字を垂れ流しながらも、決してつぶれない企業と戦ったら、どこの企業だって負けちゃいますよ」p133 「(トラックドライバー)1990年代:きついが稼げる、今:きついし稼げない」p162 「(電通過労自殺事件の公判の冒頭陳述)「クライアント・ファースト」が浸透し、深夜残業や休日出勤も厭わず働く環境があった」p197 「日本では高いサービス品質をもつサービス商品が割安な料金で提供されており、その結果、労働生産性が低くなっている(深尾京司・池内健太)」p215
0投稿日: 2019.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や社会問題である物流危機。「即日・無料配達」といった利便の陰には、働けど働けど暮らしは一向に良くならない労働者(トラックドライバー)の実態があった。サービスといえば無料のことだと理解されがちな日本では、労働者が質の高い仕事(サービス)を提供すればするほど生産性は上がらない。サービスに正当な商品価値を与えるにはどうしたら良いか。著者は、賃金は運賃と異なり、独禁法で規制されず、一企業を越えた産業全体での引き上げ(賃金カルテル)が可能であり、社会的連帯を強化し、今ある労働のあり方を見直す必要があると主張する。
0投稿日: 2019.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生の卒論参考資料として入手したが、自分自身の参考になりそう。 労働環境という切り口はありそうでこれまでなかったかも知れない。 しかし、最も重要なポイントを押さえているのではとも思う。
0投稿日: 2019.02.01
