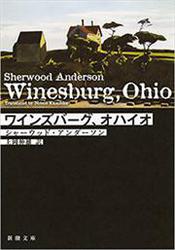
総合評価
(23件)| 6 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカの田舎町に住む平凡な人々の平凡な人生を覗き見るような小説。 登場人物たちは、国や生活様式は違えど私たちと同じように毎日毎日同じことを繰り返して生きている。みんな大なり小なり苦悩と幸福があり、どこか孤独。 この本は、そんな取るに足らないと思われるような人生を歩んできた人々の、ある瞬間を描く。 それは誰にも省みられないような小さな出来事で、大きな変化を起こすような力はない。なのにどこか惹き付けられる、その人のこころを象徴するような特別な瞬間。 どんな人間にも物語があり、この本からはそれを慈しむ心を感じる。 私にとっては相容れない人や、一生関わることが無い人にも物語がある。そのことに想いを馳せると、孤独は尽きなくとも、隣人を愛したいと思えます。
0投稿日: 2025.12.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018年に出た新訳版。橋本福夫の旧訳版に比べ、読みやすくなっている。 時代は1900年頃、舞台はオハイオ州、架空の町ワインズバーグ。その町で起こる小さな出来事をめぐる25篇。田舎の風景や季節の描写、人物の心理描写が秀逸。 それぞれの掌篇はしゃれた終わり方をするわけではないし、受ける印象も明るいものではない。でも、なにかしら心に残る。この作品にインスパイアされて、レイ・ブラッドベリは『火星年代記』を書いた。構成のしかたが似ているだけでなく、読後の印象も似ている。 (訳文は練られているが、多少気になる訳語もある。たとえば「哲学者」の章、パーシヴァル医師はさほど高齢でもないのに「わし」や「わしら」で話す。ちなみに橋本福夫訳は「ぼく」、小島信夫・浜本武雄訳は「おれ」。)
0投稿日: 2025.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログオハイオ州、ワインズバーグという架空の町に住むいろんな人々を描く物語。なんとなくちょっと変わった人物が出てくる。現実世界でも、普段は一般的な人に見えて、内側は様々な感情や孤独を感じている人が多いかもしれない。冒頭の「いびつな者たちの書」のいびつな者は、この作品に出てくる町の人とは思うが、「いびつな者たちのなかには、たやすく理解でき、愛することもできる人物たちがいる」と書かれている。なんか優しい。
0投稿日: 2025.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀のアメリカ中西部・オハイオ州の田舎町の人々を描く短篇集。 冒頭「いびつな者たちの書」で語られるとおり、この作品で描かれるのは「孤独・不安・疎外感」を感じている「完璧でない者たち」である。 いずれの話も個人的な葛藤を題材にしているものの、それらを主人公の視点からとりまとめることで、19世紀後半の中西部の雰囲気を上手く描いている。 ここで語られた「いびつな者たち」が、まさしく現在のラストベルトの労働者階級(ヒルビリー)になっていったのだと思うと非常に興味深い。 個人的には、「考え込む人」のいかにもウブなセス・リッチモンドに最も感情移入できた。 アメリカの田舎町の鬱屈を描くという点で、時代も舞台も全然違うけど、映画「ラスト・ショー」のような雰囲気の小説だった。
0投稿日: 2025.02.04 powered by ブクログ
powered by ブクログエリザベス・ストラウトが『オリーヴ・キタリッジの生活』において、クロズビーという架空の町での人々との交流を描いたり、レイ・ブラッドベリが『火星年代記』の冒頭で「こんなにすばらしくなくてもいい、これの半分だけすばらしい本でいいから……ぼくが書けたとしたら、どんなにすてきだろう!」と賛辞を送るほど影響を与えた本作。二作とも好きですが、これも読み進めるほど話に引き込まれて、読んで良かったと思いました。 本書は、ある老作家が見た夢「いびつな者たちの書」という物語から始まる連作短編の形を取っています。舞台は、オハイオ州の架空の町ワインズバーグ。どの短篇も新聞記者のジョージ・ウィラードを登場させて、一見バラバラな町の人たちの話しに一貫性を持たせており、彼が精神的に成長していく様子も読みとることができます。 それぞれの短篇に登場する人たちは、孤独感に苛まれていたり、臆病であったり、不器用な性格であったりと”いびつな者”に該当しています。そして、そんな皆が、どこか夢想家や野心家だったりするため、当然一花も咲かせずに一生を終えたり、先を思い悩んで気狂いになる人もいたわけですが、その行動の細やかな描写や心の内を炙り出す巧みさに引き込まれてしまいました。 それにしても、作中の不器用な人たちを”いびつな者”とみなすのは簡単ですが、現実世界でも程度の差こそあれ、誰しも悩みを持っているものです。そういう意味では、単に田舎町の住人の鬱屈した孤独感の代弁にとどまらないものを感じて興味深かったですね。
27投稿日: 2024.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀アメリカ西部の田舎町、ワインズバーグ。新聞記者の若者ジョージ・ウィラードを中心に、町に住む「いびつな者たち」の物語を綴る連作短篇集。 この作品に描かれた「いびつな者たち」とは、大きく括って社会的なマイノリティーの人たちを指しているのだと思う。さまざまな理由ではぐれ者扱いを受けている人たち。「手」のビドルボームや狂言回し役のジョージが抱える葛藤から、〈男らしさが至上の世界からこぼれ落ちた人びと〉というテーマを受け取った。ヒーローにも不良にもなれず、世間から賞賛されるようなことはひとつも成し遂げられない苦しみ。〈落ちこぼれ〉のなかには当然〈女〉も入ってくる。 ジョージの母エリザベスを主人公にした「母」からものすごいのだが(一つ前に置かれた「紙の玉」との対比がのちのち「死」で効いてくる構成も見事)、「狂信者」の息子を愛せない女性ルイーズの描き方には本当にギョッとした。赤ん坊が「家に侵入してきた人間の欠片のようなもの」に見え、「これは男の赤ん坊だから、欲しいものを自分で手に入れるわよ」「これが女の子だったら、どんなことだってしてあげるでしょうけど」と言い放つルイーズ。でもこの小説はネグレクトする母親を断罪しない。100年前の男性の手で書かれたと思えないくらいフラットに彼女の鬱屈した感情に寄り添っている。 ルイーズの反対目線、つまり女性を妊娠させた責任から逃れきれなかったことを後悔し続けている男性レイの物語「語られなかった嘘」もしっかり入っていて、最後の段落でタイトルが回収されるとレイへの悪感情がすべて霧散し、寂しさだけが残る。男と女、それぞれに押し付けられた役割とそこから逃れようとする〈弱さ〉を描き、解放されたいという願望も「タンディ」のように新しい言葉を創りだして提案する。「冒険」のアリス、「教師」のケイトなど当時ならまだオールドミス扱いを受けただろう年齢の女性たちの苦しみも、なんと現代的に描写していることか。 田舎町に住む変人たちを観察する青年の成長物語ということで、サローヤンの『僕の名はアラム』に近くもあるが、サローヤンが人種的マイノリティのコミュニティをどこかユートピア的な連帯感のある場所として書いているのに対し、『ワインズバーグ、オハイオ』は一人ひとりが孤独な星のように描きだされる。だからこそ、「見識」でジョージとヘレンが無言のままお互いに敬意を示し合う場面の美しさが胸に迫るのだ。「それぞれの心には同じ思いがあった。『この寂しい場所に来たら、この人がいた』」。 さまざまな生きづらさにスポットを当て、架空の町ワインズバーグに息を吹き込んだ古典的名作。ミルハウザーの芸術家小説や、ルシア・ベルリンの刺すようなユーモアなど、自分の好きな現代小説が描く〈孤独〉のルーツがここにあるような気がした。
2投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ1919年に発表された小説だとは思えないほど現代的。 頭に全く入ってこない話もいくつかあったが、「変人」、「神の力」、「品位」は特に良かった。
0投稿日: 2022.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ19世紀後半(推定) オハイオ州ワインズバーグ――架空の地名――に暮らす人々の 悲喜こもごもが、 主に地元新聞の若き記者ジョージ・ウィラードの目線で描かれる 掌短編連作集。 地味だが奇妙な味わい深さがある。 流行らなくなったホテルの経営に悩みつつ 打開策を見いだせない女性(ジョージの母)、 スキャンダルで職場を追放された元教諭、 ほとんど診察しない医師、 狂信的に神を愛す農場主と、それに反発する家族、 流れ物の身の上話と教訓に深く感じ入る女児、 心の平衡を失った牧師の強硬策、etc。 興味深いのは、人間関係が密な昔の田舎町を舞台にしながら、 本当は誰も共同体内の真実を知らない、 といったストーリーになっていること。 これは作者が利かせた黒いエスプリなのかもしれないし、 事件の背後に子に対する親の過干渉が潜むケースもあって、 ううむと唸らされた。 最も共感したのは、 職を求めて大都会へ出た初めての恋人ネッド・カリーを想い続ける アリス・ハインドマンの奇行を綴った「冒険」。 自分の生活に変化が起きないことに虚しさを覚えたものの、 我に返った彼女は結局、一人で生き、 死んで行かねばならない事実を痛感する、という……。
2投稿日: 2021.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「CONFUSED!」という漫画のインスパイア元だと聞いて読んでみた。オハイオ州の架空の街ワインズバーグをめぐる連作短編集。1つの街を新聞記者の主人公を中心に立体的に描いてくところがオモシロかった。ただ本著は1919年に発表されたこと、またアメリカ中西部の話なのでなかなか情景が想像しにくい部分もあった。しかしテーマとしては人生における悲喜交々、艱難辛苦なので今の時代でも十分に響いてくる。 街に住む人たちの生活が描かれていて、その中から教訓めいたものが提示される。決して大きな事件ではないものの人生の中で一度は考えたことあるなぁという内容が多い。ゆえに時代を超えた普遍的な強さがあるのかと思う。また登場人物が大量に出てくるのも特徴的で「あれ、この人さっきの話で出てきたな?」という短編間の繫がりも強い。登場人物の相関図を書く必要があるのでは?と思わされる、まさに人間交差点。そこには当然「正しくない」人も出てきて自分の知らないことに対する想像力が鍛えられるような感覚もあった。これは人生のどのタイミングで読むかが重要だと思われるのでタイミングを見て再読したい。
1投稿日: 2020.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生が複雑怪奇であるということは真実だ。平凡な人生というものはありはしない。と、解き明かすような、アメリカの想像上のある町「ワイインズバーグ」に住む人々の暮らしや心模様の物語群でした。ひとつひとつの物語でもあるが、若い地方新聞記者ジョージ・ウィラードは聞き役でもあり、つなぎ役でもあり語り部です。 1900年代の初めに書かれたアメリカ文学、ヘミングウェイやフォークナーに影響を与え、モダニズム文学のさきがけということです。この前に読んだ佐藤泰志『海炭市叙景』の下敷きのようなものということで読みました。 なるほど、あるまちを創造、住人の人生模様を癖や性格などを素材にして物語るのは同じようです。でも、この「ワイインズバーグ」に住む人々は、「海炭市」に住む人々の生活がなんだか哀しげな様子なのに対して、こちらはとても奇妙な、むしろあっけらかんとしているような人間模様です。それなのにすごく人間らしいんですよ。人間はみんなどこかしら「いびつ」なところがあるんだよ、と言っています。 作者の観察眼、資質の違いですね。それともアメリカモダニズムと私小説派の違いかも。 こちらも結論は出ません、明るい未来の予言もありません、けれどもどこかしらおかしみを感じ、ほっとしたのも本当です。それに両方とも人間観察の背景に自然が美しく配されているのが印象深く、感動します。
3投稿日: 2020.07.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ実はあまり期待していなかった。要するに成長というか変化。とてもクールな散文詩。あまり書かれている意味とかストーリーを読み取らずに、理解しようとせずに、スーパーフラットに読んで欲しい。正しいブコウスキー。
2投稿日: 2019.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい、綺麗事が一つもない。 かといって救いがない訳ではない。 決して人からはよく思われないし共感もされないような衝動、感情がつまっていた。 個人的にはとても共感できた。 全く関わりがない人々と町の話なのに親近感を覚える。 ましてや違う国の話なのに。 人に言えないような感情や行動を、実はみんな抱えているんじゃないか。 田舎においても都会においても、何かに縛られている現代人にとってこの物語は自分自身の物語だと思う。
0投稿日: 2019.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「欲望のバージニア」を読んでこの著者のアンダーソンのことを知り、すぐに読みたかったが、結構な時間が経ってしまった。 惹句にはマークトゥエインとヘミングウェイの橋渡しをした作家と、紹介されている。
0投稿日: 2019.06.15 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか読み終わらなかった。そんなに人は出てきてないのかもしれないけれど、たくさんいる気もする。架空のスモールタウンに暮らす人々のそれぞれの物語。オムニバス。 地元紙の記者ジョージウィラードが町から旅立つ一編は場面は映画「アメリカングラフィティー」を想起させた。 妙に印象的な本。
0投稿日: 2019.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログシャーウッド・アンダーソン、初めて読んだ。 ヘミングウェイとか、カーヴァーとかに影響を与えた作家らしいのでとっても楽しみにしてた。 すっかり長編小説と思ってたのだがなんとオムニバス形式の小説だった・・・。 【オハイオ州のワインズバーグという架空の町を舞台にした22編の短編からなる】それぞれは独立した短編作品だが、登場人物が他の物語に再登場する相互リンクの要素があり、多くの作品に登場する青年、ジョージ・ウィラードが作品集全体の主人公格である。】 ジョージ・ウィラードが不器用でいとおしい。 この世代の小説、土着のもの多くないか?なんでだろう。 次は長編読みたいなあ。
1投稿日: 2019.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ最後の数節、死、見識、旅立ち、この3つが、この小説で積み上がってきたものをひと息に遠くへ押しやる。全てが(悲しいけれど)遠ざかっていってしまう、その儚さ・切なさみたいなものを、この三節が一気にまとめあげる。 センチメンタル過ぎるかもしれないが、泣ける小説だ。
1投稿日: 2019.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログオハイオ州にあるワインズバーグという架空の町を舞台にし、そこに住んだり関わったりしている人の日常的な話を短編として綴ったもの。よく登場する人物はいるが、一人だけに焦点を当てているのではない。かといってキャラクター小説というわけでもない。 話に盛大なオチがあるわけではない。大事件が起きるわけでもない。日々過ごしている中で自分の中に突如現れる衝動とそれに対する行動に焦点を当てていると感じる。登場人物は町のなかでも変わり者扱いされている人も多く不可解な言動も多いが、突然沸き起こる感情や衝動、その行動の中には何か納得するものもあるから不思議。納得できないと読み手がおいてけぼりになることもあるが。
0投稿日: 2019.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ随分前に橋本福夫の訳で読んで、大好きだった本。上岡伸雄の新訳が出て、『リンカーンとさまよえる霊魂たち』の訳も良かったし、再読してみた。 とてもいい訳だと思ったが、福田訳を何度も読んでいたので、どうしても違和感があった。特に美しい「紙玉」(上岡訳では「紙の玉」)の「ひねこびたリンゴ」という言葉が心に残っていたので「ごつごつしたリンゴ」には物足りなさを感じてしまった。 しかし、全部読んでみると福田訳よりずっと分かりやすく、福田訳では読み飛ばしがちだった「狂信者」(福田訳では「信仰」)は思い込みを信仰に結びつける者の恐ろしさ、愚かさ、悲しさが伝わってきて、ラストのジェシーの哀れな姿は胸に迫るものがあった。 「冒険」は福田訳よりずっと良かった。これはソフトな「天人唐草」(山岸凉子)だなと。知らぬうちに世間や常識や親の教えにがんじがらめになって、若さと正気を失う女は、今もいると思う。 これは南北戦争のあとの物語だが、過去の物語ではない。今もこういう人たちはいるし、自分もその一人なのだと思う。 しかし、若いのにこれに共感してしまうとは何と寂しいことか。過去の自分を哀れに感じた。
0投稿日: 2019.01.02 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカのチェーホフ、或いは中西部のチェーホフ、という事らしいので読んでみたが、確かにその通りだった。 チェーホフにおいての閉塞感は、社会的なもの、制度的なもの、慣習的なもの、それらが生み出した慢性的な怠惰、というものが主で、ここではないどこかというテーマは、彼ら彼女ら個人では果たせない夢である事が多い。 出てもどこへも行けないし、多分何も変わらない。個の努力や能力によっては果たされない。 そこで生まれるのが、何百年かあとの世の中の幸福、というヴィジョン(ファンタジーとも言える)。或いはどん詰まりを何とか昇華させるためのユーモアやペーソス。 アンダーソンにおいては、流石にアメリカの田舎であって、行こうと思えばここではないどこかへ、ひょいと行ける。しかしそれからは個人の努力や能力、そして運。 全ては自分の責任であるせいで、ある意味、もっと過酷と言っても良いのかもしれない。ファンタジーの入る隙間は無い。 だから突きつけてくるものは(皮肉にも)さらに厳しく、つらい。 そこで我々はいびつにならざるを得ない。そのいびつさはチェーホフほどにはユーモラスではなく、まるで錐で刺される様に痛い。 しかし、何か神的な仕草がそこに宿ってもいるのかもしれないし、彼らが生きる時、そのフォルムは神話的にさえ見える。それはある種の美なのだろうか。人が愚かなりにも生きる意味も実はそこにあるのではないか。その感触はスタインベックに引き継がれたのかもしれない。 あなたは誰に似ている?私に似ているのはリーフィ医師。 簡素で硬質で映像的な表現は見事。 最小限の言葉で、多くを語らずに暗示させる手法はチェーホフから受け継ぎヘミングウェイへと繋がるのだろう、その流れが良くわかる。「誰も知らない」とか、とくに。 一度で読み切れる様な本ではなく詩の様に味わうべきだろう。 「チェーホフのような筆力で、母親の臨終を書くことができたら、……」と彼は自伝に書いているらしいが、「死」とチェーホフの「大ヴォロージャと小ヴォロージャ」を読み比べて御覧なさい。結婚に失敗した女性はアメリカだと馬車を乗り回すが、ロシアならトロイカなんですわ。
1投稿日: 2018.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
オハイオ州ワインズバーグを舞台にした短編集のような長編。その街に住む一人の青年を中心に、街の人々の人生を物語る小説。色んな人生を温かく見つめるような作者の視線が、とても優しい気持ちにさせてくれるような。人の温かさに触れたくなったら、ぜひ。
0投稿日: 2018.09.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ新潮社の名作新訳コレクション「Star Classics」の一冊として刊行された本書は、19世紀後半から20世紀前半を生きたアメリカ人作家、シャーウッド・アンダーソンによる長編作品である。全く知らなかった作家及び作品であるが、これが大変素晴らしい。 20世紀のアメリカ文学を眺めたときに、我々は牧歌的なマーク・トウェインやO・ヘンリらの作風と、ヘミングウェイやその後のフォークナーに流れていく実存主義的な作風との間に断絶があることに気づく。シャーウッド・アンダーソンは、まさにその断絶を埋める世代の代表的作家である、というのがアメリカ文学史における位置づけなのだそうだ。 本書では、オハイオ州の架空の町、ワインズバーグを舞台に、主人公である地元新聞記者のジョージ・ウィラードのもとに寄せられた町中の様々な人物の絵姿が連作短編の形で綴られていく。都会への憧憬、恋愛(ロマンス)への思慮、セックスの欲望など、市井の人々が抱く様々な感情が包み隠されることなく描かれる、かつ彼らの抱える課題が決してハッピーエンドに回収されるわけではない様子は、そのあとのフォークナーの作風に繋がるような不穏さを感じさせて止まない。かつ、架空の町を舞台に市井の人々を動かすという舞台の設定も、フォークナーにおけるヨクナパトーファ群を想起させる。
1投稿日: 2018.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ必読書としてよく挙げられてはいるものの、なかなか読む機会を得なかった『ワインズバーグ、オハイオ』、新訳が出た、ということですぐに入手した。 で、読み始めたものの何やかやで途中でページが止まっていた、のだが、今朝、ふと再開したところ、とにかく止まらなくなってしまった。 無数の人たちが次々に現れては短い物語の主人公となったり、脇役となったりする。当初は、だれに心を寄せればよいのか掴み切れず物語に入り込むことを難しく感じたていた。それも途中で手が止まっていた要因かと思う。 ところが、なぜか、今日は読み始めたときに「これは、読める」と思った。そして案の定、一日をかけて、すべてを夢中で読んだ。読書には、なぜか「その時」があるものだ。 今からちょうど100年前のアメリカの小さな町に暮らす人々の話だというのに、なぜこうも瑞々しいのだろう! 少しずつ読み進めるにしたがって、誰が誰やら、という状態だったのが、ひとりの青年に少しずつ焦点が集まってくる。そして次第にワインズバーグという町が立体的になってくる。 川本三郎さんによる巻末の解説に、とてもよい一文があった。 「アンダーソンは良き人々の心のなかの負の部分に着目する。それでいて決して彼らを否定するのではない。心に屈託を抱え、周囲に溶け込めない、心寂しき人々を、その負の部分を含めて肯定しようとする。愛そうとする。だから、読み終ったあと、読者は夜の暗さのなかに、夜明けの光を感じ取り、穏やかな気持ちになる」 善良で「いびつな」人たちの小さな物語(とはいえ、わずか数ページに人生が凝縮されていたりもする)は、今後また手に取れば、また違う面白さを見出すのだろう。ああ、それにしても面白かった。今はただ豊かな読後感に浸っている。
2投稿日: 2018.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ新潮文庫のStar Classics新刊。 秀逸なオチがあるわけでもなく、捻りがきいた作風でもないが、不思議な魅力がある。解説に佐藤泰志『海炭市叙景』が挙げられていたのがちょっと嬉しい。
0投稿日: 2018.06.28
