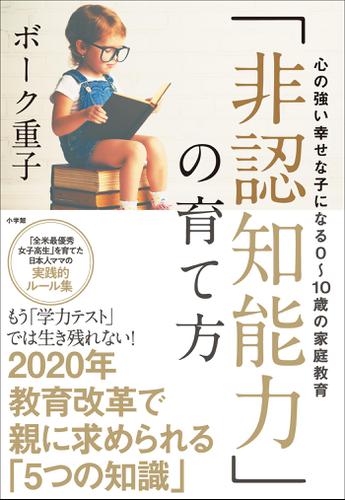
総合評価
(46件)| 17 | ||
| 16 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ親が子どもにしてあげることについて、実体験を元に書かれた1冊で読みやすい内容だった。 ・子どものフロー状態を見逃さない→何が好きなのか ・他の人と比べない ・選択肢を用意して子どもに決断させる ・子どもが決めたことを全力でサポートすると伝える ・「なんのためにやるのか」の質問を習慣にする ・他人から否定されたとき「だから何」の精神 分かっていることだが、徐々に薄れて忘れかけていること。定期的に見直したい。
1投稿日: 2025.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ2025.8.12 図書館貸出にて読了。 要点だけかいつまんで読んだが、非常に大切なことが読みやすくまとまっているように感じた。 全米の女子高生No.1を育てた実績ということで、子供にも、そして夫や自分自身にも愛が溢れた対応をされており、人として学ぶことがたくさんある。 自分の子はまだ数ヶ月なのでちょっと早かった。子が言葉がわかって、コミュニケーションが始まった頃に再度読み返したいと思った。
0投稿日: 2025.08.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ恐らく非認知能力の育て方として有効な方法がほとんどなのだろうけれど、エビデンスがご自身の子育て経験のみなので、説得力に乏しい。参考文献が多数掲載されていると良かったのに。それはあなたの子どもが優秀だっただからでは?と感じる人も少なくなさそう。もう少し俯瞰的に書いて欲しかった。家族のルールは取り入れてみたい。とにかく目の前の子どもに個人としてしっかり向き合うことが大事。
2投稿日: 2025.06.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもがより良く成長するために たくさんの知識が入ってくると 何がいいのか迷います 自己肯定感とか お受験とか 習い事とか 親が導くべきこともたくさんあるけれど 子どもの力を信じることも大切 そして 自分が母だけではなく1人の自己として どう生きるかを考える そういう姿を子どもは見ていると
1投稿日: 2025.04.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこれはもう全人類が読んでください。 親であるならば必ず読んでください。 それくらい大切なことだらけでした。 私のできていないことがありました。 おそらくこの本は手放さないし、これから何度も読むことになるだろうと思います。 それくらいの必読書です。 非認知能力がいかに大切かを 具体例を用いてわかりやすく書かれています。
0投稿日: 2025.03.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ改めて幼少期の親の関わり方がその後の子供の人生に大きく影響するんだなと実感。 ついつい怒ってしまったりするけど、また読み返して意識したい。 もう少し子供が大きくなったら家族のルール作りしたい!
0投稿日: 2025.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこどもの自己肯定力、論理的思考力が子育て、接し方が培われるのかと改めて思いました。 親と子でいわゆるコーチングと近しいやりとりが今後こどもが自身の力で生き抜く力を身につけるために必要なんですね。 親側もこれを実践していくためには、忍耐、論理的思考力、メタ思考などいろいろと自身の心のあり方、スキルが問われるなと思いました。
0投稿日: 2024.11.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ娘が赤ちゃんの時に購入し、積読本になっていましたが、娘が3歳になった今読みました。 赤ちゃんの時に読むより、よりリアルに感じられてよかったです。 なんとなく知っていることや、そうした方がいいのだろうなと思うことが多くありましたが、今日から実践できることばかりで、早速意識しようと思いました。 子供が思春期に入るまでに何度も読み返したいと思います。
0投稿日: 2024.10.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ正解のない問題に、自分らしく立ち向かって解決していく力である非認知能力は、まさに今の社会に必要だと言われてることだと思った。 科学的知見に基づいて、家庭での非認知能力、またそれに求められる自己肯定感を育む方法が例を含めて書かれており、とても参考になった。
1投稿日: 2024.09.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ育児書は基本的に科学的根拠に基づいているものか、臨床や実践件数をたくさんお持ちの専門家のものを好んで読む。 こちらはナラティブな1人のママの話だが、ある学校の教育方針や研究や調査を参考にされていて、たいせつなことに気づかせてくれる良書だと思う。 特に「家庭で子どもの自己肯定感を育む12の方法」と「親自身の自己肯定感を高める」の第5章:子どもと自分を受け入れる は必読だ。 12の方法は読んでもらうとして、特に覚えておきたい自分の感想をメモ ・親ができるのは手本を見せて導くことだけ。子どもが試したことは、それがどんなに下手な出来でも親は決してやり直さない。 ・正しい言い方や書き方は大切。でも、子どもが小さい頃はそれほど重要ではない。そのうち子どもは自分で発見するのだから放っておく。どうしても必要なら本や動画で一緒に学べば、子どもは自分で発見する。 ・他人からどんな評価をくだされても「自分は親にとって最も大切な存在だ」という確信があれば大丈夫。日頃から伝える。 ・世間体が悪いと思うなら、それは親の問題である。子どもは関係ない。親の問題を子どもに押し付けると、子どもは「親の理想を体現できない自分」を嫌悪し罪悪感でいっぱいになる。 ・英エセックス大社会経済研究所のジョンアーミッシュ教授らの四万世帯を対象とした数年に及ぶ大規模調査によると、子どもの満足度は両親との関係、特に母親の幸福度と明らかな関係があるとわかった。 ・何事もきちんと子どもに説明する。説明すればほとんどの場合わかってくれるし、「自分はきちんと説明をうけるに値する人間なんだ」と思える ・母親自身が育児や人生を楽しまずに自分にダメ出ししていては子どもと楽しく接することはできない。
1投稿日: 2024.09.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ現在子育て中でどう接すればいいのか、何が正解なのか(正解がないのはわかっているのですが)悩むことが多々あるのですが、子供にとっての非認知能力の大切さや、子どもとの向き合い方の方向性が見つけられたり、自分自身の在り方についても向き合える一冊でした。
0投稿日: 2024.06.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非認知能力向上に主眼をおいたアメリカの学校で娘を育てた筆者による家庭でできる実践メソッド。 実践対象の年齢が幅広いため、また読み返したい。
0投稿日: 2024.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供と一緒に家庭のルールを決めて家族全員で守る、自己紹介を考えさせておく、というのがいいなと思った。実践してみたい。
0投稿日: 2024.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ我慢強さややり切る力など、非認知能力を育てようとする側の非認知能力もかなり求められることを感じました。 じっくりと対話する時間や、挑戦をして失敗を許容する機会をこの多忙の中で確保しようとできるかですね。
1投稿日: 2024.03.05 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく参考になった。 まだ、3歳と1歳だから、 これからって感じ。 母親が笑顔で 幸せなら子供も幸せなんて びっくり。 まずは自分の幸せを♡ あと会話やあそびも 大切ってよくわかった
2投稿日: 2024.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「非認知能力」について分かりやすく書かれており 、我が子がもう少し大きくなったら実践してみたいと思える内容だった。 最近、脳科学の本を読み漁っているが どの本にもよく書かれていることが ◇子どもに選択させる機会をつくる ◇能力ではなく過程を褒める ◇家庭の中で子どもに役割を与える といった内容。 まずはわたしも その辺りから始めてみよう。
6投稿日: 2023.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
また読みたい 具体的にどうやって子育てしたのか書かれていてわかりやすかった 家庭の中でもルールを決めるということが気になりました
0投稿日: 2023.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ育て方 ・子供に頻繁に声掛けをして、触れ合う ・話をよく聞く ・感情的にならない ・感謝する ・よく褒める ・他のこと比べない ・欠点を治すのではなく長所を伸ばす ・子どもに決断させる ・選択肢を用意し、自分で決めさせる ・やってあげるのではなく、手本を見せる ・子供の感情が爆発した時は、責めない。話を聞く。まず抱きしめる。 ・「あなたはパパとママにとって、一番大切な存在」と伝える ・子供の気持ちが一番大事 親のマインド ・最も幸せな子どもは、両親と一緒に暮らしており、家族と一緒に週3回以上の夕食を食べ、母親が幸せを感じている家。 ・働く時間を半分にし、主婦業はお手伝いさんもお願いして、焦ったりイライラすることなく、幸福度を増やすこと! ・苦手なものは苦手と認め、無理してやらなくてもいいようにする。 ・健全な捌け口。神に殴り書きして、ビリビリに破く ・週一回デートの時間を作る。30分でも。夫は最大の協力者だから、なぜ手伝ってくれないのかと批判するのではなく、「本当に大変なの」と甘える。 ・幸せは伝染する。楽観的で前向きな人といるようにして、ネガティブな人は、耳を傾けないようにする。 ・子供の勉強内容は、好き、楽しいという感情から始める(ボーヴォワール校)-学校選びだいじだなぁ。 子供のパッションの育て方 ・いろんなことに挑戦させる(観察!興味の対象、頑張れること、悔しがること、壁の乗り越え方) ・色んな人に会う機会を設ける ・好きなことが見つかるまで探す。 ・やめ方のルールを決めておく(3ヶ月とか) ・なんのためにという質問を習慣にする ・仕事には4種類。有償の仕事、無償の仕事、ボランティアという社会をよくする仕事、 ・
1投稿日: 2023.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非認知能力をどのように伸ばしたら良いかのヒントが詰まった節目節目で読み直したい本。 ルールを作る、対話をする、遊ぶという3つの軸で非認知能力の伸ばし方が解説されている。 子供へのアプローチだけではなくまず親自身が自分の人生を活き活きと自信を持って生きるべきという点に共感した。
0投稿日: 2023.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供との関わり方についての章も共感できたが、最後の章で、アメリカと日本の専業主婦という考え方の違いが個人的にすごくしっくりきた。自分も確かに子供を産んだら、周りの環境に流され自分の人格がなくなるような気がしてしまって苦しい時期があったけど、自分という人格に母親という役割が加わっただけであって自分の人生を生きるという考え方が最初からできたら楽しく過ごせたんじゃないかなと思う。 実際、母親になるって事ということを自分がなくなる、不安と思っている人はたくさんいると思う。 確かに環境は急激に変わるけど、生き方は変わらない気がする
0投稿日: 2023.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ子育てで話題の非認知能力についての本です 声かけを大切にする等、子育てをしていると当たり前に感じることが多く書かれ、全てを読むと回りくどくボリュームが多く感じました。 自分が気になる所だけ読むのをおすすめします。 私が学びたかったことは、母親としての自己肯定感の高め方です。その点については5.6章で多く書かれており、自分を省みることができ、とても満足しています。1-4章は軽く見ましたが微妙でしたので-1にしました。
0投稿日: 2022.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ再読 親として子どもにしてあげられることは、自分で自分の人生を切り開き乗り越えていける力を養う手伝いをしてあげられることだけだと実感。 そのためのノウハウがたくさん詰まっていた。 まずは、 ・自己肯定感を下げる声掛けをしない ・こどもに感謝する ・一緒に楽しむ ・自分自身が幸せになる努力をする から始めようと思った。 そして、家族の基本ルール、doルール、dontルール作りは参考にしたい。
0投稿日: 2022.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
書いてあることは難しい事ではないし全部できたらすごく良いけど、実際にやるとなるとなかなか難しいだろうなあと思う。 それでも子どもの非認知能力を育てたいと思っている私にはかなり有益な内容だった。 心に残ったフレーズは2つ ①私たちは親になったのではなく、自分という人格に親という役割が加わっただけ 親だけど、親も1人の人間。 子どもがいるからといって、自分の「好き」や「やりたい」を一時的に我慢する事はあるかもしれないけれど、ずっと全て抑え込む必要はないとわかって心が軽くなった気がする。 むしろ、子どもがある程度大きくなってきたら親も好きなこと、やりたいことで楽しんでいるって事を背中で見せるのも一つの子育てなんだなと気付かされた。 ②人から批判された時は、「so what?」の精神で 自分も他人の目をつい気にして、やりたいことに足がすくみそうになる事は多々あるし、これからもあると思う。 でも人からなんと思われようとたとえ失敗しようと、それよりもとりあえずやってみるということの方がはるかに大事だということを改めて気づかせてもらえた。自分の人生なんだから。
1投稿日: 2022.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供がちゃんと自立して幸せに生きていくためには、親自身が子供に向き合って対話をしていくことが大事なんだなと。 お金はかからないけど労力はかけろっていうのも分かる。けど、親自身の性格や置かれている状態によっては難しいこともあるだろうし面倒なことはあると思う。できることから始めてみてもいいかな。 母親の自己肯定感が低いと子供に影響があるのも分かる。幸せそうじゃない母親を見てると気を遣うなと思う。私自身、自分の母親は私がいていいのかな、楽しいのかな、幸せなのかなと思った時はある。顔色を伺いすぎたり気を遣いすぎる人生に自分の子供にもさせないように、私自身も自己肯定感を高めて好きなことやったり経済的精神的自立して変わろうと思った。(経済的自立しても離婚する意味ではない) 子供の「なぜ?」にはちゃんと答えてあげたいし、もう少し大きくなったら辞書を買っておこう。 本当に「なぜ?」に答えてあげると勉強ができて探究していく力は伸びます。(私の弟がそうでした) 子育ては子供だけでなく自分育てでもあると改めて感じた。
0投稿日: 2022.08.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ2022/07/05 読了 子育て、不安だから事前に調べる。 不安なことは安心するまで調べる、それが私流。 さて、その視点で読み始めたこの本だったが、個人的には「一般論」というよりも「著者の子育て」を書いている本だと思った。 とはいえ、著者のお子さんは有名な賞を受賞しているようなので、そういう意味では「客観的にも」子育てに成功した、と考えられるかもしれない。 ただし、アメリカ在住というところも忘れてはいけない。 この本を通して私が感じたのは ・子供も「ひとりの人間」として尊重する ・「子育て」は自分の人生の一つの側面で、全てではない。自分の人生を生きることが重要。 ということだろうか。 子供は周りの環境や親の背中をみて育つ部分も大きい気がしたので、これがいい方法かどうかは、どう取り入れるかかな?と思った。
0投稿日: 2022.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が育児に際して、気をつけていたことなど非認知能力の育て方に焦点を置いたもの 非認知能力とは、何かという説明はないので、それが何かはよくわからなかったが、 子育てに関する記載には共感できるものが多々あり、とても参考になった。 特に子供の行動について、結果ではなく努力を認めてあげるなど、言い回しが少し違うだけで受ける印象に大きな差があると感じた。
0投稿日: 2022.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非常に読みやすいし納得できる。 けど、子供ひとり育てた経験でこんなに普遍のルールみたいに書けるのはすごいわ。 ちなみに著者のインスタはかなり強烈。なに見せられとんねん、って感じ笑。インスタからも著者の強い自己肯定感が伺える。 以下、メモ。 非認知能力とは、数値化できない。くじけない、想像、コミュニケーション、問題発見と解決、行動、やり抜く、我慢 早期教育ーなんのためにやるのか?文字が読めたら本を読めて楽しい、英語を話せたら他の国の人とも話せる レジリエンス 逆境からも這い上がる折れにくい心 家庭での非認知能力の伸ばし方 ルール(どうなりたいかを考え、こどもと一緒に作る。) 豊かな対話とコミュニケーション 思いっきり遊ぶ 育児とはなんのため?我が子が自立して幸せに生きられるようにサポートする 安全な環境ー存在を認め、個性を認め、楽しむ ルールを決めれば自由になれる、自制心、達成感、ママもしつけに迷わない シンプル、年相応、こどもと一緒に作る。 どうでもいいルールは作らない。宿題も、失敗したら自分で工夫するようになるから、言わない。 ヘリコプターペアレンツにならなくてすむ 例えば 基本ルール 家族の責任ある一員、自分のことは自分で。 do テーブルマットをしく、挨拶、朝食を家族の分作る don't 怒鳴らない 嘘をつかない 夜10時から7時はママ終業時間 こどものなぜ?は対話のきっかけ。単に気を引きたいだけのときも。 テレビやパソコンでは言葉は覚えない。 今日はどうだった?廊下の飾り、頑張ったね! 親はちゃんと見ているという安心感 子供に指示するのではなく対話を通じて、答えを自分で導けるようにする ひとつのおもちゃを2人で使うにはどうしたらいいかな? 読み聞かせは語彙力を増やす テーマを決めて本を選んだり、子供がすぐ手に取れるところに辞書や図鑑を置く 怒鳴らない、否定的な声かけしない。階段で遊ぶと落ちてママが悲しい、とか、論理的な順序を辛抱強く教える 努力をほめる。点数を誉めるとチャレンジしなくなる。 丁寧な声かけが衝動を抑え自制心を育む マインドフルネス 今ここで起こっていることに集中すること 絵を描いたり、心を穏やかにする フィーリングボード 感情を観察して客観的に分析する 感情で決めずに論理的に考えられるこどもを育てるには親との論理的対話が必要 テーマを決めてこどもと話す。今日の出来事 外遊びは子供の脳の発達に不可欠 子供の仕事は遊ぶこと。早期教育で知識偏重になると、精神的に不安定になりやすい 特にスポーツは必ず負けるときがあるのでレジリエンスを高める 家庭で自己肯定感を育てるには 声かけ、話をよく聞く、親が感情的にぬらない、子供に感謝する、他人でなく過去の子供自身と比べさせる、長所を伸ばす、子供自身に決めさせる(選択肢を3つくらい用意)、代わりにやってあげるのではなく手本を見せる 親のストレスは子供に伝染する 家族以外の人間関係を大切に(ママ友はつい子供の話。比較してしまう。) やらないのも立派な選択肢 豊かな人生にはパッションが必要。夢中で好きになれるもの。パッションは酸素。 アメリカでは専業主婦はいなかった。子供を預けてボランティアしているひともいた。 国連の定義 人間開発のための仕事 有償、無償、ボランティア、クリエイティブなことや趣味など自分を育てる仕事 他の人が何か言ってきてもso what? パッションで食べていけないから諦めるのではなく、パッションを続けるためにどうしたらよいか。 子供のパッションは何かよく観察しよう。さまざまな挑戦と出会いを経験させよう 子供は無条件に親を愛して親を育ててくれる。子供の非認知能力を育てることは自分の非認知能力を育てる
1投稿日: 2021.12.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ0-10歳の子供とタイトルにあるけど 意外と大人も10代も得られる視点はありそう 非認知能力というと堅苦しいかもしれないが 子どもを1人の人間としてみて自立のサポートをすること 子供との対話も実は面倒大変…と正直に書いてたのに好感持てた。 第5章の実践∶家庭で子どもの自己肯定感を育む12の方法が、共感の嵐だった!
0投稿日: 2021.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者のアメリカでの生活を元に、いかに非認知能力が大切か、どのように家庭で育てるかがかかれた本。 これからの時代、ますます重要になる能力。 筆者が行っていた、家庭でのルールづくりはぜひ取り入れたい。
0投稿日: 2021.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ非認知能力の内容や、心理学の実験など、もう知っていることも書かれていて目新しさはないものの、パッションが大事という考え、パッションで食べていけないなら、経済基盤となる有償の仕事を探せばいいという内容に大きく納得。参考にしたい。
0投稿日: 2021.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもと一緒にルールを作る、遊びから色々なことを学ぶことが、なぜ?・なんのために?と問いかける、感情的でなく論理的に話す、間違いは素直に謝るなど…教師をしている自分にとって、家庭での子育てと学級経営の大切にすべきポイントは同じだということに気付きました。 親だから100点の子育てをしないといえない!というのはしんどいので、80点できていたら良いという考え方をもつ。これも、気持ちに余裕ができるという面で共感です。面白かった。
0投稿日: 2021.08.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ非認知能力って言葉は知っているし、聞いたことあるけど実際に説明してみてと言われたら難しい…。 この本を読んで少しですが分かったような感じがします。
0投稿日: 2021.06.12 powered by ブクログ
powered by ブクログとても共感できる本でした。 確かに、そうだな、と思えること、気付かされることがたくさんあり、教育に興味がある方々にお勧めしたい本です。
0投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ非認知能力は大事だってわかってるけど 結果がすぐ見えないから、ついつい結果の見える 認知能力が気になってしまう。 でもヘックマンの実験や、著者の娘さんが非認知能力が求められる全米最優秀女子高生コンクールで優勝する結果を見ると生きる力の大切さを感じる 幼児期からの読み書きや計算などの詰め込み教育はせず、勉強しろとも言わず、ドリルもやらず、テレビやゲームも禁止せず。 ルールをつくる 対話する 自己肯定感を高める会話 論理的な会話 とにかく遊ぶこと 子ども同士で遊ぶ 外遊び 子供のフロー状態、ゾーンに入ったときを見逃さない
1投稿日: 2020.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログなるほど…とうなずく部分が多いものの、実践できるかとなると。。。 これが出来たからこそ、ボークさんの娘さんは全米最優秀女子高生になれたんだろうなぁ…と思います。
0投稿日: 2020.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログワーママはるさん推薦 読みやすいと言えば読みやすいが 参考文献にある本をなぞっていると言う印象もある。 参考文献にある本を読んでいたら、 新しい発見は少ないかも。 ややエッセイ風な本。 タイトルを見て、 もう少し論述系の本かと期待してしまっていた。 第1章非認知能力とは 非認知能力とは、 主体性、柔軟性、想像力、自制心、自己肯定感、自信、回復力、やり抜く力、社会性、協働力、共感力など 非認知能力が注目されるきっかけ 2000年にノーベル経済学者を受賞したシカゴ大学のジェームズ・ヘックマン教授の幼児教育の研究から この研究によると、 就学前の幼児教育を行った子どもと 何もしなかった子どとを比べたところ、 高校卒業率や平均所得、生活保護受給率、犯罪率に大きな差が現れたと言うもの。 幼児期には詰め込み教育で 学力を伸ばすより 非認知能力の基礎を身に付けて 魅力的な人間性の土台を築く方が重要だということがわかった。 非認知能力が高くなれば、学力も高くなる 非認知能力が最も伸びるのは0から10歳頃の時期 家庭で伸ばせる非認知能力 ①家庭のルール作り (世の中のルールがあることを教えて守らせる) ②豊かな対話とコミニケーション (表現する力と自信を養う) ③思う存分、遊ばせる (遊びの中から問題解決能力を伸ばす) 意識したこと ①子育ての目的を明確にする ②子どもが安心してチャレンジできる「安全な環境」を作る ③子どものもつ力を最大限に引き出すため労力を惜しまない ④自分も子どももありのままの姿を受け入れ、認める 第2章ルールを作る 欲しいものは1回で買わせない 衝動買いを我慢させるようにする 「欲しいものは何でも買ってもらう」 のが当たり前だと 「やってもらって当たり前」 と言うメンタリティーを形成され、 感謝の心が育たない。 これでは非認知能力も育たない。 第3章対話する (3000万語に書かれていることのなぞりがほとんど) 論理的に物事を考える子に育てるためには、 親との論理的対話が不可欠 自己紹介を数パターンつくる 能力よりも努力を誉める 子どもの「なぜ?」は「どうしてだと思う?」と返すことで、考える力を伸ばす 第4章遊ぶ 早期教育で知育偏重になった子どもは 精神的に不安定になりやすい 外遊びは子どもの身体能力を高め、脳の活動を活性化させ、非認知能力をあげる 自然の中で遊ぶ機会の多い子どもの方が、自己肯定感が高い傾向がある 第5章子どもと自分を受け入れる 人と比べるのではなく、 今日の自分と昨日の自分を比較する。 親の幸せは子どもに伝染する 母親の幸福度が下がった場合、 最も不利益を被るのは子ども 母親につきまとう子育てのプレッシャー5選 ①自分のために時間を 使ってはいけないと言う強迫観念 ②自分はきちんとやれていないのでは ないかという自信のなさ ③もっともっとやれるはずだという焦燥感 ④皆と同じにやれているか?という不安 ⑤私は誰?と言う自己喪失感 第6章「好き」を見つける 非認知能力を育む入り口が「好き」 子どものパッションを探し、支えるのが親の仕事 習い事は、 始め方と辞め方のルールを決めておく 常に「何のためにあるのか?」を問う 「あなたは、何のためにそれがしたいの?」 「何のためにそれをしているの?」 →子どもに1番になる、お金持ちになるなど 自己実現にとどまらない大きな目的意識を持たせることができる 親にもパッションが必要。 「どうしたらそれを続けられるか?」 と子どもに問うことも大切 ⇒親の質問力も重要だと感じた 著者は、 ライフコーチでもあるので、 質問力も試される部分が多いと感じた。
0投稿日: 2020.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログご自身の経験に加え、教育の研究結果に基づいたエビデンスが提示されており教育方針を立てるうえで大変参考になりました。特に家庭内でのルール作りはマネしようと思いました。 親としてだけでなく、職をもち、自分自身も大切にして生きていくために必要なヒントが多く、母親業だけで縛られないライフスタイルを目指す人にはとてもおすすめです。
1投稿日: 2020.03.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ学力などとは異なる、目標に粘り強く向き合うなどの、数値にしめされない非認知能力の育て方について書かれた本。読む前から分かっていたが、子育ての親に向けた本である。つまり、子どもの非認知能力の育て方だ。 こんな風に育てられたかったーってなる。 当たり前だが、育てる側の大人に非認知能力が備わっていない限り、子供のそれを育てることはできないので……じゃあ結局、非認知能力が低く、自己肯定感の低いような大人はどうしたらいいんだろうねってなった。 3歳児神話が嘘であったように、大人になっても非認知能力を育てる方法が知りたい。
0投稿日: 2020.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ルールは人を解き放つもの」について。オケをやっていて思うのは、楽器も楽譜で縛られているからこそその中で自由を味わえるということ(アドリブとかあるジャンルの音楽はまた違うのだろうけど)。家でのルールを決めることの効果が6つ挙げられているけれどどれも納得。小さいころからなるべく「危ない」と言って制限しない例として滑り台が挙げられていたけれど、私も同じように、たとえば登り物の場合、手でしっかり掴むんだよ、と言ってコツを伝えるようにしていた。スパゲッティタワーのゲームは楽しそう。「So what?(だから何?)」は意味は違うけれど、直前に読んだ安宅和人『イシューからはじめよ』にも出てた。「非認知能力」を育む入口となるのが「好きという気持ち」だということには実感としてたしかにそうだと思う。赤ちゃんが足の指を見つけて口に入れる行為はよくあることなんだなと認識した。うちでもやってる。
0投稿日: 2019.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
一体験談をあたかも子育ての本質かのように綴られている。エッセイとしてならなんの問題もないのだが、学術書ではあり得ない。間をとって啓発本といった趣き。 3人の父として実感するのは子育ては子どもの性質に大きく依存、左右されるものであり、そもそも一人っ子の母に子育て論を諭されても「そういうケースね、ここは長男に当てはまり、ここは次男、んでここが三男っぽいね」くらいにしか思わない。 これはこれで結局「こうすればうまくいくはず、うまくいかないのはやり方の問題で子どもじゃない」って母親を追い詰めている。 つまり凄かったのは夫と娘、著者は根っから自己肯定感が強く、きっとそのせいで子どものときにいじめられたり、大人になって恥ずかしげもなく1人の子育てでこんな本出しちゃった。
2投稿日: 2019.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ同著者の他書籍と重複する内容も多数あったが、終始非認知能力について自身の経験に基づく経験とエビデンスがシェアされており、学びの多い一冊だった。 個人的には、スーパーマザー症候群への言及に対する共感度が高かった。
0投稿日: 2019.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ心に響いたこと↓ 親の自己肯定感を高めること 家族みんなでルールを決め、それをみんなで守ること 子どものパッションを見つけて伸ばすこと 課題に直面したら解決策を一緒に見つけていくこと
0投稿日: 2019.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ母親の目線から、ご自身の経験を基にした子どもの育て方について書かれていました。 これまで脳科学や児童心理学などの本も読みましたが、どれも切り口が違うだけで、しなければいけないことは同じなんだなぁと再認識しました。(だからといって実践できているとは限らないのですが...トホホ) 明日からの生活に活かしていきたいと思います。
1投稿日: 2019.08.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ文章が好き ◯ 作品全体の雰囲気が好き ◯ 内容結末に納得がいった また読みたい ◯ その他 「非認知能力」を育てるには自己肯定感を育む必要があるが、 こどもの自己肯定感を高めるためには、親自身の自己肯定感も高めなければならない。 まずは自己肯定感を高めるところからだな、私。 本文は読み流すつもりでいましたが、読んでみたらなかなか読み応えのある内容でした。 子育てのヒントを得るつもりが、自分自身の生き方の気づきを得ることもできました。ちゃんと読んでよかった。 子育てって、親も育てられるって、ホントですね。 ただウチの子は 怒鳴らないで論理的に、なんてことが通用しないのです。 そんなことができるならとっくにやってるわい、と思ってしまったので、☆1つ減らしましたが、 いやいや、そうできるようになるまで、親も辛抱強く、子に寄り添っていかなければいけないのですね。
1投稿日: 2019.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019.3月。 これからの学校教育で行われるアクティブラーニングとやらを少し前に体験してきておもしろかったので。マネするつもりはないけど、なかなか参考になった。ルール作り、対話、遊び…。自分で自分の人生を楽しむことができるように、自分で自分を幸せにできるように。
0投稿日: 2019.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログさすがのボーグさんの本ですが、うーん、お金、子供が一人という手間的に難易度が高い。P32 こどもの安全な環境の為に、「こどもの存在を認める」「個性を認める」「子どもが楽しむことを重視した環境」p89 否定的な言葉を用いると、自己肯定感を下げ、自発的にやろうとする気持ちを下げる。肯定的な言葉を掛ける。P99 マインドフルネスで自制心を高める。「マインドフルネス」とは、「今、ここで起こっていることに集中する心の状態を作り出すこと瞑想やヨガなどを用いて冷静で静かな心を穏やかにするマインドフルネスの状態を作り出す」P102 こどもに対して命令と支持を止めて親が一方的に「~しなさい」「言ったとおりにやればいい」と言うのを止め、子供の意見を聞く。「あなたならどうする?」「どうしてそう思うの?」などと尋ね、話をさせ、感情的な判断から離れた徐々に論理的な結論を導かせる。大人から意見を求められることで自分の存在意義を感じ、自分の思いを表現することで自信もつき、自分の意見に耳を傾けてくれる人がいることで自己肯定感に繋がる。 ★★★P148 自己肯定感が高い人の特徴には。・何かを成し遂げようという気持ちが強い。・悩みや不安を感じて落ち込むことが少ない。また、落ち込んでも立ち直りが早い。・感情的になることが少なく、いつも精神的に安定している。・相手の話を素直に聞くことができる。・仕事や学業、決めた目標などに対して、途中で挫折することが少ない。・障害があっても、柔軟に対応策を練り、やり抜くことができる。・自分を素直に表現でき、人のことも素直に受け入れられるため、友人が多い。自己肯定感の高い人は挫折やストレスに強く、やり遂げようとする意志が強いので、結果的に学業や仕事の成果が上がりやすくなる。結果を出したことで達成感も高まり、実力に応じた自信が付く。また自分も他人も素直に受け入れることができるために周りに人が自然に集まってきて、良い循環ができる。 ★★★P149 家庭で子供の自己肯定感を育む12の方法。 1. こどもに頻繁に声を掛ける 2. こどもの話をよくきく。 3. 親が感情に左右されない。 4. 子どもに感謝する。 5. 子どもをよく見て、よく褒める。 6. 子どもを他の人と比べない。 7. 欠点を直すより、長所を伸ばす。 8. 子どもに決断させる。 9. 選択肢を用意して、自分で決める力を育む。 10. やってあげるのではなく、手本を見せて手伝う。 11. 子どもの感情が爆発したときは、子供を責めない。 12. あるがままの子どもを認める。P167 世間体より大切な子供の気持ち。
2投稿日: 2019.01.14
