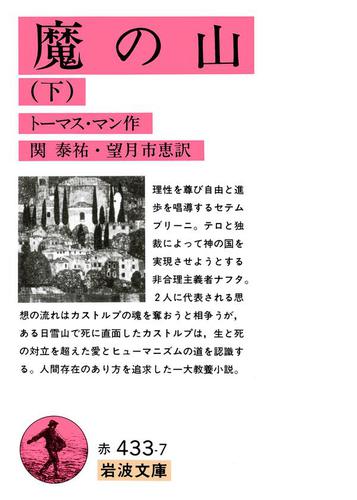
総合評価
(24件)| 10 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ1999年に観た2本の映画「マトリックス」と「ファイトクラブ」が、四半世紀たったいまもfavouriteだ。この2本の映画は、ひたすらに画面が暗い。暗い画面の中に、ひとりの憂鬱な男。クソみたいな人生。しかし、男はやがて気付く。こんな世界は偽物だと。ザックの声と、ブラック・フランシスの声が、目を覚ませと、魂はどこにあるのかと、呼びかける。こんなにも気持ちを昂らせてくれる映画はそれまで観たことが無かった 私がトーマス・マンの「魔の山」を読んだのは、その3年後くらい、2002年の頃だった。「魔の山」のラストシーンで、私は同じような、いやそれ以上の気持ちの昂りを感じた 「魔の山」のラストシーンでは、「社会や人生を変えてしまうような歴史の転換点においては、その転換点の直前であればあるほど、遠い昔の出来事であるかのように思われる」と語られ、ハンス・カストルプは7年過ごしたサナトリウムを離れ、第一次世界大戦へと向かって歩き出す それの何が昂るのかというと、別に戦争に行きたいわけではない。抜け出せない泥沼の中で長い間苦しんだ後に、主人公は魂としか呼びようのないものを手に入れて、さらに苦しい絶望に向かって歩き出す。その姿を描くトーマス・マンの文章が、私の背中を押してくれているような気がして、生きていく勇気が湧いたのだ 魂を掴んで歩き出した後、一度だけ振り返ってみると、その転換点直前の出来事は遥かに遠く感じられ、その転換点というのは、2本の映画においては21世紀のことだったし、「魔の山」においては第一次世界大戦だったということだと思う トーマス・マン。なんてイカれたチョビ髭オヤジなんだ!って思った
0投稿日: 2025.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ一人の青年が街から遠く離れたサナトリュウムという特殊な社会で、色んな影響を精神的にも肉体的にも受けて成長していくが、結局戦争というごちゃ混ぜな渦の中に消えて行くという…
0投稿日: 2025.04.17 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
上巻に引き続き、サナトリウムで過ごすカストルプ いつのまにか従兄弟よりも施設に馴染み、さまざまなことに興味を持ち楽しんで過ごす 従兄弟のヨーアヒムは、ここの生活、治らない自分に苛立ち、早く普通の生活に戻らなければとあせっていく やがて、ヨーアヒムはついに医師の忠告を振り切り、軍隊に帰っていく 月日がたつにつれ、季節はうつり変わりにそして、カストルプは植物に興味をそそられ 瞑想にふけり、セテムブリーニやナフタの宗教や、思想に耳を傾け、サナトリウムに溶け込んでいく、怖いくらいに‥ もうこの世界から抜け出したくない 抜け出せなくなっていく まさに魔の山 雪山で遊びながら遭難しかけたり、周りの人々との関わりの中でさまざまな感情を捏ね回す どんなにあがいても、サナトリウムの中でのこと で、守られていることに気がついていたのだろうか やがて最愛の従兄弟が帰ってきて、最後の別れとなるあたりから、ますます魔の山に飲み込まれていく サナトリウムの壁のような存在になるまでには 何年もの歳月が必要ではあったけれど それは 「長き間の束の間」 思想や宗教に関する話にはなかなかついていかれないがそんな話の中にも現実みがないような 狭い世界での討論に聞こえてせつなくなる そして突然迎えるカストルプの転機 これは、作者の作品の中断にも関わっているのだろうか? 第一次世界大戦と言う悲惨な歴史の中に主人公を放り投げ、物語もまた投げ上げてしまった 当時の世界情勢に飲み込まれていくようで これもまたせつない サナトリウムでの、出来事のあれやこれは なんだか楽しく読めたので、満足
38投稿日: 2025.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻では自分の従兄が死亡してしまう。そして交霊術が行われ従兄とであう。山を下りて軍隊に入り爆撃の場面に遭遇して歩き回るところでこの小説は終わる。 会話以外の説明のところでトーマス・マンの思想が書かれているのであろうがはっきりとはわからない。
0投稿日: 2024.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログセテムブリーニとナフタの論戦が所狭しと繰り広げられるが、肝心の登場人物たちの造形は、いささか記号的人物のように感じられて仕方がない。/ 第一に主人公ハンスだが、ショーシャ夫人に心惹かれるが、彼女がいったん山を降りると、手紙のやり取りで恋情をつのらせることもなく、たちどころに夫人を忘却の彼方へと打ち捨ててしまったように見える。 また、『八甲田山』ばりの死の行軍に足を踏み入れるも、肺に浸潤を抱えているにもかかわらず、生還後に深刻な病状悪化があった様子など微塵もない。/ 第二に従兄弟のヨーアヒムにしても、明るくて豊満なマルシャに惹かれるが、胸の内を告白するでもなく、ハンスに恋の悩みを打ち明けるでもなく、とうてい血の通った人間とは思えない。 おまけに、彼自身はさほど興味を持ってはいないはずのセテムブリーニとナフタの論争を聞くために、従兄弟に毎回つきあってやるというのは、軍人として生きるのを志す人間にはおよそあるまじき救いがたい主体性のなさだ。 彼はなぜ、ハンスとは別行動をとって、可愛いマルシャが視界に入る範囲内で、時を過ごさなかったのだろうか? このような彼の行動は、彼がハンスを愛しているという場合以外には、およそ考えられないものだ。 ずっとそういう不満を抱えながら読んでいたので、自らの死期を自覚した彼が、初めてマルシャのかたわらに立った姿は感動的でさえあった。/ この物語、僕はどうしても感情移入して読むことができなかった。 愛すべき人物が一人も見出せないのだ。 マドンナ、ショーシャ夫人にしても、彼女はなぜいつもドアを「ガチャン、ガラガラ」と開け閉めするのだろうか? 少しでも自らの美しさを意識している女性なら、普段の立ち居振る舞いにも当然それにふさわしい細やかな気配りがなされてしかるべきではないだろうか? キルギス人のような細い眼をはじめとする彼女の描写にも、この女性ならハンスが虜になるのも当然だと読者が納得するだけの魅力は感じられない。/ セテムブリーニとナフタの論戦についても、なにしろ顔を合わせるたびに角突きあっているので、小型犬がキャンキャン吠えあっているようで、もとより『カラマーゾフの兄弟』の「大審問官」には及ぶべくもない。/ 【しかし、ナフタの世界とヨーアヒムの世界とになによりも共通していたものは、血にたいする二者の関係で、手に血ぬることをおそれないという原則であった。 ー中略ー この神殿騎士修道会士たちは、信仰を持たない人々との戦いで死ぬのを、ベッドで死ぬのよりも名誉な死であると考え、キリストのために殺したり殺されたりするのは罪悪ではなく最高の名誉であると考えたのであった。】/ マンは、終盤のハンスとショーシャ夫人の別れにはほとんどふれずに、しまいには「こっくりさん」と降霊術のエピソードにページを費やしている。 彼がいったい何を書きたかったのか、僕にはさっぱり分からない。 どう考えても、あれこれ盛り込み過ぎではないか? どうやら、マンは「鉛筆」はどうにか借りたものの、「消しゴム」は持っていなかったようだ。/ 終盤まで読んで来て、どうしてもビュトールの言葉を思い出さざるを得なかった。/ 《偉大な作家とは、登場人物に存在感をあたえられる人、つまり登場人物のひとりひとりにそれぞれ一つの声をもたせられるような人のことです。》(ミシェル・ビュトール『即興演奏』)/ 僕には、この物語に描かれた人物たちがそれを獲得しているとは到底思えなかった。/ おそらく作者であるマン自身も、そのことをうすうす感じていたのではないだろうか? 【つづられたこの詩は必ず忘れられてしまうだろう、ちょうど夢をおぼえていることが困難であるのと同じように】(本書第七章)
1投稿日: 2024.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ長期滞在が続くハンス・カストルプは、ショーシャ夫人との出来事のあとも、様々な出会いと別れを重ねていく。 まぁ、本を手に取った時点でわかっている話(700ページ近い厚さ)ではあるが、下巻もとにかく長い(汗)。ストーリーそのものだけにしぼればもっと短くできそうなものだが、音楽(レコード)やオカルト(こっくりさん的な降霊術)などにハマる長々とした描写も含め、ダラダラと論争や語りが続くところに意味のある小説なんだと思う。 上巻以上に重要な出会いと別れが続き、単調であるはずのサナトリウム生活には話題が尽きない。多様な登場人物との触れ合いがこの小説の魅力だ。病いと死に隣り合わせのため、面白おかしいというわけにはいかないが、下界とは一線を画する環境であるゆえの人物描写が独特の味わいをみせている。 本書最大の山場はおそらく、第六章にある節「雪」だろう。スキーに出た雪山で吹雪におそわれたハンス・カストルプは、幻想的なビジョンを夢で見たあと、対照的な思想を持つセテムブリーニとナフタの論争を超越し、理性に代わって生と死の対立を超える「善意と愛」に目覚めていく。 後半でハンス・カストルプに大きな影響を及ぼすペーペルコルンが物語に活力を与えている。三角関係のようになってしまうショーシャ夫人との顛末も面白く、素直に楽しめた。 作中で「人生の厄介息子」と称されるハンス・カストルプの生き様は、現代でいえばニートに類似するものではあるまいか。訪問者が時間の感覚を失って居座ってしまう、この「魔法の山」での生活のなかで、生と死、社会と人生における広範なテーマを模索し学び、長いモラトリアム期間を過ごしたあと、現実に戻っていくというような、青年期におけるイニシエーション的な奥行きがあると思った。 映像的かつ詩的なラストの描写には大きな感動を覚えた。ああ、そうなるのか、と。 非情に深い感慨を受けた本作。一読では消化不良の部分もあるため、ぜひともいずれ新潮文庫版も読んでみたい。
6投稿日: 2023.08.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局完全に理解できないまま読破してしまいました。けれども読み終わってから、心がゾワゾワするような感じがします。いつか再読したい作品です。
0投稿日: 2021.11.02 powered by ブクログ
powered by ブクログこの上下の大長編を読み終えて無言で本を閉じることはありえるだろうか。否、ありえない。私たちはニヒリズムという平行線から逃れ、ベルクホーフという山あいで生み出した綜合的な思想の萌芽を見逃さずにはいられない。退廃主義、退嬰的、ニヒリズム、ペシミズム、デカダンス、などありとあらゆる悲観主義を表す言葉は物語上では一定の水準に収まった一個人の叫びにすらならない悲壮の体現者の特徴にしかならず、どのような感受性も生まれない。それに対してトーマスマンはセテムブリーニの啓蒙主義とナフタの原初主義かつ神秘主義の思想がぶつかり合わせる弁償的論理でハンス・カストルプに新たな見地を植えつけた。その後ペーペルコルンの身に起きたことも含め、全てがバランスの上で螺旋状に向上する物語であったといえよう。それはある意味、たった一つの世界の定理を求める問いであるように思えた。
0投稿日: 2020.02.11 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
巻末の解説で「ハンス・カストルプには、一貫した魂の発展はなく、それに、この主人公はまこtのい受動的な主人公で、小説の主人公らしくない主人公である。彼の特徴は決断をしないことと、精神上の印象にたいして感受性が強いことである。」と書かれている。しかしそんな彼は何故か人を結びつける力も持っており、そんな彼の周囲の人々が繰り広げる陣取りを俯瞰して眺める物語が『魔の山』なのだと思う。 ところで最後に垣間見た彼は魔の山にいた彼と同一人物とは思えない状態だったが,これもまた人間の可能性だ。『服従の心理』に書かれているエージェント化のことや『夜と霧』で語られる極限の世界のことなどが頭の中にちらついた。 『魔の山』は一度読んだくらいでは分からない。何度読んでも理解に到達できないと思う。が,何度でも読んでみたくなる物語でもあると思う。まずは「雪」をもう一度読んでみようと思う。 ヨーアヒムもセテムブリーニも別れの瞬間に初めて「ハンス」と呼んだ。「du」と「Sie」の持つ深い意味を理解できていない日本人には所詮わからない機微なのだろうと思うが心に刺さった。
0投稿日: 2019.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
とてつもなく大作。 様々な人が入り混じり 通り過ぎ去っていく… そしてハンス青年は変わらず… 彼の心はどこか空っぽだったのかもしれませんね。 最終的には強制的に魔の山からは 去らざるを得なくなり、 必然的にこの物語は幕を閉じます。 いつかはやってくるのですよ。 自主性を持つ日が… 結局のところセテムブリーニやナフタのような存在は 机上の空論を食っているだけで やはりどこか読んでいて違和感を覚えました。 ハンスは彼らにとっては無知の象徴でしたが 染まらなかった点では無知でないと思いましたが。 人には様々な誘惑もあり、 その中には悪のものもあります。 ショーシャ夫人がある種の堕落の 象徴なのかもしれませんね。 この版は読みづらいので 別エディションをいつか読みたいな。
0投稿日: 2018.06.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ上巻からは想像できないくらいの死。ナフタが登場してセテムブリーニとの宗教論争、政治論争、平和論争が延々と続き、終盤のペーペルコルンの登場で突然円周率の計算についてのご託がはじまって、ひょっとしたらハンス・カストルプの将来の姿かと思わせる。初読のときラストが衝撃だった。物語としては「ブッデンブローク家の人々」の方が面白いかもしれないが、サナトリウムで展開される人間模様が切れ目のない、否もしかしたらあらゆる所に切れ目があるような構造を持っているので、漱石の「我輩は猫である」のような読み方が可能かもしれない。
1投稿日: 2013.10.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻に入ると俄然興味深くなってきた。フリーメーソン会員であるセテムブリーニとイエズス会士のナフタによる論戦は20世紀初頭の時代精神を感じさせるし、そうした形而上学的議論を吹っ飛ばすペーペルコルン氏のわかり易い器の大きさとその退場の仕方は現代的だ。物語は「人間は善意と愛を失わないために、考えを死に従属させないようにしなくてはならない」という言葉が感動的な「雪」の章の後、緩やかに下山するかの様に死の景色が強くなるが、先の言葉を思い返すことでその景色を越えていくのだ。そして物語の時は止まり、私達の時が動き出す。
1投稿日: 2013.04.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に世界最高傑作とよんでいい大作。 ヨーアヒム•チームセン、ペーペルコルン氏、圧倒的な一人一人のキャラクター。 そのような一人一人と過ごす時間がずっと続いて欲しいと思うが、これまた圧倒的なフィナーレを迎えてしまう。 大学生諸君に読んでいただきたい。 そうして、十年ぐらいしたら、再読してみて欲しい。 素晴らしい感動が待っているよ。
1投稿日: 2012.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログこの分厚い(原文1200ページ)のドイツ小説でマンが為したこと、ハンス・カストルプ青年が為したこととはなんだったであろうか。 ここでふいに一言で置き留めてみるならば、それは時の引き延ばしと押し縮め、それによる自由の獲得であった。カストルプ青年はベルクホーク(サナトリウム)に降り立つやいなや、時の概念へ疑問をもつ。それはほかならぬ、彼自身が鋭敏に感じとった時からの逸脱、そしておとずれる自由への予感である。彼は時の収縮と弛緩との繰り返しによるその停滞を見抜き、ついにはそこへ足を、手を、頭を差し込んだのである。 いかにして時は停滞するのかー それはマン自信がふれてきた死への、解説者も後編にて語る「親愛感」その向こうにある死の完成、完全、実現である。現実としての死への到達、それのみによって人間、生命は時間の流れから逸れ岸辺にあがりこみ、自由の河原、その向こうの繁り多い大陸へと目をむけることができるのである。 余談、まったくの余談、この小説の価値を貶めることは一切ない指摘ですが、682ページの「セテンブリーニ」は誤植でしょう。
0投稿日: 2012.06.24 powered by ブクログ
powered by ブクログサナトリウムという特殊な閉鎖された状況下で主人公が様々な経験を通じて肉体的・精神的に成長する様を描いた教養小説。 哲学的な内容から宗教、民主主義、失恋などテーマが盛り沢山で読み始めは難解なものかもしれません。難しいとお感じになられた方は「時」の流れに注目しながら読み進めることをお薦めします。何と言おうと物語の舞台が世俗と切り離された空間なのですから。 一度読むだけでは理解しきれないほど奥が深い作品です。幾度と読む度に新たな発見があることもこの小説の魅力と言えましょう。 内容が難解で文量が多いため敬遠される方もいらっしゃいましょうが、声を大にして読んでほしいと言える傑作です。
0投稿日: 2012.03.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ世界史にも出てくる名著。 正直かなり長く、読むのがしんどかったが、途中から引き込まれていったことは否定できない。 非現実的な「魔の山」と主人公の生活ぶりは、とても面白かった。 最後の急展開には驚いたし、生きて帰ってきていたらいいなと思う。
0投稿日: 2011.11.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ日常の幸福と恐怖は眼にはみえない。その「狒狒」は中指をあげてファッキューという。 それは当人が死亡したときであり、神や論理に敬虔深くともかまいやしない。
0投稿日: 2011.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ本当に断片的な読後感をつらつらと書いて、後日また書き直すと思う。 ・所々に(共感の意味でも反発の意味でも)気に入った言い回しがあったり、自分が好きそうな哲学めいた文章があったのでそこは楽しめた。だが、物語を楽しめた気にはなれなかった。 ・長編小説を読んで、思い入れのある登場人物がほとんどいなかった小説は初めてかもしれない。しかし、その希薄さが重要な気がした。主人公の希薄化。(普通の定義は難しいが、)主人公が極めて普通に近いということ。 ・最後に主人公ハンス・カストルプに山を下らせたものが何だったのかまだ言い切れない。他にも登場人物の行為でわからないことがある。だから、わからないことが多くてとても引っかかる小説なので、この点ではすごく楽しいと言っていい。 ・村上春樹が「魔の山」を意識しながら「ノルウェイの森」を書いていたのが、物語の途中にもたびたび思い出された。 ・最後の問いかけはずるい。 こんなに適当なことをコメントしていいのか、いや、まずいのだが、このよくわからない読後感を書き出しておきたい気持ちが強いのだった。
0投稿日: 2009.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログマンの超大作の下巻。中心的な登場人物はハンス・カストルプ、セテムブリーニ、レオ・ナフタ、ペーペルコルン氏。ハンス、ヨーアヒム、セテムブリーニ、マダム・ショーシャのあいだで保たれていた均衡が破れる。マダム・ショーシャの転院もさることながら、最大の原因はレオ・ナフタという反近代的――反セテムブリーニ的――な知性の登場である。ハンスは、セテムブリーニの人格には好意を抱き続けるがナフタの懐疑的で破壊的な知性に取り込まれかかる。しかし、そこでさらに登場するのが反知性的な権力者としてのペーペルコルン氏である。ハンスは、ペーペルコルン氏の登場によって知性への憧れを曇らされる。このような展開のなかでハンスの立場にある読者は行き場を失う――いかなる指針の下で生きればいいのだろうか。マンがハンスに与えた解決は穏やかな死だった。結局、理性的でも反理性的でも反知性的でもあるより前に人間は自然的に――すなわちいつかは必ず駄目になる身体として――生きているのである。結核療養所という環境に置かれながら、そのことに最後まで気づかないハンスが滑稽でもあり、同時に「明日は我が身」のようでゾッとする。
0投稿日: 2008.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ難解。きっと何度読んでも読むたびに新しい訓が得られるに違いない。 食堂、横臥療法中の音楽鑑賞、ショーシャ夫人の肖像画、は面白い。 ヨアヒムの死は美しいし悲しい。 手回しオルガン弾きと生臭坊主とは胡散臭い。 ハンスは何故下山し戦地に赴き空しくあっけなく散ってしまうのか、その意味がまだ理解できない。
0投稿日: 2007.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻ではハンスはすっかり魔の山に毒されている。 ペーペルコルン氏はあまり好きじゃない。むしろ、ペーペルコルン氏の「人物の大きさ」に惹かれ、でもセテムブリーニ氏を「愛すべき」というハンスが好印象。 終盤、サナトリウムがヒステリーに満ち、同時に平地でも戦争が始まる部分の雰囲気が、時代の空気を表しているようだと思う。
0投稿日: 2007.02.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ中学生の頃から何度も読んでます。 主人公は魔の山に入り、白血病(だったっけ?)を直そうとするのだが、その感じがとってもノラーリクラーリ描かれています。 健康に良い黒パンをまいにち食べるのだが、その黒パンとチーズの組み合わせの表現の美味しそうなことと言ったら! 何が面白いって表現しにくいが、本読みだったら、一度夏の暑い時、もしくは冬の寒い日に、家から一歩も出ずに3日位かけて読むと、とても良いと思う。
0投稿日: 2006.05.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ療養生活を終えたハンスが向かったのは、戦場だった。 あらゆる混沌を抱えたまま銃を片手に戦地をつきすすむ彼の後姿は、爆煙の彼方に消える。人的資産の浪費として、第一次世界大戦を痛烈に批判。
0投稿日: 2006.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログナフタ登場で上巻より愉快度は下がるが、それでもトランプで駄目人間状態(?)のカストルプ青年などミドコロは多い。
0投稿日: 2005.02.10
