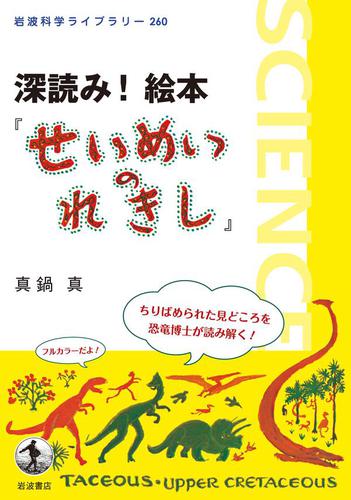
総合評価
(13件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ第47回ビブリオバトルinいこまテーマ「かえる」で紹介された本です。チャンプ本。 2017.6.25
0投稿日: 2024.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
「絵本 せいめいのれきし」の解説本。 歴史……そう。歴史は新しい情報が出てくることで変わる。本が出版された当時の情報と今は変わってしまってる部分は『改訂版』として新しい絵本を出している。という話から始まり、絵本の中には収まり切らなかった情報をこれでもかと事細かに説明している。 しっかり、『絵』の引用をして、ここに書いてあるこの生物は~~という説明になってる。 絵本を読むときは文章を中心に見てたので、『絵』で解説あるのがいい。こんな動物いた?? え?これって、馬? ん?サル??と新たに発見しながら、絵本と見比べて解説本を読んだ。 面白い。絵本への愛があふれすぎていて、細かい。 もちろん、新しく見つかった化石や、図解なども載っていて絵本に出てきた生物の事がより分かるようになっている。 一番面白いと思ったのは 「チキンを食べながら学ぶ鳥類進化」44p 小タイトルからして、ナニコレ?だけど、読むと骨の説明をしつつ、『今度食べたときには気にかけてみてね』という話だった。雑食な人間が一番怖い。 女性の古生物学者になったかもしれないメアリー・アニングの話も興味深かった。 彼女の家は恐竜の化石を発見して家計を立てていて、彼女も多数の化石を見つけたという話。当時、女性差別が激しくなければ、彼女は発見だけではなくて研究もしていたのではないかとなっていた。そういう女性がいたことが素敵だなと思う。 解説本も素敵で読んでいてワクワクした。 ごちそうさまでした。
0投稿日: 2024.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵本『せいめいのれきし』の解説本。絵本から注意すべき点を絞り、科学的な解説を交えながら深く読むためのガイドブックとして機能している。
2投稿日: 2023.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵本「せいめいのれきし」の各ページに関する解説。子どもに読んだときはかなり端折ったりかみ砕いたりしつつ読んでいたのだけれども、もう少し大きくなったら絵本を持って国立科学博物館に行くのがよさそうな気がしてきた。 あと、学説の変化に伴って恐竜のポーズを変えたという話が、とても興味深かった。他にもそういうもの、あるんだろうな。ついつい企画展ばかり行ってしまうけれども、国立科学博物館の常設展をじっくり見に行きたい。
0投稿日: 2019.10.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
恐竜博士による「せいめいのれきし」の解説書。 原本(絵本)がなくても、この本単体で充分に楽しめます。 図のあるページはカラーがいいけど、フルカラーでなくとも良いのでは。こんなに重たい「岩波科学ライブラリー」って、初めてかも(笑)。
0投稿日: 2019.10.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵本「せいめいのれきし」が半世紀以上前に書かれたとは知らなかった。その後に得られた科学的知見を踏まえて改定されたとのこと。さっそく改定前と比較しようと、改訂版を購入した。 本書は図を多用しながら(当たり前か)平易な言葉で書かれているので、中学生くらいから読める。古生物を学びたい人にも格好の入門書だ。
0投稿日: 2019.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ絵本『せいめいのれきし』について、各ページを紹介しながら、その後の研究ではどのように知見がかわったのかがあわせて解説されている本でした。こんな風に過去の作品を紹介しつつ現在の知見と比較して解説を出すのは、新たな本を出すよりずっと手間のかかることだけど、こういうものが出されたら、絵本もずっと楽しむことができる。この本によると、絵本『せいめいのれきし』を読んで興味をひかれて研究者になった方も複数いらっしゃるらしい。もともと知識のない私でも楽しく読むことができた。
0投稿日: 2019.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ2018/12/25 詳細は、こちらをご覧ください。 『あとりえ「パ・そ・ぼ」の本棚とノート』 → http://pasobo2010.blog.fc2.com/blog-entry-1159.html 2018/06/10 予約 6/22 借りる。6/26 読み始める。8/4 読み終わる。 本書には、絵本『せいめいのれきし』に夢中になった著者が、専門的な立場から絵本の見どころを教えてくれます。 もちろん 絵本を見て 想像を膨らませるだけでも 十分楽しめるでしょうが、 もっと知りたい!という読者に 「バージニア・リー・バートン」さんの意図を組みながら、最新情報をとりこんだ解説をしてくれるのが、魅力的です。 絵本『せいめいのれきし』だけでは見逃しそうな「バートン」さんこだわりの絵に深い意味があることを知って、感動しました。 考古学も 進化しているので、絵本「せいめいのれきし」は改訂版が出ています。 さらに内容をよく知りたくて 本書を読みました。 2冊合わせて読むと 面白い! 絵本『せいめいのれきし』せいめいのれきし 改訂版 バージニア・リー・バートン岩波書店 ( 2015-07-23 )
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ古生物の世界はもともと苦手で「せいめいのれきし」も実はまともに開いたことがなかったのだけれど、俄然興味が湧いてきました。「せいめいのれきし」これから読みます。(逆だ!)
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ別に悪くはないけど、改訂版の『せいめいのれきし』を読めば充分かと思う。岩波と科博の宣伝みたいな本。 でも改訂版を読んだときの「ここまで石井桃子訳を変えなくても!」という腹立たしい気持ちは、この本を読んでおさまったかも。 巻末に協力者として岩波の編集者が入っているのは当然だが、東京子ども図書館のスタッフも入っていたから(東京子ども図書館のスタッフの石井桃子への敬愛の気持ちが半端ないことを知っているので)、変えたところも考えに考えてのことだろう、と。また、読んでいて著者の謙虚で公正な性格も何とはなしに伝わってきたから。 全然関係ないが、この著者、あの真鍋博の息子さんだとか。真鍋博の絵は未来や宇宙を情緒を排した線で描きながら、なぜかユーモアとアイロニーがあった。あの絵で読む前からSFやミステリーに対して好印象を持った。 真鍋博の息子が科博の偉い人になるなんて嬉しいな。
1投稿日: 2018.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ”絵本の解説”という変わった試み。 『せいめいのれきし』という絵本自体は未読。 三葉虫、メガネウラ、イクチオサウルス、ミクロラプトル、パラサウロロフス、プテラノドン、オヴィラプトル、トリケラトプス、ティラノサウルス、ディアトリマ、パラケラテリウム、ホモ・サピエンス。 恐竜の時代を中心に、有名どころはしっかり描かれている印象。 アノマロカリスは未登場だそう。 生態や進化の仕組み、絶滅に関してなど、古生物学の本としても十分。 ティラノサウルスは、小さな前足のせいで受け身がとれず、安全に走れる速度は18km/hまで、という説は面白い。 第6の大量絶滅は、現在すでに始まっているらしい。
0投稿日: 2018.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログバージニア・バートンの「せいめいのれきし」改訂版・監修者による該当絵本の説明本。 絵本の場面が章の始めにあり、場面の説明があります。説明を読んでいると、バートンさんが8年間かけて作成しただけあって、その絵の科学的な正しさや、舞台のようにして時代を象徴する生き物を描いてあるところが素晴らしいです。 1ページだけではなく、本を全体で「せいめいのれきし」を見渡せるように時代での生き物の進化を描いています。説明されることで、この本が名作たる所以がわかりました。
0投稿日: 2017.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ初版から半世紀たって新版が出版されたバージニア・リー・バートンの絵本「せいめいのれきし」の監修をした著者が、バートンへの尊敬と新しい読者への期待をこめて、分かりやすく解説。 真鍋氏の科学愛が伝わってきます。
0投稿日: 2017.08.06
