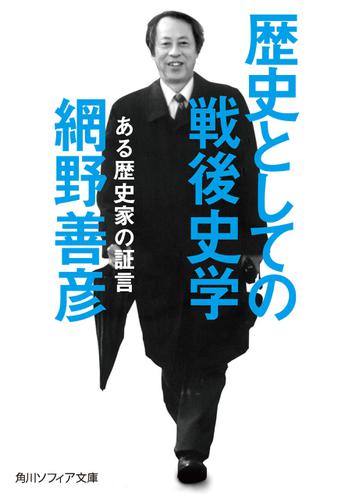
総合評価
(5件)| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログはじめに - 日本常民文化研究所における文書整理の仕事の重要性とその背景。 - 戦争犯罪人としての自覚と、自己批判の過程を経た著者の思索。 自己の変革 - 1953年に自らの過去を振り返り、過去の誤りを糧にした反省の重要性。 - 戦争犯罪人としての重い心の疲労と、その克服に向けた努力。 研究の開始と発展 - 歴史学会での発表を通じて、地方史研究に取り組む決意。 - 文書の丹念な読み込みを通じて、研究テーマとして霞ヶ浦に関するノートをまとめ、『歴史学研究』に投稿。 高校での活動 - 東京大学史料編纂所での活動や、自己の研究を続ける過程。 - 執拗に原稿を投稿し続けることで、学問の深化を図る。 マルクス主義史学の潮流 - 戦後の歴史学界におけるマルクス主義の二つの流れの存在。 - 羽仁五郎と井上消の影響を受けた流れ。 - 民族派と国際派の対立の構図。 歴史学の実践 - 歴史学研究会の大会での議論や、自己批判の重要性。 - 1955年以降の歴史学の集大成と、さまざまな論争の展開。 地方史研究の重要性 - 地方史研究の発展と、それに伴う社会的な意義。 - 文書返却のプロセスを通じて、社会的信用を回復する努力。 結論 - 過去の誤りから学び、未来に向けての歴史学の進展に寄与する姿勢。 - 常民文化研究所での活動を通じて得た教訓と、今後の研究への展望。
0投稿日: 2025.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「歴史としての戦後史」ではなく「歴史としての戦後史学」であることに注意が必要です。つまり、史学界の動きが生々しく記された書物です。史学界の方や、登場する史学者たちの書物をよく読む方に意義あるものと思います。 私は戦後史そのものに関する本だと早とちりして買って、読みながら過ちに気づきました。なので内容は私からすると予想外だったのですが、このような世界や動向があったのだとは知らず、少し世界が広がりました。
0投稿日: 2023.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ終戦時10代後半だった著者が学生のときから今まで戦後史にずっと係わってきて、どういう変遷をたどったかという話。 ……だが、戦後史が体系的にまとまっているわけでもなく、○○について主張していた○○さん達学派が、とか……知らんわ。内輪で楽しむ分にはいいかもしれないが、その分野に詳しいわけでもない一般人が教養として読んで楽しめる本になっていないと感じた(ので、途中からは正直斜め読みで流してしまった)。
0投稿日: 2022.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本中世史の大家、網野先生の目を通しての戦後の日本史研究史といった本である。あとがきで著者自ら「老人の思い出集、しかもくり事であり、いまさら書物として多くの人々の目にさらすのもはずかしく、躊躇する気持ちもあったが」とあるように、戦後の日本史学かいわいの事情とそれにまつわるテーマで著作された論述をまとめたものである。したがって少々まとまりに欠けるところがある。 この本を読もうと思ったきっかけは、他の先生がかかれた中世史の本を読んでいるときに、まるでマルクス経済学者の書くような文章で、こんな文章を書く学者が出る背景とはどんなものかと疑問に思ったところにある。 本書を読むと、そういった背景がうまれた状況もなんとはなくわかるものである。 後半にある、日本常民文化研究所の文書整理については他の書物にも詳しくかかれていた内容。渋沢敬三ほかの作品集の解説を掲載した部分はあまり本書タイトルとの関連性を感じない。
0投稿日: 2021.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ戦後の“戦争犯罪” 1 戦後歴史学の五十年 2 歴史学と研究者 3 史料を読む 4 日本常民文化研究所 5 渋沢敬三の学問と生き方 インタビュー 私の生き方 著者;網野善彦(1928-2004、山梨県、日本史) 解説:清水克行(1971-、東京都、日本史)
0投稿日: 2019.03.23
