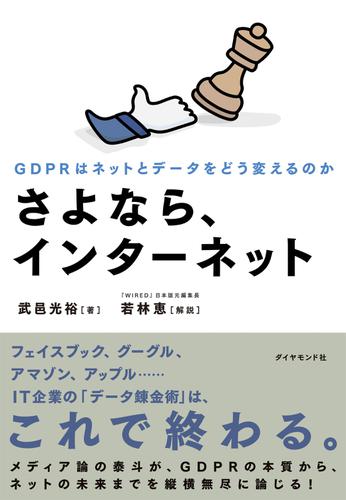
総合評価
(15件)| 1 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://www.diamond.co.jp/book/9784478105849.html , https://wired.jp/
0投稿日: 2022.01.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
EUがGDPRの導入によってGAFAなどのインターネットプラットフォーム企業への対抗を目指す動機や、その実現に向けた道筋(著者の期待含む)を描いている。 著者はGDPR立法に向けた動向を知ってからベルリンに在住しているため、立法の立役者であるSPD(ドイツ社会民主党)の果たした役割や東ドイツ時代のシュタージュによる市民監視を踏まえた市民のデータ監視への拒否感といった歴史的背景、またEU議会などが進めている各種取組の説明が詳しく、理解が深まりやすい。 読者として興味がわいたのは、鉄道や電力がそうであったように、インターネットプラットフォーム企業による特定分野ビジネスの自然独占が公共化されたり、競争法によって規制をかけられることがあるのか、またはそういった政策の検討状況について。 本書の留意点として、文章表現が独特で、著者の分析なのか、著者の期待なのか解りづらい箇所がある。
0投稿日: 2021.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ"現在のインターネットの概念"を超える世界を期待して手に取ったので、"対GAFA(特にFacebook)"の目線に寄りすぎていて、多少退屈。 主張は理解できるものの、古典や宗教など、ただでも難しい内容をさらに難しくしている感があり、あまり好きではない。
1投稿日: 2021.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログEUとEEA域外への個人データ(個人のプライバシーを特定するデータ、という意味ではなく、GoogleやFACEBOOKを利用する際に、摂取されているすべてのデータ)の持ち出しを禁ずるGDPRという法は、無料アプリの使用と引き換えに、GoogleやFACEBOOKといった一部の企業が独占的に所有している現状はおかしくないだろうか、という問題提起から、個人データは個人が取り戻すべきであるという精神に基づいて生まれた。個人データを個人が所有管理し、所有者の意志において自由に削除、あるいは他社への提供を可能にする、という考え方こそが、現状のIT巨人の個人に対する不当な監視のような歪んだ関係をリセットし、あらたなインターネット世界を構築するという提言。こういう自立性や主体性に関する概念に鋭いのが欧州のさすがなところ。日本人社会からは生まれないもののような気がした。
0投稿日: 2020.05.12 powered by ブクログ
powered by ブクログひらめきブックレビューに掲載されていたので、このデジタル時代の先を見据えるための一冊になるかと思い借りてきた、がしかし、ちょっと読みにくい本で斜め読み。 もう一度、ちょっと時間があるときに読みたい。
0投稿日: 2020.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPR とインターネットの関係を俯瞰的に見た一冊。 テクニカルな法規制としてのGDPR は見ていたけど、そのバックグラウンドや影響はあまり考えていなかった自分にとって、大変参考になる本だった。
0投稿日: 2019.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPRにより広告がダイレクトからブランドへ逆戻りする事は考えられないなあ。エストニアの事例の様に、個人の統合マスタにトランザクションとして情報を付与して、個人=企業間で共有するなんて、大規模で出来ない気がするけどどうなのだろう。
0投稿日: 2019.11.29 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPRに関心があって読んだ。雑な理解だがざっくりまとめ。 ■GDPR概要 GDPR(一般データ保護規則)はEU市民の「個人データ」について、原則、EUの外に転送することを禁じる。現状では、米IT巨人が実質無際限に個人データを吸い上げ、それにより莫大な広告利益を上げて独占している。GDPRでは、個人データの所有権はあくまでもユーザにあり、ユーザはどの個人情報をどの事業者に提供するかを選べ、その同意があって初めて事業者はそれを入手、活用することができる。またユーザは「データポータビリティの権利」、つまり提供した個人情報を事業者の同意なしに他の事業者に乗り換える権利、また事業者が持つ個人情報を取り戻す権利を持つ。 個人データとは、名前、写真、メールアドレス、SNS投稿、位置情報、個人の信条から入れ墨、生体認証情報まで広範なデータが含まれる。GDPRでは情報(データを編集、解釈したものであり、人間が読むことができるもの)になる以前のデータ(二進法で記述され、人間は読むことができない生データ)も、規制対象となる。ヨーロッパ市民に関する個人データを扱う企業なら、国を問わずすべての企業が対象。直接扱っておらず、外部委託していたとしても、その責任を負う。 違反した場合の制裁金は巨額。グローバル売上高の4%か、2000万ユーロ(≒24.2億円)の高いほうを支払わねばならない。 2016年4月に成立、2018年5月前面施行。 ■GDPRの理念とその背景 フェイスブックはじめとするSNSやグーグルの検索サービスなどをユーザは「無料で」利用しているが、実際のところ、自分の個人情報を対価として差し出している。そして、米IT巨人はそれを広告業界などに提供し利益を独占している。EUは、この「データ錬金術」は、EU市民の基本的人権(プライバシーの権利?、「忘れられる権利」)を脅かしていると考える。 GDPRは、GAFAはじめIT巨人が個人データを無秩序に吸い上げ、利用することを許さず、個人データ/個人情報の所有権をユーザに取り戻し、主客を逆転させることで、新しいデータ経済の秩序を構築せんとする野心的な試みである。 個人データはフェイスブック、グーグル、アリババ、アマゾンなどの巨大企業が独占すべきものではなく、市民が所有権を持ち、さらに言えば、企業ではなく市民の監視が効く民主的な主体「データコモンズ」が管理すべきものなのだ。 また、旧東ベルリン出身者は、かつてのシュタージによる監視社会を記憶している。誰かが個人情報を独占し、それに人々が怯えるディストピアを身をもって体感しており、懐疑的。 ・米IT巨人が理想とするデータ経済の在り方: 個人のプライバシーやデータは積極的に公開し、透明性を極限まで高めていくべきもの。プライバシーという概念は歴史的には異常なもの。「プライバシーの死」を宣言。 ・EUが理想とするデータ経済の在り方: 個人のオプトイン/オプトアウト(同意/非同意って感じでいいのかな)に基づいて、個人が個人情報の提供するか否かを選択するインテンション・エコノミー。 筆者が主張するところによれば、現代は、この二つのイデオロギーが衝突する「新しい冷戦」なのである。 2013年のスノーデン事件、ロシアゲート(ロシアによる選挙干渉広告の購入)などの事件が明らかになり、SNSが人々の政治的意見を操作する手段として使われている現実がある。SNSは極右組織やテロ組織のリクルート手段にもなっている。 ■変容してしまったインターネット空間 かつてのインターネットはカウンターカルチャーの先駆者だった。今や、誰もが平等で開かれた空間ではなく、プラットフォーマーが独占する経済空間に成り下がってしまった。フェイスブックは、多様な人とつながるツールではなく、同類の人とだけつながり(ホモフィリー)自分にとって心地いい主張だけが増幅され残響する(エコーチェンバー)空間だった。※これは周囲のSNSにハマっている人間を見てもそう思う。あえて自分と反対意見の人と議論を交わし、自分の考えを深めるなんてことはしていない。自分に同調する人だけを集め、どんどん視野を狭めていってないか?と思う。 米IT巨人たちは、IT業界外からではなく、内部から批判にさらされている。フェイスブックの初代社長であったショーン・パーカー、ツイッターの創設者のひとりであるエヴァン・ウイリアムズといった面々から痛烈な批判を食らっている。 ■インターネットと環境 インターネットが環境に与える影響を意識することは多くないが、暗号通貨が消費する電力はアイルランド一国以上、データセンターの消費電力、レアメタルなど…環境と無関係ではない。 ■サービスとしての国家 エストニアが電子住民登録を開始。電子住民は、エストニアに物理的に入国または居住する権利はないが、エストニアに会社を登記し、ビジネスを実行する能力を人々に提供する。ビットネーション。 ■ディストピア オルダス・ハクスリーの『すばらしい新世界』。 ■感想 私は、この本で「テクノポリー(テクノロジー崇拝)」と揶揄される態度だった。AppleWatchをつけてすべての生体情報がAppleに吸い取られ、Googleが私の検索履歴を全て知り、そのデータが私の知らないところで売買されていたとしても、それに基づいた健康管理方法や好みそうなサイトをサジェストしてくれるんなら、便利でいいじゃないかと。読み始めは米IT巨人への批判が続く文章にうんざりした。しかし、GDPRが目指す未来と、それを実現するためのDECODE、次世代インターネット・イニシアティブはじめとする野心的な試みについて読み進めるにつれ(ブロックチェーン技術と結び付けているというのも面白い)、その社会のほうが望ましいのかな、という気もしてきた。 次のデータ経済の金脈は遺伝子情報だという。 遺伝子情報だの、生体情報だのがターゲット広告の材料にされるだけなら、ユーザとしては正直無視すればいいだけなのでまだマシだが、それが基で「フェイクニュース配信のターゲットにされる」とか、最近のリクルートの事件であったように、「事業者に漏れて採用・不採用の判断材料にされる」とか、「医療機関に漏れて治療の優先順位の判定基準にされる」とか、果ては「子供を産んでいいか悪いかをパターナリズム的に決定される判定基準にされる」とかなってくると、それはおっそろしい話だなと思う。
0投稿日: 2019.10.20 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPR general data protection regulation っていうEUとか出した個人情報に関するやつと、GAFAとかの情報戦争みたいな感じ。 あとで、もっと必要になったときに読み返そう。
0投稿日: 2019.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネットの未来はオーウェルの描いたような恐怖による支配ではなく、ハクスリーのすばらしい新世界で描いたような甘い誘惑による無意識な支配になる。というかもう既になってるよなぁと感じた。
0投稿日: 2019.06.17 powered by ブクログ
powered by ブクログインターネットは価値をもたらしてくれた。 一方でプライバシーを収集して、それをAIやアドテクなどのビジネスに利用していることに消費者は気付いているのだろうか? EUが開始した「一般データ保護規則」(General Data Protection Regulation:GDPR)の対策について触れる。 1.企業は、個人データの削除要求への対応が必須 2.個人は、データ処理方法情報を持ち、利用可能 3.個人は、データハッキングのタイミングを知ることが可能 4.企業は、サービス設計時にプライバシー保護についても設計が必要
0投稿日: 2019.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPRって鬱陶しい法律だ!と思っていたけど個人を守ろうしてくれるもの、長期的に安全なインターネット社会を再形成するものだと理解!
0投稿日: 2019.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
現状のプラットフォーム独占の原資(個人データ)をデータファオンドが引き継いでいないと、21世紀社会のデジタルインフラを制御するリスクは甚大である。これは、ソーシャルネットワーク自体を公共事業化するという見取り図でもある。将来、国や都市を構成する市民が、コモンズに運営委託するフェイスブックやグーグル、そしてアマゾンまでもが誕生するかもしれない。 フェイスブックやアルファベットが将来直面するのは、彼らが所有する莫大な個人データが、コモンズに変換され、電気や水道のような公共インフラとして再構築されるという脅威なのだ。(p.102) カナダのメディア学者マーシャル・マクルーハンはかつて次のように述べた。「ただのちっぽけな秘密は保護を必要とする。大きな秘密の発見は、人々の公共的不信感によって匿われている」と。(p.146) オーウェルは、監視社会の抑圧によってわたしたちが支配されると警告した。しかしハクスリーには、人々の自主性や創造性を奪うビッグブラザーは必要ではなかった。ハクスリーは、人々が監視や洗脳を愛するようになり、人間の思考能力を奪い取る「技術」を崇拝する世界を描いた。この「すばらしい新世界」こそが、底知れぬ恐怖であることをポストマンは後世に伝えた。 オーウェルは本を禁止しようとする独裁者を恐れた。ハクスリーは、本を読みたいと思う人が誰もいなくなり、本を禁止する理由がなくなる社会を恐れた。 オーェルはわたしたちの情報を奪う者を恐れ、、ハクスリーは、私たちに多くの情報を与え、人々が受動的な利己に還元されてしまう世界を恐れた。 オーウェルは真実がわたしたちに隠されることを恐れていた。ハクスリーは、私たちが真実とは無関係な情報の海に溺れてしまうことを恐れていた。 『1984年』が描いたのは、人々は痛みを追いながら制御されている世界だ。『すばらしい新世界』では、彼らは喜びを与えられることによって制御される。 オーウェルは、わたしたちが恐れるものがわたしたちを台無しにすると恐怖し、ハクスリーは、わたしたちが望むものがわたしたちを台無しにすると恐れた。(p.225)
0投稿日: 2019.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPRについて巷のビジネス系の本とは別の視点から捉えている。賛否は分かれるだろうが、GDPRを多様な側面から理解するには読んでおいて損はない。
0投稿日: 2019.02.21 powered by ブクログ
powered by ブクログGDPR制定の背景、EUの“大義”を日本人が書いた珍しい本。賛美が過ぎる感もあるが、GDPRの理解に役立つ良書。
0投稿日: 2019.02.03
