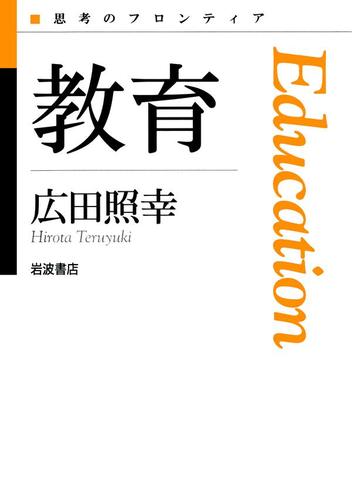
総合評価
(4件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ[ 内容 ] 教育を基礎づけていた普遍的・超越的な原理が崩壊し、グローバリゼーションとあいまった新自由主義的教育改革が進行しつつある中で、「教育」を語る対立軸は揺らぎ、その思想の危機が臨界に達しようとしている。 「教育はいかにあるべきか」について語る、現在の錯綜した言説を位置づけ直し、教育の未来に向けて、新たなオールタナティヴを構想する。 [ 目次 ] 1 現代の教育(「教育をいかに組織化するか」という言説について;教育の変動への視角) 2 個人化・グローバル化の中の教育(教育をめぐる構造変動(制度につなぎとまらない個人;制度の改善・改革要求) 一つの解としての新自由主義的教育改革(制度と個人の再調整;新自由主義的改革;オプションの必要性) 一つの代案) 3 基本文献案内 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2010.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ従来の教育本より確実に読みやすい。 実践的教育学と教育科学の性質をもとに、 教育学の概要を語っている。 よく教育学を学ぶ人は、この2つがあることを知らず、 どちらかだけに偏りがち。 現場ではA、でも科学的にはBの方が効果が上がる。 だから、AとBは喧嘩になる。 なぜなんだかわからない方は一度読んでみると面白い。
0投稿日: 2010.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学のときの勉強会で読んだ一冊。 まあ、この本をはじめに読んでおけばよかったなあっていまさら思っています。
0投稿日: 2010.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ学校の役割の中心に、何が正しいのかを判断するための知識の基礎を置き直すという提言は、混迷する政策に振り回されている現場(実際はもっとしたたかではあります。でないとやってられませんから。)を大いに勇気づけてくれる。
0投稿日: 2005.01.04
