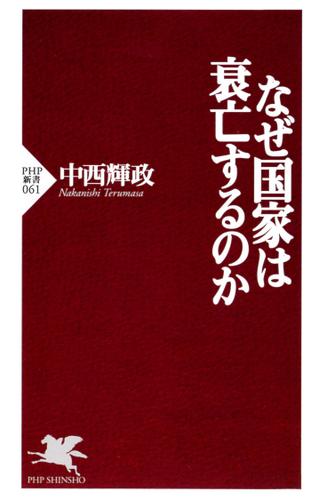
総合評価
(23件)| 5 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ第三章までは興味深かったが、それ以降は、背景の異なる時代についてクロスすることが多く、肝心の【なぜ衰退するか】については結局何もわからなかった。 読む価値は無いだろう。
0投稿日: 2024.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ好き嫌いが分かれるところだ。 未来は歴史から学べる部分が多くなる程確かにと頷ける箇所とそうかな?と立ち止まって考えてしまう部分も多々ある。普通は読んでいてもそれ程違和感なく頁をめくれるが本書はそうならない。過去に起きた事実は間違いない事象として描かれているが(当たり前)、その経緯や要因が断定的な記載(必ずしもそうなの?)が大半なため、これが「ではないだろうか?」であればスルーできる箇所もどうしても立ち止まる。歴史がそうだ、通説だ、と言うものだけなら良いが、幾つかは持論に基づく想定である箇所も見られる。一度批判的な目で見てしまうと、いちいち気になって先にも進まない。勿論、筆者の主張が見受けられないかの如く、断定的表現が一切無いものは余計に困るが。 さらに遅々として進まない原因は多用される難解な(私にとって)熟語の連続。これも漢字の得意な方には問題ないだろうが先を読みたくさせる気が失せてしまう。 それに内容に違和感を持つとなおさらだ。もう少し勉強しろと言われればそれまで。歴史や漢字(国語?)に至るまで着いて来れないものは非常に切り捨てる事が理解できないわけでも無い。最後まで読むのに時間がかかりすぎて記憶にも余り残らなかった。結論、本書のタイトルに繋がった内容の中心点がどこにあるかわからないような、勉強不足な自分を大いに反省する。
0投稿日: 2023.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ概要 ・おかげ参りは江戸時代のカタルシス。 ・日本史は物質的な欲の時期と、迷信のようなものを信じる人が多くなる時期が交互にくる。 ・天明のききん、浅間山の噴火などの災害⇒田沼の失脚 田沼時代はバブルの時代であり、不道徳な時代 モラルの破壊の時代 ・寛政の改革 きゅうくつな時代と思われたかも・・・ 田沼の時代を奇妙に時代にあったともちあげる歴史学者や江戸を論ずる人が今もいる 改革とは高い志が必要になる!!日本をどうすべきか真剣に考えた改革だ! アクションプラン ・今の時期、この令和の時代のあるべき国家像とは何だろうか、それを自分なりに考えていきたい。だから、もっと本を読んでいきたい。 ・松平定信の改革は中西輝政氏が言うほどそんなに評価されるべき改革なのか、寛政の改革をもっと知りたい。
0投稿日: 2022.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
端的に言うと、うーむ、残念。という一言。 本作は、佐藤優氏と手嶋雄一氏の対談で言及されていて興味を持ったと記憶しています。(武器なき戦争引用) 現実世界を取り巻くパワーバランスは米国中心。彼の国がどうなるのか、中国はどうか、インドだってわからない、中東の平和は、というか日本の行く末は、等々の疑問について、衰亡の理(ことわり)が開陳されるのではとの期待から購入しました。 期待は大きく裏切られました。 骨太なロジックにより主題が展開されることを期待しましたが、疑問を呈する短絡的な論述が多く、これらがいちいち気になって集中できません。 例えば。イギリス人がスポーツ(サッカー)を愛するのは人生が先の分からないゲームであるからであり、だからこそ開き直ってイギリス人はプロセスそのものを愛する(P.51)とある。サッカーは主に下層大衆に愛好されていると私は習いましたが、そうした大衆がプロセスを愛するとは到底思えません。サッカー好きは男性に顕著であろうと思いますが、それをもって全英国を特徴づけるというのもどうか。演繹が過ぎると感じました。 他にも、大英帝国の衰退の因として享楽的になった部分というのがあり、海外旅行ブーム、温泉ブーム、イベント好きという事象を挙げ、ローマでの「パンとサーカス」や温泉好きと絡めて、そこに共通因をみている。ひいては日本のレジャーブームや軽薄化から衰退の原因をほのめかしている(第三章)。これもなぜ英国人が享楽的となったのかを聞きたいし、その結果としてどうやって当時の英国の「エッジ」が失われなかったのかをしりたい。 また結局本旨も良くわからないという状況に陥りました。 序章には、国家の衰退について論じる、とあります。なかんずく著者が日本人であるからには日本の衰退局面に生かそうということは類推できます。ただ、本論では明示しないことで一層わかりづらくなっています。 結びではようやく、日本のあるべき姿が述べられています。因みにそれは、 「一口で言えば、「自由で、活力に富み、伝統と歴史を重んじて、世界で自立し名誉と協調を重んじる国」(P.234)」 ということです。私としては具体性を全く感じませんでした(そもそも衰退を認定する現状分析が希薄であったこともありますが)。 結局私はこのように解釈しました。『日本は今、なんだかヤバい。過去を振り返るとローマとか英国は過去享楽的になってヘコんだ。日本は今なら間に合う、誇りと伝統と自信をもって気合いで生きていこう』、こんな感じにしか解釈できませんでした。 ・・・ ということで、ネガティブなことばかり口にして反省しています。勿論私の理解力不足は火を見るより明らかであります。きっと深遠なことが書いてあったのであろうとは思います。 なにしろ筆者は京都大学の名誉教授であるし、間違いなく私よりもインテリジェントな方でしょう。ただ、議論の進め方は、昭和日本風で、結論から切り出す明快な欧米的なものではありませんでした。また、衰退を論じるにあたり、色々な可能性や仮説が考えられる中で、それでもこれが一番ふさわしい何故なら・・・という他の可能性の検討を経ず、筆者の感ずるままの話に付き合わされた感がありました。 安易な答えを求めすぎたことを反省し、ギボンの『ローマ帝国衰亡史』を読み進めることにしました。
0投稿日: 2021.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ結局何が言いたいのかサッパリ理解できず。第1章を読んでも衰退とは何かが読み解けないし、全体を読んでもなぜ国家が衰亡するのか明示されていない。 英国エドワード朝との共通点が嫌というほど列挙されている。曰く、インフラ整備で住みやすくなった大都市に若者が流入し、中産階級が膨らんで貧富の差が縮小し、わざわざ危険で暮らしにくい海外に出ていく必要もなくなり、その代わりに楽しい海外旅行ブームが起こり、伝統にとらわれない新しい「軽薄な」文化が芽生え、個人の尊重と女性の権利が認められた、らしい。何て素晴らしい社会なのか! この理想社会に到達した後、それ以前に比べて発展のペースが減速することを「衰退」と呼ぶのなら確かに衰退なのだろう。おまけに1920年代は世界恐慌で全世界的に衰退したのであり、このような「享楽的」(?)な社会変化が衰退の原因とはとても思えない。 本書を読んで結局「発展が衰退の唯一の原因」「盛者必衰の理」は真理であると確信した。著者の視点では、個人を犠牲にした全体主義国家でビジョンを持ったリーダーが蒙昧な国民を指導して衰退を防ぐのが好ましいと言っているように聞こえるが、そもそも衰亡論が誰のための議論なのかがすっぽり抜け落ちている。仮に国家が全体として繁栄しても、大多数の一般市民が犠牲になるのならまったく意味がない。 おかしなことを言う人だと思って経歴を見てみたら、石原や安倍の右派政策ブレーンか。こいつらの言う「美しい国」とはそういうことなのね。納得。
2投稿日: 2021.06.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ江戸時代のお蔭祭りというものでガス抜きをして江戸は続いていたという話が印象深い。 また、中国はアジアではなくヨーロッパに近いという感覚を持っているというのは意外だった。たまからこそアメリカとも本質的なところでつながっているのかと
1投稿日: 2020.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ再出版されたんですよね それでも、もう時評ですらも忘れられて。 内容的に今現在でも斬新と言いますか、歴史の繰り返し を突きつけられてオドオドするしかなかったですね。
0投稿日: 2019.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の在り方を、日本の伝統と歴史に立ち返る事の重要性から解き、その論拠をアングロサクソンの歴史に求めるとは、全く斬新で面白かった。 これが20年前の著書であり、働き続けてきた今、腹に落ちる。 サッチャーやレーガンの政策が、誤った自由主義によって日本で解釈されているとは、正にその通り。
0投稿日: 2019.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ国家というのは大きく繁栄すれば、必然的にその後には衰亡というものが控えている。歴史の中から大帝国などの「文明の衰退」を見つめ、その中からメカニズムを導きだそうという試み。今日、本が置かれている状況を見つめ直し、そういった衰退に備える。 日本政治のリーダーシップの不在→ビジョンの欠落 「国家目標」「国民的結束」が無いという状況 衰亡の可能性を意識することが再生への道 「自動化と創造性の矛盾」→「不断の柔軟性と自発性」 日本における官僚機構の硬直性と、旧日本軍の盲目性。 「より豊かに、平和でより自由に」からの脱却。 そもそも平和とは?自由とは?豊かとは?そういった問いもほぼ日本ではなかった。自国だけの平和、権利の首相のみ、物質的豊かさ。オンリーの文化。 成長=美ではない。 拡がるキーワード:ミメーシス
1投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログなかなか示唆に富んでいたので、中西輝政の近著を購入した。 アイデンティティは脈々と受け継がなければならない。
1投稿日: 2015.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスの衰退と日本の現状の比較や、ローマ帝国の衰亡とビザンチン帝国の繁栄の秘密、アメリカと中国の文明論的観点からの考察、松平定信の改革の意義や、大正デモクラシーと戦後の日本に共通する問題の指摘など、あまりにも話題が多岐に渡っていて、正直なところ著者の考えをうまく捉えることができませんでした。著者も「あとがき」で書いていますが、新書の分量には収まりきらない内容が盛り込まれていて、結果的に見通しが利かない本になってしまっているような気がします。 一つ、たいへん興味深く思ったのは、著者が文明の衰退の徴候を、衰退の徴候から目をそらして問題を直視しないことに求めている点です。文明論という極めて広く視野を取る学問において、衰退の原因論を外部から考察するのはほとんど不可能なのではないかと考えていましたが、著者の視点は文明に内在的な観点に置かれており、文明とは何よりも、私たち自身が担っていくものだという立場から批評がなされていると言ってよいのではないかと思います。
0投稿日: 2014.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
100年前の英国で流行ったもの、海外旅行、温泉ブーム、グルメブーム、そして不倫、インテリ青年たちの古典離れとマンガ、健康への異常な関心、得体の知れない新興宗教、快適な都市生活の享受と海外勤務の敬遠、イベントばやりの生活、そしてポピュリズム・・・当時はローマの末期に似ていると言われたとか。そして第一次大戦で は、英国は最も没落することになります。どこかの国に似ています。しかし、筆者は先進国とは衰退も経験した国だとのこと、何時までも右肩上がりではないとすれば、このような時に行なうべきことをしっかり見極めていく必要を感じます。
0投稿日: 2013.08.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ(略)トインビーはメレディスの言葉を引きながら、「成長と衰退とは裏腹である」と述べ、文明の成長はつねに「創造的な少数者」によってなされるという。社会というものは、常に全ての人が創造的な活動に従事しているわけではない。必ずしも創造的ではない一般大衆が圧倒的多数であり、すべての人を創造的活動に向ける事は不可能であるとトインビーは指摘する。 たとえば産業革命が起こって社会が急速に変化していくとき、指導者は社会をいっそう効率的に進歩させるべく方向づけ、そこでは「誰もが模倣できる仕組み」をつくらねばならない。そのたびごとにそれぞれの個人が想像するのではなく、誰もが取り扱うことができ、簡単に模倣ができるメカニズムによって、圧倒的多数の人々を成長のプロセスに参加させねばならない。 トインビーはこの仕組みをギリシャ語で「ミメーシス」と呼んでいる。ミメーシスとは「順応あるいは模倣すること」で、大多数の人が創造的な少数者の行為を忠実に模倣しそれを繰り返すことによってのみ、社会全体として意味のある生産活動につながりうるわけである。 中西輝政著『なぜ国家は衰亡するのか』p33
0投稿日: 2013.05.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ1998年初版の本。買って大分経つ。僕が購入したのは2001年で、購入当初ざーっと読んでいたのだけれど、今となっては中身を殆ど覚えていない。 最近読んだ松井博さんの『企業が帝国化する』に触発され、今の世界と企業について少し考えたく思い、本棚の奥から拾い出し、読み直しているところ。 この本を読む手前で佐藤優さんの『人間の叡智』、寺島実郎さんの『国家の論理と企業の論理』を読み直しているんだけど、『なぜ国家は衰亡するのか』にいたって、問題の構造が大分すっきりした感じ。国家、企業、社会、個人この4つを立体的に捉えないと駄目だということを改めて感じた。「帝国」という概念とその歴史については、もう少し勉強しないと状況を自分なりにクリアにするところまではいかないけど。 再読完了。 内容紹介に「世界史的・文明史的視点から、日本の衰退と再生を洞察する衰退学の集大成である」と記載があるが、まぁ新書程度で集大成なんて出来ないよね、という構成と記載内容ではある。著者もあとがきで似た様なことを書いているw。 しかし、読む価値無いかと言ったら全然そんなことはない。 少なくとも僕には非常に示唆に富む内容であった。そして、本書で指摘されている問題や課題は2013年のいまでも解決されているとは思えないわけで、今読み直して正解だったなという思いが強い。 僕たちは基本的に政治は政治で政治家がちゃんとやってくれ。経済は経済で起業家や経営者がちゃんと経営してくれ、って思っちゃうところあるよね。でも実際は「政治経済」という視点でモノゴトを理解したり、施策を立てて取り組んだりしないと駄目だよねと気づかされる。おまけにどれほど企業がグローバル化したとしても、国という概念がなくならない限りは、僕たち日本国籍を持つ人は日本国民なわけで、どうしても国家というものを視野に入れておかないといけない。一方ではグローバルな時代なんだから国なんて関係ない、なんていう輩もいるだろうけど、僕は寺島実郎さんのいう「世界は国籍不明のコスモポリタンなんて相手にしない」という言葉のほうが説得力あると思う。 そういう意味で今回の再読をキッカケに、世界、国家、社会、企業、個人という骨太な理解の軸を作れるよう、読書に施策に仕事に取り組んでいこうと思う。
0投稿日: 2013.04.06 powered by ブクログ
powered by ブクログここの所モヤモヤとしてた中国、米国の身勝手さも解説されており、頭の中がスッキリと整理された。 やはり、「憲法改正」まで行かないとね!!
0投稿日: 2012.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログいまだに「坂の上の雲」を目指している国や業界、シニアのための、健全なる衰退学の本。 二十世紀初頭イギリスの女性進出やグルメブーム、ビザンチン帝国が千年続いたワケなど。
0投稿日: 2011.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 文明の衰亡は必然なのか? 衰退から逃れる道はないのか? 本書ではローマ帝国、ビザンチン帝国、大英帝国、アメリカ、中国そして江戸時代の日本など独自の世界を確立した大国の興亡の光景を描き出し、その「文明衰退の理」を歴史の教訓から導き出す。 史上、外敵の侵入で滅んだ国はない。 衰退はその国の「内なる原因」によってなされたと著者は論ずる。 世界史的・文明史的視点から、日本の衰退と再生を洞察する「衰退学」の集大成である。 [ 目次 ] 序章 愚かなるオプティミズム 第1章 衰退とは何か 第2章 衰退を考える視点 第3章 大英帝国衰退の光景 第4章 ローマの衰退とビザンチンの叡智 第5章 衰退の行方を決める文明の構造 第6章 江戸時代の衰退と改革 第7章 衰退する現代日本 [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.19 powered by ブクログ
powered by ブクロググーグルブックスで半分ぐらい読んだ。ローマ、イギリスの栄枯盛衰から日本の衰退を批評しているらしいが、はっきり言ってどうでもいい講釈という印象をもった。こんなことをグダグダ書いている前に、いまのデフレをなんとかできるのか、という問題意識をもってほしい。
0投稿日: 2011.02.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ大国の興亡の光景を描き、文明衰退の理を歴史の教訓から 導き出す。 史上、外敵の侵入で滅んだ国はない。 衰退はその国の「内なる原因」によってなされる 企業経営も同じで内部からの崩壊が原因となる。 ☆ミメーシスのパラドックス ☆千年続く帝国 ☆外来の神
0投稿日: 2008.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ+ ・道徳の頽廃とその社会の活力の衰えとは表裏一体であるとした上で、文明の衰退は内なる要因、特に精神的、文化的要因などの自己決定能力の喪失から発するという観点から、衰退のケースとしてローマ帝国・大英帝国を、反例として外部文化を巧みに自己化することで文化の破綻を防ぎ1000年以上命脈を保ったビザンチン帝国と、普遍的な理念を持ちえることで継続していた中国とアメリカの繁栄の要因が解かれていた。 ・文明の成長は創造的な少数者にて行われ民衆は機械化された仕組みのもとでエネルギー効率の上昇を図るべきであるという普遍的な理論を『よき指導者と馬鹿な大衆の組み合わせが高度成長の要因』 と標榜した上で、『しかしエネルギー効率に傾倒すると組織が硬直化するために、予防としての普段の柔軟性と自発性という創造力もまた重要である』とし、日本の衰退の一要因を指導者の後継者が育たないことである、と主張している。 やや脱線するが、日本の更なる問題点は、創造的な少数者が現れて改革を成し遂げようとしてもその成果は一日にしてははかりしれない上に、改革とは既成権威にとって本質的に害となりうるために批判的な権威がメディアを用いて、盲目の激情に身をゆだねがちな大衆を眼前の取るに足らない問題の糾弾へと誘導し世論を形成させることで、改革を阻害することにあると思われる。そこで、次はメディアリテラシーについて学ぼうと思う。 - ただ、本書において数例の例示にとどまっている点と実例と主張の間でやや論理の飛躍がなされていると感じた上に、論旨の根幹箇所にて『思う』などの主観を交えた文章が多用されていた点から筆者の主張に説得力が薄く感じた、新書という枠では収まりきらない論点であったことにも起因していると思われるので著者の他の本も読むことで論旨の補完をおこないたい。 --------- --------- ・ローマ、大英帝国にて精神の弛緩、新奇さや派手さに傾倒、自己規律の欠如、新興宗教が衰退要因。極端に物質主義に傾斜する時期と逆にそれへの無意識の罪悪感が働き不合理な迷信なようなものに敏感に反応する時期が交錯する中で、いかに国家としての体制を保つか。 ・ビザンチン帝国は自己の国家体制と文明構造のなかに位置づけなおす、習合という文化摂取方法にて伝統を継続と外部要因への適応力を維持することで命脈を保つ。 社会科学、現実の社会が当面している問題を関心から搾り出し、極狭い歴史の視野から解決策をみいだす。 ポストモダニズム、近代を超克、退廃の現象 ・文明の更地性や論理性・合理性と抽象観念などの純粋な理念のみが表出する普遍主義的な性格ゆえに特別な論理の必要性のある米中。 国の本質として膨張する活力のはけ口を力にて実行しその行動理念を民主主義と据え置き、その力の名のもとに世界を蹂躙しようと試みたのがアメリカ 儒教と共産主義による世界の解放というイデオロギー、中華的な普遍性を放棄せざるを得なくなった上で、国家として掲げるべき理念が消失し対日感情の勃興させることで民意 の矛先をかえ、中央への支持をなんとか維持しているのが中国
0投稿日: 2008.09.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ【一言】 ・国家を再生するためには国民の意識改革が必要。 【要約】 ・国家が衰亡する主な原因は2つ。 ?国家が生来的に有する衰亡と再生のサイクル。 ?外来の神を導入することによる価値観の変化。 ・国家を再生するためには、国家のシステム改革だけなく国民の意識改革が必要だ。 【感想】 ・?を原因としつつ国民の意識改革が必要というのは矛盾している。(誤読かも) ・「意識改革」といっても具体的な施策がイメージできない。 ・論理展開が雑な印象でもうひとつ納得感がない。 (H)
0投稿日: 2008.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログかなり目からウロコ的視点があり、個人的には結構納得のいった一冊。面白かった。残念ながら読んだ直後に感想を書いていない為、ウロコの一例を挙げられないのが無念・・・。そんな曖昧な中にも関わらず、一読はススメます。ローマ帝国との対比なども興味深かったです(辛うじて大雑把な一例だけ)。
0投稿日: 2007.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は、国際政治学者であり、文明論も専門とする中西輝政(京都大学大学院人間環境研究科教授)さんです。 新しい歴史教科書を作る会の理事もやったことがある人で、いわゆる保守派の人です。 本書は、世界史的・文明史的視点から日本の衰退と再生を洞察しています。 著者は、日本の再生のために、個々の改革の必要性は認めつつ、それはあくまでも「日本」の歴史や哲学を基礎とした「日本の改革」でなければならないと主張しています。 世界史的・文明史的な視点が面白いと思います。 ハンチントン教授の『文明の衝突』と合わせて読むと、より一層理解が深まるでしょう。
0投稿日: 2006.08.09
