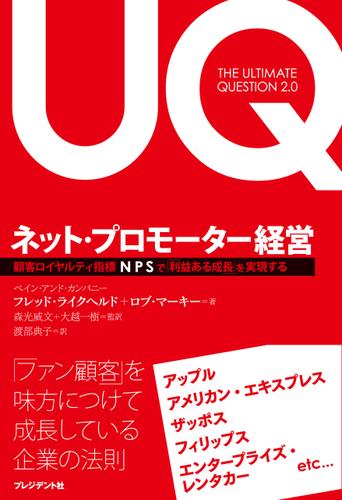
総合評価
(20件)| 6 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計的な処理においてや日本企業での導入において課題はあると思いますが、簡単な質問から顧客の満足度を図る指標としては優秀だと感じます。 同時に、単なる数値をどのように解釈して企業の改善に活かすのかは導入企業の力に委ねられる気がしますね。
10投稿日: 2024.09.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客の満足度を高い精度で把握できるとともに、活用のやり方によっては、満足度の高い顧客を拡大し、長期的な業績拡大につなげることができるとされるNPSについての解説本。あくまでNPSはツールであり、トップを含めた全社的、徹底的な取り組みが必要であろう。成功事例をみると、まさにそういう企業が並ぶ。思い付きでちょっと取り組むくらいでは意味がなさそう。
0投稿日: 2023.09.07 powered by ブクログ
powered by ブクログNPS は以前から知っていたが、実際に NPS をどう経営に活かすのかについては全く分かっていなかった。本書に書かれている様に、財務情報と同じ重要性で組織全体で活用できるようにすることが真の意味での活用になる。
1投稿日: 2022.11.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ良き利益は、劇的なまでに異なる性質を持つ。悪しき利益が顧客を犠牲にして得られるとすれば、良き利益は顧客の熱心な支持によってもたらされる。顧客が心から喜び、もっと買おうと積極的に利用してくれる場合に、さらにはその企業と取引するように友人や同僚に薦めてくれる場合に、企業は良き利益を獲得する。満足した顧客は実質的にその企業のマーケティング部門の一員となり、自分自プロモーター身の購入量を増やすだけでなく、熱心に紹介してくれる「推奨者」となる。悪しき利益への依存症を断ち切りたいと思う企業にとって正しい目標とは、推奨者を生み出し、良き利益につながり、成長を促進するような、高品質の顧客リレーションシップを築くことである。 10年間に及ぶ研究を通して、ほとんどの業界で次のような事実が確認できた。すなわち、批判者に対する推奨者の比率が業界内で最も高い企業は、一般的に高い利益と健全な成長を享受している。直観に反すると考える向きがあるかもしれないが、突き詰めると、高い顧客ロイヤルティを誇る企業は、競合他社に比べてマーケティング費や新規顧客獲得コストを大幅に抑制できる場合が多い。また、既存顧客向けのサービスに集中し、新規顧客の獲得はきわめて選択的に実施しているが、これらはいずれも、一般的には成長を阻害するものと思われるかもしれない。しかしデータは嘘をつかないものだ。NPSリーダーは、競合企業の二倍以上のスピードで成長しているのである。先述したように、10年間を通して継続的に利益ある成長を遂げてきた企業は全体の9%ほど存在 するが、そうした企業のNPSは平均して、同業他社のスコアの2.3倍だった。 ファンクイックは、フィリップスに入社する前にプロクター・アンド・ギャンブルとスターバックスで働いたことがあり、顧客中心主義の組織で働くことがどういうものかを理解し、今回の取り組みが大規模な変革となることを心得ていた。そこで、フィリップスが顧客志向への移行を達成するのに役立ちそうな選択肢を幅広く調べた。世界中の大手企業が用いている手法をすべて評価した後で、ファン・クイックはNPSを活用することに決めた。それについて、次のような説明をしている。「NPSが気に入った理由は、すべての事業部で導入可能な単一の基準だったことです。どこの事業部でも、それぞれが独自の顧客満足度の指標を開発し、それを継続していきたいと思っていますが、実際に結果に結び付いているのはごく少数で、財務業績と直結したものはつもありません。そのため、私たちは他の有効な解決策を探さなくてはなりませんでした。NPSの最大のメリットの一つは、売上成長に直結しており、行動を引き出せることです」 「売上成長に直結する」という点について、NPSについて調査したファン・クイックと経営幹部 チームは、競合他社と比較した自社のNPSと、競合他社と比較した自社の成長率との相関性が高い ことを見つけた。 ■NPS測定の重要な要素 1.信頼性ときめ細やかな調査 2.タイムリーさ 3.顧客の行動との関連付け ■NPSの原則 1.究極の質問を尋ね、それ以外の質問は極力減らす 2.有効な評価尺度を選び、それを使い続ける 3.自社顧客調査(ボトムアップ)のスコアと外部調査(トップダウンやベンチマーク)のスコアを混同しない 4.適切な顧客からの回答率を高めることを目指す 5.財務データと同じ頻度で、NPSの報告や議論を行う 6.調査単位を細かくして、より速く学習し、責任を持たせる 7.正確さを担保し、バイアスを取り除く 日本人のスコアが五点を中心に偏るというのは よく見られる現象ではあるものの、ベインの日本におけるプロジェクト経験では、五点をつけた人の詳細なコメントを拾っていくと、明らかに何らかの不満を持っていることが多い。すなわち、必ずしも満足しているわけではないことがわかる。一方で九点、一〇点をつけた人は、それ以下のスコアをつけた人とは明らかに異なる行動をとっていることが多い。 ■NPS向上が企業にとって経済的な価値をもたらすことの証明が十分でない NPSを効果的に導入するには、いくつかの事前準備が必要であるが、「NPSを向上することが会社にとって目に見えるメリットがある」ことを証明しておくことは、最も重要な準備の一つである。当たり前のことであるが、NPSを上げるという努力が会社にとって、また個人にとっても報われるという納得感がないと、旗を振ってもついてきてくれる社員は少ない。したがって、導入の際には社員に対して十分なコミュニケーションを行うこと、NPSのコンセプトや定性的な意義だけでなく、実際にどのような価値が生まれるのかを説得力あるデータで示すことが重要である。 二つ目のポイントに挙げた「推奨者を増やすことに焦点を当てる」というのは、従来型の顧客満足度調査とは違ったアプローチであり、新鮮さを感じやすい。何よりも本質的に重要なポイントである。「普通のことをやっていては推奨者にはなってくれない。どうすれば顧客の期待を越えられるような感動体験をつくれるか?」という問いを考えることは、難しくはあるものの、社員のモチベーションを高めることも多い。われわれがNPS導入を支援する際にとるアプローチの一つに、推奨者のインタビューをビデオ収録し、営業担当者に見せて顧客からのフィードバックがいかに建設的でポジティブなものが多いかを理解してもらい、また推奨者をつくるためには何をすればよいかを一緒に考えるワークショップを何度か行う、というやり方がある。推奨者のポジティブなフィードバックによって自信を深め、さらに推奨者を増やすためには何をすればよいかという前向きな発想になり、ひいてはフィードバックを積極的に貰おうという好循環をつくることが目的の一つである。また、実際の施策も、顧客担当部署が単独で考えるよりも、顧客接点の直接の担当者が自発的に考えたものと組み合わせたほうが効果的であることも多い。こういった動きをつくり出すのが「クローズド・フィードバック・ループ」なのである。 ■NPSを成功させるための三つの鍵 ①シニアな経営陣、特にCEOが個人的にネット・プロモーター・システムを通した顧客ロイヤルティの改善を、きわめて重要な優先事項として受け止めている。彼らは経済的に取り組むべ理由(収益ある成長につなげること)と、動機付けや士気の面で取り組むべき理由(自社が基本的価値観をどれだけ実現できているかを測定すること)の両方を理解している。 ②NPSの顧客フィードバックを組織全体の主要な意思決定プロセスに組み込み、学びと改善の「クローズド・ループ」をつくっている。何か特別な部署の責任やプログラムとしては扱わず、日々の基本的な優先事項の中に組み込まれている。 ③短期的なプログラムや取り組みとしてだけでなく、企業文化の変革と成長にいたる長期的な道のりとしてネット・プロモーターに取り組んでいる。企業が収益を伴う持続可能な成長を実現させたいのであれば、組織全体でNPSに取り組まなくてはならないことを理解している。 頑丈なアーチ橋がそうであるように、ネット・プロモーター・システムは、二つの柱の上に成り立っている。どちらか一本でも柱を欠けば、すべてが崩れてしまう。一つ目の柱は経済性である。NPSの考え方によって顧客ロイヤルティに投資を行い、その投資収益率を計算することができる。顧客ロイヤルティが高まれば、より大きな収益がもたらされ、その収益をさらにロイヤルティ構築のために投資するという好循環に持ち込める可能性がある。このような経済面での優位性を加速していける企業は、競合他社を大きく引き離すことができる。 もう一つの柱は動機付けである。多くの人々は、顧客に対して正しい行動をとりたい、プラスの方法で顧客の生活に影響を与えたいと思っている。NPSは、こうした側面で自分たちがうまくいっているのか、まだ不十分なのか、なぜそうなのかといった理由を明らかにしてくれる。こうしてNPSは改善に役立つのである。アップルでは、NPSで九点または一〇点をつけてもらうことはスタンディングオベーションに値すると考えられている。それは良い仕事をしているという証であり、心からの満足感を生み出す源泉となっている。 …アップルでは、店長が二四時間以内にすべての批判者に電話をかけることになっている。だが、なかにはどうしても連絡のとれない人もいる。そこでアップルは、店長から連絡のとれた批判者と連絡のとれなかった批判者の購買パターンを追跡することにした。二年間の追跡で、連絡のとれた批判者はとれなかった批判者よりもたくさんのアップル製品やサービスを購入していたことが判明した。アップルは、この「クローズド・ループ」を実現するための電話対応にかかる時間を計算してみた。すると、批判者に一時間電話したときに得られ追加売上高が一〇〇〇ドル以上になること、また取り組み初年度で二五〇〇万ドルもの追加売上高を生み出すことが判明した。たいへん高い投資効率だ。しかも、この数字には批判的な口コミを避けられたことによる効果は含まれていない。また当然ながら、店長がそのやりとりから店舗改善に役立ヒントを学んだ効果も含まれていない。 重要なことは、毎日のリズムの中に組み込むことだ。ネット・プロモーター・システムで優れた結果を出している企業には、もちろん多くのやらなければならないことがある。しかし、意味のある進歩のために不可欠なポイントを一つ挙げるとすれば、それは顧客フィードバックを毎日の通常業務に組み込み、個々の顧客と話をして「クローズド・ループ」をつくって適切な措置をとることである。「適切な措置」は多くの場合、直接的なサービス・リカバリー(失敗の事後フォロー)、つまり個々顧客の問題を解決することが関係してくる。しかしその際には、全顧客の体験を向上させ問題の再発を防ぐために、製品とプロセス改善を行うことも必要である。推奨者を増やし批判者を減らすために、最終的には会社の基本戦略や優先事項の見直しまで求められる場合もある。大事なのは、「クローズド・ループ」によるフィードバック、学び、行動にいたる一連のプロセスにおいて、顧客と直接接点のある従業員から経営幹部までを含めたすべての人々を巻き込まなくてはならないということだ。そうすれば、顧客からの直接的でタイムリーな意見を反映させた、より良い意思決定を組織全体が継続的に行っていくことができる。 顧客フィードバックを心に強く訴えかけるものにする最良の方法の一つは、マネジャーによる解釈や統計分析の要約ではなく、顧客の実際の声を従業員に聞かせることだ。プログレッシブ・インシュアランスでは、批判者との「クローズド・ループ」において(本人の許可をとって)電話の会話を録音し、その顧客に応対した従業員にデジタル音声ファイルを転送している。顧客の声を聞くことで、従業員は声の調子に触れ、感情的な効果を感じとる。それだけで学習や行動の変化への動機付けとなり、別途コーチングする必要性はほとんどなくなる。 ここでは、約一兆四〇〇〇億ドルの資産を管理するアメリカ最大の投資信託会社、バンガード・グループCEOであるビル・マクナブを紹介しよう。マクナプのスケジュールは、管理業務、直属の部下のマネジメント、規制当局とのやりとりなどで簡単に埋まってしまう。しかし、彼はそうしない。彼やほかの経営幹部は皆、顧客からコールセンター(バンガードでは「スイス軍」と呼んでいる)にかかってくる電話の量が多いときに、顧客との電話のために時間をとる。全員徴兵制度がとられていスイスのように、経営幹部は全員、ピーク時に顧客サービスの電話対応にあたらなくてはならないのだ。一般社員と肩を並べて働くことで、これが顧客にとっての懸念や大事なことに直接触れることできるかけがえのない機会となっていることを、マクナブもほかの幹部たちも理解している。そう経験を通して、電話担当者が日々格闘しなければならない複雑なシステム、方針、手続きに代表される課題も、彼らは痛いほど実感することになる。たとえば、市場崩壊のような危機の際には、すべての経営幹部はそのときにやっていることを中断して、コールセンターへと急ぐのである。 だが、顧客のコメントを一言一句まで見ていたとき、プログレッシブの経営幹部は奇妙なことに気づいた。「オンライン支払い」は、推奨者だけでなく、批判者のコメントでも最も頻繁に出てくる文言の一つだったのである。さらに分析していくと、オンライン支払いプロセスが最初の一回でスムーズにいくと、顧客NPSが大幅に高まることがわかった。しかしスムーズにいかなかった場合、NPSは二〇ポイントも低くなった。当時、オンライン支払いプロセスが失敗する割合は一八%だった。これらの失敗は、最初の月の支払いは口頭で依頼できるが、その後も支払いを続けるには署名入りの契約書類の提出を求めるという、銀行の手続きから生じていた。つまり、銀行側がその書類の提出を受けていないとEFTは機能せず、プログレッシブは後日、従来通りの郵送で顧客に請求書を送っていたのである。そのせいで混乱が生じ、回収不能や不払いによる契約キャンセルが増える恐れも高くなっていた。 これらの失敗は、最初の月の支払いは口頭で依頼できるが、その後も支払いを続けるには署名入りの だった。 契約書類の提出を求めるという、銀行の手続きから生じていた。つまり、銀行側がその書類の提出を 受けていないとEFTは機能せず、プログレッシブは後日、従来通りの郵送で顧客に請求書を送って いたのである。そのせいで混乱が生じ、回収不能や不払いによる契約キャンセルが増える恐れも高く なっていた。 プログレッシブは、パートナー企業と決済に関する新しいプロセスについて交渉し、決済システムを再設計した。新プロセスでは、顧客は自動の電話案内(「今後の毎月の支払いに同意するなら、一を押してください」というような説明が流れる)を利用して電子署名ができるようになり、自署での契約書類を出さなくてもよくなった。この解決策が実施された後、批判者がオンライン支払いに言及する頻度は減り、頻度の高い上位二〇ワードにも入らなくなった。また、保険契約者の維持率も大幅に改善されたのを見て、マネジャーたちは喜んだ。そして経営幹部は、オンライン支払いというオプションについて、自信を持って新たに宣伝できるようになったのである。今のところ、EFT利用顧客の平均NPSは、EFTを利用していない顧客の平均NPSよりも八ポイントほど高くなっている。 誰もがすべての仕事を終えるのに十分な時間がとれないこの世界では、「クローズド・ループ」が自動的に重要な意思決定の一部となるように日々の業務フローに組み込まなくてはならない。業務フローに組み込んで初めて、NPSの恩恵を享受することができるようになる。アップル、シュワブ、ラックスペース、インテュイットなど、NPS活用におけるスター企業は、一貫して二四時間以内にすべての批判者に連絡をとろうと努めている。ほとんどの企業がこの目標を九〇%以上(執筆時点)達成している。皆さんの組織では、どのくらい頻繁にこうしたことが実現できているだろうか。 ラックスペースは人材募集の際に技術力を求めることが多いが、それが最優先されるわけではない。技術的なスキルは教えられるが、物事に対する態度は教えられない。したがって候補者が成功するには、ほかの人々を世話するのが本当に好きであることを示さなくてはならない。「私たちはサービス好きのオタクといえるほどに、他人にサービスすることが好きな人材を採用します」と、ネピアは言う。財務指標と同じくらい測定基準を重視させるために、ラックスペースではチームメンバーに顧客NPSの説明責任を持たせている。しかし、ラッカーズが顧客の役に立ちたがるのは、NPSと連動する報酬が目当てではない。そうした欲求は彼らの基本的性格の一部となっているに違いないからだ。 フォーシーズンズ・ホテル・グループで長年マーケティング責任者を務めたバーバラ・タルボット(現在は引退している)、ラックスペースと同じ感覚を持っている。優れた顧客体験を提供するには、顧客と直接接点のある従業員の性格が最も重要だと、彼女は確信している。 フランクリン・コヴィーのチームは、レシート調査のスコアに基づいた店舗ランキングと、同じ店舗で同時期に実施したエンタープライズ方式の電話をかけるプロセスで得られた店舗ランキングとを比較してみた。ヘルスケア、ペットショップ、レストラン、電子機器、自動車部品、自動車修理、ヘアサロンなどについて、標準値との差を測定する八種類のテストを行ったところ、半分以上でランキングに大きな違いが見られた。その後、電話プロセスで一位になった店舗で、実際に顧客の言動が結果と一致しているかを調べてみた。すると予想通り、ランキング上位店の顧客維持率と平均購買金額は高く、一方レシート調査の上位店の顧客維持率と平均購買金額は同チェーンの平均以下だった。電話の場合の平均NPSがレシート調査のスコアよりも約一五ポイント低かったことから、電話アプローチのほうがより多くの批判者を調査対象に含められていたことが明らかとなった。
1投稿日: 2022.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログNPSは過去にもいくつかの本を読んだことがあったが、やっぱり本家本元の本を読むことが大事だなと感じた。厚いし、理解しにくい部分もあったけれど、原本を読むことで実務のヒントになることも見つかった。難しくても原本を読むことは大切だな。
0投稿日: 2021.09.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、中国の平安保険グループの本で、初めてNPSについて知り、もう少し深く学んでみたいと思って読んでみた本。 NPS自体についても、またそれを経営指標の一つとしてフル活用している事例などがよく理解できる本でした。 【なるほど!そうだよな!と思ったフレーズ】 NPSの数値については、バスケットボールの試合と同じで、自社のスコアがどれだけ高いかは重要ではない。競争相手より高い得点を取ることが重要なのだ。
0投稿日: 2020.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
すべての優れた組織のミッション(使命)は、自社が関わり合う人々の生活を豊かにし、ロイヤルティを築くことにあると信じている。そして、優れた組織は株主だけでなく、従業員、ビジネスパートナー、とりわけ顧客に対して、プラスの影響を及ぼさなくてはならない。 顧客リレーションシップを犠牲にして獲得した利益が、悪しき利益だからだ。もし顧客が惑わされたり、不当な扱いを受けたり、無視されたり、強制されたりしたと感じたとしたら、その顧客からもたらされる利益はすべて悪しき利益である。 良き利益と悪しき利益とを識別するための質問とは、どのようなものだろうか。質問自体は単純なものだ。すなわち、「この会社を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか」というものである。そしてこの質問を基に得られる指標が「 推奨者の正味比率(NPS)」である。 NPSは、どんな企業の顧客も三つのカテゴリーに分類できるという基本認識に立脚している。すでに説明したとおり、「 推奨者」というのはロイヤルティの高い熱心な顧客で、自らが継続購入客であるのと同時に、友人に対しても顧客になるように薦める。「 中立者」というのは、満足はしているがそこまで熱狂的でない顧客で、競合他社からの働きかけになびきやすい。そして「 批判者」は、劣悪な関係を強いられた不満客である。先の質問に対する顧客の回答が、三者を分類する基準となる。たとえば、一〇点満点中、九点または一〇点と答えた顧客は推奨者であり、以下、中立者、批判者の順に点数が下がっていく。 顧客は二つの条件が満たされない限り、個人的な推奨を行わないことも判明した。まず、その企業が優れた価値を提供していると、顧客が信じていなくてはならない。 第一の条件は顧客の理性を惹きつけるものであり、第二の条件は顧客の感情に訴えかけるものである。この両者が満たされたときに初めて、顧客はその企業を熱心に友人に薦めるようになる。 NPSが目覚しい改善をもたらすのは、次のような場合である。 ①シニアな経営陣、特にCEOが個人的にネット・プロモーター・システムを通した顧客ロイヤルティの改善を、きわめて重要な優先事項として受け止めている。彼らは経済的に取り組むべき理由(収益ある成長につなげること)と、動機付けや士気の面で取り組むべき理由(自社が基本的価値観をどれだけ実現できているかを測定すること)の両方を理解している。 ②NPSの顧客フィードバックを組織全体の主要な意思決定プロセスに組み込み、学びと改善の「クローズド・ループ」をつくっている。何か特別な部署の責任やプログラムとしては扱わず、日々の基本的な優先事項の中に組み込まれている。 ③短期的なプログラムや取り組みとしてだけでなく、企業文化の変革と成長にいたる長期的な道のりとしてネット・プロモーターに取り組んでいる。企業が収益を伴う持続可能な成長を実現させたいのであれば、組織全体でNPSに取り組まなくてはならないことを理解している。 この三つが成功への鍵である。 結局のところ、顧客に喜んでもらうための最も強い要因の一つは、企業がきちんと話を聞き、不満や提案に応えることだ。そうした取り組み姿勢は、同社が顧客を重視しており、大切にしていることの証明となる。それが、顧客と良い関係を築くための基本的な必要条件となる。 ほとんどの企業は、より顧客志向の企業文化を築きたいと思っている。ネット・プロモーター・システムは、この目標の達成に役立つ一連のさまざまなツールや有用な手法を提供するものである。だが、顧客にフィードバックしてくれたことを感謝し、根本原因を確かめ、顧客へのサービスを向上させる方法を学び、適切な対応をするといった「クローズド・ループ」をつくることよりも強力なものはない。NPSは根本的に、測定やサービス・リカバリー以上の存在である。NPSは、人々を大切に扱うことを基礎にビジネスを行う方法なのである。
0投稿日: 2020.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログNPSは単なる指標ではなく、顧客ロイヤルティを定期的に測り施策を見直していくシステムだ ってマーケティング講習で聞いて 読んでみたのだが NPSのSはシステムだって強調されているもののシステムの説明はなく、事例がひたすら書かれていて うーむまだVerupが出来るものなのかな
0投稿日: 2019.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログまとめ NPSの教科書。 ◯勧めたくなる条件は2つ ・理性を惹きつけるもの(価格、特徴、品質) ・感情に訴えかけるもの(信頼関係) ◯NPSのメリット ・業務プロセスの改善 ・コスト削減と品質向上 ・顧客ロイヤルティの強化 ・価値観(ビジョン)の達成、指標で見える化になりわかる ◯批判者は最高の盟友 欠点の特定を手伝ってくれる。 感想 NPSは質問内容は1つで顧客満足度測れるに便利なシステムである。 だけど下記に記載してる内容通り利用方法が難しい。その利用方法に対して、本には参考になることが書いてある。 「そのNPSを「誰に」「どのタイミングで」取るべきなのか」 「お客様に意見に対してどのように返答すればいいのか」 「結果をどう受け止めて製品をよくすればいいのか」 「NPSと収益の関係性をどう見つけるべきなのか」
0投稿日: 2019.10.06 powered by ブクログ
powered by ブクログずっと読みたかった本だが、中々再販がされなかった。 NPSの解説書ではあるものの、得られる知見はそれにとどまらず、広くUXやお客様との向き合い方、といった顧客中心主義に関することそのものである。 悪しき利益(=顧客が離れていく企業活動によって得られた利益)を抑え、真の利益を得て企業が成長するには? また、その方法を企業内に広めていくには? なぜNPSを測定し、上げていかなければいけないのか? 個人的には普及させたく、かつ、そのために今後も何度も読んでいくことになるだろうと思うので星5つ。
0投稿日: 2019.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ究極の質問自体は素晴らしいと思う。そのサービスに満足しているかどうかを知る簡潔にして最大の問いである。 しかしながら本著で紹介されている企業も、身近な企業も、NPSを活かしていると言えないと感じることがある。そもそも活かしている会社なんているのか?
0投稿日: 2019.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログNPSの有効性 そもそもの経営が目指す姿(良い利益、悪い利益) NPS導入にあたる注意点 が分かりやすくまとまっている。
0投稿日: 2019.03.17 powered by ブクログ
powered by ブクログNPSについて学ぶには必読な本。 序草と第I部にて、基礎についてはよく理解できる。 しかしながら、事例については、あちこちに記載され、重複もあり、まとまっていないために読みづらい部分も多い。 序章にて、 「〇〜一〇点で表すとして、この企業(あるいは、この製品、サービス、ブランド)を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか」 「そのスコアをつけた主な理由は何ですか」 の質問や、推奨者・中立者・批判者について、 NPSの算出方法を説明してくれる。 NPSは柔軟かもしれないが、 絶対に省くことのできない三つの基本的な要素がなければ、 その効果を得ることができず、 その要素の一つが「クローズド・ループ」である。 第1章では、 AOLやブロックバスターの事例を用いて、 悪しき利益について説明している。 一〇年間に及ぶ研究を通して、 ほとんどの業界で、 批判者に対する推奨者の比率が業界内で最も高い企業は、 一般的に高い利益と健全な成長を享受している。 第3章では、 NPSの経済性について説明している。 顧客の生涯価値を計算すると、 多くの場合、推奨者・中立者・批判者の行動は 大幅に異なっており、 推奨者と批判者を分かつ要因として、 顧客継続率、価格、年間購入額、費用対効果、口コミ が挙げられる。 相対的(競合対比の)NPSと 相対的な有機的成長率との関係性はきわめて強い。 第4章では、 エンタープライズの事例を基に、 有用な手法になるまでや、導入方法、 成功の秘訣について説明している。 第5章では、 8つの原則について記載されている。 特に、原則四の 経験則からいうと、調査の回答率が65%未満なら、 プロセスを改善する必要があるということは 覚えておきたい。 第II部では、事例と教訓が散りばめられている。 自社で導入しクローズド・ループを回していく際には、 参考にできる内容もあるだろう。 以上
0投稿日: 2019.01.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本でもすっかり定着した感のあるNPSに関する生半可な知識を本家本元で確認。企業の持続的成長にはNPSに基づくマネジメントが有効であり、通常の顧客満足度調査と違うのは、「究極の質問2.0」という原題に象徴されるように、質問内容が非常にシンプルであり、収益性との因果関係が見えやすい、関係者の動機付けを刺激しやすい、といった点が挙げられるが、やはり重要なのはクローズド・ループの部分か。また、NPSが低めになってしまう日本特有の問題(オランダも!)や日本での事例(平成建設、アメックス)なども補足されており、なかなか読み応えあり。弊社でもご他聞にもれず採用しており、対象セグメントの収益とNPSが上昇しているのだが、これが因果関係あるのか擬似相関なのか半信半疑。相対的NPSが充実すると比較判断できるのでいいのだが。いずれにしても、顧客のフィードバックをタイムリーに反映させ、顧客障害価値に応じて推薦者も批判者も施策を重点化し、ひいては従業員の満足度をも高めリてテンションまで効果発揮できるのが理想かな。今度どのように展開するか、また活用の幅もどう広がるか要注目です。
0投稿日: 2018.04.23 powered by ブクログ
powered by ブクログあなたの知人や関係者に、XXを薦めますか?という質問に0~10点で回答し、またその主な理由は?と自由入力のアンケートを行う。そのスコアと記述内容からフィードバックをきかせる。 単純にいうとそれだけだが、これは従来のお客様満足度調査よりもはるかに業績相関がある調査であると直感的に言える。またAISASモデルの時代とあわせて考えてみても、確実にこちらが意味のある調査だ。 10年後には、世の中のお客様調査はほとんどこれになっているのではないかと思う。 以下、memo P19.質問文の例「0~10点で表すとして、この企業を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか」、「そのスコアをつけた主な理由は何ですか」 P46.良い利益と悪い利益 →その違いは、マジ価値からお金を頂けているかどうかだと思う。 P.48悪い利益の例 ・飛行機の便数が少なく価格が高い。競合の参入を切望される。サウスウェスト航空の参入により、一気にシェア低下 P61.財務会計の数字だけでは、それが良い利益からもたされたのか、悪い利益なのか。コスト削減はサービス低下によってもたらされたのか、顧客離反率をおさえたものなのか。それがわからない P81~82.インテュイットの事例 電話による技術サポートの有料化に踏み切っていた。プログラムのインストールさ操作に四苦八苦する新規顧客も、その例外ではなかった。ところが、技術サポートに電話した経験がある顧客のNPSが全体の平均よりも著しく低かったことから、即座にこの方針に問題があることが判明した。担当チームは複数の代替案を出し、NPSへの影響をテストした。そして最終的に、購入後30日間は技術サポートを無料化することが、経済的に最も有利な解決策だと結論付けた。結果として、技術サポートに電話した顧客のNPSが、30ポイントを上回る改善を示した。(中略)電話サポートをインドからアメリカに戻した P99.肯定的な推奨の80%~90%は推奨者からもたらされる。「口コミによる利益」は全て、推奨者からもたらされると概算して問題ない。 P99, P212.推奨者を増やすメリット 経済性 - 価格に敏感ではない。 - 訴訟やサポートを受けるないので、LTCが低い - 販売コストが低い(クロスセル・アップセル) - 口コミによる新規顧客獲得 - 推奨者による新規顧客は、推奨者になりやすい 動機づけ - 肯定的なフィードバックによって、従業員の士気向上、離職率の低下 P100. 批判者のDMの大きさ - 否定的なコメント1件を消すのに、3件~10件の肯定的なコメントが相殺される。(こちらは定量分析に乏しいが、DELLが行ったアンケートではそのような回答を得ている。またこれまでの経験知的にもそれぐらいが妥当とのこと) p104.推奨による新規顧客獲得量の調査方法 - 新規顧客に何故購入したのかを聞く(複数回答) - 口コミによると答えた人数を、現在の推奨者の数で割ることで、推奨者1人につき、何人の顧客を獲得できたのかを知ることができる - (これ、複数回答でいいのかな?) - これにLTVをかけることで、推奨者を1人増やすことのLTVが算出される。 p108.競合調査の目的。直接的な競合よりも早く改善する p126. あなたはどれぐらい満足したか?という質問もある P148, P194.雑感。カスタマーサポート部署が問い合わせ対応に使う時間は、このNPSスコアを上げる価値と、そのコストという計算式で導き出すことができる。 P149.雑感。全体を表す必要はないが、定点観測を適切な顧客から実施するのは重要。 P149. 無回答者はすべて批判者と定義している会社もある。この簡単な質問にすら答えられないのは、推奨者が行う行為ではない。また無回答者の動向を追うことで、彼らの経済的価値を明らかにすることも可能である P154. コールセンターが質問回答後に聞くことも可能。サポートセンター経由での情報収集も、手段のひとつとして考えてよい。 P159. サンプルの偏りは少なからず発生するので、定点観測を意識すれば、特に問題ない。 P164. スコアと行動の相関は定期的に検証をする。(これは恐らく、質問が複数だったり、代替的な手法によってNPSをはかろうとするときにおこる問題だと思われる。) P218. 批判者に俊敏な対応をすることによるメリット - appleでは追加売上高が1000ドル以上になる - 批判から中立・推奨にかえるメリットもある - ここも費用対効果を分析したうえで、実行する価値がある P224. 口座残高の多寡で手数料を取るようにしたところ、口座残高が多い顧客からも批判の声が上がった。悪い利益を生むことは、それで得をする人にも、悪い印象を与えることがある。 p227. e-NPSも同様に重要である。これは入社90日と、入社記念日で調査するのが良いのではないか。 P310.e-NPS質問文例「働く場所として、この会社を薦める可能性はどれくらいありますか」 P236. 批判者にTELするなら、0点から対応すべき P248.アメックスでは、カード紛失後の対応で、NPSスコアが大きく変化する。NPSスコアが大きく変わるキーポイントを見付けられれば、そのための対策が打てる P298. 一年以内の極端な値上げは、それがリーズナブルなものだったとしても、NPSを下げる要因になった。ので、定期的な契約更改を行うようにした。このように、NPSを変化させるスポットを見付けるのも重要。 P252.エンジニアは顧客フィードバックが届くことを喜んでいる。=直接電話しなくても、その声を届ければ、エンジニアにも、改善が届く P255.投資信託会社のバンガード・グループでは、顧客からの電話が多い時、徴兵制度によって、経営陣にも顧客との電話をさせる P256.インテュイットのフォローミーホーム。家に行って、インストールする様子を観察させてもらう P257.インテュイットの全事業の戦略計画の中には、NPS目標とスコアを上げるための重要な取り組みが盛り込まれている P262.回答分析ツールも欲しい プログレッシブでは、「オンライン支払」というワードが、推奨者にも批判者にも多いことに気づいた。詳細分析の結果、それが一回でスムーズにいくかどうかが大きな分かれ目になっていることがわかった。 P266.インテュイットの事例。回答によって、次の質問を変化させる。批判者にはその主な理由を、中立者には、どうすれば推奨者になってくれるかを、推奨者には薦めるときにどんな話をするのかを。 P282.NPSに取り組む際には、最前線のチームを小さな単位に再編して責任をより明確化するか、すべての顧客体験を効果的に取り扱える機能横断型チームを作る必要がある。 P286. 熱狂的な顧客サポートという文化を構築し、維持するためには、適切なタイプの人材を採用することが重要である。byラックスペース P302.クロスセルを行うときに、以前の回答結果を踏まえて行うとより効果的である P316.NPSを活用できているかのチェック項目 - 少なくとも1年に1度NPS調査を受ける顧客比率は何%で、どのくらいの回答が戻ってくるか。これらの顧客は売上高の何%を占めているか - 「クローズドループ」を用いて、フォローアップのために48時間以内に連絡をとっている批判者は何%にのぼるか。連絡をとった人々のうち、講じられた対応に満足した人はどのくらいいるか? - 所属部門の現在のNPSとその目標を知っている従業員はどれぐらいいるか。また、その目標を達成するために必要な最も重要な改善点を一つ挙げることのできる従業員はどのくらいいるか。 - ターゲット顧客セグメントの中で、推奨者と批判者の障害価値の違いはどのくらいか - 推奨者を増やすために最も重要な取り組みは何か。推奨者1人を生み出すためにかかるコストはどのくらいか P322.調査疲れとの戦い - 顧客との事前合意 - 調査後にコミュニケーションをとる - 投票のような仕組みを用いた調査 P339. 期待値を大きく超えた瞬間を、真実の瞬間と定義している。 P342.第三者機関に対して調査を依頼して、競合比較を行う。(これはパイの取り合いになってからでよいか。) P353.インテュイットの事例 - 推奨者、中立者、批判者の経済的価値を信頼性が高い形で試算する。財務リーダーをプロセスに参加させる -マネジメント変革への長旅としてNPSに取り組む - 取り組みに参加している企業のほとんどは、突き詰めていくと、社内の人々にかかっていると答える。「サービス」志向な人材を新たに採用する方法や、初日から彼らの心を惹きつけ、うまく溶け込ませるための方法を探さなくてはならない。 - 物語と事例の共有を通して、企業価値は強化されていく。学習するそしきとなり、強い意識とスキルを開発する、有意義な方法を開発していかなくてはならない。 by 顧客体験及びビジネスエクセレンス担当バイスプレジデント ブライアン・アンドリュース
0投稿日: 2017.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ顧客満足度を計る新しい指標についての解説本。 解説本なので、これに興味をいただかない人にとっては読む価値はゼロ。でもビジネスをやっていて顧客満足度を気にする人であれば一読の価値あり! これまでの顧客満足度調査は、確かに小難しすぎて自社でやるには難易度が高いし、やったあとに残るのは、お客様の満足度がどうだったかというだけで、具体的な改善アクションに移りにくい。そのため顧客満足度ではなく顧客満足度を知ることによる自己満足に過ぎない。 ネットプロモータースコアによる調査は、自社でやることも出来るし、その後のアクションも単純明快で分かりやすい。ただしその分、全社を挙げて本気でやらなくては何も意味はなさないのだけど・・・。
0投稿日: 2014.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ◼︎定義: ・UQ:この会社を友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか。 ・優れた価値を提供しているか(理性)、良いリレーションがあるか(感情) ・推奨者−批判者 ・推奨者を増やし批判者を減らす、それが正しい行いであるという想い ・単なる市場調査ではなくPDCサイクルのCでなければならない ・自らが他人に求めることを他人に行えリーダーは去る時に置き土産を残していくもので、それによってリーダーとしての軽重が計られる。 ・悪しき利益:短しがんてき、顧客とのリレーションを犠牲にして稼ぐ利益。→批判者を増やすことにつながる、批判者は企業の成長を阻害する。 ・感動を与えるためにより踏み込んだ工夫が必要 ・成果報酬サービスにおけるNPSの経済性 ・NPSを計測する目的→行動が5DNAに則っているかを確認する ・ロイヤリティの高い従業員がロイヤリティの高い顧客を作る ・顧客とのクローズドループを日々のリズムに組み込む(顧客からのFBへの対応スピードが重要)
0投稿日: 2014.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自社に対する顧客や従業員のロイヤリティを測定るするNPSという指標について提唱されているg本。事例も載っていて理解しやすい。万能ではないけれど曖昧なCSRという概念にこうした指標を取り入れるのは面白い
0投稿日: 2014.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ・分析手法の有益性、競合との相対比較に意味があり、マーケットシェア、成長率との強い相関あり ・良い利益と悪い利益を定性的に区別する ・加えて、生涯利益のフレームワークを活用しえ推奨者の経済的なインパクトを定量化できる ・ボトムアップとトップダウンによる正確な計測が鍵だが難しい、報酬連動は慎重に ・コアプロセスにクローズドループを取り込むことが肝要、しかし、時間も組織としての太いコミットメントも必要
0投稿日: 2014.03.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ■ファン顧客 A.近年、多くの企業が顧客中心主義を掲げているが、あまりうまくいっていない。それは、顧客ロイヤルティは目標とするにはつかみどころがなく、売上ノルマなど、日々の優先課題に追われるうちに、顧客との関係を犠牲にして獲得する「悪しき利益」に誘惑されてしまうからである。 B.悪しき利益は、企業からひどい扱いを受けたと感じる「批判顧客」を生む。彼らは購入を減らし、否定的な口コミを広める。これに対し、自社を熱心に紹介してくれる「推プロモーター奨者」がもたらすのが「良き利益」で、企業に持続可能な成長をもたらす。
0投稿日: 2013.04.07
