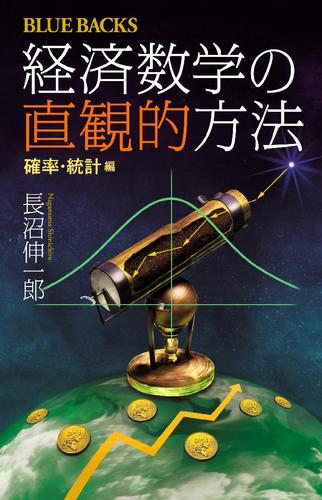
総合評価
(28件)| 7 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ〝経済数学″の頂点は、マクロ経済学の「動的マクロ均衡理論」と、金融工学の「ブラック・ショールズ理論」の二つであり、それゆえ「二大難解理論」とされる。 本書は、その〝難解な理論″をできるだけ直観的に解き明かそうとする一冊だ。私は長沼伸一郎氏の「〜の直観的方法」シリーズを好んで読んでいるが、正直、本作はかなりの難物である。正規分布曲線のメカニズムなど、統計学の基本的な部分はまだ理解できるとしても、金融工学の章に入ると途端に霧の中に置き去りにされる。「確率過程とランダム・ウォーク」「ブラウン運動とブラック・ショールズ理論」「伊藤のレンマと確率微分方程式」「測度とルベーグ積分」などは、雰囲気しか掴めなかった。 それでも、理解できた範囲で考えてみたい。 正規分布とは、試行を重ねるうちに結果が平均値の周辺に集中し、平均から外れた値が少なくなるために、自然と山のような形になる分布のことだ。平均のまわりが高く、左右がなだらかに減っていく— あのベル型のカーブである。これは、美術のデッサンに似ている。複数の線を重ねながら一本の“正しい線”を見いだす作業。その試行錯誤が、本質を浮かび上がらせる。哲学における言葉の素描— 対話を重ねながら議論の中心を探るパロールの作業にも似ている。 その背景にあるのが「中心極限定理」だ。バラバラな出来事を平均すると、なぜか必ず正規分布に近づくという不思議な法則。テストの点数も、身長も、株価の変動も— 多くの要素が重なった結果、平均を中心に山型の分布を描く。著者はこれを「神の意志のような法則」と表現していたが、結局“平均”とは、物事の背後にある設計図や特性を見抜こうとする行為なのだろう。狙い(設計)と実際のズレの集積が、あの山型を形づくる。 そして、株価の変動に潜む「確率的なゆらぎ」を金融工学に取り込んだのが、ブラック=ショールズ方程式である。株価がランダムに動くことを前提に、「リスク」「時間」「金利」などの要素を組み合わせて、オプションの“公正価格”を導き出す。偶然性を逆手に取って未来を予測しようとする、実に大胆な理論。 この論理の細部は依然として難しい。だが、乱暴に言えば、酔っ払いのようにランダムに歩く人でも、なんとなく進む方向の“意思”はある。その微かな傾向を確率論で掴み取り、未来の価格を推定する。そこにこの理論の凄みがあるのだと思う。
75投稿日: 2025.10.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ一応理系の大学院を卒業しているものの、基礎的な統計学の勉強から逃げてきたので、本当に初歩的なところも理解できていないことに、なんとなく後ろめたさというか、世の中も重要なことから逃げているような気がしていた。 そんな中ひょんなことから統計学の勉強に手をつけるようになり、数年前に購入していた本書を再度手に取ってみた。あらためてしっかりと読み始めてみたけれど、めちゃくちゃ面白い。 自分の中で「とにかく世の中のたくさんのことは正規分布で表現できることが多い」くらいの理解し保てていなかったことに対して、パチンコやベルトコンベヤーなどの巧みなメタファーを用いて本質的な説明をしてくれる。ゾクゾクするほど面白い。 なるほどな。二項分布というものにおいて、その確率を50%として、nをどんどん増やしていくと正規分布になるのだな。
1投稿日: 2025.09.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ物理学と経済学の橋渡しとなる考え方を教えてくれる本の第2部「確率・統計編」。 ブラック・ショールズ式の理解をゴールに進む誌上レクチャーは、段々と見えないものがおぼろげに姿を現すという快感が得られる。
0投稿日: 2025.07.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ●2025年5月26日、東京大学・書籍部にあった。セッションで寄った日。 むずいが、これぐらい分かりたい。
0投稿日: 2025.05.26 powered by ブクログ
powered by ブクログブラックショールズ方程式の"気持ち"を噛み砕いて説明してくれる。著者のイメージは独創的で新たな考え方を与えてくれる。
0投稿日: 2024.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ文系挫折経済学科出身修士にはベストな難易度。 語り口が面白いし、ストーリーテリングに全振りしたが故に枝葉は捨てていることもちゃんと書かれている。
0投稿日: 2023.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。頭でイメージを描きながら読むといいかもしれない。以下、要約。 ❶初級編 ①確率統計論が本格的に進化したのが19世紀である。ガウスの貢献が大きい。ニュートン力学が17世紀に始まったことを考えると発展は遅れている。 ②ガウスの思考を辿ることが確率統計論を本質的に理解するのに必要と考える。ガウスは確率論を真正面から考えていたのではなく『誤差』を基準に考えていた。そして、この誤差を考えて導き出したのが『正規分布曲線』である。 ③誤差というものは2つに分類できる。1つは『一定方向に出る誤差』、もうひとつは『+方向と-方向に同じだけ出る誤差』である。前者は逆方向に修正かければ良いので問題にならない。ガウスが扱ったのはランダムに動く後者である。 これを株価の考えに落とし込むと、前者が『トレンド』といわれるものである。後者が『ボラティリティ』である。 そして、ブラックショールズは『ボラティリティ』を中心に扱うオプション価格の算式であり、ボラティリティが時間と共に拡大することを利用して利益を上げることを考えるのである。 ④標準偏差を考えるにあたり重要なのが2つ。1つは平均がどこか、もう1つがバラツキ具合(平均からの距離)である。 ⑤正規分布において、σは中心線から変曲点までの長さで表現する。 ⑥e*-x^2が正規分布を表す基本形であり、釣鐘型の曲線となる。 ❷中級編 ①確率論を学ぶのに重要な概念は3つ。1つめは最小2乗法、2つめは中心極限定理、3つめは確率過程とランダムウォークである。 ②最小2乗法とは、得られたデータが誤差でばらついて本当の値がわからない時、その真の値を割り出して、誤差を最小にするための手法である。 ざっくりいうと、中心がどこにあるのか測るために使う。 ばらつきが正規分布に基づくのであればその中心(平均)からの距離の2乗は最小になる。2乗する理由は精度が上がるからである。感覚的にも、中心に近いデータは数が多いが誤差が小さくなる一方、中心から遠いデータは数が少なく誤差が大きい。そのため、中心からの差を2乗することでデータのばらつきを測る精度を上げるのである。 ③様々な確率分布はたくさん集めて重ね合わせると、結局、正規分布に行きつく。ポアソン分布、ベキ分布、二項分布などは正規分布をベースに特殊化を行ったり、バイアスをかけた形で成り立っている。もっとも、二項分布は正規分布とはニワトリと卵のような関係で、試行回数が少ないと二項分布になるし、試行回数を無限回に近づけると正規分布になるからである。 ④経済予測する立場としては中心極限定理は極めて有用である。マーケットなどは多種多様な要因が重なり合って数字が形成されていくが、この定理に基づけば様々な確率分布は結局、正規分布に集約していくと考えることができる。 例えると、様々な光が集約すると、白色になるように全てを合成すると正規分布になり、人間が扱いやすいものになるのである。 ⑤金融市場では正規分布に基づくモデルは古く使い物にならないという話もよく聞く。ただ、プログラム売買の弱みは、なまじマーケットにフィットするプログラムを使っていると、皆が同じものを使い始めて結局一方向にマーケットが振れやすくなってしまうのである。他者を出し抜こうという動きが出れば出るほど、この呪縛からは逃れることができない。 あらゆる分布の始祖は正規分布であり、様々なプログラムを作っても、数多く集めれば結局は正規分布から外れることはないのである。 ⑥時間的な拡散の幅は√t倍で拡散していく。これは2次元でも3次元でも同じである。標準偏差がσの確率分布をn個集めてそれらを足し合わせるとそれらを合計した確率分布は√n・σとなる。 この時間の平方根と標準偏差σを掛け合わせたものが確率過程を考える上でポイントとなる。 ° ⑦オプションを考えるにあたって時間的価値は非常に重要な概念だが、それは確率過程を考えるにあたって利益は時間tに比例する形で拡大すると考えているからである。 ⑧経済全体を『トレンド』と『ボラティリティ』に基づいて考えてみる。例えば、名目成長3%程度の経済成長を世界経済は『トレンド』として想定している。これは指数関数的な動きを想定しているので、物質的な動きが連動するとは現実的には考えにくい。そのギャップをインフレという形が埋めるしかない。そもそも、現代金融が金利の計算を複利計算を前提としており、経済全体の前提を指数関数的に捉えざるを得ない状況になっている。 『ボラティリティ』で大きな役割を果たすのが金融だろう。特に、リーマンショック以降は先進国は量的緩和を行い、資産高にすることで資産効果が成長率底上げにつながった部分はあると思われる。 ❸上級編 ①確率微分方程式の中核をなす理論は伊藤のレンマである。 ②今までやってきたことはdx=Adt+Bdwで表すことができる。つまり、Adtは『トレンド』にあたる部分、Bdwは『ボラティリティ』にあたる部分である。 ここで欲しい答えはxという独立変数があって、その影響で動くy、つまりy=F(x)があって、これが時間tの影響でどう動くかが知りたいのである。つまり dy=○dtのようなものが欲しい。 ③天体力学を扱う視点からは上記のAdtの部分の答えが欲しいのである。Bdwはノイズであり、何とかこれを除きたい。それを可能にしたのが伊藤のレンマである。 ④これを解くのに必要なツールが『テーラー展開』である。いわゆる、近似値をとるためにF(x)を微分していくものである。例えばdx=0.1の場合、dx^2=0.01、dx^3=0.001であり、使うのは最初の2つか3つであり、あとは無視できるのである。 上記のAdtの『トレンド』だけ抽出するツールとしてはうってつけである。 ⑤ケインズ経済学では最も役に立つツールが等比級数の和とテーラー展開の2つといわれている。 ⑥テイラー展開をしていく中で極小の値は切り捨て、拡散半径が時間的にどれだけ拡大するかの式、dw=√dtを使って書き換えを行うことにより、dtとdwに分かれた式の抽出を行うことができる。 Bdwは『ボラティリティ』を表す式で、この中には+と-が混在しているはずである。そこでBtw^2の2乗というものがポイントになり、絶対値として評価すると正規分布を表す式として活用できるのである。 ⑦この伊藤のレンマはx→y→zのように多段式になっている場合も活用できる。通常は先に進むと式が汚くなって前進不能になるが、伊藤のレンマで単純化することにより、前に進めるようになるのである。 ⑧最終的なブラックショールズの式に至るのに、重要なツールとしてフーリエ級数というものがある。これは、いろいろな三角関数の動きを使って目的となる関数を描こうとする試みである。 ❹測度とルベーグ積分 ①経済などは本質的にはデジタル(=買う、買わないの2択)などで表現されるものであり、いわば不連続なものである。 この不連続なデジタルをアナログに変換するためのツールが測度とルベーグ積分である。
0投稿日: 2023.01.22 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057418
0投稿日: 2022.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ近著「世界史の構造的理解」が面白かったので、既刊本を著者買いした。結論としては買って正解だった。 当方(文系)の能力不足により、上級編は「科学読み物」になってしまったが、確率・統計の基本を書名通り直観的に解説した初級編・中級編が非常に有益だった。 正規分布、標準偏差等の概念が真の意味で理解できるようになったし、トレンドとボラティリティの違いも使える知識として記憶に残った。文系でも「実用書」として読む価値あり。
1投稿日: 2022.08.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ数学III・C → 20年前に履修 物理 → 未履修 経済学 → 完全にど素人 という自分が読んでも、大筋の内容が理解できた。 聞いたことのない難解な経済学上の考え方が次々と自分の理解に落ちていくのは結構爽快。
1投稿日: 2022.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生の時は覚えるだけだった正規分布、分散・標準偏差、中心極限定理などのイメージづけから、 その時間経過、ブラックショールズ理論の直感的イメージ、経済モデルの展望までつながったのは、 確率統計の枠を超えて何か壮大な物語を見ているようだった。 同著者の他の本も読んでいるが、初学者から専門家への橋渡しをするために果敢にチャレンジする姿勢と、 あくまで直観的方法だと割り切りながらも橋の繋ぎ目への気配りが丁寧になされており心地よい。 まるで近所で親しくしてくれるお兄さん・おじさんのような、距離感を大事にした愛を感じたのだった。
1投稿日: 2021.12.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ評判は良いようだが,自分には余計なイメージばかりで,まるで使い道が無かった。ガウス『誤差論』あたりを念頭に置いた構成か?
0投稿日: 2021.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログまず√tが肝だと思った。 直観は人を騙すことも多いが、この本はアイデアが分かりやすくなっている。 誤差をトレンドとボラティリティに分かれるのは知っていたが、ボラティリティだけで利益が得られるのは驚いた。しかし、芥川龍之介の[蜘蛛の糸]のように、みんなが真似したら、利益は減るということは当たり前だと思った。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000194946 , http://pathfind.motion.ne.jp/
0投稿日: 2021.02.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ話のテーマとしては経済学関連の内容だが、確率統計の基本思想を学べるため、統計学を学ぶ人にとっても有用。 確率統計は何を目的に作られたのか、といった具合に学問が生まれる過程から解説されているのもあり、数式の意味合いが直感的に理解できるようになった。 ひととおり統計学の基礎を学んだ上で、この本を読むことで、より理解が促進されるように思う。
0投稿日: 2020.12.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計学を噛み砕いて分かりやすく教えてくれそうな本であってくれ!と思いながら手に取った。 正規分布に関する説明はかなり分かりやすく、今までの本の中で一番しっくりきた。正規分布とは何かというところの理解は統計学を学ぶ上で土台となるので、今後の学習にプラスになったはず。 誤差には2種類ある。 一定方向に現れ、予測しやすいもの=トレンド 左右均等に現れ、神の手によるもの=ボラティリティ 現代はトレンド要素がなくなり、ボラティリティの世界らしい(ITは例外であると思う。ハード面の豊かさかな)。 ボラティリティの世界とは、誤差が左右均等に現れる世界であり、いろんな事象が正規分布に従う。 以前「その数学が戦略を決める」で、絶対計算が優位になっていく世界について知ったが、それもボラティリティの世界であるからこそ。 もう一冊くらい統計の本読んで、必要性を理解したら自然に統計の勉強が捗ると信じている笑 To 統計学は最強の学問である
0投稿日: 2020.06.24ボラリティ大事
理系・文系ともにオススメしたい。いわれて見ればソニーの事業構造が整備されたのは、金融部門やコンテンツが製造部門に加わって事業のポートフォリオで「ボラリティ」が上手く出来たことが大きいですね。ボラリティはたぶん大事な概念。
0投稿日: 2020.01.06 powered by ブクログ
powered by ブクログすごく良かった。ブラックショールズ理論の概略の理解を目的地にして、確率論の勘どころみたいなものを読み物として教えてくれる。これまで確率論にほとんど興味を持てなかったのだけれど、興味を惹かれるようになった。 学生時代に読んでおけば数学の学び方になったかもしれない。 190404
0投稿日: 2019.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最初は良いが、だんだん著者の独特な語り口調が鼻につくようになる。特に文系と理系を分けて述べていくが、著者のこの区別が独りよがりのように響いてくる。わかったようでわからない読後は不思議な気分。
0投稿日: 2018.08.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ筆者が理系読者と文系読者を区別し過ぎてる感はあるが、両方を対象と想定していることもあり、内容は分かりやすくて良い。
0投稿日: 2017.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログマクロ編は面白かったので喜んで確率統計編に突入するものの、ちょっと風向きが変わっててあまり楽しめませんでした。統計は大体わかっていたのがいけなかったのかも。それで、そのわかりかたは長沼さんの理解の仕方とはちょっと違っていて、どちらも不正確な例え話なので似ていると余計にちょっと違うんじゃねえの?って感じになっちゃう。まあ、アプローチがそのような本なのでこのような読者が出るのは仕方ないかも。マクロ編と違って著者の個人的な考え方が全面に出ているんだけど、この部分は控えめに言ってまあ読まんでもよいかなという感じでした。ブラック・ショールズの説明とか、ルベーグ積分とか、やっぱ知らないことに対しての説明はすごいよいので、まあ知っているか知らないかによって全く評価がわかれるんだろうなと。
0投稿日: 2017.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ概念を大まかに掴むという発想で書かれており、知識の整理に役に立つ。もう一度、厳密に確率論を学んでみたくなった。
0投稿日: 2017.01.23確率微分方程式と伊藤のレンマ
非常に分かりやすく本質が絞られた本だと思う。 特に絶対値とばらつきを使った導入から伊藤のレンマへの持ち込み、微積分の合成積分を使った特性毎の分割への到達はこの分野に興味を持ちながら手をこまねいている読者には天啓のように響くように思う。 最後のルベーグ積分の説明も良かった。 良書です。 星5つ。
7投稿日: 2017.01.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ先行の「マクロ経済学編」に続く今作のテーマは「正規分布」。前著同様、自然科学に対する西洋科学のスタンスが、経済という人文系分野の現象を理解するメソッドにも適用されているという含意が底流にある。本著では、天体等の自然現象を観察して得られたデータのバラツキを、データそのもの持つ「バイアス」と、ノイジーな「ランダムネス」に分解して理解することがが可能であることが示され、その思想が金融工学で扱われる「ブラック・ショールズの公式」に目に見える形で(数式を見ればそうなっている、ということがわかる形で)取り入れられていることが紹介されている。他の方のレビューにもある通り、本著の方が論点がシンプルで理解しやすい。 数式をほとんど使わない初・中級編、やや数式が頻発する上級編という構成も前著を踏襲。基本的に上級編まで読んだ方がより理解が深まるとは思うが、ブラックショールズを論じる上で必須と思われる「テイラー展開」がほぼ端折られているので、結局上級編を飛ばしても直感的理解にはさほど影響しないかも(テイラー展開をまともに扱われたら私などの手にはとても負えなくなるが)。それでも、相対的なオーダーの大小を大胆に利用してバイアスとランダムネスを切り分ける「伊藤のレンマ」の解説は一読の価値あり。一般に精緻だと思われている数学が、現実世界に適用される場合には意外なほどの寛容さを見せることの驚きを経験できる。 他には、例えば様々な現象の分布状況を足し合わせると、それぞれの分布のバイアス部分が相殺されて純粋な正規分布が残されるという「中心極限定理」が、人間の顔写真を無数に重ね焼きしていくと徐々に平準化され最後には美女・美男子が現れるという話が想起され面白かった。この辺り、前作の「ミクロの集積→マクロ」とも繋がっている気がしなくもない。また「神」が定めて人間が変えられない部分と、人間が扱える部分を峻別するスタイルが、如何にもキリスト教的「西欧」だなあと思った。
0投稿日: 2016.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作では専門外ながら「動的マクロ均衡理論」の直感的理解が簡単にでき、続編の出版を待望していた。今作を実際に読んでみて、前作同様”直感的”という意味では「ブラック・ショールズ方程式」の背景・内容ともに理解はできたかと思う。その意味では非常に素晴らしく可能ならばシリーズ物として続いていって欲しい。また、本書読了後、さらに詳しく知りたくなり大学教科書を読み始めた。そういう意味で経済をバックグラウンドとして持たない人にとっては専門書との架け橋ともなりうる本なのかなとも感じた。
0投稿日: 2016.12.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ最新の経済学が物理数学と密接につながっていることがよくわかった。まさか変数分離が出てくるとは予想もしなかった。前著よりもこちらの方が読みやすく、意味深い。トレンドとボラティリティを忘れずに。
1投稿日: 2016.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ現代社会を浮き彫りにする経済学。この経済学を表す経済数学は高度に発展してきました。なかでも、マクロ経済学の「動的マクロ均衡理論」と、金融工学の「ブラック・ショールズ理論」は「二大難解理論」として、その頂上をなしています。 この『経済数学の直観的方法』の2冊では、目標をこの「二大難解理論」にしぼっています。これらを直観的に理解してしまえば、そのツートップの頂上から経済数学全体を見渡す格好になり、今までのミクロ経済学などのたくさんの数学的メソッドを、余裕をもって見ることができるという狙いです。 本書では、「確率・統計編」として、現代の金融工学の礎となる「ブラック・ショールズ理論」を身につけます。70点に及ぶ図・グラフを中心に、「正規分布曲線が生まれるメカニズム」「標準偏差、分散の意味」「最小2乗法の基本思想」「中心極限理論の不思議」「確率過程とランダム・ウォーク」「ブラウン運動とブラック・ショールズ理論」「伊藤のレンマと確率微分方程式」「測度とルベーグ積分」など、重要テーマの本質的理解を試み、教養としてのブラック・ショールズ理論を身につけていきます。
0投稿日: 2016.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者の他の本と同じく、語り口はややくどい。 パスカル三角形や酔歩のイメージは、他の解説書でもよく提示するが、なぜ「自乗が登場するのか?」という問題提起や、それを幾何学と「運動」っぽいイメージで解説するようなところが、物理出身の人ならでは、というところか。
0投稿日: 2016.11.16
