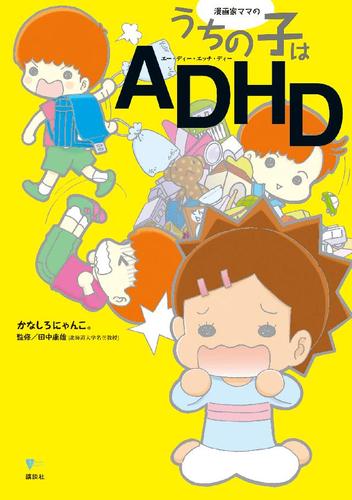
総合評価
(12件)| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ【あらすじ】 片付けができない、モノをよくなくす、学校ではケンカばかり……、そんな問題だらけの息子、実は発達障害でした!「愛情不足じゃないか」と言われて落ち込んだ幼稚園時代、息子と友達の家に謝りに行った小学校のあの日、そして大ケガをきっかけに相談所へ。児童精神科医が下したのは、ADHDの診断だった。いろいろあるけど、かわいい息子との悪戦苦闘の日々を、漫画家ママがていねいに描いた傑作コミック。 ・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆ ADHDと診断された息子さんを持つお母さんが描いた、発達障害と向き合う日常のコミックエッセイです。私の子どもも先日「ADHD・自閉症スペクトラム」と診断され、話を聞きに行ったクリニックで紹介されていたためこの本を手に取ってみました。 思ったこととしては、子ども本人が落ち着いて過ごせることを一番大事にしてあげることと、「性格」として世の中に受け入れられていくのを粘り強く見守ることが大事なのかな。とにかく、イライラしたり叱ったりしても事態は好転しない ということを肝に銘じないといけないと思いました。 昔は「ちょっと変わった子」と捉えられていたものにも病名が付くことで、浮き彫りになってきた側面があるのではないかと思います。子どもの頃、そして大人になった今の私自身にも心当たりがある行動傾向がいくつもありますが、社会人として働いていますし、家庭も持っています。ADHDか否か、白黒はっきり付けるのは本当に難しいのだと思いますが、ADHDという診断が、「生きにくさ」を少しでも和らげるキッカケになると良いと思います。
14投稿日: 2025.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログかなりキレまくるお母さん。キレたって本人もお母さんも辛いだけ。 とか簡単に言えるのは外野だから。 お互い人間ですからね。神も聖人もなれない。 だからこそ知ることが大事。 そしてやっぱり、保育者や教師には知っておいてほしい。 でもやっぱり先生も人間だから、そうそう上手くはいかない。 だけど、うまく行かないからこそ知っておくこと、知識を得ておくことは大切なんだと思う。
0投稿日: 2023.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログADHDでも、この子の場合は酷すぎるように思える。二次障害出ているのでは…? 自転車で坂をノンブレーキで滑り降りるとかも、人が死んでもおかしくない。(実際これで子供が人を不随にして、1億円くらい賠償命令出たことあるらしい) 危険予測ができない子だが、こんな子を目を離して遊ばせている方も危険予測できていない。 この親にしてこの子ありのような気もする。 親子共にIQとかは検査したんだろうか。 でもこういう子供がどういう大人になるかを追えるのは興味深い。 小学校低学年の頃、フラフラ席を離れてしまう男の子はクラスに2、3人はいた。 当時はまだ体罰の名残があって、教師が飛びかかり床に押さえ付けて反省させていた。犬の調教のようだった。 その子達は高学年になると、そんなに目立たない存在になっていった。中学年頃のちょっと大人しくなった時が一番程よく愉快で面白い時期だったかも。 あの子達はどうなったんだろう。Facebookでも、あの子達だけは全然出てこないのだ。 今は犬のようにふん縛って調教する教師はいない。 ニコニコしながら廊下の隅の反省部屋に押し込む教師はいる。 こういう子達の未来は良くなったのだろうか? そもそも「皆と同じ事をしなければいけない空間(保育園、学校)」がなければ、不幸になる事も自尊心を失くす事もないのではなかろうか?
0投稿日: 2023.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画で読みやすい。ADHDの特質を作者の実体験を元に描かれている。実際にそういうタイプの子の親になった時このような知識があるのとないのとでは全然違うんだろうなぁと思った。
3投稿日: 2021.05.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ作者のお子さんの様子がマンガでとてもわかりやすく描かれていた。この本を読んで、うちと一緒と思える人もたくさんいると思う。作者が様々な人と出会って子どもとの関わり方が変わっていくのも素敵。
0投稿日: 2021.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログADHDの子どもについて理解するための第一選択として、オススメ! マンガなのでエピソードからADHDの特性が大変わかりやすい。(もちろん、ADHDがみな同じわけがないので、一例でしかないが。) そして、マンガの後にはこの道の第一人者、田中康雄先生の解説がかなり詳細にわたって書かれている。その中で田中先生が「トットちゃん」の例なども引きながら、普遍的な大切なことについて語られている。 子育て中の親だけでなく、学校関係者や支援関係者にもオススメ。「どうしたらいいか」という悩みにも、かなり的確に応えてくれる。
0投稿日: 2020.02.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ立ち読みで読み切りました。 マンガで読みやすい。 気づくまでに時間がかかってしまうことも多いのですね。
0投稿日: 2017.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログいままでずっと、手のかかる息子だと思っていたら、ADHDだったといういきさつを描いた漫画です 漫画だから、買っちゃいました。 専門書は同じようなことばっかり書いてあって、しかも長くて読みづらいので笑 原因は親の育て方じゃないんですよ~。 「お母さんはあなたのこと大好きだよ」 って言葉に心あたたまりました
0投稿日: 2013.05.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ確かにADHDの特徴を持った子ってクラスに一人二人いた。 精神の症状を細分化すれば誰でも何かしらの障害を持っている事になりそう。 でも名前を付ける事によって接し方の道しるべになる可能性がある事がよいと思う。自分にとっても相手にとっても。
0投稿日: 2012.08.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ・小児科の待合室にあったので読んだ。 ・多分多くの人が「自分も落ち着きなかったし片付け苦手だからADHDの傾向があるかも」なんて感じに都合良く考えたりしてる気がするけど、実際のはとてもそんなもんじゃないだなと体験談を通じて理解。 ・病名をつけられた事でホッとしていた母親と対照的に、レッテルを貼られたくないといった拒否反応を示していた父親が印象的。どっちもわかる。
0投稿日: 2011.09.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ漫画でさらっと描いてあるけれど、ADHD児の辛さ、生きにくさが、そして母親としての育て方を周りから、そして自分自身でも責めてしまう心が、辛くて泣けました。 ここに描いたことなんてほんの一部で、現実は地獄のような日々だったかもしれません。 診断名がつき、育て方を学んで、母子共に笑顔で暮らせるようになり、本当に良かったと思います。
0投稿日: 2011.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ前から密かに思ってはいたが、この漫画で出てくる子どものキャラって、自分の小さい頃そっくり。自分が今の時代の子どもだったら診断名が付いたのだろうか? そう考えるとカテゴライズされるのも善し悪しだなぁ。
0投稿日: 2009.12.23
