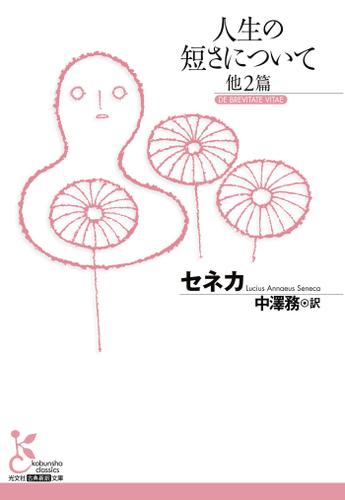
総合評価
(96件)| 21 | ||
| 37 | ||
| 24 | ||
| 4 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこれまで哲学書を読んだことがない自分でも理解しやすく、現代にも当てはめやすい内容になっている。古典新訳文庫のコンセプトがとても活かされていると感じた。特に、時間を奪われることに無頓着になりがちである話は共感できる人が多いような気がした。出会えて良かったと思える本だった。
0投稿日: 2025.10.14 powered by ブクログ
powered by ブクログミヒャエル・エンデの『モモ』を読了後、人生における時間について再考してみたくなったとともに、古代ローマの古典哲学も読んでみたいと思い、より読みやすい光文社古典新訳文庫版を購入。 本書は書名の「人生の短さについて」の他に「母ヘルウィアへのなぐさめ」「心の安定について」の2篇が収録されている。 セネカは代表的なストア派の哲学者とされるが、資産家の名家に生まれ政治家として活躍しつつも、8年余り離島に追放された経験を持ち、ローマに復帰してからは暴君で名高いネロの補佐役を務めた後にネロ暗殺の陰謀に加担したとされ自害しており、そのような波乱万丈の人生を送っていたことを本書を読んで初めて知った。 本書を読んでいると、およそ2000年前に著されたにも関わらず、当時のローマ人の人生観と現代人のそれとは本質的に変わっていないということに驚く。 当時のローマ人も現代人と同様、人生がいかに短いかを嘆き、それでも来るべき未来をより良く生きるために日々を過ごしていたのだ。 そんな状況の中でセネカは、「人生は本来短いのではなく、多くの人がそれを浪費しているため短くしている」と説く。 過去から学ぼうとせず、不確定な未来に頼ってばかりで今この時を(多忙を理由に)無駄に過ごしているからこそ、人生はあっという間に過ぎ去っていくのだと。 ミヒャエル・エンデ的に解釈するなら、「時間どろぼう」の存在が人生を短くしているともいえるだろう。 人生を長く充実したものにするためには、不確定な未来ではなく不変の過去に向き合い、そこから学んだことを基に現在という時間に集中して生きよと説くのである。 それがセネカのいう「閑暇な生き方」であると。 これは、頽落な時間を過ごす民衆を嘆いた実存主義のハイデガーにも通ずるものがある。 その他の2篇でも、実の母親や友人の悩みについてセネカの思想を基に説かれており、これら3篇を読み通すことでセネカとストア派の思想の源流を垣間見ることができるのではないだろうか。 ただ個人的には、「時間どろぼう」に囲まれながら生きていかざるを得ない現代人にとって、「過去から学び今を懸命に生きよ」と説かれても、困惑するだけなのではないかと思えてしまう。 自分を含め現代人は、「過去を振り返らずに未来に生きよ」という考え方や価値観に、あまりにも長い時間刷り込まれてきたのだ。「時間どろぼう」にがんじがらめにされている現代人にとって、いかに閑暇に生きることが難しいかを改めて思い知らされる。 そんな現代人が今を生きるために、『スマホ時代の哲学』や『暇と退屈の倫理学』に書かれているような「趣味への没頭」がひとつのヒントになるかもしれないが、時間どろぼう達がそれを許してくれるかどうか、結局は個人の時間に対する価値観や向き合い方次第ということになるであろう。 文字通り"ストイック"な生き方をこれでもかと説く本書は、3編を読んでいるうちはあまり共感できる部分は多くなかった。 ただ、全体的に注釈が充実していたのと、3編の後に約40ページの紙面を割かれている訳者中澤務氏の解説部分が、時代背景の説明とともに非常に分かりやすく述べられていたことで理解の助けになったので、星4つとした。
0投稿日: 2025.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ最高だった〜〜〜!!読んでよかったすぎ! 2025ベスト3に絶対に入れたい。 本当に最高だったから図書館で借りてたけど買ってくるし、他2編のうちの一つが岩波だとまた違うものが収録されているそうなのでそっちも買う予定! 読みやすいし生きるうえで役に立って格言がどっさり!安定の光文社古典新訳文庫なので注釈も同じ見開きにあるし解説や後書きも非常にやさしいつくりです。以下はお気に入りの言葉! 135 精神こそがわれわれを豊かにしてくれるのです。精神は、追放の地にも、荒れ果てた原野にもついてきてくれます。そして、体を維持するのに充分なものを見つけ出してくれるのです。その時、精神の内部には、自分自身のさまざまな良き性質が満ち溢れ、精神はそれを楽しんでいます。 143 自分自身に軽蔑されるようなことをしなければ、だれも、他人に軽蔑されることはないのです。卑屈で賤しい精神であれば、そのような侮辱を受けやすいでしょう。 こんな感じで最高なお言葉がたくさん! 2000年後の今も素敵な教えは生きているよ〜 あと親友セレヌスからのお悩み相談に登場した セネカすらベタ褒めの謎人物、カヌス・ユリウス! ガイウス帝にお前を殺すように命じたもんねー!と言われるも、あざす!尊い皇帝陛下!みんなー!魂が不死かどうか気になってたよね?自分が死んで身体から分離できたなら、みんなにそれを知らせてまわるからね〜!! すごすぎる…!自らの死すら学びに変える! セネカもこんな凄い人物が忘れ去られて言い訳ないって言ってる。私は今知ったけど、みんなに広めるよー!ということでここに残します。 本当に最高だったな。ストア派アツいかもしれん!そのうちまた再読して学び深めたいね!
6投稿日: 2025.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ本編を読んでいるかぎりは、何か頭を上滑りしていくようで、あまりよく理解出来なかったのだけれど、翻訳者の丁寧な解説を読んではじめて、ああ、なるほどなと思った。 セネカ自身が言っているように、ストア派のいう賢人などはこの世に存在しないのだろう。勿論その賢人が持つとされる徳に満たされるような人物になろうとしているのだけれど、なれるかどうかではなくて、その過程のうちに死を迎えるのが大事なのだろう。 未来、ではなく現在に向き合うために、過去をつまり歴史の英知を学び、人類全体の幸福を追求しようとしたのがこのストア派なんだという解説をみて、他の本も読んでみたくなった。 確か、松井秀喜がストア派の本の帯で勧めていたのを記憶しているが、あの長嶋茂雄さんとの1000日計画において、過去の英知にそれこそ、浸れたのだろうと思うと、凄い時間だったんだろうなと思う。
1投稿日: 2025.07.31 powered by ブクログ
powered by ブクログいかに生きるべきかを哲学者のセネカがズバッと述べている本だ。人生は使い方次第で長くなる、浪費して短くしてしまう、現在は短い、アウグストゥス、キケロ、ソクラテス、エピクロス、ガリア、セレヌス、ヘラクレイトス、デモクリトス、カトー、哲学も少しは知っておく必要がある。
0投稿日: 2025.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログセネカの哲学から人間いかに生きるかを学ぶことができる本。 人は人から時間が欲しいと言われるとすぐに使ってしまう、そして自分の時間がなくなっていく、時間は目に見えないもので一見多く残されるように見えてしまうからであると言えるが、自分の時間を大切にし時間にけちであることも大事であると学ぶ。 また多忙であることにも注意が必要である。忙しいとは心が奪われている状態であり、自分に向き合えていない状態と言える、そして過去を振り返ることも嫌い、今を多忙に過ごしている人たちもいる。しっかりと自分自身に向き合い、多忙ではない閑暇な時間を作ることも生きる上で重要であると学ぶ。 時間の長さは時間で測ることができるものでなく、時間の過ごし方の質で変わるということ。一見おかしな解釈に聞こえるが、過去に向き合い今の時間を大切にすること、物事を先延ばしにして未来の時間を奪うことなく今の時間を大切にすることが重要であり、その質が高く生きていれば人生は十分に長いと言える、感じられるということと理解する。 その他、このセネカという人物の教えはストア派という自然哲学の思想からきている。財産や地位といった世俗的で人為的なものを排除し自然的なものを価値のあるものとして受け入れる考え方である。こういった哲学、それを取り入れている背景を学ぶことがまた重要である。
2投稿日: 2025.07.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生は長いようで短く、短いようで長い。それは自分の時間を善く丁寧に生きれば、充分に充実した時間を得られるだろうと説く良書である。 セネカの死生観や哲学は現代でも活かされており、時代や国、文化を超えて問いかけと生き方を教えてくれる。 さて、人生は有限だ。だが、時間は無限のようにあるように体感してしまう。だから、時間を浪費してしまうのだろう。現代では時間を溶かすコンテンツはありふれている。これからもそれらは増え続けていくだろう。1日は24時間しかない。使える時間はもっと限られる。その中で、どう生きればいいのかわからないときは、自分の死をイメージして行動せよとセネカは説く。死を意識することで視点は大きく変わる。人生は何が起きるかは誰にも自分でもわからない。今日死ぬかも知れない。そう意識いして生きるだけでも悔いの残らない善く充実した人生になりえよう。
0投稿日: 2025.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ「四六時中、他人を危ない目にあわせようと画策したり、自分が危ない目にあうのではないかと心配したりしている。」 私にはどっちの発想も無いので、余計な思惑や心配が無い分穏やかに人生を過ごせて生きやすいと思ってる。 しかしページがちっとも進まない。 大切なことが書いてあるのは分かっている。でも海外文芸特有の翻訳の言い回しが昔から苦手で、読んでも読んでもちっとも頭に入ってこない。文字が上滑りしていく。 だから途中で読むのをやめた。また今度読もう。 #人生の短さについて #セネカ #読書
0投稿日: 2025.05.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者、セネカは、ウィキペディアによると、次のような方です。 ---引用開始 ルキウス・アンナエウス・セネカ(ラテン語: Lucius Annaeus Seneca、紀元前1年頃 - 65年4月)は、ユリウス=クラウディウス朝時代のローマ帝国の政治家、哲学者、詩人。 ---引用終了 で、本書の内容は、BOOKデータベースによると、次のとおり。 ---引用開始 人生は浪費すれば短いが、過ごし方しだいで長くなると説く表題作。逆境にある息子の不運を嘆き悲しむ母親を、みずからなぐさめ励ます「母ヘルウィアへのなぐさめ」。仕事や友人、財産とのつき合い方をアドヴァイスする「心の安定について」。古代ローマの哲学者セネカが贈る“人生の処方箋”。 ---引用終了 今回は、古代ローマの哲学者を、少々調べておきます。 ・セネカ---ストア派 ・キケロ---政治家 ・アウレリウス---ストア派 ・エピクテトス---ストア派
38投稿日: 2025.04.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間は有限で、平等に与えられている。 それをどう使うかで、人生は変わってくる。 セネカが本書で語ることの1つに、「先のことばかり考えずに、今に集中して生きろ」ということがある。 まさにその通りだと思う。 未来に不安を抱くのは自然なこと。 だけど、不安を抱きすぎても、今が良くなることは少ないように思う。 それよりも、今できることを精一杯やり、楽しみ、充実した人生を心掛ける方が、未来は開けると信じている。 だからといって、日々気負いすぎても疲れてしまう。 自分を大事に、自分が良いと思うことに時間を使い、今を生きること。 それが、人生を短くも長くもするのだと思う。
2投稿日: 2025.04.14 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
役に立たないものに熱中、を、批判してるけど、それは反対!でもなんだかセネカの怒りで丸め込まれた!話はそれたがって自分でも言ってる( ◠‿◠ )
2投稿日: 2025.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作は「時間をいかに使うか」という問題の考察で,どう生きるかという問題全般に言えることが多数ある。
1投稿日: 2025.02.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
背景が全然わからず内容が難しかった。 けども、 「だらだら無意味な、無駄なことをしてるから、 1日が短く感じるのでは?? 無意味なことを手放して、 意味のある仕事や趣味に時間を費やしましょう」 「人生に辛いことは多々あるけど、 現状で出来ること、満たされてることに 目を向けて生きれば、辛さが紛れます!」 「心を安定させるには、 自分と、周囲の環境や関わる人との バランスをとりながら、 目的を持ってしっかり頑張っていけば いつかはどうにかなるよ多分〜」 ってことは理解できた。
2投稿日: 2025.02.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
お金のように、時間にケチになることを薦めた本。 自分の時間を見直したい。 人間の誤りを乗り越えた偉大な人物は、自分の時間から、何一つ取り去られることを許さない。 あなたの人生の日々を監査してみなさい。あなたの手元に残る日々は、ほんのわずかな残りかすにすぎない。 全ての時間を自分のためにだけ使う人、毎日を人生最後の日のように生きる人は、明日を待ち望むことも、明日を恐れることもない。
0投稿日: 2025.01.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の時間の使い方、重要性についてセネカの考え方がまとめられている。2000年前に生きた人の考えを知るだけでも素晴らしいことだが、現代人にも刺さる考え方である。お金をケチることはあっても、時間をケチる人はほとんどいないように時間というものを軽視しすぎている、という考え方はすぐにでも取り入れる必要がある。
23投稿日: 2025.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
光文社古典新訳文庫の訳のおかげなのか、プルタルコスやキケロよりだいぶ読みやすい。読みやすいけど、内容は哲学というより自己啓発的な内容でちょっと退屈でもあった。 「われわれは、短い人生を授かったのではない。われわれが、人生を短くしているのだ」という「人生の短さについて」はなかなか耳の痛い話だ。過去の哲人の英知により打ち立てられたものこそ(世俗の名誉と違って)永遠である、という部分はちょっとプラトンの「饗宴」を思い出した。多忙な仕事に追われることをやめ、そのような過去の英知を知り求める事が真の閑暇である、とセネカは言う。そうして永遠につながることができる、というのはなかなか美しいと思った。しかし、当時のセネカのような裕福なローマ人は奴隷がいるから生活のためにあくせく働く必要がなかったわけで、そこは考慮に入れる必要があるとは思うが…。 「薄くなった髪を、あちこちから前のほうに寄せ集めたりしている」という一文には、2000年前もそういうことしているんだなあとちょっと面白くなってしまった。
0投稿日: 2024.12.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ・セネカの思想の背後には、ストア派の哲学の強い影響を見ることができます。ストア派とは、古代ギリシャのアテネにおいて、キティオンのゼノンという哲学者によって創設された哲学の学派です。ゼノンは、キュプロス島キティオン出身の人物で、アテネで哲学を学び、アゴラにあったストア・ポイキレ(彩色柱廊)という公共の建物で講義をしました。ストア(柱廊)とは、大理石の柱を並べて屋根をかけた長い廊下のような建築物です。壁面が壁画で飾られていたので、この名前で呼ばれていました。
0投稿日: 2024.12.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ終始、多忙であるな閑暇であれ、が飛び交っていたが、言わんとしていることはよく分かった。要は、「振り返らなかった過去に、現在の瑕疵が隠れているのだから、振り返る時間を確保した人だけが、人生を謳歌している」という事だと解釈した。 この本の中でめちゃくちゃ皮肉っているのが、遊び回っている人のことを「多忙」と呼称しており、こいつらは軒並み「からっぽで無生産な人生を過ごしている」そうだ。 セネカさん、贅沢が死ぬほど嫌いだったんだなぁ。
20投稿日: 2024.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった....!2000年前とは思えない。 セネカの言葉はストイックで厳しいな〜と思いながら読み始めたが、かといって頭でっかちなわけでもなく、現代人が読んでも響く言葉がたくさんある。 「心の安定について」での青年のお悩み相談も、現代のお悩みコーナーなんだろうか...と思えたくらい、人の悩みはこうも変わらないのかと驚いたし、興味深く、なんだか感慨深くもあった。 セネカはカリグラ、クラウディウス、ネロなどいわゆる悪帝で知られる皇帝の時期に政治生活を送っており、そのあたりも今後もう少し知ってみたいと思った。
1投稿日: 2024.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログメモ→ https://x.com/nobushiromasaki/status/1835859652279713995?s=46&t=z75bb9jRqQkzTbvnO6hSdw
0投稿日: 2024.09.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代ローマの哲学者セネカの思想がわかる本。題名に惹かれて前から読みたかった。暴君で有名な皇帝ネロの教育係だったセネカ。激動の人生から迸るローマ帝国の重責の任に就くバウリヌスへ宛てた手紙。 人生は短いが過ごし方次第では、長くなると言うセネカ。人々はあまりにも忙しく過ごしすぎていると。「未来に頼らず、現在を逃さず、過去と向き合う」未来は不確かで現在は流れがあまりにも早くあっと言うまに過ぎさっていく。過去と向き合えと言う箇所は新しい発見。言い換えれば、いい思い出が作れるように今を生きろと言うことかな。
5投稿日: 2024.08.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ私はセネカ先生的には宙に浮いた存在かもしれない。人生において私は何の組織にも適せないのではないか…と悩むこともあるが土地よりも自分の欠点について考えるべきという言葉が響いた。構成は”セネカの人と思想を理解してもらう”というのがコンセプトらしいがすごく良かった。人間の生活に関わってくる実践的な哲学なので今の時代でも響く所が多いと思う。「心の安定について」にいたってはアドバイスですし結構具体的で面白いです。人間って変わらないね
1投稿日: 2024.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログTwitterでたまたま見かけて手に取った。 古代ローマの哲学者の本なんて理解できるのか…と不安だったけど、とてもわかりやすい訳で驚くほどすんなり読めた! 表題作よりは「心の安定について」が一番面白く読めた。「人生の短さについて」は他の文章より例えの連続という感じで、読んでいて退屈なときもあった。 紀元1世紀のローマの人の例えが時代や国が違う自分にも共感できること、文章がしっかり残っていること、日本語訳ができていることなど、全てが新鮮で驚きの連続だった。 セネカ自体が大昔の人なのに、セネカが例え話に出す人物が紀元前5世紀…みたいな感じで、セネカの時代はどうやって過去の人物のことを勉強してたんだろうとか、どんな形でこの文章は残っているんだろう、原典はあるのか、とかいろんなことが気になった。 さすが今の時代にまで残っているだけあって、普遍的で理解しやすい考え方だと、ただただ感心した。
1投稿日: 2024.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ「あなたは、どこを見ているのか。あなたはどこを目指しているのか。これからやってくることは、皆不確かではないか。今すぐ生きなさい。」 約2000年前のローマ時代 ストア派の哲学者セネカによる実践哲学書。 妻の近親者(?)・母・友人へ宛てた手紙、3篇。 人生の時間の過ごし方、不運への立ち向かい方、毅然とした心の持ち方を説いている。 2000年前と現代では娯楽も増え、生き方も変わっているとは言え現代にも思想は通じる。ビジネス書のように読みやすかった。 時間という財産の浪費、自分自身を見直すきっかけになる。
8投稿日: 2024.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ今こうしている時間も全て浪費なのだろうか やりたいことを出来ていない時間は浪費なんだそう 人生は何かを成すには短いなんてよく言うけれど、 セネカに言わせれば浪費してる時間を無くせば、 何かを成すには十分すぎる時間があるそうで。 ただただ、この世に存在するのではなく、 私は「生きてる」って胸を張れたらいいな。
1投稿日: 2024.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間の篩にかけられた古典は、一文一文が金言ですね。自分の時間を他者に奪われることなくいかに生きるかについて、そして人生について、その他生きていく上で大切なことが沢山学べます。本当に素晴らしい内容です。
0投稿日: 2024.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【背景】 ストア派のエリートであったセネカだったが、色々なことに巻き込まれ流刑にあった。その後ローマ皇后によって、息子の教育係となることを条件にローマに戻してもらった。その息子ネロは後に暴君となってしまい、セネカは政界から身を引いた。その後、働きすぎの穀物管理責任者である男に向けて書かれたのがこの作品である。 【要約】 金や土地といった財産については皆必死に守るのに、時間という財産については皆簡単に浪費してしまう。 浪費というのは、欲望に溺れること、仕事に追われること、怠惰に過ごすこと、他人の目を気にして神経をすり減らすことである。今までにどれくらいの時間を他人に掠め取られてきたか? 君は自分は永遠に生きられると勘違いしていないか?長生きできる保証はどこにもないし、老いてからやりたいことを始めるのでは遅い。「生きる」という最も難しい学問を自分で学べ。 人生の時間とは、どれだけ時間を自分だけのために割くことが出来たかどうかである。だから寸暇を惜しみ、一日一日を人生最後の日だと思って生きよ。人生は急ぎ旅のようなものだ。 過去とは、唯一運命の力を受けない、動かしようのない神聖な時間だ。その全てが所有物で、好きな時に好きな分だけ取り出すことが出来る。 だからこそ、過去を振り返る時間的余裕を持ち、良き過去を作ることができるよう日々を生きていくことによって、いつ最後の日が来ても躊躇うことなく死へと向かうことが出来る。
0投稿日: 2024.02.22 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の短さにについて、というに対し、細かくテーマを設けて簡単な説明がなされる本。人間はずっと変わらないんだなと思う。
1投稿日: 2023.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間の悪しき習慣やその原因等について述べ、本質的な言葉でその解決策を述べている。分かってはいるけど、なかなか改善できないんだよな〜と思いながら読み耽っていた。
2投稿日: 2023.11.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人生は自分が上手く管理すれば、長い。 他人へ阿れば、短い。 自分自身を顧みず、他人に自分を気にかけてもらいたい、評価してもらいたいと依存してはいけない。自分の人生は、自分と共に歩みたい。 「おまえがそんなことをしたのは、他者と共にありたかったがゆえではなく、自己と共にあることに耐えられなかったがゆえなのだから。」(p.16)
0投稿日: 2023.08.29 powered by ブクログ
powered by ブクログもっと早くこの本を読んでおけばよかったと後悔するくらいに、素晴らしい本だった。これから先の人生で折に触れて読んでいきたい本になった。 「人生の短さについて」を始めに3編の作品が収録されているが、どれもどう生きていくか、困難に直面したときどう対処すれば良いかという実践的な知についてのエッセンスが散りばめられていると思った。 どの作品からも読み取れるセネカの考えは は、2000年経っても色褪せることはないと感じた。比喩や例え話こそ当時のものだが、その主張自体は現代でも十分に通用するものだと思う。どれも古典として読み継がれてきた所以をはっきりと見せつけられる作品だった。現代の自己啓発本もセネカの作品を焼き直した陳腐なものに思えてしまうほどだ。
2投稿日: 2023.08.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
人生の短さについて セネカ ただ生きている、なんか存在してるだけ、では人生は短い 忙殺され、人に時間を奪われて、時間を与えて、自分の人生を短くしていないか 適当に時間を潰しているときやら、仕事が忙しくて早く終わらないかと思う時、欲に溺れて時間が早く過ぎ去る時、それは存在していただけで自分のための人生とは言えないのでは とのこと その代わりに何が提示されるかというと、過去の哲学者の教えや生き方に習って、寄り添いあうことで救われるとのこと やりたいことや自分のための目標があるのに先延ばしにしてないかい?今若い間にやっておかないと、この先いつ死ぬかわからんぞ?高齢になって元気がないのにやりたいことできるんか? とのこと それはそれで自分のための時間だしいいと思うけど、そこに時間を奪われて盲目になっているんなら自分の人生は長くはならないのでは てか人生長く生きるとかどうとか難しすぎない? これが哲学??? まあやりたいことやってくれ、それがお前が主人公の人生や 自分の人生と時間は大切にな 別に人に合わせて何かしてやる必要はないんやで でも人はひとりじゃ生きていけないし人との関わりがあるから楽しいって思うこともあるじゃん だから時間の使い方も自分のためなら誰かに与えててもいいんじゃないの だいたい死ぬときに人生後悔やわ〜ってなるってみんな言うけどそうなんやな そうだとしてももう死ぬんやしどうにもならんしなあ どうせめちゃくちゃ人生謳歌できててもそういう感情になりえるしそこを恐る必要はないと思うんよな
0投稿日: 2023.07.22 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私にとっては難しいなと思う部分が多々ありました。 しかし、昔と今で繋がるところもあって興味深かったです。 ▪︎印象に残ったフレーズ ・『長く続いた幸せに甘やかされて、力を失った精神の持ち主は、いつまでも涙を流して嘆いていればよい。最も軽い災難の一撃で、崩れ落ちればよい。しかし、生涯にわたって災厄に見舞われ続けてきた精神の持ち主には、最も重い災難にも、強靭で確固とした不屈の心で、耐えていただきたいのです。』 ・『悲しみというものは、まぎらわせるよりも、克服してしまうほうがよい』 ・『信頼に満ちた心地よい友情ほど、心に喜びを与えてくれるものはない。』 →はるか昔にも友情とかあったんだなと思い、ホッコリしました。
0投稿日: 2023.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Kindleで無料だったので、とりあえず「人生の短さについて」だけ読んだ。 少し難しい部分も感じたが、軸となっていることは理解して腑に落ちた。解説動画なども見たが、主な内容は ・他の生物と比べても生きる年数は長いのに、人生が短いと感じるのは、自分で短くしてしまっているから。 ・ほとんどの時間は生きているとは言えず、単に時間が過ぎてしまっているだけ。仕事で忙しいのも、それは時間の浪費。他人に奪われてはいけない。自分に向き合う。 ・未来現在過去の内、不変のものは過去だけ。過去をいかに自分にとって充実させて、向き合いたいと思える過去にするか。それが則ち自分に向き合うことが出来ている状態。 ・また、過去とは偉人が残してきたことを知れる。 「真の閑暇は、過去の哲人に学び、英知を求める生活の中にある」 これらの主張はもちろん生きる上で軸になりうる。 しかし、働かないと生きていけない以上、どうやっても忙しくなってしまう。さらに、この本が書かれた2000年ほど前よりも、明らかに娯楽が増えているため内容がそぐわない部分もあった。 逆に、だからこそ、この本の主張が響くのではと思う。個人レベルで振り返っても、意味もなくスマホを見たりダラダラしたりする時間が多い。 もちろん他人に合わせることも大事だけど、やはり自分は自分である。誰のものでもない 少しクスッときたフレーズ 「いまや、宴会に出ることが仕事になってしまっているではないか」 →この時代から飲み会がめんどい人っていたんだなー
0投稿日: 2023.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ思ったより難しかった。ストア派の基本概念を理解してから読むといいので、解説から読むことをお勧めします!
0投稿日: 2023.05.21 powered by ブクログ
powered by ブクログあらゆる世俗的な営みから離れて、閑暇な生活の中で、過去の哲人に学び、英知を求める生活を送ることだけが生きているといえる。 多忙な生活は人生を浪費してるだけ。 生き方のヒントがあると思って読んだけど期待外れだった。書いてある主張が受け入れ難すぎる。 自分が食べていくために(家族を養うために)多忙な生き方(働き方)をしないといけない人がいるのに、俗世間から離れてお勉強してても生きていける人間が、そういう生き方のみが真に生きているということなんだって主張するのはグロテスクすぎる。 全体的に的はずれな決めつけが多すぎる。 p82「几帳面で仕事熱心な人間なら、ほかにいくらでもいる。荷物を運ぶには、歩みのおそい家畜のほうが、血統のよい馬よりも、はるかに適している。わざわざ重い荷物を載せて、生まれながらの俊足をだいなしにしてしまうような者が、どこにいるというのか。」 ほんとうに最悪。ここの前後はひどすぎる。 p88「ひとは、互いの時間を奪いあい、互いの平穏を破りあい、互いを不幸にしている。そんなことをしているうちは 、人生には、なんの実りも、なんの喜びも、なんの心の進歩もない。」 人と関わり合うということは、まさに時間の奪い合いだし、嫌な気持ちになったり、傷ついたりすることは避けられないと思う。だからって社会的な営みを意味がないと切り捨てるのは理解できない。 俗世間を離れて、一人でしこしこ読書していい気になってる人間には見えない世界があるんだと思う。 他2篇は読まなかった。
0投稿日: 2023.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ古典ゆえ、語り尽くされたことを再確認する内容。 過去は確定している、現在は短い、未来は不確定なので不安。 読了40分
0投稿日: 2023.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ同じ時間の長さでもそれをどう捉えるかどう使うかによって全く異なる長さ(濃さ)になることを語っていた。ぼんやりとなんだかんだ生きてると時間だけが経って悔いの残る人生になってしまう。
0投稿日: 2023.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
【哲学に興味を持った理由】 若い時から自己啓発本やコミュニケーション本をよく読んでいた。しかし多読すればするほど、書いてあることが非常に似ており、書かれている知識は過去の哲学書からの引用が殆どだと、遅まきながら気づいた。であれば、元ネタである哲学書を時系列に沿って読んでいこうと思ったのが理由。 【セネカとは?】 約2,000年前のローマ時代を生きたストア派の哲学者。ストア派とは、理性に従い禁欲的に生きることを推奨する哲学。カリグラ帝の時代に政治の世界に入り、クラウディウス帝の時代には、コルシカ島への8年間の追放生活を経験。アグリッピナ(クラウディウス帝の妻)の進言により、赦免されローマに帰還。アグリッピナの要請によりネロの教育係に就任。その後ネロが皇帝に就任した後、セネカは補佐役としてネロの政治を支える。しかし、セネカは謀反の嫌疑をかけられ、自殺。 【本の構成】 訳者まえがき ・人生の短さについて ・母ヘルウィアへのなぐさめ ・心の安定について 解説 年譜 訳者あとがき 【それぞれのパートの構成】 ・「人生の短さについて」 (簡単な概要) パウリヌスという人物に宛てて綴られている。パウリヌスはセネカの妻パウリナの近親者と考えられている。パウリヌスはローマ帝国の食料管理官を務めていた。国家の食糧供給をつかさどる食料管理官は、きわめて責任の重い重職であり、多忙を極める仕事だった。本作でセネカは、パウリヌスに対して、多忙な職から身を引き、閑暇な生活を送るよう勧めている。 (感想及び得た気づき) この章でセネカが終始訴えているのは、人生は決して短くはない、だが、ただ漫然と日々を過ごしていれば、あっという間に時間が過ぎてゆき、何も成し遂げぬまま、人生は終わってしまう。なので、そうならぬ様、多忙な生活から離れて、閑暇な生活を送るよう勧めている。 セネカの言う閑暇な生活とは? →自分が本来なすべきこと、自分のためになることをしている時間のこと。 閑暇な中でなすべきこととは? →英知を求め、英知に従って生きること。 この章を読んでいるときに思い出したのが、スティーブ・ジョブズの名言だ。 「もし今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることは、 本当に自分のやりたいことだろうか?」 これとほぼ同じことを、約2,000年前のセネカが既に教えてくれていた! 以下、セネカの言葉。 「すべての時間を自分のためだけに使う人、毎日を人生最後の日のように生きる人は、明日を待ち望むことも、明日を恐れることもない。」 この言葉から得た気づきが、『この世で唯一、全ての人間に平等に与えられているのは時間だ。だから、与えられた時間を最大限有効に使うことが、生きていく上で、何よりも大切だ』と再認識できたのが、この本を読んでの最大の収穫。 「母ヘルウィアへのなぐさめ」 (簡単な概要) クラウディウスが皇帝に就任した際、セネカはコルシカ島に追放される。罪状は、カリグラ帝の妹ユリア・リウィッラとの不倫関係。不倫が事実か冤罪かは不明。結局8年間もの間、流刑の罪を耐え抜く。本作はコルシカ島に追放されて暫く経ってから、母ヘルウィアに向けて書かれたもので、息子の不運を嘆き悲しむ母親を、自ら慰め、励ます内容。 (感想及び得た気づき) ストア派の哲学において、いかに運命に立ち向かうかと言う問題は、きわめて重要な問題とある。セネカは本書で追放という運命に見舞われた自分がどのように運命を克服したか、そして母親がいかに自らの運命を克服すべきかについて、具体的な考察をしており、ストア哲学における生き方の指針を示す、実践例になっているとこと。 セネカ自身は今回の追放をどう克服したのかというと、常識的な価値観を視点を変えることによって、転換したとのこと。 具体的には、追放を「住む場所が変わること」と規定し、視点を変えることによって、物の見方を転換しようとしたことのこと。 つまり、人類は絶えず移動し続けており、その意味では誰もが追放状態ともとれる。 セネカによれば、人間どこに住んでいても、自然のもとで、自分が所有する徳と共に生きて行けるとのこと。 では、追放につきまとう貧困や恥辱などの様々な不利益とは、どう向き合えば? セネカによれば、貧困はそもそも恐れるものではない。なぜなら、人間が生きるのに必要なものは皆、自然が与えてくれる。ただ、贅沢な生活に慣れてしまうと、それを失うことに恐れてしまう。その恐れてしまう心こそが、心の病のあらわれなのだと言う。また恥辱については、徳を持っていれば、そもそも恥辱を受けたと感じないし、仮に受けたとしても、容易に耐えることができるとのこと。 前置きが長くなってしまったが、この章から得た気づきは、意味を規定しなおし、視点を変え、転換するとの部分だ。 これってズバリ、世界で3,000万部も売れた、スティーブン•R•コービィー氏の7つの習慣にある、「パラダイムシフト」のことじゃないか!と思わず声に出しそうになってしまった。 パラダイムシフトとは、自分に起こったネガティブな事象を、ポジティブな事象に変換できるよう解釈を変換することだ。 コービィー氏が書籍で最も大切と言っていたパラダイムシフトが、既に2,000年も前から書物として残っていたんだ! しかし、ローマ時代の哲学恐るべし! この先の人生、きっと困難や辛いこともきっと数え切れない程あるはずだが、パラダイムシフトで乗り越えていこうと再認識したのがこの章での気づきだ。 ・「心の安定について」 (簡単な概要) 年下の親友セレヌスに向けて綴られてたもの。セレヌスが心の弱さを克服して、ぶれることのない安定した心を手に入れるためにはどうすれば良いか?との質問に対してのセネカのアドバイスを書いたもの。 (感想及び得た気づき) 本作品におけるセネカのアドバイスは、厳格なものというよりは、むしろ、セレヌス現状にに合わせた、現実的なものになっている。 以下セネカのアドバイスの箇条書き。 1.自分の仕事に打ち込み、自分に許された場所で、自分の義務を果たすこと。そして状況が悪化したら、自分から仕事を離れ閑暇の中で生きること。 2.仕事を選ぶときには、自分の適性を考えると共に、自分の力量で対処出来ない仕事や際限のない仕事は避けること。また、一緒に仕事をする、良い友人を選ぶこと。 3.少ない財産で質素な生活を送り、運命に翻弄されないように気をつけること。 4.自分の置かれた境遇に不平を言わず、それに慣れること。どんな運命に襲われるか分からないから、常に警戒を怠らず、備えをしておくこと。 5.決して、無意味で無益な仕事はしないこと。運命に翻弄されることなく、自分を保ち、逆境でも動じないこと。 6.人々の欠点に絶望して嘆くようなことをせず、それを笑って受け止めるか、冷静に受け入れるかすること。 7.正しい人間が不運に見舞われる姿を見ても、決して絶望しないこと。 8.自分を取り繕うようなことをせず、率直な生き方を心がけること。 9.人との交わりに疲れたら、孤独に逃げ込むこと。 10.心が疲弊したら、様々な方法で気晴らしを与え、活力を回復させること。 なるほど。ほとんど過去に読んだ自己啓発書に書いていたことばかりだ。 つまり人間は、2,000年前から思い悩むことは、現在と何も変わっておらず、またその克服方法も、既にローマ時代から人類の叡智として残っていたとこうことなんだ。 また、気づいたこととして、仏教(特に禅)の考え方にセネカの考えが似ているなぁと思った。それはセネカだけが似ているのか、ストア派全体、あるいはローマ時代の哲学全体なのか、その辺りは西洋哲学の本を読み始めたばかりなので、今後哲学書を多読していくにつれ、新たな発見がありそうで、今から楽しみだ。過去に自己啓発書を多読してきたことも、全く無駄では無かったと実感できたのも、良い発見だった。
17投稿日: 2023.02.20 powered by ブクログ
powered by ブクログとっつきにくいと思いきや、生き方のメッセージが詰まっていて、とても面白かった。 人生は多忙さに忙殺され、浪費すれば短い。 過ごし方次第で、人生は長くなる。 じゃあどういうふうに生きたらいいのっていう話になれば、無駄なことに時間を無益に費やさず、また未来に頼りすぎず、今をしっかり生きようということ。 それが難しい。 でもそれを意識して生きることが大切だと思った。
4投稿日: 2023.01.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ偶然から生まれたものはみな不安定 精神は、自分を刺激して、気を散らしてくれるようなものなら、なんでも歓迎する。 自分自身と向き合えないひとは、そうした退屈を嫌い、あえて多忙な状態を求めるわけです。 人生がほんとうに長いのか否かは、時間の量で測れるようなものではなく、むしろ、その過ごし方の質によって決まるものなのです。 文章を書いている自分に酔ってはならない。簡潔な文を書くように心がけよ。とかなんとか
0投稿日: 2023.01.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ①私達は、人生を浪費している。 ・我々の時間は決して短くない。 ・人は人生を乗っ取る人を自ら招き入れている。 ②多忙ではいけない。 ・多忙=生きる事から最も遠く離れる事。 ・毎日を人生最後の日のように生きよ。 ③人生を長くする時間の使い方。 ・先延ばしは、人生 最大の損失。 ・過去は永遠に所有できる。 ・真の暇があるとは、英知を求める生活の中にある。 ※人々に尊敬される高名な過去の偉人達は、 我々の為に生まれてくれた。そして、私達の為に 生き方のお手本を用意してくれた。
0投稿日: 2023.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ短い人生の中で、今を生きて、徳を積んでいこうと思える内容でした。 2000年前からセネカの教えが継承されていてすごい、、
0投稿日: 2023.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルから、人生の短さについての持論をつらつらと述べるだけの本かと思っていたが、そうではなかった。人間の生き方の1つとして参考になる本だと思う。 勉強や趣味、仕事などどれに時間を割けばいいのか分からない。時間がない、分身が欲しいと普段から思っている人には、ぜひおすすめしたい。逆に、なんとなくでも現状に満足している人には合わないと思われる。 セネカは、人間は無意味なことを享受しがちだと説いている。人間関係、娯楽、仕事などに時間を取られて、自分のやりたい事を探す暇もない。そのような人は、最後まで、閑暇を見つけ出すことができないのだ。だから、過去を振り返って、自分のやりたいことに気づくべきである。 セネカは、学問に勤しむべきと言っているが、個人的にはそうでなくても良いと思う。ただ、自分を顧みて、仕事を変えるなどもう少し心に素直になってみることが大切だと考える。
0投稿日: 2022.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ本文を読んでいく中で、「この人はどういう思想に則ってこう考えているんだ?」「ここの線引はなぜ発生しているんだ?」「さっきと言っている事が矛盾してないか?」と、色んな違和感を感じたが、最後の解説を読んでかなりそのもやもやが払拭された感がある。 よく生きるための実践哲学として、スコラ派から一歩人間くさい方に踏み込んだ考え方がここでは展開されていると思う。とはいえ「言うは易く行うは難し」の内容ではあるのだが……。そうだとしても、心の片隅にこれらの提言を置いておくことはマイナスにはならないだろう。 個人的には、本を読む中でセネカの生きた時代背景や文化が見えてくるのも楽しかった。
0投稿日: 2022.11.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ「われわれは、短い人生を授かったのではない。われわれが、人生を短くしているのだ。われわれは、人生に不足などしていない。われわれが、人生を浪費しているのだ。」 身分が低い者も高い者も関係なく、ほとんどの人が人生を浪費しているとセネカは語る。人は多忙や他人のため、怠惰、その他諸々のことによって、大切な時間を無駄に費やしている。時間の浪費は生きていることにはならない。ただ存在しているだけだ。 だが上手に時間を使えば、人生を長くすることができる。どうすれば人生を長くできるか。セネカは閑暇の中で過ごすことを勧めている。閑暇とはただぼーっと過ごすことではないし、趣味に没頭することでもない。過去の哲人に学び、英知を求めることである。そうすることで、高みに登ることができる。 ストア派は決まった運命というものが存在していると考えている。その中において心を乱さず快活に生きるためには、あらゆることを知り、受け止めておく必要がある。その究極系を「賢者」としている。賢者はどのような運命が待っているかを予測することができるため、未知の不安に怯えることはない。 賢者になることは無理でも近づくことはできる。そうやって英知を求め、広めることで自身や他者を幸福にことできると、セネカは考えていたのだろう。 今から2000年も前の価値観の中にあり、全てをそのまま受け入れることは難しい。どんな分野であろうと自己実現が美徳とされている世の中で、哲学を極めることだけが幸福とは私には言えない。だが、自分のために貴重な時間をどう使うのか、というのは現代の我々にとっても重大テーマであり、それを考え直す良い機会になった。 ところで、作中でセネカは雑学に夢中な人々を批判している。その割に結構長いこと雑学が羅列されてて面白かった。
0投稿日: 2022.11.21 powered by ブクログ
powered by ブクログセネカが言う「暇な」大学生活を送る自分にとっては深く考えさせられる一冊でした……。 確実に、一読の価値あり。
0投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ理由もなく、落ち着かない時に読む本 著者はセネカ、第5代ローマ皇帝ネロの家庭教師として知られています。 本書は、それぞれ下記の相手に対して、送った手紙をまとめた内容です。 ・人生の短さについて:親戚の(父親または義父?)パウリヌス ・母ヘルウィアへのなぐさめ:母親のヘルウィア ・心の安定について:年下の青年のセレヌス 属性の違う3人が相手なので、手紙の内容も大きく異なります。 しかし、それでも共通している内容がありました。 これは、自分の私見になりますが、自身の精神の成長を第一にしているように 思います。 俗世や自分の欲望とうまく距離をとって、自分自身の精神を安定・成長させることの重要性を説いているという印象を強く受けました。 特に、「心の安定について」は青年セレヌス相手ということもあり、具体的なアドバイスが多かったです。 人生のふとした瞬間、落ち着かない時にこの本を読むと安心できました。 説教くさい面もありますが、若い人に是非、一読していただきたい本です。
0投稿日: 2022.11.20 powered by ブクログ
powered by ブクログセネカの哲学の入門テキスト3通とあります。 セネカは、帝政ローマ初期の哲学者で、ネロの家庭教師でもあった人です。ストア派に属していました。 <心にのこった言葉> 人生の短さについて ・多忙な人間はなにごとも十分になしとげることができない ・生きることは、生涯をかけて学ばなければならないのだ。 ・ひとはだれしも、未来への希望と、現在への嫌悪につき動かされながら、自分の人生を生き急ぐのだ。 ・賢者はいつ最後の日が訪れようとも、ためらうことなく、たしかな足取りで、死にむかっていく ・すべての人間の中で、閑暇な人といえるのは、英知を手にするために時間を使う人だけだ。 ・過去を忘れ、現在をおろそかにし、未来を恐れる人たちの生涯は、きわめて短く、不安に満ちている 母ヘルウィアへのなぐさめ ・賢者に従い、運命に頼らない自分は、なにも辛い目にはあわない ・順境にあって思い上がることがない人は、たとえ状況がかわっても、落ち込むことはありません。 ・人間が自分を維持するために必要なものは、じつにわずかです。(貧困のうちに追放生活を迎えても) ・賢者とは、自分だけを頼りとし、大衆の見解からは距離を置く存在です。 ・運命から逃れようとするすべての人が逃げ込むべき場所に、あなたを案内しましょう。すなわち学問です。 心の安定について ・人間の精神は、生まれつき活発で、動きやすいものだ ・まず心に留めるべきは、持たないほうが、失うよりも、はるかに苦痛が少ないという事実だ。 ・無益な目的のために仕事をすべきではないし、無益な動機から仕事をすべきでもない。 ・なんの成果も得られない無駄な仕事をするべきでないし、得られる成果に見合わない仕事をするべきでもない ・どんな仕事をするときでも、かならず一定の目的を設定し、その目的を見すえる必要がある。そして、仕事に専心すれば、心がぐらつくことはない ・(本書を読めば)心の安定を保つ方法と、それを回復する方法と、忍び寄る欠点から身を守る方法を手にしたことになる。 <解説から> 時代背景 セネカの時代 初代から、五代までを生き抜いた 初代 アウグストゥス ネロまで5代 ユリウス・クラウディウス家という 二代 ティベリウス 晩年は恐怖政治 三代 カリグラ 愚行の皇帝 暗殺死 四代 クラウディウス ただの傀儡、愚帝 セネカをコルシカ島へ島流し 五代 ネロ 后アグリッピナが、その子ネロを皇帝につける、セネカも許されて政権へ復帰、だけども、暗殺計画に参画したとして自殺に追い込まれる ローマ各地で反乱がおき、ユリウス・クラウディス家は5代で終焉する。内乱の時代へとローマは入る。 セネカが属したストア派とは ・ギリシア アテネのキティオンのゼノンが創設者 ・自然に従う 人間が作りだした人工物は、人為的であり軽視 ・自然と宇宙はロゴスという理性によって支配される世界 ・人間は理性的な能力が重視され、苦痛、快楽、欲望、恐怖のような情念は理性の敵対するものとして否定的に評価される ・禁欲的なをストイックというのは、ストア派から派生している ・運命とは、ロゴスによってもたらされる必然的な因果連鎖。 ・徳を完成させた人間であれば、何が起こるかを的確に予測して対処できる。 ・ストア派の生き方を実践できる有徳者を賢者とよび、理想として掲げた。賢者は完全な徳を実現した人物であり、あらゆる情念から自由でいられる存在である。 目次は以下です。 訳者まえがき 人生の短さについて 母ヘルウィアへのなぐさめ 心の安定について 解説 年譜 訳者あとがき
11投稿日: 2022.11.09 powered by ブクログ
powered by ブクログスラスラ読めるけど、文章の意味が捉えづらいところが多い。でも、印象的な言葉がたくさんあった。再読必須。
4投稿日: 2022.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人生の短さについて」「母ヘルウィアへのなぐさめ」「心の安定について」の3篇からなります。自分としては、友人の選び方、付き合い方についてかかれた3篇目の「心の安定について」が一番心に刺さり、印象に残りました。
2投稿日: 2022.09.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ今も昔も人の悩みは変わらない。人生を浪費せず生きれば、十分に生きることができる。自分のために生きる。先延ばししない。
2投稿日: 2022.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かった。訳がとても平易で読みやすく、セネカの説く実践的なストア派哲学、というか、ストア派の哲学を実生活に活かすための方法がものすごくよく伝わってきて、読みやすさに驚いた。 巻末の訳者中澤努さんの解説もとてもわかりやすくて、セネカとその周辺や、ローマ哲学のあり方の入門書としてともよかった。
1投稿日: 2022.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ読みづらいけど、とても大切なことが書いてある。 最後の解説を読んでから読むとわかりやすい。 2000年前も人間や人生の本質的な部分は変わらないと実感した。 人生の短さについて 人生は無為に過ごすと何も出来ずに終わる 自分の時間を他人に奪われないようにする 時間を浪費してしまうのはやりたいことがないから 閑暇を持って目的のために時間を使う 心の安定について 自分の実力や得意なことを見極める 仕事は自分の能力に見合ったものを選ぶ 付き合う人を選ぶ。欲の少ない人が良い 質素な生活を心がける。足るを知る 疲れたら休息をとって精神を回復する。息抜き大事
1投稿日: 2022.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログさっと読めるのが良い。 いつの時代でも哲学者のいうことはあまり変わらないと思ったが、当時の言葉やその環境からうまれる言葉から紡がれて心地は良い。 時間を人のために使うなら、残された時間はわずかで、自分のために生きないと意味がないということ。 人生は有限なのだ。 知っているけど、どうしたら良い?と自答しながらも、読んでよかった
0投稿日: 2022.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ『人生の短さについて』目的で読みました。 難しく平易な言葉で書いてあり、哲学書のような難しさはなくビジネス書感覚で読めました。 人生はどう過ごすかによって長くも短くもなる。多忙という状態にまかせておくとどんどん人生は短くなってしまう。自分で考え、英知を発揮する事が人生なんだと。 普遍の真理はどんなに時が経とうが変わらないんだなと改めて感じました。
0投稿日: 2022.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログプライムでの評価の高さから慣れない哲学書を読んでみたのですが、これが2000年以上前に書かれてると思うとすごい。時代は全く違えど、人間の苦悩や理性的な部分はやはり同じなんだと思える。翻訳文は少し難しく感じたから、先に解説から読むと分かりやすい
0投稿日: 2022.03.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ何歳になったら〜というたらればに対して、 なんでもっと考えないの?今を生きろと。 ・時間に浪費家すぎる ・生きることをやめる年齢で、 生きることを始めるのは遅すぎるのでは? ・先延ばしは人生最大の損失。 期待は生きる上での障害であり、明日に縋り付いて今日を滅ぼすもの。 ・英知を手にするために時間を使う人が、 生きているといえる。
0投稿日: 2022.03.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分がいかに他人のために時間を今まで使ってきたのか反省した。過去は振り返らないと今まで言ってきたけれど、過去を反省して、今生きる大切さをしることができた。 お金と同様に時間についても、使い方に注意をしないといけない。人に振り回されない生き方は大切だなと。
0投稿日: 2022.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題の他2編も通して、 自分を大切にすることが最重要なのだと諭された。 豊かな時間を過ごすこと、学ぶこと、愛する人々と交わること、そして心を十分に労わること。 常に基本としていきたい。
1投稿日: 2022.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ今も昔も変わらない、本質的なことについて教えてくれた本。 何も生み出さない仕事で日々を忙しく過ごして、気付いたら死の直前だった・・・という人生ほど哀れなものはない。 不確かな未来にばかり期待して今なすべきことを先送りにしてはいけない。 過去としっかり向き合い、今この瞬間に集中して生きるべき。 そのことに今の歳で気付けていてまだよかった。 自分しだいで、人生の時間はいくらでも長くすることができると実感する日々。
1投稿日: 2022.02.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ一言でいうと 【人生が短いのではなく、自分の行いが人生を短くしてると分かる本】 本書は2000年前、皇帝ネロを育て上げる役として仕事に就いたセネカが晩年に書いた本であり、内容は仕事に埋もれる若い一人の男性に当てて書かれた手紙だ。 古代のアリストテレスから、現在その辺にいる見知らぬオジちゃんまで誰もが「人生はあっという間で短い」と嘆く。 しかし、セネカによれば「人生は本当は長いもので、短くしてるのは自分のしょうもない行いに費やしてるからでしよ?」と迫ってくる。 私が本書からセネカのいう、しょうもない時間を現在にあてると下記リストが浮かぶ。 ・自分以外でも出来る仕事時間 ・惰眠時間 ・性欲にふける時間 ・物欲にふける時間 ・酒にふける時間 ・相手に話しかけられる時間 正直、他の誰かができる帳簿をつけながらそれに必死になるばかり時間をとられ、疲れ果てた故に休日は惰眠に時間をとられ、性欲や物欲にふけってスマホを片手に時間をとられ、あげくの果てに馴れ合いの飲み会やに時間をとられ、ラインでくる通知や電話の返答に時間をとられる。 一日の何時間を、それらに費やしているのか。仮に寝る時間を除いた半分の時間を費やしてると考えれば、80歳までの人生の人は、40年しかないのだ。あなたは、私は今何歳??ほとんどないのではないかと私は焦った。 自分にとっての内省や、成したいことに時間を注ぐべきだと感じる。ユダヤ人である哲学者ハンナ・アレントのいう「鑑照生活」の時間をいち早く獲得する必要がある。
1投稿日: 2022.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ【過去を見失わずにふり返ることの大切さ。】 ローマ帝国の政治の中枢で活躍するも追放、8年の後に、幼年期のネロの教育係として呼び戻されるも、後年その暗殺嫌疑をかけられ自死したルキウス・アンナエウス・セネカ(紀元前1年〜65年)。 波乱万丈すぎる生涯から、漠然と野心的な内容を想像して読み始めたけれど、良い意味で裏切られる内容でした。 表題の「人生の短さについて」では、人がいかに他人のために時間を浪費して簡単に生を終えてしまうかが指摘され、人生を長くする術として、自分の過去と向き合うこと、過去の哲人たちの思想に学ぶことが大切だとされています。 セネカ、学ぶことや思索することが、大好きだったんだなあ。 「悔やんでいることを思い出すのは不愉快なこと」という言葉に、自分の弱点を指摘された気がしてドキッとしました。 なぜなら、私はそれが、大の苦手だから。 思い返せば、小学生の時から、テストで解けなかった問題をふり返るのが嫌で嫌で。 自分の力が及ばなかったこと、できなかったことに向き合うのが、あまり好きではないのは、大人になった今も同じだなあ。 そういう意味では、今こうやって、古典を読んでいるのも、「読んでいなかった過去」に向き合うという、私にしては一大決心をともなって行っていることなのだけれど、そうやって手にした本の中で、自分自身を鏡にうつしたような言葉に出会うなんて、なんて不思議なんだろう。 過去を受け止めて、哲人たちの知恵で包み込むことによって、安らかで静かな時間が得られる。 そんなセネカの思想が頭に流れ込んでくるごとに、過去と向き合う辛さが温かくほどけていく気がした1冊でした。
13投稿日: 2021.12.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ光陰矢の如し。日常の雑事にばかり心を奪われていると、気付いた時に人生はあっという間に終わりを迎えてしまうかも知れない。 ではどう生きればいいか。 閑暇な時間を持つこと。自分と向き合うこと。気落ちせず、少しずつ実践できるようになっていきたい。
0投稿日: 2021.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログセネカの生き方格好良き。 1mmでも良いから近づきたいな。 未来に頼ることなく、過去と向き合い、現在の時間に集中して生きよう。 もっと自分に向き合う時間を。
0投稿日: 2021.10.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ1章 ローマ帝国の食料管理官という多忙な仕事をしていたパウリヌスに対して、セネカがその任を辞めて間暇な日々を送れと諭している章。多忙な日々をしていると人生を浪費しているので、間暇な生活をせよとのこと。間暇というのは何もしないことではなく、自らの人生の使命を全うせよという意味であると解釈した。間暇な人というのは現在を自分の力で生きている人であり過去に固執したり未来に孤独を感じる人ではない。Appleのスティーブ・ジョブズも毎日が最後の日として生きていたが、セネカ自身も毎日が人生最後の日のように生きることこそが人生を長くするものであると説いている。 また、過去の哲学者は我々の生き方のお手本を用意してくれたという表現もいいと思えた。過去と向き合えばついにはソクラテスと議論できるというのは秀逸で、確かに自分と向き合う時間は誰にも邪魔させない自分だけの貴重な時間である。そういった自分との、自分だけの、自分のための時間を大切にすべきというのだろう。 2章 カリグラ帝の妹との不倫関係の罪でセネカはコルシカ島に追放となり、そのことを悲しんでいる母ヘルウィアに向けて書かれた章。この章は大きく分けて2点の主張があり、1点目がセネカは現在精神的に安定しているということ。セネカは全く不幸ではなくむしろ多忙から解放されて本来やりたかった研究に専念できると話しており、母の心配を打ち消している。2点目に母に悲しみに打ち勝つために学問を薦めていること。ここでいう学問は数学などといったものではなく哲学や思想などの教養といった学問であると解釈した。そのような学問こそが、悲しみに越えられるお守りになるという。セネカも母ヘルウィアも双方とも残酷な運命が書かれているが、セネカなりの生き方や思想がよく表れており、どのような状況であっても精神を大切にする哲学がいいと思えた。 3章 政治への大志を抱く青年セレヌスが、セネカに対して悩みを打ち明け、セネカがそれに対するアドバイスをするといった章。この章の前半部分はセネカが考える心の安定について書かれており、どんな境遇でも徳を持つことで精神に安らぎを与えると話している。後半部分はオデュッセイアなどの古代ギリシャ神話などを用いて、生き方を話している。私はこの青年は何を悩んでいるのかが正直つかめていないが、仕事に対する無力感であったり将来の不安などが心を蝕んでいることに悩んでいると解釈している。それに対してセネカがさまざまな比喩表現を使って精神の安らぎを持つことを話しているのかなと思う。 この本の要約を3行で - 人生を長く過ごすために、自分自身と向き合う間暇な時間を過ごすべき - 過去の叡智を参考にして、現在を生きていくべき - どんな境遇であっても精神に安らぎを持てば心の平安は保たれる 点数 90/100
0投稿日: 2021.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
Amazonプライムで無料だったので。 とてもよい。時間をただ過ごすことについてほんとうにそれでいいのか考えるようになる。これまで古代ローマも哲学も興味はなかったけど、よい生き方とはなにかを模索する上でこの本はとてもよいきっかけをくれた。読みやすいのにぐっとささる。 無料で読めるものが増えている中で、この本に早いうちに出会えたことは感謝しかない。 —————— 多忙は人間から有意義な時間を奪い、人生を浪費させて、短くしてしまいます。 『われらが生きているのは、人生のごく僅かな部分なり。』生きているとはいえず、たんに時間が過ぎているだけ。 ひとは、自分の財産を管理するときには倹約家だ。ところが、時間を使うときになると、とたんに浪費家に変貌してしまう (人生の総決算) では、計算してください。 (あなたの生涯から、債権者によって奪われた時間、愛人によって奪われた時間、主人によって奪われた時間は、手下によって奪われた時間、夫婦喧嘩によって奪われた時間、奴隷の懲罰のために奪われた時間、つとめを果たすために、街中を歩き回って奪われた時間、みずからの手で招いた病気[のために失われた時間]、使われることなく無駄に過ぎていった時間、) もうおわかりでしょう。あなたの手元に残る年月は、失われた年月よりも短いのですよ。 あなたがしっかりした計画を立てたことが、いつありましたか。あなたの決めた通りに事が進んだ日は、どれほどわずかでしたか。自分を自由に使えたことが、いつありましたか。あなたの普段どおりの顔つきでいられたことが、いつありましたか。あなたの心がおびえずにいたことが、いつありましたか。これほど長い生涯をかけて、あなたがなしとげた仕事は何ですか。 いわれのない悲しみや、愚にもつかない喜びや、飽くことのない欲望や、甘い社交の誘惑が、どれだけの時間を奪っていったでしょうか。あなたに残された時間は、どれほどわずかでしょうか。――もうおわかりでしょう。あなたは、人生を十分に生きることなく、死んでいくのです 閑暇のうちにあるときでさえ、多忙な人たちがいるのだ。彼らは、自分の別荘や寝床の中でひとりきりになると、ようやくすべての人から自由になったというのに、今度は自分自身がわずらわしくなるのである。そんな人たちの生活を、閑暇な生活と呼ぶべきではない。むしろ、怠惰な多忙と呼ぶべきだ。 (自分自身と向き合うことを嫌がり、なすべきことをなにもしていない状態が、セネカの批判する「ひまな時間」だと考えることができます。セネカが述べているように、このような時間からは、退屈と倦怠しか生まれてきません。) 大きな心で、人間の弱点である視野の狭さを克服しようとするだけでよい。そうすれば、広大な時間が目の前に広がり、われわれはそこを訪ね歩いていくことができるのである。 できるかぎり自分自身に頼り、すべての喜びを自分の中から引き出せるように、つねに努力をしている おまえたちの体がどんなにちっぽけなものか、考えてみようとは思わないのか。わずかなものしか受け入れられないのに、たくさんのものを欲することは、狂気であり、精神が陥る最悪のあやまちではないか。~~おまえたち[の体]には、その蓄えをしまっておく場所がないだろう。 満足を知らぬ精神は、決して満たされません。 祖先たちは、未亡人たちに、亡き夫を哀悼するための十ヶ月の期間を与えました。公的な制度を作ることによって、女性の執拗な悲しみとの妥協をはかったのです。 長くつきあっていれば、よいものにばかりでなく、悪いものにだって、愛着がわいてくるものですからね。 自己嫌悪の発生源は、だらしのない心と、それが抱く欲望である。 古代ローマの詩人ホラティウスの詩の有名な一節に、「この日を摘み取れ」という言葉があります。これは、不確実な明日を頼りにするよりも、今日この日を大切に生きよ
0投稿日: 2021.09.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生を短くしているのは自分 仕事を効率化して空いた時間は自分の為に使おうかな。更なるスキルアップが出来て気持ちに余裕が出来れば人生がもっと豊かになりそう。 常に時間を奪われている意識を持って奪う相手がそれに値するのか(正当に自分を評価してくれるのか)吟味して対応していきたい
0投稿日: 2021.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ2000年前から人間とは変わらず同じ悩みや苦悩を抱えているものだと痛感。 現代人にも響くということは、わかっていながらやはり出来ないことであるという事。 人生は短いものではなく、短くしているという言葉は心に響く。時間は万人に平等に与えられるものであるが、時の過ごし方は人によって違う。時間は有限。目に見えないので簡単に浪費してしまうが、大切に使わないと明日にも終わる可能性がある。 一日一日を後悔のないよう精一杯生きる。当たり前だが出来ない自分がいる。
1投稿日: 2021.09.08 powered by ブクログ
powered by ブクログセネカ「人生の短さについて他2編 「人生の短さについて」多忙な生活から自分自身と向き合う時間こそが大切であり今に集中しなさい。 「母ヘルウィアへのなぐさめ」女性の悲しみを克服するには学問が必要である「心の安定について」少ない財産で質素な生活をおくること。ストイックとはスコア派哲学に由来。約二千年前のローマ時代も現在も人の悩みはあまり変わらずですが、こんな厳しい答えばかりでは相談したくない(泣)
0投稿日: 2021.07.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ一行目の「人生は使い方しだいで長くなる。なのに、ひとはそれを浪費して短くしてしまう」という言葉が、生きる上で大切なことを教えてくれている
0投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ‘’人生を短くしているのは我々だ’’ 時間=命だと考えているので、時間を浪費しないようにして常に時間を投資に使っていく!
0投稿日: 2021.07.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ「他人のために時間を使っているから『人生は短すぎた』と嘆くのだ。本当に貴方の時間と言えるものの割合はどれだけあるか。」って感じのところは本当に心に響いた。取捨選択しよう。 他にも色々、人生のヒントとなる言葉が沢山ある。それは本当にありがたいけれど、自分の哲学と合わない生き方を(本人が後悔しているのなら別だけど)否定から入るのは好きじゃない。接待とかパーティをかなり貶していたけれど、そう断じるのもつまらない人。現代は様々な生き方が選べる時代。自分にとって良い生き方を選ぶのはとっても大切だけど、逆に他人を受け入れて一度は理解することも、生き方を選ぶ上で大切なはず。理解していない価値観をセネカに押し付けられて、それで良い人生になれるとは思えない。自分は生きてる中で無駄な経験なんてなかったと思ってるから、セネカは視野が狭いように思えて苦手。 解説は気が向いたら読む。おそらく向かないけれど……。
4投稿日: 2021.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ今まで読んだ哲学系の本が難しかったせいか、 哲学ってすごくとっつきにくいし、よくわかんないイメージがあった。 けど、図書館でタイトルに惹かれて手に取ってみた。 中身を読む前は、どうせ人生について悲観的なことが書いてあるんだろうなぁ、と思ったけど全然そんなことなかった。 本の中にあった、人生における時間の使い方、私たちが得ている時間は短くないはずなのに、私たちの使い方によって短くなっているというのは、本当にその通りでしかないんだけれど、今まで見ないふりをしていたことをまじまじと突きつけられた気がして、すごく心にささった。 2000年も前の人が書いた文章なのに、古臭さやわかりにくさを感じさせず、 今の私たちも共感できる文章であるというのがすごい。 後々思い出すことが多い本だったので、図書館で借りた後本屋さんでわたしは購入しました。
0投稿日: 2021.06.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の短さについて 人生は短く、時間というものは常に過ぎ去っていく。しかしながら、人々は時間をあたかも無限のように扱う。しかしながら、人間は死すべき人のようにすべてに恐れ、死を知らぬ神のように強欲である。毎日、本当に必要かどうかがわからない仕事に心血を注ぐ。そうした上で時間がない時間がないというのだからおかしな話である。閑暇を大切にし、自分の心に耳を傾ける時間が必要である。そして、自分の心にさえ耳を傾けることができない人が、他人に自分の話を聞いてほしいと願うのもおかしい。では、具体的に自分の心や、本当に聞くべき声はなんなのかといえば、それは過去である。未来は不確かであり、現在は去り行く。過去のみが他人の手を加えても、左右されない確固たるものである。多忙を極め、自分を見つめ直す時間がないものは、自分の過去を見つめ直すことができていないということである。未来に生きるのではなく、過去を重んじ、時間の流れを緩める生活をすべきである。そして、自分の過去のみならず、偉大な人の過去についても学ぶべきである。古典がまさにそれにあたり、古典こそが見るべき価値のあるものである。 要旨としては上記の認識であるが、単純にさもしさを感じた。たしかに現代人を含め、人間は無限に時間があるように過ごす。そして、これは咎められるべきである。しかしながら、現世を見ずに古典ばかり読んでいることで何が得られるのかとも思う。セネカは哲学的思索のもとに、未来への期待を無駄なものと結論付けたが、そうした人間が古典を読み、どう人生を謳歌できるといえようか。
0投稿日: 2021.05.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ人の生き方について解く、哲学者、セネカによる本作。 紀元一世紀の人物による書籍というだけでも驚きですが、その内容もかなり洗練されており、人生において大切な心構えというか、生き方を示してくれます。人はときに閑暇を求め、学問に没頭することにより人生を充実させ、心の安定を得と教えるところには同意できます。自分にとっての問題は、何を学ぶまかか、その学びは人の為になるか、ですが難しいですね。 同時に、今就いている仕事にも疑問を感じてしまいそうですね。人のために生きることも肯定されているので常に自問しながら生きていきたいと感じます。 財に拘ない考え方は、将来の安定した生活を考えると難しいのですが、物に拘らない生活には一層励みたいです。 解説についても当時の社会情勢や人々の暮らしなどが紹介されておりも見応えがあります。ストイックの語源がストア派である豆知識も紹介されています。
1投稿日: 2021.05.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ感想は人それぞれだけど自分は、 「老いて死に直面したとき、堂々と俺の人生は良かった悔いはないと胸を張れる生き方をしよう。じゃあ、それってどんな生き方なんだろう?」という話だと感じた。 この本で、セネカは3つの手紙を通してその話をしてくれる。 自分に他人にも嘘をつかず、自分に恥ずかしくない生き方をする。老いて時間が短くなったときに後悔しないように、自分のための時間を持つ。他人にあげている時間は本当に必要な時間か考える。自分がなにのために人生を使いたいかを考える。そうすれば、人生は短くなくなり、死を迎えるとき堂々とそのときを迎えられる。 二千年以上前から人間はこういうことを考えてたんだと、感慨深くなった。 現代にも通じる、人生の時間の使い方、生き方を考えさせられる普遍的な話でした。
0投稿日: 2021.05.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ人生の短さについて(生の短さについて)の他に収録されてる2作と解説も良い。 下手な自己啓発本を読むよりも良い
0投稿日: 2021.05.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ2000年前の古代ローマの哲学者セネカの作品だが、現代にも思想は通じる。 時間の使い方、過去と向き合って今を大切にいきる、徳と理性、自分の境遇に慣れ、逆境においても自分を見失わない等。
0投稿日: 2021.05.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ古代ローマのストア派哲学者セネカの人と思想の入門書。母へ宛てての手紙など、とっつきやすい。考え方自体については、個人的には共感するところもあれば、古典的と感じる部分も多い。世界史好きだった人は、当時の生活なども垣間見えて別の部分でも楽しめるとおもう。
0投稿日: 2021.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分自身の時間の使い方、人生の向き合い方をふり返させられる本。 高い地位や名誉を得て多忙を極めている人、トリビアのような知識をひけらかす人、おしゃれや髪形ばかりを気にする人、コレクションを自慢する人。 今から2000年も前に書かれた(しかも外国の!)本の中にこれらタイプの人が「人生を短くしている」人の例として登場してくるなんて、人間社会や人の性質は全く変わらないんだな、と痛感。 セネカは手紙を宛てたパウリヌス(重責で地位も名誉もある)に、さっさと多忙な仕事から離れて、自分自身の人生を生きることを説いている。 現代風に言うと、脱サラ隠遁生活を進めているように一見、聞こえるが、そうではない。 人生はいつ終わるかわからない。だからこそ人生の時間の量ではなく質に焦点をあて「生きる」てほしい、と言っているんだと思う。 単に齢を重ねていくことは、長く生きたことではなく、長く存在しているだけ。 (丸山眞一の「であること」と「すること」に似ている) 時の長さではなく、束の間の人生をどう掴むか。 世間の評価を気にしたり、富を追い求めたり、それらのような世俗的な事柄から離れて、自分の人生をどう生きるか。そのためには過去と向き合うべきと説く。 不確かな未来、移ろいやすい現在と違い、過去は確かなもの。過去の偉大な賢人たちの言葉(古典)に触れ、過去という悠久の時間に向き合う。偉大な賢人たちとの対話が、歩むべき未来の人生を照らしていくから。 2021/8/20 追記 セネカは大西英文訳、茂木元蔵訳あり ラテン語でvitaは生、人生
1投稿日: 2021.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ耳読で読破できた。ギリシャの時代でも、今と悩みが一緒!みんな幸せになりたいのは変わらない。幸せになれた人となれなかった人の違いは、自分に幸せな環境を整えられたか否かか。
0投稿日: 2021.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題の「人生の短さについて」のみ読了。 ほとんどの人は時間が有限であることを忘れて生きているということが主題。 人は最後は皆死ぬことを意識しておらず、最期に人生が短いと嘆くのは愚かだという意見には同意。 しかし、かといって過去を振り返る事による賢者との会話や閑暇以外を批判するような論調には同意しがたかった。 生きている間はそれ以外は全て無意味だという論調は柔らかいニヒリズムのような感じがした。 Ex.雑学や歌手の否定。 本の内容は難しいが興味深い、しかし内容には同意できない部分が多かったのでこの評価。
0投稿日: 2021.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ表題作の「人生の短さについて」目当てで読み始めたけど、「心の安定について」がよかった。理念的な「人生の短さについて」と比べると、もっと生っぽくて自己啓発的。 「不完全で、凡庸で、不健全な人々に向けて、わたしはこの話をしている」とセネカは言う。 われわれは新しい刺激を求めてはすぐに飽きて次第に疲れてしまうとか、自分の能力を過大評価して仕事で失敗するとか、覚えのあるような話ばかりで(しかも説明がいちいち生々しい)引き込まれた。 心の不安定な私たちはどうすればと思ってページをめくると、結局アドバイスは「仕事に打ち込んで適度に休め」とか「質素な生活をしろ」とか「人間嫌いになるな」とかよくあるものなわけだが、主張に至る説明過程への納得感が強いため身にしみる。 マイルドなストア派的生活実践ハウツーとして折に触れて読みたい。
0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間とは何かについて考えさせられた。 多忙な時間も充実していて良いかもしれないが、自分と向き合う時間も必要だと思った。過去から学び、今をより充実させた生き方をしたいと思った。
1投稿日: 2021.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ1. この本を一言で表すと? 時間の使い方、悲しみへの対処、自分の弱さとの向き合い方について、まとめた短編集。 2.よかった点を3~5つ ・われわれは、短い人生を授かったのではない。われわれが、人生を短くしているのだ。われわれは、人生に不足などしていない。われわれが、人生を浪費しているのだ。(p.17) →時間を浪費するか有効利用するかは本人次第ということだろう。 ・人間の誤りを乗り越えた偉大な人物は、自分の時間から、なにひとつ取り去られることを許さない。それゆえ、彼の人生はきわめて長いのである。なぜなら彼は、自分の自由になる時間が長かろうが短かろうが、それをすべて自分のためだけに使うからだ。(p.38) →自分の時間というものは、放っておくと、どんどん奪われると思う。防ぐためには、自分のやりたいことを明確にしておく必要があると思う。 ・真の閑暇は、過去の哲人に学び、英知を求める生活の中にある すべての人間の中で、閑暇な人といえるのは、英知を手にするために時間を使う人だけだ。そのような人だけが、いきているといえる。(略)人々に尊敬される諸学派を作り上げた高名な創設者たちは、われわれのために生まれてくれた。そして、われわれのために、生き方のお手本を用意してくれたのだと。(p.66-67)(p) →先人の残してくれた学問は有効利用して時間を有効活用すべきと思う。 ・だが、あなたがそんなに長生きする保証が、どこにあるというのか。あなたの思い通りに計画が進むことを、だれが許したというのか。人生の残りかすを自分のために取っておき、善き精神的活動のために、もうなんの仕事もできなくなった時間しかあてがわないなんて、恥ずかしいとは思わないのか。生きることをやめなければならないときに、生きることを始めるとは、遅すぎるのではないか。 自分が死すべき存在だということを忘れ、五十や六十という歳になるまで懸命な計画を先延ばしにし、わずかな人たちしか達することのない年齢になってから人生を始めようとするとは、どこまで愚かなのか。(p.25 – 26) →現代では、年代ごとに時間の使い方を考える必要があるのではないか。投資の時間、消費の時間をうまくバランスさせる必要があると思う。 2.参考にならなかった所(つっこみ所) ・悲しみというものは、まぎらわせるよりも、克服してしまうほうがよいのです。(p155) →あなたの孫たちのこともお考えになってください。(p160)は紛らしているだけでは? ・ストア派というのがよくわからなかった。 5.全体の感想・その他 ・スティーブ・ジョブズのスタンフォード大学での有名なスピーチの一節に通じる部分があるのではないか。 If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? 「もし今日が人生最後の日だとしたら、私は今日やろうとしたことを本当にやりたいだろうか」
2投稿日: 2020.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ富は人を幸せにしない。 必要な物は最小限で済む。 富よりも精神が大事。学問が大事。 精神を高める事が真の豊かさを与えてくれる。 という内容。 印象に残ったのは、希少なツボや大理石を収集して何になる。という話。高価な希少品を集めてもたしかに死んで時代経ったら何にもならない。何が大切かよくわからなくなってる証拠だ。 一方で富が才覚や広い見聞、さまざまな体験や将来の可能性、精神の安定に直結する。貧しさは世界の狭さや奴隷的労働、精神の不安定に繋がる。親の離婚で貧しさや奨学金で苦しむ人もいる。富と学問には相関関係がある。そして例外があるにしろ富と幸福にも相関関係があると思う。 大金を得ると人間がおかしくなるというのも良く聞く。貧しくとも学問を志し、生活に必要な十分なだけのお金を得るというのが理想なのかもしれないが、なかなかそうはいかないのが世の中。 ただ学びを通じて精神を高め、自分を信じる事が安定をもたらす。そしてそうした精神は侮辱されても侮辱を受けた事にならない。というような趣旨の具体的な表現はとても参考になる。歴史や場所が全然違うところで書かれた書籍であるが故に本質をついているところもある。年齢を重ねるにつれ味わいがわかる人生観を考えさせられる良書だと思う。何度も読み返したい。 この本を読むにあたりセネカがストア派であり、ストア派が生まれた背景は知っておいた方が色々な見方ができる。
1投稿日: 2020.03.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ2019/2/1 古代ローマの哲学者、セネカの著作。ストア派は倫理で習った程度の知識だが、本作を読んでこんなに現代にも通じる教えなのかと驚いた。運命に翻弄されず、逆境にも動じないというのは仏教の考え方にも共通するところがあるので、セネカは日本で人気が高いのだと思う。セネカに従い、今後は日々の生活に疲れたら、読書という名の閑暇に逃げ込むことにします。
0投稿日: 2019.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ”二千年前の古代ローマの哲学者による「いかに生きるべきか」論。 本屋Titleで出逢い、お店の奥のカフェで食事しながら掲題作を読みきった。シニカルだけど真理をついてる。 過去の英知とふれあうことを解くこの本が、「いま、息をしている言葉で、もういちど古典を」の光文社 古典新訳文庫から出たのも素敵なご縁。 今後、人間塾などの読書会で読むにもよさげ。 <キーフレーズ> ・われわれは、人生に不足などしていない。われわれが、人生を浪費しているのだ。 ・閑暇な人といえるのは、英知を手にするために時間を使う人だけだ。 ・パウリヌスへの助言──多忙な生活から離れ、ほんとうの人生を生きなさい <抜き書き> ・われわれは、短い人生を授かったのではない。われわれが、人生を短くしているのだ。われわれは、人生に不足などしていない。われわれが、人生を浪費しているのだ。(p.17) ・人間の誤りを乗り越えた偉大な人物は、自分の時間から、なにひとつ取り去られることを許さない。それゆえ、彼の人生はきわめて長いのである。なぜなら彼は、自分の自由になる時間が長かろうが短かろうが、それをすべて自分のためだけに使うからだ。(p.38) ※多忙な人たちとの対比。 ・真の閑暇は、過去の哲人に学び、英知を求める生活の中にある ※小見出し すべての人間の中で、閑暇な人といえるのは、英知を手にするために時間を使う人だけだ。そのような人だけが、いきているといえる。(略)人々に尊敬される諸学派を作り上げた高名な創設者たちは、われわれのために生まれてくれた。そして、われわれのために、生き方のお手本を用意してくれたのだと。(p.66-67) ★だからこそ、俗人たちのもとを離れなさい。親愛なるパウリヌスさん。あなたは、その年齢に釣り合わぬほど、たくさんの出来事に翻弄されてきた。だから、静かな港に帰るのだ。 (略)あなたは、たえまない苦労を乗り越え、その中で十分な徳を示してきた。こんどは、閑暇な生活の中で、その徳が何をなしとげるか試してほしい。 ・ストア派の哲学者たちにとって、人間の目的は、快楽を追求したり、欲求を満たしたりすることではありません。(略)ストア派の哲学者たちは、このような情念に打ち勝った状態を、アパテイア(無情念)と呼び、そのような状態に至ることを人間の理想としました。みずからの欲望を抑えた禁欲的な態度を「ストイック(ストア的)」というのは、これに由来します。(p.284:解説 by 中澤務さん) ★われわれは、過去という時間を訪れ、そこで過去の優れた英知と交わることによって、現在という短い時間から解き放たれ、永遠の時間の中に生きることができるようになるのです。 (略)このようにして「今を生きる」ことによって、現在という短い瞬間は、無限に広がっていくことになるのです。(p.292:解説) <きっかけ> 本屋Titleで文庫だなの上部に面出し陳列していたのにひかれて…。”
1投稿日: 2019.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ岩波文庫はKindleで読めなかったので、こちらにした。訳や注釈も読みやすく、必ずしも岩波文庫にこだわる必要はない。 人生の短さについて、だけを読んでの感想になるが、内容としては残念ながら星2つレベルである。ストア哲学では理性、自省録を書いたマルクス・アウレリウスは自然(宇宙の秩序)に則って生きる事を推奨している。 セネカにおいては、その自然は哲学者になることであると言っている。いや、哲学者とは明確に述べてないが、『英知を手にするために時間を使う人』を定義とし、例として哲学者を挙げているので、哲学者という解釈で問題ないと思う。 この哲学者の話が出るまでは、とても吸い込まれるように読んでいた。時間というものが見えないものであるし、当たり前すぎて、お金の浪費は気にするのに、時間の浪費は気にしない人が多い。とか、他人のために時間を費やしすぎている。とか、そういう話は納得がいった。 だからこそ、どのように生きるべきか?が気になっていたのだが、その結論が哲学者とはあまりにも面白くない。 たしかに自然に従って生きることの解釈が人間にとって出来ることの追求だとすれば、『考える』という事なので、哲学者という流れは正しいように見える。 ただ、それはある意味究極論でしかない。考えることだけをすれば、一番理性的というのは理想論で実践的ではない。 もし世界中の誰もが考えることだけをして、生きるとは何か?とか幸福とは何か?だけを考えていたら、誰が国を運営し、誰が食べ物を育てるのか? そういう事をしている人たちの恩恵の上に、哲学者たちが生きられている事を忘れてはならない。哲学者でさえ、他人の時間を奪い、それによって生かされているのだ。 私の思う理想は、自省録で書かれているように、自分の本質や本性を見つけ、それに従って生きていく事なのだと思う。 ただし、自分らしさが自然、つまり宇宙の秩序に反してはいけない。あくまで秩序、理性ある中での自分らしさを発揮する事が大事なのだと思う。 実践的であるはずのスコア哲学が、全く実践的でない点が腑に落ちず、この点数とした。 ==追記== 人生の短さについて、を読んだ後の2つの話、特に心の安定について、はより実践的であり、読み応えがあった。 最も重要な違いは、自分に適した職につくことを勧めている点だ。哲学者こと全てだったはずが、晩年の作品では意見が変化している。 ここにセネカの考え方の変化が見られ、人生を送っていく中でおそらく変化が出たのだと思える。 3つの作品を踏まえれば、星4つくらいなるレベルの話になる。 つまり、2000年前もひとたちの過ごし方も、現代の過ごし方も、文明の差はあれど何も変わってないのだなぁという事だ。 哲学を読み進めるのは確かに大変だ。が、しかし、そこには読むべき意味がしっかりとある。 過去に学び、今を全力で生きるためには、自分の過去だけでなく、2000年以上ある歴史から学べることを学ぶべきである。 その上で何をするのかを考える方が、合理的だと思うから。
4投稿日: 2019.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ時間の使い方、悲しみへの対処、自分の弱さとの向き合い方について。セネカの親身な語り口のおかげで、小難しい哲学的考えも抵抗なく受け取れた。古代ローマの人々の暮らしを舞台にしているにもかかわらず、自分の体験とも照らして実感することができ、時代が違っても人の感情は普遍だと思った。
0投稿日: 2019.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログストア派の哲学者の本とは思えない人間味に溢れ平易で愛に満ちた言葉。 人間の姿は文明を超えて変わりないと分かる。
0投稿日: 2019.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログいい歳過ぎて古典を読み始めたのだが、面白い! もっと早くに出会いたかった!光文社の新訳古典は読みやすいです。
0投稿日: 2019.01.04 powered by ブクログ
powered by ブクログなぜ、僕がこの古典を読んだのかというと、 セネカはカリグラ、ネロというローマ帝国二大悪皇帝に仕え、最後はネロ暗殺の嫌疑をかけられ、自殺した、というその人生を知り、読みました。 表題の人生の短さについては、妻の父にあてた手紙形式の「ヒマの勧め」である。 素晴らしいではないか。 「ヒマ」というと語弊があるので。セネカ流に言えば「閑暇」です。 それは人生を充実させる重要な仕事なのだ。 ローマ帝国時代のストア派・哲学者セネカの味わいある「哲学」が読めます。
0投稿日: 2018.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ哲学者セネカの入門書。 人間は理性的に行動するべきであり、その方法を述べている。理想を追求するだけでなく、いかに欠点を和らげるかかかれている点など、実践的な内容である。 2000年前に書かれたにも関わらず、現代人にも多くの示唆があると思う。
0投稿日: 2018.03.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ2017/3/17読了。流石古典新訳、スラスラ読める。もう少しストア派って厳格な印象があったけど、なかなか現実的な内容だった。そもそものストア派に対する認識がズレてたのか、セネカさんが一般化してくれているのかはわからないが。 『心の安定について』の中の蔵書に関する内容が、胸を突いた。 「多数の作家によって道に迷うより、少数の作家に身を任せた方がはるかによい」 わかっちゃいるんですがね〜
0投稿日: 2017.03.17
