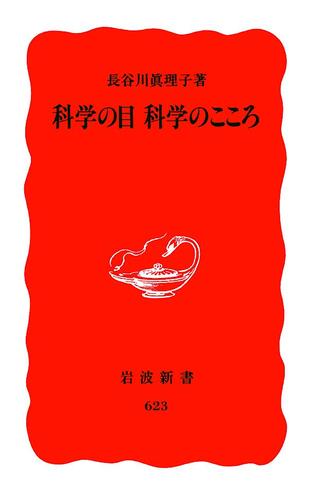
総合評価
(15件)| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ858 数学的な線や物理法則は、なぜ人間の審美的感覚を 刺激するのだろう?自然界の生物が作り出す形は、 なぜ美しくみえるのだろう?その答えは、数学や物 理学ではなく、私たちの神経系の構成に関する生物学 の中にあるに違いない。 ミルクが欲しければ、ミルクが異常に出る牛を作るのがよいのか、どうしても子ども が欲しいという個人の欲求の実現は、あくまでも尊重されるべき権利であるのか、生き 延びたければヒヒを殺して肝臓をとってもよいのか。「それをすることは可能ですよ」 とささやくのは科学であるが、「では、やってくれ」と欲するのは人間である。 優しい顔をしたドリーはすくすくと育っているが、彼女の存在は私たちに難問を突き つけている。 そこには、「生物学はイデオロギーである」式の発言が満ちあふれている。 しかし、それでは科学もイデオロギーの一種かというと、そうではないはずだ。科学は仮説構築の連続であ り、対立競合する仮説を観察に対して照合することによって、より事実に近い仮説を選び出していく手続きで ある。これ以外に、私たちを取り巻く自然界に関する知識を得るための、よりよい方法があるだろうか? しかし、私たちの手持ちのやり方の中では科学は一番客観的だし、間違いを正すための 自浄機構を備えている。研究者の偏見や信念が研究の足を引っ張ることもあるが、いずれ間違いは正される。 科学は、まったくの真実そのものを提供するわけではないが、手持ちの説の中から、より真実に近そうなもの をとっていくことによって、つねに改訂の可能性を前提としている。これらのことは、「イデオロギー」とい うものの性質とは大いに異なるだろう。これは、実際に仕事をしている科学者たちの多くが実感していること にちがいない。 ダーウィン以外では誰に会おうか?やはり、アイザック・ニュートンという人には会ってみたい。いろい ろ伝記を読んでみると、議論では相手を完璧に叩き潰さずにはおかなかったとか、けっして人前で笑わなかっ たとか(一度だけ笑ったが、それは他人を馬鹿にした笑いだった)、講義がむずかしすぎて学生が逃げ出し、教 室には一人も学生がいなかったのに講義を続けたとかいう話が多いので、あまり人間的におもしろい人ではな かったかもしれない。しかし、微積分を作り上げて古典力学を完成させた、あの分析力と洞察力の素晴らしさ には、科学者なら誰でもあこがれるだろう もう一人、私が興味を惹かれる一七世紀オランダの画家は、フェルメールである。この人も、その幾何学性 と静寂さに惹かれるのだが、フェルメールの場合は、これに色の要素もつけ加わっている。彼の絵は、サーン レダムよりもずっと色がきれいである。とくに青と黄色がすばらしい。 科学が自然の成り立ちを次々と明らかにしていくことは、自然界の美しさを奪うものではないはず だ。一七世紀、科学は自然を理解する哲学の新しい姿として台頭し、芸術家であれアマチュアであれ、ものを 考えることの好きな人々は、みな科学に熱中した。そのような、科学と芸術の密接な関係は、現代では薄れた かもしれないが、科学が明らかにする自然の姿は、自然の美しさに対する感動の、一つの源でありつづけるだ ろう。 科学も人間のやっていることなので、嘘もあればデータの捏造もある。なかでも、ピルトダウン人のいかさ ま事件は、どことなくロマンスと探偵小説風の興味のある、しかも今世紀最大の詐欺事件であった。 ダーウィン自身の著作を読むことは、科学史の上で興味深いばかりではない。いまだに解けていない問題に 対して彼が行なった考察や、さまざま事実を組み合わせて議論を構築する彼の洞察は、一〇〇年以上を経た 現在でも、私たちに新鮮な驚きとひらめきとを与えてくれるアイデアの宝庫なのである。 チャールズ・ダーウィンは、一八〇九年にシュルズベリにある、「ザ・マウント」(The Mount)と呼ばれる 大邸宅で生まれた。父親のロバート・ダーウィン氏は、裕福な医者だった。この家はいまでも残っており、不 動産の査定に関する政府のオフィスとして使われている。中を見学したい訪問者には、役所の人がついててい ねいに案内してくれる。 ダーウィンは、一生自分が働かなくてすむ金持ちの家に生ま れ、自分のすべての時間を自由に使えた。のびやかな学生生活を 送り、ビーグル号で五年間かけて世界をみるというすばらしい機 会に恵まれた。多くの知的な友人や師にも恵まれた。しかし、後 半生のうちの半分以上は、原因不明の病気で苦しみ、生まれた子 どものうちの三人は幼くして死んだ。 ふつう、店でハチミツの瓶を買うと、四五〇グラム(一ポンド)である。行動生態学者のハインリッチによる 、一ポンドの蜜を集めるために、ミツバチは一万七三三〇回の蜜集め飛行をせねばならない。一回の飛行 は平均二五分で、およそ五〇〇個の花を回る。したがって、一瓶のハチミツには、およそ八七〇万個の花を回 ったミツバチの七二二〇時間の労働が集約されているのである。 今度ハチミツを食べるときには、この数字を思い起こし、相互扶助の大切さとともに、騙されないことの大 切さも忘れないようにしよう。 本当に、ほんどいないのだろうか?私が調べた範囲では、国公私立大学の理学部、農学部、薬学部の講 師以上の職のうち、女性が占めているのは、わずか二・七パーセントである。これは、もともと科学を志す女 性がそれほど少ないからというわけではない。先の『サイエンス』の記事にも示されているが、理学部の学部 学生のレヴェルでは、女性の割合はおよそ三分の一に達しているのである。 アメリカは自由と平等を謳っているが、実は根強い 人種差別の社会であることはよく知られている。そし て、二〇世紀初頭には、その人種差別と優生思想とは 手に手を取りあっていた。一九二一年の移民法や、そ の前から進められていた断種法などの法案は、まさに 優生思想を実践するものである。 社会にとって「好ましい「好ましくない」というのは、いったいなにを基準に判断するのか。「好ましい」日的のためには、「好ましくな い」人間の人権を制限することができるのか。短絡的な目的のために導 入された科学技術が、結局は人々に悪をもたらすという話は近年数多く ある。 本書は、もともと岩波書店の雑誌『科学』に、一九九六年一月から 九九九年四月までの三年間にわたって連載したエッセイに、加筆・修正 を加えたものである。 科学技 術のどんどん進んでいくこの時代に、専門の科学者ではない人々が、科 学とどのようにつきあうべきか、サイエンティフィック・リテラシーと 呼ばれるものの基本はどうあるべきかというのが、本書のエッセイを通 じての、一つの思考の結び目のような役割を果たしてはいる。私にもま だ答えの出ない難問である。
0投稿日: 2023.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログとても読みやすくて面白かった。科学者と一般人のコミュニケーション以上に、異なる分野の科学者同士のコミュニケーションは難しいのかもしれない。
0投稿日: 2018.05.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
1999年刊行。著者は専修大学法学部教授(ただし専攻は行動生態学)。雑誌「科学」に寄稿したエッセイ集。敷衍すれば何百頁ものハードカバー書籍が出来そうな多種多様なテーマを簡潔に叙述。性淘汰仮説や生存競争、ハンディキャップ理論等、生物学に関心があれば既知の事項も多いが、大学論、あるいは科学哲学者と科学者との噛み合わせの悪さに関する著者による得心のいく説明など、読破の価値ある一書。ここまで言い切れるかは自信はないが、多くの人が保有することを著者が願う、科学的教養の一端に触れることが出来る書とも言えようか。
0投稿日: 2017.01.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ元は雑誌に連載のエッセイだっただけあって、短い文章に内容が纏まっていてとても読みやすい。 科学にさほど興味のないひとにおすすめしたい本。
0投稿日: 2014.09.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ人類学者・進化学者の長谷川眞理子による岩波書店の雑誌『科学』の連載エッセイをまとめた本。テーマは、進化生物学・進化心理学の話、ポストモダン批判、ケンブリッジでのエピソード等多岐にわたる。含蓄があって人に話したくなる内容である。
0投稿日: 2013.08.25 powered by ブクログ
powered by ブクログタイトルと内容の整合性に疑問を感じるが、短編の集まりなのですぐに読めた。留学のエピソードや日本の大学の在り方に関する考察は面白かった。
0投稿日: 2012.10.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ確か高校生の時にふとしたきっかけで著者の存在を知って、それ以来ずっと頭の片隅にはあったが、数年の時を経て、こうしてようやく読む機会が訪れた。雑誌『科学』に掲載された、科学に関するエッセイをまとめたものだ。高校生から大学生の初めころまではエッセイという形式が好きで、よくいろんな人のものを読んでいたが、ここ数年はあまり食指が動かなかった。今こうして久しぶりにエッセイを読むと、やはりあまり面白いと思えるものではなかったのだが、それは内容云々というよりは、一つ一つの話が短く、単純に読み物として物足りないからだろう(エッセイなどの軽い読み物は、やはり電車の移動時間とか、ちょっとした時に読むものであると思いました)。 著者は、専門は自然科学(行動生態学)だが、社会科学、人文科学などにも関心があるせいか、本書も、科学と社会との関わり、人間との関わりなどにも幅広く言及していて、そのあたりがエッセイを非常に親しみやすいものにしていると思う。 あとがきにもあるが、著者の主要な関心である「科学とどのようにつきあうべきか、サイエンティフィック・リテラシーと呼ばれるものの基本はどうあるべきか」というのは、勉強としての自然科学が苦手だった僕の関心事の一つでもあります。今後も機会を見つけては自分なりに考えていきたい。
0投稿日: 2012.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
非常に興味深い内容で、示唆に富んでいたように思います。 なんだか既視感がありましたが。 以下、引用 「シェイクスピアのハムレットのセリフを知らないと無教養だと思われるが、熱力学の第二法則を知らなくても無教養だと思われないのはおかしい。ーC・P・スノウ」 「人間は天使でもなければ野獣でもない。困るのは天使のように振る舞おうと思っている人々が、実は野獣のように振る舞うことである。ーパスカル」
0投稿日: 2011.09.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ今や科学は思いもよらぬ発展を遂げて、今なお、その発展は止まる事をしらない気がする、いつ人類の探求が終わりを遂げるのか? いや、終わりを遂げることがあるのか?私達は常に科学の発展を目にして行くだろう。 19世紀のダーウィンの時代には考えもつかないことがありすぎる。しかしその発展は、時代を変えてきた先人の知恵があってこそ今がある。 そんな気がしてならない。 では、一体ダーウィンの時代にはどの様な思想や考え方があったのだろう。それを今回紹介する書籍から考えていこう。 まず、科学の発展は古代ギリシアから始まっていた。 その当時何かな構造やシステムを考える上で必要にモデルがあったと言われている。それは人体の構造である。 ギリシア人は自然を理解する上で人体の構造を一つのモデルにしていたと言われている。 いまではその対比は人体ではないのかもしれない。しかしその当時のことを考えると、人体以外で複雑で自然に近いものとといえば、人体以外なかったと推測できるのではないだろうか。 というように昔はそのような考えのもとで科学を発展させてきた。 今では。バソコンや主に機械、動物など様々なものを活用できるような時代になった。 本書はこのように出発して、この後に生物全般の話し、そして科学と社会の話し、そしてまとめにはいるという流れである。 最後にはこんな内容になっている。 ダーウィンの時代にはより優れた血統改善のためにより優れた血統を増やし、望ましくない人間の繁殖を妨げることによって人類を改良するための科学と定義されている。これを優生学というのですが、何故このような思想が生まれたかというと、この時代は資本主義の発展で貧富の差の増大によって、悲惨になったので、その社会を改良せねばならないと思い、その考え方に至ったとされている。 本書ではこのようにまとめられている。「優生思想は1900年代初頭における急速な遺伝学の発展と社会改良思想とを背景に、人類の生物学改良が可能であると考えた、性急な理想主義の産物であった。」 しかし、その思想に関して、社会にとって何が好ましくて、何が好ましくないのか?いったい何を基準にして判断するのか。という社会思想が科学を安易に使おうとして失敗した例でもある。 では私達はなにを基準にすればよいのか?悩むところである。 今の政治でもそうだが、日本にとって何が好ましくて、何が好ましくないのか?という問いに対して、頭を悩ませる次第である。 しかし一つ言えるのは、好ましくないものを排除するという考え方は今後の社会にとってもよくないだろうと思う。 不必要だと思われていたものにもれっきとした考えがあり科学があります。 それを見極めることが本書で伝えたかったことではないだろうかと私はおもう。 以上で話しは終わりだが、ここで長谷川氏が建築について話している箇所があったのでちょっと紹介しよう。 このようにまとめている。 「数学的な線や物理法則は、なぜ人間の審美的感覚を刺激するのだろう?自然界の生物が作り出す形は、なぜ美しくみえるのだろう?その答えは、数学や物理学ではなく、私達の神経系の構成に関する生物学の中にあるに違いない」と著者は考えている。 数学的な線とかは20世紀の建築が装飾から解き放たれて、線の美、合理主義な建築美が現れてきた背景にある。 おもしろい見解だと思う。生物学と建築学はなんの接点もないかのように見えるが、実は建築学ももとは人体をモデルにしていたし、なんのおかしな点もないことが時代を読めばわかることである。 とまぁ話がそれたが、これで今回の書籍の紹介を終えたいと思う。
0投稿日: 2011.06.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ長谷川眞理子は懐かしい。実際に講義を受けたことのある、先生の著書を読むのは実は初めてかもしれないという意味で新鮮だ(自分の元専門分野を除いて)。彼女はてっきりうちの大学の教授だと思っていたのだけれど、あれは出張授業だったらしくて、夫はうちの大学の教授だったみたいだ。だとすれば、「うちの大学では女性を採用するつもりはない」と言われた屈辱を彼女は今も晴らせないでいるのか、わざと蹴っているのかそのあたりは不明である。 本著を読み進める際に、少し躊躇したのは、全ての分野が彼女の専門である「行動生態学」や「進化生物学」のジャンルからつづられていはしないかということだったのだけれど、比較的「科学」という総体なるものを捉えようと話題が選ばれており、そのあたりの不安は杞憂であり、話題自体も少々古いものもあるが基本的にはまだホットと言えるのものや、古典的に問題としてずっと佇んでいるものなどが多くて、引きこまれる。彼女がしきりに訴えているのは、科学にもモラルを与えるべきだとする「サイエンティフィックリテラシー」なるものなので、一応元文学少女のような顔を持つらしい彼女は、科学哲学と科学という二つの分野があるのだけれど、自分はどちらかというと中間的に位置する人物であるとして、両者の橋渡しが出来ないものか、さもなくば、両者が歩み寄ることは可能ではないのか、といったことをつづっているのだけれど、彼女自身は明らかに科学サイドについた考え方が根強く、ラディカルに科学哲学を攻撃しないだけであって、基本的に科学サイドだということを認識してほしいものだとは感じる。しかし、それは別に悪いことではなくて、人にはそれぞれ立場や立位置があるので仕方なく、対立自体は別にいいのではないかなとも思う。個人的には両者があまりにも頭が固いのだろうと思われる。ポストモダンは真理なるものを嫌う傾向にあるので、相対主義という言葉を当てられているのだけれど、相対主義という言葉自体が痛烈な皮肉にも思われるが。ただ、この対立っていうのは難しいところで速い話見ている部分が違うのだろうとは思う。哲学っていうのは成り立ちを見るのだけれど、科学っていうのは実際に成り立っているものを見る。なので哲学の方がより一歩先へと遡る。科学が客観世界を捉えているとするならば、哲学はそれは確固たる客観世界なのかというあたりに疑問を馳せる。科学は「だって今目の前で成り立っているでしょ?」と言うけれど、哲学は「我々は成り立つ前を考えているのだ」ということになる。これを両者がでしゃばり、科学が「成り立つも成り立たないのもこれが真理だろう?」というようなことを言い、哲学は「全ては我々の認識だからあんたらのやっていることは仮象の産物なのだよ」と言い、混迷する。両者はそれぞれ根本的に担っているところが違うというのが実情ではないか。ただ、根本的には哲学があり、我々が捉えているところの現実は科学が網羅しようとしている、でいいと思うのだ。科学は根本に哲学があるというのを認めたくないし、哲学はそれゆえに俺らが優位なのだと言いたい。哲学にはなまじ歴史があるし、科学は哲学から分派したという意識もあるから、科学サイドは余計ヒステリックになるし、哲学も哲学で今の科学主義になりつつある風潮に焦りを感じていてより攻撃的になる。彼女にはこのあたりの構図を見つめてほしいものだと感じる。とはいえ、彼女は現在の哲学はともかく、過去の哲学に対しては認めてもいる。ダーウィンと同じくらいにデカルトの名前が頻出するのも彼女のそのあたりの意識によるものだろう。やや批判的になってしまったけれど、彼女がもし本当に両分野に通暁しているなら、両者の立場からそれぞれ迫って欲しかったのである。建築では近代建築を褒めるけれど、ポストモダンに対しては批判をくれる。両者の美しさをそれぞれ比較批判してくれたらと思うのは高慢だろうか? 本著の内容としては、どれもこれも面白いというのは最初に述べたとおりである。「コンコルドの誤り」や「ハンディキャップの原理」はそれぞれに面白くそれぞれ対を成しているような考え方である。後者は信号が信用されるためにはそれだけコストがかかっている必要があるとする考え方であり、孔雀の雄があれだけ奢侈な格好をするためにはそれだけのコストが費やされているとするものであり、前者はむしろコストをそれだけかけてしまった以上は必ずその生存戦略をとらなければいけないと考える誤解であり、人間界では戦争でこれだけ死者を出した以上は戦争を継続するしかないとする考え方である。これらは別々の節で書かれているけれど、それぞれ対を成し補い合っている法則であると言える。基本的にはコストの量がものを決めるが、コストにばかり捉われていてはいけないし、コスト絶対主義とはなりえないというのが両者から見え隠れする本質だと思われる。他にも見所はいくつもあるが、個人的に印象に残った文章をいくつか引用してみたい。 「対象を数学的に扱うことは、対象を極度に抽象化することである」 →この考え方には興味がある。外界より内界が好きで具象より抽象が好きであり、この考え方に数学と自分との親和性を見つける。 「ヒトの顔を合成してどんどん左右対称に作っていくと、その魅力は増していくようだ。しかし、そこで、ほんのちょっと対象を崩した顔が、もっとも魅力的だと思われるらしい」 →福山雅治が想起される。 「人間は天使でもなければ野獣でもない。困るのは、天使のように振舞おうと思っている人々が、実は野獣のように振舞うことである」――パスカル。
0投稿日: 2011.06.16 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 膨大な科学的知識の消化よりも、科学の基本にある考え方や意味についての確かな理解こそ、現代の私たちにとっては大切なことだろう。 著者は、根っからの理科系でも文科系でもないと自称する生物学者。 クローン羊の誕生、ムシの子育て、イギリスでの見聞など、多彩な話題をおりまぜながら、科学と人間と社会について考えるエッセイ集。 [ 目次 ] 1 生物の不思議をさぐる 2 科学・人間・社会 3 科学史の舞台裏 4 ケンブリッジのキャンパスから [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.25 powered by ブクログ
powered by ブクログしている途中で無駄だということが分かっていても、それまでかけていた労力のことを考えると、どうしてもやめられない…後から後悔するのは分かっているのに…。コンコルドの過ち?ちなみにこれの逆が三日坊主? 専門のことだけでなく総合的な考えを持っているほど、幹が太くなる気がします。
0投稿日: 2010.12.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ長谷川さんは生物学者です。この本の内容はあとがきに著者が示しています。『私自身の専門である,動物の行動と生態の研究に関することばかりでなく,科学や学問一般について,およびそれらの社会との関係など,日頃考えていることをいろいろな角度から書いてみた。』 まさにその通りの大変面白い本でした,興味を引いた箇所が沢山あります。その内の「コンコルドの誤り」をご紹介します。 この「コンコルドの誤り」は言葉とその意味と一緒に覚えておくとよろしいと思います。「コンコルドの誤り」とは『過去における投資の大きさこそが将来の行動を決めると考えること』だそうです。語源はもちろん英仏共同開発の超音速旅客機からきています。『コンコルドは、開発の最中に、たとえそれができ上がったとしても採算の取れないしろものであることが判明してしまった。つまり、これ以上努力を続けて作り上げたとしても、しょせん、それは使いものにならない。ところが、英仏両政府は、これまでにすでに大量の投資をしてしまったのだから、いまさらやめるとそれが無駄になるという理屈で開発を続行した。その結果は、やはり、使いものにならないのである』 だそうです。行動生態学の分野では・・・ 『いま、一羽の雄の鳥が、ある雌に求愛しているとしよう。これまでに雄は、ずいぶん長い時間を費やし、たくさんの餌をプレゼントに持ってきたが、雌は一向に気に入ってくれない。雄は、このまま求愛を続けるべきか、やめるべきか? このような状況で、動物たちがどのように行動するよう進化してきたかを考えるとき、一昔前には、雄はもうこの雌に対して大量の投資をしてしまったので、いまさらやめると損失が非常に大きくなるから求愛をやめないだろう、という議論があった』 しかしこれは誤りで,『さきほどの雄がむなしく求愛を続けている雌のとなりに、その雄はまだ一度も求愛していないが、求愛されれば十分に応える気のある雌がいたとしよう。もしそうならば、雄は、過去の投資の量にかかわらず、さっさとそちらの雌に乗り換えるだろう。将来の行動に関する意志決定は、過去の投資の大きさではなく、将来の見通しと現在のオプションによらねばならない』然り! ですが,人間はちょくちょくコンコルドの誤りを犯すようです。
0投稿日: 2010.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2008.06.25読了) 長谷川眞理子さんの書いた、科学に関するエッセイです。岩波書店発行の月刊誌「科学」に、1996年1月から1999年4月まで連載したものを一冊にまとめたものです。 専修大学にいたころは、文系の学生に教えていたので、科学全般について考えることになったのでしょう。「大学の一般教養で、理学部ではない学生に対して科学とは何かを教えるという仕事をするはめになってから、科学というものを少し外から眺めることができるようになった。科学と社会との関係なども、理学部にいたときよりもずっと考えるようになった。」(6頁) ●コンコルドの誤り(14頁) コンコルドは、開発の最中に、たとえそれができ上がったとしても採算の取れないしろものであることが判明してしまった。ところが、英仏両政府は、これまでに大量の投資をしてしまったのだから、いまさらやめるとそれが無駄になるという理屈で開発を続行した。その結果は、やはり、使い物にならないのである。 このように、過去における投資の大きさこそが将来の行動を決めると考えることを、コンコルドの誤りと呼ぶ。 ●数理生物学者(30頁) 数理生物学者と、羊を連れた羊飼いが牧場で出会った。数理生物学者が羊飼いに、「あなたが何頭の動物を持っているかを、もしも私が正確に当てたら、羊を一頭くれますか」と聞いた。羊飼いが承諾したので、数理生物学者は「278頭」と答えた。それは当たっていたので、数理生物学者が一頭取った。 今度は羊飼いが、「もしも私があなたの職業を正確に当てたら、それを返してくれますか」と聞いた。数理生物学者が承諾すると、羊飼いは「数理生物学者」と答えた。 彼が驚いて、「どうしてわかったのですか」と聞くと、羊飼いは、「今あなたが取った、その動物はね、それは犬だよ」と答えた。 ●命の実感(93頁) 人類の存続のために生態系全体の保全が叫ばれているが、それだけではなく、自然とのふれあいは、自分自身を含めた命の実感をはぐくむ上で人間に不可欠なのだろう。 ●翻訳の読みにくさ(97頁) 翻訳書が読みにくい理由。①誤訳、②学術用語を知らないための誤訳、③意味は正しくても日本語としてまずいため意味が伝わらない。 日本の出版社、編集者は、自分が読んで素直に理解できないものはもっとどんどん断るべきだ。よくわからない文章というものには、訳している本人にも、それを読む第三者にも、直感的に変だと感じられるものがあるはずだ。 ●女性科学者はなぜ少ないのか(175頁) 二つの異なる意見がある。一つは、女性差別であるというもの、もう一つは、科学は女性に向いていない、というものである。 私は、かつて、東京大学理学部の助手をしていたころ、所属教室の主任から、「東大理学部では女性は採らないのだから、出て行きなさい」と面と向かって言われたことがある。 後者については、科学のほとんどの分野は数学を必要とする。女性には、数学が苦手な人が多いから、結局、理系に進む人が少ない、という話である。 話の視点が結構面白く、一編がさほどながくないので気楽に楽しめます。文系の人でも楽しめます。 ☆長谷川眞理子の本(既読) 「オスとメス・性はなぜあるのか」長谷川眞理子著、日本放送出版協会、1997.04.01 「進化とはなんだろうか」長谷川眞理子著、岩波ジュニア新書、1999.06.21 「科学の目 科学のこころ」長谷川眞理子著、岩波新書、1999.07.19 「生き物をめぐる4つの「なぜ」」長谷川眞理子著、集英社新書、2002.11.20 「ダーウィンの足跡を訪ねて」長谷川眞理子著、集英社新書、2006.08.17 (2008年6月26日・記)
0投稿日: 2010.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクログこれ、買ったけど未だ読んでません。ゴールデンウィークにでも読むか。書いた人は動物行動学の有名な先生です。
0投稿日: 2005.04.24
