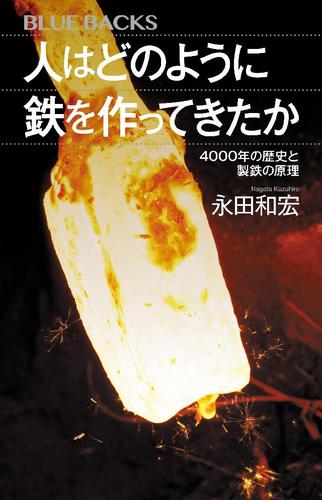
総合評価
(13件)| 0 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ金属工学の専門家による鉄の歴史と実験報告、たたら製鉄から考案した電子レンジ製鉄の提案。個人的にはオーパーツであるデリーの鉄柱の記事や日本刀の刀身の表現に注目。 専門家故製鉄炉の構造や素材の数値に詳しいが、そもそもをよく分かっていないので理解できたとは言い難い。
1投稿日: 2025.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ炭素含有量が2.1%以上 鋳鉄、銑鉄 炭素4.1%で融点1154 炭素含有量が0.02%以下純鉄で融点1536 0.02~2.1%鋼 隕鉄ウイドマンシュテッド構造 和鉄はFe2O3の黒錆被膜ができてさびにくい 鉄が溶ける時沸き花ができる マイクロ波で鉄を作り出す方法も
0投稿日: 2025.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ全19章のうち、第2章「鉄を作る」とはどういうことか が、唯一理解できる章だった。 「焼入れ」と「焼鈍し」の原理を理解出来ただけでもよしとしよう。。 鉄と炭素の組合せの妙、熱処理のやり方次第で硬くも柔らかくもできると言うのはすごいことだ。 あまり意識したことなかったけど、世の中に多目に存在する原子は、ヘリウム(質量数4)同士による核融合の結果として生まれているので、質量数はだいたい4の倍数である、というのは、なるほど、だった。炭素12、酸素16、ケイ素28、硫黄32、カルシウム40、鉄56、銅64、とか。
20投稿日: 2024.01.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ他の方もかかれてるように、マニア向けです。 歴史上の製鉄法を分かりやすく解説してくれる一冊かと思いきや、分かりやすくない!図が少ないし分かりにくい…。既に製鉄に精通したマニア以外はまず言葉から装置を想像することもできず、置いてきぼりになります。
2投稿日: 2023.12.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の頃から製鉄にかなり興味を持っていたという工学博士による本。多くの製鉄の方法やその歴史を掘り下げている。 学者らしく成分や製法についてかなり詳しく書かれており、工業系に興味を持つ人や製鉄マニアは楽しめそうだ。しかし私はなかなか興味が持てず、「科学研究のない古代からよくぞ製鉄技術があったものだ」と感心するにとどまってしまった。
1投稿日: 2022.11.12 powered by ブクログ
powered by ブクログhttps://elib.maruzen.co.jp/elib/html/BookDetail/Id/3000057445
0投稿日: 2022.09.05 powered by ブクログ
powered by ブクログカーボンニュートラルの理解を深める上で、二酸化炭素排出量の多い製鉄業、高炉メーカーによる水素還元鉄を勉強しようと思った。 鉄中の炭素濃度を高めると融点が下がり、より低い温度で製鉄する事ができて、リン濃度も低くなる。強く送風する事で脱炭が起こり、炭素濃度が下がってしまう。炉を高くして、浸炭領域を長くする事が重要。ブードワー反応による、一酸化炭素での還元。この過程で二酸化炭素が排出されるという事。 化学成分分析が出来なかった時代でも、理屈にあった物づくりが出来ていたという事実は面白い。何故、インドのデリーの鉄柱は錆びないのか。陰謀論のような話もあるが、原理を知る事が重要だ。
0投稿日: 2022.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ「グプタ朝期に建てられた鉄柱」とはデリーの鉄柱である。一般的にアショーカ・ピラーと呼ばれているようだが誤り。アショーカ王碑文が認(したた)められているのは摩崖・洞窟・石柱である。 https://sessendo.blogspot.com/2021/06/16004000.html
0投稿日: 2021.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ実際にたたら製鉄を文献調査や監察で止まらずに、再現実験で研究した著者によるものなので、文明が崩壊したあとになっても、この本があれば製鉄技術が回復できるのでは無いだろうか?というレベルの書籍。 実験データの部分を読み飛ばしても、製鉄の歴史について興味深く読めるし、実験データを(ある程度)読むことで、たたら製鉄の話が、現代の主流となっている製鉄法とは別の、CO2排出量を抑えた新たな製鉄法の提言(どこまで大規模にできるモノなのかはなかなかわからないが)に繋がっていく。
0投稿日: 2020.01.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ始めの10ページぐらいは読んだがそれ以上の気力がでなかった。 内容がかなり堅苦しいので、鉄について強い興味がある場合を除いて面白くは無いと思う。 さすがに炉の詳しい作り方には興味がないです。
0投稿日: 2019.05.25実験・フィールドワーク中心
タイトルの通り、歴史的な製鉄法(材料の入手も含む)中心の内容です。著者が実際に実験してみた内容やフィールドワークが充実しているのが特徴。反面、分子構造の変化などは文章での説明では分かりにくく、他の本と併せて読むのが良いかと。
0投稿日: 2017.09.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ冶金の専門家が手作りでたたら製鉄してみる、みたいな。ひどく繰り返しが多かったりの独特の文章(専門誌の連載記事が元記事らしい)。でも鉄をつくるというのは手間もかかるし文明の重要な部分だったのねえ。製鉄の具体的な部分というのは本当に専門家のしごと。
0投稿日: 2017.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ鋼、玉鋼、錬鉄、銑鉄、溶鉱炉、転炉、平炉、反射炉、たたら…… 古代から現代までの製鉄法と、その技術を探る。 人類が鉄を作り始めて4000年。「鉄」ほど人類の社会と文明に影響を与えた物質はない。温度計もない時代に、どのように鉄を作ったのだろうか? 「鉄鉱石を炉に入れ加熱すれば、鉄は自然にできてくる」とうわけではない。鉄鉱石から鉄を作るには、厳密に温度を管理し、含まれる炭素の量をコントロールし、リンやイオウなどの不純物が混ざらないようにしなければならない。温度計すらない時代から、鉄を作ってきた人々は、それらをどのように知り、何を目安に鉄を作ってきたのだろうか。 アナトリアの最古の製鉄から現代の製鉄法、さらに日本固有の「たたら製鉄」の技術を解説しながら、鉄づくりの秘密に迫る。
0投稿日: 2017.05.16
