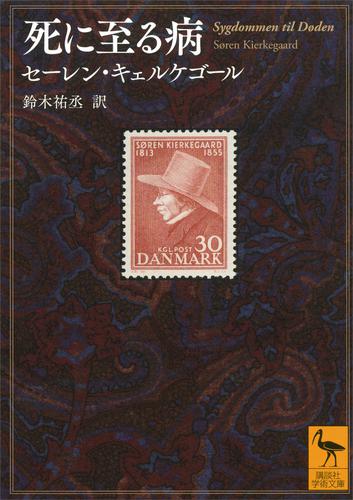
総合評価
(8件)| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ訳者解説を読むとわかる通り、キェルケゴールは信仰に生きた人で、理想的なキリスト教信仰の形を説いた人だ。 ここから読んだらもっと分かりやすかったはずなのに! 内容は、日本人には理解しにくい部分も多い。 全てを理解したとはとても言えないが、少なくとも、何かに絶望した人が読むための本ではないです。
0投稿日: 2025.11.27 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今の社会はこの病に冒されているのではないだろうか 死に至る病=絶望 絶望の3つの分類 無意識の絶望:自分が絶望していることに気づいていない。目先の快楽に流され、真に生きていない人 自分になりたくない絶望(逃避):自分の欠点・弱さを否定して逃避する。社会的成功で空虚を埋めようとする 自分になりたいがなれない絶望(闘争):本当の自己になろうとするが、神との関係を欠く。自力での克服に限界を感じている人
4投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログヤバいサイコパス小説。 シリアルキラーの恐ろしさの本質は物理的な残虐性ではないことがよくわかる。 どんでん返しとしてはそれほどの衝撃はない。
0投稿日: 2025.01.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ(精神的な)死に至る病である絶望・罪を治すため、理屈じゃなくキリスト教を信じよう、みたいな感じ。キリスト教に結び付けるところは、屁理屈でいいから説明してみてほしい。 訳は読みやすいと思います。
0投稿日: 2023.05.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ第1編 死に至る病とは絶望のことである(絶望が死に至る病であるということ この病(絶望)の普遍性 この病(絶望)の諸形態) 第2編 絶望は罪である(絶望は罪である 罪の継続)
0投稿日: 2021.07.13超難解
「死に至る病」とは絶望のことだが、徹頭徹尾何を言っているのか理解できなかった。日本語だから文章としては分かるが、何を訴えたいかは全く分からない。巻末に翻訳者による解説が付いているが、それを読んでもやっぱり分からない。 キリスト教徒として絶望とどう向き合うのか、ということなのだろうと想像される。だが、現代に生きるキリスト教徒が読んでも理解できる人は少ないのではないか。
0投稿日: 2020.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログセーレン・キェルケゴールによる、有名な哲学書。我孫子武丸の小説の由来になるなど、多くのところで用いられているため、誰もがタイトルだけでも聞いたことがあるだろう。内容は2部構成で、「第一編 死に至る病とは絶望のことである」「第二編 絶望は罪である」から成り、中でも前者が白眉で、まさにタイトルどおりの論旨が展開されている。絶望をめぐる考察についてはなかなか参考になる部分も多いのだが、しかしいかんせん著者があまりにもキリスト教に傾倒しすぎていて、クリスチャンでもなければ関聯する素養もなんら持ち合わせていないわたしとしては、なかなか受け容れがたい記述も頻出しており、そこまで傑作であるとも思えなかった。とくに「第二編」では異教徒に対する攻撃が激しい。しかし、絶望とキリスト教や神の存在は、本質的には関係がないはずで、キリスト教を別段信仰しているわけではないわたし自身も、あるいは無宗教の人が多い日本人でも、絶望することは珍しくないのである。そう考えると本作の記述は冒頭から信頼ができるかどうかがいよいよ怪しく、本作は哲学書ではなく単なる宗教書ではないかという思いも頭を擡げてくる。内容が難しく、読むことに難儀したわりには、異教徒に対する罵詈雑言なんぞを読まされて、正直ガッカリしてしまった。
0投稿日: 2019.06.04 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
絶望こそ死に至る病である。 現代においてもそれは同様だが、その“絶望”こそどこから訪れ、どこに存在しているのか。それを解説し、考察したキェルケゴールの本著作だが、最終的には似非キリスト教徒への糾弾と、本来あるべき信仰の姿を示唆する内容になっている。 それゆえか、キリスト教徒ではない人間からすると、いささか読み取りにくい部分が多く、前半こそ“絶望”に関する考察を深める良著だと感じられたものの、後半においては、本来手に取った目的(絶望とは何か、どこから訪れ、どう対処する“病”なのか)をかなえてくれるものではなかった。 あとがきにおいても、翻訳家がそれを認めており、またキェルケゴールの生涯や他の著作から、彼がどんな目的で本書を仕上げたのか解説してくれているので、彼にとって“絶望”とは“信仰”より対を成す形で、思索する対象であり彼が理想とする信仰への在り方のために必要だったかを補足してくれている。 “深淵を覗く時、深淵もまた見つめ返しているのだ”とはニーチェの言葉だったか。 その名言と同様に、“絶望”を考察するとき、絶望もまた考察者に絡みつくのだろう。 では、それにおいて思索をすることは全くの無駄であり、不必要であることなのか? しかし本著では、そういった意識がない人間であっても、絶望は生涯の友のよりもひっそりと寄り添っているのだと示している。 キリスト教的な部分は難解ではあったが、絶望から解き放たれるためには信仰が必要だということはわかった。 信仰、という言葉を使うと、なにやら厳しく重々しく宗教的になりがちだが、柔らかく表現するのであれば「信じる心」が必要ということだ。 何においてもでもいい。未来でも、自身の能力でも、他人への絆でも。それらを感じている時だけ、絶望は身を潜めて影に還る。 あるいは、現状絶望している状態であれば、絶望の信奉者だということだ。 彼等は決して姿を消すことなく、人生において常に見張り、虎視眈々と様子を伺っている。 人が想像するという力を失わない限り、彼らはそこに在る。それを認め、それに飲み込まれることのない、信仰する“何か”が必要なのだと、改めて考えさせられた。
2投稿日: 2018.05.19
