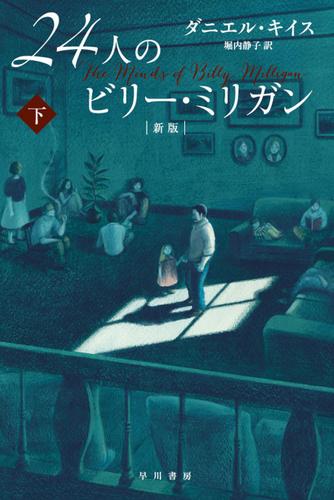
総合評価
(17件)| 6 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ被虐待児は全国でかなりの人数に上ると思うが、その中で解離性同一性障害を発症するのはどのような特徴を持った人間なのか。 ビリー・ミリガンは多才で知的にもかなり高かったようだけど、それも関係しているのか。 そもそも人格なんてものがあるのは人間だけで、その人格が分裂していることが良いこととも悪いこととも見なせない。最終的にミリガンが社会の中で生き、生活していけるのならば「共同経営」でも「個人経営」でも「会社組織」だろうと問題は無いと言ったドクターコールの見解にその通りだなと思った。 ミリガンは癌を患い亡くなったようだが、彼が晩年幸せな時間を少しでも多く過ごせたことを願ってやまない。
0投稿日: 2025.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログノンフィクションということだが、出来事が実際にあったのかもしれないが作者によってかなり脚色された内容に感じた。 出てくる人物が、友人から医師や弁護士、収容所の人物など数え切れない。特に、病院はいくつか場所を転々とする中で、医者と看護師の名前をいちいち述べるので、とても読みにくかった。 面白かった部分は、犯罪を起こしてしまったが多重人格によって無罪となる所だ。それによる社会復帰と世間の目、無罪となっても上手くいかずにもがくビリーはリアルに描かれていたように思う。(この部分は、下巻の最後の100ページくらいだったと思う。) 上下巻に分かれているが、もっとコンパクトに読みやすくできた内容のはずだ。
0投稿日: 2025.07.20 powered by ブクログ
powered by ブクログこんな症状になるまで、幼児期に虐待されるなんて、本当に気の毒だ。物語が終わった後の、日本の精神科医の方のお話を読んで、さらに、悲しくなった。
0投稿日: 2024.05.29 powered by ブクログ
powered by ブクログさて、読了。 上巻と違い★3なのは、前半若干冗長だったから。 ダニエル・キイスがこの本を執筆した動機は、ビリー・ミリガンが望んだからであり、おそらくは、キイス自身も世間に伝えるべきだ、と考えたから。 それを考えると、その冗長さは必要なものなのだろう。 私はと言えば、一読者として読むだけなので、このずれは致し方ないのだと思う。 問題の最中にいる生きている人間についての本のため、読み終わっても、”終わった”という安堵感はない。続編もあるので、気になる人は手に取れば良いと思う。 私はおそらく読まないが。 なぜなら、ある時代の(あるいは現在もそうなのかもしれないが)精神疾患への偏見や公然と行われる人権侵害は十分わかったし、ドキュメンタリーであるが故に、続きにすっきりするハッピーエンドが待っているとは思えないからだ。 同じもやもやが続き、もしかすると何か救いはあるのかもしれないが、それは情報として知ることができるレベルのもので、読み物としてのドラマティックな展開はおそらくない。 しかしながら人間というのはいつになったら大人になるのだろう。 罪を犯した人間は迫害しても良いのか。 レイプ犯は正義の名のもとに殺すことは正当化されるのか。 精神疾患を持った人間は人間扱いされなくても当然なのか。 罪悪感を全く感じずに、寧ろ自分は正しいことをしているのだと信じて、他人を迫害することができる人間がいることに驚く。 ビリーは罪を犯したが、罪を償なわなければならないことは人間扱いされない理由にはならない。 そういう意味では、世界が抱える様々な問題の一端を示す意味で、本書は有益だと思う。
0投稿日: 2023.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公はレイプ犯として逮捕されるが、自分は多重人格だという訴えは無罪になるための演技ではなく、彼も壮絶な過去を大変な思いで乗りこえてきた人だった。当事者と家族、彼を信じる治療者と疑う治療者、社会の人々の気持ちの揺れが、痛いほど伝わってくる本。 個人的には、本に一瞬出てくる作業療法士が、彼個人としっかり向き合い寄り添う援助者として描かれてるのが、嬉しかった。
0投稿日: 2022.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
辛い現実を前に、人格を分散させることによって心を保ち、命を守る。そんなこともある人間の精神や脳の不思議。一人ひとりの人格はビリーが生み出したもののはずなのに、統合されていくと一部の人格だけしか表れなかったりする。 じゃあ、本当のビリーって?? そんな問いは、場面によって顔を使い分けることにも重なるようで。友人と過ごす自分、家族と過ごす自分、恋人と過ごす自分、一人で過ごす自分。どれも現実で本物なのに、本当の自分に悩んだりする。もしも、これらが統合されて一つの顔しか持てないのなら、どの自分が残るんだろうか、なんて。 ー現実の世界を閉めだすことによって、ぼくたちは自分たちの世界で平和に暮らせます。 ぼくたちは、苦痛のない世界は感情のない世界だと知っています……でも、感情のない世界は、苦痛のない世界なんです。 ビリーの中の子どもの人格を見るたびに切なくなる。犯罪者の人権問題も考える。
0投稿日: 2022.05.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ多重人格者が出てくるドラマをずっと以前に見たことがあるし、そういうことが実際にあることは知っていても、読みながらやはりとても驚きました。 特に人格が入れ替わったり人格同士がやりとりしたりする場面の描写のリアルさがすごい。それをしっかりと認識して医師や「作家」など周囲に伝えられた本人(の中の複数の人格たち)の知力や表現力には目をみはるものがあります。 事件を起こし、あらゆる施設を転々とさせられる(もしくは閉じ込められる)、ビリーや、ビリーを支える人たちの姿を、読者はおそらく完全に彼らの側から捉えるでしょう。でも、多重人格そのものが知られていなくて、詐病だと誰もが思うような状況では、私もおそらく「あんな事件を起こした犯人を施設の外に出すな」と思ってしまうだろうな、と感じました。 理解されないことの辛さや悔しさは想像を絶するものがあったでしょう。 大事なエピソードを読み飛ばしていそうだし、時系列が曖昧になっていたりもしそうで、一度で理解するのは私には難しかったかもしれません。 またいつか読み返します。
7投稿日: 2021.12.18 powered by ブクログ
powered by ブクログかつて〈モンスター〉として描かれてきた多重人格者を、〈モンスター〉の側から書くことで理解を深めた記念すべきノンフィクションの傑作。連続レイプ犯として逮捕されたビリーミリガンには犯行の記憶がなかった。ビリーの症状、24人の人格との対話、生い立ち、裁判の様子など非常に興味深く描かれる。虐待が生み出したと思われる多重人格。しかし犯罪者の人格も彼の一部であり、それが一人の人格であるなら文句なしに罰される罪を犯している。そしてどれも彼の人格なのだ。その中から一人格を正しいと決めて集約させようとすることは治療なのか、矯正なのか。また犯罪を犯すほどではない多重人格者はどうしているのだろう。問題視されなければ個性でしかないのか。普通に生活してるのだろうか。判断はシャッフルされるが、ビリーのような患者に同情は覚えつつも犯罪を犯してしまえば被害者への同情を優先したい。そんなことを頭の中でぐるぐる考え続けさせられる。
0投稿日: 2021.04.05 powered by ブクログ
powered by ブクログこれが実話であり、他にも精神分裂病苦しんている人々がいることは真実であると考える他ない。 幼少の頃の虐待によることが要因であるならばこのような事象を広く世間に認知され、虐待のない世の中になることを願う。虐待する側も病んでいるのだろうし、病が伝染すると考えさせられる。 ビリーの場合、主人格を乗っ取る交代人格による性犯罪で窮地に陥るが、その犯罪履歴を持つものが身近にいるのは確かに恐ろしいし、隔離しておくべきとの主張もよくわかるので難しい問題である。 その犯罪、フィリップが主犯であろうが、レイゲンの暴走による所が大きいと感じた。 多国語を読み書きできる人格がいるのも驚き。自分の脳にも強いきっかけがほしいものである。 上巻では多重人格というものに憧れすら覚えたが、下巻の悲惨な状況に閉口。多重人格という病気が正しく認知され、治療法が確立されることを願う。
0投稿日: 2020.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ原書名:THE MINDS OF BILLY MILLIGAN 著者:ダニエル・キイス(Keyes, Daniel, 1927-2014、アメリカ・ニューヨーク市、作家) 訳者:堀内静子(1941-、翻訳家)
0投稿日: 2018.10.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ下巻に関しては、恐らく書きたい事例が多すぎ、かえって消化不良を起こしているように感じられる。ノンフィクションであるので、客観的な事実を列記するというよりは、内面の描写が多く途中から創作なのか良くわからなくなった。 問題は多重人格者をどう更生させるかももちろんながら、幼い頃の虐待・暴力がその人格形成の大きな影響をきたすことを社会がよく理解したうえで、コミュニケーションをとっていかないといけないのだろうと感じる。
1投稿日: 2018.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
子供の頃テレビで見て、彼についてなんとなくは知っていた。今でも内容が頭を離れず、ようやく読むことができた。 解説にもあったが、多重人格は親からの虐待に起因することが多いらしい。ビリーの場合は、継父からの性的虐待、実父の死によるショック、母親からの激しい叱責などが原因で、自分を守るために人格が分裂していった。怪力のレイゲン(スラブ訛り)、愛を渇望するアラダナ(レズビアン)、知的能力の高いアーサー(イギリス上流階級訛り)、全ての苦痛を引き受けるデイヴィッド(幼児)などなど。それぞれが全く異なる人格やバックグラウンドを持っているのも驚きだし、リーダーを作って人格をコントロールしていたというのも衝撃だった。 ある人格がビリーになっている間は他の人格の記憶がなくなるため、ビリーの混乱は激しく、例えば気づいたらアメリカにいたはずがロンドンにいたり、苦手な科目のテストで満点をとったり、何より覚えのない罪に問われ苦悩する姿が読んでいて辛い。 法廷に立つにあたり精神科医が人格の統合に尽力、成功したものの、社会からの冷遇によりまた分裂する。統合と分裂を繰り返し、人に裏切られ、彼を救おうとする人も周囲からの嫌がらせや家族との亀裂が生じ、苦しむこととなる。 あまりに過酷だが、読むことができて良かった。
1投稿日: 2017.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ主人公に据えられているはずなのに、徐々にビリーにうんざりしてしまったのはなぜだろうか。自分の望まないことを回避するように統合と分裂を無意識にコントロールしているのでは?とか、自分が性根では善人なのだと喧伝したいがための正当化なのでは?という気がしてくる。 作中の作家は中立であるように描かれていると思うが、一方で、実際のキイスはビリーに心を寄せていたのではないかとも感じた。 そう感じたのに、ビリーに対して上記のような感想を覚えたのが少し不思議だったけれど、それがこの作品の妙なのかもしれず、また最後の方はストーリーが一進一退だから、そのためかなとも思う。
0投稿日: 2017.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ教師という人格が登場し回復の兆しを見せているのに、偏見などによるマスコミの煽りに遭い、必要な治療もままならならず、症状も悪化するのは残念だった。 ふと思ったのだが、人格の統合=回復としてもいいのだろうか? ビリーの頭の中では全員が会話することができていたのだし、それさえできていれば無理やり統合しなくてもいいような気がした。 それでも、後書き?の部分の他の多重人格の症例を読んでいると、彼は良い方に好転したケースのように思えた。 ビリー自身は2014年に生涯を閉じたが、彼の晩年が幸福なものであればいいと思った。
0投稿日: 2017.02.19 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ずっと読んでみたいと思っていたが、手を出すのが怖かった本。やっと読み終わった。下巻は人格の入れ替わりが激しく、本来の「ビリー」が少なく感じる。実際も、1/24しか生きてないのかな。。 幼少期の悲惨な記憶がもたらした信じがたい事実。☆4を付けたが、あまりにも辛すぎて読後感は良くない。
4投稿日: 2016.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ24人もの人間をビリーとして人格を統合していくことの、なんと難しいことか。 イギリスアクセントの英語、ボストン訛り、オーストラリアの英語、セルボ・クロアチア語を読み、物理・科学・医学・電気・武器に詳しく、絵など‥多才の才能をもち合わせ、それがバラバラの人間の中では発揮できても、統合していくにつれて、その能力が薄められていく不思議さ。 自分の知らない自分を引き出す、俳優・女優のような職業もある様に、本当の自分を分かっていないのかも知れない。 行った事のない、住んだことのない地域の言語まで習得できてしまったその能力とは、心の傷とは裏腹に、その異常にまで発達したその能力に、現代だったら、また違った評価が出てきたのだろうと思う。
1投稿日: 2016.02.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ[長文です]24人のビリー・ミリガン読了。 彼が多重人格だったのか、それを装っていたのか、実際の彼に会えなかったわたしには想像もつきませんが、 ひとつ言えることは、彼は実際は非常に頭の良い人間であったこと(Arthurを見れば分かりますね)、 そしてチャーマーに関する話が本当であれ嘘であれ、悲惨な(miserable)幼少期を送っていたということ。 親が死ぬ、離婚する、そういった経験を幼少期にした時、親に聞かれれば、子どもは"わたしは大丈夫"というに決まっています(それなりに分別のある子どもならば)。 頭が良くて思いやりのある子どもほどそういった反応を取りがちですが、心の奥では寂しさを必死に抑えています。 会いたくないほど嫌い、という気持ちと、寂しい、という気持ちはきっと両立します。当然ながら子どもは大人ではありません。それを上手く発散できずに、心に闇を抱えたままになってしまう子どもも多いでしょう。 きっと頭の良い子どもほど、そうやって闇を抱えがちです。親を悲しませまいとするために、かえって自分を傷付けます。 親が亡くなるのは不可抗力でしょう。離婚だってそうです。しかしながら、ひとつ考えていただきたい、"平気ね、大丈夫ね"という一言が、お互いの知らず知らずの内に、子どもの心へ傷を付けていることを。 うん、とは言いますが、平気ではありません。平気な振りをしているだけです。 周りにそんな立場に立たされた子どもがもしいたならば、遊び相手でも話し相手でもいい、ほんの少し目をかけてあげて下さい。そのほんの少しは、子どもにとって大きなものです。 ビリーもキイス氏も、既にこの世の人ではありません(ふたりとも昨年逝去しております)。素敵なお話をくれたふたりに思いを馳せましてこの文の結びとさせていただきます。
0投稿日: 2015.07.19
