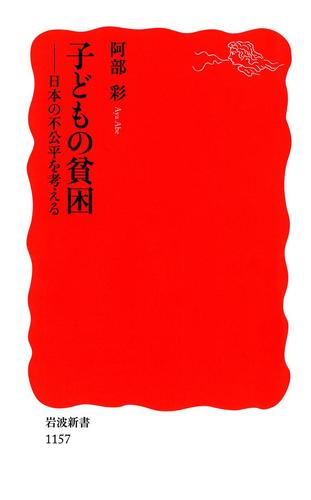
総合評価
(79件)| 17 | ||
| 33 | ||
| 15 | ||
| 0 | ||
| 1 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ刊行から15年経っていますが、多くのことを考えさせられる1冊です。一方で、15年経っても、国で行われている子ども政策の議論の内容は残念ながらあまり変わっていないように思われてなりません。 著者が最後に記しているように、「子どもの数を増やすだけではなく、幸せな子どもの数を増やすことを目標とする政策」をぜひ議論してもらいたいと思います。 親の貧困や学歴が子どもたちに大きく影響していることをデータで示されるとやはり大きなインパクトがあります。 子どもたちのスタートライン格差を少しでも縮め、希望を持って暮らせる国になってほしいなぁと思わずにはいられません。 ※15年経っているので、現在のデータをいろいろと知りたい気持ちはとても出てきます。
2投稿日: 2023.02.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧困関係の本を15冊、阿部彩さんの他の著作も読んだことがあったのですが、まだ知らないことがありました。 投資論、良い親論、モデル論、ストレス論、学歴下降回避メカニズム、文化的再生産論、福祉依存文化論、大衆教育社会論、相対的剥奪、ディーセントジョブなどを自分の言葉で説明するとなると、少し戸惑うという方は読んでみてもいいかもしれません。 人によっては物足りないのかも?
0投稿日: 2022.06.28 powered by ブクログ
powered by ブクログデータが多いので理解するのに時間がかかる。 入門書としては重いかな。 データではっきり見たい人にはおすすめ。
0投稿日: 2022.04.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本でも貧困で苦しんでいる人がいることを実感させられました。 母子世帯だけでなく父子世帯でも貧困があるという事実を重く受けとめ、母親が働けるようにするだけでは貧困は解決せず、子供に直接援助がいくようにしなければならないと主張していました。 母子世帯の母親に対してのアンケートで書かれていた切実な思いや不安には胸が痛くなりました。 この本が出版されたのは2008年なので、当時とはまた状況は変わってきていると思います。 この本の続きが2014年に出版されているので読みたいと思います。
0投稿日: 2021.10.04 powered by ブクログ
powered by ブクログさまざまな調査の結果をもとに、貧困、中でも子どもの貧困に絞っておりわかりやすかった。所得の再配分が行われているはずの制度がむしろ貧困を増やしている、という数値は、いかに今の制度が子育て家庭に厳しいものかがわかる。ただ、子どもを持たない現役世代も多い中で、子どもの貧困の切実さや重要性が広まり、政策に反映されるまでは長い道のりがあるとも感じる。
0投稿日: 2021.06.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の貧困の原因と、日本の対応策の問題点とを、統計・調査に基づいて明らかにしている。事実の羅列的で少し退屈感もあるが、日本の子供の貧困がかなり深刻であることがよくわかる一冊。
0投稿日: 2021.06.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧困と格差は異なる。貧困撲滅を求めることは、完全平等主義を追求することではない。貧困はそのことを社会として許すべきではないと言う基準。価値判断である。機会の平等という比較の理念ではなく、子どもの権利の理念に基づく考え方である。 すべての親は「温かい家庭」を築こうとするのであろうが、親の年収によって子育ての環境は大きく異なっているのである。 晩産化が進んでいる。貧乏人の子沢山は少数派 子どもの貧困率は、親が中規模以上の企業に勤める常用雇用の場合のみ少ない 二人の就業世帯であっても、子どもの貧困率は10.6%。母親の就労が貧困率の削減にほとんど役に立っていないと言える。 0歳から2歳の乳幼児のこども、多子世帯、若い父親を持つこども、母子世帯の子どもの貧困率が高い 日本は家族関連(児童手当、児童扶養手当、現物給付等)の社会支出が、他の国と比べても相対的に低い傾向がある 児童手当もイギリス・フランスと比べても支出が少ない。社会保障も緩やかな逆進性を孕んでいるので、再分配後所得の貧困率が再分配前所得の貧困率を上回ってしまっている。 母子世帯の平均年齢は40歳 17人に1人が母子世帯に育っている 独立母子世帯と同居母子世帯がある 希望格差が生まれている。 子供の幸福度(ウェルビーイング) ヘッドスタートの調査によると、乳幼児期(0〜5歳)の貧困が、ほかの年齢の子ども期の貧困よりも、将来の子供の成長に一番影響を与える
0投稿日: 2020.08.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
★内容★ ・後日追記 ★学んだこと★ ・もう一回ちゃんと読みたい。逆機能の部分が衝撃的である。 ★もっと知りたいこと★ ・所得の再分配、逆機能について
0投稿日: 2019.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもを持って、色々と恩恵を受ける場面もあるにはあるんだけど、課税や社会保障費用の負担についてはちょっともニョルところもあったりなかったり。10年以上前の本ではあるけど、根本的なところはあまり変わっていないかな、とも思う。他国との比較を見るとやっぱりちょっと、微妙な心持ちになってしまうなぁ…。続編もあるようなので、そちらも読みたい。
0投稿日: 2019.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み終えた上での、再配分に対する自分の考え 「成人するまでの機会の平等を担保するために、貧困世帯のこどもには機会への平等なアクセス権(無償化、学習支援など)、親には必要な額の支援(あくまで機会の平等のため)が必要である」 努力不足によって所得に格差が生まれることに問題はない。ただ、それでも結果として貧困になった個人には、最低限のセーフティーネット(生活保障)と、努力次第で再起できる機会(職業訓練 / 教育機関での学び直し)は与えるべき。また、その所得格差が次の世代の子どもにまで連鎖するのであれば、それは生まれた時点で差がつくため、機会の平等が保たれているとは言えない。 よって、連鎖が生まれない、また、生まれた家庭環境・地域・国籍にかかわらず、こどもの機会の平等が保たれるためには、貧困・低資本世帯のこどもと、親への支援が必要である。 親への支援に関しては、こども機会の平等に必要な金額以上の支援は、正当に努力して高所得を獲得した世帯との不平等が生じてしまうため、あくまで「➀こどもの機会の平等を保つため」、「➁競争に敗れたとはいえ、人として最低限の生活を送るため」の2つの目的達成のためにのみ行われるべき。 理屈はこうだが、高所得者の人が「理屈は理解できるけど、自分は頑張ってその結果としてお金を手にしたのに、頑張ってもない人に再分配したくない」というのはすごくよくわかる。ここをどう解決するか。(親ではなく、こどもに再分配する、再分配によって努力しようとしているか、継続監視する→マイクロファイナンス?) こどもの機会の平等のためには、「家庭内の治安の改善と介入システム」、「公的教育機関の教育の質」、「私的教育機関の無償化」、「労働人口増加」あたりが鍵になりそう。 いかに1人1人の国民と経営者が格差問題を、 ・「自己責任」の一言で片付けず、 ・こどもとその生活環境や文化資本の差に目を向け、 ・払っている税金など、”一部”ではなく、”全体”のお金の流れを意識でき、 ・貧困家庭のこどもの不平等に共感→同感でき、 ・共感している人たちが、このシステム実現のための実行力を持てるか、 が最大の焦点。 ーーーーーー 感想 低所得者への再配分は、「努力が足りないだけ」という自己責任論に行きがちだが、「そもそも貧困家庭に生まれた時点で、教育へのアクセスや家庭環境等で、ディスアドバンテージがある」・「金銭面だけでなく、家庭環境や学力による低い自己効力感」など、こどもの自己コントロールでは管理しきれない影響がたしかにあるために、自己責任論は適切ではなく、きちんと社会全体で支援をするべきである、という論がとてもしっくりきた。 機会の平等には、2つの条件がある。1つは「公平な競争」で、もう1つは、「だれでも頭がよく生まれる確率が等しくあり」、「生まれつきの遺伝子ではなく、後天的な学習と自由意志によって、だれでも頑張れば」それなりの業績をあげれるという前提。 しかし、貧困家庭のこどもは、頑張らなくて学力が低いのではなく、生まれた環境のために自己肯定感、自己効力感が低く、努力できていない。これは、前提に立っていない。そのため、支援を受ける権利がある。 こどもの貧困を解決するためには、親への金銭的な支援も必要になるが、それは機会の平等という観点で難しいなと感じた。貧困家庭に生まれたとか、障害があるとかだったら理解されそうだが、単に努力不足で収入が低い場合、支援の正当性やインセンティブ設計をどう担保するのか。
1投稿日: 2019.07.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ格差、本人の素質の違い、社会は平等ではないのが当たり前、などと混同されることも多いですが、子どもの貧困は社会が許容すべきでない生活水準のことである、とはっきり言って、いろいろなデータを示して、今後の政策に何が必要かを述べています。2008年に出た本ですが、10年たった今、当時と比べてどれくらいよくなっただろう、、と残念な気持ちになりました。
0投稿日: 2019.05.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ終始データに基づく話。 親の年収や学歴との相関など、わりと知ってる内容が多いが、データを用いているので、具体的。
0投稿日: 2019.02.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本は昔から「子どもに寛容で優しい国」であったはずなのに老人だけが権利を主張して得をする国になってしまった。 日本の子どもの貧困について豊富なデータで説明し非常に説得力がある本。 「相対的剥脱」「貧相な貧困感」「保育所は子ども達の最初の防波堤」「意欲の格差」「希望の格差」 など勉強になった。
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ「こども手当て」はどの現状に対するどの程度の数値目標を掲げた政策かという視点での議論はそういえばあまり起こらなかった。この著書のようにデータで社会を視る視点での「子ども」「若年層」の考察がもっと世の中に広まって欲しい。でないとスーパー高齢化社会の日本で誰が子どもを育てるのだ?
0投稿日: 2018.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「少子化大臣」よりも「子ども大臣」の設置。この言葉が、ストレートで分かりやすかった。直接、子どもの貧困に焦点を当てた対策の急務。離婚率増加、母子家庭の増大、養育費を踏み倒す元夫や養育を支払えない元夫の現実、母子家庭における母親のダブルワークやリーセントワークの問題。
0投稿日: 2018.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこどもの貧困について書いた本。 格差と貧困の違いや、親の、特に一人親家庭の経済状況とこどもの貧困について、が前半で、 それに対する政策について、が後半。 前半が私の知りたいことでした。 ちょっと前の本なので、紹介されている政策などが現状は更新があるかもしれない。
0投稿日: 2018.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の体験してきたことがようやく日の目を浴びたような気がした。 そして、日本全体が子供の貧困に対してどれだけ無関心であるかを思い知り落胆もした。 クリスマスなんてなくても生きてはいける。誕生日を祝われなくても生きてはいける。でも普通の人みたいにまっすぐ素直な人間になることはできなくなる。本著でも触れられていたが、相対的に貧困をはかろうとしたその試みは大変画期的だった。
0投稿日: 2017.06.23 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
2008年刊行。◆国立社会保障・人口問題研究所勤務の著者が、子供の貧困(相対的貧困)を身近な問題と捉え、その実像と処方箋を解説する。◆本書からは、日本人はできるだけ多くの子供に対し、高度な教育を費用をかけて与えようとは考えていないことがわかる(第6章。教育の私事性)。◇第2に、日本は先進18国の中で唯一、再分配前所得に基づく貧困率よりも再分配後所得のそれが上がる国。社会保険・税制により貧困率を悪化させるのだ。まして社会保険料は一部定額主義で、ゆるい逆進構造である。こんな制度で誰が安心して暮らせるだろう? なお、本書で示されているが、離婚後の養育費について公的徴収の制度は、先進諸国に習い早期に整備する必要がある。
0投稿日: 2017.01.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分以外の家庭の事情はなかなか見えにくいので、衝撃を受けた箇所が多々ありました。相対的貧困がキーワードかな。
0投稿日: 2015.07.04 powered by ブクログ
powered by ブクログとてもよく整理されて書かれていて、読みやすく、そしてぐっと迫ってくる内容だった。 この筆者の本はもっと読んでみたいと思った。 大人が、「子どもにとって最低限必要だと思うこと」が、日本では非常に厳しいという話が印象的だった。 確かに自分にもそういうところがあるかもしれない。 某野球少年の話とか、某おそばの話とか、「貧しいけど頑張る」的な、そういう話に慣れ親しみすぎているのかもしれない。 具体的に対処案も挙げられていて、きちんと対処されれば効果が上がっていくはずだという希望も感じながら、しかしこの書籍が書かれてからしばらく経つのにさらに大きな課題となってきている現状に、焦燥も感じる。
0投稿日: 2015.05.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの貧困について、客観的なデータをもとに論じられている一冊。 2008年に出版されている本なので、データはやや古いですが、わかりやすく整理されているため、基本的なポイントを押さえるのにとても助かる内容でした。 子どもの貧困と、学力、健康、家庭環境、非行、虐待の関係が、データとともに示されています。 大人たちが「子どもにとって最低限必要だと思うこと」の調査で、学習の機会や医療保障についての項目が私の予想よりもはるかに数値が低かったことに驚きました。 日本の大人が子どもを見る目の厳しさ、、それくらいは仕方ない、我慢すべきだ、とする姿勢に、調査に答えられた方ご自身の辛さの経験や生活の余裕のなさを想像しました。 経済的な問題、社会保障についても、もっと勉強しなくてはと思いました。
0投稿日: 2015.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「子どもの貧困」という言葉を、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。OECDが2006年に報じたところによれば、2000年の時点で、日本の子どもの相対的貧困率は14%であったといいます。同時に、この数値が、OECD諸国の平均に比べても高いこと、母子世帯の貧困率が突出して高いことが指摘されました。これは、大きな衝撃を持って受け止められ、日本の報道でも多く報じられました。 本書は、このような「子どもの貧困」について、数量的なデータをもとに、その実態を分析した良書です。中でも、これまで日本においてあまり焦点の当たることのなかった、「母子世帯における貧困の実態」を、データを用いて実証的に示した点に、功績があると言えます。 ところで、「貧困」と聞くと、モノが溢れていて、みんなが義務教育を受けることができている今の日本には、全く関係のないことのように思うかもしれませんし、今日の日本において、それがどのような状態を指すのか、イメージしにくいところがあるかもしれません。本書では、そのようなともすれば曖昧になってしまう「貧困」という概念を、データを用いて定義し、なぜ貧困であることが問題となるのか(貧困研究の問題の所在)、生活のなかで貧困はどのように現れているのか(貧困の実態)、子どもの貧困にたいして政策の観点からどのような対策を講じていけばよいのか(貧困への対策)について論じています。 新書でありながら、ボリュームたっぷりの内容で、一読の価値アリです。本書を通じて、「子どもの貧困」が、決してごく一部の特殊な現象ではなく、すべての人の身近にある問題だと気づいてもらえたらと思います。 (ラーニング・アドバイザー/教育 SAKAI) ▼筑波大学附属図書館の所蔵情報はこちら http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=1333240
0投稿日: 2014.11.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ母子家庭の貧困というニュースを目にする機会が増えてきたので、興味をもって手に取った。この本が書かれたのは2008年、どれだけ自分の目が開いていなかったのかがよくわかる。少子化対策がさらに取り沙汰されるようになったが、それ以前に子供の貧困は許容できないものであり、撲滅しなければならない。 この本は精緻に貧困の定義の測り方、日本と世界の比較から語る。そして日本の政策、母子家庭の経済状況、学歴社会における貧困の不利をデータで示す。さらに、子供の必需品とはなにかもデータで示すことで、より具体的な貧困の姿を目に見えるようにしてくれる。 この子供の必需品とは何か、で明らかになる世間の認識がまたすごいものだ。世間的に50%以上が必需品と考えるものが与えられていない状態を剥奪された状態として、貧困の具体的な姿を描くものとしてアプローチした結果、日本ではそもそも子供の必需品として考えるものが少なすぎるのだ。おもちゃも誕生日のお祝いもクリスマスプレゼントも、大学までの教育も、お古でない靴や文房具も、一年に一回遊園地や動物園に行くことも、与えられなくても仕方がないと認識されているのだ。なんて悲しい社会なんだろう。そんな子供の姿をしょうがないとして許容することはあり得ないと思う。
0投稿日: 2014.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ学生時代の読み残し。 まだまだ多くの人にとっては想像しにくい世界であろう「子どもの貧困」について、日本の現状を解説する本。 データが豊富で、丁寧に解説してくれているのでこの分野について興味をもった方が最初に手に取るにはとても良いと思います。 「総中流」の幻想からはだんだん解き放たれつつあるように感じる昨今ですが、 それでも貧困というものに対するイメージ自体まだまだ貧しいですよね。 日本政府が(というか自民党が)、そもそも視点として子どもの貧困対策というものを持ってこなかったというのは確かだろうけど、その背景にあるのは何よりも社会全体の意識の低さ。 ある程度は日々感じていたところではあるけれど、第6章で示される、厳しすぎる貧困観には正直悲しくなる。 ただ、これは子どもとか、貧困といったテーマに限った問題ではないですね。 人権意識というものがあまりに貧相な社会、日本。 「剥奪状態(deprivation)」という概念がまったく理解できない人が多すぎる。 今後日本では否が応でも相対的な貧困は増加傾向を辿っていくので、 社会的な合意基準は作って行きやすくはなるんだろうか。 それでも、政権担当者だけに任せていて進展していく分野だとは思えないので、 福祉、教育業界、関連のNPO業界などからの継続的な働きかけが必須でしょう。
1投稿日: 2014.07.10 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
長い間「一億総中流」という意識を持っていたために「貧困」に対する想像力が欠如した。その結果、対策が非常に遅れている。特に子供については貧困との関連付けがタブー視されてきた経緯があり、親の自己責任論で片付けられてしまうことが多かった。そのため「子ども」を中心とした政策が必要である、という内容。 社会学系の文章はあまり読み慣れていないせいもあって、言っている内容が難しいなぁと思うことが多かった。また、統計学の知識をある程度は使う(中央値など)ので、そのあたりも必要なのかな?一番ショックだったのは第6章で、「金銭的に余裕がなければ、……は子供に与えられなくてもよい」という項目が、海外と比べて日本は低い傾向にあること。一概に比較はできないにしても、貧困に対する想像力が貧困なのかなぁ、と感じる結果だった。とはいえ、自分が同じアンケートを受けたら、どう答えるのだろうか不安ではある。
0投稿日: 2014.04.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ確実に貧困があることがわかったということと、 子供に関する社会的必需品については、あったほうがいいと思うが、与えられなくてもよい、与えられなくても仕方がないと考える人の割合が多いのに驚いた。
0投稿日: 2014.03.16 powered by ブクログ
powered by ブクログアメリカが酷いという認識はあったが、日本もここまで酷いとは、データは雄弁だ。貧困の概念も初めて本書で深まった。社会福祉士として恥ずかしい。 ・非行と貧困 ・15歳時の貧困と現在の低い生活水準の直接的な相関 ・日本では母親の収入が貧困率の削減にほとんど役に立っていない。 ・日本よりアメリカの方が家族政策に予算をつぎ込んでいる。 ・教育支出も日本は最低。 ・日本は唯一、再分配後の所得の貧困率の方が、再分配前よりも高い。 ・日本の母子世帯はワーキングプア ・女性の貧困経験と学歴 ・乳幼児期の貧困が、一番将来に影響がある。 ・日本の一般の意識は大幅に低い。子どもの必需品調査から。 ・所得にはある一定の閾値がある。400万くらい
0投稿日: 2014.02.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「少子化対策」ではなくて、「子ども対策」を。言葉だけの問題かもしれないが、まさしくその通りだと思う。そして、なぜ高校などで、将来自分が子どもができた時の子育ての勉強がないんだろう。本当に大事なことは、学校では教えてくれず、個人任せになっている。地域の関わりが希薄化している以上、周りが教えてくれるではなく、教育内容としてやっていく必要があるように思う。
0投稿日: 2013.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
親の貧困は、子どもの人生にも不利を背負わせてしまう。しかし、その不利を仕方ないと容認することはできないというのが著者の立場です。 貧困とは、一言でいえば普通の生活が出来ないということです。絶対的・相対的貧困という考え方もありますが、これらの考え方よりも貧困を具体的に想像しやすくするための指標として、6章では相対的剥奪という考え方が紹介されています。 そして、子どもの貧困に陥りやすいリスクをもっとも抱えているのが、ひとり親世帯だといえるでしょう(ただ、これはひとり親世帯にだけ支援すればいいという話ではない)。生活保護や母子家庭への給付については、「働く気になればそれなりの生活はできるだろう」とか「離婚したのは自分の選択だろう」というような自己責任的な考え方があるわけですが、3章で政策的な視点から、そして4章で母子世帯の実情という細かい視点から貧困の問題をみてみると、そういう給付が、彼らの自立にはほとんど機能していないということがわかります。 つぎに、税・社会保障制度の逆機能。これは驚くべきことです。なぜなら、税などを負担することによって貧困状態にあると認められる人が増加したということだからです。所得を公平に近づけるための制度が、まさに逆方向に機能しているということです。いまでも、逆機能はないにせよ再分配の問題は続いていますね。 結局のところ、うえで書いた「働く気になれば・・・」というような自己責任的な考え方は、政策にもあったのではないかと思います。経済的に自立できる収入を得て、子どもは保育所などに預けられればいい、と。 しかし、親の貧困によって子どもがこうむる不利は色々な側面があるわけですね。健康、家庭環境、親のストレス、子育て時間の不足、学習意欲など、いろいろな視点を見据えたうえで、より多くの子どもが安定した家庭で幸福に生きられるように、政策として支援すべきではないか、支援しないことは、結果として社会の損失につながるのではないか・・・という問題があります。 それと同時に僕がこの本からあらためて考えたことは、政策には「結果」をみる視点が必要なのだということです。どれだけの予算を使ってどんな政策を実施したかというだけでは不十分です。たとえば、「母子家庭への金銭的な給付がどれだけ受給者の自立に役に立ったのか?」。著者のいう、「薄く広い」生活保護もそうです。結果をみずに、予算上の問題から給付対象を狭めたりすることに対して、受給している人から反発が出るのは、それなりの理由があるのだろうとあらためて考えました。
2投稿日: 2013.08.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧しい子どもはそうでない子どもに比べ「不利」な立場にある。子ども期に貧困であることの不利は大人になってからも持続し、さらに次の世代へと受け継がれる。親の収入は、様々な経路を通して、子どもの成長に影響している。すべての子どもに最低限の生活を与えることと、格差を縮小しようと努力することが必要である。 第1章 貧困世帯に育つということ 1.1 なぜ貧困であることは問題なのか 1.2 貧困の連鎖 1.3 貧困世帯で育つということ 1.4 政策課題としての子どもの貧困 第2章 子どもの貧困を測る 2.1 子どもの貧困の定義 2.2 日本の子どもの貧困率は高いのか 2.3 貧乏なのはどのような子どもか 2.4 日本の子どもの貧困の状況 第3章 だれのための政策か――政府の対策を検証する 3.1 国際的にお粗末な日本の政策の現状 3.2 子ども対策のメニュー 3.3 子どもの貧困率の逆転現象 3.4 「逆機能」の解消に向けて 第4章 追い詰められる母子世帯の子ども 4.1 母子世帯の経済状況 4.2 母子世帯における子どもの育ち 4.3 母子世帯に対する公的支援――政策は何を行ってきたのか 4.4 「母子世帯対策」でなく「子ども対策」を 第5章 学歴社会と子どもの貧困 5.1 学歴社会のなかで 5.2 「意識の格差」 5.3 義務教育再考 5.4 「最低限保障されるべき教育」の実現のために 第6章 子どもにとっての「必需品」を考える 6.1 すべての子どもに与えられるべきもの 6.2 子どもの剥奪状態 6.3 貧相な貧困観 第7章 「子ども対策」にむけて 7.1 子どもの幸福を政策課題に 7.2 子どもの貧困ゼロ社会への11のステップ 7.3 いつくかの処方箋 7.4 「少子化対策」でなく「子ども対策」を
0投稿日: 2013.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ子どもの貧困について基本的なデータを用いながらインタビューも入れてとてもよく調べている本である。日本の教育について論文を書くためには欠かせない本であろう。
0投稿日: 2013.03.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の子供の貧困について。統計データをもとに子供の相対的貧困について記述。今自分ができることを考えさせられる本
0投稿日: 2013.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の貧困の現状について、多くの人が納得できるデータを作りたい。それが、私の研究テーマである。(p246) という言葉を裏切らない本。 社会や子供や貧困の問題は色々とあるけれど、この本で扱うのは「子供」の「貧困」ですよときっちり線を引いて、データと論理をしっかり使って説明していく。 ・子供時代の貧困は、学歴・仕事・健康・結婚などその後の人生に大きな影を及ぼす。 ・日本における子供の貧困率は、貧困自体もさることながら政策によって悪化している。 ・控除や税金を加味すると貧困率が悪化する。 ・母親が働いても大した額にならないから二人で働いても父親が一人で働くのと大して変わらない。 ・高校を無料化しても、それ以前でこぼれてしまう子供を救えない。 貧困でも成功する人もいる・幸せな家庭もある、というのは問題じゃない。 貧困家庭に生まれるか、そうでない家庭に生まれるかで人生の選択肢や可能性に大きな偏りがでてしまうことが問題。 ここでもまた「語られない」という問題がでてきた。 「子供が健全に育つために不可欠なもの」だと一般人が認識する水準の日本と外国(主に欧米)の差がある。 だから子供が受け取れないものがたくさんあっても、大した問題じゃないと思われて議論の対象にならない。 『切りとられた時』http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4900590355にあった「疎開児童に必要だとされるもの」の差が未だに縮んでない。 そんな世論を背景に、政府はOECDに注意されても意に介さないし調べもしない。 "「格差社会」は急速に子どもの生活をまきこんできている。与党や政府は、子どもの貧困率の上昇を今までの政策への批判と受け止めずに、新しいチャレンジとして真っ向から立ち向かうべきであり、野党は、これを政府批判の材料とすべきではない。日本の政府に求められているのは、この変化に敏感に反応する姿勢である。せめて、この変化をモニターできるようなしくみを構築する必要がある。"(p221) この部分で目からうろこが落ちたというか腑に落ちた。 ずっと同じ政権だと、「これじゃダメだから変えよう!」っていうのは「諸先輩方への批判」になっちゃうのか。 で、批判も現状への批判じゃなくて「お前らがちゃんとしないから!」になっちゃうのか。 「報道災害」http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4344982223にあった、反対意見と人格否定を区別できない(批判される側もする側も)というやつか。 「世界の貧困と社会保障」http://booklog.jp/users/melancholidea/archives/1/4750336378で、北欧の高税高福祉に反対意見が少ないのは、北欧人が素晴らしい人たちだからじゃなくてみんなが恩恵を受けているからだとあった。 子供には教育、大人には住居や仕事、老人には年金、みんなに医療…みんな自分も世話になるから「あいつらばっかりずるい!」にはならないと。 「子供の貧困」にはピンポイントで子供の貧困を解決しようとあるけれど、子供の貧困をどうにかするには親(保護者)が貧困じゃなければいいんだから、男女ともにまともに生活していけるようにするのが抜本的な解決だともある。 一番なんとかすべきは「あいつらばっかり!」が「俺にもおくれ」ではなく「やつらを優遇するな」になってしまうメンタリティなんだろうな。 この本が出たのは2008年。子供の貧困が話題になったけれど、「流行りのテーマ」というだけで終わってしまうことを著者は懸念している。 で、今。生活保護への攻撃を筆頭に、状況は悪化している。
0投稿日: 2013.01.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の子どもでいられることの幸せと不幸な面を何となく感じてはいたけど、数値と様々なグラフで表される「子どもの貧困」のまぎれもない現実を見た。 原因としては経済状況の悪化もあるし、離婚後の母子家庭の生活境遇の困難もあり、一概に子どもの貧困の解決を提示できるものでもないと感じた。 ただそこに、政府としてできることがたくさんあり、これまでは政府は少子化対策としての育児手当を支給してきたが、子どもの貧困を減らすための方向性が間違っており、少子化対策ではなく、あくまでも子どもの貧困をなくすための子ども対策が必要であることを、本書から学ぶことができた。 よって今後の政治の舵取りと政策のいかんによっては、子ども対策も良い方向へ向かっていく可能性もあり、我々国民もどうあるべきかを考えることが大切であると思った。
0投稿日: 2012.09.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本では、何が「子どもの貧困」をもたらし、何が問題なのか、どのような対策をとるべきか、について書かれた本。図表を多く挿入して、解説を加えています。 第1章では、15歳時点の暮らし向きがその後の生活水準に影響を与えていることを示しています。子ども期の貧困は、その時点での学力や生活の質などへの影響に留まらず、大人になってからの就労状況などに影響を及ぼして。更に、その「不利」が次の世代(子)にも受け継がれていくことを述べています。 第2章では、「相対的貧困」について説明し、世帯タイプ別の貧困率、年齢別の貧困率を提示しています。特に心配されるのが、乳幼児の貧困率の増加です。低年齢での貧困が、子どもの健康やその後の成長に、大きく影響するからです。 第3章では、国際比較を通して、日本の政策を検証しています。税制度や社会保障制度には「所得再分配」の働きがあり、通常、その前後で貧困率が軽減されるのですが、日本は、先進諸国のなかで唯一、制度があるために、子どもの貧困率が悪化しています。「負担」と「給付」が、高所得層に優しく、低所得層に厳しい制度になっていると考えられます。 第4章は、子どもの貧困率が特に高い母子家庭の現状について書かれています。母子家庭では、働いて収入があるにもかかわらず生活保護を必要とする低所得層が多いことなどが問題となっています。そして、低所得であることは、第1章で提起された問題へとつながるわけです。また、女性の「ワーク・ライフ・バランス」が保障されないことは、女性の貧困問題でもあります。 第5章では、貧困層の子どもが低学歴であるのは、高校や大学の授業料が払えないから、ということだけではないといっています。貧困層の子どもは、意欲を失い、努力しなくなっているという、子どもの意識の差が生じていることをデータで示しています。学校や家庭環境、家族の意識などが、子どもの学習意欲に影響を及ぼしていることは明らかです。高卒でさえ、ワーキング・プアになってしまう現状にあって、就学前から支援する施策が必要になっているといえます。 第6章では、「相対的剥奪」という概念が紹介し、この相対的剥奪概念と「合意基準アプローチ」によって、子どもにとっての「社会的必需項目」を選び出しています。その各項目の支持率を調査して、どのような世帯の子どもが、「社会的必需項目」の欠如を強いられているか(必要であると支持され、本人も希望しているのに、家庭の事情などで与えられない状態)を示しているのですが、きわめて水準の低い最低生活が浮かび上がってきます。 第7章では、イギリスのマニフェストを参考にした「日本版子どもの貧困ゼロ社会へのステップ」という提言が示されています。
2投稿日: 2012.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ貧困問題を抱える多くの層の中から子供に焦点を絞り、まとめられた一冊。 資料が豊富、論理的な流れで読みやすい。
0投稿日: 2012.06.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ少子化対策ではなく子ども対策が重要。 子どもの数を増やすだけではなく、幸せな子どもの数を増やす対策が必要と著者は言う。 貧困は教育の機会を奪い、それが就業の機会を奪ってしまう。 そうやって貧困の連鎖が続いていく。 子どもは社会の財産だという認識の下、すべての子どもが享受すべき最低限の生活と教育を社会が保障するようにならなくてはならない。 OECD加盟国の中で唯一日本が再分配後所得のほうが貧困率が増加する国、というのが非常に衝撃的。
0投稿日: 2012.05.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ再分配後の方が、前よりも貧困率が上がっているなんて全く知らなかった。 このバカげた不条理な状態を、国民は知らなければいけないし、子どもから金を頂いている国はもっと公表するべきだ。 私の場合、平成生まれの母子家庭育ちという、(といっても中学を卒業してから親が離婚しているので、まだ恵まれてるが)この本で書かれている当事者に近い立場なので、内容はとてもリアルに入ってきた。幼い頃から、衣食住にそんなに困る事もなく、物理的にはほとんど何も、不自由ない暮らしをしていた。教育もきちんと受けてきたし、絶対的貧困とは無縁の生活だ。実際に親や教師に、昔の日本と比べても、また今現在でも世界中で見ればかなり恵まれてる側なんだから、むしろ今の立場に感謝しなさい。苦労知らずのガキがちょっとした事ですぐに文句言ってきやがって、これだからゆとり世代は全く俺達の時代の頃はもっと今よりもっと今よりもっと今より(ry とか言われて育ってきたし、ついこの間までそれを言われても何も言い返せなく、一理あるなとも思っていた。高校の時から最新のケータイを持っているし、映画とか音楽とかもネットでタダで観たり聴いたりしてるし、図書館で本もタダで借りられるし、大多数の人が通う公立の学校で小中高と均一な教育も受けてきた。牛丼も安くで食える。この様に金がなくても結構快適な生活ができるインフラは整ってる。しかも日本は世界的にも格差が比較的小さい国だから、今いる階級からのジャンプも何だかんだいって難しくない様に感じる。(しかし、そのハンデ自体当然許してはいけないというのが本書の主張だ) 交流でいっても同世代なら、大体同じものを見て感じて育ってきているので会話に齟齬が生まれる事はあまりないと思うし、またSNSとかのコミュニケーションツールがかなり充実してるので、一人一人がつながっている距離もずっと近い。 しかし、だからこそ、相対的貧困をずっと近くに、よりリアルに感じる事になるんだと思う。皆同じ様に全裸のカッコで、一部の限られた豪族の馬鹿でかい古墳を作るのを手伝わされるという事よりも、隣の家が毎晩食卓を囲んで夕食を過ごしているという事の方が、とても生々しく格差を感じられる。 何度も言うが、ものに溢れて生きている現代人は、物理的には困っていない。でもその事によって自己責任論を展開し、精神的な部分をないがしろにするのは、やはり鈍いし無責任だと思う。めぐりめぐって富裕層にも影響が出るのだ。社会の為に人があるんじゃなく人の為に社会があるべきだ。人が生まれることと、また生まれた場所と時代を選べない以上やはり無視できない問題だと思う。
0投稿日: 2012.03.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ母子家庭でしかもワーキングプアに陥っている世帯が多いことはショッキングです。 僕は子育ての経験がありますが(0~5歳)、お金がかかるのもありますが、それ以上に『一緒にいる時間』を大事にしていたので、それはそれは大変です(笑)ノイローゼになるのも頷けます。 お金で解決するのって、簡単なんですよね。だから僕はあまり好きじゃないんですが、それよりも、労力(時間)を提供することの方が尊くて、子育てもお金をかければ良いというわけではなくて、子どもの両親が一緒に過ごしたり遊んだり、スキンシップをとったり、子どもにとっても、そっちの方が喜びます。 ですから、母子家庭に必要なのは、所得の向上もさることながら、『子育てする時間』も確保しなければなりません。お金は代わりがききますが、子どもにとって、親というのは基本的に代替が不可能です。 政府支出にみる教育費の国際比較で、どの国よりも日本は支出が低いというのは知っていましたし、この現状を打開しなければと思いますが、ではどこから財源を持ってくるのかが問題で、広い視点から判断しなければならないと思います。また、『他国に比べて日本は~』云々を言い出したら、それはもう日本ではなくなるし、社会背景や歴史・文化的要因が各国によって置かれている状況・立場が違うので、何でもかんでも『教育費の公的支出を欧米並みに』とか言い出したら、『煙草税も欧米並みに』、『消費税も欧米並みに』『法人税も欧米並みに』となり、高齢社会には対応できなくなります。乱暴な議論だけは避けてほしいです。 本書は所謂『ゴネ得』で子どもの貧困に警鐘を鳴らしているのではなく、あくまで冷静に日本の悪しき現状を直視して論じているので好感が持てます。 子どもと言わず、大人も貧困なんですよね。自分が貧困だから未来に投資できない。そうなると、必然的にこれから生まれてくるであろう命にまで負担を強いることになります。負の遺産の継承は何としても避けなければなりません。 子どもが暮らしやすい、子ども主体の社会にすることは、ともすると「大人は子どものための奴隷になれ」と社会で強制しているのでは?と疑問を抱かざるを得ません。自分の人生は自分のもであるはずだし、子どものために大人が犠牲になるのは納得(国民的合意)が得られるでしょうか?僕は、これにプラスして、「もっと多様なライフスタイルを認めるべき」だと思います。フリーターはダメ、ニートはダメ、というようなレッテルを貼るのではなく、そういった人たちを受け入れる社会の寛容さ、そしてすべての人の生活水準が向上するように、社会の構造や認識が変わっていくことを強く望みます。 怠け者が野放しになるのは問題ですが、全体の割合でみるとそう高くはないと思うので、さしあたっては、生活保護の不正受給による厳しい目や上記のフリーターやニートへの偏見を改善していくことが先決です。 これを通じて僕が言いたいことは、「選択の自由を確保すべき」ということです。自己責任論の強い風潮には賛同できませんし、そもそも格差の継承や海藻の固定化が組織の循環を滞らせている現状が大いににあります。大学まで進学すれば多様な仕事を選べる、しかし、中卒では仕事の選択肢が限られている、というような、機会の平等をもっと確保し、そして失敗しても再チャレンジ可能な社会につくりかえていく。そんな社会が理想だと思います。 「子どもの貧困」を考える時、それは子どもだけに限定されず、僕を含むすべての日本人に関わる問題です。政府はこのことをもっと真摯に受け止めて議論を深めてほしいと思います。 感想が支離滅裂ですが、色々と考えさせられる、内容の詰まった良書中の良書なので、僕の評価はSにします。
0投稿日: 2012.03.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ(「BOOK」データベースより) 健康、学力、そして将来…。大人になっても続く、人生のスタートラインにおける「不利」。OECD諸国の中で第二位という日本の貧困の現実を前に、子どもの貧困の定義、測定方法、そして、さまざまな「不利」と貧困の関係を、豊富なデータをもとに検証する。貧困の世代間連鎖を断つために本当に必要な「子ども対策」とは何か。
0投稿日: 2012.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログTFJが向き合っている子どもたちの状況について、客観的なデータを用いながら概観することができます。 ============================= 【著者「阿部彩」の紹介】 貧困研究の第一人者として活躍。 国立社会保障・人口問題研究所に所属。 研究テーマ: 貧困、社会的排除、社会保障、公的扶助 【本が与えた影響】 2000年代に入り様々な貧困や格差研究がされてきた。研究対象は成人が中心であったが、子どもの貧困に焦点をあてた研究は少なかった。(数ある貧困の中の1つとして取り上げることはあった) 発行後、子どもの貧困を取り上げた本が多く出版されるようになった。 【内容】 ・絶対的貧困と相対的貧困があり、日本に置ける貧困研究は相対的貧困を定義する ・貧困によって、子どもの生育環境がきまる。それにともない、機会の損失、可能性の制約が起こる。 ・高齢者・若年層の社会保障だけでなく子どもの社会保障(教育)にも目を向ける必要がある。 ・広い視野で見ると、日本社会全体の機能不全に原因がある。議論し尽くせない問題である。 ※上記の【内容】は以下2つの章を中心に記載 第4章追いつめられる母子世帯の子ども 第5章学歴社会と子どもの貧困
0投稿日: 2012.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ思いもよらないほどに日本の貧困度の高い事を知っておどろく 自分の視野の狭さがこれほどに実態を見損ねている無関心さに愕然とする 目の前に見えることでアップアップとなり 身の回りの事以外は見たくも触れたくもないのだろうか 先進国の動向と逆行している事に付いてもこれほどに身勝手な 縄張り根性が染み付いているとは思いもよらなかった 日本はいまだに後進国の意識を引きずったままで 明治以来の成り上がりのヤクザ稼業から成長できていないようだ 特に母子家庭のイジメラレ方は尋常でない 法律を初め職場や地域社会で目の敵のようにイジメの対象にして 恥ずかしげも無く搾取をむさぼっている 法律的にも行政的にも司法においてもいちじるしい憲法違反だし 各国との比較においてもはなはだしい格差であり ビジョンの方向性すらソッポを向いて逃げている この事をOECD2005年のデーターで見ると 誤魔化しで格差を広げてうそぶいていることが歴然としている これは当然ながら母子家庭においても同じ状態で 弱い者イジメの典型なのだろう 「逆機能」と言う言葉を生んだ福祉対策と絡めた税制で 弱気をクジキ強気に媚びる大勢は 島国で濃縮された依存主義によって友食いしてきた民族のなれの果てなのだろうか ユニセフが2007年「子供のウェルビーイング=幸福度」を公表している 物の過不足・健康と安全・教育・家庭と人間関係・行動とリスク・主観的満足度 の六項目による国別調査を行っている それによるとオランダを筆頭とする北欧諸国が上位を占める中 イギリスが21位と最下位でアメリカが20位である 財政に苦しんでいるギリシャが13位で東欧のポーランドとチェコそれに続く 日本はデーターを出さず不参加であるけれど OECDによる貧困率で見るとイギリスと日本は並んでいるので 同じく最下位の部類になるだろう これに対して日本政府はこの調査を信頼できないし 改善もしていると言う見解を国会で述べ 調査することすらこばんでいると言う 見せ掛けのバラ蒔きはするけれど トータルとしてはジワジワト貧困率を上げる政策に偏っている それに引き換えイギリスではこの最下位を受けて 貧困撲滅のための10カ条を掲げて対応している その第一に、すべての政党が貧困撲滅政策を目標にする事 第二に、すべての政策に貧困に対する観点を盛り込む事とある OECD二〇〇五年・日本における母子家庭の就労率はスイスに次いで四位である それに引き換え同じデーターによる貧困率はトルコに次いで二位である まさに働けど働けど楽にならずどころかひどくなる一方である そのくせ少子化によって搾取の相手が減ることには神経を尖らし 子供を増やせと動揺して気をもんでいる 少子化対策でなく貧困対策こそが健全な環境を創る事に気付いていないらしい あるいは気付かない振りをしているようだ
0投稿日: 2011.12.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ1年以上積読状態だった本書をやっと読了した。 学校教育に携わる者として、本書をどう読むか。やはり教育に関する部分に関心を持つことになる。 初等中等教育は、とりわけ子供の生活の中で中心的な位置を占める。子供にとって居心地がよく、クラスの一員として認められた生活が送れるかどうか、という点でも格差が生じているという(P.17)。このことは教職員の意識と工夫次第で、学校種の違いを問わずに活用できるのではないか。 日本の子供の貧困率は約15%であり(P.53)、子供の貧困の不利(1章)をこのまま放置していくと、貧困大国のアメリカに迫ってしまうことになる。貧困率は、相対的貧困を数値化したもので、原因には、意識の格差、努力の格差、希望格差といった、子供間の格差があるという。また、貧困率が同じでもは、国によって具体的な生活状況は異なる。このことは、終章の結論で重要な示唆を与える論拠となる。(アフリカ諸国の貧困とは質が違う。) P.187の表6-1「子どもに関する社会的必需品」の中で、「希望すれば高校・専門学校までの教育」を、「希望する全ての子供に絶対に与えられるべきものである」の割合が61.5%で、「短大・大学」の場合は、42.8%と示している。P.210で筆者はこの数値の低さを指摘し、貧相な貧困観を改めるよう主張し章を閉じている。 これに対して、あえて、筆者の視点と違う解釈をしてみたい。トロウが提唱した高等教育の発展段階説によると、50%という進学率が、「マス」から「ユニバーサル」への高等教育の段階移行の指標とされる。この段階移行が、質保証コストと無関係でないことは、多くの大学人の日々の業務の中で感じているところだろう。仮に何らかの要因で、進学率が42.8%前後で推移していたら、今打ち出されている高等教育政策は、だいぶ趣が異なっていたはずと感じるのは私だけだろうか。どのレベルまで多様化した学生を受け入れることを求められるのか。今後も注視していきたい。 7章で、子どもの貧困ゼロ社会への11のステップの提案がある。 ①すべての政党が子どもの貧困撲滅を政策目標として掲げること ②すべての政策に貧困の観点を盛り込むこと ③児童手当や児童税額控除の額の見直し ④大人に対する所得保障 ⑤税額控除や各種の手当ての改革 ⑥教育必需品への完全なアクセスがあること ⑦すべての子どもが平等の支援を受けられること ⑧「より多くの就労」ではなく、「よりよい就労を」 ⑨無料かつ良質の普遍的な保育を提供すること ⑩不当に重い税金・保険料を軽減すること ⑪財源を社会全体が担うこと ⑥では、高校までの教育の必需品として認識するよう提唱している。大学・短大の件は特に終章では、ふれられていない。 上記の提案は、日ごろ意識している姿勢とは、だいぶ異なっている立場で展開されている、と感じる人も多いのではないか。 日ごろ見聞きする、今の日本の大学における市場化・競争的環境の醸成は、大学の個性という差を促進、少なくとも容認している気がしてならない。大学改革という名の差別化戦略を実行している。やはり高等教育と子供の福祉は、別に分けて考えた方がよさそうだ。その分、業務外で子供の貧困に対する行動を模索していきたい。
0投稿日: 2011.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ総中流幻想は過去のものになったとはいえ「選挙権を持たない」がゆえに社会から忘れられている日本の子どもの貧困に関する本です。 具体的な実例を挙げるのではなく、冷静にデータを積み上げて現状を分析しております。 政権交代前の2008年に書かれた本ですので、子ども手当も高校無償化もでてきませんが、社会保険料負担の逆進性や母子家庭に対する社会的偏見、高卒ではまともな仕事に就きにくくなっている現状を詳細に書いております。 貧困問題は得てして政治的に利用されたり、正義を振りかざす感情論に落ち込むことも多いのですが、この本は非常に冷静です。 子ども手当の引き下げと増税が決まった状況も踏まえ、改訂版を出して欲しい1冊です。
0投稿日: 2011.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ所得の再分配により貧困率が増加する国・日本。何故だ。 現行の「子ども手当」は意味があるのか。甚だ疑問である。給付つき税額控除の方が良いのではあるまいか。 今の日本は、社会的・経済的に見ても「上昇気流」はなく、ただ停滞感のみ漂っていて、いつか来るであろう破滅のときを回避しようと「先送り」をしているだけである。 未来の日本を支える子どもたちが、階層の固定化により希望をなくし、やむなく貧困の連鎖を生んでしまう。そのような社会にならないように、今のうちに子どもに優しい税制・社会保障制度を作っていくべきであると感じた。
0投稿日: 2011.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ今の高齢者世代は日本を支え盛り上げた自負があると思う。 時代が味方してくれた。努力はいつだって報われた。 だけど今はどうだ。 生まれおちた時代が悪いのか。運がなかったのか。 子どもたちが大人になる頃は…想像もしたくない。 子どもは国の宝だと思う。 そこに対する政策があまりにも手薄すぎる。 実態をもっと世間に訴え、意識改革が必要だと思う。
0投稿日: 2011.10.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ私が母子家庭であること、それがきっかけで行政や福祉に興味を持ったこと、それで進路を決定したこと……。 複雑な気持ちで、この本を読んでおりました。 貧困の基準ってなんでしょう。 「貧困」と聞くと、何となくあばら骨の浮いたアフリカの子供を思い浮かべます。 これは「絶対的貧困」なんですね。 そして先進国では、絶対的貧困が撲滅されたと仮定したうえで、その社会の中での「相対的貧困」を貧困問題を論じるうえでの「貧困」と定義するんですね。 で、貧困というのは「許容できないもの」がその定義。 その許容できない状態も国や状況、価値観によって異なるわけで。 う、まー…ケースバイケースですね。社会学は難しい。 この新書のすごいところは、データの豊富さ。 一番びっくりしたのは、アメリカの実験で、ビンボーな子供を10年、20年と継続してフォローし、どんな大人になっていくかということを調査したもの。 結果として貧困経験者は所得が上がらないことがわかるのですが……いや、研究だっていうのはわかるんだけれども、データをとり終わった後のその子は放置されてるんでしょうか、ね……。 その話の流れで、貧困が連鎖しているというデータが示されます。 生活保護世帯の25%が親の世代でも生活保護世帯(大阪府堺市)、母子家庭に限って言えば41%……。 筆者は、非正規雇用労働者の増加と、彼らが親になったらどんなに大変だろうかという予測を立てています。 経済界は、労働力不足になったら困ると政府に少子化対策を要請する一方、非正規雇用を増大している。この矛盾はいったいなんだ、とも指摘しています。 そして日本の児童手当は「薄く、広く」で、「少子化のために何かをしている」というパフォーマンスでしかないとも言っています。 そういえば以前、日本は高齢化社会だから、政府は高齢者の票を獲得するために老後重視の政策を立てている、そして若年層に対する手当は薄い、なんて誰かが書いていたような。 なんか、うーん……誰かが負担をしなきゃいけない、誰が得して誰が損をする、とかじゃなくて、みんなで社会を支えよう、みたいな視点になれるといいんですけれどもね。難しいですよね、うん。どうすればいいのかな。 で、「貧困者=給付金をもらっている=ズルい」なんて公式で語られることが多いのですが、実際はそうではない。 社会保険料や税金を引いて、所得の再配分をした結果、他国では貧困率が下がっているのに、日本ではむしろ増加している。 これは貰う分より、負担のほうが大きいからだ――そんなデータを見て、びっくりしました。 現役世帯が、苦しんでいる。 母子家庭の場合だと、それが顕著。 確かに日本の母子家庭の母親は、他国に比べて就業率が高く、労働に従事している時間も長い。 でもそれは、ワーキングプア状態なのだ。 ワーク・ライフ・バランスが取れていない。 もう働きすぎている母親たちに、これ以上働け、自立しろなんて酷だと思いました。 離婚であれ、死別であれ、子供は心に傷を負う、ケアが必要。 でも、それができていないのが今の社会。 「戦争中は大変だった。今の子供は恵まれている。贅沢だ」なんて論じゃなくて、その子供が、この社会において「貧困」であるということを認め、どうしていくかを考えなくてはならない。筆者はそう繰り返します。 あと、離婚の場合の母子家庭の話。 アメリカ、イギリス、スウェーデンでは、養育費の取り決めは税と同じように公的制度が整備されていて、6割の離婚夫婦が養育費の取り決めをしている。 全額未納者は2割のみ。6割は全額支払っている。……まずまずである。 でも、日本はその取決めまでの道のりが大変なうえ、払われなくっても仕方がない、養育費を徴収しにくいのが実情。 子どもには罪はないのに。何で。 読みながらずっとそう思っていました。 「総中流神話」「努力すれば報われる神話」そんな神話たちは崩壊。 でも、その神話が流布し、「負け組」「勝ち組」「上流」「下流」とゲーム感覚で言っているから、現状を直視しないから、変わらない。 やっぱり、大人になってもずっと勉強しなきゃいけないなと思いました。 現実の直視って大事。 PISA調査で明らかなように、中二の段階で学力や学問への意欲、階層によって差が出てきてしまっている以上、高校授業料無償化は意味をなさないのではないか、高校に行く前での学力格差をどうにかしなければならないとも述べていました。 やっぱりそのとき思ったのは、貧困から抜け出すルートが整備されていないんだなっていうこと。 子どもの段階で、本人の意思とは関係なく将来が決められてしまう。そんな社会があっていいはずなんてない。 別に、高等教育は全員が受ける必要はないと思います。行きたい人だけが行けばいい。でも、高等教育を望む人が受けられる、あるいは、受けなくても生きていける社会、一人一人の個性が生かせる社会。 そんな社会になったらいいなと思います。 最後に。 私は母子家庭ですが、離婚じゃなくて死別で、父が年金の掛け金を払っていてくれたおかげで遺族年金が出て、保険に入っていたおかげで高校までの学費はずいぶん助かっているので、こうして学校に通えているわけですが。 あらためて、自分の環境が恵まれていることを知りました。 (そりゃもちろん、母ともいろいろあるし、色々あるけれども……) 今生きていること、勉強したいことを学ぶことができること、いろんなことに感謝です。 もっと勉強して、いい大人になりたいです。
1投稿日: 2011.10.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は、主に日本の子どもの貧困についての現状を解説したものである。 本書は膨大な分析と社会調査アンケートから、子どもの貧困を明らかにしている。正直、この分析から得られる事実は衝撃的なものばかりと言わざるをえない。 最終章では、ここから得られた結果や、海外の事例をもとに政策提言も行っている。 筆者は低所得者の立場を重要視しているため、その価値観に合わない人もいるだろうし、政策提言も財政の問題に着目せず理想を描いているように見えなくもない。しかしながら日本の社会の一側面を見るという意味で、本書は有用なものに思われる。
0投稿日: 2011.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログえ?っと思う発言やデータもあるけど、基本的には日本の子どもを育てることに対する補助がどれだけ少ないかがわかる良書だと思います。 金銭的な問題だけじゃなく、子どものやる気や努力などの研究についても言及しているところが信頼おけました。 自分の中で今一度中身を整理しておきたいです。
0投稿日: 2011.07.05 powered by ブクログ
powered by ブクログいつのころからか、「格差」とか「貧困」という言葉がすっかり現代を象徴するようになってしまった。 この本はつまるところ、「大人になってからも不利」な影響を及ぼす子ども期の貧困について、統計を用いつつ説明するものである。 そして社会保障問題を研究する著者は、政策についての具体的な提案も用意している。 金銭面の悩みはつきものだが、ひとまず大学に通えていることは感謝しなければ、と思う。 ところで「社会保障と税の一体改革」は「いったい」どうなるのですか?
0投稿日: 2011.06.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
昨今貧困の問題が俎上に上ることが多いが、この本は貧しい家庭に生まれた子どもたちが健康、学力、意欲、将来の職業といった面で不利な状況に立たされていることを豊富なデータを用いて客観的に証明している。この問題は、親世代の不安とも直結しているので、少子化にもつながる危険性がある。 興味深かったのは、母子家庭だけでなく一人親世帯全般(母子家庭、父子家庭)への保障、貧困世帯への医療費、保険料などの全般的な見直し、無料で良質・普遍的な保育制度の確立、財源を社会全体が担うことである。単なる「少子化対策」ではなく「幸せな子どもを増やす」という「子ども政策」を打ち出すということ重要だということも本書で述べられている。 こうして見ると日本のセーフティネットは穴だらけだということを改めて考えさせられた。高度経済成長期の頃は年功序列制が生活を保障していたたが、国際競争の激化に伴う成果主義の普及して、保障が成り立たなくなった。かといって生活保護の対象拡大は財政難で難しい。 先日こんなニュースもあった。通説が正しいと証明された結果。 http://www.kanaloco.jp/kyodo/news/20090804010007221.html
0投稿日: 2011.06.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
[ 内容 ] 健康、学力、そして将来…。 大人になっても続く、人生のスタートラインにおける「不利」。 OECD諸国の中で第二位という日本の貧困の現実を前に、子どもの貧困の定義、測定方法、そして、さまざまな「不利」と貧困の関係を、豊富なデータをもとに検証する。 貧困の世代間連鎖を断つために本当に必要な「子ども対策」とは何か。 [ 目次 ] 第1章 貧困世帯に育つということ 第2章 子どもの貧困を測る 第3章 だれのための政策か?政府の対策を検証する 第4章 追いつめられる母子世帯の子ども 第5章 学歴社会と子どもの貧困 第6章 子どもにとっての「必需品」を考える 第7章 「子ども対策」に向けて [ POP ] [ おすすめ度 ] ☆☆☆☆☆☆☆ おすすめ度 ☆☆☆☆☆☆☆ 文章 ☆☆☆☆☆☆☆ ストーリー ☆☆☆☆☆☆☆ メッセージ性 ☆☆☆☆☆☆☆ 冒険性 ☆☆☆☆☆☆☆ 読後の個人的な満足度 共感度(空振り三振・一部・参った!) 読書の速度(時間がかかった・普通・一気に読んだ) [ 関連図書 ] [ 参考となる書評 ]
0投稿日: 2011.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ課題図書。主に、法の隙間におとされた(母子)家庭の子どもに焦点をあてた一冊で、データをもとに強い主張を繰り返してくる印象。
0投稿日: 2011.03.21 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
今となっては少し古い情報ではあるけど、 豊富なデータと分析で数々の驚きがあった。 そのなかでも、まず社会保障制度や税制度によって日本の子どもの貧困率は悪化しているということ。 現役世代から資金を集め、高齢世代に給付するという仕組みはどこの国も同じなのに、日本は子どもがいる貧困世帯に過度な負担をしいているということ。うーむ。 また「貧しくても幸せな家庭神話」によって、日本人の意識は子どもに与える必需品の支持が極めて低いということ。与えすぎも良くないけども、与えなくても大丈夫といった概念が根強いため、子どもの貧困に対する問題意識も低い。 よく給食費や税金の未納問題がテレビで流れるけれど、それを個人の責任問題として済ましてはいけないんだと。 恥ずかしながら私自身もそう思っていたので、この本を読んで沢山の気づきがあった。
0投稿日: 2011.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ「総中流社会」という幻想に惑わされ、貧困、特に子供のそれに目を背けてきた日本社会に対して警鐘を鳴らした一冊。様々なデータや研究を元に、子供の貧困の定義、測定方法、子供への影響、政府の貧困対策、そして理想の対策を検証している。新書とは思えない程濃い内容であるにも関わらず、理路整然としていてとても読み易かった。筆者の他の書籍も読んでみたい。
0投稿日: 2010.12.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本にも子どもの貧困が存在するという衝撃。 しかも所得の再分配を行う事で、貧困率が逆に高まるという弱者に厳しい社会保障。 生まれた世帯によって、生を受けたその瞬間から彼らの貧困人生はスタートしてしまう。 そんな現状を変えるために、筆者は常に「子どもにとっての幸せ」という視点から、国内外の非常に多彩で豊富なデータを基に論旨を展開する。 正直重く、疲れる内容ですが、日本人なら知っておくべき。
0投稿日: 2010.11.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者が、多彩なデータを武器として、子どもを貧困に陥れる「貧しくても幸せな家庭神話」に斬りかかっていく姿が見えるような気がした。また、「相対的貧困」をイメージしやすい前提として、議論を展開していく。
0投稿日: 2010.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の子どもの貧困。 ある程度は感じてはいたけど、数字的に見せられるとさらに身近に感じられた。 想像や仮説ではなく、これらは今の日本で起こっている現実なのだと。 俺は、機会の平等は100%実現できなくても、出来る限り実現するべきだと思う。 理由としては、最初から格差が決定的であれば、努力に対して希望を失う。 それは、本人の損失もあるが、社会ひいては日本国の損失であるといえる。 そう考えるのなら、それらに税金をあてがうことは正しいと個人的には思う。 (ただ、所得の再分配は行き過ぎてしまうと問題がある。バランスが大切) 再分配後のほうが子どもの貧困率が上昇するという現実。 税の徴収意義のひとつと考えられている「富の再分配」が機能していない。 おいおい、日本政府は何をやっているんだ?政治家は何をしている? 教育は国の行わなければならないもっとも重要な仕事のひとつである。 もっと国民は教育に関して目を向けなければいけない。 決定的な損失が目に見えてからでは遅い。今、取り組まなければならない。 文部科学省は、東大の中でも人気が低い省として知られていて、 霞ヶ関の中でも力が弱い(=予算がとれない)。そのため現状あまり期待が出来ない。 自分が考える教育制度について。 【目標】 機会の平等を最大限実現できるようにする。 実務的勉学に限り本人が望む教育を受けられるようにする。 教育に市場競争を持ち込み、教育力を高める。 子どもの貧困率を0%にする。 【アクション】 専門学校までは、国が全て補助をする。 予算が厳しいのであれば、一部は将来返還できるようにする。 奨学金については、誰しもが受け取れるようにする。 公立を無くす。全て私立とする。(基本的に非営利組織) 充実した教育を行っている学校に多少優先して補助をする。 このあたりは、フリードマンの『資本主義と自由』で書いてる内容(チケット制)にほぼ同意。 小学校を区域で区切ることを無くす。 競争を促すことにより、小学校の教育充実を目指す。 累進課税を強める。 政府の支出を限りなく抑え、教育に割り当てる。 ざっと考えたら、こんなところか。 教育・軍事・小さな政府作り。 これらを充実させることが今の日本の急務である。 一人一人が誇りに思える国を目指さなければならない。 それが、将来日本を支える子ども達の希望の1つになる。 もし、子ども達が希望を持つことが出来ないのなら、 それは社会の責任であり、その社会を作った我々の責任でもあるのだ。
0投稿日: 2010.08.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ我が国が、子どもの貧困大国であることの事実。子どもは国の将来を担う宝。 投資的に貧困の連鎖を断ち切らないと自分が今生きている意味もないのではなかろうか。
0投稿日: 2010.06.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ大学の先輩に薦められて読んだ本。その人は教育に関心があり、自ら行動を起こそうか悩まれている。 筆者本人が貧困についての納得のできるデータを示したいというように、データがとても充実しており、日本の子どもの貧困を語るのにはほとんど事欠かないだろう。 そのデータは多くの示唆に富む結果を示しており、特に日本人は、誰にでも与えられるべきと考えるものが海外に比べてとても少ないというのは印象的だった。 外国人と比べて最初から差が有って当然と考えているのかもしれない。そしてそれは足るを知るという意味では幸せに近い態度のような気がする。 しかし、だからといって貧困を放置して良いとは思わない。貧困削減は幸せのためではなく、機会の保障のためだと思う。不幸だと感じていないからといって機会の保障をしなくていいとは思わない。 ところが、1点だけ、そしてこれは貧困のかなり本質的な部分だが、気になるのは相対的貧困、それも日本国内におけるものはどれほどのイシューなのかという点だ。 日本国内では大きな政治的イシューになるのだと思うが、客観的に世界の問題は何か、という観点で捉えるとたいしたイシューでないように思える。 もちろん学力や貧困が階層によって固定化されるのは望ましくないのかもしれないが(これも逆の因果関係を主張する余地は依然としてあると思うが)、あくまで国内の基準に照らした話。 筆者の言うような全ての絶対的貧困が相対的貧困であるという主張は違うのではないかと思う。例えば基本的人権のような、そこには何らかの絶対的な基準を設けることは可能であるし、そうしないと解決すべき問題の優先順位が曖昧になってしまう。たとえ、その基準が時代によって変わることはあるとしても。 貧困の解消と機会の均等は全く別の議論であってしかるべきだろう。
0投稿日: 2010.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「格差」という言葉でしか語られない日本の貧困問題。 やっぱり総中流神話が浸透している日本社会では「貧困」という言葉は受け入れられにくいのかな。 私の友達の中には、「日本は豊かだからそんなに心配しなくていい、それより海外に目をむけなきゃ」という人が割と多いですが、日本の貧困問題ももはや目をそむけられない段階まできていると思います。 もちろん日本に存在する貧困の大部分は絶対的貧困ではなく相対的貧困やけど、だからといって見過ごせる問題ではない。(ここでは書かないけど、異なる社会同士を比べて片方を貧しいということに関しては限界がある) 機会の均等というのも神話でしかなく、アンダーグラフの言葉をかりれば「生まれたら既に勝ち組(負け組)」という状況が生まれてきている。 この本では様々なデータを元に、日本の子どもに対する社会保障の弱さを他のOECD諸国と比較しながら述べています。 一番衝撃的やったのは、日本においてはOECD諸国の中で唯一、政府による所得再分配前と再分配後では、分配後の方が貧困率が上昇しているという事実です。 つまり、貧困削減や所得格差の是正のためであるはずの日本の所得再分配は貧困・格差を助長しているのです。 これでは何のための政策なのかわからない。 子どもへの援助も「広く・浅く」しか与えられず、しかも親の雇用も不安定化している中で、今後子どもの貧困を削減していくには抜本的な福祉政策の改革が必要だと思われる。 そのために、もっと各政党は子どもの貧困問題に目を向けて欲しいし、そのためにも国民の意識も向上しなければいけない。 データ分析が多くて少々小難しい本やけど、広く読まれてほしいなと思う1冊でした。
0投稿日: 2010.04.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ途中で断念。データ的なものが多いけど、 やはり著者もいっているように(?)、 データから見えないものを見たい。
0投稿日: 2010.03.07 powered by ブクログ
powered by ブクログこれは非常によかった。読み応えアリ。考えさせられる内容が多かったというか、何を考えるべきなのかがよくわかった。「子ども手当」なんて、バラ撒いても駄目なんです。
0投稿日: 2010.03.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供は生まれてくる家を選べない、という点からして、すでに不幸。、貧困の連鎖は政策で断ち切らないと・・・という提言の本。著者の知性・慎ましさ・プロ根性が見える、いい本。
0投稿日: 2010.02.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の人生におけるスタートラインの不公平さについて考えさせられました。 スタートラインは違っても自分自身の努力で補えば、追い越せばそれでいいなどと考えていましたが、しかし、もし“未来すら望めない家庭環境”だったら? 「格差」や「機会の不平等」をいたしかたないものと放っておくのではなく、せめて努力である程度その差を縮められるようにしなければならないと思います 親のモラルと子供は関係がなく、子供に直接向けた政策が必要なのでしょう。
0投稿日: 2009.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は私の大学時代の恩師と同じアメリカのタフツ大学フレッチャー法律外交大学院で博士号を取得された後に国連に進んだ女性で、現在は国立社会保障・人口問題研究所の国際関係部第2室長をつとめられている方です。 引用されているデータの豊富さはこれまで読んできた新書の中でもずばぬけて多いと感じます。そのデータから読み取れる数値的な表層部分と、そのデータの奥にひそむ実際的深層の両方をうまくえぐり出すことにこの本は成功していると思います。昨今の格差をめぐる議論は聞き及んでいたもののそれが子どもという年少の世代にどのような影響を与えているかを知る機会のなかった私にとっては、現代日本の暗部にようやく光が当たったと感じさえしました。 一億総中流をばっさりと否定し、その名残で日本人が目をつむってきた「あるはずない」と考える多くの人に厳然たる貧困の存在を突きつけられます。しかし問題の所在を認めない限りは、生活に苦しみ人々を思った行動を起こすことなど出来る筈もありません。その意味ではこの本は人の前を醒まさせる強い薬とも言えるかもしれません。だからこそ世界水準からみた経済力を理由に立ち直れるとも思いがちなところに、「そんなまさか!」と思われる相対的貧困状態の「世代間連鎖」という衝撃的な言葉にも現実感が伴っています。 子どもの17人に1人は母子家庭で育つ、という自分が今まで知りえなかった事実にも目を大きくします。私には母子家庭に対して、10代結婚した後に離婚した若い母親と子供というイメージがありましたし、実際そのような方が仕事場にもいたことがありました。しかし、実際母子家庭の母親の平均年齢は40歳であり、それには晩産化が影響していることも知ることができました。そこに現在の労働市場の流動化や正規・非正規間の不平等な取り扱いや賃金格差の視点を持ち込めば状況の深刻さも理解しやすくなります。 日本では成り立っていない養育費の徴収については、多くの先進諸国で制度化されており、税金の支払と同様の感覚で養育費が支払われている事例も紹介されており、日本人自身に社会制度を支え合う意識の欠如を問うている一面も垣間見えます。給食費未払いの問題も一部の親をモンスターペアレントとして描き報じるメディアへの一方的な情報依存をただし、相対的貧困層がその支払いに苦慮する社会状況まで深堀りできる視点の必要性を説いています。 今月末にある総選挙でも子育てや生活支援は大きな柱です。しかし、著者は社会保障制度や税制度によってOECD諸国の中で日本だけが受給後に貧困率が上昇しているという反作用的調査結果を持ち出しています(P.96)。システム全体の再構築が要求されていることは確かです。少子高齢化を嘆いていても改善しないので冷静に事実を認めて、より弱者救済を社会成立の根幹とできるために知っておくべき情報がこの本には詰まっています。
0投稿日: 2009.08.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2009年7月6日読了) ・親の学力や職業によって子どもの学力に格差が生じている。P5 ・アメリカは全ての国民を対象とする公的健康保険制度が存在しない独特な国だが、低所得層の子どもに関しては州政府が無料の医療保険を提供している。アメリカもカナダも少なくとも子どもの医療のアクセスは平等になるように政府が努力している。P10 ・虐待を発生させてしまうような家庭の経済問題に目をつむってきたことにより、虐待を防止する本当に必要な手段が講じられてこなかった。P13 ・家庭の貧困は、子どもが非行に関わってしまう確立をも高める。P14 ・15歳時点での暮し向きは、その後の人生の人間関係の希薄さにも関係。「15歳時の貧困」→「限られた教育機会」→「恵まれない職」→「低所得」→「低い生活水準」P23 ・子ども期の貧困は、子どもが成長した後にも継続して影響を及ぼしている。P24 ・親の収入は多かれ少なかれ、子どもの成長に影響する。P33 ・子どもの基本的な成長にかかわる医療、基本的衣食住、クスなくとも義務教育、そしてほぼ普遍的になった高校教育(生活)のアクセスを、全てのの子どもが受けるべき。P37 ・今日においては、ある程度経済状況にゆとりがある世帯のみが2人目、3人目、4人目の子どもを持つ決断をすることができるかもしれない。P66 ・どこの国でも就業者が1人の世帯に比べ、2人世帯の貧困率は大幅に低いが、日本は2人就業世帯でも貧困率は10.6%と1人就業世帯に比べ、1.7%の減少しかない。P69 ・母子世帯に育つ子どもの生活レベルが低いのは他の先進諸国と同様だが、日本は「母親の就労率が非常に高いにも関わらず、経済状況が厳しく、政府や子どもの父親からの援助も少ない」P109 ・母子世帯の所得が低い第一の理由は、そもそも母子世帯の母親を含めた全労働女性の就労条件が悪化していること。P113 ・離婚母子家庭においては子どもの父親からのり送り(養育費)は子どもの養育には非常に重要だが、養育費の取り決めをしているのは全体の1/3であり、取り決めをしても仕送りが続くかどうかはまた別の問題。実際に19%の母子世帯しか受け取っていない。P117 ・育児に手間のかかる6歳未満の子どもを育てながら働いている母子世帯は平日の平均仕事時間は431分、育児時間は46分しかない。共働きの母親は、113分。P120 ・母子世帯の経済状況は、母子世帯になった当初に比べると、所得については横ばい、または微増になるが、その後は特に教育費など子どもに関わる経費の増加によって苦しくなっている。P139 ・所得保証や就労支援に関しては、「母子世帯対策」を廃止し、代わりにその子どもが属する世帯のタイプに関係なく行われる「子ども対策」を立ち上げる必要がある。主目的は子どもの貧困の撲滅と適切なケアの確保。P141 ・「学歴がモノをいい、やり直しが困難な社会では『学校』『学歴』『親』『友人』を欠いた彼らが、自立して安定した生活を送れるような職につくことは難しいのが実情」P150 ・参考「階層化日本と教育危機」、「希望格差社会」P151 ・「意欲」を示す指標として「落第しない程度の成績を取っていれば良いと思う」という質問の回答が近年上昇傾向にあり、97年には社会階層が下位とされた生徒の半数以上が「落第しなければよい」と考えており、上位生徒の3割を大きく上回っている。P155 ・「与えられた方が望ましいが・・・」という消極的な意見も含めると高等専門学校、大学・短大まで含め高等教育の無償化は大多数の人が支持している。P172 ・文化の違いはあるものの他の先進諸国と比べると日本の一般市民の子どもの必需品への支持率は大幅の低い。 ・ある一定の所得以下になると、剥奪の度合いが急激に増える。所得には「閾値」がありそれを超えて所得が落ちると生活が坂道を転がっていくように困窮に陥る。P202 ・母子世帯の母親の多くが、子どもに「みじめな思いをさせたくない」として、自分自身が「がまん」する傾向にある。P208 ・子どもの基本的な物品的充足が満たされていなかったり、健康と安全が脅かされている中で、高い教育の達成は困難であろうし、よい教育がない中で、子ども自身が満足した生活を送る事もまた困難。P214 ・人口が減少しつつある日本の重点戦略は、労働人口の増加と出生率の増加。育児中の女性・男性や高齢者を労働市場に参加させ、そして将来の労働力としての子どもを増やす。P218 ・現在の戦略からは、何とか子どもを高校・大学に行かせようと2つ、3つの非正規雇用を掛け持ちして頑張っている母子世帯の母親が、せめて平日5時以降は帰宅し子どもと一緒に夕食を食べながらゆっくり過ごせるように支援しようだとか、貧困世帯の子どもが大学の費用の心配をすることなく勉強にいそしめるようにしようという配慮は見受けられない。P218 ・現役世代の中でも、子どもを育てていたり、貧困率を下回る生活をしている世帯に対してはせめて、負担が給付を上回ることがないように、税制、公的年金、公的医療保険、介護保険、生活保護をむくめた全ての社会保障制度で考慮すべき。P222 ・子どもに対する現金給付をどのような対象の子どもに与えるべきか、どのような方法を用いるべきか、という問題は別として、まずその額について今一度検討する必要がある。P223 ・政策の対象を「世帯」から「子ども」に移し、子どものある世帯に対する政策を一本化した「子ども対策」を打ち出し、全ての子どものウェル・ビーイングを向上するという理念を訴えたい。P226 ・国民年金・国民健康保険の未納問題も保育料や就学費の滞納と同じく、個人の責任論が主流。保険料の取立ての強化や資産の差し押さえといった政策ばかりが注目を浴びているが、多くの研究では、世帯所得の低さや、失業問題にあることが未納の主要因である事を報告している。P232 ・先進諸国の税制による優遇措置では、貧困世帯や多子世帯など、よりターゲットを絞った制度が導入されている。中でも子どもの貧困に対して有効なのが、「給付つきの税額控除」。これは払うべき税金の額そのものを減額する制度。P235 ・子どもの数を増やすだけでなく、幸せな子どもの数を増やすことを目標にする政策が必要。特に全ての子どもがうけるべき最低限の生活と教育を社会が保証するべき。P243、P244 ・ ・
0投稿日: 2009.07.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ統計学的な本でした。 日本の政策が、いかに「スタート時点での格差」を黙認しているか。 ただ社会正義を振りかざすのではなく、このような統計的手法で示すことは、とても重要であると思います。 ただ、統計というのは恣意的な客観だと思うので、★は3つ。
0投稿日: 2009.06.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ「実際には、子ども期の生活の充足と、学力、健康、成長、生活の質、そして将来のさまざまな達成(学歴、就労、所得、結婚など)には、密接な関係がある。その関係について、日本人の多くは、鈍感なのではないだろうか。」 ほんっっっとうに、その通りなんだと、この本を読んで改めて思わされあったのであります。 貧困って、子どものもそうだけれど、日本人の貧困って普通の生活を送っている人たちにとっては本当に他人事なんだなぁとつくづく感じた。 でも、それって国というか政治ががそうだから国民もそうなってしまうんだろうと、本を読んでいてわかった。 あまりにもお粗末すぎる、日本の政策。筆者の言わんとすることは最もだ。 特にこの本では経済面の施策について言っているのだけれど、もちろんそれだけじゃダメだ。 フィジカルな部分とメンタルな部分、両方のケアが急速に必要。 と言っても、憂えるこの現状。 まずは、一人でも多くの人が日本でも子どもがこんなにも貧困状態にいるということを知らなくてはならないと切に思う。 【4/22読了・初読・大学図書館】
0投稿日: 2009.04.24 powered by ブクログ
powered by ブクログ(2009/4/7読了)P188の『日本の一般市民は、子どもが最低限これだけは享受すべきであるという生活の期待値が低いのである。このような考え方が大多数を占める国で、子どもに対する社会支出が先進諸国の中で最低レベルであるのは、当然といえば当然のことである』に、問題の根源が凝縮されているように思う。
0投稿日: 2009.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ●未読 「週刊ダイヤモンド」2009.03.21号 「あなたの知らない貧困」p.40〜41「貧困本」×16冊 1-3 人生のスタート時点での「不利」の、理不尽な現実。そもそも「貧困世帯に育つ」とはどういうことなのか。豊富なデータをもとに「不利」の実態に迫り、貧困の世代間連鎖を断ち切るための「子ども対策」を提唱する。
0投稿日: 2009.03.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ子供の貧困を断ち切ることで大人の貧困も断ち切れる。その為には少子化という近景ではなく、子供対策という遠景からのアプローチが必要としている。埋蔵金含めて日本の限られた予算をいかに分配していくかを考えて欲しいと思った一冊。内容としては貧困世帯で育つことによる貧困の連鎖を取り上げた上で、日本の子供の貧困状態に関して、あらゆるデータから、定量的、定性的に示す。?日本の相対的貧困率がOECD諸国の中でアメリカについで第2位?日本の子供の貧困率が徐々に上昇傾向。2000年には14%。OECD諸国平均と比較し、高い?母子世帯の貧困率が突出して高い。特に母親が働いている母子世帯の貧困率が高い。強烈だったのは、日本は唯一、社会保障制度や税制度によって、再分配後所得の貧困率のほうが、再分配前所得の貧困率より高くなる(=日本の子供の貧困率は悪化しているケース)があるということ。おまけに、2002年の母子政策改革により5年間の期限付き、かつ逓減していく形での自助努力が促されているが、支援は弱められているということ。少子化対策を、子供対策という視点で捉え直し、日本の世代間不公平を是正する必要があると思った。
0投稿日: 2009.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近堅い文調の本読んでなかったから読みごたえが中公新書並みにあった。やはりというか母子世帯に生まれる子どもの強いられる環境は困難を極めていると思った。給食はもちろんのこと、身だしなみや修学旅行と必要な経費はたくさんかかる。母子世帯がそれを上手くやっていくにはきついだろうと思った。ただ、当事者である子ども達が何を思っているかは不明瞭な部分が多いと思う。アンケートも親目線のものがほとんどであった。社会保障負担が低所得層ほど強いられる現状は改善されなければならないとも思った。余談だが相対的剥奪の質が他国とは違うetc大学の授業に通ずる部分も多かった。
0投稿日: 2009.02.03 powered by ブクログ
powered by ブクログあらためて、貧困が子どもに与える影響が認識できた。 なぜ日本では苦労話が大手を振ってるんだろう。 「ムカシは貧乏学生が一生懸命勉強して、会社の社長にまでなったものだ」というような成功譚をどれだけ聞かされ、また、現在もなお、子どもの貧困にたいしては、この程度の談話で片付けているようだ。 著者は答えているだろうか。 なぜ、日本にこの成功譚が根強く残っているのか・・・までは答えていない。 国家の政策として子どもの貧困を撲滅することは必要だ。その意味で、正面から取り上げられたことはいいことだ。 しかし、政策の足を大きく引っ張っているものが何か・・を問われなければならない。 日本には宗教が根付かない・・・と遠藤周作氏が言われていた。 この西洋的なものが根付かないもどかしさ・・・・、そういうものと同じ気がしてならない。 日本人は「子ども貧困」については、真剣に考えない種族のようだ。
0投稿日: 2009.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書の良さは、数多くのデータに基づいて考察が行われている事である。 よって、非常に客観的であるが故に、納得させられ、危機感を実感できる。 内容は、こどもの貧困に焦点を当てたもので、大人の格差はしょうがないと としても、子供の格差はなくすべき!というのが著者の主張だ。子供の格差を 是正しないと将来私達自身にとっても良い結果を生まない。負の連鎖は なるべく早くに断ち切るべきだ。との事。 本書で驚いた内容が、日本は世界的にみてもこどもの貧困率が高い事である。 貧困と言っても、著者が言うように絶対的貧困と相対的貧困(周りの環境によって 左右される)のように定義付けの違いがあったり、貧困とは何か?に答えるのは 難しいが、それは本書を読めばかなり考えられての上記の結果である事が分かるので、 やはり日本のこどもの貧困率は高いのであろう。 そして、自分も考えさせられるのが、子供に対してあまり豊かにさせようという 気持が日本人は少ないとの結果も本書では報告させられている。例えば、こどもの おもちゃは必需品か?という問いに対して、はっきりとイギリスと日本では差が出ている。 私も言われてみれば、必要ないかなと考えてしまう。 また、このような現状に対しての政府の対応が先進国の中でも遅れている事、 行われている施策が、十分に効力をはっきしていない事などひどいありさまである。 確かに、著者が言うようにこどもの貧困は、負の連鎖を断ち切るためにも必要である。 そのために、国民全体で負担をしなければならない事は理解できる。では、その財源を どうやって確保するのか。なかなか難しい。しかし、富める者からより多く負担させる事は 明らかである。しかし、富める者が政治を行っているからなかなか後始末が悪い。 私は思うが、税の名称をはっきりさせ、消費税というようなあやふやな名前ではなく そのはっきりした名称で、給料から天引きしたり、物を買ったときに引いたりすれば みんなも納得するのではないか?と思う。単に消費税・所得税と記載されるよりも こども保護税1%・環境税1%・・・といったように。そうすれば、消費税が高いとは 言えず、こども保護税が高いとはなかなか心が綺麗な日本人は言えないだろう。 それでも、この問題を改善させるには、やはり首相レベルでのプロパガンダが 必要なのかもしれないな。
0投稿日: 2009.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ日本の社会がこどもの必須だと考えるものが、 他国に比べ低いというデータは面白かったが、 議論自体はお粗末な感じ。 結局低所得者の子どもは他国に比べてデータ的に 貧困な状況に置かれているから、 子どもに対する所得支援(手当、税額控除etc)の拡充と サービスの拡充をしろという結論になっている。 大きな財政赤字を抱えてる日本でこの議論をするには、 じゃあその費用をどこから持ってくるのかという視点がいるだろうし、 もっと現在の教育制度の検証もいるはず。 あと海外比較をするなら単純に数値を引っ張ってくるだけでなく、 もっと社会的条件の違いも踏まえて、 どうしてそういう数字が出てくるのかという分析も欲しいところ。
0投稿日: 2009.01.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ予測していた内容だったので☆4つ。 本書の主張は以下の二点と書かれていたので、主張が簡潔で理解しやすかった。第一に、子どもの基本的な成長にかかわる医療、基本的衣食住、少なくとも義務教育、そしてほぼ普遍的になった高校教育(生活)のアクセスを、すべての子どもが享受するべき。第二に、たとえ「完全な平等」を達成することが不可能だとしても、それを「いたしかたがない」と許容するのではなく、少しでも、そうでなくなる方向に向う努力するのが社会の姿勢として必要。
0投稿日: 2009.01.11 powered by ブクログ
powered by ブクログ2008/12 多くのデータを用いて、現代日本では子どもの貧困という問題があることを示している。児童手当やひとり親支援関連の制度などを細かく検証している。ただ、データの量を詰め込みすぎているきらいはある。
0投稿日: 2008.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「総中流社会」だった日本は終わり、すでに「格差社会」になっている。 果たしてこれで良いのだろうか? 読後感を簡単に言えば無力感が一番近い。 半年近く教育のことを考えてきたが、 恥ずかしながら「貧困」ということにきちんと向き合っていなかったと思う。 国の定める制度の問題に結局は行き着くのだが、 こんな大きな問題にも個人で出来ることはないのかと悩んでしまった。 視野が狭くなっていた自分にとって転機となる本だと思う。 2009.10.09メモ 「貧困」=「許容できないもの」(そのことを社会として許すべきではないという基準)
0投稿日: 2008.12.08
