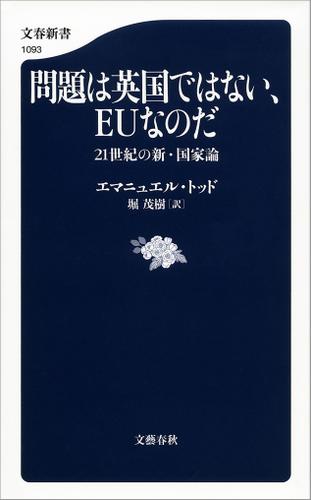
総合評価
(35件)| 4 | ||
| 19 | ||
| 8 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
EUが欧州統合の象徴ではなく、ドイツをトップにしたヒエラルキー構造であることを分かりやすく説明してくれる。
0投稿日: 2022.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ自分の見てきたヨーロッパはとても解像度が低かったんだと改めて感じた。 今のEUがドイツが牽引していて、EUの移民政策に関しても、他国ではさほど問題になっていない人口減少がドイツでは深刻で、それを移民でまかなおうとした結果だというエマニュエルさんの見方も面白かった。 もっと他の本も読んでみよう
0投稿日: 2022.08.08 powered by ブクログ
powered by ブクログブレグジットに対して、いわゆるエリートが反対し、庶民が賛成した構図と断言されている。日本でもだいたいそういう論調だったと記憶してます。トランプ現象に対しても同様。 5年が経過した今、世界はコロナとCO2と戦っているわけですが、控えめに言って訳がわからない。虚構と戦っている。それでもグローバリズムを維持できればエリートとしては良いのでしょう。 健全な民主主義を維持できる言論空間の必要性を痛切に感じますし、トッド氏のような良質なエリートの方々の活躍を切望します。
0投稿日: 2021.11.06 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
カバー裏の窓には筆者の肩書として歴史人口学者・家族人類学者とあります。私は存じ上げなかったのですが、数字を引き合いに出して議論するちょっと面白いことをいうオジサンだな(失礼!)、という印象でした。 何が面白いかというと、時事的なトピックについて欧州人として率直かつ分かりやすく語っている点。例えば表題ですが、Brexitの件です。私がぼんやり考えていたのは、折角国連みたいな連帯組織であるEUにいるのになぜに抜けてしまうのか? もったいないなー、英国、みたいなとらえ方です(バカ丸出し済みません)。筆者から言わせると、いやいやEUがやばいのであって、寧ろ英国はフツーですよ、と説きます。一部移民の制限をしたいという英国側の思惑も報道がありましたが、筆者の言わんとするのは英国の「主権の回復」です。英国はこれまでも通貨発行権も手放していませんでしたが、より自国を中心に考えるという事のようです。まあ主権の話も社説等でチラチラ出ていたりしますが、実際EUに住まう学者から説明されると、真偽はともかく「やっぱりそうかぁ」的に思いました。 ちなみに、ここから敷衍して、自由主義を標榜する英米二大巨頭が一方はBrexitとして他方はトランプ元大統領が行った保護主義として自己否定しているという事を述べており、行き過ぎた自由主義にはちょっと反対な私としては、心のなかで激しく同意した次第です。 他方で、いまいちだなと感じたのは、まとまりのなさ。 7つほどのインタビューや論説の寄せ集めであり、余り深さを感じませんでした。人口学や家族論が専門の方ですが、そうした方が移民について語ったり、フランス国内のテロが移民家系の国民が起こした点について語るのはなるほどと思うのです。ただ、そうした学者が米国政治の行方とか、中東情勢について語るのは、あたっていることもあるかもしれませんが、ぱっと見、テレビのコメンテーター的な雰囲気を感じてしまいました。 ・・・ 上にも書きましたが、ちょっとコメンテーター的ではありましたが、言っている内容は割と同感する部分が多かったです。家族論が専門とのことで、うちのように国際結婚した家からすると筆者がどんなことを考えているのか他の専門書も読んでみたいと思いました。 欧州やEUについて学びたい方、フランスの現代社会の歪みや移民政策に興味のあるかた、政治全般に興味のあるかた、人口学・家族論に興味のある方にはおすすめできる本だと思います。
0投稿日: 2021.07.27 powered by ブクログ
powered by ブクログトッド2冊目。ずっとカバンに入れてて細切れで読んだのと、中身も細切れなので印象は散漫。それでも面白い。こういうのは基本的にそのとき読むべきものなのだろうけど、少し遅れて読むとまた違う評価ができますよね。そろそろ主著に手を伸ばすべきだな。多作なので全部は無理だろうが。
0投稿日: 2021.03.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ「今、世界で一番危なっかしいのは、アメリカではなくヨーロッパなのです」2016年刊行時点の衝撃的な発言だが、改めて読み返してみるとなるほどと感じてしまう。EUの求心力低下が危惧される。
0投稿日: 2020.04.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ「ヨーロッパとは何か? ヨーロッパとはドイツを怖がる全ての国民の連合。そして、この定義はドイツ人を含む」という冗談がかつてEU本部のあるブリュッセルで流行った、とトッド氏は言います。EU内一強となったドイツを抑制する力が働かず、暴走する危険について氏は警鐘をならしています。 トッド氏は、家族形態の分類から国家や地域の文化的背景を特定し、出生率、高齢化率、識字率などの統計データの動向により国家の発展や衰退を予測する手法で、ソ連の崩壊を予測したことで知られています。 本書では、日本について言及した部分も多く興味深く読みました。日独の直系家族制度の類似性と相違点。日本の家族の重視とその功罪、など。 また日本の移民の受け入れの必要性について、同質性を重んずる日本人がパーフェクトな調和を前提とするあまり、移民による異質な文化の流入を受け入れづらいと指摘しています。逆にそうしたパーフェクトな状態がそもそも国内に無いフランスやアメリカが異質なものを内包するタフさを持っている、と氏がのたまう点に考えさせられるものが多くありました。 英国の分断性とフランスの連続性、中東イスラム宗派の家族形態の違いなど、氏の縦横無尽な分析力がそこかしこに感ぜられました。
1投稿日: 2018.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
遅ればせながら読み始め…前作を上梓してフランス国内では批判の対象となった著者。前作の前書きでは「読売と日経の記者が心のよりどころになったこともあった」と明かしていたが、今作では「あの本を出したことで今、自由に物が言える立ち位置になった」と話す。 前回よりだいぶ読みやすくなって、持論の人口学的な話もわかりやすかった。 トッドいわく、イギリス人のいないヨーロッパ、それはもはや民主主義の地ではない。1930年代の大陸ヨーロッパはポルトガルのサラザール、スペインのフランコ、ムッソリーニ、ヒトラー、チェコスロバキア以外はいたるところに独裁者がいた。 フランス、アメリカ、イギリスは自由を強制されている。絶対核家族のアングロサクソン世界の平均的個人は権威主義を許されていない。 「自由」が強迫観念になっていない日本のような権威主義的社会のほうがトッドの「家族構造が政治的行動を決定する」という決定論を受け入れやすい。日本で最初の講演を終えたら「トッドさんは長男ですか、次男ですか?」と聞かれた。スキャンダル視されることなく受け入れられた。「人間の自由には限界がある」ことを認識できるという意味で日本のほうが実質的に自由なのかもしれない。そういう能力を今日の西洋人は失っている。自由が強迫観念になり、ゆがんだ人間観を持っている。リベラルと言われる社会が実はさほどリベラルでなく、先進国のナルシズムともかかわる問題。「シャルリとは誰か?」のテーマでもある。 日本は出生率を上げるには、女性により自由な地位を認めるためには、不完全さや無秩序も受け入れるべき、子供を持つこと、移民を受け入れること、移民の子供を受け入れることは無秩序をもたらしますが、そういう最低限の無秩序を日本も受け入れるべきではないか。 歴史学者、社会学者から見れば、ISは西洋が生み出したもの。ジハード戦士の大半は西洋から現地入りした者。アルジェリア人は「なんでヨーロッパ人は、あなた方のクソみたいなものをこっちへ送ってくるのか」イスラム社会から生まれたとはみなしていない。 グローバリズムへの漠然とした不満がイスラムヘイトにつながっている。社会と国際関係の安定を望む民衆は過剰なまでのグローバリズムの進展に小休止を呼び掛ける権利をもっている。経済格差の拡大はスケープゴートを求めてイスラム恐怖症という妄想のカテゴリーを生み出している。
2投稿日: 2018.11.28 powered by ブクログ
powered by ブクログイギリスがEU離脱したことを受け、現在の主にEUの情勢を分析した一冊。 著者がフランス人ということもあり、フランスによってる部分はあるものの、ヨーロッパ人が見たEU、アメリカ、そして日本の情勢を知ることができた。
0投稿日: 2018.11.22 powered by ブクログ
powered by ブクログトッドにはかねてから興味はあったのだが、ぶあつい著作にはなかなか手が出なかった。これはインタビュー・講演や雑誌への寄稿をまとめたお手軽な新書。現時点で最新のようでもあるので気軽に手にとってみた。時事ネタを扱っているのも良いし、なるほどとうならせる箇所も多いのだが、一方で分量ゆえ仕方ないながら、踏み込み不足というか物足りない感じもある。なかなかうまい広告なのかもしれない。 1,2はBrexitに関する論考で、やや内容はかぶる。本書の中では小手調べ的なかんじ 3はトッド自身の仕事や方法論を振り返っており、初読の身には大変おもしろかった 4は人口学による各国近未来予測、これも興味深い 5は中国論、日本への言及も 6,7はお膝元フランスでのテロ(およびその後の国民の反応)を受けて。切実な問題意識を感じる フランス人らしくなく観念論は嫌いで経験主義的。定量的な歴史人口学が性に合った。ただイギリス留学で、イギリス人のヒエラルキー感覚を目の当たりにし、自分の平等主義的フランス人性に気づいたと。 「自由」をめぐるパラドクス。トッドによる家族構造が政治体制を決めるという発見は決定論的であるが、かならずしも個人の選択を決定するものではない(それでもイギリスのような絶対核家族の文化に生まれると、自由でなくなる自由にとぼしい)。ただ、それが人間の自由を否定する決定論と捉えられ批判もされている。特に自由(リベラル)な国において。自由が強迫観念になってなぜ自分が自由であるかを自覚できない。また、個人主義ほど国家を必要とする。 歴史を動かすのは中産階級。今日の先進国では、高等教育を受けた層が中産階級と言える。 →米大統領選挙のNate Silverによる分析(学歴が投票行動を決めるファクターだった)を思い出した 核家族のほうが共同体家族よりも原始的な家族形態。現代での分布から伝播モデルで推測できる →日本での方言の分布なんかと同じ話か 普遍性と文化相対主義、多様化と画一化のせめぎあい。トッドは家族構造が似ている文化同士に普遍性を見出す。 場所(テリトリー)のシステム。移民なども行った先の文化に同化することが多い(例:アメリカ)。人間は可塑性を持った存在であり、文化の差はそれほど決定的でない(弱い価値)。ただし場所単位で見ると、永続的な「文化」が立ち現れる。それは家族由来の価値観が「弱い価値」であるからこそ ネオリベラリズムにより家族の扶助なしに個人で生きるのが難しい状況ができてきている。個人主義的なものと矛盾がある。アメリカにとって国家とは何なのかが大きな課題。国家の再評価が必要。一方、日本では家族の過剰な重視が、少子化による家族の消滅につながっているのでは ネオリベラリズムの次の潮流だが、世代ごとの断絶があるアングロサクソンからまた次の流れが出てくる可能性は高い。 ロシアの復活。出生率も1.8まで回復し、女性の高等教育進学率もあがって社会が安定化に向かっている。プーチンみたいな強権的なリーダーを好むのは家族構造ゆえ。 →認識が古かった。よいインプット サウジアラビアは出生率激減、中東の不安定の核。安定化しているのはイラン 中国はいびつな人口構造、過剰投資など不安定。また中国の家族構造は平等主義的で(だから共産主義も根付いた)本来的には格差を許容できない ドイツにも辛い。低い出生率をむりやり移民で埋めようとしているが、トルコからの移民の社会統合ができていない。シリア人は家族構造的にもっと遠いのでさらにむずかしい ヒエラルキー的な家族構造を持つ日本では、国際関係もヒエラルキーで考えがちである(アングロサクソンや中露は対等な国際関係が前提としてある)。また、日本の家族構造では長男以外は家族構造の外で一人で生きようとするので、いったん強い国であることをあきらめると孤立主義への誘惑がある。それを乗り越えて米露と連携して中国問題にあたる(方向性は助け舟)べき。 フランスでカトリシズムはすっかり衰退したが、その文化的影響は地域ごとにはっきり残っている。 とにかく日本は少子化対策をがんばれよと
0投稿日: 2018.11.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・ 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・ 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ英国のEU離脱問題をはじめとした現代の国際的な諸問題に対し、主に文化人類学的観点からメスを入れた本。 あらかじめ告白すると、ボクはこの本が非常に読みにくかった。というのは「全体として、ネオリベラリズムおよびグローバリズムの言説に抵抗する本」(あとがき)であり、経済学がめたくそに批判されているので、はっきり言っていい気持ちがしないです。が、視野が狭くなるのは大問題で、耳障りが悪いものほどしっかり読んだほうがいい。 面白かったのは、家族システムから世界を捉えるという考え方。アメリカやイギリスは核家族。子供は大きくなったら親元を離れます。兄弟は平等だし、親子の関係もそこまで縦の関係ではありません。一方、日本やドイツは基本的に一家の長男が家を継ぐ直系家族制度で、長男とそれ以外の兄弟の間には差があります。親子の関係も対等ではありえません。アメリカやイギリスは個人主義で自由主義。対して日本やドイツは全体主義で権威主義。家族システムが「下意識」(無意識と意識の間。おそらくunder-consciousの訳だけど、日本語にすると変な感じだね。)となって個々人の思想が作られていく。言語や宗教もそうだけど、そのひとの思想の根幹を成している部分を無視して、経済的な利害だけで繋がれって言われてもっていうのは、確かにそうだ。いとこ婚が盛んな地域もあり、そういう地域では考え方も違ってくるでしょう。 日本についても言及されています。「日本の唯一の問題は人口問題」とし、「移民を受け入れない日本人は排他的だと言われますが、実は異質な人間を憎むというより、仲間同士で互いに配慮しながら摩擦を起こさずに暮らすのが快適で、その状況を守ろうとしているだけなのでしょう。その意味で日本は完璧な社会です。」(p184)その完璧さを守ろうとすると、日本は存続できないかもしれない、ということです。
0投稿日: 2018.05.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ出版のタイミングとタイトルから、ブレグジットを中心として書かれた書籍かと思いましたが、それは話のきっかけでしかなく、内容は世界動向のなかでのEUについて記載されているもので特に独仏の現状を懸念する内容でした。 予想していた内容とは若干異なりましたが、人口学や家族構成から世界の動向を探る見方は新鮮でした。
0投稿日: 2018.03.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ直系家族の社会は、アングロサクソンの核家族の社会ほど、国家を必要としない。直系家族自体が国家の機能を内部に含むから。核家族は個人を解放するかシステムだが、そうした個人の自立は、公的な、つまり国家の福祉を前提としている。ネオリベラリズムは、それを忘れている矛盾がある。この話は、奇しくも、渡辺京二の話と同じ結論になってる。
1投稿日: 2017.11.17 powered by ブクログ
powered by ブクログ人口学者の視点から見たヨーロッパとはどう見えるのか、というよりもすでにヨーロッパというものは存在していない、とまで言い切る著者の魅力は素晴らしい。 今回は日本についての記述が多く、フランスの人口学者から見た今の日本(というネーションに存在する自分自身)についての客観的な視点が得られるのも素晴らしい。
0投稿日: 2017.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログEUはドイツとその手下たち 移民の受け入れは慎重に 2016年の話の内容だとするとかなり予見があってると思った
0投稿日: 2017.10.11 powered by ブクログ
powered by ブクログヨーロッパ内部の視点から世界がどう見えるか、とても面白かった。家族の成り立ちが政治イデオロギーの成り立ちに影響を与えているという主張は、一見無理矢理感があるが、家族の成り立ちを決める根源的な好き嫌いが社会の構造に影響を与えるのはもっともと思えた。
0投稿日: 2017.09.03 powered by ブクログ
powered by ブクログ初トッド本。ヨーロッパを中心に世界が抱える問題を人口や家族感の観点から分析した本。手前味噌感が強すぎてちょっと鼻に付く。トッド氏が基本的にどんな考えを持っている人かよく分かってなかったためちょっと難しかった。
0投稿日: 2017.06.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近読みはじめたトッド本、3冊目。前の本より手前味噌感がなくもないが、明快な主張は良い。イギリスとドイツ、アメリカ(ついでに日本も)を中心に、イギリスEU脱退直前の状況を分析する。 現在、まさに脱退後の混乱状態にあるので、続書が出るはず。これをぜひ読み、比べたい。
0投稿日: 2017.06.08 powered by ブクログ
powered by ブクログ本書は書下ろしではなく、7編の時事論集である。すべてBrexitやパリ多発テロなど2015-16年頃のものなので、当然ながら似ている内容が多い。また、ほとんどが日本で収録または日本で発表されたものということで、日本に言及した部分も多い。 ヨーロッパを主にした世界情勢論、家族形態の歴史に基づく文明論、などが展開されているが、いかに日本人向けにアレンジされて読みやすくなっているとはいえ、決して理解が容易な内容ではない。編をまたいて繰り返されることで、辛うじてぼんやりと分かったような気にさせてくれるが、それは本書の主張を支持するものである。 氏の論調は自国では批判が多いようだが、世界は難しい問題に溢れていることだけは確かなようだ。
0投稿日: 2017.05.13 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
■問題はポピュリズムではなく、エリートの無責任さ 英国EU離脱に象徴される大衆の抵抗を「ポピュリズム」という表現で説明しようとする向きもありますが、私はむしろ「エリートの無責任さ」こそが問題を理解するキーワードだと考えています どんな社会でもエリートは特権を持っています。しかし、同時に社会に対して責任を負うべき立場にあります。ところが、最近では指導者たちが自分の利益のみを追求するようになっている。ポピュリズムよりも、そうしたエリートの無責任さこそが問題です。 注目に値するのは、ボリス・ジョンソン前ロンドン市長に代表されるエリート層の一部が民衆側とともに離脱を叫んだ点です。 イートン校、オックスフォード大学出身のジョンソンは、英国王室にも連なる血筋の持ち主で、紛れもないエスタブリッシュメントの一員です。そんな彼がエリート層の少数派として民衆側についた。政権与党である保守党議員の半分くらいがEU離脱派に名を連ねた。だからこそ、イギリスはポピュリズムから免れつつあるのです。 これが、私が羨望してやまない、国家の自己改革のために登場するリーダーの姿です。イギリスには、常にウィンストン・チャーチル、あるいはボリス・ジョンソンのような政治家が体制内にいます。フランスにとって問題なのは、エスタブリッシュメントの中から、大衆の利益をあえて引き受けるエリート少数派が出てこないことです。 フランス国立行政学院などのグランゼコールは、たしかに優秀ではあるけれども、尊大で他人を見下すようなエリートをコンスタントに輩出しています。現代のフランスが、今後イギリスのようなリーダーを生み出せるのかどうか、私には自信がありません。 ■英国の「目覚め」に続け! イングランドから始まった産業革命は、欧州全体を経済的に一変させました。そして、1688年には名誉革命によって議会主義の君主制が確立されました。欧州各国で採用されている、近代的な民主主義の出発点はイギリスにあったのです。1789年のフランス革命の夢と目的は、政治的近代化のモデルである英国に追いつくことにありました。そのイギリスが、自ら先鞭をつけたグローバリゼーションの流れからいち早く抜けようとしている。イギリスの国民国家への回帰は、歴史的にも最重要の段階であると言えます。 私は長期的には楽観主義者ですから、近代国家の再台頭というモデルについて、いかなる疑いも持っていません。イギリスに続く「目覚め」がフランス、そして欧州各国で起こることで、ドイツによる強圧的な経済支配から「諸国民のヨーロッパ」を取り戻せるはずです。それこそが欧州に平和をもたらす、妥当だと言う意味で理性的な解決策であると私は確信しています。 ■歴史を動かすのは中産階級 中産階級とは、所得や教育水準がある程度高く、階層として一定の規模を持った集団です。この階層が歴史の変動を左右しているのであって、この階層を考察しなければ歴史の現実は見えてきません。中産階級に比べれば、上層の貴族層も、下層の庶民層も、現実社会への影響という点ではさほど重要ではありません。現在のフランス社会が閉塞状況にあるのも、中産階級に原因があるのです。 「1%の支配」という超富裕層とそれ以外との格差の問題は、確かに存在します。まったく不公正な格差です。しかし、このことを指摘したからといって、「西洋先進社会は閉塞状況に陥っているのに、なぜみずから方向を変えられないのか?」という問題の説明にはならないのです。この問題を解くには中産階級の分析が不可欠です。つまり、1%の超富裕層の存在を許し、庶民層の生活水準の低下を放置しているのは、中産階級だからです。 「中産階級こそが歴史の鍵を握っている」ということは、歴史を眺めて確認できます。ナチズムは中産階級の現象でした。フランス革命も同様です。日本の明治維新も中産階級に主導されたものだったはずです。上級武士ではなく、下級武士という中間層が中心的役割を担ったわけですか。 ■核家族と国家 「核家族」は、それぞれバラバラに存在するのではなく、ある大きな社会構造の中に存在している。これはいつの時代にも言えることです。 イギリスは、最も早く産業化し、最も早く貧者救済施設を創設した国ですが、それが、絶対的核家族がそれだけでは存続できないことを当時の人々も理解していたことの証しです。公的・社会的な援助を受ける独居老人の比率が高いのが、当時のイギリス社会の特徴でした。 たとえば、直系家族の社会は、核家族の社会ほどには国家を必要としません。なぜなら直系家族自体が、いわば国家の機能を内部に含んでいるからです。家族としての団結そのものが「ミニ国家」的です。その分だけ、通常の意味での国家の必要性は弱まります。 核家族は個人を解放するシステム、個人が個人として生きていくことを促すシステムですが、そうした個人の自立は、何らかの社会的な、あるいは公的な援助制度なしにはあり得ません。より大きな社会構造があって初めて個人の自立は可能になります。「個人」とより大きな「社会構造」には、相互補完関係があるのです。 ■ネオリベラリズムの根本的矛盾 - 「個人主義」は「国家」を必要とする 絶対核家族のアメリカは、大恐慌以降のニューディール政策から第二次世界大戦にかけて、黄金時代を迎えました。ちょうど国家が積極的に社会に介入した時代です。各国から移民が大量に流入した時代ですが、その移民たちがそれぞれの移民コミュニティから離れ、個人として自立するのを助けたのは国家なのです。1935年、ルーズベルト大統領が社会保障制度を導入します。それがその後のアメリカ繁栄の礎となりました。 しばしば、「個人」と「国家」は対立させられますが、国家が大きな役割を果たすことと、核家族システムのなかで個人が個人として生きることは、矛盾するどころか、実は相互補完的なのです。この点を、ネオリベラリズムの信奉者はまったく理解していません。 ネオリベラル革命がもたらした逆説的結果の一つは、核家族の進展、つまり個人の自立を妨げたことです。 この文脈では、核家族を、(1) 古いタイプの核家族と、(2)純化された絶対家族とに分けて考えると良いかもしれません。(1)が「パパ・ママ・子供の世帯」であるのに対して、(2)は、独身者、独居老人などといった「一人世帯」です。ネオリベラル革命は、ここでいう(2)のような世帯を否定するのです。 大人になれば、家を出て自立するのが、個人の自立を尊重する絶対核家族のアングロサクソン社会の特徴です。ところが、ネオリベラル革命の皮肉な結果として、成人になっても経済的に親元を離れられない子供が急増しました。ネオリベラリズムは、個人主義であると言われていながら、実際には個人の自立を、つまり個人主義を妨げているのです。 いま世界で真の脅威になっているのは、「国家の過剰」ではなく、むしろ「国家の崩壊」です。 いま喫緊に必要なのは、ネオリベラリズムに対抗する思考です。要するに、国家の再評価です。国家が果たすべき役割を一つずつリストアップすることです。 ■サウジアラビア崩壊という悪夢 フランスの石油会社トタルの要請で、「サウジアラビアのリスク」という報告をしたことがあります。そこでとくに強調したのは出生率の激減です。1990年頃に6だった出生率が、現在、3を割っています。 サウジアラビアは昔ながらの部族社会で、一見、何も動かない世界のように見えます。保守的で、惰性的で、停滞している世界だと言われます。ところが、出生率の急減が示しているように、深層では大きな地殻変動が起きているのです。社会全体が不安定化しつつあります。 サウジアラビアは、西洋世界にとって、中東における重要拠点です。仮にサウジアラビアが崩壊すれば、その影響は計り知れません。ただでさえ国家建設がほとんど不可能か、極めて困難なこの地域に、さらに広大な「国家なき空白地帯」が生まれることになるからです。 これまで、アメリカとサウジアラビアは特別な関係を築いてきました。それはなぜなのか? 中東の原油を押さえるためだという説明がよくなされます。しかし、実はもともとアメリカは中東の原油にまったく依存していません!それも、近年、米国内のシェールガスの開発でエネルギー自給率を高めたからではなく、以前からそうだったのです。アメリカが中東の原油をコントロールするのはむしろ、ヨーロッパと日本をコントロールするためなのですよ。
0投稿日: 2017.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログリベラルと言われる人々の主張に、うんざりする今日この頃ではあるが、じゃあそのうんざりする気分というものは、どんな背景から湧き上がってきて、どう言語化できるものなのか、ということをはっきりさせておきたく、読んでみた。 なんだか分かるような、わからぬような… スッキリ、とはいかなかった。 もう少し考えてみたいと思う。
0投稿日: 2017.04.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ短編や講演をまとめた為か、体系だった論点というより、気付きをもらえる本。 自由を強制される西洋に対し、自由に限界があると認識している日本の方が内面的に自由でいられるというのは、欧米はポリティカル・コレクトネスが行き過ぎてしまった、とも重なるのだろうか。 大家族主義の国家で共産主義が発達し、各家族主義の国家では発達しなかった、というのは結果論では納得できるし、EUの移民許容度を内婚率(イトコと結婚率)で説明するも興味深いが、その論点だけの説明は、危険なプロパガンダと感じた。(すべて、それが原因なの?) 本人の主義にのっとり、多様化した視点を聞きたい。
0投稿日: 2017.03.12 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバリゼーションの崩壊から、 『多様性の共生』へ。 人類学的見地からの、家族構成、家族システムによる相違を言及した視点は、非常に感心させられた。 コチラの本は、これまでのと違って、非常に読みやすく、個人的にはほぼ納得がいくものであった。
0投稿日: 2017.01.30 powered by ブクログ
powered by ブクログトッド氏の著作3作目にして一番わかりやすく あっという間に読むことが出来た。 個人的な難易度としては 本作<「ドイツ帝国」が…<シャルリとは… トッド氏の著作は毎度だが 客観的な数字、統計を基にしており 大変説得力があった。 盲信することというのは危険だと思うが トッド氏の言っていることは非常に確からしいことと思う。 予言していた!などという帯に違和感はあるが まぁ手に取るためのふれこみとしては仕方ないのかしら。 とにかくまぁ面白かったし為になった。
0投稿日: 2017.01.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ20170106〜0118 アラブの春、ユーロ危機といった事象を予言していったエマニュエル.トッド氏の時事論集。ドイツの頑なな財成規律主義が、他のユーロ諸国を危機に陥らせていること、氏の母国フランスは中央部と周縁部の二つに分かれていること、などが示されている。この議論を読むと、日本人は実に宗教的な国民なのだと考えさせられた。
0投稿日: 2017.01.08手頃なトッド入門書かも 時事ネタも網羅
トッドにはかねてから興味はあったのだが分厚い著作にはなかなか手がでなかった。これはインタビュー・講演や雑誌への寄稿をまとめたお手軽な新書。時事ネタ(2016年末時点)を扱って読み進めやすいし、「なるほどー」とうならせる箇所もとても多い。フランス人らしくなく哲学嫌いの経験主義者というだけあって話が分かりやすい。一方で、分量ゆえ仕方ないながら踏み込み不足というか物足りない感じもある。本格的な著作に誘導するなかなかうまい広告なのかもしれない。 あと、とにかく日本は少子化対策をがんばりなさいよ、とのこと。仰るとおりで。 [目次より] 1,2はBrexitに関する論考でたがいにやや内容はかぶる。タイトルにもなっているのだが、本書の中では小手調べ的なパート 3はトッド自身の仕事や方法論を振り返っており、初読の身には大変おもしろかった 4は人口学による各国近未来予測、手短ながら興味深い。個人的にはロシアの復活には気づいていなかった 5は悲観的な中国論、日本への言及も多し 6,7はお膝元フランスでのテロ(およびその後の国民の反応)を受けて。切実な問題意識を感じる
4投稿日: 2016.12.31 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史人口学者エマニュエル・トッド氏の来日公演の内容等を本にまとめたもの。 グローバリゼーションをけん引してきた張本人である英米が逆方向へ舵を切ろうとしている昨今の国際情勢を、社会科学と歴史的考察で分析しています。 ここ数年、マスメディアといわゆる知識人の思考パターンは、リベラリズム、グローバリゼーション、ポリティカルコレクトネス等を「絶対正」として繰り広げられてきました。 しかし、歴史や文化、教育、芸術、宗教の観点がごっそりぬけおちているのです。 トッドは、Brexitはマスコミが言うような大衆の気まぐれな失敗などではなく、これまでも歴史を切り開いてきた英国の目覚めであるとしている。 また「私はシャルリ」は、下位の社会階級の人々に対して利己的な態度をとる中・上位階級の人々による無自覚な差別主義の発露であるとしている。 ドイツ率いるEUの行き先は? 先の見えない歴史的転換点で、はたして日本はどうすればいいのか。 マスコミ等が拡散させている言説では何かしっくりこないモヤモヤを感じてしまう人は、ぜひ読むべき本であると言えます。 ※ちなみに、トッド氏はフランス人です
0投稿日: 2016.12.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ新たな歴史的転換をどう見るか? 人口論からの解析、トッド氏の独自の言説をまとめた本でした。 1 なぜ英国はEU離脱を選んだのか? 2 「グローバリゼーション・ファティーグ」と英国の 「目覚め」 3 トッドの歴史の方法――「予言」はいかにして可能 なのか? 歴史家トッドはいかにして誕生したか? 国家を再評価せよ 国家の崩壊としての中東危機 4 人口学から見た2030年の世界 ――安定化する米・露と不安定化する欧・中 5 中国の未来を「予言」する――幻想の大国を恐れるな 6 パリ同時多発テロについて――世界の敵はイスラム 恐怖症だ 7 宗教的危機とヨーロッパの近代史 ――自己解説『シャルリとは何か?』 という内容ですが、経済学的解析の限界性があり、人口論からのアプローチは、説得力があります。 フランス人でありながら、フランス国内では評価されないトッドさん、日本との親和性はいいようであります。 彼の言っていることには、賛同できる部分が多々ありまして、楽しく読むことができました。
0投稿日: 2016.12.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ家族システムの分布を伝播主義モデルで説明すると、初期の人類は双系性の核家族で暮らしていたと考えられる。核家族の社会では個人主義的な傾向が強く、直系家族の社会では世代間の連帯が重視され、共同体家族の社会では兄弟間の連帯が重視される。 ヨーロッパでは、中世末期から直系家族に変化し、宗教改革によってそれが強化された。フランス革命の半世紀前には、パリを中心とする広い地域でカトリシズムが崩壊し、世俗化していた。絶対核家族のイギリスは貧者救済施設を最も早く創った。個人の自立は社会的な援助制度なしには可能ではない。 イスラム社会の中でも、シーア派では息子がいなければ娘が相続することがあるが、スンニ派では娘がいたとしても相続することはなく、父系の親戚筋が相続人となる。 共産主義革命は、親子は権威主義的で兄弟は平等な外婚制共同体家族の社会で起きた。マルクスが予想したプロレタリアートを有する工業先進国では実現していない。 1914年の狂気は、中産階級の自殺率が高く、精神疾患やアルコール依存症が増え、精神状態が不安定だったことによるもので、中産階級が歴史を動かしている。ローレンス・ストーンは、革命の前には識字率が上昇していることを示唆した。現在は、高等教育の進学率が重要な指標となる。
0投稿日: 2016.11.26 powered by ブクログ
powered by ブクロググローバリゼーションの崩壊から未来世界について、人口動態、家族形態、教育、宗教観など多彩な指標からデータを分析して解説すると共に、著者自身の学問的背景についても語り、世界を経済だけではなく広い視野で観る重要性を説きます。 地域に根付く家族構造によって、共産主義になったり、教育水準が高くなったりするなどとても興味深い考察が詰まっている好著です。
0投稿日: 2016.11.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ前作に続いて独自の視点で欧州を中心とする世界の動向を解説している。 ただ簡単な本ではないと感じた。欧州のことについての基礎知識を積み上げてから、再び読んでみたい。
0投稿日: 2016.10.30 powered by ブクログ
powered by ブクログ最近、著作がいろいろ出たり、雑誌に書いていたりするのは知っていたが読むのは初めて。家族のあり方と国家を結びつけるというおもしろいアプローチ。それで、ソ連崩壊とかアラブの春とかを予言し、今回のイギリスのEU離脱も。多少難しく書かれている部分もあるが、インタビューの採録などはわかりやすい。いろいろと考えさせられる一冊。
0投稿日: 2016.10.27 powered by ブクログ
powered by ブクログウクライナ問題やトランプ現象等、昨今の大国は「グローバル」から「ネイション」へ回帰しつつある。言うなれば「ソフトナショナリズム」とでも言おうか。かりにそこまで大げさじゃなくとも、主権を守るためにEU離脱を決断した英国の姿勢はなんら不思議ではない。むしろ連合という名のドイツ支配圏と化してしまっているEUこそ危うく、国家的アイデンティティの見えない構成国こそ危険であると著者は説く。人口学という視点からソ連崩壊、リーマン・ショック等を予言し的中してきたからこそ、その説得力に鳥肌がたつ。だが一方で、ナショナリズムが善というわけではなく、むしろ暴走の危険をはらむことを忘れてはならない。そして著者がこのタイトルから本当に言いたかったのはおそらく「問題はISではない、フランスなのだ」。他人を侮辱することと報道の自由とを履き違えるフランスはいま、経済危機と宗教の空白を同時に迎えている。これはナチス台頭を許したかつてのドイツとオーバーラップする。そしてアジアでは中国による挑発行為の連続。ふたたび全体主義が台頭する暗黒の時代がやってくるのだろうか?
0投稿日: 2016.10.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ【現代最高の知識人の最新作。日本オリジナル版】ソ連崩壊から英国のEU離脱まで、数々の「予言」を的中させた歴史家が、その独自の分析の秘訣を明かし、混迷する世界の未来を語る。
0投稿日: 2016.09.01
