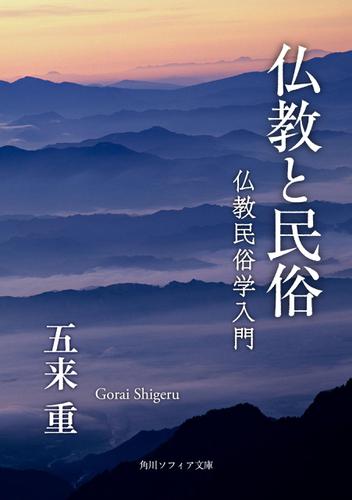
総合評価
(3件)| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ歴史と言う学問上で語られる我が国の文化は常に外からの影響により変化してきたと言う思い込みで成り立っている。が、その認識に否定ではなく抗う術を提供してくれているのが、本書の骨子だと思った。また文化と宗教と政治の絡みかたについても細やかながら暗示しておられる箇所が有り好感が持てる◎明治維新と言う、政治の暴挙を受け、世界大戦でグチャグチャにされている我が国の心の文化を改めて整理したい欲求に駆られる書籍
0投稿日: 2021.02.07 powered by ブクログ
powered by ブクログ1970年代に角川選書で刊行された同書名の文庫化。 思想としての仏教と、民俗、つまり慣習としての仏教との間に違いがあることは、なんとなく理解していても、意識化していない。 例えば、墓地に葬り墓を建て、家にも仏壇を設け、位牌を置く。当たり前だと思い続けてきた「両墓」が、仏教伝来以前の祖先崇拝によるという指摘は、とても新鮮だった。 この時代に進められていた既存宗教教団の、仏教の本来の思想としての布教活動を、祖先崇拝を時代遅れと切り捨てていることの、その危うさを著者は警告していた。時代が過ぎて、皮肉にも、結果は真逆で、多くの仏教者は、墓守と化してしまった。それだけ、日本民俗の祖先崇拝の根は、深いということか? そう、仏教が新思想としてもたらした時に、祖先崇拝を取り込んで、大衆への布教成に功したように思えたはずが、逆に大衆に飲み込まれてしまったように。 形は何であれ、個として今を生きる上で、生を終える不安、死との直面した時の動転、生きる上で積み重ねてきた小さな嘘や生き物を殺めてきた罪意識、これらの浄化(生きる上での過去清算)をどうするかは、時代ごとに形は変わっても、通時的には、祖先を祀るということで、済ませてきている。その遺伝子レベルでの説明のつかない行動の大きさは地下のマグマのようで制御不能ということか? そこに、例えば、なんでもありの日本人的いい加減さ、すべてを水に流す危うさがある。それが、祖先崇拝の象徴として天皇制に結び付き、国家としての集団意識となったときに、ヒステリックな暴力となる、というのは丸山真男の指摘通りかもしれない。 一方で、祭りを支えるムラの崩壊により、祖先崇拝を執り行う仕組みそのものが喪失し、意味を失った上での、イベント化(茶番劇)が何をもたらすのか? そこにつけ込む、歴史の歪曲と単純化という流れが現在の日本の状況だろう(日本のみならず、民俗主義の台頭という意味でより広範な共時な状況かもしれないが)。それへの批判という意味でも、再評価したい一書だ。 蛇足ながら、著者の五来重は、茨城県の出自。あとがきに、加波山禅定の一文が散見される。郷土の偉人としても再評すべき人物だ。
2投稿日: 2018.01.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ五来重さんの本は初めてだ。この人も柳田國男に触発されて民俗学に入ったクチらしい(日本の民俗学者はみんなそうかもしれないが)。 とても平易な語り口で、特に最初の章はごく簡単なエッセイの羅列のようだったが、途中から宗教民俗学的な知識が出てくる。 しかしどの項目も短すぎて、まとまった知が得られない歯がゆさを感じた。 山伏、修験道あたりについてもうちょっと知りたかったのだけど・・・。
0投稿日: 2012.04.28
