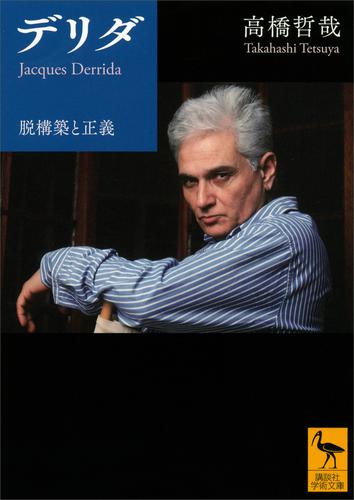
総合評価
(8件)| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ難しかった〜〜 パルマコンの話まではなんとなくわかったんだけど、「不可能なもの」、「まったき他者」とかについてはもっと読み込まなきゃだめだ 最後のキーワード解説と解説でちょっとわかった気になった 「アポリア」、「不可能なもの」(本書ではたくさん挙げられてる)をキーに、階層秩序的二項対立を掘り起こしていく感じなのかな その上で、揺らいだ(ように見える)秩序を前にしたときに、真に「決定」するとはどういうことなのか、それを考えてるのかな デリダ、デカすぎる
1投稿日: 2025.07.15 powered by ブクログ
powered by ブクログ構造主義に対するその先の概念「脱構築」を考案し、ポストモダン思想の旗手となったジャック・デリダ。本書は彼の思想の中心となる「エクリチュール」、「正義」、「他者」といった諸要素について、デリダに師事していた作者が解説した、いわばデリダ学の入門書である。 とはいえ、そもそもの概念がそれまであった哲学思想を元に生み出されたものなうえ、その概念自体かなり難解で、さらにデリダの書いた本も(ついでに本書も)脱構築の概念を説明しつつ、"実践する"よう書かれているため、常に単純な理解を阻むような構成となっている、と私には感じられた。要はすげーむずい。 なので、仮にデリダ(および脱構築)について初歩から知りたいという方がいるとしても、いきなりこの本から入ることはおすすめできない(そうした向きにはまず千葉雅也『現代思想入門』を手に取ることを個人的にはすすめたい。マジでわかりやすいから)。 でも不思議なことにこの本、よくわからないなりにじっくり読んでいくと、デリダがどのような方向を向いて思考を重ねてきたのか、その先にどんな世界を望んでいたのか、それが何となくわかってくる。わかってくるような気がした。 構成としては、第一章でデリダの経歴を時系列順に紹介し、その生い立ちから1998年までの業績を知ることとなる。ここまでは特に難しくない。 第二章からはグッと難度が上がり、プラトンの『パイドロス』を引き合いに、脱構築の実践を図る。どのような場合においても脱構築は己の頭の中だけで終始するようなものではなく、「他者」という存在が先んじてあり、であるからこそ、この実践編においても他者の作品が用いられるのだ。文章(エクリチュール)を一切残すことの無かったソクラテスに対し、彼の声(パロール)を残したプラトン。この関係性は脱構築の思想を理解する上で非常に魅力的な題材になると著者は言う。言葉(ロゴス)はパロールとエクリチュールという2つの段階に分けることが可能だが、脱構築の考え方からすればそこに内部/外部的な境界を設けることはそもそも不可能なことであり、下位の概念だとされていたエクリチュールはパロールと同程度のものとなる。脱構築はそのような境界の解体を可能とする。 ……みたいなことが書かれてると思うのだけど、やっぱしむずい。続く第三章では脱構築に関する諸要素である「反復可能性」や「まったき他者」という概念、「ウィ」という肯定の姿勢について。 第四章、第五章では法と正義が脱構築とどのような関連性をもっているのかなどが解説されていく。 「脱構築はある意味で、新たな「決定」(décision)の思想であるといえる。それは決定不可能性の思想であると同時に、決定の思想でもあり、同時に決定不可能性の思想でもあることこそ、脱構築をして新たな決定の思想たらしめているといえるだろう。」 と書かれているように、脱構築とは物事に対する新たな見方を提示するための概念なのだと思う。先日読んだばかりの『チョンキンマンションのボスは知っている』と似たような考え方として「贈与に責任を負わない」という事柄についても言及されており、社会制度を解体し、不可能性を引き受けながら、また別軸の可能性を探る思想なのかな、と思った。 感想を書いてて、どうもまだまだ理解不足だなあと感じているのだけど、脱構築が「中心」というものを断定せず、すべてをいったんフラットに見ようとする概念だとするならば、ある意味それに沿った感想になった気がするので、これはこれで良いのだ(ほんとかおい)。なぜならデリダも脱構築も「ほとんどすべてがこれから」なのだから。
5投稿日: 2025.04.01 powered by ブクログ
powered by ブクログデリダの著作は『ほとんどすべて、デリダ自身が読むこと』を起点に書かれており、その読解の元となる著作に対して『解釈を提起し、それをとおして自身の思想を展開していく』というものである。つまりデリダを読むことは、ただでさえ難解なデリダの著作に加えて、読解の対象である原典についてもある程度の予備知識が必要となるという、ハードルの高いものになっている。そうであるから、本書のような概説書は非常に有用である。 デリダの代名詞でもある『脱構築』とは、ある著作の主張に対して、その主張に矛盾するような記述が同じ著作内に含まれることを指摘したり、その主張を顕在化させるために排除された何かを浮き彫りにしたりして、当の主張の正当性を揺るがせたりする、そのような読解である。総じて、従来のオーソドックスな読みとは全く異なる解釈が取り出される。そうはいっても、これだけでは意味不明であると思うので、本書の第二章における、プラトン『パイドロス』における『エクリチュール』論の『脱構築』を読む方が理解が早いだろう。こういった読解を興味深いと思えるか、あるいは、取るに足らないことにこだわっていてナンセンスだと感じるか、そこがデリダが合うかどうかの分岐点だろう。著者自身が『プラトン論を『パイドロス』のエクリチュール論から始めること』は『尋常なこととはいえない』、『ほとんど「本末転倒だ」といいたくなるところだろう』と前置きしている。これが正統派の率直な感想だと思う。私個人としても正統派の感性に近い。『パイドロス』という書き物においてプラトンは、『エクリチュール』≒書き言葉について『死んだように沈黙している』などの理由で否定的な評価を下している。デリダはその『脱構築』的読解で、肯定的に評価されている『パロール』≒話し言葉について、プラトン自身が『魂のなかにほんとうの意味で書きこまれる言葉』などと表現している箇所に着目し、『エクリチュール』と『パロール』という二項対立において『内部/外部の境界線は究極的には決定不可能であり、可変的、流動的、不安定なものであるということ』を示すわけである。私としては、そういう話をするならば、そもそも『パイドロス』自体が書き物じゃないか、とでも言いたくなる。著者によれば、プラトンは『自分の書物の存在をみずから否定せざるをえなかった』ために『多くの書物を書き、それを書いたことを否認するためにまた手紙文字を書き、そしてその手紙を「焼き捨てる」ことを求め』たそうである。それが本当なら、哲学の源流に自己矛盾を見出す『脱構築』的読解も、一周回ってある種の正当性があるようにも思えてくる。 言語論で印象的だったのは、『固有名』を付与すること=『反復可能性』を与えることは『根源的暴力』であるという指摘である。要するに、言語では表現不可能な個の特異性を消し去ったうえでないと、公共の言語による表現は成立しない、ということだろう。このことは十分に理解できるが、それを『暴力』と呼称すべきことなのかは疑問が残る。このような『暴力』に抗うことを命じるのが『まったき他者』への『応答(réponse)』であり、それこそが『責任(responsabilité)』だと説明される。私の興味を引いたのは『応答(réponse)』と『責任(responsabilité)』についてである。私はフランス語は知らないが、英語における「責任」に相当する語としてresponsibilityを知ったとき、似たようなことを考えた。この語を見れば一目瞭然、responsibilityとは応じる能力であって、日本的な黙して腹切りとはまったく異なる概念である。responsibilityを「責任」と訳すことは意味の取り違えに他ならないと、私はずいぶん前から思っていたのだ。デリダの『まったき他者』という考え方や、『ウィ(oui)』は常に『他者』の『ウィ(oui)』に先立たれているという主張などは、かなりレヴィナスの主張に近いように感じた(ouiは英語のyesに相当する)。実際、デリダとレヴィナスは相互的な影響関係にあったようだ。言語論では他に、テクストは『反復可能性』=『引用可能性』によって原理的に他の意味へと開かれていることから帰結する『散種』という概念が興味深い。これは『脱構築』的読解が可能である根拠といえるものと思われるが、恣意的読解が可能である根拠にもなりうるように思う。しかしデリダ的に考えれば、唯一正解の読みというものは存在しないということになるかと思うので、そうであれば、恣意的な読みという事態そのものが熟考を要するものとなる。私の理解が正しいか疑問ではあるが、おそらくそういうことだろう。 法については、デリダ自身が『あらゆる法の「起源」には無根拠な暴力があるということ』だと言い切ってくれたことは大変好印象であった。これは普通に考えたら十分に理解可能な単なる事実である。法律の根拠は憲法であるが、さらに憲法の権威を保証する何かがあるのだろうか?それは作成者の『無根拠な「力の一撃」』に他ならない。著者はこの事態を『ある法は〈法の支配〉(rule of law)のもとで合法的でありうるけれども、〈法の支配〉それ自体は合法的ではありえない』、それに加えて『法や〈法の支配〉はみずからの起源を隠蔽し、暴力の痕跡を抹消』して『不可能な正当化を企てる』と表現する。しかし私としては、そもそも純粋な力それ自体は道徳や倫理とは無関係なのではないかと思われた。それでも著者の言わんとすることは理解できる。著者はアメリカの独立宣言を例として説明しながらも明言はしていないが、そこで『抹消』された『暴力』となると、アメリカ先住民への迫害という歴史的事実が思い出される。では法とはそのようなものだから破棄すべきかといえば、当然そのようなことは『最悪の暴力につながる』ため最善策ではない。著者は『正義』について、『法=権利をとおして、法=権利のたえざる脱構築のプロセスによってしか追求されえない』と表現する。私なりに日常的な言葉で考えれば、どういった形であれ法律は必要だが、それが何か見落としていないか、それが十分かつ最適か、常に見直しは必要だ、くらいの意味であろう。また著者は『不可能性の経験』としての『決定』における『責任』について、『すべての他者にその特異性において同時に応えることは不可能』であり、だからこそ『十全に正しい、正義であるということはありえない』と説明する。これもある意味当然で、何かを選ぶということは同時に、他の何かを選ばないということに他ならないのだから、少なくともそのように自覚せよという倫理的要請だろう。 『贈与』というものについて、それが『真の意味』であるためには、つまり心理的負荷を含む一切の意味での『交換』でないためには、『贈り手と受け手のあいだに相互性』があってはならないという指摘は非常に印象的であった。私は「ごんぎつね」の物語を思い出した。本当に人のために何かをするということについて考えるときに、これは覚えておきたい。 デリダは『正義』の反対である『絶対悪』を、『他者』の『痕跡一般の絶滅による他者一般の絶滅の企て』と定義し、『絶対的な灰』という強い言葉が使われる。このあたりの表現には、まだ生々しかった第二次世界大戦、とりわけ絶滅収容所に消えていった多くの人たちへの想いが表れているように思う。それに対して『メシア的なもの』とは、『他者の到来』および『到来するものの絶対的で予見不可能な特異性』の経験であり、それは『正義』の経験の別名なのだとされる。このあたりの表現にはユダヤ的なものが強く感じられる。 このように知的に刺激されながら読みとおすことはできたのだが、どうも私には、デリダ自身の方法論にしっくりこないものがある。それは、自己の主張を打ち出すのに、他者の著作の読解というスタイルを取るという一点に尽きる。本書後半で展開される『他者』や『正義』についての論も、例えばレヴィナスはストレートに自分の言葉で表現している。デリダの思索は、方法論的にはハイデガーの存在論の『解体』、つまりプラトン以来の形而上学が覆い隠したとされる存在の根源的な意味を問い直す作業を引き継ぐものであるようだ。一方でテーマ的には、『他者』の重視など、先にも触れたレヴィナスにかなり近い。第一章の評伝で詳述されているが、デリダの出自が『アルジェリア生まれのユダヤ系フランス人』という、極めて『他者』らしいものであったことも、後年の思索の遠因だったのだろう。 『脱構築』の特性を考えると、それは概念というより運動であり、固定的なゴールを持つようなものではない。人や社会が何かを考えるとき、動くものでも固定して考えざるを得ない。そうしなければ思考そのものが不可能であることも事実である。そうであれば、『脱構築』の運動が、どのくらい思想や社会に現実的に有意義なものを提示できるのか、私には十分な理解が及ばないのも正直なところである。一つ言えるとすれば、考え続けることの重要さだろうか。著者は、『脱構築』とは『ニヒリズム』ではなく『ある無制限な「肯定」の思想』だと宣言している。
0投稿日: 2025.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ脱構築は正義のための決断を促す思想 そこに至るまでには、混沌や矛盾を知覚することになる。 いや、ここを知覚すればこその正義なのだろうか。 もう今や誰もが気がついている世界の至るところの無限性について、合理の暴力から、ただ恐れ慄く必要は無くなった。
0投稿日: 2024.04.28 powered by ブクログ
powered by ブクログすごい。知っている世界が、くずれていく、、 すべての他者との、初めから暴力的な関係性の中に、すでにある絶対的正義
6投稿日: 2023.02.26 powered by ブクログ
powered by ブクログ【1】 30 修論 36 五月革命 43 脱構築は哲学を文学に →ハーバーマスは批判、ローティは歓迎 →デリダ・サール論争 48 デリダの抵抗、ブルデュー 52 ド・マン論争 【2】 55 解体の仏訳語としてデコンストラクション 64 エクリチュールはパルマコン(知恵の、記憶の秘訣)である 81 プラトン主義哲学、形而上学=二元論的分割 82 形而上学の要素 ①ロゴセントリズム ②フォノセントリズム ③現前(←ハイデガー) ④存在・神・目的論の構造 ⑤ファロセントリズム(ファルス) 84 現前(古代・イデア→中世・絶対神→近代・自己現前(コギト・意識・主観性)) 92 外部は内部の内部 102 コーラ(場) 106 パルマコン 115 パルマコス Holocaust 121 ソクラテスの幽霊、灰 【3】 129 破壊不可能な責任 130 決定不可能性における決定=非暴力ではない 原エクリチュールの原暴力があるから 「暴力のエコノミー」非暴力を追求する行為自体が暴力となる 133 固有名の暴力 142 レヴィナスの暴力 143 暴力性に無知なのは無責任→暴力にあらがう 147 脱構築は他者への肯定的な応答、まったき他者の侵入 149 言語の反復可能性(エクリチュールだけでない) ①パロールは語る主体が現前するが、エクリチュールは主体はない ②パロールは外的・現実的コンテクスト(周囲)も内的・意味的コンテクスト(文脈)もオリジナルで現前するが、エクリチュールはそうではない 154 マーク(記号) 159 引用 意味のイデア的同一性(←反復可能性) 「最小のイデア化」 162 形而上学的反復は同一の反復だが、デリダの反復は差異を伴う 164 散種 無限の意味の繁殖可能性 167 反復と散種でマークからマークの他者へ向かっていく運動を知る 175 テクストを読むことは他者の署名に連署すること 178 oui 183 自由で自律した決定のまえに、他者への呼びかけへの責任、応答可能性がある 【4】 193 批判法学 197 法は脱構築可能、正義は脱構築不可能 203 独立 208 現前は再現前の再現前 214 不可能性の経験そのものが正義 222 幽霊 228 古典的な解放の理想を肯定 【5】 232 贈与 254 主体は決定できない 257 幽霊 274 死者を葬る 277 忘却
0投稿日: 2023.01.28 powered by ブクログ
powered by ブクログデリダ入門書として非常によみやすい。 エクリチュール、反復可能性、差延、散種などのデリダ語の使い方が見えてくるだけでなく、デリダ思想を一つの正義の思想として読み解くことで、脱構築が単に哲学の破壊ではなく肯定的な思想であることが分かってくる。 本書を読む以前はポストモダン思想には破壊的・ニヒリズム的なイメージを持っており、脱構築もテクスト斜め読みのようなイメージを持っていたが、本書を読むことでそれとは全く異なる肯定的な他者の思想が見えてくる。 現象学において他者とはなんなのか?という問いをぼんやり持っていたが、デリダはそこに一つの新しい他者像を提示しているのだろう。 デリダの著作の入口として非常にモチベーションが湧く良い入門書でした。
0投稿日: 2021.06.01 powered by ブクログ
powered by ブクログおそらくよくまとまっているのだと思う。デリダを読んでそれを有意義に受け取ることはその性質上難しい。そこになんとか最低限度の錨を下ろそうという苦悩が見える。デリダの脱構築においては正義は脱構築し得ないというのが一応の最低ラインにはなるのかな。何にせよ使う側の誠実さが求められると思う。
0投稿日: 2017.12.18
