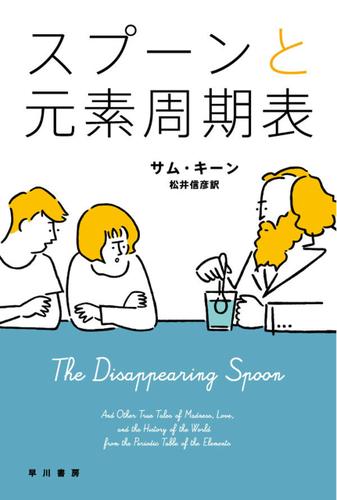
総合評価
(10件)| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ友達のおすすめの1冊。ページ量と中身の濃さに手こずって読み終わるまで正味3週間くらいかかった。その分この半年で読んだ中で一番良い書籍だったように思う。 高校時代、化学は得意科目の1つだった。応用力を問われる数学や物理と違って、化学はトイレの壁に貼った周期表や有機化合物のチャートを覚えさえすれば得点源となることが多い科目で、化学のおかげで2浪を避けられたけれど教養として何か身に付いたかと言えばうーん…という。しかしそのときの勉強がなければ本書を読むことは間違いなくできなかった。 先人を気にして論文発表をしなければならない、常温核融合といった病的科学の存在、国家対抗新しい元素発見レースみたいな、周期表には見えない人間臭さが常在菌のように染み付いていて、化学は人の営みの成果そのもの、というのが新たな知見として得られた。万物は元素から成るというより、人間ドラマの積み重ねであるという印象を強く受けた。受験勉強のために機械的に学んだことが数十年を経て教養に化けたような感動すらある。勉強それすなわち教養の扉を開く鍵であると。 本書を紹介してくれた友達が、まさに教養と人間臭さを兼ね備えたような人で、友達のことをより理解しようとおすすめの1冊を聞いて回る試みが功を成したのではないか。それと、この化学入門にしては読みづらい学術書を、こいつなら読めるだろうと信頼しておすすめしてくれたこともまた嬉しくなりました。
0投稿日: 2025.07.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ周期表の各元素に纏わるこれでもかというエピソード。その中で関連する歴史的事件や人物、社会背景を交えて語る。いわば、元素を主人公にした物語。 文系のぼくにとって、化学はどちらかというと苦手科目。高校の時、必死に覚えた周期表。この本を読んだあとでは違った感覚で眺めることができる。 味気ない周期表がただの記号の差列ではなく、人類の歴史と密接に関わる壮大なドラマであることを体感した。 400ページを超える大著。ぼくにとっては消化不良の面あるため、ときを置いて再読しよう。 100種類以上ある元素。元素を構成するのは、陽子、中性子、電子。元素の違いはこの数。どうして数が違うだけでこんなにも元素の特性に違いがあるの?紅茶に溶ける金属製のスプーン。本書のタイトルにもあるが、これは原子番号31のガリウム。どうしてホウ素、アルミニウムだと溶けないの? 左巻先生の解説。「私の元素講座に、小学生や中学生が参加することがある。「乾燥空気の成分は多い順に窒素、酸素だが、3番目は?」などと参加者に問うと、子どもたちが「アルゴン」と即答する」との記載がある。恐るべし子供たち。 それにしても周期表を作ったメンデレーフは偉い。ただし、ノーベル賞の受賞は逃している。唯々残念。
0投稿日: 2025.07.01 powered by ブクログ
powered by ブクログ面白かったー。 こういう科学エッセイ大好き。 興味深い話はたくさんあったが、一番驚いたのは天然核分裂反応炉のオクロの話。 ウランと水と藍藻類だけで稼働していたというのだ。 びっくり。 そんなこと初めて聞いた。 藻類が過剰な酸素を作り、水が強い酸性になり、ウラン235を溶け込ませ、藻類が水をろ過してウランを特定の場所に集中させ、臨界量に達した。 ただ、それだけではウランが核分裂を起こしても連鎖反応は起こさない。 水があることで中性子の速度が落ち、連鎖反応が起きたのだ。 そのため、核分裂が発生すると高熱になり、水が蒸発し核分裂がストップ、冷えて水がたまると再度核分裂が発生、とのサイクルが発生していた。 (15万年かけて6トンのウランが30分/2時間半のオン、オフのサイクルで消費された) この話だけでもこの本を読んだ価値はあったが、ほかにも失われた日本刀の作成技術の話とかフォンノイマンがメーザーに関しては誤った認識を持っていたとか楽しい話がたくさんあった。
0投稿日: 2023.06.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ元素記号にまつわるエピソード集。新たな元素を巡る科学者たちの争いがやはり印象的で、元素の名付けを巡って混乱があったり、新たな元素の発見が覆されたり。人間臭い内容が実に多い。ちょっとボリューム満点すぎて、文系にはちょっとお腹いっぱいになってしまったが。。
0投稿日: 2021.04.04 powered by ブクログ
powered by ブクログ理系を自認しているが、どうも化学が苦手で特に炭素がでてくると思考がストップしてしまうくらいなのだが、親しみやすそうな本書のタイトルに惹かれて読み始めてしまった。 やはり自分にはちんぷんかんぷんでした。 タイトルの「スプーン」って、ガリウムでつくったスプーンのことらしい。これで紅茶に砂糖をいれてかき混ぜると溶けてしまうそうな。
1投稿日: 2018.01.23ノーベル賞狂想曲
元素の性質だけでなく、新元素発見に奔走した科学者やノーベル賞選考にまつわるあれこれのエッセイです。面白いけど、やや話があちこちに飛び過ぎという印象。科学エッセイというより、科学者エッセイですね。
0投稿日: 2017.12.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ元素周期表と個性豊かな元素たちを、その歴史と多様なエピソードをもって紹介する本。 やや厚め(500p弱)の文庫本にこれでもかと様々なエピソードが詰め込まれ、飽きることがない。 高校の化学がつまらなかった人にも楽しく読める一冊。 世界の理解と興味を促進してくれること請け合い。 「本書には元素や周期表を切り口に『こんなことまで読み取れるのか』と驚かされる。 特に、人間臭い話が多い。 著者も指摘しているとおり、周期表は科学の成果であると同時に人間の営みの結果なのだ。」 ―――訳者あとがきより
0投稿日: 2017.08.16 powered by ブクログ
powered by ブクログ元素周期表とそこに記載された元素をめぐる多彩なエピソードを紹介するカジュアルなサイエンス本、とはいっても門外漢にはちょっと重たい内容。元素だけでここまで話を広げられるのか、という今さながらの驚きとトリビアルな逸話は大いに楽しめる。
1投稿日: 2016.03.13 powered by ブクログ
powered by ブクログ結構な分量のある本だけど、読む手が止まらず、気付いたら読み終わっていました。 単純な元素の性質についての話だけではなく、その元素発見の背景にあった人間ドラマ(苦労や名声をかけた争い)やその元素を巡るいざこざ、失敗譚など、あらゆる角度から元素という物を眺めるような構成になっており、非常に楽しめました。 訳者あとがきからの下記引用を見るだけで、ワクワクしてきませんか? "どんな話が飛び出すか少しばかり紹介すると、第1部では学校で習わないような周期表の見方、いちばん長い英単語、ケイ素系生物の可能性、ノーベル賞を横取りしようとした物理学者、七つの元素名の由来となった場所・・・、第2部では地球の年齢、恐竜の絶滅、毒ガス戦、コンゴ紛争、原子爆弾・・・、第3部では何度も「新発見」された元素、元KGBエージェントの毒殺、放射性ボーイスカウト、スペースシャトルの空中爆発ではない死亡事故、インドの塩事情・・・、第4部では万年筆のデザイン、トウェインのSF、マッドサイエンティスト、裏切られた女性科学者・・・、第5部ではビールが科学に果たす役割、国際キログラム原器、地球外生命体の存在確率、天然の原子炉・・・。これでもずいぶん端折ったつもりだ。" 個人的に一番面白いと思ったのは、とあるSF作家が風刺した、グローバル資本主義における通貨の最も優れた材料は何か?という話。 答えが気になる方は303ページを見てみて下さい。 なるほど、確かにそうかもしれないw
1投稿日: 2016.02.18 powered by ブクログ
powered by ブクログ局所的に面白い話がいろいろ書いてあるけど、全体は見通しが悪くてちょっと読みにくい。それこそ「化学」というイメージなんだ。
0投稿日: 2015.11.26
