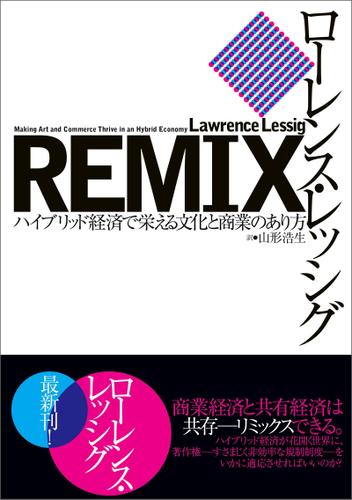
総合評価
(7件)| 1 | ||
| 0 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ書き出しのスーザの話は面白い。彼は魅力的な味方だろう。しかし、読んでいても説得的に感じない。レッシグはもっとできる子、だよね。。
0投稿日: 2014.06.30 powered by ブクログ
powered by ブクログレッシグの子供、将来の世代への視線がとても温かい。 目新しい議論が展開されるわけではないけど、 子供たちへの思いは、子どもが生まれた今こそ自分にも わかるものがあった。
0投稿日: 2014.06.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ「著作権」を中心にハイブリット経済によって変わる未来を考える。 所在:展示架 請求番号:021.2/L56
0投稿日: 2012.07.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
私は著者ローレンス・レッシグを、この本が送られてくるまで全く理解していなかった。 ローレンスはクリエイティブ・コモンズの創設者であり、この他にもCODEなども書かれた偉大な人だ。現在は、ハーバードで法学の教授を務めている。 さて、このREMIXについてだが、RO(Read Only)文化とRW(Read Write)文化に分けて考えている点が違う点だ。つまり、iTunesやその他のコンテンツデリバリングシステムをRO文化、初音ミクのやYoutubeにおけるAMVなどをRW文化と彼は呼称している。 そして、一時的に猛威を振るったP2P技術によってこのRW文化へメスが入れられかけ アメリカでも日本でも訴訟や削除の嵐になった時期もあったが、そこで出てくるのが著作権のあり方を見直し、この両方の文化を取り込むことで共生経済を生み出せば良いのではないかと綴っている論文である。 しかし、彼はアマゾンのロングテール(ヴァイラルと引用も広義のRW)からセカンドライフまでのRW文化について説明することで、自分の理論を証明して見せようとするが、ここでクリスアンダーソンやWikipedia等を持ち出しても説得力にかける。 むしろ、初音ミクに関するの著作権の取り扱いやニコニコ動画とJASRACの関係のほうがよほど先を行っているように私には思える。これについてはkawango38の驚異の粘り強さが、政府や業界団体を巻き込み新しいステージへと昇華できたことを意味している。もちろん、バンダイヴィジュアル等、本当は最もネットのRW文化に適しているコンテンツを保有している割にはRO文化で儲けようとしている物もいるわけでまだまだこれからの分野ではあるが、ここで言いたいのは、そのRW文化でRO文化側のコンテンツホルダーが本当に収益をもたらさないのか?という点にあるのではないかと感じた。 はっきり言えば私も2年ぐらい前まではRWでも充分に売れると思っていたが(☆キラッが爆発的に流行ったあたり)、それでは収益は産まない事が現在では分かり始めており、次のステップとしてフリーミアムの踏襲と不正なアップロード防止のための期間限定無料放送が昨秋あたりから開始され、一定の成果を見せている。 これに関しては、テレビ東京のアニメネット放送に関する見解のインタービューがニコニコニュースに掲載ていたのでリンクしておく。 「映画業界と同じ失敗はしない」テレビ東京がニコ動にアニメを流す理由 NCN このように、一定の理解が生まれれば収益性は出てくる。このようにユーザは正規コンテンツに対して、適正な値段と適正な供給ルートが確立されれば金銭を払い始めるという好循環を行う事がわかったのである。また、ストリーミングによる供給であり、全体の99%は不正行為はしないであろうこと、また、供給者側から見ればコンテンツからの収益がロングテール化しているように見えるであろうことがわかるであろう。つまりは、適切な検索環境とポータル、そして安価な供給プラットフォームさえ整えばコンテンツホルダーからしたら、これほど美味しい物はない。新技術に振り回されてその都度パッケージングされた在庫を持たなくても良いわけで、これほど高収益なモデルも無いだろう。 さらに、ニコニコ動画やYoutubuのような共有型のCDNを使うことでより安価にその維持が可能だ。もちろんプラットフォーマーからすれば喉から手が出るほど欲しかった【正規コンテンツ】ということになるためWinーWinなのである。同様にYoutubeにもNHKオンデマンドが供給されている。これは今までとずいぶん違う現象だ。自前でCDNやストレージを持たなくても良いのだ。テナントとなってしまえば面倒な管理から解放されその分コストも下がるのは道理だ。もし収益が出ないと諦めているのであれば、コストを下げる意味でも相談してみるとよいだろう。自社のアーカイブとしても充分に活用できる。そういう意味ではUstreamでも同じだろう。どちらかと言えばこちらは生放送側であるが、ソーシャルストリームとの連動性では非会員でも見ることが出来るという点ではかなりのパフォーマンスをもつし、最近では有料課金が出来るようになったのもプラスだ。 しかし、これではまだまだRO文化でしかない。消費され続けるのだ。だが、適正なコンテンツを適正に供給することがこの10年間の役目だとしたら、次は適正にRW出来るコンテンツ供給方法を創りだすことが役目なのかもしれない。そのためには文化も変えなければいけないが、法律もマインドも変えていかなければならない。 著者も最後に述べているように、著作権とその背後にある経済理論は必ずしも現在の世界にはマッチしない。なぜならばインターネット前に作られたものだからだ。資本主義も変わらなければならないが、まだそれには時間がかかりそうだ。
0投稿日: 2011.01.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ冒頭、どんな内容になるのかと期待したが、意外とアッサリした主張。 訳者のあとがき読むだけで良かったのではないかって気がする。
0投稿日: 2010.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログ「CODE」はテクノロジーがどんな社会を生み出しうるか、という現状整理であり思考実験であったのに対して、これはどんな社会を目指しうるのか、という行動指向のもの。だから、 CODEほどのカチッとしたロジカルさはないし、思想面でも納得のいかないところがある。レッシグの実現したい社会がほんとうにいい社会なのか、まだ納得がいかない。それでも一つの可能性として、商業経済と交換経済とのハイブリッドの形はありうるだろうし、ただ商業経済だけを考えるのでは片手落ちであることは疑いようがない。 ひとつ疑問なのは、こういうかたちで社会制度を考えているひとというのはどの程度いるのだろう。とても可能性があると思うのだけど。コードという考えかたは、すくなくとも日本では社会分析の、ツールくらいにしかなっていないようにおもう。
0投稿日: 2010.09.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ基本的に訳者の山形浩生氏の解説に同意。 レッシグの言いたいことも分からなくはないが、子供たちを犯罪者にしないというだけの理由で、ファイル共有を合法化するというのはさすがに無理だろう。 それを合法化するなら、せめて ・それにより失われる、RO的著作者達の創造活動のためのインセンティブ、(会社等の支援環境を含めた)創造環境、及びそれらから生み出されるはずだった作品の量 と ・それにより生み出されるりミック作品の量、ファイル共有環境の充実により新たに生み出されるリミックス的ではない作品の量 を比較し、少なくとも後者が前者と同じ以上でないとだめだろう。 でもどう考えても、Winnyやマジコンを使う人間が創造活動にいそしむとは思えない。もちろん膨大な著作物利用可能環境の中におかれることで、新たな想像力・創造力が刺激されることはあるかもしれない。 しかしそもそも創造活動にいそしむものは、自分の作品について愛があり、それが故に他人の作品についても、自分の身に置き換えることで尊重することができる人間だろう。ファイル共有を行っている人間が追及しているのはただ単に自分の快楽だけであり、そこにモノを生み出すことに関する敬意はみじんも感じられない。 著作権のあり方を見直すというのであれば、人が自身の創造活動から得られる利益の範囲みたいなものについての考え方を示して欲しかったな。自己の作品の利用許可・禁止に関するn人ゲームの均衡解を求め、それによりどのような属性の人だとどのような著作物利用戦略の解になり、それにより得られる利益はどのくらいになるか。こういった話でもあれば、著作権に関する進展のない議論の応酬を超えた知見が得られると思うのだが。子供のため云々の情緒的な話をいくら繰り返しても、RO側は全く譲らないだろうし、一般人の意識も変わらないだろう。 訳者あとがきによると、レッシグは今後政治とか民主主義に関する問題に軸足を移すらしいので、多分彼の本を読むのはこれが最後だろう。うーん、まだ問題山積みだから、色々なアイデアを読みたかったんだけどな。
0投稿日: 2010.05.22
