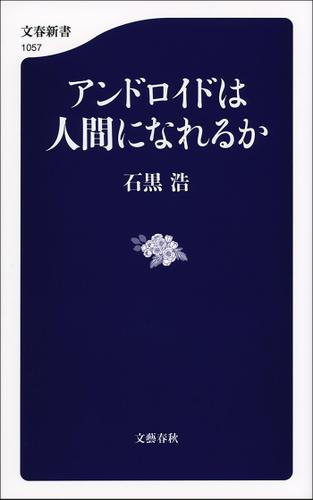
総合評価
(26件)| 8 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 |
 powered by ブクログ
powered by ブクログ◆未来のアンドロイドとわたしたち◆ 『アンドロイドは人間になれるか 』 は、驚きのタイトルです。大阪万博の「いのちの未来」パビリオンでも人間と共存するアンドロイドが注目されています。ロボットが人間らしさを持ち、社会にどのような変化をもたらすかという内容です。倫理課題を乗り越えたなら楽しい未来が見えてくるでしょうか。この本を読んだなら、あなたはアンドロイドを「人間」として認識するか機械として扱うか、そんな問いに向き合うことになりそうです。
0投稿日: 2025.08.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ精巧なアンドロイドのトップクラスの研究者 石黒浩によるヒトとアンドロイドの違いについて むしろ、違いはないのではないか?という哲学的な問いかけになっている 目次だけ読んでもある程度の内容は推測できる -------------------- プロローグ 「人の気持ちを考える」 第1章 不気味なのに愛されるロボット──テレノイド 誰もが気味悪がるロボット 高齢者の話し相手として大人気 人間らしさと「不気味の谷」 落ち着きのない子が一瞬で静かに! 第2章 アンドロイド演劇 人間よりも人間らしい アンドロイド演劇が映し出す「心」の正体 第3章 対話できるロボット──コミューとソータ ロボットが家庭教師になる日 ロボットと赤ちゃんは同じ 第4章 美人すぎるアンドロイド──ジェミノイドF 生身の人間よりアンドロイドに夢中な男たち ロボットが変える家族 第5章 名人芸を永久保存する──米朝アンドロイド ロボットと宗教 ロボットが死生観を変える 第6章 人間より成績優秀な接客アンドロイド──ミナミ ミナミの接客テクニック 第7章 マツコロイドが教えてくれたこと マツコロイドにキスするとどうなったか もう一人の自分 第8章 人はアンドロイドと生活できるか ロボットは人間の敵なのか? ロボットは当たり前の隣人になる 第9章 アンドロイド的人生論 「自分らしさ」など探すな エピローグ -------------------- 世間の度肝を抜く斬新な発想で注目を集めてきた鬼才・石黒は、子どもの頃、「人の気持ち」がわからない子どもだったという。 大人になった今でもその正体がわからず、「人の気持ち」の謎を知りたいという思いから人工知能の研究、そしてアンドロイド開発・研究へと足を踏み入れた──。 アンドロイドが教えてくれる「人の気持ち」や「人間らしさ」の正体とは? 今まで常識と信じて疑わなかったことが次々と覆されていく様は鳥肌が立つほど面白く、またちょっと不気味でもある。 アンドロイドやロボットは、近い将来、必ずあなたの隣人となる。手塚治虫やSFが描いた未来はすぐそこまで来ている。最先端の場所に常に身を置く石黒浩の見ている未来をお見せしようではないか。 人間存在の本質に迫る興奮の知的アドベンチャー。これはもはや哲学だ! -------------------- アンドロイドに心はあるか?という問いの実証として 実在するアンドロイドに対して、周囲の人がそれに心の存在を意識すれば心があるとみなしても良いという定義 チューリングテストの心バージョンということなんだろうけど あまりにも暴論ではなかろうか? この理屈で言えば、まったく動きもしないモノに対しても周囲の人が認めれば心があるという事になってしまう 宗教は正にこれなんだろうけど、やはり哲学的な問題になってしまうので、科学として扱うには「心」の定義が難しい ・ジェミノイド:見た目の人間らしさを追求したアンドロイド ・テレノイド:人の個性を削ぎ落とし、人の存在を感じる最小限の要素を持ったロボットト ・ハグビー:テレノイドよりもさらに個性をそぎ落とし、最低限想像を喚起させるロボット。携帯電話をホルダに挿して、抱きしめながら通話ができるガジェット 人の存在を感じるためには、二つのモダリティ(知覚)があればいいらしい 二つのモダリティ(知覚)とは、例えば「声」と「触感」など 五感全てでわかっていなくても、二つの表現がつながった瞬間に「わかった」と、人は言うらしい 面白いアプローチとしては、人間をプログラミングするというところ ---------------- 「ロボットをプログラミングする」のではなく「人間をプログラミングする」ことが可能かを実験しているんです。具体的には、大学の学生を実験対象にして、授業に出席し論文を読み書きするといった学生生活を送るように逐一スマホから人間に指示を出しす実験を行ったのだそうです。その結果、プログラミングを導入した学生の方がそうでない学生に比べて効率良く勉強を進めることができたと記されています。 ---------------- これに近しい事は既に実用化されているなぁ コンビニの仕組みもそうだし、マニュアル化できるような業務は既に人間はある種の単なるオブジェクトに過ぎないのかもしれない ジェミノイドを利用した会議には人件費を払えないという主張に対する反論 人が出席する事の定義 評価されるべきは結果や成果であり、生身の身体が必要というのは何を盛って本人とするのか? また、センサーは信用するのに、ロボットを信用しないのはおかしいという主張 当時とは違って今やテレワークなど、物理的に直接顔を合わせなくとも済む会議が増えている中 画像を共有せずに本人らしい声で出席した会議はもしかしたらフェイクの可能性もあるわけで すべての責任はその人という取り決めがされているのであれば求められるのは成果というのは理解できる となると、「本人」という属性が必要になるのは何なんですかね? 本人を模したAIが同様の仕事をこなす未来が容易に想像できるけど、その際にもまた議論される事になると思う 技術に対して信用をしない人達 「技術への偏見は時間と共に解消する」という言葉がしっくりくる 今や技術を利用せずに生きている人間がほぼいない 導入当初は嫌悪の要素があったかもしれない技術も普通に許容されているわけで アンドロイドに対する嫌悪も社会に浸透していくに連れて解消していくというのも納得 アンドロイドの進歩に感情的な拒絶を示す人間に対する言葉 「人間はアンドロイドのスイッチを切ることができます」 しかし、アンドロイドのスイッチの切れない場合もあるのではなかろうか? アンドロイドの運用がブラックボックス化していくのが容易に想像できる昨今 一部に問題があるからと言ってすべてのシステムを止めるわけにもいかない また、システムが様々な方法で冗長化されている場合なんかも、スイッチを切りたくとも切れないケースが想像できる そんな危うさはあるあもしれない タイトルの問題として、「人間とはなにか?」という定義が必要になる それこそ、人間っぽく振る舞うアンドロイドというのはいずれ作られるし この本でもアンドロイドに心はあると感じる人もいる しかし、そこにクオリアはあるのか?というのはどうしても検証できないのではなかろうか? クオリアを全く持たない哲学的ゾンビが正にアンドロイドなのだとしても、それを私達は確認する術がない やはり、「人間とはなにか?」という哲学的な問題に帰結してしまう気がする
2投稿日: 2023.10.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ特に亡くなった人を墓ではなくアンドロイドにして遺すと言う話が面白かった。 確かに形式化した墓参りよりも亡くなった両親に自分の近況を報告しに行くような状況、そしてそれに生きていた時のように応えてくれる両親のアンドロイドという構図はとてもいいなと思ってしまった。 考えること、をやめない限り人間としての価値を残せるのは、間違いないと感じるし、今後も考えることのできる人間になりない。
0投稿日: 2023.09.27 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者がいう「ロボット作製とは人間とは何か、心とは何かを探求すること」という意味が良く分かりました。人は自分の外に「心、気持ち」を感じるんですね。二つの知覚の組み合わせで「わかった」という気分になるとのこと。ロボットに対する方が人間は素直になれる、という事実。人間が生み出した技術を外部化して突き詰めていったのがロボット。であれば人間とロボットとの境目はない。何故石黒さんが話題の人になっているか、理解できました。更に先を知りたくなりました。
0投稿日: 2021.07.21 powered by ブクログ
powered by ブクログ著者は阪大の先生らしい。僕もオーケストラの方で阪大とは縁があるので勝手に親近感笑。たまたま友達に貸してもらった本だったのだけどめっちゃ面白かった。ロボット、アンドロイドをどのように作っていくかの紹介と同時に、アンドロイドがこれから果たすであろう社会的な役割、人間の心とは何か?という所まで話を広げていて刺激になった。シンギュラリティが来てアンドロイドが人間の能力を凌駕すると嫌悪感を感じるみたいだけど、「何となく嫌」ではなくて何故そう感じるのか、本当に嫌なことなのか?と理詰めでどんどん切り込んでいくスタイルはさすが研究者だと思った。タブーとされていてみんなの中で暗黙のうちに、曖昧に把握している世界にズバっと踏み込んでいける姿勢は真似したいなぁ。僕も肉体がもう一つあって、頭脳もついていけるならこんな研究してみたいなぁ...。
1投稿日: 2021.02.09 powered by ブクログ
powered by ブクログ読み始めるまであの、イシグロイドやマツコロイドを作った石黒さんによる本だということに気付いていなかった。 さすが石黒さん、こんなこと考えながらロボットやアンドロイドを作っているんだなあ。少し前に読んだAIは心を持てるか、という本よりだいぶ分かりやすい。言ってることはわりとラディカルだけど。 石黒さんの思い描く社会が早く実現するといいな。楽しそうだ。
8投稿日: 2020.08.23 powered by ブクログ
powered by ブクログ図書館でふと気になっで読んでみた。脳科学的なアンドロイドの有用性が述べられていて面白い。石黒先生的な人生や科学に対する哲学も興味深い。
0投稿日: 2020.03.29 powered by ブクログ
powered by ブクログアンドロイドロボット研究の第1人者である石黒先生がご自身のロボット研究について語っている。 石黒先生のことは知っていたが、本を読んだのは初めて。 一言一言がかなり強烈だが、うなづける。 先生の考えが、途中でカギかっこでくくられてバーンと訴えかけてくる。 「人の気持ちを考える」という言葉を理解するためにロボット研究をしている、という。ロボット研究にのめりこめばのめりこむほど、ロボットではなく「人間」とはどのような存在なのかを考えずにはいられない、という。 ロボットの研究は哲学なのだ、という言葉にとても納得がいった。
0投稿日: 2019.11.14 powered by ブクログ
powered by ブクログペッパーくんが20万ほど(月額使用料を入れると約120万)で手に入る現在。 ロボットが身近にいる時代がもう来てます。 個人的には近い将来ロペットが「コンバインOKコンバインOK」って言うてる時代が来るように思います(笑) 「技術への偏見は時間と共に解消する」 これは至言やと思います。 いかにテクノフォビア(科学技術恐怖症)の人であっても便利さには勝てないんやと思います。 おそらくマイナンバーも過渡期でこれからの少子高齢化で労働力不足問題に直面する中において手作業で名寄せしたり突合させたりするのが正義という人は減ってくるんやと思います。 AI時代になったらますますブラックボックス化が進んで誰もその結果に説明をつけることが出来ない時代が来るんですから。 そういった意味でも今こそ正しい科学技術に対する理解を深めて隣にいるテクノフォビアな人たちに説明することが必要なんやろなあと思います。
2投稿日: 2019.09.29 powered by ブクログ
powered by ブクログ「人の気持ちを考える」ことへの著者の幼い頃からの疑問から始まる。アンドロイド、ロボットの技術的な話ではなく、哲学的な話であったり、相手が人間であるよりもロボットのほうが心を許して接しやすくなることが中心。
0投稿日: 2019.01.20 powered by ブクログ
powered by ブクログ以前、NHKのSWITCHインタビューや「最後の授業」という番組で とても面白く興味深かった石黒さん。 「最後の授業」に内容が通じていて、語りを文章にまとめた形で読みやすい。 本人の持つ雰囲気、ユーモアのセンスが、この本の中からもうかがえる。 人の気持ち、感情という曖昧なものを突き詰めていくと、 プログラミング可能な範囲がどんどん広がっていく。 結局「自分」は「他人の目」によってしか規定されない。 「自分」だと思っているものも、 もともとは他者をまねて覚えたものなのだ。 仕草や間(ま)などを覚えさせることで、 見る側もロボットであることを越えて、親しみを感じることができる。 対人の生々しさの無さが、より気持ちを近くし、引き出しやすくなる。 何度でも同じ動きを、倦まず繰り返すロボットだからこそできる 丁寧で継続的な教育や指導や仕事の可能性。 逆に人間のピークのときのパフォーマンス(芸術や技能など)を残し、 その人が亡くなってからも後世に伝えていくことの可能性。 また、ロボットだからと、信頼しているからこそ起こってくるであろう弊害に どう対応していくべきかを、早くから準備しておく必要があること。 ロボットを作る人、仕組みに立ち入って使える人と、 ただ使う人の間での格差は、より一層大きくなっていく。 それは今の、PCからスマホに移り、 誰にでも簡単に使えるようになった情報端末における格差よりも なお大きくなるだろう。 番組「最後の授業」では、 人間がいなくなった後の、 ロボット(アンドロイド)だけになった世界についても触れていたが それこそが、いずれ来るかもしれない外部の生命体に対し、 当時の世界の姿を残し、伝える手段になるというくだりにはゾクゾクした。 人間を考えアンドロイドを考えまた人間を考える。 石黒さんの仕事の可能性と挑戦の今後が気になる。
0投稿日: 2019.01.12 powered by ブクログ
powered by ブクログ【由来】 ・図書館の新書アラート 【期待したもの】 ・ ※「それは何か」を意識する、つまり、とりあえずの速読用か、テーマに関連していて、何を掴みたいのか、などを明確にする習慣を身につける訓練。 【要約】 ・ 【ノート】 ・「マツコとマツコ」で全国的にブレイクした感のある石黒ハカセ。ロボットを作っていく過程でのブレイク・スルーが「心は捉える側の問題」。そこから、モダリティを抽出してから具体に還元していく。それも二つで十分。例えば触覚と匂いだとか。 【目次】
0投稿日: 2018.10.28 powered by ブクログ
powered by ブクログアンドロイドは人間になれるか。 この問いに対して、著者は肯定的な答えを、説得力をもって提示します。 むしろアンドロイドと人間はどれだけ違わないのか。 人間を「動物+技術」と定義すれば、人間とアンドロイドを比較すること自体が疑問なのかもしれません。 数々の発明と、それに基づく発見。 例証を駆使して語られる本書は、最前線の研究者による考察がきらめく一冊です。
0投稿日: 2017.12.02 powered by ブクログ
powered by ブクログ・2つの感覚(ex.触覚と聴覚)がその存在感を強化する。残りは想像でポジティブに補完(ex.電話で相手の声がきれいだと美人だろうと想像する)。 ・人間らしさとは・・振り向いて話すとき、同時には行うと不自然。振り向く、半歩遅れて話す。(平田オリザ演出)
0投稿日: 2017.10.05 powered by ブクログ
powered by ブクログ書名でもある『アンドロイドは人間になれるか』という問に答えているかというと、否だろう。私としてはそこにもっと切り込んでほしかった。 本書を通して感じられる考え方は「人間がアンドロイドを見て、それを人間だと思ったら、アンドロイドは人間になったと言える」というもの。 たとえば、心というものは自分の中にあるものではなく観察する側に生じるものだ、というようなことを書いている。だから「こいつは心を持っているな」と人間に思わせられるような見た目や仕草をアンドロイドにさせることができれば、それでアンドロイドが人間になったことになるのだ、と。要はチューリングテストと同じ発想だ。 では、私たちの内面にある「こいつは心を持っているな」と感じる観察者としての"心"をアンドロイドに実装することはできるのか?人間対アンドロイドではなく、アンドロイド対アンドロイドとか、多数のアンドロイドだけで構成される社会を作ったときに人間らしい営みが生まれるのか?アンドロイドは人間の問いかけに答えるだけでなく内発的な行動をしたり創造的な活動をしたりできるのか? このような問いに答えてこそ「アンドロイドは人間になれる」と言えるのだと思うし、(どうやらこういったことが出来るようになってきているらしいので)そのあたりのことを知りたくて本書を買ったのだけれど、残念ながら表面的な話に終始していた印象。
0投稿日: 2017.09.13 powered by ブクログ
powered by ブクログアンドロイドが教えてくれる、人の気持ちや人間らしさの正体とは?石黒氏の常識を覆した記載、人間の本質についていろいろ考えさせられる。 心とは複雑に動くものに実体的にあると言うより、その動きを見ている側が想像しているもの、心はプログラミングできる、心があるように見える複雑な動きをプログラムをすれば、人はロボットに心を感じる アンドロイドの性的利用、ソフトバンクのペッパーのもたらす将来、レーニン毛沢東の遺体とアンドロイド、様々な宗教の偶像
0投稿日: 2017.06.14 powered by ブクログ
powered by ブクログ人と対話するロボットのありようは真剣に模索される時期である。 そして我々人類のコミュニケーション欲求の根源には、自己保存欲求、種を残したいという(性的な)欲望がある。 「人とつながりたい」という事と「性的な関係を持ちたい」ということには強い関係がある。
0投稿日: 2016.11.03 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
マツコロイドでも有名な石黒さんが、開発したロボットの亜話を交えながら、人間について考察した本。あえて、感情移入できるよう作られたテレノイド。アンドロイドに演劇させたり、米朝のアンドロイドを作ったり。コミューとソータは2体のロボットと会話することで自然な会話になるそうだ。「心とは観察する側の問題である」「今のロボットは1、2歳のアカチャンくらいだと思ってほしい」ジェームス・ランゲ説「悲しいから泣くのではない。泣くから悲しいのだ」「75%の仕事がロボットに変わる」「中国の空港には上海ガにの自販機がある(人間より機械が信用される)「義手の人の義手を刺すと痛みを感じる」「将棋がAIに負けたとしても競技の面白さは変わらないだろう。自動車やロケットが発明されても100m走の素晴らしさが変わらないように」
0投稿日: 2016.04.16人間らしさとは?
アンドロイドの進化を楽しむとともに 人間というものを考えるきっかけになる本だと思います。
0投稿日: 2016.04.10 powered by ブクログ
powered by ブクログ複雑な動きによって、アンドロイドに人間性を見出す。 人間特有の機能を持つことが人間性を持つ条件ではなく、見ている側が複雑さの理解を補うために人間性を想像することで見ている人の中でアンドロイドが人間性をもつ。
0投稿日: 2016.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログ石黒先生の本を読んだのはこれが初めてですが、面白いですね、これ。 「人間(や心)について知りたいと思った結果、アンドロイドの研究にたどり着いた」という点は、逆説的でありつつも、本質をついた過程だと思います。 もしかしたら、これからの心理学は、アンドロイドが活躍したりするのかもしれませんね。 そのことも含め、アンドロイドの可能性の大きさについて、得ることの多い本でした。
0投稿日: 2016.03.25 powered by ブクログ
powered by ブクログこのレビューはネタバレを含みます。
ロボット研究の第一人者、石黒浩氏による「人間論」。要するに、アンドロイドを人間に似せようとすればするほど、「人間とは何か」という問いを避けて通れなくなるのだ。 個性を極限までそぎ落とした「テレノイド」、アンドロイドによる演劇、対話するロボット(コミューとソータ)、美しいアンドロイドFなど、様々なアンドロイドが登場する。 確かに、この人がいうことは説得力があるし、こんなアンドロイドを次々に作ってしまうので、天才だと思う。だが、どうしても納得できない面があった。 アンドロイドにより人間が永遠の生命を得るわけではないと考えるし、政治的指導者や宗教的指導者をアンドロイド化してしまうことには抵抗がある。 そもそも永遠の生命がなぜ必要なのか。人生は有限で、しかもやり直しがきかない。だから、一時一時を大切にできるし、だから全力を尽くす。また、アンドロイドを利用しなくとも、その人の意思が真に価値のあるものであれば、必ず誰かに受け継がれてゆく。歴史上、これまでもそうして人間は生きてきたではないか。 あくまで「アンドロイドは物であり、道具に過ぎない。アンドロイドを使うのは人間」これを見誤ってはならないような気がしている。
0投稿日: 2016.03.19 powered by ブクログ
powered by ブクログマツコロイドなど、人型ロボットの開発者による書籍。 人型ロボットがあちこちで見かけるように鳴ったら人間の生活環境もかなり変わるんだろうか。でも案外、ドラえもんみたいに特に代わり映えなく生活していくような気もしなくはない。 ところで、テレノイドが無茶苦茶怖いのだけど、高齢者にはいいらしい。自分の子どもよりテレノイドのほうがいいという人も多いんだとか。三次より二次のほうがいいみたいな感じなのだろうか。 逆に、ハグビーはちょっとほしいと思った。ざわざわしている子どもにハグビーを与えると、先生の話を聞くようになるらしい。この現象は面白いと思った。 後、美人過ぎるロボットのジェミノイドFは、見てみたいと思った。このロボットに蔑まれたり罵られたりすると気持ちいいらしい。いやでも、それはただMなだけじゃ……。 人間のコンパニオンよりロボットのコンパニオンのほうが人気というのは、ただたんに希少性なだけじゃないか。ロボットがあふれたら多分、人間のほうに注目が集まると思うのだけど。 後、この著者の顔っていっつも機嫌悪くて怒っているように見えるのだけど、実際には怒るのは苦手だったんだとか。ただ、講義中の教室が騒がしい時に教壇を思い切り蹴飛ばすようにして怒ったら、次の回から静かになったんだとか。怖すぎる。もしそれがロボットなら、自分は教室から飛び出して逃げる。実際、自分のロボットをアメリカに持って行って、日本にいながら講演したこともあるんだとか。それより、あのロボットって分解できるのか。想像しただけで怖い。
0投稿日: 2016.02.06 powered by ブクログ
powered by ブクログ人間がしている考えるという行為を細かく定義し、個別の作業に分解していくと、ほとんどのことは簡単にコンピューターに置き換えられる。定義可能な作業においてはほとんど全てロボットが勝つ。
0投稿日: 2016.01.19 powered by ブクログ
powered by ブクログ【アンドロイドがあなたの「常識」をひっくり返す!】マツコロイドの開発者で「世界を変える8人の天才」にも選ばれた世界的ロボット研究者のアンドロイド的人生論。
0投稿日: 2015.12.22 powered by ブクログ
powered by ブクログカズオ・イシグロ 大人になるということは、子どものころの疑問に折り合いをつけること 人間は、あるものに対して「形とにおい」「形と声」のような2つの要素がつながり重なると、わかったと思う 人間が何かを認識するために必要な要素をモダリティという 美人とは、見た者に想像を促すから美人なのだ 人に想像させる余地を作ることが、人間らしいアンドロイドの要素だと気づいた 子どもたちにハグビーをだかせ、ハグビーから読み聞かせの声が聴こえるようにしたら、静かになった 心とは観察する側の問題である 心とは、複雑に動くものに実体的にあるというより、その動きを見ている側が想像しているものだ ペッパー 19.8万 メンテナンスを合わせると120万 要求、意図、動作の順番で意図ができるわけではない 起こるから怒鳴るのか、怒鳴ってから感情がうまれるのか すべては行動が先か、ないしは行動と感情が同時に起こっている 米朝アンドロイド この芸をロボットに残してくれ 文楽 アンドロイドは宗教指導者になれるか 人間には、僕のように新しい物をどんどん作っていかないと我慢ができない、未来を向いて生きていきたい人と、豊かな記憶に包まれた過去に生きたい人がいる 遠隔操作ロボット さわられると、まるで自分が触られたようなざわったした感覚を覚える 遠心コピーの予測と、視覚フィードバックおよび自己受容感覚で感じた結果が合致することがわかれば、「自分の思い通りに腕を動かせている、だからこれは自分の身体だ」という自己身体の認識に至る。 遠隔操作ロボットを使うと、自己身体受容感覚がない人でも、アンドロイドに起きたことを、自分の身体のように感じると科学的にいえた シンギュラリティ 人間の定義がはっきりしない
0投稿日: 2015.12.20
